除蝗録
江戸後期、大蔵永常が著した『除蝗録』は、害虫駆除の「注油法」を説く。これは平和な江戸社会が育んだ合理的技術で、戦国時代には不可能だった。
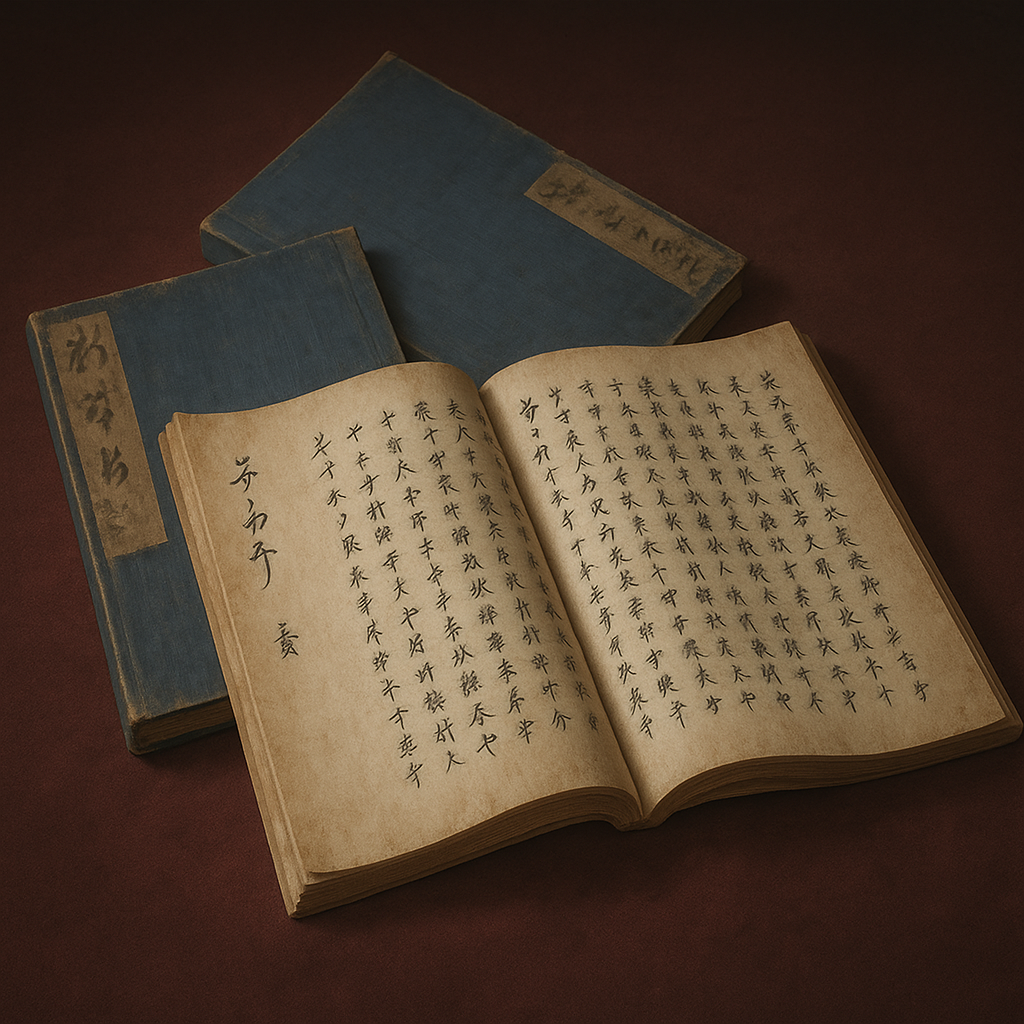
『除蝗録』の深層分析:戦国時代との比較史的考察を通してみる近世日本の技術と社会
序論:『除蝗録』研究の視座 ― 近世農学の到達点と戦国への問い
本報告書は、江戸時代後期の農学者、大蔵永常(おおくら ながつね)が著した農書『除蝗録(じょこうろく)』を、単なる一冊の技術書としてではなく、江戸後期という時代の社会、経済、文化が生んだ「統合的技術システム」の結晶として位置づける。その上で、戦国時代という「『除蝗録』が存在しえなかった世界」を対置し、比較史的アプローチを通じて、日本の近世化の特質と、その画期としての『除蝗録』の歴史的意義を徹底的に明らかにすることを目的とする。「戦国時代という視点」という要請に応え、一つの技術の有無が社会全体に与えうる影響を具体的に考察する。
「農聖」とまで称される大蔵永常の著作群は、机上の空論ではなく、彼自身が諸国を遍歴し、現場の農民との対話から得た知見に基づく、徹底した実践の書であった。この永常の遍歴活動そのものが、戦国時代には到底不可能であった「泰平の世」の産物である点は、看過されてはならない。彼の知識収集の方法論は、徳川幕府による全国支配が確立し、五街道をはじめとする交通網が整備され、庶民がある程度の安全を確保しながら広域を移動できる社会基盤に支えられていた。対照的に戦国時代は、領国間の境界が絶えず変動し、山賊や落ち武者狩りが横行するなど、領国を越えた自由な移動は極めて危険かつ困難であった。したがって、永常のように全国規模で知見を集約し、体系化するタイプの学者は、個人の才能の問題以前に、時代の構造的な制約によって戦国時代には生まれ得なかったのである。この事実は、『除蝗録』がその内容だけでなく、その成立過程においても江戸時代特有の所産であることを強く示唆している。
第一章:『除蝗録』の書誌学的・技術史的分析 ― 合理主義の曙光
第一節:著者・大蔵永常の実像と国益思想
大蔵永常は、商人から農学者へと転身した異色の経歴を持つ人物である。彼の視点は常に「富国」、すなわち経済的実利と深く結びついていた。彼の著作は、個々の農家の救済に留まらず、藩や国家レベルでの生産性向上を志向する、マクロな視点に貫かれている。『農具便利論』や『広益国産考』といった他の著作群と『除蝗録』を並べて分析すると、本書が彼の「国益増進」という一貫した思想体系の一部であることが明確になる。彼は、農業技術の改良こそが国を豊かにする基盤であると確信し、そのための具体的かつ実用的な方法論を生涯にわたって追求したのである。
第二節:『除蝗録』の内容詳解 ― 「注油法」という名の革命
『除蝗録』が刊行されたのは文政九年(1826年)である。この時期は、化政文化が爛熟し、商品経済が全国の隅々にまで浸透した時代であった。このような時代的文脈があったからこそ、本書は生まれ、そして広く受け入れられたのである。
本書が提示した技術の核心は「注油法(ちゅうゆほう)」と呼ばれる画期的な害虫駆除法である。その手順は極めて具体的かつ物理的であった。まず、水を張った水田に鯨油を撒き、油膜を水面全体に広げる。次に、数人で竹竿などを持ち、稲を揺すって株に付着した害虫を水面に払い落とす。水面に落ちた害虫は、油膜によって気門(呼吸孔)を塞がれ、窒息死するという仕組みである。
特筆すべきは、駆除対象の特定である。書名にある「蝗」は一般にイナゴを指すが、本書が主たる駆除対象として想定していたのは「浮塵子(ふじんし)」、すなわちウンカ類であった。これは、漠然とした「虫害」を対象とするのではなく、特定の害虫の生態を冷静に観察し、その習性に応じた対策を講じるという、近代的な病害虫学の萌芽と見なすことができる。
さらに、本書の普及に絶大な効果を発揮したのが、本文に添えられた木版画の絵図である。これらの図像は、注油法の具体的な作業手順を視覚的に示しており、文字の読解が必ずしも得意ではない農民層にも、技術の要点を直感的に理解させるための画期的な情報伝達手段であった。江戸時代の出版文化の成熟と、寺子屋教育の普及による一定水準の識字率の向上が、このような「ビジュアルな技術マニュアル」の大量生産と広範な流通を可能にしたのである。
永常の戦略的な思考は、代替案の提示にも表れている。彼は、鯨油が入手困難な地域や、価格面で導入が難しい農家のために、菜種油、魚油、荏油(えのあぶら)といった代替油の使用法を具体的に記している。この記述は、永常が鯨油を軸とする「全国市場」の存在を前提としつつも、その中での「地域格差」や「物流の限界」を正確に認識していた証左である。彼の視点は、全国に通用する普遍的な技術を提示しながら、同時にそれぞれの地域のローカルな実情にも配慮する、複眼的かつ実践的なものであった。なぜ彼は代替油を記したのか。第一に、鯨油は高価であり、特に海から遠い内陸部では入手が困難、あるいは経済的に見合わない場合があったからである。彼はその事実を、自らの全国遍歴を通じて肌で知っていた。第二に、彼の目的は単なる新技術の紹介ではなく、日本全国での「実装」と「普及」にあった。一部の富裕な地域だけの成功では、彼の目指す「国益」の増進 には繋がらない。このような全国的視野と地域的配慮の共存は、経済圏が細かく分断され、領国ごとの自給自足が原則であった戦国時代の領主や知識人には持ち得ない、統一国家ならではの発想であった。
第三節:『除蝗録』の革新性 ― 呪術から科学へ
『除蝗録』の真の革新性は、その技術的有効性もさることながら、その根底に流れる思想にあった。近世以前の害虫対策は、鉦や太鼓を打ち鳴らして害虫を他の村へ「追い払う」ことを目的とした「虫送り」や、神仏に豊作を祈願する祈祷といった儀礼的・呪術的な手法が中心であった。これらの方法は、害虫を人知を超えた存在、あるいは祟りとして捉え、「鎮める」「追い払う」という発想に基づいていた。
これに対し、「注油法」は害虫を物理的に「殺滅する」という、直接的かつ合理的な発想に立脚している。これは、自然現象を冷静に観察し、原因(害虫)を特定し、物理法則(油は水に浮き、虫の気門を塞いで窒息させる)を利用して問題を解決するという、紛れもない科学的思考の表れである。ここに、日本社会における世界観の大きな転換点、すなわち、自然を畏怖の対象としてだけでなく、観察し、理解し、統御可能な対象と見なし始めた精神の近代化を見出すことができるのである。
第二章:江戸後期という時代背景 ―『除蝗録』を可能にした社会システム
第一節:泰平の世と農業生産の飛躍
『除蝗録』のような高度な農書が生まれ、普及するためには、それを支える社会経済的基盤が不可欠であった。二百数十年という長期間にわたって続いた平和は、日本の農業生産に飛躍的な発展をもたらした。大規模な新田開発が各地で進められ、治水・灌漑技術も向上し、全国の石高は著しく増大した。農業生産の安定と向上は、さらなる技術改良への意欲と投資を促す社会的な土壌を形成した。
同時に、農村経済の構造も大きく変化した。米だけでなく、木綿、菜種、藍、紅花といった商品作物の栽培が全国に広がり、農民は自給自足の生活から、貨幣経済の論理に深く組み込まれていった。この変化は決定的であった。鯨油のような「購入する生産資材」を農業に投下するという、戦国時代には考えられなかった経済行動が、江戸時代後期には現実的な選択肢となったのである。農民は単なる食糧生産者から、市場を見据えた農業経営者へと変貌しつつあった。
第二節:知識と情報の流通革命
江戸時代は、知識と情報が爆発的に流通した時代でもあった。全国的な寺子屋の普及は、武士階級だけでなく庶民層の識字率をも著しく向上させた。これと並行して、木版印刷技術が高度に発展し、書籍が比較的安価で大量に生産される出版文化が爛熟期を迎えた。『除蝗録』が、一人の学者の書斎に眠るのではなく、大量に印刷・販売され、全国の村々にまで届いた背景には、この書籍流通という「情報インフラ」の存在が不可欠であった。
この時代、多くの農書が出版され、一つのジャンルとして確立した。これにより、優れた篤農家や学者の知見は、特定の家や流派が独占する「秘伝」から、誰もが費用を払えばアクセス可能な「共有財産」へとその性格を変えた。知識が閉鎖的な集団内でのみ継承された中世・戦国時代との、これは決定的な違いであった。
第三節:捕鯨業という巨大産業の勃興
『除蝗録』の根幹を支える「注油法」は、その主たる資材である鯨油の安定供給なしには成立し得ない。その供給源となったのが、江戸時代に巨大産業へと発展した日本の捕鯨業である。
特に紀州(現在の和歌山県)、土佐(高知県)、西海(長崎県北部など)を中心とした地域では、「網取式捕鯨」という高度な技術が開発された。これは、多数の船団が連携して鯨を網に追い込み、銛で仕留めるという大規模かつ組織的な漁法であった。この漁法を実践するためには、巨大な資本を投下して船や網を整備し、多くの漁師や職人を雇用・組織化する必要があった。こうして生まれた「鯨組」と呼ばれる分業制の経営体は、単なる漁撈活動の集団ではなく、計画性、組織性、資本集約性を備えた近世日本の代表的な「産業」であった。
鯨組によって生産された鯨油は、当初は主に灯火用として利用されたが、やがてその用途は拡大する。鯨の骨や肉粕は、貴重な肥料(金肥)として農業生産に貢献し、そして鯨油は『除蝗録』が示すように、画期的な農薬として新たな価値を見出された。これらの鯨関連商品は、菱垣廻船や樽廻船といった海運業者によって、全国的な流通網に乗せられた。西日本の生産地から、消費地であると同時に巨大な集散地でもあった大坂や江戸の市場へと効率的に輸送・供給されるシステムが確立していたのである。
ここに、『除蝗録』の成功を支えた極めて重要な構造が見えてくる。それは、農業分野だけの閉じた話ではなく、「海(捕鯨業)が陸(農業)を支える」という、異業種間のダイナミックな相互依存関係、すなわち産業連関の上に成り立っていたという事実である。この構造こそが、江戸時代後期の成熟した経済システムの証左に他ならない。「注油法」の普及には大量の鯨油が必要であった。その鯨油は、網取式という技術革新と巨大資本に支えられた鯨組によって生産された。そしてその鯨油は、西廻り・東廻り航路という安定した海運と、大坂・江戸という中央市場の存在によって全国に行き渡った。これら産業、技術、資本、物流のすべては、戦乱のない「泰平の世」でなければ決して成立し得ないものであった。したがって、『除蝗録』は、一冊の農書であると同時に、江戸時代の産業と物流の到達点を示す、壮大な社会システムの記念碑でもあるのだ。
第三章:戦国時代の農業と蝗害 ―『除蝗録』不在の世界
第一節:戦乱が蝕む大地
時代を遡り、戦国時代の農村に目を向けると、そこには江戸時代とは全く異なる過酷な現実が広がっていた。兵農分離が未成熟なこの時代、農民は領主の命令一下、兵士として頻繁に戦場へ動員された。その結果、田植えや収穫といった重要な農作業が中断、あるいは放棄されることは日常茶飯事であった。さらに、敵軍による意図的な破壊活動、すなわち収穫前の稲を刈り取る「青田刈り」や、集落そのものを焼き払う放火も横行し、農業生産基盤に壊滅的な打撃を与えた。恒常的な労働力不足と、戦乱による農地の直接的な荒廃が、食糧生産の極端な不安定化を常態化させていたのである。
第二節:蝗害 ― 天災か人災か
このような脆弱な農業基盤を、自然災害が容赦なく襲う。特に蝗害、すなわちイナゴ(蝗)の大発生は、しばしば大規模な飢饉の引き金となった。『後奈良天皇宸記』などの同時代史料には、享禄四年から五年にかけて(1531-1532年)、西日本一帯を襲ったイナゴの大発生が、深刻な「享禄の飢饉」を引き起こしたことが記録されている。この蝗害は、ただでさえ戦乱で疲弊した社会に追い打ちをかけ、夥しい数の餓死者と流民を生み、社会不安を極度に増大させた。
当時の人々は、こうした害虫の大発生という現象を、合理的に理解し、対処する術を持たなかった。彼らにとってそれは、神仏の祟りや、為政者の不徳が招いた天罰と解釈された。それゆえ、対策は盛大な祈祷や、前述の「虫送り」といった儀礼に頼らざるを得なかったのである。戦乱という人為的な「災い」と、蝗害という自然の「災い」は、当時の人々の心性において分かちがたく結びついていた可能性がある。予測不能な暴力が日常を支配する世界では、自然の猛威もまた、人知を超えた存在の仕業と解釈されやすい。合理的な対策が生まれなかった背景には、こうした時代の「精神構造」も深く関わっていたと考えられる。安定した世界が合理主義を育むのに対し、混沌とした世界は呪術的思考と高い親和性を持つのである。
第三節:技術的・社会的「壁」の分析
ではなぜ、戦国時代に「注油法」のような革新的な技術が生まれなかったのか。その要因は、複合的かつ構造的な「壁」の存在によって説明できる。
第一に、 科学的知見の欠如 である。害虫の生態に関する断片的な経験的知識は存在したかもしれないが、それを体系化し、物理的法則に基づいた対策を考案するような科学的思考が、社会全体として未発達であった。
第二に、 情報共有網の不存在 である。領国が細かく分断され、領主たちが互いに敵対しあう状況では、仮にどこかの地域で有効な技術が生まれても、それが国境を越えて全国に共有されることはあり得なかった。むしろ、食糧増産に直結するような重要技術は、敵に利することのないよう「軍事機密」に準ずるものとして秘匿された可能性すら高い。
第三に、そしてこれが最大の障壁であるが、 資材調達の絶望的困難 である。注油法に不可欠な鯨油を工業的に生産するような大規模な捕鯨産業は、影も形も存在しなかった。また、仮に沿岸部で少量の鯨油が生産されたとしても、それを山賊や敵兵の危険が満ちる内陸部まで、安全かつ大量に運ぶ全国的な商業流通網は存在しなかったのである。菜種油などの植物油も、その生産量は限られており、まずは貴重な食用や灯火用として優先された。広大な水田に農薬として大量に投入できるほどの生産余力は、到底望むべくもなかった。
第四章:歴史的仮説 ― もし戦国大名が『除蝗録』を手にしたら
第一節:富国強兵の切り札? ― 石高と領国経営への影響
ここで一つの思考実験を試みたい。もし、ある戦国大名が何らかの奇跡によって『除蝗録』の技術を手に入れ、領内で実践できたとしたら、何が起こっただろうか。
まず考えられるのは、領国経営の劇的な安定化である。注油法によって蝗害による収穫減を抑制できれば、食糧生産は飛躍的に安定する。安定した年貢収入は、大名の財政基盤を直接的に強化し、より多くの兵士を雇い、より良い武具を揃えることを可能にする。また、飢饉のリスクが低減すれば、領民が餓えて他国へ逃散することを防ぎ、領主への支持と求心力を高めることができる。これは、常に飢饉と一揆の脅威に晒されていた他の大名に対する、決定的なアドバンテージとなり得たであろう。まさに「富国強兵」の切り札となる可能性を秘めていた。
第二節:兵站革命 ― 軍事行動へのインパクト
軍事面への影響はさらに大きい。戦国時代の軍事行動の成否を左右する最大の要因は、武器の性能以上に兵糧、すなわち兵站であった。安定した食糧供給は、長期間の遠征や、敵城に対する執拗な包囲戦を可能にする。例えば、織田信長の石山本願寺攻めや、豊臣秀吉の鳥取城・高松城攻めのような大規模な兵糧攻めにおいて、自軍の兵糧が盤石であることは、戦術的な絶対的優位性をもたらしたであろう。『除蝗録』は、間接的にではあるが、戦争の様相すら変えうるポテンシャルを秘めていたと言える。
第三節:越えられぬ「時代の壁」
しかしながら、上記の仮説は、技術の導入を阻む構造的な障壁を無視した、あくまで「絵に描いた餅」に過ぎない。なぜ『除蝗録』が戦国時代では機能し得なかったのか、その結論は明白である。
最大の障壁は、繰り返しになるが鯨油の供給問題である。仮に戦国大名が紀伊や土佐の沿岸部を一時的に支配したとしても、それは点と線の支配に過ぎず、江戸時代の鯨組のような産業レベルの生産体制と、全国への安全な輸送ルートを確立することは不可能であった。
さらに、統治能力の限界も存在する。技術を領内全域に普及させるには、情報を末端の村々まで正確に伝達する行政システムと、農民を指導する人材(読み書きができ、技術を理解した役人や村役人)が不可欠である。戦国時代の統治機構は、何よりも軍事と徴税に特化しており、このような民生技術の普及を目的とした、きめ細やかな行政能力は備えていなかった。
そして根本的な問題として、社会の優先順位の違いがある。明日の戦いに勝つことが何よりも優先される世界において、効果が数年、数十年単位で現れる農業技術への体系的な投資は、どうしても後回しにされざるを得ない。大名の関心は、直接的な戦力である鉄砲や馬の調達に向かい、田に撒く油にまで及ぶ余裕はなかったであろう。
以下の表は、これまでの議論を要約し、二つの時代の構造的な差異を視覚的に示したものである。
表1:戦国時代と江戸後期における農業技術関連システムの比較
|
比較項目 |
戦国時代(15世紀末~16世紀末) |
江戸時代後期(18世紀末~19世紀中頃) |
|
政治体制 |
分裂・抗争(群雄割拠、実力主義) |
統一・安定(幕藩体制、世襲制) |
|
経済システム |
荘園制の解体、地域経済圏の分立、自給自足が基本 |
全国規模の市場経済、藩経済と「天下の台所」大坂の連動 |
|
主要な害虫対策 |
祈祷、虫送り、人海戦術による捕殺(呪術的・儀礼的) |
注油法、その他合理的・経験的農法の確立(科学的・物理的) |
|
技術・知識の伝達 |
口伝、秘伝。限定的・閉鎖的(一子相伝、流派) |
出版文化の隆盛(木版印刷)、農書の普及。広範・開放的 |
|
鍵となる資材(鯨油) |
ほぼ入手不可能。産業として未成立。 |
専門の捕鯨集団による産業化、全国への流通網確立。 |
|
社会の優先課題 |
軍事力の強化、領土の拡大・維持(生存競争) |
経済の発展、民生の安定、藩財政の健全化(統治の安定) |
|
支配者の役割 |
軍事指導者、征服者 |
行政官、経営者 |
この表が示すように、『除蝗録』の成立と普及は、単一の要因ではなく、政治、経済、技術、情報、資材といった社会システム全体の成熟の結果であったことがわかる。
結論:『除蝗録』が映し出す時代の相貌
本報告書の分析を通じて明らかになったのは、『除蝗録』が単なる一冊の優れた農書ではないという事実である。それは、江戸時代という二百数十年間の平和が育んだ、 ①合理的精神、②全国規模の産業連関、③情報共有インフラ という三つの要素が奇跡的に結実した「時代の記念碑」なのである。
戦国時代との比較は、この記念碑を打ち立てるために、日本社会がどれほど巨大な構造変革を必要としたかを鮮明に浮き彫りにする。それは、単なる技術の進歩の物語ではない。政治の安定、経済の統合、社会の成熟、文化の変容、そして自然を統御の対象と見なし始めた人々の世界観そのものの変容の物語であった。戦国時代に『除蝗録』が存在しなかったのは、鯨油がなかったからという単純な理由だけではない。その技術を受容し、実装し、普及させるための社会システム全体が、まだ存在していなかったからである。
大蔵永常という一人の農学者の業績は、近世日本が到達した一つの極点を示すものであった。そして、彼の著作に貫かれた合理主義と実学の精神は、飢饉に苦しむ同時代の人々を救っただけでなく、明治維新以降の日本の近代化を準備する、重要な思想的遺産の一つとなった。彼の視線は、過去から続く農民の苦難を直視し、未来の日本の礎を築く、壮大な時間軸の中にあったと言えるだろう。