陰徳太平記
『陰徳太平記』は江戸中期に編纂された西国戦国史の軍記物語。毛利氏の興隆を描き、岩国藩の政治的意図も反映。史実と創作が混在するが、当時の歴史認識を伝える貴重な史料。
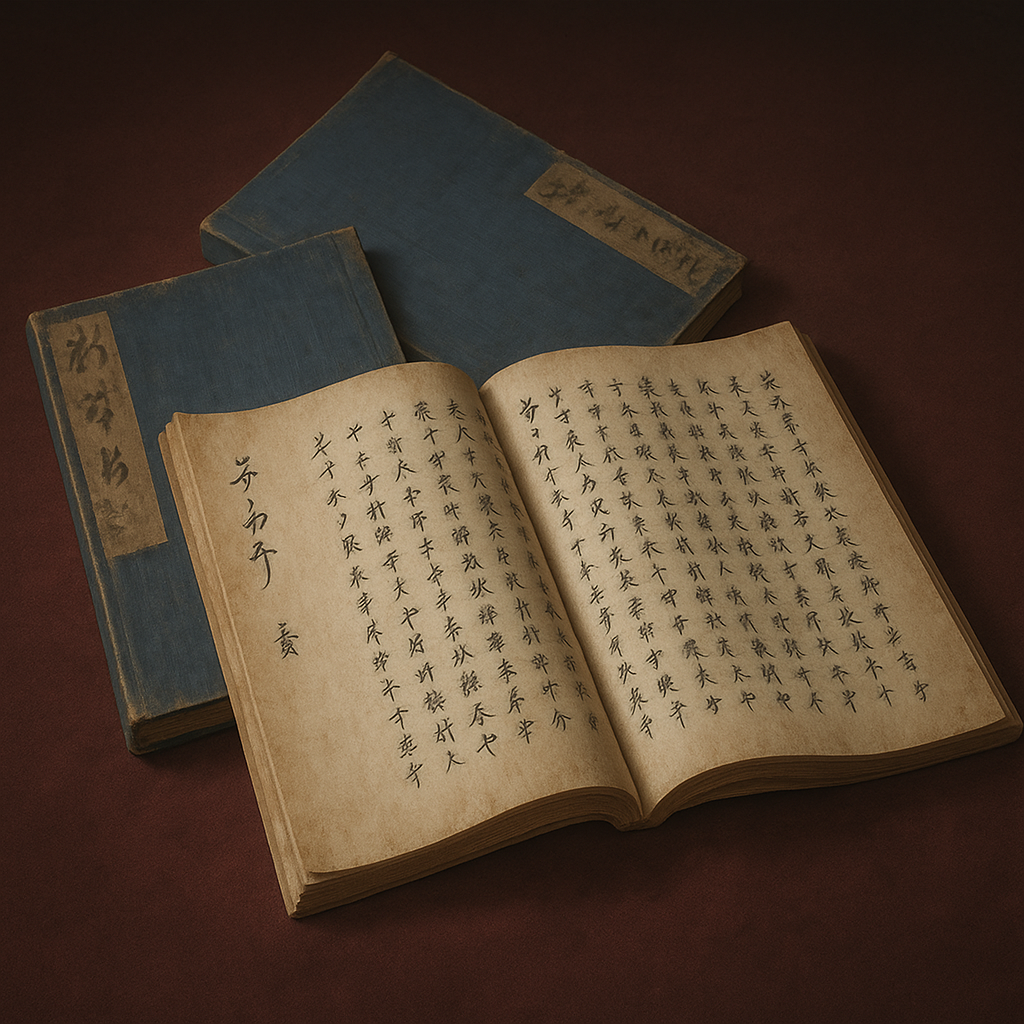
『陰徳太平記』の総合的分析 ― 戦国叙事詩の成立と受容
序論:江戸時代が生んだ西国戦国史の巨編
『陰徳太平記』は、戦国時代から安土桃山時代にかけての西国の動乱を、毛利氏の興隆を主軸に描いた壮大な軍記物語である。しかし、本書を単に過去の出来事を記録した歴史書として捉えることは、その本質を見誤ることになる。本書は、戦乱の記憶が遠のいた泰平の世、すなわち江戸時代中期に、特定の政治的、文化的意図をもって編纂・出版された「物語られた歴史」として位置づけられるべきテクストである 1 。
本書の成立は、周防岩国藩の家老であった香川正矩と、その次男・景継(宣阿)という父子二代にわたる一大事業であった 1 。その編纂の背景には、父・正矩の主家への忠誠と歴史記録への執念、子・景継による文学的潤色、そして岩国藩そのものが抱える政治的思惑という、三重の構造が存在する。正式名称を『関西陰徳太平記』ということからも 2 、本書が南北朝時代の軍記物語の金字塔である『太平記』を規範とし、それに比肩する西国版の戦国叙事詩を志向した壮大な試みであったことが窺える。
本報告書は、この『陰徳太平記』について、その成立の背景から、物語の構造と内容、史料としての価値、そして後世に与えた影響に至るまでを多角的に分析し、その全体像を明らかにすることを目的とする。
第一部:『陰徳太平記』の成立 ― 父子二代の編纂事業と岩国藩の思惑
本章では、『陰徳太平記』が単なる文学作品としてではなく、江戸時代の複雑な政治力学の中で生まれた産物であることを、著者父子の動機と藩の戦略という二つの側面から解明する。
第一節:原作『陰徳記』の誕生 ― 家老・香川正矩の執念
『陰徳太平記』の源流は、香川正矩が著した『陰徳記』にある。正矩は慶長18年(1613年)、岩国領主吉川氏の家老職を務める安芸香川氏の一族として生まれた 7 。彼が生きた時代は、戦国の動乱が終息し、武士が武功ではなく文事によって身を立てることを求められる過渡期であった。そのような時代背景の中、正矩は主家である吉川氏の輝かしい武功と、その歴史的正当性を後世に伝えることに自らの使命を見出し、『陰徳記』の編纂に着手したのである 7 。
その執筆態度は極めて真摯なものであった。正矩は、既存の文書や記録のみに依存することなく、自ら古老を訪ねて聞き取りを行い、さらには諸国へ調査員を派遣して広範な資料を収集したと伝えられている 8 。この徹底した資料収集こそが、後に『陰徳太平記』へと発展する物語の堅固な骨格を形成した。
全81巻からなるこの大部の軍記は、万治3年(1660年)に完成し、藩主吉川広正に献上された 2 。藩の公式な歴史書、すなわち「正史」としての性格を帯びていた可能性も指摘されるが、広正はこれを世間に流布させることを望まず、結果として『陰徳記』は木版刊行されることなく、写本としてのみ一部で伝えられるに留まった 2 。
第二節:『陰徳太平記』への大成 ― 香川景継(宣阿)による潤色と増補
父・正矩の死後、その遺志を継いだのが次男の香川景継であった。正保4年(1647年)に生まれた景継は、梅月堂宣阿と号した歌人でもあり、豊かな文学的素養を持っていた 9 。彼は単に父の遺稿を整理するにとどまらず、それに大胆な「潤色」と「増補」を施し、新たな軍記物語として『陰徳太平記』を大成させたのである 1 。
景継の作業は、乾いた骨組みに血肉を与えるようなものであった。例えば、永禄4年(1561年)の関門海峡における毛利・大友両軍の「門司城合戦」に関する記述を見ると、その違いは明らかである。『陰徳記』では約千字で比較的簡潔に述べられているのに対し、『陰徳太平記』では登場人物や地名が格段に増やされ、海峡を挟んで対峙する両軍の緊張感や合戦の具体的な描写が加わり、読者に強い臨場感を与える物語へと変貌している 1 。
景継は父が集めた資料に加え、さらに広範な地域の伝承や逸話を積極的に取り込むことで、物語性を飛躍的に高めた 1 。これにより、『陰徳太平記』は単なる記録の集成ではなく、通読に耐えうる面白さを備えた文学作品としての性格を強く持つに至ったのである 1 。この景継による改訂作業は元禄8年(1695年)頃に完成し、正徳2年(1712年)に大坂の書店から刊行され、広く世に知られることとなった 1 。
第三節:出版の政治的背景 ― 岩国吉川家の「家格」を巡る闘争
『陰徳太平記』の出版は、単なる文学的事業ではなかった。それは、江戸時代中期の岩国藩が、宗家である萩藩(毛利本家)に対して自らの「家格」の正当性を主張するために行った、高度な政治的プロパガンダ(宣伝活動)としての側面を色濃く持っていた。
関ヶ原の戦いの結果、毛利氏は大幅に減封され、その支藩であった岩国吉川家の立場も微妙なものとなった。萩藩は岩国藩主を直臣ではなく「陪臣(家臣の家臣)」として扱ったが、岩国側はこれを不服とし、幕府への直接の働きかけを通じて大名への昇格を目指す「家格昇進運動」を粘り強く展開していた 2 。
まさにこの政治的緊張が続く中で、『陰徳太平記』の出版計画は進められた。資料によれば、この出版は「吉川家の家格の宣伝を主たる目的として」おり、「世上に流布する軍書に吉川氏の主張を織り込む一連の政治活動であった」と指摘されている 2 。つまり、本書における毛利元就や、その次男で吉川家の祖である吉川元春の英雄的な描写は、物語上の要請であると同時に、「毛利家を支えた中心は吉川家であり、断じて陪臣などではない」という政治的メッセージを世論に訴えかけるための戦略であった。
父・正矩の「主家の武功を後世に伝えたい」という純粋な動機から始まった編纂事業は、子・景継の代で、藩の存続をかけたより戦略的な広報活動へと昇華されたのである。物語の力を利用して世論を味方につけ、幕府に対するロビー活動を有利に進めようとした、岩国藩のしたたかな生存戦略の現れとして、『陰徳太平記』の出版を捉えることができる。
【表1】『陰徳記』と『陰徳太平記』の比較
|
項目 |
『陰徳記』 |
『陰徳太平記』 |
|
主著者 |
香川正矩 2 |
香川景継(宣阿) 1 |
|
成立年 |
万治3年(1660年) 2 |
元禄8年(1695年)完成、正徳2年(1712年)刊行 1 |
|
目的 |
主家吉川氏の武功と正当性の記録、後世への伝達 7 |
父の遺志継承に加え、吉川家の家格宣伝、物語としての普及 2 |
|
形態 |
写本のみ、非公開 2 |
木版による刊本、市販 2 |
|
文体・内容 |
比較的簡潔、骨格的。より史実に近いとされる 1 |
潤色・増補が多く、文学的・物語的。臨場感ある描写 1 |
|
史料価値 |
比較的高く、研究者も引用 3 |
「俗本」と批判されるが、当時の歴史認識を知る資料価値あり 3 |
第二部:軍記物語としての構造と内容
本章では、『陰徳太平記』がどのような物語世界を構築しているのか、その構成と内容を分析する。
第一節:『太平記』を規範とした壮大な構成
書名に『太平記』を冠していること自体が、本書の野心的な構想を物語っている。これは、南北朝時代の動乱を描いた軍記物語の最高傑作『太平記』を意識し、それに匹敵する西国版の戦国叙事詩を創造しようという編者の意図の表れである 1 。全81巻という長大な巻数も、その壮大さを物理的に示している 1 。
思想的基盤においても、『太平記』が儒教的な大義名分論や仏教的な因果応報思想を基調としていたように 15 、『陰徳太平記』もまた同様の思想的枠組みを持っている 3 。特に、書名の由来となった「陰徳」という概念は、本書の根幹をなすテーマである。これは中国の古典『淮南子』に見える「陰徳あれば必ず陽報あり(人知れず善行を積めば、必ず目に見える良い報いが現れる)」という思想に基づいている 3 。本書は、毛利元就の驚異的な成功を、この「陰徳」を積み重ねた結果としてもたらされた「陽報」として位置づけ、物語全体を貫く思想的支柱としているのである。
第二節:描かれた西国の興亡史
物語が扱う時間的範囲は、室町幕府10代将軍足利義稙が政争に敗れて都を追われ、西国の大大名である大内義興を頼った明応年間(1490年代後半)から筆を起こし、慶長3年(1598年)の豊臣秀吉の死と、それに伴う五大老の盟約で筆を置くまでの、約100年間に及ぶ 5 。
その舞台は中国地方を中心に、四国、九州にまで広がる 1 。物語の中核をなすのは、安芸の一国人に過ぎなかった毛利氏が、智将・元就の登場によって中国地方の覇者へと成り上がっていく過程である。そして、その覇業の過程で鎬を削った周防の大内氏、出雲の尼子氏、豊後の大友氏といった西国の雄族たちの栄枯盛衰が、縦横無尽に描かれる 5 。
本書の物語手法の特徴として、単一の時系列に沿って歴史を追うだけでなく、九州から山陰にまで広がる複数の戦線を同時に描くことで、歴史を立体的な「面」として捉えようとする試みが見られる 1 。これにより、読者は戦国時代の混沌とした状況を、あたかも巨大な擂り鉢の縁を移動しながら俯瞰するような、包括的な視点で体験することになる 1 。
【表2】『陰徳太平記』が描く主要な合戦と出来事の年表(抜粋)
|
年代 |
主要な出来事・合戦 |
主な登場人物 |
関連するテーマ |
|
1500年代初頭 |
尼子経久の月山富田城奪還 18 |
尼子経久、山中氏 |
下剋上、智謀 |
|
1517年 |
有田中井手の戦い(元就初陣) 1 |
毛利元就、武田元繁 |
元就の智将としての覚醒 |
|
1540-41年 |
吉田郡山城の戦い |
毛利元就、尼子晴久 |
毛利家の結束、籠城戦 |
|
1551年 |
大寧寺の変 |
陶晴賢、大内義隆 |
下剋上、因果応報 |
|
1555年 |
厳島の戦い 1 |
毛利元就、陶晴賢 |
元就の謀略の集大成、奇襲 |
|
1557年 |
防長経略、三子教訓状 21 |
毛利元就、隆元、元春、隆景 |
毛利家の安泰、息子への教え |
|
1560年代 |
第二次月山富田城の戦い、尼子氏滅亡 |
毛利元就、尼子義久、山中鹿介 |
毛利の中国制覇、尼子再興の誓い |
|
1570年代 |
尼子再興軍との戦い 23 |
山中鹿介、吉川元春、小早川隆景 |
英雄の悲劇、執念 |
|
1582年 |
備中高松城の戦い、本能寺の変 |
羽柴秀吉、清水宗治、毛利輝元 |
織田政権との対決、天下の転換 |
|
1598年 |
豊臣秀吉の死 |
豊臣秀吉、五大老 |
一時代の終焉 |
第三部:史料価値を巡る重層的評価
本章では、『陰徳太平記』が歴史研究においてどのように評価されているのか、その限界と有用性の両面から深く考察する。
第一節:「俗本」との批判 ― 『陰徳太平記』の限界
『陰徳太平記』は、歴史学会においてしばしば「俗本」、すなわち信頼性の低い通俗的な書物として厳しい評価を受けてきた 3 。その最大の理由は、本書が掲げる思想的テーマ、すなわち毛利元就を「陰徳の仁将」として理想化するために、「事実をまげながら」記述しているという点にある 3 。元就を称賛するという明確な目的のために、彼にとって都合の悪い事実は巧みに改変・削除され、輝かしい功績はさらに劇的な脚色が施されている 3 。
その典型的な事例が、吉川元春の夫人(新庄局)を巡る「醜女説」の創作である。本書は、元春の妻が「絶世の醜女」であったと記しているが、この説は本書の原作にあたる『陰徳記』で初めて登場し、それ以前の信頼できる史料には一切見られない 2 。この異様な記述の背景には、著者である香川氏が、同じ吉川家臣でありながらライバル関係にあった熊谷氏(新庄局の実家)を貶める意図があったと推測されている 7 。主君の妻の容姿を中傷するという、通常では考えられないこの逸話は、編者の個人的な感情や一族間の対立が歴史叙述に歪みをもたらした顕著な例であり、本書の客観性に対する根本的な疑念を抱かせるものである。
このように、本書には編者の主観、藩の政治的意図、そして物語を面白くするための創作が色濃く反映されている。したがって、そこに書かれている内容を無批判に史実として受け入れることは極めて危険であり、厳密な史料批判の目を向けることが不可欠である 3 。
第二節:歴史テクストとしての有用性
一方で「俗本」と批判されながらも、他方で「当時の人々の思想などを知る意味で、貴重な書物」 3 とも評価される。この一見矛盾した評価こそが、『陰徳太平記』の本質を捉える鍵となる。本書の真価は、戦国時代の「事実」を正確に伝える一次史料としてではなく、後代である江戸時代の人々が、過ぎ去った戦国時代をどのように認識し、解釈し、記憶していたかを示す「歴史意識の記録」としての価値にある。
この視点に立つと、史料としての「欠陥」そのものが、貴重な情報源へと転換する。例えば、毛利元就の徹底した理想化は、戦国時代の元就の実像というよりも、泰平の世となった江戸時代に求められた「理想の君主像」や「深謀遠慮の智将像」が投影された結果と読み解ける。また、山中鹿介の悲劇的な英雄像の強調は、武士の生き様が変質した時代に生きる人々が、過去の武士に寄せたロマンチシズムや忠義への憧憬の現れと解釈できる。
郷土史の解説書や観光地の案内板などで、学術的な正確さを度外視して本書の逸話が頻繁に引用される現象も 3 、この文脈で理解できる。それは、客観的な史実そのものよりも、地域の人々にとって親しみやすく、感情移入しやすい「語られた物語」の方が、地域の歴史文化を形成し、アイデンティティの拠り所としてより強く機能してきたことを示している。
したがって、『陰徳太平記』は、失われた伝承や逸話の宝庫であると同時に、江戸時代の人々の価値観や歴史観が結晶化した一種の「文化的なプリズム」であると言える。このプリズムを通して戦国時代を眺めることで、我々は史実の層のさらに奥にある、人々の心性や記憶のありようという、もう一つの歴史の側面に光を当てることができるのである。
第四部:『陰徳太平記』が描く英雄・智将・合戦
本章では、物語を彩る具体的なエピソードを取り上げ、『陰徳太平記』がいかにして英雄像を造形し、合戦のドラマを描き出したかを分析する。
第一節:毛利元就像の造形 ― 「三本の矢」の物語
本書の絶対的な主人公である毛利元就は、一貫して「陰徳陽報」を体現する智謀の将として描かれる 3 。彼の成功は、単なる武力や偶然によるものではなく、人知れず徳を積み、深く謀を巡らせた必然的な結果であると、物語は繰り返し強調する。
その象徴的な逸話が、元就が臨終の際に息子たちを呼び寄せ、結束の重要性を説いたとされる有名な「三本の矢」の教えである。一本の矢は容易に折れるが、三本束ねると折れにくいことを示し、兄弟の団結を諭したというこの物語は、本書を通じて広く知られるようになった。実際には、この逸話は元就が息子たちに宛てた直筆の長文の書状『三子教訓状』という史実を元にした創作である 21 。『陰徳太平記』は、この長く教訓的な手紙の内容を、誰にでも理解できる視覚的で印象的な物語へと見事に昇華させた。こうした逸話の創造を通じて、元就は卓越した謀将であると同時に、子孫の繁栄を願う理想的な家父長、そして深遠な教えを垂れる賢人としても描かれているのである。
第二節:悲運の英雄・山中鹿介の表象
主家である尼子氏が滅亡した後も、その再興という絶望的な戦いに生涯を捧げた武将・山中鹿介(幸盛)は、本書において最も読者の感情に訴えかける人物の一人として描かれている 1 。中でも、彼が三日月に「願わくは、我に七難八苦を与えたまえ」と祈ったとされる逸話は、その悲壮な決意と不屈の精神を象徴する場面として、後世の日本人の心に深く刻まれた。
『陰徳太平記』は、鹿介の武勇や智略、そして志半ばで謀殺される悲劇的な最期を極めてドラマチックに描き、彼を「忠義と執念の化身」として造形した 23 。その武名は「樵(きこり)の子供や猟師の老人までもが日常の会話にしたほど」 23 であったと記し、彼の存在が当時から既に伝説的なものであったことを強調している。ただし、物語の中には、例えば品川将員との一騎討ちの描写のように、毛利方の資料である本書と、尼子方の視点で書かれた『雲陽軍実記』とで勝敗の経緯が異なって記されている部分もあり、ここにもそれぞれの立場による叙述の違いが明確に表れている 23 。
第三節:クライマックス「厳島の戦い」の叙述
弘治元年(1555年)、毛利元就が陶晴賢率いる大内氏の大軍を、厳島において奇襲によって打ち破った「厳島の戦い」は、本書における最大のクライマックスの一つである 1 。
『陰徳太平記』は、この乾坤一擲の大勝負を、手に汗握る筆致で描き出す。元就が家臣の反対を押し切って暴風雨の夜を突き、厳島へ渡る決断を下す場面、兵力で圧倒的に劣る毛利軍が奇襲を成功させ、大混乱に陥る陶軍、そして逃げ場を失った大将・陶晴賢が自害に至るまでの過程が、鮮やかに叙述される 19 。敗軍の将である晴賢の最期もまた、栄華を極めた者の滅びゆく悲哀を込めて描かれており、軍記物語特有の仏教的な無常観が色濃く漂う。この戦いの劇的な勝利によって、元就の「謀将」としての評価は不動のものとなり、毛利氏が中国地方の覇者となる道が決定的に切り開かれたと、物語は力強く結論づけるのである。
結論:後世への影響と現代における意義
『陰徳太平記』は、その出版と流布を通じて、毛利元就を始祖とする西国戦国史の「正典」とも言うべき物語的イメージを、広く世に定着させる上で決定的な役割を果たした。本書で造形された英雄像や創作された逸話の数々は、後の時代の講談や演劇、そして現代の歴史小説や映像作品に至るまで、繰り返し参照され、再生産され続けている。
その影響は、中国地方の地域文化にも深く根付いている。石見神楽には本書に題材を得た演目が存在し 28 、各地の史跡案内や観光パンフレットでは、本書の記述が史実として紹介されることも少なくない 30 。幕末の第二次長州征伐を描いた瓦版が、幕府の目を憚って『陰徳太平記新図』という題で出版された例は 31 、本書の知名度の高さと、それが「戦記物」の代名詞として一般に認識されていたことを示す興味深い事例である。
現代において『陰徳太平記』を読むことの意義は、単に戦国時代の出来事を知ることには留まらない。それは、一つの歴史的事件が、後の時代の人々によってどのように記憶され、解釈され、そして特定の意図をもって「物語」として再構築されていくのか、そのダイナミックなプロセスを追体験することにある。史実と創作の境界を意識しながら本書を読み解くとき、我々は歴史の多層性と、それを語り継ぐ人間の営みの豊かさ、そして複雑さに触れることができる。それは、歴史学と文学が交差する地点に立つ、刺激的な知の探求の旅なのである。
引用文献
- 陰徳太平記 (香川宣阿) http://www.e-furuhon.com/~matuno/bookimages/7642.htm
- 陰徳太平記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B0%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98
- イマドキ『陰徳太平記』 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/sue-castle/intoku-taiheiki/
- 一乗谷ゆかりの刀剣 -籠手切正宗- - 福井県立図書館 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/01/20221222R/20221222.html
- 陰徳太平記(いんとくたいへいき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%99%B0%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98-33077
- 陰徳太平記. [首巻],巻第1-81 / 香河正矩 集編 - 早稲田大学 https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/ri05/ri05_02271/index.html
- 香川正矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E5%B7%9D%E6%AD%A3%E7%9F%A9
- 陰徳記 (香川正矩) http://www.e-furuhon.com/~matuno/bookimages/11729.htm
- 宣阿 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A3%E9%98%BF
- 香川正矩(かがわまさのり)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A6%99%E5%B7%9D%E6%AD%A3%E7%9F%A9-1287765
- 陰徳太平記 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1242136
- 吉川広家 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB22461347
- 錦帯橋-下巻-香川家長屋門 - 株式会社中野グラニット https://www.nakanog.co.jp/kintainakano64.html
- 参考資料(軍記) http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/shiryo/shiryo3.htm
- 太平記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E8%A8%98
- 太平記館 | ネットミュージアム兵庫文学館 - 兵庫県立美術館 https://www.artm.pref.hyogo.jp/bungaku/kikaku/taiheiki/
- 陰徳太平記(部分) - | 貴重資料画像データベース | 龍谷大学図書館 https://da.library.ryukoku.ac.jp/page/220824
- 陰徳太平記』曰く「尼子経久の陰謀 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/flower-palace/intoku-taiheiki-chapter-02-9/
- 山口歴史探訪 西国一の守護大名大内氏の足跡を訪ねて 20 大内義隆公終焉の地大寧寺 https://4travel.jp/travelogue/11890944
- 厳島の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 元就。とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%85%83%E5%B0%B1%E3%80%82
- 毛利元就の名言・逸話35選 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/63
- 山中鹿之助とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E9%B9%BF%E4%B9%8B%E5%8A%A9
- 布部山の戦いとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B8%83%E9%83%A8%E5%B1%B1%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 『陰徳太平記』が描く「大内氏の先祖について」(現代語訳) - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/flower-palace/intoku-taiheiki-chapter-06-2/
- 負傷者の四肢をもぎ取って、その肉を食べていた…豊臣秀吉による「史上最悪の兵糧攻め」の凄惨な光景 天下をとる前から出ていた豊臣秀吉の残虐性 (2ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/85846?page=2
- 山中鹿之助(山中幸盛)の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/97873/
- 近畿島根県人会だより - 第93号 https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/kikan/osaka/kenzinkai/kinki_kakehashi.data/kakehasi93.pdf
- CONTENTS - 石見大田法人会 http://www.iwamiohda.jp/wp-content/uploads/2024/04/202003_%E5%A4%A9%E9%A0%98-vol.67-compressed.pdf
- 第3章 史跡の概要 - 安芸高田市 https://www.akitakata.jp/akitakata-media/filer_public/e7/44/e744194c-2721-49ef-b5f9-3a5e0f25b894/shiseki-mouri-shi-shiroato-kouriyama-shiroato-hozon-katsuyou-keikaku-3shou-4shou-_.pdf
- ひろしまWEB博物館:陰徳太平記新図(福山市教育委員会蔵)/中国戦場大島郡記大炮大焼之図『陰徳太平記図会』(広島城蔵)/石州口周布之合戦(福山市教育委員会蔵)/九州小倉合戦図(福山市 https://www.mogurin.or.jp/museum/hwm/details/tenzi06/1/t06_1_g2_dai01.html