霞流砲術書
霞流砲術は、丸田盛次が諸流を学び創始した幻の砲術。上杉家で大筒運用に特化し、兼続の軍事改革を支えた。その技術は関之信に継承され関流として発展、土浦藩で現代に伝わる。
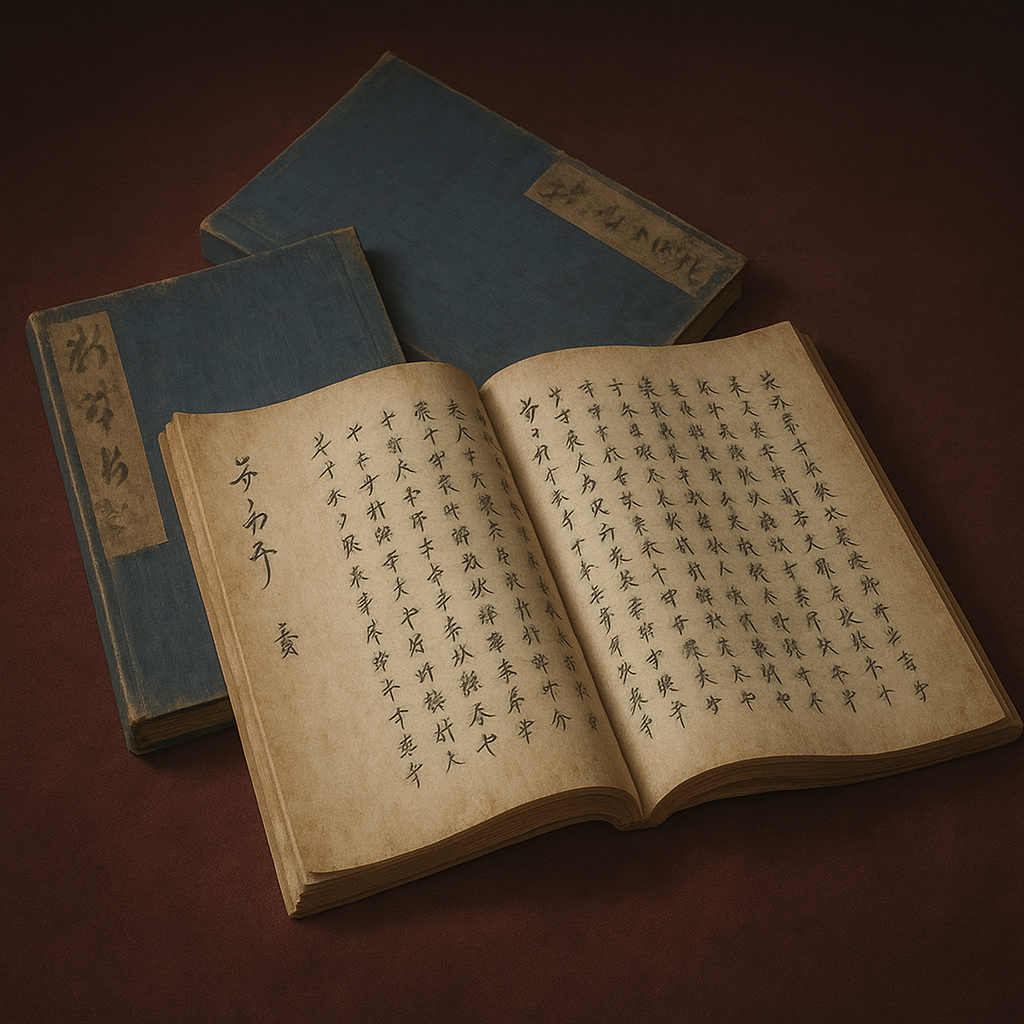
霞流砲術書の総合的考察:戦国期上杉家の軍事戦略と武芸の変容
序論:幻の砲術書「霞流砲術書」とその時代背景
日本の武芸史において、その名は伝わりながらも現存が確認されず、謎に包まれた伝書が数多く存在する。「霞流砲術書」もまた、その一つである。この書は、戦国末期から江戸時代初期にかけて活躍した砲術家・丸田盛次が創始した霞流砲術の極意を記したものとされ、特に大筒の扱いに秀でていたと伝えられている [ユーザー情報]。しかし、その具体的な内容や流派の全容は、断片的な情報の中に埋もれているのが現状である。
本報告書は、この「幻の伝書」をめぐる謎を解き明かすため、単に書物そのものを追うのではなく、より広範な歴史的文脈の中に霞流砲術を位置づけることを試みる。具体的には、霞流を創始した開祖・丸田盛次の人物像、彼が仕えた上杉家の軍事思想、そしてその技術を正統に継承した関流砲術という三つの視点から、多角的かつ徹底的な調査を行う。これにより、霞流砲術の実像を立体的に再構築することを目的とする。
本調査が直面する核心的な課題は、霞流砲術に関する直接的な一次史料が極めて乏しいという点にある。この困難を克服するため、本報告書では周辺史料を駆使するアプローチを採用する。すなわち、霞流を育んだ「土壌」である米沢藩の軍事思想と、その技術的「果実」と言える土浦藩の関流砲術を詳細に分析することを通じて、失われた霞流の実態を浮かび上がらせる。
報告書の構成として、まず第一章では、霞流が誕生した歴史的背景、すなわち上杉家の鉄砲戦略、特に重臣・直江兼続による先進的な軍備改革を詳述する。続く第二章では、開祖・丸田盛次の経歴と人物像に迫り、彼が如何にして霞流を創始するに至ったかを考察する。第三章では、現存する他流派の伝書や後継流派の記録を基に、「霞流砲術書」に記されていたであろう技術と思想の内容を再構築する。第四章および第五章では、霞流が関流へと継承され、土浦藩で発展・保存されていく過程を追い、その技術的特質と歴史的変遷を明らかにする。最後に結論として、これらの分析を総合し、霞流砲術が日本の武芸史において持つ独自の意義を総括する。
第一章:霞流誕生の土壌 ― 戦国期上杉家の鉄砲戦略と直江兼続
霞流砲術の誕生を理解するためには、その母体となった米沢藩上杉家の軍事思想、とりわけ戦国末期から江戸初期にかけての鉄砲に対する先進的な取り組みを深く考察する必要がある。この時代の軍備改革を主導したのが、上杉景勝の第一の重臣、直江兼続であった。霞流は、兼続が描いた壮大な軍事戦略の一環として、その必然性をもって生み出されたのである。
第一節:上杉謙信から景勝へ ― 鉄砲導入と軍事思想の変遷
鉄砲が日本に伝来したのは天文12年(1543)とされ、織田信長を筆頭とする戦国大名たちはその威力に着目し、導入を進めた 1 。上杉謙信もまた、この新しい兵器の重要性を認識し、その導入に力を入れたと伝えられる 1 。永禄2年(1559)の上洛の際には、将軍足利義輝から鉄砲と火薬の調合法を伝授された記録も残り、第四次川中島の戦いでは鉄砲隊を編成したとも言われる 2 。
しかし、謙信の時代における鉄砲は、まだ主力兵器としての地位を確立するには至っていなかった可能性がある。越後国が鉄砲の主要生産地である近江や堺から地理的に離れていたこと、そして雨雪の多い気候が火縄銃の運用に不利であったことなどが、その要因として考えられる 2 。
上杉家の鉄砲戦略が本格的な転換点を迎えるのは、次代の上杉景勝と、その家臣・直江兼続の時代である。特に関ヶ原の戦いを経て会津120万石から米沢30万石へと大減封された後、限られた国力で軍事力を最大化する必要に迫られた上杉家にとって、鉄砲は「戦用第一の利器」として極めて重要な位置を占めることになった 3 。この戦略的判断こそが、後の霞流誕生の直接的な背景となる。
第二節:直江兼続の軍備改革と専門家集団の形成
直江兼続は、鉄砲戦力の強化を藩の最重要課題と位置づけ、体系的かつ大規模な改革を断行した。その取り組みは、単なる兵器の導入に留まらず、生産、訓練、組織化の全てに及ぶものであった。
第一に、兼続は鉄砲の国産化と量産体制の構築に着手した。慶長9年(1604)、彼は鉄砲鍛冶の名産地である江州国友村と和泉堺から、吉川惣兵衛や泉谷松右衛門といった高名な鉄砲師を招聘した 4 。そして、人目を避けることができる山中の白布高湯に鍛冶工場を設け、秘密裏に1000挺もの火縄銃を製造させたと伝えられる 4 。これは、藩の軍事機密を保持し、先進技術を独占しようとする兼続の強い意志の表れであった。
第二に、鉄砲隊の組織化と訓練の制度化を進めた。兼続は「鉄砲稽古定」と称される十五ヵ条の規則を制定し、射撃技術のみならず、火薬や火縄の管理、稽古における心構え、組織運用といった細部に至るまで厳格な規定を設けた 5 。さらに、城下に鉄砲隊の専門部隊が居住する「鉄砲町」を設けるなど、鉄砲組を常備戦力として制度的に確立した 5 。
第三に、兼続は多様な砲術流派の専門家を積極的に招聘した。上杉家には、集団戦術に優れた岸和田流、実践的な射法で知られる稲富流、そして基礎技術である種子島流など、それぞれに特徴を持つ流派が複数伝来していた 1 。これは、単一の技術に固執するのではなく、異なる特性を持つ技術を藩内で競わせ、あるいは組み合わせることで、総合的な火力を高めようとする兼続の高度な戦略的思考を反映している。この専門家集団の中に、後に霞流を創始する丸田盛次も含まれていたのである 3 。
第三節:「上杉の雷筒」の威信と霞流の萌芽
兼続による軍備改革の成果は、慶長19年(1614)に勃発した大坂冬の陣で遺憾なく発揮された。この戦いで上杉軍は、680挺の鉄砲に加え、50挺もの大筒を戦場に投入した 5 。その大筒が放つ轟音と破壊力は「上杉の雷筒」と敵方から恐れられ、戦局に大きな影響を与えたと伝えられている 5 。
この「上杉の雷筒」の威信を技術的に支えたのが、大筒の専門家たちであった。霞流の開祖・丸田盛次は、まさしくこの大筒運用のスペシャリストとして上杉家に招聘されたと考えられる。米沢藩が導入した他の流派、例えば稲富流が集団での連続射撃を得意としたのに対し、霞流は藩が戦略的に求める特定の軍事能力、すなわち「大筒による敵拠点制圧能力」を専門に担う特殊技術として、他の流派とは異なる独自の位置づけで発展していった可能性が極めて高い。
霞流の創始は、丸田盛次という一個人の武技探求の成果であると同時に、直江兼続が藩の存亡をかけて主導した「米沢藩軍事力近代化」という壮大な藩営プロジェクトの産物であったと結論づけることができる。霞流の技術は、藩の戦略的ニーズに直接応える形で磨かれた「特殊兵器運用術」であり、その教えを記した「霞流砲術書」もまた、藩の重要な軍事機密としての性格を帯びていたと推察される。これが、この伝書が一般に広く流布することなく、その存在が謎に包まれる一因となったのかもしれない。
|
【表1】米沢藩における主要砲術流派の比較 |
|
|
|
|
|
流派名 |
流祖(または主要師範) |
伝来時期(推定) |
技術的特徴 |
米沢藩での役割(推定) |
|
岸和田流 |
(唐人秀正が学ぶ) |
天正14年(1586)頃 |
鉄砲の早込之法、集団戦術 |
鉄砲隊の基本的な組織運用法の導入 1 |
|
稲富流 |
大熊伝兵衛 |
慶長年間(1596-1615) |
実戦的な集団射法(段撃ち等)、膝撃ちを主とする 9 |
歩兵部隊の中核となる火力支援、野戦における制圧射撃 3 |
|
種子島流 |
丸田盛次(が学ぶ) |
慶長年間(1596-1615) |
鉄砲の基礎技術、片桐少輔より伝わる 6 |
全ての砲術の基礎となる基本技術の提供 |
|
霞流 |
丸田盛次 |
慶長年間(1596-1615) |
大筒の扱いに特化、遠距離・対物射撃 [ユーザー情報] |
攻城戦における拠点破壊、戦略的目標への精密射撃 3 |
|
逸韓流 |
- |
江戸初期 |
(詳細不明) |
藩内での技術的多様性の確保 6 |
この表は、米沢藩という一つの「実験場」に、目的別に多様な砲術流派が集められていたことを示している。稲富流が野戦における面制圧を担う「歩兵砲」的な役割を果たしたとすれば、霞流は攻城戦や特殊目標の破壊を担う「工兵砲」的な役割を期待されていたと推測できる。この機能分化こそ、直江兼続の合理的かつ先進的な軍事思想の証左である。
第二章:開祖・丸田盛次の実像と霞流の創始
霞流砲術を理解する上で、その創始者である丸田九左衛門盛次(まるた くざえもん もりつぐ)の人物像を明らかにすることは不可欠である。彼は単なる一介の砲術家ではなく、戦国の実戦経験と諸国の先進技術を統合し、一つの流派を確立した、卓越した技術者であり教育者であった。
第二節:丸田九左衛門盛次の経歴と修行
丸田盛次の出自に関する詳細な記録は少ないが、織豊時代から江戸時代前期にかけて活躍した砲術家であったことが確認されている 7 。彼の砲術の基礎は、片桐少輔に学んだ種子島流にあった 7 。種子島流は、鉄砲伝来の地の名を冠する通り、日本の砲術の源流の一つであり、盛次が確固たる基礎技術の上に自身の体系を築き上げたことを示唆している。
彼の経歴を語る上で特筆すべきは、「諸国を巡って18人の師に学び、その全てで免許皆伝を得た」という伝承である [ユーザー情報]。この逸話の真偽を完全に証明することは困難であるが、これは盛次の人物像を象徴する重要な情報である。特定の流派の枠内に留まることなく、全国の優れた技術を貪欲に吸収し、それらを比較検討、統合昇華させることで独自の高みへと至った、彼の飽くなき探究心と卓越した技量を物語っている。彼は、戦国乱世という技術革新の坩堝の中で、最も効果的な技術を求めて旅を続けた、実践的な研究者であったと言えよう。
第二節:上杉家における役割と活動
諸国での修行を終えた盛次は、出羽米沢藩主・上杉景勝に仕官する 7 。彼が招聘された時期は、まさしく直江兼続が藩を挙げて軍備改革を進めていた時期と重なる。盛次は兼続のもとで鉄砲組の整備に深く関与し、その専門知識を藩の軍事力強化のために注ぎ込んだ 7 。
米沢藩の史料によれば、盛次は稲富流の専門家であった大熊伝兵衛らと共に「代々鉄砲頭として努める」と記されており 3 、藩の砲術部門において最高位の指導者の一人であったことがわかる。これは、彼が単に一個人の技量に優れるだけでなく、部隊を組織し、訓練を施し、藩の戦略目標に沿って砲術部隊を運用する能力を持った、高度な軍事技術者であったことを示している。
これらの豊富な実戦経験、諸国で学んだ多様な技術、そして上杉家での組織運営の知見を統合し、盛次はついに自身の流派「霞流」を創始するに至る 7 。これは、単なる技術の寄せ集めではなく、独自の理論、射法、そして思想に裏打ちされた、一つの完成された武芸体系が誕生したことを意味する。
第三節:「霞」の名称に込められた意味の考察
流派名である「霞」には、この流儀の技術的、思想的な核心が込められていると考えられる。その意味については、複数の解釈が可能である。
第一に、 技術的な解釈 として、大筒の発射時に生じる膨大な白煙が「霞」のようであることから、流派の得意とする大筒射法そのものを象徴するという説である。敵の視界を遮るほどの煙の中から放たれる必殺の一撃は、まさに霞の中から現れる龍の如き威容を誇ったであろう。
第二に、 弾道学的な解釈 として、遠距離射撃における高度な技術を指すという説である。標的が遠く霞んで見えるような状況下で、風や湿度を読み、弾道を計算して正確に命中させる技術の妙を「霞」という言葉で表現した可能性が考えられる。これは、後継の関流が照準具(櫓)の研究に力を入れていたことからも裏付けられる 12 。
第三に、 思想的・秘伝的な解釈 として、「霞」という捉えどころのない言葉が、容易には窺い知ることのできない奥義や、心眼といった精神的な境地を象徴するという説である。同時代の砲術流派である稲富流には、鳥の鳴き声だけを頼りにその姿を見ずに撃ち落としたという逸話が残るように 13 、当時の名人たちの射術は、五感を超えた領域にまで達していた。霞流もまた、単なる物理的な射撃技術に留まらず、精神を研ぎ澄まし、敵の気を読むといった高度な精神性を重視していた可能性があり、「霞」はその象徴であったのかもしれない。
丸田盛次は、単なる射撃の名人ではなかった。彼は、戦国の実戦から得た多様な技術を体系化する「研究開発者」であり、藩の軍事組織を指導する「マネージャー」であり、そして次代にその技術と思想を伝える「教育者」でもあった。彼の最も著名な弟子である関八左衛門之信に対し、霞流の奥義を授けた上で、独立した流派「関流」を称することを許したという事実は 12 、盛次が自身の技術を独占するのではなく、その発展と普及を願う、懐の深い宗家であったことを示している。この多面性こそが、霞流という一つの流派を確立し、後世に大きな影響を与える関流を生み出す原動力となったのである。
第三章:「霞流砲術書」の内容再構築 ― 伝書から読み解く技術と思想
「霞流砲術書」そのものは現存が確認されていない。しかし、同時代の砲術流派の伝書や、霞流を正統に継承した関流に残された膨大な資料を分析することで、その失われた書の内容をある程度、論理的に再構築することが可能である。
第一節:近世砲術伝書の標準的構成
まず、近世の砲術伝書が一般的にどのような構成を持っていたかを確認する。例えば、近世を代表する砲術流派である稲富流の秘伝書には、鉄砲の起源に始まり、射撃の心得(精神論)、得物(銃)に応じた射撃方法・姿勢、弾丸の種類と用途、弾丸の重量(玉目)による鉄砲の仕様、火薬原料の配合法、そして照準具の説明などが含まれていた 14 。関流においても、その伝書は全部で百六十八冊にも及び、階梯に応じて段階的に伝授される体系的な内容を持っていた 15 。
これらの事例から、「霞流砲術書」もまた、単なる技術マニュアルではなく、流派の歴史、思想、精神性から、具体的な兵器の仕様、火薬の調合、射法に至るまでを網羅した、総合的な知識体系であったと推測される。
第二節:霞流砲術の核心技術(推定)
「霞流砲術書」の中核をなしていたのは、間違いなくその得意とした専門技術に関する記述であったと考えられる。
- 大筒射法: これが霞流の真骨頂であり、伝書の中でも最も重要な部分を占めていたはずである。戦国期から江戸初期にかけて、一人で抱えて発射できる限界に近い大口径の「抱え大筒」が用いられた 16 。伝書には、こうした大筒の具体的な運用法、すなわち城壁や櫓といった構築物を破壊するための対物射撃、密集する敵部隊を薙ぎ払うための対集団射撃など、目的に応じた専門的な射法が詳述されていたであろう。
- 火薬調合の秘伝: 大筒の威力を最大限に引き出し、同時に銃身の破裂という致命的な事故を防ぐためには、極めて高度な火薬の知識が不可欠であった。大筒用の強力な火薬の配合比率、湿気対策を施した製造法、長期保存のノウハウなどが、流派の秘伝として記されていた可能性は極めて高い。後継の関流の記録にも、藩命を受けて火薬の調合を行い、「骨が折れた」といった記述が見られることから 18 、火薬の管理が極めて重要かつ困難な作業であったことが窺える。
- 照準と弾道計算: 大筒による遠距離射撃を可能にするため、高度な弾道学に関する知見が含まれていたと推測される。関流では「櫓」と呼ばれる特殊な照準尺が用いられたことが知られているが 12 、その原型となる技術が霞流で開発されていた可能性は高い。目標までの距離に応じて火薬の量を加減し、適切な仰角をつけて射撃するための具体的な手順や計算方法が、図解などを用いて解説されていたかもしれない。
- 多様な実戦射法: 基本的な立ち撃ち、膝撃ちの構えに加え 3 、より実戦的な状況を想定した特殊な射法も記されていたと考えられる。例えば、遮蔽物を利用して身を隠しながら射撃する法、移動しながら射撃する法、あるいは腹ばいの姿勢で射撃する「這い射ち」など 1 、戦場のあらゆる局面に対応するための多様な技術が体系化されていたであろう。
第三節:「霞流砲術書」の思想と精神性
武芸の伝書は、技術のみを伝えるものではない。射手としてあるべき精神的な在り方を説く、思想書としての側面も併せ持つ。
「霞流砲術書」にも、一撃に全てを込めるための集中力の高め方、敵と対峙しても揺るがない不動心の保ち方、そして自らの技に対する驕りを戒める謙虚さといった、武人としての心構えが説かれていたと考えられる。
また、近世の武芸流派では、全ての技術が書物として明文化されるわけではなかった。特に流派の根幹をなす奥義や秘伝とされる部分は、「三人唯授」(三人の高弟にのみ授ける)や「一人唯授」(ただ一人の後継者にのみ授ける)といった形式で、師から弟子へと直接、口伝によって伝えられるのが常であった 15 。「霞流砲術書」は、こうした口伝を補完し、流派の正統な継承者であることを証明する「免許状」としての役割も担っていたのである。
この「霞流砲術書」の行方について、一つの合理的な推論が成り立つ。それは、この書が物理的に失伝したというよりも、むしろ関流が成立・発展する過程で、その内容が関流の広範な伝書体系の中に**「吸収・再編」**されたのではないか、というものである。霞流の正統な後継者である関之信は、師・丸田盛次の教えを基礎としながらも、そこに自身の研究や工夫を加えて新たな技術体系、すなわち関流を構築した 12 。この過程で、霞流の教えは解体され、関流の目録、中伝、奥義といった各階梯の伝書の中に、その精髄が有機的に埋め込まれていったと考えられる。したがって、失われた「霞流砲術書」という単一の書物を探すという行為は、現在、土浦の関家に残されている膨大な文書群 20 の中から、その源流たる霞流の痕跡を丹念に拾い集めるという、壮大な考古学的作業に等しいと言えるだろう。
第四章:霞流の遺産 ― 関流砲術への継承と技術的特質
霞流砲術は、その創始者である丸田盛次一代で終わることはなかった。その卓越した技術と思想は、高弟・関八左衛門之信によって受け継がれ、「関流砲術」として新たな発展を遂げる。関流は、霞流という戦国実戦技術の「原石」を、江戸泰平の世にふさわしい洗練された「宝石」へと磨き上げた存在であった。
第一節:高弟・関八左衛門之信と関流の創始
関八左衛門之信(せき はちざえもん ゆきのぶ、1596-1671)は、元和3年(1617)、丸田盛次に弟子入りし、霞流砲術の修行に励んだ 12 。この時期は、大坂の陣(1614-1615)が終結し、日本社会が戦乱の時代から「元和偃武」と称される泰平の時代へと大きく舵を切った転換点にあたる。
之信は師の下で研鑽を積み、やがて霞流の奥義を極めるに至る。その卓越した技量を認めた師・盛次は、之信に対して独立し、自らの名を冠した「関流」を称することを許した 12 。これは、単に弟子が師のレベルに達したことを意味するだけでなく、師が弟子の創造性を高く評価し、流派のさらなる発展の可能性を認めたことを示す、武芸史上でも特筆すべき出来事であった。
第二節:関流に受け継がれた技術的特質
関流は、霞流の核心技術、特に大筒射法を色濃く受け継ぎながら、それをさらに洗練させるための独自の工夫を随所に凝らしている。その特徴は、使用する鉄砲そのものに顕著に表れている。
- 特注仕様の鉄砲: 関流で用いられた鉄砲は、汎用品ではなく、近江の国友丹波やその技術を受け継いだ鉄砲鍛冶に特注された、独特の形状を持つ秀作であった 21 。
- 肉薄の銃身: 関流の銃は、銃身が薄く作られているという特徴を持つ 21 。これは、大筒の威力と飛距離を維持しつつ、その最大の欠点である重量を軽減し、戦場での機動性を高めることを意図した工夫と考えられる。薄くても破裂しない強度を保つためには極めて高度な鍛造技術が必要であり、霞流時代からの課題であった大筒の運用性向上に対する、一つの技術的な回答であった。
- 猿渡り(長い用心金): 用心金(引き金を保護する部品)が後方へ長く伸びた「猿渡り」と呼ばれる構造は、関流の鉄砲を象徴する外見的特徴である 21 。この独特の形状の機能については、射撃時の安定性を向上させるためのグリップとしての役割、大筒の重量バランスを調整する役割、あるいは地面に銃を置いて射撃する際の支えとしての役割など、複数の目的が考えられる。いずれにせよ、霞流の実戦的な工夫が、より洗練された形で継承されたものと推察される。
- 大筒射法への特化: 霞流の神髄であった大筒射法は、関流の中核技術として継承・発展した。その象徴が、現在も茨城県土浦市に伝わる巨大な大筒である。特に有名な「谷神(こくしん)」は900目玉筒、「抜山銃(ばっさんじゅう)」もそれに次ぐ大口径を誇り、その射撃演武は凄まじい爆裂音で観客を圧倒するという 23 。これらはもはや個人が携行する「鉄砲」というよりも、城攻めなどを想定した「軽火砲」としての性格を帯びており、その運用には流派に伝わる高度な専門知識と熟練の技術が不可欠であった。
第三節:江戸時代の「武芸」としての体系化
戦国の実戦技術であった霞流は、関流へと継承される中で、泰平の世における「武芸」として高度に体系化されていった。
その特徴の一つが、厳格な修行体系である。関流への入門は武士身分以上の者に限定され、入門から免許皆伝に至るまでには10年もの長い歳月を要した 23 。さらに、修行の進捗に応じて使用する銃の口径が段階的に大きくなっていく、極めて合理的なカリキュラムが組まれていた。入門初年は十匁玉から始まり、二年目に二十匁、三年目に三十匁、四年目に五十匁、そして五年目には百匁玉の大筒を扱うことが許されるという階梯が定められていた 15 。
このように、関流は霞流から受け継いだ実戦技術を、江戸時代の社会構造と価値観の中で**「最適化」 し、同時に 「ブランド化」**することに成功した流派であったと言える。技術の最適化とは、戦国の多様な状況で求められた技術の中から、特に大筒射法に焦点を絞り、そのための専用銃を開発し、運用法を洗練させたことを指す。そしてブランド化とは、厳格な入門資格、長期にわたる体系的な修行課程、そして膨大な伝書群によって、関流の技術に他流にはない権威と希少価値を与えたことを意味する。これにより、関流は単なる一技術ではなく、土浦藩お抱えの格式高い「武芸」として確立され、その価値を藩内外に広く知らしめることに成功したのである。
|
【表2】関流に伝わる主要大筒の諸元 |
|
|
|
|
|
|
|
名称 |
玉目(匁) |
玉目(kg換算) |
最大射程(推定) |
所蔵 |
文化財指定 |
備考 |
|
谷神(こくしん) |
900目 |
約 3.38 kg |
36町(約 3.9 km) |
土浦市立博物館 |
土浦市指定文化財 |
関流を代表する最大級の大筒 23 |
|
抜山銃(ばっさんじゅう) |
(詳細不明、大口径) |
- |
- |
土浦市立博物館 |
土浦市指定文化財 |
「谷神」と共に演武で用いられる 23 |
この表が示すように、「谷神」の放つ弾丸の重量は約3.4kg、その射程は実に4km近くにも及んだとされ、霞流・関流が追求した技術の恐るべき到達点を物語っている。
第五章:土浦藩における関流の展開と保存
霞流の血脈を受け継いだ関流砲術は、その発祥の地である米沢を離れ、遠く関東の常陸国・土浦の地で根を下ろし、花開くこととなる。土浦藩は、この稀有な技術体系を藩の公式武芸として手厚く保護し、結果として今日我々が霞流の姿を垣間見ることができる、貴重な「生きたアーカイブ」を形成した。
第一節:関家の移籍と土浦藩砲術指南役
関流の祖・関之信は、元は上杉家の家臣であったが、その後、上総国久留里藩(現在の千葉県君津市周辺)の藩主・土屋利直に仕官した 22 。寛文9年(1669)、主君である土屋家が常陸国土浦藩へ転封となると、関家もそれに従って土浦へ移り、以降、代々藩の砲術指南役を務めることになった 22 。
土浦藩において、関流砲術は極めて高い評価を受け、藩を象徴する武芸として重んじられた。当時、「刻の太鼓と関の鉄砲」という言葉が人々の間で語り継がれていたほどであり 25 、時刻を告げる城の太鼓の音と並び、関流の大筒の轟音は土浦の日常に欠かせない音風景の一部となっていたことが窺える。関家は土浦藩の江戸屋敷に詰め、藩士への指導はもちろんのこと、その名声を聞きつけた諸国の大名や藩士にも広く門戸を開き、砲術を伝授した 23 。これにより、霞流を源流とする大筒の技は、土浦の地から全国へと広まっていったのである。
第二節:現存史料から見る関流の実態
米沢藩が霞流を「生み出した」場所だとすれば、土浦藩は霞流の技術と思想を「保存し、可視化した」場所であると言える。幸運なことに、土浦には関流の遺産が、文書、武具、そして現代に続く演武という三つの形態で、奇跡的に保存されている。
- 文書(文字情報): 土浦市立博物館が所蔵する「関正信家文書」は、関流砲術の実態を知る上で最も重要な第一級史料群である 20 。ここには、流派の技術と思想を記した伝書類、日々の射撃訓練や鉄砲製造の克明な記録、さらには藩内での役職に関する公的な資料までが含まれている 18 。これらの文書を解読することで、流派の技術体系、組織運営、そして藩との密接な関わりなどを具体的に解明することができる。
- 武具(物的情報): 前章でも触れた大筒「谷神」や「抜山銃」をはじめとする、関流特注の鉄砲そのものが現存している 23 。これらの武具は、肉薄の銃身や猿渡りといった構造的な特徴を実際に目にすることを可能にし、文献資料だけでは完全に理解することが難しい技術的な工夫を雄弁に物語る物的証拠である。
- 演武(身体技法): 関流砲術は、過去の遺産として博物館に眠っているだけではない。現在も「土浦藩関流炮術保存会」によってその技が継承されており 21 、土浦城跡である亀城公園での公開演武などを通じて、その迫力ある大筒射法が定期的に披露されている 23 。これは、文書や武具だけでは伝わらない、構え、操作手順、射撃のリズムといった、生きた身体技法が現代にまで伝えられていることを意味し、極めて貴重な事例である。
これらの三位一体の遺産に加え、土浦市立博物館が1990年に開催した特別展の図録『火縄銃-関流炮術の冴えと奥義-』 27 や、日本銃砲史の権威である宇田川武久氏による研究書『江戸の砲術師たち』 26 といった優れた研究成果も存在する。これらは、専門的な視点から関流の歴史と技術を深く掘り下げており、霞流から関流への流れを理解する上で不可欠な道標となる。
我々が今日、幻の流派である霞流についてここまで深く考察できるのは、ひとえに土浦藩が関流を藩の誇りとして手厚く保護し、その結果として他に類を見ない「生きたアーカイブ」が形成されたからに他ならない。霞流砲術を研究することは、すなわち土浦に残された関流の豊かな遺産を解読することと同義なのである。
結論:霞流砲術の歴史的意義と武芸史における位置
本報告書は、現存する直接史料が極めて乏しい「霞流砲術書」という謎に対し、その源流である米沢藩上杉家の軍事思想と、その正統な継承者である土浦藩の関流砲術という、二つの確かな文脈から多角的にアプローチを試みた。その結果、霞流砲術は、単なる一砲術家の個人的な技芸に留まらず、戦国末期の熾烈な軍事競争の中から必然的に生まれた、大筒射法に特化した先進的な技術体系であったことが明らかになった。
霞流の 独自性と先進性 は、その専門性にある。戦国末期、多くの流派が小口径の火縄銃による集団での連続射撃、すなわち面制圧による火力投射を模索する中、霞流は「大筒」という特殊兵器の運用に特化することで、他流とは一線を画す独自のニッチを確立した。これは、野戦から攻城戦へと戦闘の主眼が移り変わる時代を見据えた、極めて戦略的な技術開発であったと言える。直江兼続という稀代の戦略家の下で、藩の軍事プロジェクトとして磨かれたその技術は、まさしく時代の最先端を行くものであった。
武芸史全体を見渡した時、霞流砲術は、日本の戦闘技術が大きく変容する過渡期に位置する、重要な**「ミッシングリンク(失われた環)」**としての意義を持つ。すなわち、戦国時代の過酷な実戦の中から生まれた純粋な「兵器術」が、江戸時代の泰平の世の中で、厳格な教育体系と高度な精神性を備えた「武芸」へと昇華していく、まさにその転換点に霞流は存在する。戦国の実戦を知る最後の世代である開祖・丸田盛次から、新たな時代の中で武芸として大成させる次代の担い手・関之信へと、その技術と魂が受け継がれた点に、この流派の歴史的価値は集約される。
「霞流砲術書」は失われた。しかし、その精神と技術の精髄は、後継の関流砲術の中に脈々と生き続けている。そして、その関流の遺産は、土浦の地に「生きたアーカイブ」として奇跡的に保存されている。幻の書を追う旅は、我々を日本の武芸が最もダイナミックに変容を遂げた時代へと誘い、一つの技術が如何にして生まれ、磨かれ、そして文化として継承されていくのかという、普遍的な物語を教えてくれるのである。霞流砲術は、その存在が霞のように朧げでありながらも、日本の砲術史、ひいては武芸史を理解する上で、欠くことのできない重要な光を放ち続けている。
引用文献
- 別 紙 米沢藩上杉砲術について (概要・特色) 鉄砲(火縄銃)は、天文 12 年(1543)に種子島 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/material/files/group/35/H29besshi.pdf
- 上杉鉄砲隊: WTFM 風林火山教科文組織 https://wtfm.exblog.jp/11495780/
- 宮坂考古館|火縄銃 https://www.miyasakakoukokan.com/hinawaju.html
- 直江兼続の鉄砲鍛造遺跡 - 米沢市 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/10/1034/5/5/287.html
- 山形県米沢市 - 上杉時代館の「直江兼続公」講座 http://www5.omn.ne.jp/~jidaikan/yone4.html
- 米沢藩で行われていた武術について知りたい。あわせて、武術の相伝者名も知りたい。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000138202
- 丸田盛次(まるた もりつぐ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%B8%E7%94%B0%E7%9B%9B%E6%AC%A1-1111731
- 米沢藩古式砲術保存会 - 宮坂考古館 https://www.miyasakakoukokan.com/hojutsu.html
- 米沢に伝わる稲富流砲術 | 米沢の歴史を見える化 https://ameblo.jp/yonezu011/entry-11296519994.html
- 昭和の風景「三十匁火縄銃発砲実演(昭和39年)」 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Z_AAtv1WY_4
- 兼続公まつりで米沢藩稲富流砲術隊が迫力の砲術実演 - 南魚沼市 https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/2615.html
- DVD 日本の古武道 関流砲術 https://www.hiden-shop.jp/SHOP/BCD75.html
- 百発百中の稀代の砲術家・稲富祐直、素人に負ける - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=w2SxuxF7SCI
- 稲富流鉄砲秘伝書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/538411
- 打、二年目に二十匁玉、三年目に三 https://www.nipponbudokan.or.jp/CDFy5t/wp-content/uploads/2016/03/tankoubon25.pdf
- 林流抱え大筒 - 秋月 http://www.snk.or.jp/cda/tanbou/amagi/amagihp/akituki/ootutu/ootutu/ootutu.htm
- 23.大砲の歴史と鋳鉄 - 新井宏(ARAI Hiroshi)のWWWサイト https://arai-hist.jp/magazine/baundary/b23.pdf
- -2021 年度冬季展示室だより- - 土浦市 https://www.city.tsuchiura.lg.jp/data/doc/1644194029_doc_44_0.pdf
- 関流(セキリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%96%A2%E6%B5%81-547513
- 市史資料目録一覧 | 土浦市立博物館 https://www.city.tsuchiura.lg.jp/tsuchiurashiritsuhakubutsukan/hanbaitoshonado/page016766.html
- 関流砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E6%B5%81%E7%A0%B2%E8%A1%93
- 砲術とは/鉄砲術|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47463/
- 土浦藩關流古式炮術(土浦市指定文化財) | 土浦全国花火競技大会実行委員会公式ホームページ https://www.tsuchiura-hanabi.jp/page/page000029.html
- 砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93
- よくある質問集 くらし・手続き - 土浦市 https://www.city.tsuchiura.lg.jp/faq.php?mode=detail&lc=0&c=7&code=138
- 江戸の砲術師たち - 平凡社 https://www.heibonsha.co.jp/book/b163460.html
- 関流炮術(せきりゅうほうじゅつ)についての資料はあるか ... https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/reference/show?dtltbs=1&mcmd=25&st=update&asc=desc&ndc1=559&ndc_lk=1&page=ref_view&ldtl=1&id=1000292042
- 関流炮術(せきりゅうほうじゅつ)についての資料はあるか - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000292042&page=ref_view
- 江戸の砲術師たち | 新書マップ4D https://shinshomap.info/book/9784582855128