富田重政
富田重政は「名人越後」と称された剣豪。前田利家に仕え、末森城一番槍、関ヶ原、大坂の陣で活躍。加賀藩の重臣として1万3千石を得た。
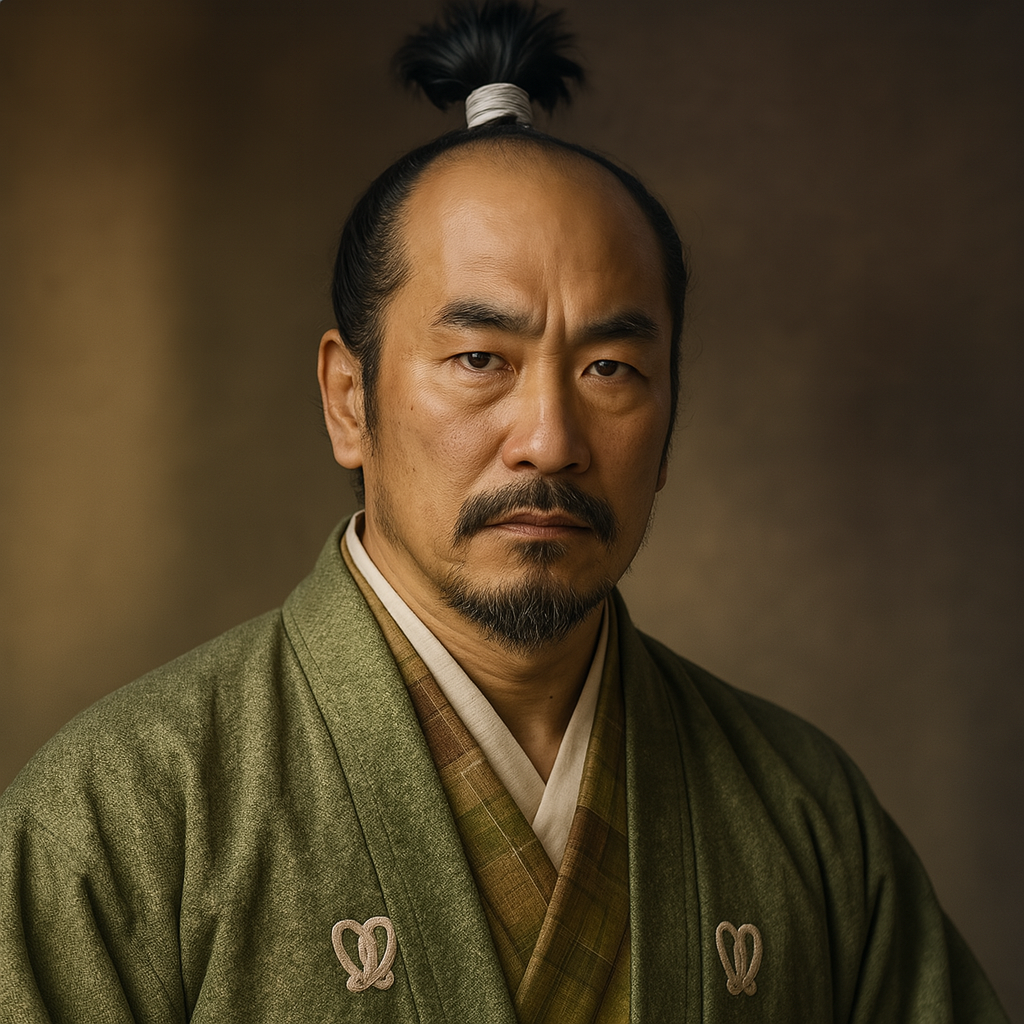
名人越後・富田重政 ― 剣、武、そして加賀百万石を支えた実像
序章:名人越後、その実像を求めて
本報告書は、戦国時代から江戸時代初期にかけて前田家に仕えた武将、富田重政(とだ しげまさ)の生涯を、多角的な視点から徹底的に解明することを目的とする。重政は、「名人越後」の異名で知られる剣豪として、また末森城の戦いにおける一番槍の武功や、関ヶ原合戦、大坂の陣での活躍で知られる猛将として、その名を歴史に刻んでいる。しかし、彼を単なる「剣豪」や「武将」といった断片的なレッテルで語ることは、その本質を見誤ることに繋がりかねない。彼の生涯は、武芸の道、武士としての忠義、そして一藩の重臣としての経営能力が交差する、稀有な事例であった。
「名人越後」の異名や数々の武勇伝の裏に隠された、彼の真の価値とは何か。なぜ彼は、徳川将軍家の剣術指南役であった柳生宗矩をも凌ぐほどの、破格の厚遇を前田家から受けたのか。本報告書は、現存する史料を丹念に読み解き、彼の出自から剣技の神髄、戦場での功績、藩内での地位、そして後世に残した遺産に至るまでを網羅的に検証することで、これらの問いに答えていく。富田重政という一人の人間が、いかにして戦国の動乱を生き抜き、加賀百万石の礎を支える重鎮へと至ったのか、その実像に迫る。
第一章:出自と勃興 ― 山崎与六郎から富田重政へ
富田重政の人生は、彼自身の類稀なる才覚と、時代の大きなうねりが交差する中で幕を開ける。名門の血筋に生まれながらも主家の滅亡という逆境を経験し、やがて一人の武将としての武功を以て、剣の名家を継承するという劇的な転身を遂げた。彼の前半生は、運命の連鎖とも言うべき出来事の連続であり、後の「名人越後」の誕生を予感させる力強い序章であった。
第一節:剣術の名門、山崎家に生まれて
富田重政は、永禄7年(1564年)、越前国(現在の福井県)に生まれた 1 。初名を山崎与六郎、後に六左衛門と称した 1 。その出自は、近江源氏佐々木六角氏の流れを汲む名族であり、越前に移住してからは代々、戦国大名・朝倉氏に仕える家柄であったと伝わる 5 。
彼の武才の源流は、その血筋と家庭環境に求めることができる。父である山崎景邦は、自身が中条流剣術の達人であり、ついには「山崎流」と称するほどの独自の境地に至った剣客であった 5 。重政は幼少期よりこの父から直接手ほどきを受け、その才能を遺憾なく発揮し、門下随一の剣士として早くからその名を馳せていた 5 。
しかし、天正元年(1573年)、主家であった朝倉義景が織田信長によって攻め滅ぼされると、山崎家は拠り所を失う 5 。この主家の滅亡は、当時まだ少年であった重政にとって大きな逆境であったが、同時に彼の運命を新たな方向へと導く重要な転機となった。
第二節:前田家仕官と富田家継承への道
朝倉氏滅亡後、浪々の身となった山崎家であったが、重政の才は織田家の重臣であった前田利家の目に留まることとなる。利家にその将来性を見出された重政は、前田家に仕官することが許され、武士としての新たなキャリアを歩み始めた 3 。
彼の人生が大きく飛躍するきっかけは、二つの出来事が重なったことによる。一つは、彼が仕える前田家の同僚であり、中条流の宗家であった富田景政の嫡男・景勝が、天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いで戦死してしまったことである 6 。これにより、剣の名門・富田家は後継者を失うという断絶の危機に瀕していた。
もう一つは、その翌年の天正12年(1584年)に勃発した「末森城の戦い」である。この戦いで、当時まだ山崎姓であった重政は、前田利家の救援軍の先鋒として敵陣に切り込み、「一番槍」という最高の武功を立てた 3 。この目覚ましい働きは主君・利家から絶賛され、その褒賞として、後継者を求めていた富田景政の娘を妻として迎えることを許されたのである 3 。
この婚姻は、単なる恩賞に留まらなかった。富田家の後継者不在という状況下で、卓越した武功を立てた若き武者を婿に迎えることは、双方にとって理想的な解決策であった。こうして重政は、富田景政の婿養子として、その名跡と家督を継承することになった 4 。これにより、山崎与六郎は「富田重政」となり、一介の前田家臣から、由緒ある中条流宗家当主という特別な地位を併せ持つ存在へと、その立場を劇的に変えたのである。
この一連の経緯は、単なる偶然の連鎖とは言い切れない。主君・利家にとって、後継者を失った名門「富田家」という家格と、類稀な実戦能力を持つ「山崎与六郎」という個人を結びつけることは、双方を救い、かつ前田家の武威を高めるための極めて合理的な人事戦略であった。利家は、重政の「一番槍」という誰もが認める武功を公の場で賞賛し、婚姻を命じることで、この養子縁組に絶対的な大義名分を与えた。これは、有能な人材を適材適所に配置し、家臣団の力を最大化しようとする利家の、優れた組織管理能力の現れと見ることができる。
|
年代(西暦) |
年齢 |
主な出来事 |
典拠 |
|
永禄7年(1564) |
1歳 |
越前国にて山崎景邦の子として誕生。初名は与六郎。 |
1 |
|
天正元年(1573) |
10歳 |
主家・朝倉氏が織田信長により滅亡。 |
5 |
|
(時期不詳) |
- |
前田利家に仕官。 |
3 |
|
天正12年(1584) |
21歳 |
末森城の戦いで一番槍の武功を立てる。富田景政の婿養子となり、富田家を継承。 |
3 |
|
天正18年(1590) |
27歳 |
小田原征伐に従軍。八王子城攻めなどで武功を挙げる。 |
4 |
|
慶長5年(1600) |
37歳 |
関ヶ原の戦いに際し、北陸で大聖寺城攻めや浅井畷の戦いに従軍。 |
4 |
|
慶長11年(1606) |
43歳 |
藩主の命により、金沢・卯辰山に摩利支天堂(後の宝泉寺)を建立。 |
7 |
|
(時期不詳) |
- |
知行が1万3670石となる。 |
4 |
|
慶長18年頃(1613) |
50歳頃 |
長男・重家に家督を譲り隠居。 |
4 |
|
慶長19-20年(1614-15) |
51-52歳 |
大坂の陣に隠居の身ながら参陣。19の首級を挙げる武功を立てる。 |
3 |
|
元和4年(1618) |
55歳 |
長男・重家が24歳で早逝。次男・重康が家督を継ぐ。 |
4 |
|
寛永2年(1625) |
62歳 |
5月25日(旧暦4月19日)に死去。墓所は金沢市・慈雲寺。 |
2 |
第二章:剣の道 ― 中条流の継承と「富田流」の誉れ
富田重政の名声を語る上で、その核となるのが剣術家としての側面である。彼は単に腕が立つ武人というだけでなく、由緒ある剣術流派・中条流の正統な継承者であった。そして、その卓越した技量と名声は、いつしか流派そのものの呼び名にまで影響を与え、「富田流」という誉れ高きブランドを確立するに至った。彼の剣は、敵を倒すための技術に留まらず、心を制し、争いを未然に防ぐ「平法」の域に達していた。
第一節:中条流と「富田流」
重政が継承した剣術の源流は、南北朝時代に中条兵庫守長秀が創始した「中条流平法」に遡る 9 。家伝の兵法に、当時流行していた念流の技術を取り入れて大成されたこの流派は、長秀の門人であった甲斐豊前守広景を経て越前の地にもたらされた 9 。そして、その奥義は富田家の祖である富田九郎左衛門長家に授けられ、代々受け継がれていくこととなる 9 。
富田家は、長家の子・景家、その子である勢源と景政、そして景政の養子となった重政と、天与の才に恵まれた剣客を次々と輩出した 9 。彼らの活躍により、中条流は越前から全国へとその名を轟かせた。富田家自身は一貫して「中条流」の正統を名乗っていたものの、特に盲目の達人として知られた富田勢源や、後に「名人越後」と称される重政の名声があまりにも高かったため、世間では彼らの一門を指して、敬意を込めて「富田流」と呼ぶようになったのである 9 。
中条流(富田流)は、小太刀を用いた絶妙な技で特に知られているが、その実態は刀の長短を問わず、槍、薙刀、棒術までも含む総合的な武術体系であった 11 。その形稽古には特徴的な点があり、師匠役である打太刀が三尺を超える大太刀を用いるのに対し、弟子役の仕太刀はそれより短い中太刀や小太刀でこれに応じる 13 。これは、常に不利な状況を想定し、それを卓越した技術と体捌きで覆すという、極めて実戦的な思想が根底にあることを示している。
第二節:「名人越後」の剣と精神
重政の剣技と精神性を物語る逸話は数多く残されており、それらは彼が単なる技術者ではなく、深い洞察力と精神性を備えた「名人」であったことを示している。
その代表格が、三代藩主・前田利常との「無刀取り」の逸話である。ある時、利常に「無刀取りはできるか」と問われ、いきなり白刃を突きつけられた重政は、全く動じることなく「謹んでお受けいたします」と応じた。そして、「これは秘伝ゆえ、他見は無用。後ろの襖の陰から覗く者がおりますので、まずはお退けください」と進言した。利常が思わず後ろを振り向いたその瞬間、重政は利常の手からするりと刀を奪い取り、「これが無刀取りにて」と静かに差し出したという 5 。この逸話は、重政の剣が相手の腕力に力で対抗するのではなく、心理的な駆け引きを用いて状況を支配し、戦わずして目的を達する高度な「兵法」であったことを如実に物語っている。これは、柳生宗矩が説いた「わが刀なき時、人にきられじとの無刀也」という、危機回避術としての無刀の極意とも通底するものである 14 。
また、彼の名声が全国区であったことを示すのが、三代将軍・徳川家光が望んだとされる柳生宗矩との御前試合の一件である。将軍直々の命とあれば断ることもできず、重政が江戸へ向かう支度を整えていたところ、出発直前に中止の使者が訪れた。表向きの理由は「龍虎相打てば、いずれか一方に汚名が付くは必定」という家光の配慮であった 5 。しかし、この後、巷間では「柳生但馬守が敗北を恐れ、事前に手を回して中止させたのではないか」という噂がまことしやかに囁かれた 5 。この噂が立ったこと自体が、加賀藩の一家臣に過ぎない重政の名声が、将軍家剣術指南役と比肩し、あるいはそれを凌ぐとさえ見なされていたことの何よりの証左である。この一件は、剣術の試合が単なる技量の優劣を決する場ではなく、藩の威信や個人の名誉を懸けた、極めて政治的な意味合いを帯びていたことを示唆している。加賀藩の師範が将軍家師範を破るような事態は、幕藩体制の微妙な力関係に波紋を広げかねず、中止の判断にはそうした高度な政治的配慮が働いた可能性も否定できない。
これらの逸話から浮かび上がるのは、重政の剣が、敵を斬り倒す「殺人剣」の次元を超え、争いを未然に防ぎ、危機を乗り越える「活人剣」としての側面を持っていたことである。中条流が自らを「平法」と称したように、重政にとって剣術とは、身を修め、不測の事態に対応するための総合的な処世術であった。彼の「名人」たる所以は、技の巧みさだけでなく、武の理を深く探求し、それを実生活のあらゆる場面で体現する「平法者」としての境地にあったと言える。そして、その剣豪としての名声は、彼個人の誉れであると同時に、加賀百万石の武威を象徴する「ソフトパワー」として、他藩に対する無言の牽制力としても機能していたのである。
第三章:戦陣の武人 ― 前田家三代に仕えた武功
富田重政は、剣の達人であると同時に、戦場にあっては常に先陣に立ち、主家の危機を幾度となく救った歴戦の武将であった。彼のキャリアは、前田利家、利長、利常の三代にわたる奉公の中で、数々の輝かしい武功によって彩られている。特に、彼の運命を決定づけた末森城での一番槍、北陸の関ヶ原と呼ばれた浅井畷での死闘、そして老いてなお衰えぬ武勇を示した大坂の陣での働きは、彼の武人としての価値を不動のものとした。
第一節:末森城の戦い(天正12年 / 1584年)― 一番槍の栄誉
天正12年(1584年)、小牧・長久手の戦いに連動して、越中の佐々成政が羽柴秀吉方の前田利家を攻撃。成政は1万5千と号する大軍を率いて、加賀と能登を分断する要衝・末森城に殺到した 15 。対する城兵は、城主・奥村永福らが率いるわずか数百名に過ぎず、城は瞬く間に落城寸前の危機に陥った 15 。
金沢城でこの急報に接した前田利家は、手勢が少ないことや秀吉から金沢を動くなとの指示があったことから出陣を躊躇するが、妻・まつ(芳春院)の「金銀に槍を持たせて戦わせるおつもりか」という叱咤激励に奮起。わずか2500の兵を率いて、決死の救援に向かった 16 。利家は佐々軍の警戒網を避けるため、夜陰に乗じて海岸沿いの道を進軍し、敵の背後を突くという奇襲作戦を敢行した 16 。
この絶体絶命の状況を打開する救援軍の先鋒として、敵陣に真っ先に切り込んだのが、当時21歳の山崎与六郎、後の富田重政であった。彼はこの戦いで「一番槍」の功名を立て、利家軍の士気を大いに鼓舞した 3 。内外からの攻撃に混乱した佐々軍は敗走し、前田家は領国防衛に成功。この勝利は、後の加賀百万石の礎を築く上で決定的な意味を持つ戦いとなった 18 。重政のこの一番槍は、単なる武功ではなく、藩の存亡を救う奇襲作戦の、さらにその先駆けという極めて価値の高いものであった。彼がこの功績によって富田家を継承する道が開かれたことからも、その重要性がうかがえる 3 。
第二節:関ヶ原と北陸の攻防(慶長5年 / 1600年)
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いに際し、前田家は東軍に与した。当主の前田利長は、徳川家康の命を受け、西軍に属した丹羽長重の小松城や、山口宗永が守る大聖寺城の攻略へと向かった。重政もこの北陸方面軍の中核として従軍し、大聖寺城攻めなどで武功を挙げたとされる 4 。
しかし、大聖寺城を落とし、金沢へ引き上げる途上、前田軍は最大の危機を迎える。「浅井畷(あさいなわて)」と呼ばれる湿地帯の狭路で、小松城から出撃してきた丹羽長重軍の待ち伏せ攻撃を受けたのである 20 。ぬかるんだ畷道では大軍の利を活かすことができず、前田軍は激しい追撃を受けて甚大な被害を出し、苦戦に陥った 22 。
この「北陸の関ヶ原」とも称される激戦に、重政も従軍していた 4 。史料に彼の具体的な活躍は詳述されていないものの、この絶体絶命の状況下で、前田軍は山崎長徳や長連龍といった猛将たちの奮戦によって辛うじて丹羽軍を撃退し、金沢への撤退を完了させている 22 。重政が、この混乱した戦場で殿軍の一翼を担い、その豊富な実戦経験と剣技を以て味方の撤退を支えたことは想像に難くない。
第三節:大坂の陣(慶長19-20年 / 1614-15年)― 老将の最後の戦い
徳川の世が盤石となりつつあった慶長19年(1614年)、大坂の陣が勃発する。この時、重政はすでに50歳を超え、家督を長男の重家に譲って隠居の身であった 4 。しかし、主君・前田利常の出陣に従い、老骨に鞭打って冬・夏の両陣に参陣した 3 。
その戦いぶりは、老将という言葉からは想像もつかないほど凄まじいものであった。記録によれば、重政はこの最後の戦役において、実に19もの敵兵の首級を挙げたという 3 。これは、彼の武が全く衰えていなかったことの証明であり、生涯現役の武人としての面目躍如たるものであった。
特に冬の陣では、前田軍の第三軍の将として夜間に行軍中、突如として敵の鉄砲玉が炸裂し、部隊がパニックに陥るという事態が発生した。しかし、その中にあって重政は微動だにせず、泰然自若としていたと伝えられている 7 。この逸話は、彼の卓越した胆力と、幾多の修羅場を潜り抜けてきた者にしか持ち得ない、指揮官としての器の大きさを示している。
|
合戦名 |
年月日(西暦) |
対戦相手 |
重政の役割・武功 |
典拠 |
|
末森城の戦い |
天正12年9月(1584) |
佐々成政軍 |
前田利家救援軍の先鋒として「一番槍」の武功を立てる。 |
3 |
|
小田原征伐 |
天正18年(1590) |
後北条氏 |
八王子城攻めなどに従軍し、手柄を立てる。 |
4 |
|
大聖寺城攻め |
慶長5年8月(1600) |
山口宗永軍(西軍) |
前田利長軍の武将として従軍し、武功を挙げる。 |
4 |
|
浅井畷の戦い |
慶長5年8月(1600) |
丹羽長重軍(西軍) |
撤退戦に武将として従軍。 |
4 |
|
大坂の陣(冬・夏) |
慶長19-20年(1614-15) |
豊臣方 |
隠居の身ながら前田利常軍に従軍。合計で19の首級を挙げる。 |
3 |
第四章:加賀藩の重臣 ― 一万三千石の知行と影響力
富田重政の価値は、戦場での武功や剣技の巧みさに留まらない。彼は加賀藩において、他の家臣とは一線を画す特別な地位を築き、その存在は藩の威信と安定に大きく貢献した。彼に与えられた破格の知行、城内に構えた広大な邸宅、そして藩の安寧を祈る重要な事業への関与は、前田家三代の藩主から寄せられた絶大な信頼の証であった。
第一節:破格の知行 ― 1万3670石の意味
重政が最終的に得た知行は1万3670石に達した 4 。1万石以上の所領を持つ者は「大名」と称されるのが通例であった江戸時代において、一藩の家臣がこの禄高を得ることは異例中の異例であった 5 。
この石高の突出ぶりは、同時代の他の著名な剣豪と比較することでより鮮明になる。例えば、徳川将軍家の剣術指南役として絶大な権勢を誇った柳生宗矩でさえ、その知行は1万2500石であった 5 。通常の剣術指南役の相場が300石程度であったことを考えれば、重政の待遇がいかに破格であったかがわかる 5 。
この厚遇の背景には、複数の要因が複合的に絡み合っている。柳生宗矩の価値が、将軍家師範という権威と幕政における政治顧問的な役割にあったのに対し、重政の価値はより具体的かつ多層的であった。第一に、末森城の戦いをはじめとする、藩の存亡に関わる局面での決定的な「軍功」。第二に、中条流宗家という剣術界における正統な「権威」。そして第三に、加賀藩の武威を内外に示す生ける「象徴」としての役割である。重政の1万3670石という知行は、単なる剣術師範への報酬ではなく、これら三つの側面から藩の安全保障と威信に貢献したことへの、包括的な評価であった。これは、中央集権体制の確立を目指す幕府と、自領の安泰と勢威を最優先する外様の大大名との、人材に対する価値評価基準の違いを浮き彫りにする興味深い事例と言える。
第二節:藩内での地位と役割
重政の家は、加賀藩の家臣団の中でも最高位に位置する「人持組(ひともちぐみ)」に列せられた 24 。人持組は、平時には家老などの重職に就いて藩政を動かし、戦時には一軍を率いる軍団長となる、加賀藩の屋台骨を支えるエリート家臣団である。重政の死後、家督を継いだ長男・重家も人持組頭を務めており、富田家が藩内で確固たる地位を築いていたことがわかる 7 。
その特別な地位を物理的に示しているのが、金沢城の新丸という城内の一等地に与えられた広大な邸宅の存在である 7 。この屋敷は、彼の官位である越後守にちなんで「越後屋敷」と呼ばれ、藩主が江戸に出府している間、国元に残った老臣たちが政務を執り行う場所としても利用されたという記録が残っている 27 。これは、彼が単に高い禄を得ていただけではなく、藩の中枢に極めて近い、絶大な信頼を置かれた存在であったことの動かぬ証拠である。彼の邸宅が藩の公的な政務の場として機能したことは、重政が単なる武人ではなく、藩政にも深く関与する重臣として遇されていたことを物語っている。
第三節:摩利支天信仰と宝泉寺建立
重政の人物像を深く理解する上で、彼の信仰心、特に摩利支天への帰依を見過ごすことはできない。摩利支天は、陽炎を神格化した仏教の守護神であり、その実体は捉えることができず、故に傷つけられることもないという特性から、武士たちの間で「護身除災」「戦勝祈願」の神として篤く信仰されていた 28 。加賀藩の藩祖・前田利家も、合戦の際には摩利支天の小像を兜の中に忍ばせて出陣したと伝えられている 32 。
慶長11年(1606年)、藩主・前田利長(一説には利常)の命により、重政は金沢城の鬼門(北東)に位置する卯辰山に摩利支天堂を建立した 7 。この寺院が、現在の摩利支天山宝泉寺である。この建立は、単なる寺院の建設ではなく、加賀百万石の城下町の安寧を永続的に祈願する「鬼門封じ」という、藩の防衛戦略上、極めて重要な意味を持つ事業であった 32 。
この国家的な事業の責任者に重政が抜擢されたという事実は、彼が藩主から寄せられていた信頼の厚さを物語ると同時に、彼自身の摩利支天への深い信仰心を示唆している。剣の道という自己の修練と、摩利支天という神仏への帰依が、彼の強さを支える両輪となっていた可能性は高い。藩の安寧を願う公的な事業と、武人としての個人の信仰が見事に一体となったこの宝泉寺建立は、富田重政が加賀藩内で占めていた特異な立場を象徴する出来事であった。
第五章:血脈と遺産 ― 富田家の終焉と金沢に残る足跡
富田重政が一代で築き上げた栄華は、しかし、その血脈によって永続することはなかった。子息たちの相次ぐ早逝により、彼の直系は比較的早い段階で途絶えてしまう。だが、彼が残した遺産は、知行や家名といった物質的なものに留まらない。その名は金沢の地名に刻まれ、壮麗な墓所は彼が受けた破格の待遇を今に伝え、そして彼が極めた剣の道は流派として形を変えながら、藩の枠を超えて現代にまでその命脈を保っている。
第一節:子息たちの運命と富田本家の断絶
重政には、重家、重康、宗高という三人の息子がいた 4 。
長男の富田重家は、父の隠居後に家督を相続。加賀藩の軍団長である人持組頭を務め、1万石を超える禄高を食んだ 7 。その正室には、藩祖・前田利家の孫娘(豪姫と宇喜多秀家の娘)を迎えるなど、まさに前途洋々たるエリートであった 26 。しかし、元和4年(1618年)、大坂の陣などで立てた武功も空しく、24歳という若さでこの世を去ってしまう 4 。
兄の跡を継いだのが、次男の富田重康であった 4 。彼もまた父や兄と同様に越後守を称し、優れた剣の腕前で知られた。後に中風を患ったが、その病を押してなお剣技は衰えず、「中風越後」と人々から畏怖されたという逸話が残るほどの剣豪であった 33 。
三男の富田宗高は、「主計(かずえ)」を称した 7 。しかし、『金沢古蹟志』によれば、彼もまた早世し、子を残さなかった 34 。これにより、あれほどの武功と知行を誇った富田重政の直系、すなわち富田本家は断絶したとされる。戦国の世を駆け抜け、巨大な成功を収めた一族の栄華が、血脈の維持という一点の脆さによって、わずか二代で幕を閉じたことは、戦国から江戸初期にかけての武家の栄枯盛衰の儚さを象徴している。
第二節:地名と墓所に残る記憶
富田家の直系は途絶えたが、その記憶は金沢の街に深く刻まれている。金沢を代表する観光地の一つである茶屋街「主計町(かずえまち)」の名は、この地に富田家の屋敷があったことに由来する 7 。この「主計」が、長男・重家を指すのか、三男・宗高を指すのかについては資料によって見解が分かれる 7 。『金沢古蹟志』の記述に基づけば、長男・重家の死後、三男・宗高が「主計」を称したとあるため 34 、この兄弟いずれか、あるいは両者に関連する地名と考えられる。
そして、富田家が前田家から受けた待遇の特別さを最も雄弁に物語るのが、金沢市東山の慈雲寺に現存する富田家の墓所である 33 。ここには、重政、次男・重康、そして娘や孫娘のものとされる四基の「石廟(せきびょう)」が並び立つ 33 。石廟とは、石で造られた小さな堂のような墓であり、加賀藩においては、藩主一族の墓所である野田山でも、藩祖ゆかりの限られた人物にしか用いられていない極めて格式の高い形式である 38 。一家臣に過ぎない富田家に対し、この石廟の建立が許されたという事実は、彼らが前田家にとってどれほど破格の存在であったかを物語る、決定的な物証と言える。この慈雲寺冨田家石廟群は、その歴史的価値から金沢市の有形文化財に指定されている 38 。
第三節:富田流の継承と分派
重政の血脈は途絶えたが、彼が継承し、その名を高めた剣術の系譜は、藩の枠を超えて広がり、現代にまで受け継がれている。重政の義理の伯父にあたる富田勢源の門流からは、一刀流の祖となる伊藤一刀斎を育てた鐘捲自斎といった高名な剣豪が輩出されている 5 。
富田流(中条流)の武術文化は、その後も全国各地に伝播し、様々な分派を生んだ。現在でも、青森県弘前市には「當田流(とうだりゅう)」として剣術や棒術が 12 、関東には「戸田派武甲流薙刀術」としてその技が 39 、そして広島県には槍術の流派として「佐分利流槍術」が、それぞれ富田流の系譜を汲む流派として現存している 39 。
重政自身は生涯を加賀藩に捧げたが、彼がその生涯をかけて体現した武術の精神と技術は、無形の文化遺産として各地に根付き、形を変えながらも生き続けている。彼の遺産は、石高や家名といった歴史の記録の中だけでなく、今なおその技を修練する人々の中に、確かに息づいているのである。
結論:武人か、剣豪か ― 富田重政の多面的な評価
富田重政の生涯を多角的に検証した結果、彼を単に「剣の達人」という一面的な評価で捉えることは、その実像を大きく見誤ることになると結論付けられる。彼は、中条流を継承し「名人越後」と称された比類なき「剣豪」であったと同時に、藩の存亡を懸けた戦場で確実に戦果を挙げる卓越した「武将」であり、さらには破格の知行と城内の邸宅を与えられ、藩の戦略上重要な事業を任されるほど信頼の厚い「重臣」でもあった。
彼の真の価値は、これら「剣技」「武功」「忠誠」が三位一体となったところにある。柳生宗矩が徳川将軍家の権威を背景とした「中央の剣」を象徴する存在であったとすれば、富田重政は、外様大藩の存立と武威をその一身で体現した「地方の武」の象徴であった。彼に与えられた1万3670石という破格の知行や、藩主一族にのみ許される石廟という壮麗な墓所は、単なる個人的武勇への褒賞ではなく、彼の多面的な価値に対する加賀前田家の正当かつ総合的な評価の現れであった。
「名人越後」の名は、単なる剣技の巧みさを示す称号ではない。それは、動乱の時代を己の武と知略で生き抜き、主家を三代にわたって支え、加賀百万石の礎の一つを築き上げた、一人の偉大な武士の生涯そのものに与えられた、最高の賛辞なのである。彼の存在は、江戸初期の武士社会における多様な価値観と、地方大藩が抱える武人たちの矜持を、今に伝えている。
引用文献
- 富田重政(とだしげまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E9%87%8D%E6%94%BF-1094693
- 富田重政 | 人物詳細 | ふるさとコレクション | SHOSHO - 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/furucolle/list/prsn08399
- 富田重政- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E9%87%8D%E6%94%BF
- 富田重政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E9%87%8D%E6%94%BF
- 富田重政-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73538/
- 富田景政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E6%99%AF%E6%94%BF
- 剣豪「名人越後」富田重政と摩利支天山 宝泉寺 https://gohonmatsu.or.jp/toda_shigemasa/
- 富田重政- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E9%87%8D%E6%94%BF
- 「剣術源流豆知識」第四回 | トピックス | 武道・武術の総合情報 ... https://webhiden.jp/topics/post_23/
- 當田流剣術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/079/
- 冨田流とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%86%A8%E7%94%B0%E6%B5%81
- 當田流剣術 - 弘前市 https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/bunkazai/shi/2021-0317-0919-141.html
- 當田流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%B6%E7%94%B0%E6%B5%81
- 柳生宗矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E5%AE%97%E7%9F%A9
- 末森城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1414
- 末森城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AB%E6%A3%AE%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 末森城の戦いとは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%AB%E6%A3%AE%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 百万石がはじまったまち?!前田利家と宝達志水町の接点を ... https://www.hodatsushimizu.jp/kanko/mottoslow/toshiiemaeda_02.html
- 近世史料館 https://www2.lib.kanazawa.ishikawa.jp/kinsei/suemori.pdf
- 一部 関ケ原合戦図屏風解説 - toukou20 https://ryugen3.sakura.ne.jp/toukou2/toukou65.html
- 浅井畷の戦い ~丹羽長重の関ヶ原~ - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/sekigahara/asainawate.html
- 浅井畷の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E4%BA%95%E7%95%B7%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 【今日は何の日?】8月9日 浅井畷の戦い、前田利長と丹羽長重が激戦を繰り広げる - いいじ金沢 https://iijikanazawa.com/news/contributiondetail.php?cid=10821
- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E8%97%A9#:~:text=%E4%BA%BA%E6%8C%81%E7%B5%84%E9%A0%AD%E3%81%AF%E5%88%A5%E5%90%8D,70%E5%AE%B6%E3%81%8C%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82
- 加賀藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E8%97%A9
- 主計町だより - 金沢市 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminkyodosuishinka/gyomuannai/3/1/5264.html
- 摩利支天の隠れ寺、宝泉寺|由来と秘密 https://gohonmatsu.or.jp/hondo/
- 摩利支天のページ 天目山栖雲寺 ホームページ http://tenmokusan.or.jp/pg3335049.html
- イノシシに乗る守護神!多くの武士に信仰された摩利支天 - RIYAK https://www.riyak.jp/column/242/
- 【仏像の知識】摩利支天とは? - 陽炎(かげろう)を神格化した神 https://shishi-report-2.hatenablog.com/entry/kiso-marishiten
- 摩利支天 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%A9%E5%88%A9%E6%94%AF%E5%A4%A9
- 日本三摩利支天、宝泉寺 - 金沢 宝泉寺 https://gohonmatsu.or.jp/history/
- 雑記:剣豪の石廟|綾 - note https://note.com/seki_hakuryou/n/nd5e7852f7444
- 【富田主計について】 富田高定の実子である富田主計と - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000232792
- 主計町の歴史 | 浅の川 金沢市主計町 金澤町家 一棟貸切り宿 https://asanogawa.jp/history/
- 富田主計重家ゆかりの「主計町(かずえまち)」〜その由来と旧町名復活について〜 | 金沢徒然日記 https://ameblo.jp/yanahimenomikoto/entry-12322393894.html
- 【まちネタ】柳生宗矩と並び称せられた剣豪 「慈雲寺」にある富田家の墓 - いいじ金沢 https://iijikanazawa.com/news/contributiondetail.php?cid=7079
- 慈雲寺冨田家石廟群 附燈籠二基 - 金沢市 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/bunkazaihogoka/gyomuannai/3/1/1/bunkazai_tagengo/2/5710.html
- 冨田流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%A8%E7%94%B0%E6%B5%81
- 戸田派武甲流薙刀術/武陽館道場 https://todahabukoryu.jp/