平田光宗
平田光宗は島津氏の老中。庶流から嫡流を継ぎ、島津貴久・義久に仕え、三州統一戦や九州制覇に貢献。肥後八代の守将や各地の地頭を歴任し、文化人としても活躍。
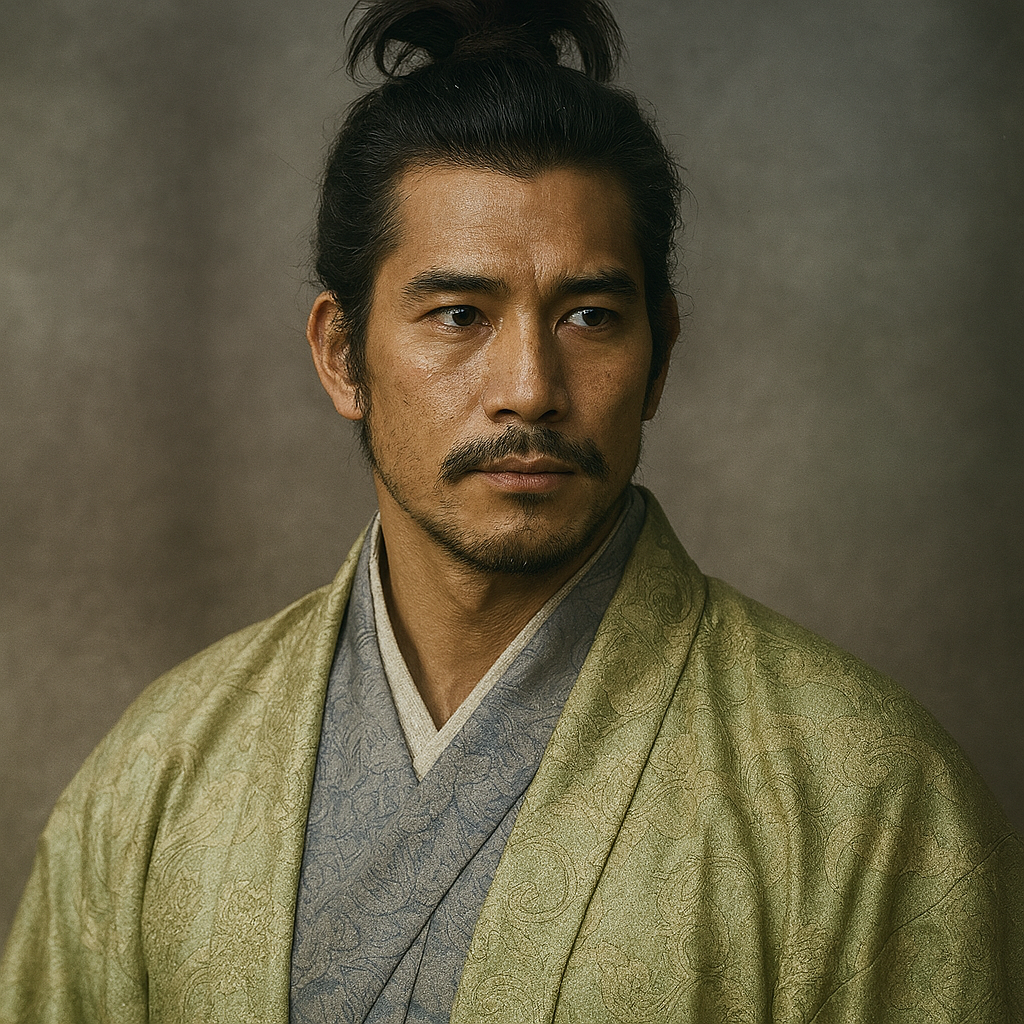
島津家老中 平田光宗の生涯 ― 九州の動乱を駆け抜けた武将の実像
平田光宗 関連年表
|
西暦(和暦) |
光宗の年齢(数え) |
出来事 |
関連人物・場所 |
根拠史料・情報源 |
|
1529年(享禄2年) |
1歳 |
薩摩平田氏の庶流、平田宗秀の二男として誕生。 |
平田宗秀 |
1 |
|
不明 |
不明 |
平田氏嫡流の平田昌宗の娘婿となり、養子として宗家を継承。 |
平田昌宗 |
1 |
|
不明 |
不明 |
島津貴久の代から老中(家老)として仕える。 |
島津貴久 |
1 |
|
1573年(天正元年) |
45歳 |
大隅国にて肝付氏との戦いの中、早崎の陣営を守備。 |
大隅国 |
1 |
|
1578年(天正6年) |
50歳 |
日向国における石城攻めに参加。耳川の戦いの前哨戦。 |
日向国石城 |
1 |
|
1582年(天正10年) |
54歳 |
島津氏の肥後侵攻に伴い、八代に守将として駐留。 |
肥後国八代 |
5 |
|
1583年(天正11年) |
55歳 |
肥後堅志田城攻めで軍功を挙げる。 |
肥後国堅志田城 |
1 |
|
1583年(天正11年) |
55歳 |
9-10月、伊集院忠棟らと独断で堅志田を攻撃し、主君・義久から叱責される。 |
島津義久、伊集院忠棟、上井覚兼 |
6 |
|
1584年(天正12年) |
56歳 |
肥前島原で勃発した沖田畷の戦いに、島津家久軍の一員として従軍。 |
島津家久、龍造寺隆信、肥前国 |
1 |
|
1586年(天正14年) |
58歳 |
豊臣軍との戦いにおいて、筑前岩屋城攻めに主君・義久の供として参加。 |
島津義久、筑前国岩屋城 |
3 |
|
1587年(天正15年) |
59歳 |
日向根白坂の戦いに主君・義久の供として参加。 |
島津義久、日向国根白坂 |
3 |
|
1588年(天正16年) |
60歳 |
主君・義久の上洛に際し、太刀役という名誉ある役目を務める。 |
島津義久 |
3 |
|
不明 |
不明 |
肥後八代、大隅帖佐、薩摩郡山、薩摩西別府の地頭職を歴任。 |
- |
1 |
|
1606年2月3日(慶長10年12月26日) |
77歳 |
薩摩国郡山にて死去。 |
薩摩国郡山 |
1 |
序章:島津氏の重臣、平田光宗 ― その生涯と時代背景
本報告書は、戦国時代から安土桃山時代にかけて、九州の南端から怒涛の勢いでその版図を拡大した島津氏の興隆を、武勇と知略をもって支えた一人の重臣、平田光宗(ひらた みつむね)の生涯を、現存する史料に基づき多角的に解明するものである 1 。
光宗が生きた享禄2年(1529年)から慶長10年(1605年)までの77年間は、島津氏にとってまさに激動の時代であった。島津家15代当主・貴久が分裂していた薩摩国内の統一を成し遂げ、その子である16代当主・義久の時代には、薩摩・大隅・日向の「三州統一」を達成。さらには宿敵である大友氏や龍造寺氏を打ち破り、九州の覇権に手をかける寸前まで突き進んだ 8 。この島津氏の飛躍は、義久、義弘、歳久、家久という傑出した「島津四兄弟」の活躍に負うところが大きいが、その背後には、彼らを支える有能な家臣団の存在が不可欠であった。
平田光宗は、その家臣団の中核をなす人物である。彼は単に戦場で武功を立てた武将に留まらず、島津貴久・義久の二代にわたって「老中」という重職を務め、政務の中枢に深く関与した 1 。その生涯は、九州各地を転戦した軍事の記録と、肥後八代の守将や各地の地頭として領国経営にあたった統治の記録とが、分かちがたく結びついている。本報告書は、利用者より提供された情報の範疇に留まることなく、武将として、そして統治者としての平田光宗の実像に、史料を通じて徹底的に迫ることを目的とする。
第一章:出自と平田氏嫡流の継承
平田光宗の生涯を理解する上で、彼が属した薩摩平田氏の家格と、彼自身が嫡流を継承するに至った経緯を把握することは極めて重要である。それは、彼のキャリアの出発点であり、その後の活躍を支える基盤となったからである。
第一節:薩摩平田氏の系譜と格式
薩摩平田氏は、桓武平氏を祖に持つとされる名門一族である 11 。島津氏がまだ鎌倉幕府の御家人として薩摩に下向した初期の時代から仕え、代々家老職を輩出してきた、いわゆる譜代の重臣であった 11 。光宗の養父である平田昌宗の父・兼宗は島津立久の家老を務め、昌宗自身も島津貴久・義久の二代にわたって家老職にあり、大隅国帖佐郷の地頭を務めるなど、島津家中において極めて高い地位を占めていた 1 。このような家柄は、一族の者が島津家の政権中枢に参画するための揺るぎない基盤となっていた。
第二節:庶流からの誕生と嫡流継承
平田光宗は、享禄2年(1529年)、この名門平田氏の庶流にあたる平田備中守宗秀(むねひで)の子として生を受けた 1 。父・宗秀は、当初薩摩国内で島津宗家と対立していた薩州島津家に属していたが、後に島津宗家の再興を成し遂げた伊作島津家の島津忠良に降伏し、その家臣となった人物である 1 。
光宗の運命が大きく転換するのは、平田氏の嫡流、すなわち本家当主であった平田昌宗に男子が生まれなかったことによる。跡継ぎを欠いた昌宗は、庶流から有能な人材を迎え入れることを決断し、光宗を自らの娘婿として迎え、養子としたのである 1 。これにより、庶流出身の光宗は、島津家中で重きをなす平田氏の宗家を継承することとなった。なお、光宗が父・宗秀の「長男」であったとする史料 3 と、「二男」であったとする史料 1 が存在するが、複数の史料が「二男」と記していることから、後者の方がより蓋然性が高いと考えられる。
この養子縁組は、単なる一個人の家督相続という私的な出来事には留まらない。戦国時代の大名家において、有力家臣団の安定は主家の安定に直結する。特に平田氏のような代々家老を輩出する一族の嫡流が途絶えることは、一族の求心力や発言力の低下を招き、ひいては島津家中の権力バランスにまで影響を及ぼしかねない重大事であった。したがって、この養子縁組は、血統の維持が困難になった際に、庶流から能力のある者を選び出し、婚姻関係を通じて嫡流に組み込むことで一族の結束を固め、「家老の家」としての地位と影響力を将来にわたって維持しようとする、極めて戦略的な判断であったと分析できる。これは、個人の能力と家格(血統)を巧みに融合させることで、激動の時代を生き抜こうとした戦国武家社会における、合理的な生存戦略の一つの典型例と言えよう。
第二章:武将としての戦歴
平田光宗は、老中として政務を担う一方で、島津氏の九州制覇事業の最前線に立ち続けた歴戦の武将であった。彼の戦歴は、島津氏の勢力圏が南九州から北九州へと拡大していく過程と完全に軌を一にしており、彼の武功はそのまま島津氏の膨張の歴史を体現している。
第一節:三州統一戦における武功(天正年間初期)
光宗の武将としての活動が史料で明確に確認できるのは、天正年間に入ってからである。天正元年(1573年)、島津氏は長年にわたり大隅国の支配を争ってきた肝付氏との最終決戦に臨んでいた。この戦いの中で、光宗は「早崎営を守備」したと記録されており、この時点で既に一軍を預かる指揮官クラスの武将として活動していたことがわかる 1 。
さらに、天正六年(1578年)、島津氏の歴史における一大転機となった「耳川の戦い」の前哨戦である「石城(いしのじょう)攻め」に参加している 1 。石城は、日向国を追われた伊東氏の残党が、宿敵・大友氏の支援を受けて立てこもった城であった。小丸川の断崖絶壁に築かれた天然の要害であり、攻略は極めて困難であったと伝えられる 4 。島津家が総力を挙げて臨んだこの重要な戦役に、光宗が加わっていたという事実は、彼が島津軍の中核を担う将帥の一人として、主家から厚い信頼を寄せられていたことを示している。
第二節:九州制覇への道(天正年間中期)
三州統一を成し遂げた島津氏が、次なる目標として肥後・肥前へと侵攻を開始すると、光宗の戦場もまた北へと移っていく。
天正十一年(1583年)、島津氏は肥後国への本格的な侵攻を開始し、光宗は「肥後堅志田城攻め」に参加して軍功を挙げた 1 。この肥後方面での活動は、後に彼が八代の守将に任じられる布石となった。
そして翌天正十二年(1584年)、九州の勢力図を塗り替える決戦、「沖田畷の戦い(島原合戦)」が勃発する。肥前の「熊」と恐れられた龍造寺隆信が、数万ともいわれる大軍を率いて島津方の有馬氏に攻め寄せたのに対し、島津家は義久の弟・家久を総大将とする救援軍を派遣した。光宗はこの決戦に、島津軍の主力部隊の一員として従軍している 1 。この戦いには、新納忠元、川上忠堅、山田有信といった島津家が誇る猛将たちが顔を揃えており、光宗も彼らと肩を並べる重鎮として参陣したのである 6 。島津軍は兵力で圧倒的に劣勢であったが、総大将・家久の巧みな指揮と、島津伝統の「釣り野伏せ」戦法を駆使して龍造寺軍を壊滅させ、総大将・龍造寺隆信を討ち取るという歴史的な大勝利を収めた 16 。この勝利は島津氏の武威を九州全土に轟かせるものであり、その一翼を担った光宗の武歴においても、最大の栄誉の一つとして記録されるべきものである。
第三節:豊臣政権との対峙(天正年間後期)
破竹の勢いで九州統一に迫る島津氏の前に、天下統一を進める豊臣秀吉の大軍が立ちはだかる。この島津家の存亡をかけた戦いにおいても、光宗は主君・島津義久の側近くにあり、最後まで忠誠を尽くした。
天正十四年(1586年)、豊臣軍の九州侵攻に先立ち、島津軍は筑前国に侵攻。その際の凄惨な籠城戦として知られる「岩屋城攻め」において、光宗は義久の供をしていた記録が残る 3 。さらに翌天正十五年(1587年)、豊臣秀長率いる本隊と島津軍が雌雄を決した日向「根白坂の戦い」においても、彼は義久の傍らにあった 3 。これらの戦いは、いずれも島津方が多大な犠牲を払った敗戦であったが、国家存亡の危機に際して、光宗が主君の側近として最後までその責務を果たしたことを物語っている。
光宗の戦歴を俯瞰すると、その戦場が大隅(早崎)、日向(石城)、肥後(堅志田)、肥前(沖田畷)、筑前(岩屋城)と、島津氏の勢力拡大の最前線と見事に重なっていることがわかる。これは、彼が単に命令を受けて戦う一兵卒ではなく、島津家の九州制覇という壮大な国家戦略を深く理解し、その各段階において重要な役割を担うことを期待された、中核的な指揮官であったことを明確に示している。彼の武将としてのキャリアは、戦国大名・島津氏の成長と膨張の物語、そのものを映し出す鏡であったと言えよう。
第三章:老中・地頭としての統治
平田光宗の真価は、戦場での武功のみに留まらない。彼は島津家の「老中」として政権の中枢にあり、また各地の「地頭」として領国経営の第一線に立つ、優れた統治者でもあった。彼の行政官としての側面は、武将としての側面と表裏一体をなし、その人物像に深みを与えている。
第一節:島津家の「老中」職
光宗は、島津貴久・義久という二人の主君の下で「老中」を務めた 1 。戦国期の島津家における老中職は、後年の江戸時代の家老に相当する最高位の役職である。薩摩藩の制度では、家老職に就くことができるのは「御一門」や「一所持」といった限られた高い家格の者に限定されていた 17 。光宗が庶流の出身でありながらこの地位に就くことができたのは、彼が平田氏の嫡流を継承したことによるものである。老中として、彼は主君の側近として政務全般を補佐し、軍事作戦の立案から外交、領国経営に至るまで、広範な権限と責任を担っていたと考えられる 10 。
第二節:肥後八代の守将と独断出兵事件
天正10年(1582年)、島津氏が肥後国へ侵攻し、長年同地を支配してきた相良氏を降伏させると、その重要拠点であった八代は島津家の直轄領とされた 6 。この肥後統治の最前線ともいえる八代の守将として、光宗は現地に派遣され、駐留することになる 5 。史料によれば、彼は堅固な城郭(当時の古麓城あるいは麦島城)に立てこもるのではなく、城下の屋敷を「宿館」として統治の拠点としたと記されている 5 。これは、軍事占領下における実務を重視した統治形態であったことを示唆している。
この八代在番中に、光宗のキャリアにおける重要な逸話となる事件が発生する。天正11年(1583年)の9月から10月にかけて、光宗は同じく八代に在番していた同僚の伊集院忠棟や上井覚兼らと共に、主君・義久の明確な許可を得ないまま、独断で阿蘇氏の領地である堅志田へ出兵し、攻撃を仕掛けたのである 6 。この行動は、義久の逆鱗に触れ、鹿児島から叱責の使者が八代へ派遣されるという事態にまで発展した 6 。
この独断出兵事件は、単なる光宗個人の血気にはやった行動として片付けるべきではない。ここには、巨大化していく軍事組織が必然的に抱える構造的な問題が見て取れる。すなわち、肥後統治の最前線に立つ光宗ら現場指揮官は、眼前の敵である阿蘇氏の動きに対し、戦術的な好機と判断して即座に行動を起こそうとした。一方で、本国である鹿児島にあって九州全体の戦局を俯瞰する総司令官・義久は、阿蘇氏との外交交渉や、より大きな脅威である龍造寺氏への備えといった、大局的な戦略を優先していた。現場の突出した軍事行動は、義久が進める大戦略を台無しにしかねない危険なものであった。この事件は、中央の「戦略的判断」と、最前線の「戦術的判断」との間に生じた、避けがたい軋轢の表れと解釈することができる。光宗らが叱責されたのは当然であるが、その後も彼が失脚することなく重用され続けた事実を鑑みれば、その行動の根底にあった島津家への忠誠心や、敵に対する積極的な姿勢そのものは、義久から一定の評価を受けていたものと推察される。
第三節:各地の地頭職
光宗は、肥後八代の地頭(守将)としての任務のほか、本国においても大隅帖佐郷、薩摩郡山、薩摩西別府といった複数の地域の地頭職を歴任したことが記録されている 1 。地頭職は、担当地域の行政、司法、警察、軍事のすべてを統括する、領国経営の根幹をなす重要な役職である。光宗がこれほど多くの、しかも戦略的に重要な地域の地頭を歴任したという事実は、彼の武将としての能力だけでなく、統治者・行政官としての手腕もまた、島津家中で高く評価され、絶大な信頼を得ていたことの何よりの証左と言えるだろう。
第四章:人物像と文化的側面
平田光宗は、戦場を駆け巡り、政務を司るだけの人物ではなかった。現存する一次史料や後世の伝承は、彼が豊かな文化的教養を身につけ、人間的な魅力に溢れた人物であったことを我々に伝えている。
第一節:『上井覚兼日記』に見る素顔
光宗と同時代を生きた島津家の重臣・上井覚兼(うわい かくけん)が残した一級史料『上井覚兼日記』には、平田光宗が頻繁に登場し、その人物像を知る上で極めて貴重な情報を提供している 20 。
例えば、天正11年(1583年)、独断出兵事件で揺れる肥後八代の陣中にありながら、光宗が上井覚兼らを自らの宿館に招いて饗応し、謡の会を催したことが記されている 20 。また、別の日の記録には、光宗の館において、島津家の一門である島津彰久(島津家久の子)や、光宗の養子である平田増宗、税所助五郎といった家中の次代を担う若者たちが集い、奥山左近将監という師範から鼓の稽古を受けていた様子が描かれている 20 。これらの記述は、光宗が単に武骨なだけの武辺者ではなく、謡や鼓といった芸能に深く通じた、洗練された文化的教養を身につけた上級武士であったことを示している。
さらに重要なのは、彼の館が文化活動の場として機能していた点である。戦国時代の上級武士にとって、茶の湯や連歌、能といった文化活動は、単なる趣味や娯楽ではなかった。それは自らの教養や社会的地位を示すステータスシンボルであると同時に、人間関係を円滑にし、情報交換を行い、時には政治的な派閥を形成するための重要な「社交の場」であった。光宗が自身の館で、島津家の一門や他の重臣たちを招いてこうした会合を頻繁に催していたことは、彼が平田家の当主として、また島津家の老中として、家中の主要人物たちを繋ぎ、その中心で影響力を行使する存在であったことを強く示唆している。彼の文化人としての一面は、政治家としての一面と不可分に結びついていたのである。
第二節:民俗芸能に刻まれた記憶
光宗の人物像は、硬い史料だけでなく、民衆の間に伝わる芸能の中にもその姿を留めている。宮崎県木城町に伝わる民俗芸能「上野臼太鼓踊り」は、その起源が平田光宗にあると伝えられている 23 。
伝承によれば、天正六年(1578年)の高城川の戦い(耳川の戦い)の際、敵味方が激しくぶつかり合う中、島津軍の士気を高めるために、平田光宗が臼を首に掛け、それを太鼓のように打ち鳴らしながら勇壮に舞ったことが、この踊りの始まりであるという 23 。この伝承の史実性を直接証明することは困難であるが、光宗という武将が、兵士たちを鼓舞し、奮い立たせるような、カリスマ的な指導力を持った人物として記憶され、後世にまで語り継がれたことを示す興味深い事例である。
第三節:主君からの厚い信任
光宗が主君から寄せられた信頼の厚さを象徴する出来事が、天正十六年(1588年)に記録されている。この年、豊臣秀吉への臣従儀礼のため主君・島津義久が上洛した際、光宗はその「太刀役」という極めて名誉ある役目を務めた 3 。太刀役は、主君の刀を預かり、その身辺を警護する役目であり、武勇に優れ、かつ最も忠誠心篤いと信頼された者でなければ務まらない。独断出兵事件で義久から叱責を受けた過去がありながらも、このような大役を任されたという事実は、二人の間にあった個人的な、そして強固な信頼関係が、終生揺るがなかったことを何よりも雄弁に物語っている。
終章:晩年と平田氏のその後
九州全土を巻き込んだ動乱の時代を、武将として、また統治者として駆け抜けた平田光宗。彼の晩年と、その跡を継いだ一族の運命は、戦国時代から近世へと移行する時代の大きな転換点を象徴している。
第一節:安らかな最期
数多の戦場を生き抜き、主家の発展に生涯を捧げた平田光宗は、慶長10年12月26日(西暦1606年2月3日)、薩摩国郡山(現在の鹿児島市郡山町)の地で、77歳の天寿を全うした 1 。戦乱の中で命を落とす武将が数多いる中で、畳の上で安らかな最期を迎えることができた彼の人生は、激動の時代を生き抜いた成功者の一つの姿であったと言える。
第二節:嫡流の悲劇 ― 平田増宗の誅殺
光宗の死後、平田氏の家督は養子である平田増宗(ひらた ますむね)が継承した。増宗もまた父・光宗同様に優れた人物であり、島津義久の家老として重用され、その信任は厚かった 11 。しかし、彼が生きた時代は、父の時代とは大きく異なっていた。
関ヶ原の戦いを経て、島津家が徳川幕藩体制下の「近世大名」として生き残りを図る中で、家中では深刻な内部対立が表面化する。その最大の要因は、義久・義弘兄弟と、家督を継いだ甥の家久(忠恒)との間の複雑な権力関係であり、これが家臣団をも巻き込むお家騒動へと発展した。増宗は、旧主である義久への忠誠心から、義久の外孫(二女・新城の遺児)にあたる島津忠仍(ただなお)を次期当主として擁立しようと画策したとされる 24 。これは、当主である家久(忠恒)の権威に正面から挑戦する行為であり、両者の対立は決定的なものとなった。
その結果、慶長15年(1610年)、増宗は主君・家久(忠恒)の密命によって誅殺されるという悲劇的な最期を遂げた 11 。これにより、光宗が継承し、守り抜いた平田氏の嫡流は、無残にも断絶することとなった。
この平田光宗と増宗という父子の対照的な運命は、時代の大きな転換を象徴している。父・光宗は、島津家が外部の敵と戦い、領土を拡大していく「対外膨張の時代」に活躍し、その武功と統治能力によって評価され、成功を収めた。一方で、息子・増宗は、外部の脅威が去り、島津家が内部の権力構造を再編・統合していく「内部固めの時代」に生きた。この時代に重臣に求められたのは、もはや対外的な武功ではなく、新たな権力秩序への順応であった。増宗の悲劇は、彼個人の資質の問題以上に、戦国的な価値観が通用しなくなった近世という新しい時代の到来と、それに伴う武士社会の変質によって引き起こされたと言える。光宗の輝かしい生涯と、その息子の悲劇的な末路は、一個の家族の物語を超えて、戦国という時代が終焉を迎え、新たな秩序が生まれる過程の光と影を、鮮やかに映し出しているのである。
引用文献
- 戦国浪漫・武将編(ひ) - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/busyo/busyo-hi.html
- 平田光宗(ひらたみつむね)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=DD03
- 平田光宗 (ひらた みつむね) https://ameblo.jp/tetu522/entry-12034033633.html
- 石城合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%9F%8E%E5%90%88%E6%88%A6
- 八代城跡二の丸 - 八代市 https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00312031/3_12031_45482_up_ky15mbll.pdf
- 島原合戦(沖田畷の戦い)と阿蘇合戦/戦国時代の九州戦線、島津 ... https://rekishikomugae.net/entry/2023/05/23/173421
- 平田光宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E7%94%B0%E5%85%89%E5%AE%97
- 島津一族(島津一族と城一覧)/ホームメイト https://www.homemate-research-castle.com/useful/16998_tour_079/
- 島津義弘の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/38344/
- 武将 島津家 http://www4.tokai.or.jp/bajoushounen/bushou%20shimadu2016.html
- 武家家伝_薩摩平田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/s_hirata.html
- 平田宗勝(四代略)―宗正宗卯―正房 正輔 正香正休 正純 - 金城学院大学リポジトリ https://kinjo.repo.nii.ac.jp/record/507/files/13_nakanishi.pdf
- 平田宗茂(ひらたむねしげ)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=3207
- 「#谷山」のYahoo!リアルタイム検索 - X(旧Twitter)をリアルタイム検索 https://search.yahoo.co.jp/realtime/search/%23%E8%B0%B7%E5%B1%B1/?p=%23%E8%B0%B7%E5%B1%B1&ei=UTF-8&mtype=image&rkf=1
- 天正六年 六月 島津忠長、島津征久、島津家久ら 石ノ城を攻む(第一次石ノ城攻防戦) - 佐土原城 遠侍間 http://www.hyuganokami.com/kassen/takajo/takajo5.htm
- カードリスト/島津家/Ver.1.2/017_島津家久 - 戦国大戦wiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengoku-taisen/pages/1512.html
- 薩摩藩家臣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9%E5%AE%B6%E8%87%A3
- 島津又七の生涯 https://kuchinoerabu-jima.org/wp_monky/wp-content/uploads/2021/06/%E2%91%A6issho-2.pdf
- 敵中突破!関ケ原合戦と島津の退き口 - 大垣観光協会 https://www.ogakikanko.jp/shimazunonokiguchi/
- 第14回「発掘調査からわかった島津氏の文化力!(能舞台編)」 - 鹿児島県上野原縄文の森 https://www.jomon-no-mori.jp/20220303-2/
- 『信長の野望・天道』武将総覧 http://hima.que.ne.jp/tendou/tendou_data.cgi?up1=0%3Btarget;target=1328;max=1328;print=25;p=52
- 上井覚兼日記 | khirin C https://khirin-ld.rekihaku.ac.jp/rdf/nmjh_kaken_medInterNationalExcange/E8071
- 高千穂町の祭りと伝統芸能 http://www.komisen.net/events.htm
- 平田増宗暗殺400年 | 膏肓記 - FC2 http://dangodazo.blog83.fc2.com/blog-entry-832.html