稲葉典通
稲葉典通は稲葉一鉄の孫、貞通の子。豊臣秀吉に仕え、九州征伐や秀次事件で失脚も復帰。関ヶ原で東軍に転じ、豊後臼杵藩二代藩主として藩政を確立。
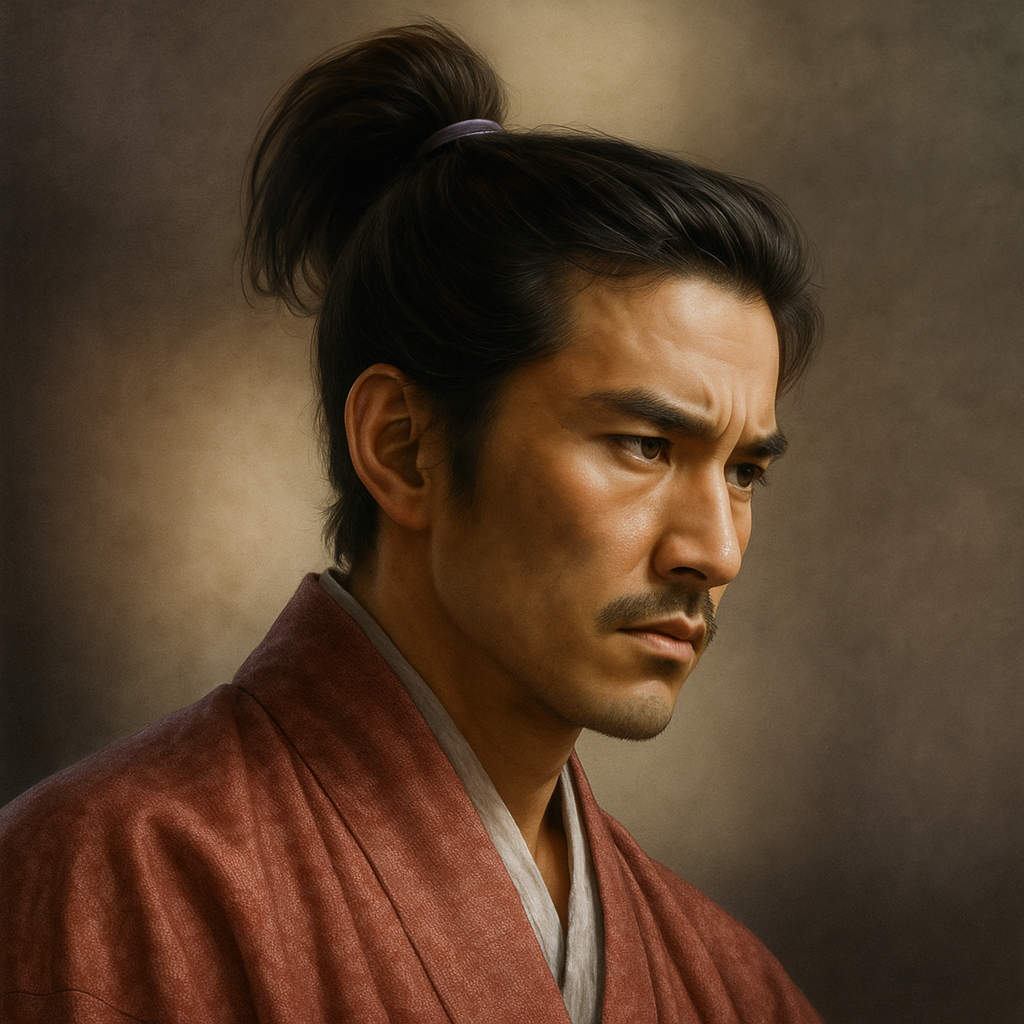
稲葉典通公に関する調査報告
はじめに
本報告書は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将、稲葉典通(いなば のりみち)の生涯と事績について、現存する資料に基づき詳細に検証するものである。稲葉典通は、美濃の有力国人であった稲葉氏の出身であり、祖父に「頑固一徹」の語源ともされる稲葉一鉄(良通)、父に豊後臼杵藩初代藩主となる稲葉貞通を持つ。彼の生きた時代は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という三英傑が天下統一を推し進めた激動期であり、典通自身もその渦中で家名の維持と発展に努めた。その生涯は、武将としての活躍のみならず、家督相続を巡る複雑な経緯や、主君の勘気を被るなどの曲折に満ちている。
本報告書では、典通の出自と家督相続の背景、織田・豊臣両政権下での動向、天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いにおける決断、そして豊後臼杵藩二代藩主としての治績、さらには彼の人物像や交流、晩年に至るまでを、関連資料を丹念に読み解きながら明らかにしていく。
表1:稲葉典通 略年譜
|
年代(和暦) |
年代(西暦) |
出来事 |
|
永禄9年 |
1566年 |
稲葉貞通の長男として美濃国にて生誕 1 。 |
|
天正3年 |
1575年 |
織田信長より刀を授与された可能性(一鉄の孫として) 3 。 |
|
天正10年頃 |
1582年頃 |
父・貞通より家督を譲られ、美濃曽根城主となる 1 。 |
|
天正13年 |
1585年 |
豊臣姓および官位を下賜される 2 。 |
|
天正15年 |
1587年 |
九州征伐に従軍するも、秀吉の勘気を被り伊勢朝熊に蟄居。父・貞通が家督に復帰 2 。 |
|
文禄元年~ |
1592年~ |
文禄の役に従軍。豊臣秀勝配下として朝鮮に渡海し戦功を挙げる 2 。 |
|
文禄4年 |
1595年 |
豊臣秀次事件に連座し処罰される 2 。 |
|
慶長5年 |
1600年 |
関ヶ原の戦い。当初西軍に属するが、岐阜城落城後、父と共に東軍に転じる 1 。 |
|
慶長8年 |
1603年 |
父・貞通の死去に伴い、豊後臼杵藩二代藩主となる 1 。 |
|
慶長19年・元和元年 |
1614-1615年 |
大坂の陣に徳川方として参戦。夏の陣では遅参 2 。 |
|
寛永3年11月19日 |
1626年12月27日 |
臼杵にて病死。享年61 1 。 |
第一章:稲葉典通の出自と家督相続
一、稲葉氏の系譜と稲葉一鉄・貞通
稲葉氏の出自については、いくつかの説が伝えられている。祖父とされる稲葉通貞(塩塵)は、伊予国の名族・河野氏の一族であったが美濃に流れて土豪になったとされる一方で、美濃の安藤氏と同族で伊賀氏の末裔であるともされている 3 。こうした出自の多様な伝承は、稲葉氏が美濃において複雑な縁戚関係や勢力基盤を築いていたことを示唆しているのかもしれない。
典通の祖父である稲葉良通、後の稲葉一鉄は、美濃国曽根城主であり、安藤守就、氏家直元と並んで「西美濃三人衆」と称された重臣であった 3 。一鉄は武勇に優れ、長篠の戦いでは織田信長から「今弁慶」と賞賛されるほどの活躍を見せた 3 。また、戦略眼に長けていただけでなく、医道にも関心が深く『稲葉一鉄薬方覚書』を伝えるなど、文化的な素養も持ち合わせていた 3 。能にも造詣が深く、その頑固な性格は「頑固一徹」という言葉の語源になったという説もあるほどである 3 。この一鉄の強烈な個性と、主君に対しても臆せず意見する姿勢は、単なる性格的特徴に留まらなかった可能性がある。例えば、織田信長が無断出家を咎めた際や、讒言により暗殺を企てた際にも、一鉄の教養や率直さに触れた信長が最終的に彼を許したという逸話が残っている 3 。これは、一鉄が単に頑固であっただけでなく、信長のような気性の激しい主君の度量を見極め、自身の価値を巧みに示すことで、かえって信頼を勝ち得ていたことを物語っている。この「一鉄」という、ある種のブランドは、その後の稲葉家、特に貞通や典通の代においても、周囲から一定の評価や警戒心、あるいは期待を抱かせる無形の資産として影響したかもしれない。
典通の父である稲葉貞通は、一鉄の次男として生まれたが、正室の子であったため嫡男として扱われた 4 。父・一鉄と共に美濃斎藤氏に仕え、斎藤氏滅亡後は織田信長、そして豊臣秀吉に仕えた 4 。美濃曽根城主、後に郡上八幡城主を経て、関ヶ原の戦いでの功により豊後臼杵藩の初代藩主となり、稲葉家の新たな歴史を切り開いた人物である 4 。貞通の生涯における決断、特に主家の変遷や関ヶ原の戦いにおける去就は、息子である典通の人生にも直接的かつ大きな影響を与え続けることとなる。
二、典通の生誕と成長
稲葉典通は、永禄9年(1566年)、稲葉貞通の長男として美濃国に生を受けた 1 。彼の幼少期や青年期に関する具体的な記録は、提供された資料からは多くを見出すことはできない。しかし、祖父・良通(一鉄)や父・貞通が織田信長の家臣として活躍していたことから、典通もまた武家の後継者として、早くから戦陣や政務に触れる環境で育ったものと推察される 2 。
天正3年(1575年)、織田信長が一鉄の居城である曽根城を訪れた際、信長は一鉄の孫達に能を演じさせて歓待を受け、その返礼として一鉄の嫡男である貞通の子(稲葉典通の可能性が指摘されている)に自らの腰に差していた刀を授与したという記述が『信長公記』に見られる 3 。もしこの逸話の対象が典通であったならば、彼は幼少期に信長と直接的な接点を持ち、その将来を嘱望されていた可能性も考えられ、彼の初期のキャリアにおいて象徴的な出来事であったと言えよう。
三、家督相続の経緯とその背景(複数回の家督変動を含む)
稲葉典通の家督相続は、一度で完了したわけではなく、複数回にわたっている。この複雑な経緯は、彼の生涯を理解する上で極めて重要な点である。
最初の家督相続は、天正10年(1582年)の本能寺の変後、父・貞通から家督を譲られたとされている 2 。この時、典通は美濃曽根城主となった 1 。しかし、別の資料によれば、天正11年(1583年)の賤ヶ岳の戦いに際し、旧主・織田信長の三男である織田信孝に刃向かうことに迷いがあった父・貞通が、典通に家督を譲ったとも伝えられている 4 。いずれにせよ、この時期の家督相続は、父・貞通の政治的判断が大きく影響していたと考えられる。
しかし、典通の当主としての地位は盤石ではなかった。天正15年(1587年)の九州征伐において、典通が豊臣秀吉の機嫌を損ねて伊勢国朝熊に蟄居を命じられたため、父・貞通が再び家督の座につくという事態が生じた 2 。これは典通のキャリアにおける最初の大きな蹉跌であり、彼の立場がまだ不安定であったことを示している。
最終的に典通が再び家督を継承するのは、慶長8年(1603年)、父・貞通の死去によるものであった。これにより、典通は豊後臼杵藩の二代藩主となった 1 。
表2:稲葉典通 家督相続および主要な地位の変遷
|
年月日(和暦) |
地位・出来事 |
関連する背景・理由 |
典拠資料例 |
|
天正10年(1582年)頃 |
美濃曽根城主、稲葉家家督を相続(父・貞通より譲渡) |
本能寺の変後、父・貞通の判断による 2 。一説には天正11年(1583年)賤ヶ岳の戦い時、貞通が旧主の子・織田信孝への攻撃を躊躇したためとも 4 。 |
2 |
|
天正15年(1587年) |
九州征伐で豊臣秀吉の勘気を被り蟄居、父・貞通が家督に復帰 |
詳細は不明だが、秀吉の不興を買う失態があったとされる 2 。 |
4 |
|
慶長8年(1603年) |
父・貞通の死去に伴い、再度家督を相続。豊後臼杵藩二代藩主となる |
貞通の逝去による自然な家督継承 2 。 |
2 |
典通の複数回にわたる家督相続と失脚、そして父・貞通による再登板という経緯は、単に典通個人の資質の問題として片付けられるものではない。むしろ、戦国末期から江戸時代初期にかけての稲葉家が置かれた複雑な政治状況と、家名存続のために父・貞通が下した戦略的な判断が深く絡み合っていた可能性が高い。貞通は、例えば賤ヶ岳の戦いのように旧主の息子と敵対するという危険な局面では、若年の典通に家督を譲ることで直接的な責任を回避し、リスクを分散しようとしたのかもしれない。逆に、典通が九州征伐で秀吉の勘気を買うという失態を犯した際には、経験豊富な自らが再び表に立つことで、稲葉家全体へのダメージを最小限に抑えようとしたのであろう。このような父の戦略の中で、典通はやや受動的な立場に置かれ、そのキャリアは父の意向に大きく左右される場面が多かったと推察される。このことは、当時の武家社会における家督の重みと、それを巡る当主の苦心を示していると言えよう。
第二章:織田・豊臣政権下の稲葉典通
一、織田信長への臣従
稲葉典通は、その祖父・一鉄(良通)、父・貞通と共に織田信長に仕えた 2 。美濃の斎藤氏が滅亡した後、稲葉家は信長の有力な家臣団の一翼を担う存在となっており、典通もその主家の下で武将としての成長を遂げたと考えられる。
前述の通り、天正3年(1575年)に信長が一鉄の居城である曽根城を訪問した際、一鉄の孫(典通の可能性が高い)に自らの腰の刀を授与したという記録が『信長公記』に残されている 3 。この逸話が事実であれば、若き日の典通が信長から直接的な期待を寄せられたことを示すものであり、彼の初期のキャリアにおいて重要な出来事であったと言えるだろう。天正10年(1582年)の本能寺の変に至るまでの典通の具体的な戦功や役職に関する記録は、提供された資料からは限定的であるが、信長の美濃支配体制下において、稲葉家の一員として活動していたことは疑いない。
二、豊臣秀吉への臣従
天正10年(1582年)の本能寺の変で織田信長が横死すると、稲葉家は羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)に与することとなった 2 。この時期に父・貞通から家督を譲られたとされる典通は 2 、秀吉の家臣として新たな道を歩み始める。天正13年(1585年)には、官位と共に豊臣姓を下賜されており 2 、これは秀吉政権下で典通が一定の地位を認められたことを示している。
1.九州征伐への従軍と秀吉の勘気による蟄居
天正15年(1587年)、豊臣秀吉による九州平定の戦役に従軍した 1 。『当代記』によれば、この時、稲葉典通は500の兵を率いて出陣したと記録されている 12 。
しかしながら、この九州征伐の過程において、典通は秀吉の怒りを買い、伊勢国朝熊(あさま)での蟄居を命じられるという事態に見舞われた 2 。この結果、父である稲葉貞通が再び家督を継ぐことになった 4 。秀吉の怒りを買った具体的な理由については、提供された資料には「秀吉の機嫌を損ねて」 4 、「秀吉の怒りを買って」 2 と記されているのみで、その詳細は明らかではない。この事件は、典通の武将としてのキャリアにおける大きな汚点となり、その後の彼の立場に少なからぬ影響を与えた可能性がある。
典通が九州征伐で秀吉の勘気を被った具体的な理由は不明であるが、この一件に対する父・貞通の迅速な家督再取得は、稲葉家全体の危機管理能力の高さを示すと同時に、典通の立場が依然として父の庇護下にあり、独立した大名としての評価を確立するには至っていなかったことを示唆している。豊臣秀吉の勘気は、些細なことであっても家の存亡に関わる可能性を秘めていたため、経験豊富な貞通が即座に責任を負う形で事態の鎮静化を図ったものと考えられる。当時、典通は20代前半とまだ若年であり、秀吉は若手の武将に対しても厳しい評価を下すことがあった。貞通の行動は、息子を守るという親心と、何よりも稲葉家を守るという大局的な判断が働いた結果であろう。この出来事は、典通がまだ一人前の当主として秀吉から全幅の信頼を得るには至っていなかったことを物語っている。
2.小田原征伐への参加
九州征伐での蟄居の後、稲葉典通がいつ許されたのかは明確ではない。しかし、父である稲葉貞通は天正18年(1590年)に豊臣秀吉が行った小田原征伐に1,200余の兵を率いて参陣し、織田信雄の指揮下で韮山城攻めに加わっている 4 。
この時期に典通が父と共に参陣していたか、あるいは別の形で軍役を果たしていたかについては、提供された資料からは直接的な言及を見出すことができない。しかし、父・貞通が主要な戦役に参加していることから、典通も何らかの形でこの北条氏攻略戦に関与していた可能性は否定できない。一部の資料では「豊臣秀吉の九州攻めなどに従軍」 1 とされており、この「など」に小田原征伐が含まれる可能性も考えられるが、明確な記述はない。
3.文禄・慶長の役における動向
文禄元年(1592年)に朝鮮出兵(文禄の役)が開始されると、稲葉典通は豊臣秀勝(秀吉の養子であり、浅井三姉妹の末妹・お江の最初の夫)に召し出されて朝鮮へ渡海し、戦功を挙げたとされている 2 。
この時、豊臣秀勝軍の実質的な指揮は細川忠興が執っていたとも言われており、典通は忠興と共に戦ったことで親交を深めたと記されている 6 。この朝鮮での共闘経験が、後の細川家との密接な関係に繋がる一つの契機となった可能性が考えられる。
父である稲葉貞通も、文禄の役においては諸将と共に朝鮮半島に渡海して各地を転戦しており 4 、稲葉家は親子でこの国策的な大事業に関与していたことになる。
4.豊臣秀次事件との関わりと処遇
朝鮮出兵に従軍した豊臣秀勝が病没した後、稲葉典通は豊臣秀次(秀吉の甥で関白)に仕えることとなった 2 。
しかし、文禄4年(1595年)に秀次事件(秀吉が秀次に謀反の疑いをかけて切腹させ、その妻子や家臣の多くを粛清した事件)が発生すると、典通もこの事件に連座して処罰されたと伝えられている 2 。処罰の具体的な内容や期間については明らかではないが、その後しばらくして再び秀吉に仕えることになったとされている 2 。年代は不明ながら、再度豊臣姓を下賜されたとも記されており 2 、完全に許されたことを示唆している。
この秀次事件への連座は、典通のキャリアにおいて再び訪れた試練であり、豊臣政権内における彼の立場が依然として微妙であったことをうかがわせる。九州征伐での蟄居、そしてこの秀次事件への連座と、典通は豊臣政権下で二度も大きな政治的危機に直面しながらも、最終的には復帰を果たしている。これは、典通個人の能力や運だけでなく、稲葉家が持つ政治力や人脈、特に父・貞通の存在や、あるいは細川忠興のような有力大名との繋がりが背景にあった可能性を示唆している 6 。また、豊臣秀吉政権の人材運用の流動性や、一度罰した者であっても能力や家の格によっては再登用するという柔軟性も、典通の復帰に影響したのかもしれない。度重なる失脚と復帰は、典通自身の政治的生命力の強さ、あるいは稲葉家が持つ総合的な力の現れと見ることもできるだろう。
第三章:関ヶ原の戦いと稲葉典通
一、開戦前の動向と西軍への参加経緯
慶長5年(1600年)、天下分け目の戦いとなる関ヶ原の戦いが勃発すると、稲葉貞通・典通親子は当初、石田三成が率いる西軍に属した 4 。父・貞通は尾張国犬山城の守備を担当しており 4 、典通も父と行動を共にしていたと考えられる 1 。
稲葉親子が西軍に加わった具体的な理由や経緯について、提供された資料からは詳細な記述を見出すことはできない。しかし、いくつかの要因が考えられる。まず、稲葉家は長年にわたり豊臣家に仕え、秀吉から官位や所領安堵などの恩恵を受けてきた豊臣恩顧の大名であった。また、本拠地である美濃国は、石田三成の盟友である岐阜城主・織田秀信(信長の孫)の勢力圏内にあり、地理的にも西軍への参加が自然な流れであったと推察される。豊臣秀吉死後の政情不安の中で、多くの大名がその去就に迷う中、稲葉家もまた、豊臣家への旧恩と、新たな覇権を掌握しつつあった徳川家康との間で板挟みとなり、難しい判断を迫られていた可能性が高い。
二、東軍への寝返り – その背景と決断
西軍として犬山城に籠っていた父・稲葉貞通のもとに、東軍の有力武将である福島正則から書状が送られたとされている 14 。この書状の具体的な内容は不明であるが、東軍への内応を促すものであった可能性が極めて高いと考えられる。
そして、織田秀信が守る岐阜城が東軍によって陥落した後 1 、稲葉貞通・典通親子は西軍から東軍へと寝返るという重大な決断を下した 1 。
この寝返りの具体的な理由としては、第一に岐阜城の早期落城によって西軍の戦略的劣勢が明らかになったこと、第二に福島正則ら東軍方からの積極的な働きかけがあったこと、そして第三に徳川家康の最終的な勝利を見越した、家名存続のための現実的な戦略判断などが挙げられる。 7 の記述は「関ヶ原の戦いで西軍から東軍に寝返り、本戦に参加して武功を挙げた」と明確に記しており、この決断が戦後の処遇に繋がったことを示唆している。
また、この寝返りの背景には、稲葉一族の内部や周辺人物からの働きかけも影響した可能性がある。例えば、典通の従兄弟にあたり、春日局の元夫でもある稲葉正成は、小早川秀秋の東軍への寝返り工作に深く関与したとされており 15 、同様の動きが稲葉本家に対してもあったかもしれない。
稲葉親子の東軍への寝返りは、単なる日和見主義として片付けられるべきではない。関ヶ原の戦いは、武力衝突であると同時に、激しい情報戦でもあった。福島正則からの書状 14 は、東軍の勢いや内部情報、そして寝返った場合の処遇に関する何らかの保証を含んでいた可能性が高い。岐阜城の早期落城という現実は、西軍の戦略的劣勢を誰の目にも明らかにし、稲葉家にとって、勝利する側に付くことが家名を保つ最善の策であるというリアリズムに基づいた判断を促したのだろう。稲葉家は過去にも、主家であった斎藤氏の滅亡に際し、織田信長に内通することで家名を保ったという経験がある 3 。このような経験は、状況に応じて柔軟に立場を変えることの重要性を、家訓として持っていた可能性も示唆している。この決断は、戦国武将が常に直面していた、家の存亡を賭けた厳しい選択の一例と言えよう。
三、本戦における軍功と戦後の処遇
東軍に寝返った後、稲葉貞通・典通親子は、同じく東軍に転じた遠藤慶隆、金森可重らが攻撃していた郡上八幡城の救援に向かった(八幡城の合戦) 4 。この戦いにおいて、稲葉父子は城内に籠る遠藤慶隆の軍勢を追放し、戦勝を収めている 14 。 14 の記述によれば、父・貞通は犬山城でこの急報を受け、自ら4000の兵を率いて八幡に向かい、途中で長男・典通の率いる一隊と合流して八幡城下に到着したとある。
その後、稲葉親子は伊勢長島城の守備に回り、関ヶ原の本戦終結後は、加藤貞泰と共に西軍の長束正家が守る近江水口岡山城の攻略にも参加し、功績を挙げた 4 。
これらの関ヶ原の戦いにおける一連の軍功が評価され、戦後、父・稲葉貞通は、それまでの美濃国郡上藩4万石から、豊後国海部郡、大野郡、大分郡の三郡にまたがる5万60石余(資料により5万石とも)の臼杵城主として加増移封された 4 。これにより、稲葉家は美濃から九州へと大きく所領を移し、豊後臼杵藩の初代藩主となった。典通もこの決定に従い、父と共に新たな領地である臼杵へと移ったものと考えられる。
第四章:豊後臼杵藩主としての稲葉典通
一、臼杵藩五万石への入封
関ヶ原の戦いの論功行賞により、慶長5年(1600年)12月、父・稲葉貞通は豊後国臼杵5万石(資料によっては5万60石余とも記される)に封じられた 4 。これにより、稲葉家は長年本拠としてきた美濃国を離れ、九州の地に新たな領地を得ることとなった。
そして、慶長8年(1603年)、父・貞通が死去すると、稲葉典通が家督を相続し、豊後臼杵藩の第二代藩主となった 1 。
二、藩政の展開
1.臼杵城の修築と城下町の整備
豊後臼杵城は、元々戦国大名・大友宗麟が丹生島という島の上に築いた城であった 19 。稲葉氏が入封した後、初代藩主・貞通と二代藩主・典通の二代にわたって修築が行われ、現在見られるような姿に整備されたと伝えられている 20 。提供された資料の中には、江戸時代後期に属する稲葉氏時代の石垣 19 や、時鐘櫓跡 21 に関する言及があり、彼らが城郭の整備に積極的に関与したことがうかがえる。
稲葉氏による臼杵藩の統治は、その後、明治維新に至るまで15代にわたって続くこととなる 18 。その初代および二代藩主として、貞通と典通は、藩政の基礎を固める上で極めて重要な役割を果たしたと考えられる。
2.寺社政策と民政
臼杵の地に寺院が多い理由の一つとして、藩祖である稲葉貞通、二代藩主の典通、そして三代藩主の一通という、稲葉氏初期三代の藩主による積極的な寺社政策が挙げられている 22 。
これらの寺院建立の目的は、太田一吉の旧領を受け継いだ際に荒廃していた臼杵の町を再興し、領民の人心を掌握するとともに、城下への人々の集住化を図るためであったとされている 22 。これは、新たな領主として民衆の支持を得て、藩体制を安定させるための重要な施策であったと言えるだろう。寺院は信仰の対象であると同時に、地域コミュニティの中心であり、教育や文化の拠点ともなり得る存在であった。
典通個人の治績として、具体的な検地の実施や専売制度の導入といった経済政策に関する詳細な情報は、提供された資料からは見出すことができなかった 7 。しかしながら、城の修築や城下町の整備、そして寺社政策を通じた民心の安定化は、藩の基盤整備に不可欠なものであり、典通の治世における重要な実績と評価できる。
三、藩主としての評価
稲葉典通の藩主としての具体的な評価を直接的に示す資料は少ないものの、父・貞通から受け継いだ臼杵藩の安定と発展に努めたものと考えられる。
18 の資料には、稲葉氏による約270年間の統治が「質素倹約、勤勉といった言葉で表すことのできる、臼杵人気質の礎を作り上げていった」と記されており、典通もその初期の藩政において、こうした気風の形成に何らかの形で関与した可能性がある。
稲葉氏が臼杵藩において約270年もの長期にわたり安定した支配を続けることができた背景には、初代藩主・貞通と二代藩主・典通による初期の藩政運営、特に城郭整備による物理的な支配拠点の確立と、寺社政策などを通じた人心掌握策が効果的に機能したことが大きいと考えられる。典通は、父の敷いた路線を継承し、藩の基盤を固めることで、その後の稲葉氏による長期政権の礎を築いた重要な人物と評価することができる。彼の治世は、戦国の動乱期から江戸時代の安定期への移行期にあたり、藩体制の確立に注力した時期であったと推察される。その功績は、派手な武功というよりも、むしろ地道な藩政運営の中にあったと言えるだろう。
第五章:稲葉典通の人物像と交流
一、史料から見る人物像
稲葉典通個人の性格や逸話を詳細に伝える資料は、提供されたものの中では限定的である。多くの場合、彼の記述は父・貞通や祖父・一鉄といった著名な人物の事績と共に現れることが多い。
九州征伐における失態 2 や、豊臣秀次事件への連座 2 といった出来事は、彼のキャリアにおける不運、あるいは若さゆえの未熟さを示唆しているのかもしれない。一方で、文禄の役での戦功 2 や、関ヶ原の戦い後の水口岡山城攻めにおける功績 4 など、武将としての能力を的確に発揮した場面も見受けられる。
大坂夏の陣において遅参したという記録 2 については、その具体的な理由は不明であり、九州からの長距離の動員であったことや、何らかの藩内事情があったのか、あるいは彼の慎重な性格の現れであったのか、解釈の余地が残る。
なお、資料中には「稲葉紀通(いなば のりみち)」という、読みは同じだが字が異なる人物に関する逸話が散見される 30 。この稲葉紀通は、狩りの獲物が得られなかったとして近隣の村民60人を殺害するなどの狂行で知られる福知山藩主であり、本報告書の対象である豊後臼杵藩二代藩主・稲葉典通とは全くの別人であるため、混同しないよう注意が必要である。
40 の資料には、稲葉貞通に嫁いだ斎藤道三の娘が稲葉典通を産み、その子孫が仁孝天皇の生母である勧修寺婧子(かじゅうじ ただこ)に繋がるという説が紹介されている。これは典通の母に関する記述であり、典通自身の人物像に直接関わるものではないが、彼が名家の血筋を引いていたことを示唆している。
二、細川忠興との関係
稲葉典通の嫡男である稲葉一通の室は、細川忠興の三女・多羅であった 32 。この婚姻により、稲葉家と細川家は姻戚関係を結ぶこととなり、これは当時の大名家間の連携強化や家格の維持において重要な意味を持っていた。
この姻戚関係の背景には、典通と忠興の間に個人的な信頼関係があった可能性が考えられる。文禄の役において、典通は豊臣秀勝の配下として朝鮮へ渡海したが、この時、細川忠興が実質的な指揮を執っており、典通は忠興と共に戦ったことで親交を深めたとされている 6 。この朝鮮での共闘経験が、後の両家の結びつきを強固にする伏線となったのかもしれない。
さらに、名古屋城普請の際には、細川家は稲葉典通、木下延俊、毛利高政と同じ「普請組合」になるよう手配したと記録されている 33 。これは、大規模な土木工事における大名間の協力関係や親疎関係を示すものであり、細川忠興が稲葉典通を信頼できる相手、あるいは親しい間柄と見なしていたことを強く示唆している。 36 の資料によれば、普請場での他家との衝突を未然に防ぐため、姻戚関係にある稲葉家や木下家、そして親しい間柄であった毛利家と組むことを優先したとあり、安全策としての意味合いも強かったようである。
稲葉典通と細川忠興との関係は、単なる個人的な親交を超え、戦国末期から江戸初期にかけての大名家としての生存戦略の一環であったと考えられる。文禄の役での共闘経験を基盤とし 6 、嫡男・一通と忠興の娘との婚姻 32 を結ぶことで、当時政界で非常に影響力のあった有力大名である細川家との間に強固なパイプを構築した。これは、中央政権との関係維持や、他の大名家との勢力バランスを考慮した上での、稲葉家の巧みな外交戦略の現れと言えるだろう。特に、豊臣政権下で典通自身が度重なる失脚を経験したことから、有力者との連携の重要性を痛感した結果、このような関係構築を戦略的に進めたのかもしれない。
三、その他の関連人物
稲葉典通の生涯において、特に重要な影響を与えた人物として、まず祖父・稲葉一鉄(良通)と父・稲葉貞通が挙げられる。彼らの事績や下した判断は、常に典通のキャリアと密接に関連していた。
主君筋では、豊臣秀吉が典通にとって恩恵と試練の両方を与えた存在であった。官位や豊臣姓を与えられる一方で、勘気を被り蟄居させられるなど、その関係は複雑であった 2 。また、豊臣秀勝や豊臣秀次も、朝鮮出兵や秀次事件を通じて典通が仕えた人物たちであり、これらの関わりが彼の運命を左右する一因となった 2 。
さらに、春日局(お福)の存在も間接的に稲葉家、ひいては典通の家格に影響を与えた可能性がある。春日局は、典通の従兄弟にあたる稲葉正成の妻(後に離縁)であり、稲葉一鉄の縁者でもあった 15 。彼女が徳川三代将軍・家光の乳母として絶大な権勢を握ったことは、稲葉一族の名門としての地位を高めたとされており 29 、これが典通の家にとっても無縁ではなかっただろう。稲葉正成と典通の関係については、資料によって貞通の従兄弟 38 、あるいは典通の従兄弟(一鉄の長男・重通の娘婿または養子) 15 など若干の記述の揺れが見られるが、一般的には春日局の夫・稲葉正成は、一鉄の長男・重通の娘婿(または養子)であり、典通から見れば義理の従兄弟(または従兄弟の子)にあたる関係が有力視されている。
第六章:晩年と死没
一、大坂の陣への参加
慶長19年(1614年)に勃発した大坂冬の陣において、稲葉典通は徳川方に与して参戦した 2 。豊後臼杵藩主として、新たに確立された徳川政権への忠誠を示す重要な機会であったと考えられる。
翌年の元和元年(1615年)の大坂夏の陣にも参加したが、この時は遅参したと記録されている 2 。遅参の具体的な理由については不明であるが、九州からの長距離の動員であったことや、何らかの藩内の事情、あるいは戦略的な判断があった可能性も考えられる。なお、稲葉紀通( 31 )も大坂冬の陣で初陣しているが、これは前述の通り別人である。
二、最期と後継者
寛永3年(1626年)、稲葉典通は江戸幕府第三代将軍・徳川家光の上洛に随行したが、その直後に発病した。そして同年11月19日(資料によっては11月9日とも記される 2 )、居城である豊後臼杵にて病死した 1 。享年61歳であった 1 。
典通の死後、家督は長男である稲葉一通(いなば かずみち)が継いだ 2 。一通の母が誰であったかについては、提供された資料からは特定することができなかった。しかし、一通の妻は細川忠興の娘・多羅であり 32 、稲葉家と細川家の間の密接な姻戚関係は次代にも引き継がれていくこととなった。
おわりに
稲葉典通の生涯を顧みると、彼は戦国時代の終焉から江戸時代初期という日本史における大きな変革の時代を生きた武将であった。偉大な祖父・一鉄や、初代藩主として功績を残した父・貞通の影に隠れがちな側面もあり、また豊臣政権下では二度にわたる失脚という不遇の時期も経験した。しかし、最終的には関ヶ原の戦いにおける的確な判断(あるいは父の判断への追随)によって家名を保ち、豊後臼杵藩二代藩主として藩政の基礎を固めるという重要な役割を果たした。
彼の人生は、個人の武勇や才覚だけではなく、家の存続という重責、主君との複雑な関係、そして有力大名との外交(婚姻政策など)といった、当時の武将が否応なく直面する多様な要素によって大きく左右されたものであったと言える。特に、父・貞通との関係性、複数回にわたる家督の変動、そして細川家との姻戚関係は、典通の生涯を理解する上で欠かすことのできない重要な鍵となる。これらの要素を総合的に捉えることで、稲葉典通という一人の武将の多面的な実像に迫ることができるだろう。
その治績は、直接的な記録こそ少ないものの、臼杵の城郭整備や寺社政策を通じた町づくりにその名残をとどめており 20 、その後の稲葉氏による約270年間にわたる安定した臼杵支配の礎を築いたという点で、歴史的な評価が与えられるべき人物である。彼の生涯は、激動の時代を生き抜いた一武将の軌跡として、後世に多くの示唆を与えている。
引用文献
- 稲葉典通(いなば のりみち)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%B2%E8%91%89%E5%85%B8%E9%80%9A-1055551
- 稲葉典通 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E8%91%89%E5%85%B8%E9%80%9A
- 稲葉良通 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E8%91%89%E8%89%AF%E9%80%9A
- 稲葉貞通とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A8%B2%E8%91%89%E8%B2%9E%E9%80%9A
- 稲葉貞通 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E8%91%89%E8%B2%9E%E9%80%9A
- 玉子の子たち、長姫・興(おき)秋(あき)・多羅姫|光秀を継ぎ、忠興を縛るガラシャ(7) http://www.yomucafe.gentosha-book.com/tadaoki-tamako7/
- 稲葉氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E8%91%89%E6%B0%8F
- 稲葉一鉄 - よしもと新聞舗:岐阜県瑞穂市情報お届けサイト http://www.yoshimoto-shinbun.com/history/%E7%A8%B2%E8%91%89%E4%B8%80%E9%89%84/
- 【宇治川の黒鉄】 稲葉一鉄 【信長の野望 出陣】 https://www.kakedashi.site/meikan-oda-inabaixtutetu-2/
- 『頑固一徹』稲葉一鉄、信長相手でも頑固と漢気を貫いた勇将の巻 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=nwGS_HdCyoo
- 稲葉貞通(いなば・さだみち)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%B2%E8%91%89%E8%B2%9E%E9%80%9A-1055530
- 歴史の目的をめぐって 大友義統 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-05-ootomo-yoshimune.html
- 1600年 関ヶ原の戦いまでの流れ (後半) | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1600-2/
- Untitled - 川辺町 https://www.kawabe-gifu.jp/wp-content/uploads/2015/10/008_%E5%B7%9D%E8%BE%BA%E7%94%BA%E5%8F%B2-%E9%80%9A%E5%8F%B2%E7%B7%A8_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%B7%A8-%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E8%83%8C%E6%99%AF-%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0-%E8%BF%91%E4%B8%96.pdf
- 十七条城、春日局と稲葉正成 - よしもと新聞舗:岐阜県瑞穂市情報お届けサイト http://www.yoshimoto-shinbun.com/history/%E5%8D%81%E4%B8%83%E6%9D%A1%E5%9F%8E%E3%80%81%E6%98%A5%E6%97%A5%E5%B1%80%E3%81%A8%E7%A8%B2%E8%91%89%E6%AD%A3%E6%88%90/
- 稲葉正成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E8%91%89%E6%AD%A3%E6%88%90
- 稲葉一鉄(イナバイッテツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%B2%E8%91%89%E4%B8%80%E9%89%84-15441
- 稲葉家下屋敷パンフ - 臼杵市観光協会 https://www.usuki-kanko.com/cms/wp-content/uploads/2025/01/inabakeshimoyashiki.pdf
- 「臼杵城跡」国史跡に指定! https://www.city.usuki.oita.jp/article/2024092200023/file_contents/0421.pdf
- 臼杵城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BC%E6%9D%B5%E5%9F%8E
- 大分県指定史跡 - 臼杵市観光協会 https://www.usuki-kanko.com/cms/wp-content/uploads/2021/08/ba916c24e2b8759093c4af66b0c4a9dc.pdf
- 臼杵市に寺院が多い理由を知りたい。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000269802&page=ref_view
- 臼杵のたび https://kuratabi-usuki.net/usuki/
- 歴史の町、大分県臼杵 武家屋敷の様式を今に伝える下屋敷 - Japan Travel Planner - ANA https://www.ana.co.jp/ja/gb/japan-travel-planner/oita/0000050.html
- 大分における蜑 人 の系譜 https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/29004/files/SB0013_157-167.pdf
- 幕藩制下における天領と藩との関係史的考察 : 天領 日田の商業資本と九州諸藩 - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/7178719/19_p029.pdf
- 「日本における近代信用貨幣への移行:国立銀行を中心に」 (改訂版) - 早稲田大学 https://www.waseda.jp/fpse/winpec/assets/uploads/2020/02/NoJ1906.pdf
- 荘田平五郎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%98%E7%94%B0%E5%B9%B3%E4%BA%94%E9%83%8E
- 臼杵藩稲葉氏のことども | 四季が美しく情緒豊かな日本の歴史と旅を探訪する瓦版 https://ameblo.jp/pandausagi37/entry-12860612769.html
- サンマにフグにイワシにブリ、魚と武将のエトセトラ /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/18306/
- 稲葉紀通 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E8%91%89%E7%B4%80%E9%80%9A
- 稲葉信通 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E8%91%89%E4%BF%A1%E9%80%9A
- 第二章 「名古屋御城石垣絵図」を読む https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/center/uploads/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0_1.pdf
- 歴史の目的をめぐって 細川忠興 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-30-hosokawa-tadaoki.html
- 名古屋城の概要 http://www.nagoya.ombudsman.jp/castle/230722.pdf
- 第四章 細川忠興・忠利父子の名古屋城石垣普請 https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/center/uploads/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0_1.pdf
- いなば https://haiyaku.web.fc2.com/inaba.html
- 慶長五年の細川家 http://www.shinshindoh.com/00-x-ennrui.htm
- 豊後臼杵 旧三の丸跡に建てられた旧藩主稲葉家当主が出仕先の東京から里帰りで滞在した『旧稲葉家別邸(下屋敷)』散歩 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10941561
- 斎藤道三(斎藤道三と城一覧)/ホームメイト https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/13/