筒井順国
筒井順国は、筒井氏の枢要な武将。兄の死後、甥・順慶を支え、松永久秀の侵攻から慈明寺城を守る。息子・定次が宗家を継ぎ、晩年は大和に残り一族の結束に尽力した。
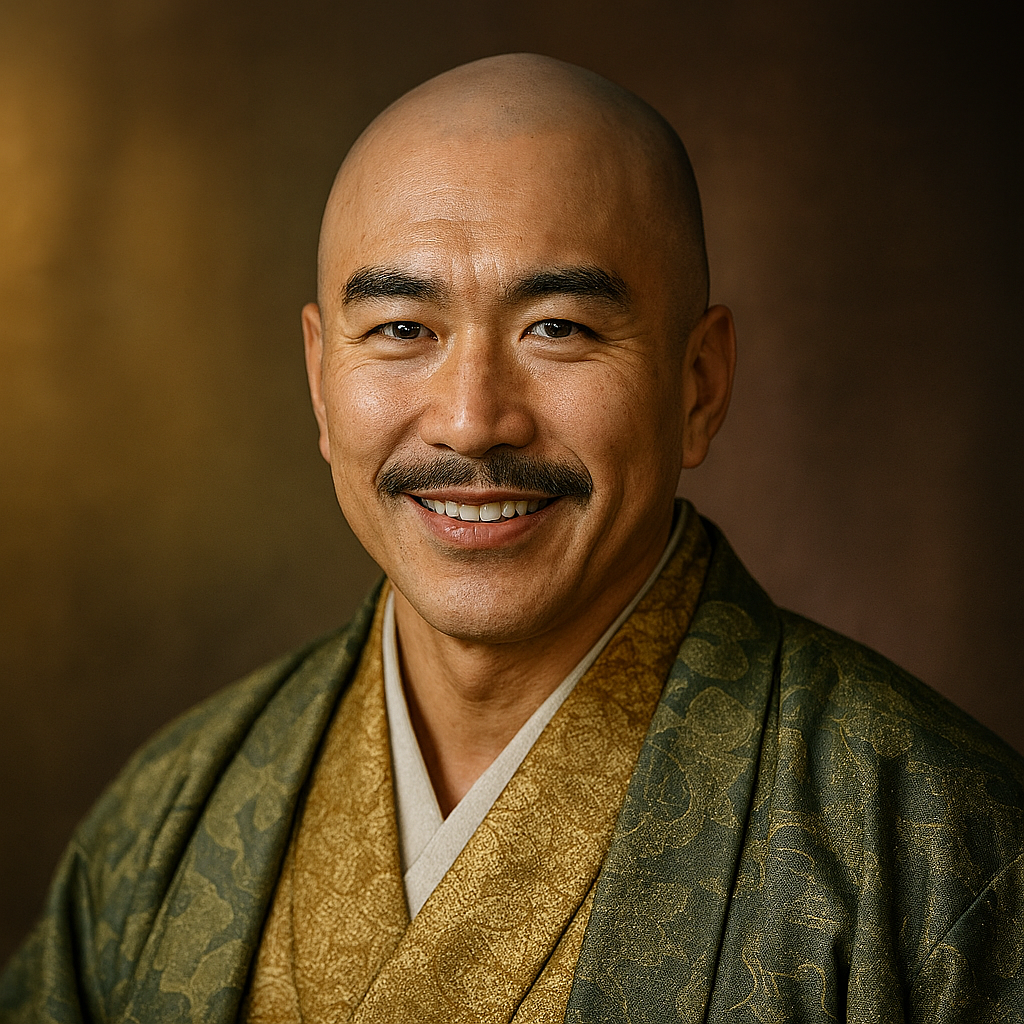
筒井順国 ― 大和筒井氏、枢要の武将の実像
序論:筒井順国、その謎多き生涯への序章
戦国時代の大和国(現在の奈良県)にその名を刻んだ筒井氏。その一族の歴史において、筒井順国(つつい じゅんこく)は、常に重要な局面に存在しながらも、その具体的な人物像や功績が詳細に語られることの少ない、謎多き武将である。兄である当主・筒井順昭の早逝、その子でまだ幼い甥・筒井順慶の家督相続、そして自らの実子・筒井定次による宗家継承という、一族の存亡を左右する幾多の転換点において、彼はどのような役割を果たしたのか。
順国に関する記録は断片的であり、その生涯の多くは歴史の影に隠されている。しかし、彼は単なる一族の一員に留まらず、筒井家の血脈と大和国人としての矜持を胸に、激動の時代を生き抜いた枢要の人物であった。本報告書は、奈良興福寺の僧侶たちが記した『多聞院日記』などの信頼性の高い一次史料と、後世に成立した『和州諸将軍伝』などに描かれる逸話を丹念に比較・検討することで、歴史の断片から筒井順国の実像を再構築し、その生涯が持つ歴史的意義を明らかにすることを目的とする。彼の生涯を追うことは、戦国大名・筒井氏の興亡を支えた内実と、大和という特異な地域社会の力学を解き明かす鍵となるであろう。
表1:筒井順国 関連年表
|
西暦 |
元号 |
年齢(順国) |
出来事 |
関連人物 |
|
1484年 |
文明16年 |
- |
筒井順興(順国の父)が生まれる 1 。 |
筒井順興 |
|
1523年 |
大永3年 |
- |
筒井順昭(順国の兄)が生まれる 2 。 |
筒井順昭 |
|
1535年 |
天文4年 |
不明 |
父・順興が死去。兄・順昭が家督を継ぐ 1 。 |
筒井順興、順昭 |
|
不明 |
- |
不明 |
順国、慈明寺家の家督を継承し、慈明寺城主となる 4 。 |
筒井順国 |
|
不明 |
- |
不明 |
兄・順昭の娘(順慶の姉)を妻に迎える 3 。 |
筒井順国 、順昭 |
|
1549年 |
天文18年 |
不明 |
筒井順慶(順昭の子、順国の甥)が生まれる 5 。 |
筒井順慶 |
|
1550年 |
天文19年 |
不明 |
兄・順昭が28歳で病死。順慶(2歳)が家督を継ぐ 2 。一族で順慶を後見。「元の木阿弥」の逸話はこの時期とされる 8 。 |
順昭、順慶、 筒井順国 、順政 |
|
1559年 |
永禄2年 |
不明 |
松永久秀が三好長慶の家臣として大和に侵攻を開始 7 。 |
松永久秀 |
|
1562年 |
永禄5年 |
不明 |
筒井定次(順国の子)が生まれる 10 。 |
筒井定次 |
|
1564年 |
永禄7年 |
不明 |
兄・順政が堺で病死。順慶の後見体制に大きな打撃 11 。 |
筒井順政 |
|
1565年 |
永禄8年 |
不明 |
松永久秀の攻撃により、順慶が居城・筒井城を追われる 11 。 |
順慶、松永久秀 |
|
1572年 |
元亀3年 |
不明 |
子・定次が順慶の養子となる(『断家譜』などによる説) 4 。 |
筒井定次、順慶 |
|
1577年 |
天正5年 |
不明 |
信貴山城の戦い。順慶、織田信長方として松永久秀を滅ぼす 14 。 |
順慶、松永久秀、織田信長 |
|
1584年 |
天正12年 |
不明 |
順慶が36歳で病死。養子の定次が家督を継ぐ 5 。 |
順慶、筒井定次 |
|
1585年 |
天正13年 |
不明 |
豊臣秀吉の命により、定次が伊賀へ転封。順国は大和に残り、新領主・羽柴秀長に仕える 4 。 |
筒井定次、 筒井順国 、豊臣秀吉、羽柴秀長 |
|
不明 |
- |
不明 |
消息不明となる。 |
筒井順国 |
第一章:大和国人・筒井一族の血脈
筒井順国の生涯と役割を理解するためには、まず彼が属した「筒井一族」と、その活動舞台であった「大和国」の特異な歴史的背景を把握することが不可欠である。彼の行動原理は、この二つの要素によって深く規定されていた。
第一節:守護不在の国・大和と興福寺の権威
戦国時代の多くの国が守護大名によって統治されていたのとは対照的に、大和国には特定の守護大名が存在しなかった 7 。この権力の空白地帯において、絶大な権威を誇っていたのが、奈良に本拠を置く興福寺であった 17 。興福寺は広大な荘園と、僧兵と呼ばれる武装集団を擁し、大和国の政治・経済に深く関与していた。
筒井氏は、この興福寺の組織に組み込まれた有力な国人領主であった。彼らの出自は、興福寺一乗院に属する「衆徒(しゅと)」、すなわち武装した寺院関係者であり、寺務の執行を担う官符衆徒の筆頭として武士化した家柄である 7 。この「武士であり僧でもある」という二重のアイデンティティは、筒井氏の行動様式を理解する上で極めて重要な要素となる。彼らは武力を行使する一方で、興福寺の権威を背景とした正当性を常に意識していた。
しかし、大和国内は一枚岩ではなかった。筒井氏のほか、越智氏、箸尾氏、十市氏といった有力な国人たちが「大和四家」と呼ばれ、興福寺の内部対立とも連動しながら、絶えず覇権を争っていた 7 。この恒常的な抗争状態が、一族の結束を何よりも重視する気風を育み、筒井氏独自の生存戦略を形成していくことになる。
第二節:惣領家と庶子家 ― 筒井一族の構造
筒井氏は、一族の長である宗家(惣領)を中心に、その兄弟や子(庶子)が分家を立てて勢力を拡大していく「惣領制」的な構造を持つ武士団であった 21 。筒井順国が「慈明寺家」を、その弟である福住順弘が「福住家」を継いだのは、この典型的な例である 1 。彼らは単なる独立した領主ではなく、筒井宗家を核とする軍事連合の重要な構成員であった。
この一族の中核を成したのが、順国の父と兄弟たちである。
- 父・筒井順興(1484-1535): 対立する越智氏らを抑え、筒井氏を大和最大の武士団へと押し上げた英主 1 。
- 長兄・筒井順昭(1523-1550): 父の跡を継ぎ、大和をほぼ統一して筒井氏の全盛期を築いたが、若くして病死した悲運の当主 2 。
- 次兄・筒井順政(?-1564): 順昭の死後、幼い甥・順慶の主要な後見人として、一族の危機を支えた武将 7 。
- 弟・福住順弘: 順国と同様に分家・福住氏を継ぎ、一族の有力な支柱として宗家を支えた 24 。
彼らの関係性を理解する上で特筆すべきは、筒井氏が駆使した戦略的な婚姻政策である。筒井順国と弟の福住順弘は、二人とも兄である当主・順昭の娘(つまり、彼らにとっては姪にあたる)を正室として迎えている 3 。これは単なる近親婚ではなく、一族の分裂を防ぐための極めて高度な政治的判断であった。戦国時代の武家社会において、惣領家と有力な分家の対立は、しばしば家門全体の分裂や弱体化を招く最大の要因であった 22 。筒井氏は、宗家当主の娘を、その弟たちが率いる有力分家に嫁がせることで、血縁関係を二重に結びつけたのである。これにより、順国や順弘は宗家当主に対して「弟」であると同時に「婿」という立場になり、その忠誠心はより強固なものとなった。この緊密な血族ネットワークこそが、後の順昭の死という一族最大の危機において、彼らが分裂することなく一致団結して難局に当たるための強固な基盤となったのである。順国の行動は、常にこの一族存続という大戦略の文脈の中で理解されなければならない。
表2:筒井氏主要人物関係図
Mermaidによる関係図
注:上図は主要な人物の関係を簡略化して示したものである。順昭には他にも娘がおり、他の大和国人との婚姻政策にも用いられている
3 。
第二章:慈明寺家の継承と順国の立場
筒井順国が歴史の表舞台にその名を現す第一歩は、大和国人・慈明寺氏の家督継承であった。この継承は、彼の生涯における基本的な立場と役割を決定づける重要な出来事であった。
慈明寺氏は大和の国人の一つであり、その本拠である慈明寺城は、現在の奈良県橿原市慈明寺町一帯に位置していたと推定される 4 。順国は筒井順興の三男として生まれたが、慈明寺氏の養子となり、その家督と城を継いだ 4 。これは、単に次男や三男の身の振り方を決めるという個人的な問題ではなく、筒井宗家がその勢力圏を安定的に支配するための戦略的な人事であったと考えられる。
筒井氏の本拠地である筒井城(現在の大和郡山市)は、大和国の北部に位置する。一方、慈明寺城のある橿原市周辺は、その南方に広がり、長年のライバルであった越智氏の勢力圏にも近接する、地政学的に極めて重要な地域であった。この戦略的要衝に、血縁の薄い国人を置くのではなく、宗家当主の実弟である順国を城主として直接送り込むことで、筒井家はこの地域への影響力を盤石なものにしようとしたのである。
したがって、慈明寺城主としての順国は、単に一城の主であるに留まらなかった。彼は、筒井宗家の意向を現地で実行し、領域支配を安定させるための重要な「アンカー(錨)」としての役割を担っていた。彼の支配する所領からの収入 31 と、彼が動員できる兵力は、筒井一族という巨大な軍事連合全体の力の一部を形成していた。順国は、いわば筒井宗家の「出先機関」の長として、最前線における領国経営と軍事プレゼンスの維持という重責を負っていたのである。彼のこの立場が、後の兄・順昭の死に際して、一族の結束を維持する上で決定的な意味を持つことになった。
第三章:当主の死と「元の木阿弥」計画
天文19年(1550年)、筒井家の全盛期を築き上げた当主・筒井順昭が、天然痘(もがさ)が原因とみられる病により、わずか28歳の若さでこの世を去った 2 。跡を継いだ嫡男の藤勝、後の筒井順慶は、まだ2歳という幼さであった 5 。当主の若すぎる死と、後継者の幼さ。これは、周囲を敵に囲まれた戦国時代の武家にとって、家門滅亡に直結しかねない最大級の危機であった。この絶体絶命の窮地を乗り切るために実行されたとされるのが、世に名高い「影武者計画」である。
この逸話は、主に江戸時代中期に成立した軍記物『和州諸将軍伝』によって広く知られるようになった 32 。その物語によれば、自らの死期を悟った順昭は、一族の重臣たちを集め、ある奇策を授けた。それは、普段から城に出入りし、声が自分に酷似していたという盲目の法師・黙阿弥(木阿弥)を自らの影武者に仕立て上げ、死を秘匿するというものであった 8 。計画は順国ら一族によって遂行され、病気療養を名目に姿を隠した「順昭(実際は黙阿弥)」の存在によって、筒井家の健在が内外に示された。この時間稼ぎのおかげで、敵対勢力は付け入る隙を見出せず、その間に幼い順慶の家督相続は盤石なものとなった。
そして数年後(一説には一周忌の後)、順慶が成長し、もはや秘匿の必要がなくなったと判断されると、順昭の死が公式に発表された 9 。大役を果たした黙阿弥は、多額の恩賞を与えられ、元のしがない法師の身分に戻ったという。この故事から、「一度は良い身分や状態になったものが、結局は元のつまらない状態に戻ってしまう」ことを意味する故事成語、「元の木阿弥」が生まれたとされている 8 。
この劇的な逸話は、しかしながら『多聞院日記』のような同時代の一次史料には一切の記述がなく、その史実性については疑問視されている 32 。当主の死を一定期間秘匿すること自体は、戦国時代においてしばしば行われた戦略であり、筒井家においても同様の措置が取られた可能性は否定できない。しかし、黙阿弥という具体的な人物を用いた物語は、後世の創作である可能性が高い。
だが、この逸話の歴史的価値は、史実性の有無だけに留まらない。むしろ、この物語がなぜ生まれ、語り継がれたのかを考えることこそが重要である。この「元の木阿弥」の逸話は、幼君・順慶の家督相続がいかに正統なものであったか、そしてそれを支えた筒井一族がいかに「結束力と知恵」に優れた集団であったかを、後世に強くアピールするための、一種のプロパガンダとしての機能を果たしていた。物語は、「亡き順昭の深慮遠謀」と、順国ら叔父たちの「揺るぎない忠誠」によって、一族が未曾有の危機を知略で乗り越えたという英雄譚を巧みに構築している。影武者というフィクションを通じて、順慶の治世が父・順昭から断絶することなく直接引き継がれたものであることを強調し、その正統性を盤石なものとしたのである。この物語の中で、筒井順国は、兄・順政や弟・順弘らと共に、私心を捨てて幼い当主を支える「忠臣」として描かれる。彼が一族ぐるみで行われたとされるこの計画の主要な共謀者の一人であったことは想像に難くなく、この逸話は、彼の果たした役割の重要性を象徴的に示していると言えよう。
第四章:松永久秀の侵攻と筒井家の苦難
筒井順昭の死後、一族が「元の木阿弥」計画で辛うじて維持した平穏は、長くは続かなかった。当主の死と後継者の幼さという筒井家の弱体化を好機と見た、畿内に勢力を誇る三好長慶の重臣・松永久秀が、永禄2年(1559年)より大和への本格的な侵攻を開始する 7 。これにより、筒井家は十数年にわたる苦難の時代へと突入することになる。
久秀は、圧倒的な軍事力を背景に、大和国内の国人たちを次々と屈服させていった。筒井家は必死の抵抗を試みるも、永禄8年(1565年)11月、ついに本拠地である筒井城を久秀に奪われ、当主・順慶は流浪の身となることを余儀なくされた 11 。この絶望的な状況下で、順慶は叔父の福住順弘が守る福住城などを頼り、失地回復の機会を窺った 26 。
この一連の戦いにおいて、慈明寺城主である筒井順国の具体的な動向を直接的に記した史料は乏しい。しかし、彼がこの苦難の時代に傍観していたとは到底考えられない。本拠地を失った筒井家の抵抗は、もはや大規模な会戦によるものではなく、一族が支配下に置く各地の城砦を拠点とした、ネットワーク型のレジスタンス(抵抗運動)へとその様相を変えた。その中で、順国が守る慈明寺城は、大和中南部に位置する極めて重要な戦略拠点であった。
松永久秀の視点に立てば、大和を完全に制圧するためには、中心拠点である筒井城を落とすだけでは不十分であり、福住城や慈明寺城といった、筒井家の抵抗の芽となりうる支城ネットワークを一つずつ無力化する必要があった。したがって、順国の慈明寺城もまた、久秀の攻撃目標になったか、あるいは順慶方の抵抗拠点として、兵站の維持、情報の収集、兵員の隠匿といった重要な役割を果たした可能性が極めて高い。
つまり、筒井順国は、単に流浪する甥を陰ながら支援しただけではない。彼は、自らの城と領地、そしてそこに住まう人々を賭して、松永久秀という強大な敵に対する長期的な抵抗戦争の一翼を担う、最前線の指揮官であったと評価できる。筒井城を失った後も、筒井家が完全に滅びることなく抵抗を続け、やがて織田信長の力を借りて復活を遂げることができたのは、順国のような一族の支城主たちが、それぞれの持ち場で粘り強く戦い続けた「筒井家レジスタンス・ネットワーク」の存在があったからに他ならない。順国は、その南の拠点を死守する、欠くことのできない存在だったのである。
第五章:甥・順慶の後見と実子・定次の未来
松永久秀との熾烈な抗争と並行して、筒井家内部では幼い当主・順慶を支えるための後見体制が敷かれていた。この体制における順国の役割と、彼の息子である定次がやがて筒井家の後継者となるまでの過程は、順国の生涯におけるクライマックスであり、彼の一族への貢献が最も明確に現れる局面である。
順慶が家督を継いだ当初、その後見体制の中心を担ったのは、次兄の筒井順政であった 7 。また、一族の長老格であった福住宗職が初期の政務を取り仕切ったとも伝えられている 7 。順国は、これらの中心人物を支える一族の重鎮として、軍事指揮や領地経営といった実務面で後見体制を補佐し、その安定に貢献したと考えられる。特に、中心的な後見人であった順政が永禄7年(1564年)に堺で病死 11 してからは、残された叔父である順国や福住順弘の役割は、さらに重要性を増したはずである。
やがて順慶は成長し、織田信長の後ろ盾を得て宿敵・松永久秀を滅ぼし、大和一国の主となる。しかし、彼には実子がおらず、一族の将来を託す後継者問題が深刻な課題として浮上した 16 。当初、順慶は一族の番条五郎を養子に迎えようとし、時の実力者である羽柴秀吉の承諾まで得ていた。しかし、当の五郎がこれを固辞したため、この話は流れてしまう 40 。
そこで白羽の矢が立ったのが、筒井順国の子である定次(幼名・藤松、あるいは小泉四郎とも呼ばれた)であった 4 。定次が後継者として選ばれた背景には、その血統的な正統性の強さがあった。定次の父は順慶の叔父(順国)であり、母は順慶の姉(順昭の娘)である。このため、定次は順慶から見て「従弟」であると同時に「甥」にもあたるという、これ以上ないほど近い血縁関係にあった 43 。この血の近さが、彼が後継者として家臣団からも受け入れられる決定的な要因となった。
この定次の養子入りは、単なる偶然や血縁の近さだけがもたらした結果ではない。それは、兄・順昭の死以来、三十年近くにわたって一貫して私心なく宗家を支え続けた筒井順国の、長年にわたる忠誠の論理的帰結であった。順国が自らの息子を当主の座に就けるために策動したという記録はどこにもない。むしろ、彼の行動は常に「家」の存続を最優先するものであった。かつて兄の娘を娶り、宗家との血縁を二重に強化した戦略的婚姻。兄の死後、幼い甥を支え続けた後見の一翼としての役割。これらの行動すべてが、彼の忠誠心と、一族全体の利益を優先する姿勢を物語っている。
結果として、筒井家の血統を最も色濃く受け継ぐ「申し分のない後継者」を、他ならぬ順国自身が用意していたのである。彼の生涯は、個人の野心よりも一族の安泰を重んじる戦国武将の生き様を、静かに、しかし雄弁に体現している。自らの息子が宗家を継ぐという未来は、彼が野心を抱いた結果ではなく、一族への奉仕を貫いた末に手にした、最大の栄誉であったと言えよう。
第六章:順慶の死後、そして歴史の彼方へ
天正12年(1584年)、長年の宿敵であった松永久秀との抗争に終止符を打ち、織田信長のもとで大和一国の支配を安堵された筒井順慶が、志半ばで36歳の若さで病死した 5 。その跡を、養子となっていた筒井定次が継承する。父・順国が見届けたこの家督相続により、筒井家の未来は安泰かに見えた。しかし、天下の情勢は、筒井家に再び大きな転換を強いることになる。
順慶の死の翌年、天正13年(1585年)、天下人となった豊臣秀吉は、畿内の支配体制を盤石にするため、大規模な国替えを断行した。その一環として、筒井定次は先祖代々の地である大和郡山から、伊賀上野へ20万石で転封を命じられた 15 。これは、秀吉が最も信頼する弟・羽柴秀長に大和国を与えるための戦略的な配置転換であった 45 。
この一族の歴史的転換点において、筒井順国は意外な決断を下す。彼は、当主となった息子・定次と共に伊賀へは移らず、故郷である大和に残留したのである。そして、大和国の新たな領主となった羽柴秀長に仕えたと記録されている 4 。この時、彼は「慈明寺左門順之(としゆき)」と名乗っていた可能性も指摘されているが、詳細は定かではない 4 。
秀長に仕えた後の順国の動向は、現存する史料から完全にその姿を消す。彼の生没年が共に「不明」とされている 4 のも、この時期以降の確かな記録が存在しないためである。彼は、豊臣政権という新たな支配体制の中で、大和の一国人として静かにその生涯を終えたものと推測される。
息子が新たな領地へ移る中、順国が大和に残ったという最後の決断は、彼のアイデンティティの根幹がどこにあったかを雄弁に物語っている。それは、彼の自己認識が、移動する大名家である「筒井宗家の家臣」である以上に、何世代にもわたってその地に根を張ってきた「大和国の国人領主」であったことを強く示唆している。彼の人生は筒井宗家と共にあったが、その終着点は、生まれ育ち、生涯をかけて守り抜こうとした土地・大和であった。
秀吉による大名の大規模な国替えは、武士たちを土地との伝統的な結びつきから切り離し、領主の個人的な臣下へと変質させる、中央集権化政策の象徴であった。順国は、この新しい時代の大きな潮流の中で、自らの家(慈明寺家)と、その基盤である土地を守るために、新領主・秀長に仕えるという最も現実的な道を選んだ。これは、変化する時代に適応しようとする一人の老将のプラグマティズム(実用主義)と、故郷への深い愛着の表れと見ることができる。彼の物語の静かな終わりは、戦国時代が終焉を迎え、土地に根差した国人たちが歴史の表舞台から去っていく時代の転換点を、象徴的に示しているのである。
結論:歴史の狭間に生きた武将、筒井順国の実像
筒井順国は、華々しい武功や劇的な逸話によって歴史にその名を轟かせた武将ではない。彼の名は、甥である筒井順慶や、実子である筒井定次の経歴の中に、付随的に記されることがほとんどである。しかし、その断片的な記録を丹念に繋ぎ合わせ、彼が生きた時代の文脈の中に位置づけることで、戦国乱世を生き抜いた一族の、縁の下の力持ちとしての極めて重要な姿が浮かび上がってくる。
彼の生涯は、筒井家への「奉仕」と「結束」の物語であった。兄・順昭の早逝と甥・順慶の幼少期という一族最大の危機に際しては、兄・順政らと共に一族の分裂を防ぐ「防波堤」となり、影武者計画のような奇策を支えた。松永久秀の侵攻による苦難の時代には、大和南部の拠点・慈明寺城を死守し、筒井家全体の抵抗ネットワークの一翼を担う「拠点指揮官」として機能した。そして、順慶の後継者問題が浮上した際には、自らの血脈を宗家に提供することで家の存続を確実にする「繋ぎ手」としての役割を果たした。この後継者選定は、彼が長年にわたり宗家との血縁を強化し、忠誠を尽くしてきた行動の集大成であった。
これらの行動から再構築される順国の人物像は、個人の野心よりも一族全体の安泰を最優先し、婚姻政策や養子縁組といった内政的な手段を通じて、家の結束を内側から固めることに長けた、極めて理性的で忠実な人物である。また、その最期に見られるように、彼のアイデンティティの根幹には、生まれ育った土地・大和への強い帰属意識が存在した。彼はまさしく、戦国時代を生きた典型的な国人領主の姿を体現していた。
筒井順国の生涯は、筒井宗家という「主役」の影に隠れがちである。しかし、彼のような堅実で信頼に足る補佐役の存在なくして、筒井家が松永久秀との十数年にわたる激しい抗争を乗り越え、織豊政権下で大名として存続することは叶わなかったであろう。歴史は、表舞台に立つ英雄たちの活躍によって彩られるが、その英雄を支え、血脈と家門を未来へ繋いだ人物の存在を忘れてはならない。筒井順国は、まさしくそのような「枢要の人物」であったと結論付けられる。
引用文献
- 筒井順興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E8%88%88
- 歴史の目的をめぐって 筒井順昭 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-18-tustsui-zyunsho.html
- 筒井順昭とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%98%AD
- 慈明寺順国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%88%E6%98%8E%E5%AF%BA%E9%A0%86%E5%9B%BD
- 筒井順慶(ツツイジュンケイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%85%B6-19174
- 筒井順慶 - 大和郡山市 https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/section/rekisi/src/history_data/h_028.html
- 筒井順慶 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%85%B6
- もとのもくあみ | 言葉 - 漢字ペディア https://www.kanjipedia.jp/kotoba/0001985600
- 【第5話】《元の黙阿弥》の語源となった史話 筒井順昭と伝香寺 - 泉屋 https://www.izumiya-gr.com/narastory-05
- 筒井順慶の家臣 - 歴史の目的をめぐって https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-18-tustsui-zyunkei-kashin.html
- 筒井順慶なる人物|【note版】戦国未来の戦国紀行 https://note.com/senmi/n/n5a9ee2b948da
- 筒井順慶のエピソードから考える判断のタイミング|Biz Clip(ビズクリップ) - NTT西日本法人サイト https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-067.html
- 筒井順慶とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%85%B6
- 筒井順慶(つつい じゅんけい) 拙者の履歴書 Vol.386~洞ヶ峠の奥の真実 - note https://note.com/digitaljokers/n/n6809a4e38e23
- 島左近(嶋左近)の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/37254/
- 筒井順慶の死 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/sakon/sakon0105d.html
- 大和国 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1997
- 筒井氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E6%B0%8F
- 筒井順昭 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%98%AD
- 越智氏 (大和国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E6%99%BA%E6%B0%8F_(%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%9B%BD)
- 武士団 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E5%9B%A3
- 日本史論述ポイント集・中世⑤|相澤理 - note https://note.com/o_aizawa/n/n16dc1ac88175
- 【高校日本史B】「惣領制」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12664/
- 福住順弘 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E4%BD%8F%E9%A0%86%E5%BC%98
- 筒井氏 - 姓氏家系メモ https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E6%B0%8F
- 筒井順慶は何をした人?「洞ヶ峠を決め込んで光秀と秀吉の天王山を日和見した」ハナシ https://busho.fun/person/junkei-tsutsui
- 筒井順政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%94%BF
- 慈明寺 - 曹洞禅ナビー寺院検索― 曹洞宗公式 寺院ポータルサイト https://sotozen-navi.com/detail/index_290079.html
- 慈明寺 - 橿原市慈明寺町/寺院 - Yahoo!マップ https://map.yahoo.co.jp/v3/place/zfoEd3k6pXw
- 奈良県橿原市慈明寺町 - 住所を探す - NAVITIME https://www.navitime.co.jp/address/29205040000/%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C%E6%A9%BF%E5%8E%9F%E5%B8%82%E6%85%88%E6%98%8E%E5%AF%BA%E7%94%BA/
- 鎌倉時代の勉強をしよう(高校生以上の質問)2 - 玉川学園 http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/kamakura/otayori2.html
- 筒 井 氏 合 戦 記 - 奈良工業高等専門学校 https://www.nara-k.ac.jp/contribution/pdf/tsutsui.pdf
- 『和州諸将軍伝』(わしゅうしょしょうぐんでん) - 筒井氏同族研究会 https://tsutsuidouzoku.amebaownd.com/posts/7693825/
- 圓證寺普賢菩薩騎象像:本尊釈迦如来坐像の左脇侍。当寺はこの地一帯を支配した戦国大名・筒井順慶の父である筒井順昭が菩提寺とした。順昭が亡くなった時に立てた影武者が木阿弥(黙阿弥)という盲目の僧で - Pinterest https://www.pinterest.com/pin/507429083004800333/
- 元の木阿弥の由来とは?語源や意味・家康など影武者を使った戦国武将となれる条件なども紹介 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/86927/
- 【悲運の戦国大名 筒井氏の深い謎①】元の木阿弥ってなに? - note https://note.com/mononofu_tsubaki/n/n492c4e86fa33
- 筒井城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 大和国を巡って18年攻防。松永久秀と筒井順慶、ライバル関係の真相【麒麟がくる 満喫リポート】 https://serai.jp/hobby/1011657
- 筒井城の戦い古戦場:奈良県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/tsutsuijo/
- 筒井定次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%AE%9A%E6%AC%A1
- 筒井定次とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%AE%9A%E6%AC%A1
- 島左近関連人物列伝1 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/sakon/retsuden01.html
- 郡山城 - 古城址探訪 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.yamatokohriyama.htm
- 筒井定次(つつい・さだつぐ) 1562~1615 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/TsutsuiSadatsugu.html
- 秀吉の弟・羽柴(豊臣)秀長が辿った生涯|天下統一に大きく貢献した秀吉の良き理解者【日本史人物伝】 | サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト - Part 2 https://serai.jp/hobby/1144318/2
- 豊臣秀長は、兄・秀吉のブレーキ役だった? 天下統一を実現させた“真の功労者” https://rekishikaido.php.co.jp/detail/11037