臼杵シモン
臼杵シモンは戦国豊後のキリシタン。田原親虎の洗礼名、野津のリアンの布教活動、大友宗麟の武器貿易の記憶が融合した複合的歴史像である。
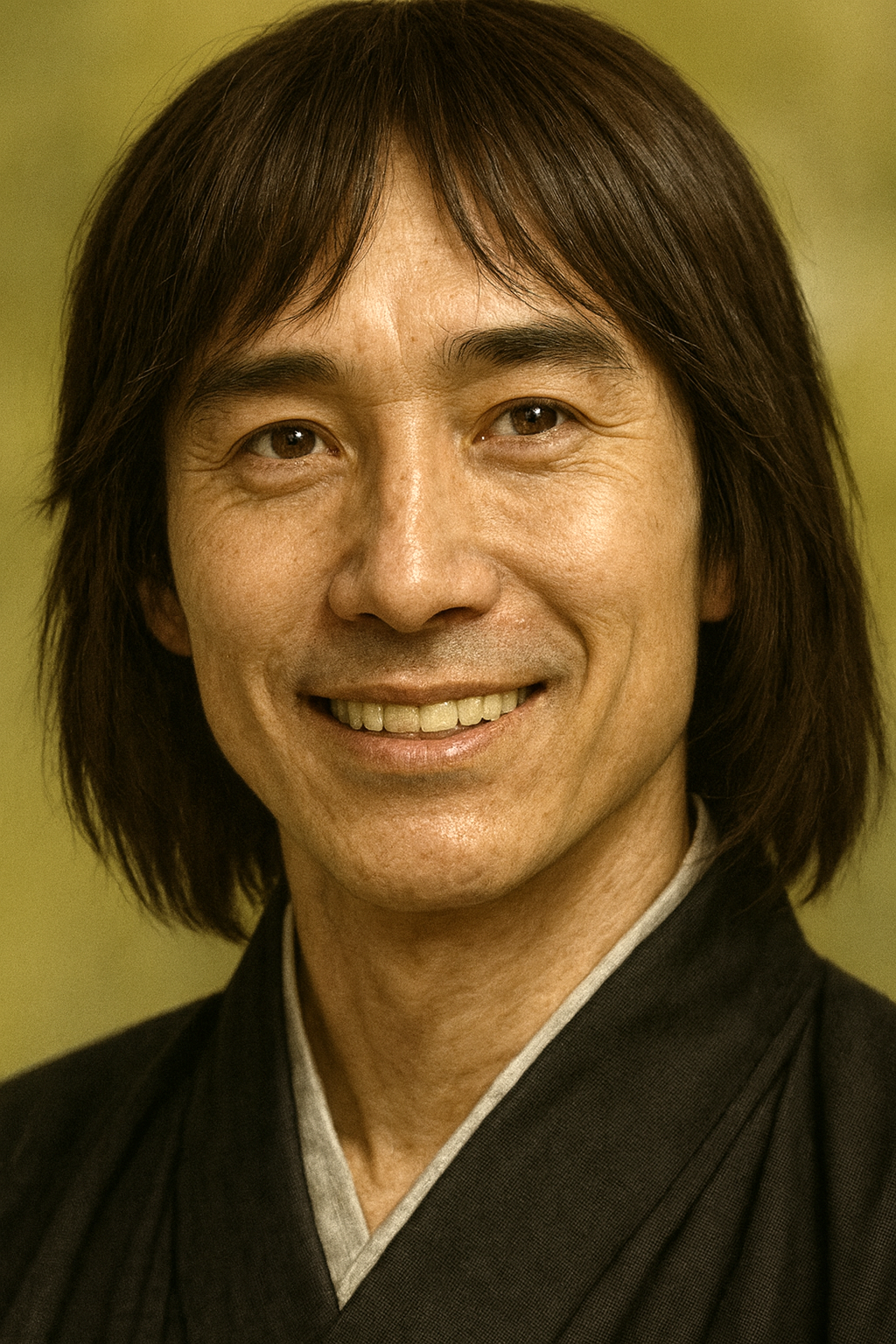
戦国期豊後のキリシタン「臼杵シモン」に関する総合的調査報告
序章:臼杵シモンの謎 ― 史料の海へ
日本の戦国時代、豊後の地で活動したとされる「臼杵シモン」― 16世紀中葉、キリスト教の宣教師として近隣の領民を教え導く一方で、大名の要請に応じて鉄砲の売買にも関与したという、謎に満ちた人物像が伝えられています。この魅力的ながらも輪郭の不分明な人物をめぐり、本報告書は、現存するあらゆる史料を駆使してその実体を徹底的に追跡する歴史的探求の記録です。
調査の初期段階において、まず我々が直面したのは、一つの重大な事実でした。ルイス・フロイスの記念碑的著作『日本史』 1 や、イエズス会宣教師たちがローマやゴアへ送った詳細な書簡・報告を集成した『十六・七世紀イエズス会日本報告集』 3 といった、当時の豊後国におけるキリスト教の動向を最も詳細に伝えるはずの一級史料群を精査しても、「臼杵シモン」という特定の名称と、伝えられる経歴を併せ持つ人物は、明確には浮上してこないのです。
この「史料上の不在」こそが、我々の調査の出発点であり、同時に核心的な問いを投げかけます。当時のイエズス会宣教師たちは、布教の進展、有力な改宗者の洗礼、地域の政治的事件について、驚くほど詳細かつ体系的な記録を残しています 1 。もし「臼杵シモン」が、伝えられるような影響力を持つ人物であったならば、その名がこれらの主要な報告書から完全に欠落していることは極めて不自然と言わざるを得ません。
しかし、この「不在」は、彼が歴史上存在しなかったことを短絡的に意味するものではありません。むしろ、この事実は、「臼杵シモン」という呼称と人物像が、後世の伝承の中で形成されたか、あるいは実在した複数の人物の逸話や属性が、長い時の流れの中で融合し、結晶化した「複合的歴史像」である可能性を強く示唆しています。
本報告書は、この仮説を立証するため、「臼杵シモン」という人物像を構成する「シモンという洗礼名」「臼杵での宗教活動」「武器貿易への関与」という三つの要素に分解し、それぞれの源流がどの歴史的事実、どの実在の人物に遡るのかを、一つひとつ丹念に解き明かしていくことを目的とします。
第一章:最も有力な候補者① ― 洗礼名「シモン」を持つ武将、田原親虎の悲劇
「臼杵シモン」の謎を解く最初の鍵は、その「シモン」という洗礼名にあります。数多のキリシタン武将の中から、この名を持ち、かつ豊後の歴史に深く関わる人物として、一人の若者の姿が浮かび上がります。その名は田原親虎(たわら ちかとら)です。
田原親虎(シモン)の特定と深刻な宗教的対立
イエズス会の史料は、大友氏の重臣であった田原親賢(たわら ちかかた)の養子・田原親虎が、天正5年(1577年)に受洗し、「シモン」という洗礼名を授かったことを明確に記録しています 4 。彼の活動時期と場所(豊後国)は、伝承と符合しており、彼が「シモン」という名の源流である可能性は極めて高いと言えます。
しかし、彼の生涯は、信仰の喜びとは裏腹に、深刻な家庭内の対立によって彩られていました。親虎はもともと京の公家である柳原家の出身で、大友宗麟の重臣・田原親賢の養子として迎えられた、将来を嘱望された若者でした 5 。ところが、彼の周囲はキリスト教に対して極めて敵対的な環境にあったのです。養父である田原親賢、そして宗麟の正室であり親賢の妹(あるいは姉)であった奈多夫人は、共に奈多八幡宮の大宮司家の出身であり、熱心な伝統宗教の信奉者でした。彼らは、宗麟のキリスト教保護政策に公然と反対し、反キリシタンの急先鋒として知られていました 4 。その敵意は凄まじく、宣教師たちは奈多夫人を、旧約聖書に登場し、預言者エリヤと対立した異教の王妃になぞらえ、「イザベル」という蔑称で呼び、その言動を警戒と共に記録しています 7 。
入信、廃嫡、そして悲劇的な末路
親虎の運命が大きく動いたのは、皮肉にも養父・親賢がきっかけでした。親賢が興味本位で、美少年として評判だった養子を臼杵の教会へ連れて行ったところ、親虎はそこで説かれる教えに深く魅了され、やがて熱心な信徒となったのです 6 。
この事態に養父・親賢と伯母・奈多夫人は激怒します。彼らは親虎に対し、「棄教しなければ、教会に火を放ち、宣教師たちを殺害する」とまで脅迫しました 7 。主君である大友宗麟は、この深刻な家族内の対立を憂慮し、親虎を庇護しようと試み、形だけでも棄教するよう諭すなど、和解の道を探りましたが、交渉は難航します 4 。最終的に、親賢は親虎を勘当し、廃嫡(家督相続権の剥奪)するという強硬手段に訴えました 4 。
信仰のために家族と将来を失った親虎は、府内のイエズス会住院に身を隠しました。その後の彼の運命については、史料によって説が分かれています。ある記録では、後に赦免され、天正6年(1578年)の日向攻め(耳川の戦い)に養父と共に出陣したものの、敵の重囲に陥り、若くして戦死したと伝えられています 10 。一方で、その死地を脱して豊後を逃れ、堺や伊予国へと渡り、そこで静かに生涯を終えたという生存説も存在します 10 。フロイスの『日本史』には、大友軍が大敗を喫した耳川の戦いの詳細な記述が見られますが 4 、シモン親虎個人の最期に関する確定的な記述は発見されていません。
なぜ田原親虎が「臼杵シモン」の核となり得たのか
ここで重要なのは、田原親虎は宣教師でもなければ、武器商人でもなかったという事実です。にもかかわらず、彼が「臼杵シモン」という複合的歴史像の核となり得たのは、その生涯が持つ強烈な物語性に起因すると考えられます。
人間の記憶は、単なる事実の羅列よりも、感情を揺さぶるドラマチックな物語を強く保持する傾向があります。田原親虎の物語は、①名門の養子という貴い身分、②禁じられた信仰への純粋な目覚め、③権力者である家族との激しい対立、④主君による庇護、そして⑤悲劇的な末路、という、まさに「信仰の殉教者」とも言うべき物語の定型を完璧に満たしています。
大友家中枢で繰り広げられたこの生々しい宗教対立の象徴として、彼の悲劇は当時の人々の記憶に深く刻み込まれたことでしょう。その結果、「シモン」という洗礼名は、豊後におけるキリシタンの苦難と信仰を代表する名前として、後世にまで語り継がれていったと考えられます。やがて、臼杵の地で語られる他のキリシタンに関する様々な逸話が、最も記憶に残りやすいこの「シモン」という名の主人公の下に集約されていったのではないでしょうか。これこそが、「臼杵シモン」という一人の人物像が形成されていく、その第一歩であったと推察されるのです。
第二章:最も有力な候補者② ― 臼杵のキリシタン指導者、野津のリアン(理庵)
田原親虎が「シモン」という“名前”の源流であるとすれば、「臼杵シモン」の“活動内容”、すなわち「臼杵の地で領民に布教活動を行った」という側面のモデルとなった人物は誰なのでしょうか。その答えは、再びフロイスの『日本史』の中に示されています。
フロイスが記録した地域の中心人物「リアン」
フロイスは、天正6年(1578年)から豊後国大野郡野津院(現在の臼杵市野津町)においてキリスト教が急速に広まったこと、そしてその布教活動の中心に「リアン」という名の人物がいたことを記録しています 13 。
フロイスが伝えるリアンの活動は、一介の信徒のそれを遥かに超えるものでした。
- 共同体のパトロン: 彼は地域の有力者であり、自らの「自宅だけで120名以上の者をかかえ」、生活の面倒を見ていました 13 。これは、彼が単なる信仰者ではなく、信徒共同体の経済的・社会的な庇護者(パトロン)であったことを示しています。
- 宗教施設の建設: リアンは私財を投じて、自らの邸内に教会を建設しました。さらに、それだけでは飽き足らず、「教会の上方にある山の適当な場所に広場を造り、そこに1基の美しい十字架を建て」、その近くにキリシタンを埋葬するための「広く良く整った墓地を造った」とされています 13 。これは、地域の信仰生活のインフラを、彼一人の力で整備したに等しい、驚くべき献身です。
日本側史料と考古学的発見による裏付け
このフロイスの記述は、日本側の史料と近年の考古学的発見によって、その信憑性が劇的に高まっています。慶長2年(1597年)に作成された検地帳『豊後国大野郡野津院御検地帳』には、下藤村(現在の野津町下藤)において、村全体の石高の約5分の1にあたる36石余りを一人で所有する「理庵(りあん)」という名の富裕な人物が記録されているのです 13 。この「理庵」が、フロイスの言う「リアン」であることは、発音の類似性からもほぼ間違いありません。
さらに決定的なのは、この理庵の屋敷があったと推定される場所の上方の山から、まさにフロイスの記述と一致する大規模なキリシタン墓地が発見されたことです。この「下藤キリシタン墓地」は、墓が整然と並び、礼拝のための広場状の遺構も確認されるなど、極めて良好な状態で残る国内最大級のキリシタン墓地遺跡として、国史跡にも指定されています 13 。フロイスが記した「リアンの居住地の対岸に仏教勢力があった」という景観も、現地の地理的状況と合致しており 13 、これらの証拠は、リアン(理庵)という人物が、この地でキリシタン共同体を指導した実在の人物であったことを疑いなく証明しています。
リアンが体現する「土着のキリスト教指導者」像
リアンの存在が明らかにするのは、戦国時代のキリスト教布教の、より複雑でダイナミックな実態です。彼はヨーロッパからやって来た宣教師ではありません。彼は現地の日本人であり、村の運営を担う庄屋クラスの有力者でした。彼の改宗と指導者としての活動は、キリスト教の受容が、単に宣教師による一方的な布教の結果なのではなく、現地の社会構造に深く根差し、日本人指導者という媒介者を通じて、共同体全体へと有機的に広がっていったプロセスを如実に示しています。
彼こそが、「臼杵の地で領民に対し熱心に布教活動を行う」という「臼杵シモン」像の、具体的な活動モデルそのものなのです。地域住民の視点から見れば、日々の信仰生活の中心にいたのは、時折訪れる遠い国の宣教師ではなく、生活を共にし、共同体を導いてくれる身近な指導者、リアンでした。
したがって、後世に「臼杵のキリシタンの偉大な指導者」の物語が語り継がれる際、その具体的な活動内容はリアンの逸話に基づきながらも、その人物を象徴する名前として、よりドラマチックで悲劇的な響きを持つ田原親虎の洗礼名「シモン」が結びついた、と考えるのが最も自然な解釈です。ここで、リアンの「活動」と、田原親虎の「名前」が、記憶の中で一つに融合したのです。
第三章:時代背景 ― キリシタン大名・大友宗麟と豊後国の武器貿易
「臼杵シモン」の人物像を構成する第三の要素、それは「大名の要請を受けて、鉄砲の売買も行った」という武器商人としての一面です。この属性の起源を探るためには、個々の信徒から、当時の豊後国全体の政治・経済構造へと視点を移す必要があります。その中心にいるのが、キリシタン大名として名高い豊後の支配者、大友宗麟(ドン・フランシスコ)その人です。
大友宗麟の二面性 ― 信仰と実利
大友宗麟は、日本で最も早くからキリスト教を手厚く保護した大名の一人として知られています 16 。彼は府内(現在の大分市)に教会やコレジオ(神学校)、さらには日本初の西洋式病院の建設を許可するなど、南蛮文化を積極的に導入しました 17 。天正6年(1578年)には自らも洗礼を受け、ドン・フランシスコという洗礼名を授かっています 16 。
しかし、彼のキリスト教保護政策は、純粋な信仰心のみによるものではありませんでした。その背後には、ポルトガル船がもたらす莫大な富と、当時の最先端軍事技術であった鉄砲や大砲を獲得するという、極めて現実的かつ戦略的な政治・経済的動機が存在したのです 7 。戦国の群雄が割拠する九州において、軍事力の優位を保つことは大友家の存亡に関わる至上命題でした。
武器貿易の主体としての大友宗麟
宣教師たちの記録や関連史料が示しているのは、個々の宣教師や信徒が私的に武器を売買していたという姿ではなく、大友宗麟自身が南蛮貿易の絶対的な主導者として、組織的かつ大規模に武器を調達していたという厳然たる事実です。
その最も象徴的な例が、ポルトガルから導入した大型のフランキ砲です。宗麟はこの大砲を「国崩し」と名付け、自らの居城である臼杵城に配備しました。この「国崩し」は、後に宿敵である島津氏の大軍が臼杵城に押し寄せた際、その圧倒的な火力で敵の猛攻を食い止め、落城の危機を救う上で決定的な役割を果たしました 8 。
また、鉄砲そのものや、その火薬の原料として不可欠であった硝石の安定供給は、大友氏の軍事力を維持するための生命線でした。宗麟は、これらの戦略物資を独占的に入手するためにこそ、イエズス会との良好な関係を維持し、彼らを貿易の仲介役として重視したのです 20 。
「武器商人」の実像は宗麟の事績の反映
これらの事実を踏まえると、「大名の要請を受けて、鉄砲の売買も行った」という「臼杵シモン」の伝承は、歴史の事実をある意味で反転させたものであることがわかります。実態は、「宣教師や一介の信徒が、大名の要請で武器を売った」のではなく、「大名(宗麟)が、宣教師を仲介役として活用し、ポルトガル商人から主体的に武器を購入した」のです。宣教師やキリシタンは、この武器貿易における重要な「触媒」や「仲介者」ではありましたが、取引の「商人」、すなわち主体は紛れもなく大友宗麟自身でした。
したがって、「臼杵シモン」が持つ武器商人という側面は、大友宗麟の極めて重要な政治・経済的活動の記憶が、後世に伝えられる過程で、より分かりやすい個人の逸話として矮小化され、キリシタンの代表者たる「シモン」という名の下に帰属されたものと考えるのが妥当です。
民衆の記憶の中では、「キリスト教の保護」と「武器貿易」という、宗麟の政策下で密接に結びついていた二つの要素が分かちがたく結合しました。そして、その記憶がやがて「キリシタンの代表者(シモン)が、武器を売買した」という、よりシンプルで人格化された物語へと変化していったと推測されます。ここで、大友宗麟の「事績」が、先の二人の人物像、すなわち田原親虎の「名前」と野津のリアンの「活動」の上に、さらに重ね合わされることになったのです。
第四章:比較考察 ― 同時代の他の「シモン」たちと歴史像の確定
ここまで、「臼杵シモン」という人物像が、豊後国に実在した三つの異なる要素―田原親虎の「名前」、野津のリアンの「活動」、大友宗麟の「事績」―から構成される複合体であるという仮説を提示してきました。この仮説の妥当性をさらに強固なものにするため、視点を広げ、同時代に「シモン」あるいはそれに近い洗礼名を持った他の著名なキリシタン武将と比較検討を行います。
比較対象となる人物
戦国時代のキリシタン史において、「シモン」という洗礼名を持つ人物は複数存在します。
- 黒田孝高(官兵衛、ドン・シメオン): 豊臣秀吉の天才軍師として名高い黒田官兵衛は、熱心なキリシタン大名であり、その洗礼名は「ドン・シメオン(Simeon)」でした 23 。「シモン(Simon)」とは綴りが異なりますが、音の響きは非常に似ています。しかし、彼の出自は播磨国(現在の兵庫県)であり、その生涯の主たる活動舞台は畿内や筑前国(現在の福岡県)でした 23 。豊後国のキリシタン史に直接深く関与した記録はなく、「臼杵の」人物という属性とは合致しません。
- 大谷吉継: 関ヶ原の戦いにおける悲劇的な最期で知られる大谷吉継も、一説には洗礼名が「シモン」であったとされています 24 。しかし、彼は豊臣秀吉の家臣として越前国敦賀(現在の福井県)を治めており、九州のキリシタン史との直接的な接点は極めて希薄です。
比較分析による結論の明確化
これらの人物と、本報告書でこれまで論じてきた豊後の人物たちを比較することで、「臼杵シモン」の正体に関する我々の仮説は、より一層の説得力を持ちます。以下の比較表は、その関係性を一目瞭然にするものです。
【表1:『臼杵シモン』像に関連する歴史上の人物比較】
|
特徴 |
田原親虎 |
野津のリアン |
大友宗麟 |
黒田孝高(官兵衛) |
|
呼称・洗礼名 |
田原親虎、 シモン |
リアン、理庵(洗礼名不明) |
大友宗麟、ドン・フランシスコ |
黒田孝高、ドン・ シメオン |
|
時代 |
1570年代に活動 |
1578年頃から活動 |
1530年~1587年 |
1546年~1604年 |
|
活動場所 |
豊後国(大友領内) |
豊後国 臼杵 (野津) |
豊後国 (府内、臼杵) |
播磨、筑前など |
|
役割・身分 |
武将、大友家臣の養子 |
地域の有力者、キリシタン指導者 |
大名(豊後国主) |
武将、軍師、大名 |
|
キリスト教との関わり |
熱心な信徒。家族との対立。 |
共同体の指導者。教会を建設。 |
保護者。自身も受洗。 |
キリシタン大名。 |
|
武器貿易との関わり |
直接の記録なし |
直接の記録なし |
南蛮貿易を主導し、鉄砲・大砲を積極的に購入 |
秀吉の側近として関与の可能性 |
この比較表が示す通り、「臼杵シモン」を構成する三つの主要な属性、すなわち①「シモン」という名前、②「臼杵」での宗教活動、③武器貿易への関与は、一人の人間に集約されることはありません。むしろ、それぞれが豊後国に実在した三人の人物、①田原親虎、②野津のリアン、③大友宗麟に由来することが明確に見て取れます。
歴史的・学術的な論証においては、単に一つの仮説を提示するだけでなく、他のあり得た可能性を検討し、なぜそれが棄却されるのかを論理的に示すプロセスが不可欠です。黒田官兵衛や大谷吉継といった他の候補者を俎上に載せ、その活動領域や時代背景を比較検討することで、彼らが「臼杵のシモン」のモデルとはなり得ないことを明らかにしました。この作業を通じて、調査の焦点を再び豊後の地に引き戻し、田原・リアン・宗麟の三者こそが「臼杵シモン」伝説の源流であるという結論の妥当性を、消去法的に、かつ積極的に証明することができるのです。
結論:複合的歴史像としての「臼杵シモン」― 記憶の創造
本報告書における詳細な調査と多角的な分析の結果、戦国時代の豊後に生きたとされる「臼杵シモン」は、単一の歴史上の人物ではなく、複数の実在の人物の属性や逸話が、長い年月を経て人々の記憶の中で融合し、創造された「複合的な歴史像」であると結論付けられます。
その像は、以下の三つの異なる歴史的要素から成り立っています。
- 田原親虎(シモン)の「名前と悲劇の物語」: 信仰のために家族と対立し、悲劇的な運命を辿った若き武将。彼の洗礼名「シモン」は、豊後のキリシタンの苦難を象徴する名として人々の記憶に刻まれ、物語の「主人公の名前」となりました。
- 野津のリアン(理庵)の「臼杵における地域指導者としての活動」: 臼杵市野津の地で、私財を投じて教会や墓地を建設し、百数十人の信徒共同体を指導した土着の有力者。彼の献身的な活動は、「臼杵の地で熱心に布教した」という物語の「具体的な行動モデル」となりました。
- 大友宗麟の「キリスト教保護と武器貿易という事績」: 豊後の支配者として、キリスト教を保護する一方で、南蛮貿易を主導して鉄砲や大砲を戦略的に導入したキリシタン大名。彼の政治・経済的活動は、「鉄砲の売買に関わった」という物語の「背景となる事績」となりました。
これら三つの異なる源流から発した記憶の断片が、語り継がれるうちに一つの流れとなり、やがて「臼杵シモン」という、宣教師であり、地域の指導者であり、武器商人でもあるという、一人の魅力的な人物像として結晶化したのです。
「臼杵シモン」を追い求める我々の旅は、結果として、一人の人物伝に留まることなく、より広大で深遠な歴史の風景を眼前に開示してくれました。それは、純粋な信仰と冷徹な政治的計算、家族の愛憎と宗教的対立、そして国際貿易がもたらす地域の社会変容が、複雑かつダイナミックに絡み合った、戦国時代末期の豊後国そのものの縮図です。
一人の謎多き人物の探求が、いかにして時代そのものの魂に触れる旅となり得るか。「臼杵シモン」の物語は、その好例と言えるでしょう。伝説や伝承の背後にある史実の断片を丹念に拾い集め、それらを論理的に再構成していく作業こそが、歴史研究の醍醐味であり、我々が過去と誠実に対話するための、最も確かな方法なのです。
引用文献
- 翻訳・フロイス「日本史」3部1〜4章 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1456058/p031.pdf
- フロイス日本史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%B9%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2
- Untitled https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/63/63041/33398_1_%E5%A4%A7%E5%88%86%E3%81%AE%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%9F%8E%E9%A4%A8.pdf
- 大友宗麟がキリスト教にのめり込む、そして高城川の戦い(耳川の戦い)で大敗、ルイス・フロイスの『日本史』より https://rekishikomugae.net/entry/2022/06/22/081649
- 田原親賢とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%94%B0%E5%8E%9F%E8%A6%AA%E8%B3%A2
- 大友宗麟、主な足跡とその後 https://otomotaiga.com/pdf/otomo_ashiato.pdf
- 大友宗麟の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46473/
- 大友宗麟は何をした人?「キリシタンの情熱が抑えられず神の国を作ろうとした」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/sorin-otomo
- 天正六年 八月 大友宗麟 宣教師を伴って無鹿に至り、キリスト教王国建設に尽力す - 佐土原城 遠侍間 http://www.hyuganokami.com/kassen/takajo/takajo6.htm
- 武家家伝_田原氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/tahara_k.html
- 耳川の戦いとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%80%B3%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 耳川の戦い(高城川の戦い)/戦国時代の九州戦線、島津四兄弟の進撃(4) - ムカシノコト、ホリコムヨ。鹿児島の歴史とか。 https://rekishikomugae.net/entry/2022/08/24/153314
- 平成27年2月19日(木)夕刊 マレガ・プロジェクト報告4 大津祐司 | 国文学研究資料館 https://www.nijl.ac.jp/projects/marega/results/oita/20150219.html
- 下藤地区キリシタン墓地 | 臼杵市 https://www.city.usuki.oita.jp/docs/2022121900036/file_contents/kirisitann.pdf
- 【大分】江戸時代の禁教令下でも残っていた「下藤キリシタン墓地」in 臼杵市野津町 https://ameblo.jp/takatch/entry-12800945673.html
- 大友宗麟|津久見市観光協会のホームページへようこそ!! https://tsukumiryoku.com/pages/54/
- 逸話とゆかりの城で知る! 戦国武将 第7回【大友義鎮(宗麟)】6カ国の太守はキリスト教国家建国を夢見た!? https://shirobito.jp/article/1437
- 大友義鎮 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E9%8E%AE
- 大海原の王 「大友宗麟」 - 大分市 https://www.city.oita.oita.jp/o029/bunkasports/citypromotion/documents/5147ff54002.pdf
- 1571年「日本人奴隷の買い付け禁止令」が出されたほどの悲惨な歴史 - ニュースクランチ https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/5038?page=2
- 大友宗麟(おおとも そうりん) 拙者の履歴書 Vol.35〜南蛮の風に乗りし豊後の王 - note https://note.com/digitaljokers/n/nc21640eff29b
- 戦国日本を動かした大砲のルーツを探る - テレメール https://telemail.jp/shingaku/academics-research/lecture/g006342
- 黒田孝高 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%AD%9D%E9%AB%98
- 大谷吉継 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E5%90%89%E7%B6%99