鰐淵寺厳空
「鰐淵寺厳空」は戦国時代の出雲で活躍した僧将で、その実体は鰐淵寺和多坊の住持・栄芸。毛利氏に協力し、寺院の存続と繁栄に貢献した。
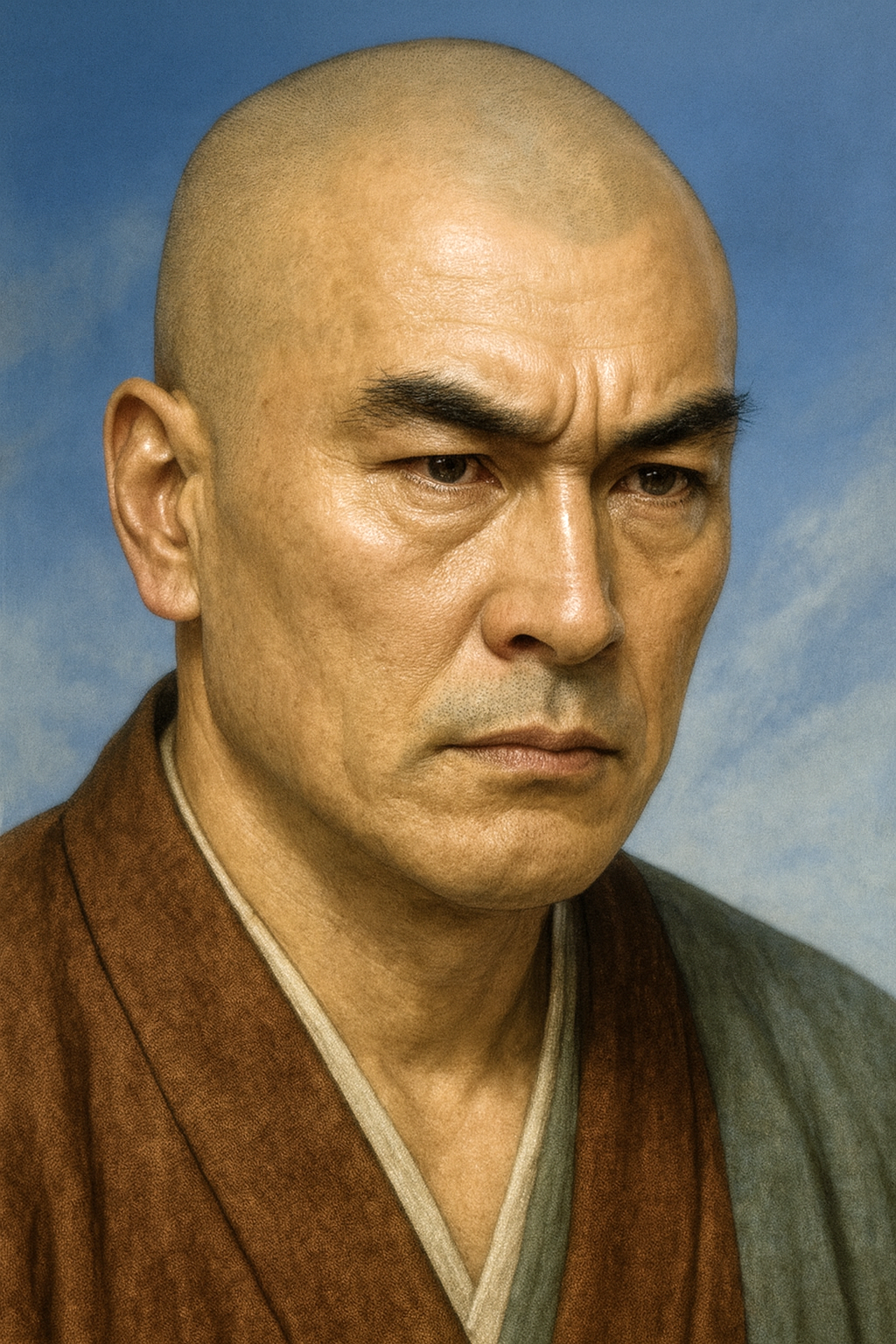
戦国期出雲の僧将「鰐淵寺厳空」に関する総合調査報告
序論:謎の僧将と戦国の出雲
本報告書は、戦国時代の出雲国において活動したとされる「鰐淵寺厳空」という人物の実像を、学術的観点から徹底的に調査し、その生涯と歴史的背景を解明することを目的とする。利用者より提示された「1504年から1592年頃に活躍した旧仏教系の住持であり、大名の要請を受けて一軍を率いた」という人物像は、戦国時代の寺社勢力の動的な役割を象徴するものであり、歴史探求の対象として極めて興味深い。しかしながら、この「厳空」という名は、主要な史料上ではその存在を確認することができない。本報告は、この「謎」を起点とし、史料の断片を繋ぎ合わせ、歴史の深層に埋もれた一人の高僧の実像を追求する調査の記録である。
調査の舞台となる16世紀の中国地方は、出雲の尼子氏と安芸の毛利氏という二大戦国大名が覇権を賭けて激しく角逐した時代であった 1 。その抗争の渦中にあったのが、出雲国北部に位置する天台宗の古刹、鰐淵寺である。この寺院は、単なる宗教施設ではなかった。広大な寺領と多数の僧兵を擁し、地域の政治・軍事情勢に大きな影響力を行使する「寺社勢力」として、自らの存亡をかけて重大な判断を迫られる存在であった 2 。
したがって、「厳空」なる人物を理解するためには、まず彼が属した鰐淵寺そのものの歴史的性格と、それが有した権威と武力を解明する必要がある。本報告書では、第一章で鰐淵寺の実像を明らかにし、続く第二章で尼子・毛利の争乱期における寺の動向を追う。そして第三章において、これらの背景情報を基に「厳空」の実像へと迫る。最終的に、一人の高僧の生涯を通して、戦国時代における寺院の多面的かつダイナミックな役割を浮き彫りにすることを目指すものである。
第一章:権威と武力―「国中第一之伽藍」鰐淵寺の実像
「厳空」が一軍を率いることができたという伝承の背景には、彼が属した鰐淵寺そのものが有した特異な性格が存在する。本章では、宗教的権威、経済的基盤、そして軍事力が分かち難く結合した中世寺院としての鰐淵寺の姿を具体的に描き出す。
第一節:古代・中世における発展と権威の確立
鰐淵寺の権威の源泉は、その古くからの由緒と、出雲国における宗教的中心性にある。寺伝によれば、その開創は推古天皇2年(594年)に遡る。信濃国の智春上人が、推古天皇の眼病平癒をこの地の浮浪の滝に祈願したところ成就したため、天皇の勅願によって建立されたと伝えられている 2 。この伝承は、鰐淵寺に「勅願寺」という極めて高い格式を与えた。また、寺号の由来となった、智春上人が滝壺に落とした仏器を鰐(ワニザメ)が奉げたという伝説も、この地の神秘性を高めている 2 。
古代より、鰐淵寺は浮浪の滝を中心とする修験道の聖地として発展した 2 。後白河法皇が編纂した『梁塵秘抄』にも「聖の住所」としてその名が見えることから、平安時代末期にはすでに全国的な知名度を持つ修験行場であったことがわかる 7 。
平安時代以降、鰐淵寺は比叡山延暦寺との関係を深め、天台宗寺院として「出雲の叡山」と称されるほどの地位を確立した 8 。さらに、その権威を決定的なものとしたのが、出雲国一宮である杵築大社(現在の出雲大社)との不可分な関係であった。神仏習合の進展の中で、鰐淵寺は杵築大社の祭礼に関与するなど相互補完的な関係を築き、後にはその別当寺(寺院を管理する寺)としての役割を担うに至る 7 。この結果、杵築大社が「国中第一之霊神」と称されたのに対し、鰐淵寺は「国中第一之伽藍」と公に認められる、出雲国で比類なき権威を持つ寺院となったのである 9 。
第二節:武装する聖域―僧兵と軍事力
中世の有力寺社は、その権威と広大な荘園(寺領)という経済的基盤を守るため、自衛の武装集団を組織することが一般的であった。これがいわゆる「僧兵」である 3 。鰐淵寺もその例外ではなく、史料には「多数の僧兵を抱え」「出雲有数の勢力」であったと明記されている 3 。この軍事力は、寺院の自立性を担保すると同時に、戦国の動乱期において、各大名が無視できない政治的・軍事的カードとなった。
鰐淵寺の「武」の側面を象徴するのが、かの有名な武蔵坊弁慶にまつわる数々の伝説である。弁慶は青年期に鰐淵寺で3年間修行に励んだとされ、その際に鳥取の大山寺から一夜で釣鐘を担いできたという伝説は特に名高い 5 。現在、国の重要文化財に指定されているその銅鐘には寿永2年(1183年)の銘があり、伝説に歴史的な奥行きを与えている 5 。今日でも、毎年10月には「武蔵坊弁慶まつり」が開催され、僧兵姿の行列が参道を練り歩く 16 。これらの伝説や祭事は、鰐淵寺が単なる祈りの場ではなく、武勇を尊ぶ気風を持つ強力な組織であったことを、後世にまで強く印象付けている。
鰐淵寺の力は、単一の要素では説明できない。古代からの由緒と出雲大社との連携によって確立された「国中第一」という宗教的権威、広大な寺領からもたらされる経済力、そして動員可能な物理的「武力」としての僧兵。この三者が三位一体となり、互いを補強しあうことで、他の勢力が容易に干渉できない強大な「寺社勢力」を形成していた。この複合的な力こそが、戦国大名から見ても、敵に回せば極めて厄介であり、味方にすれば非常に有用な存在と見なされた根源であった。まさしくこの強固な基盤があったからこそ、後に詳述する栄芸(=厳空)のような人物が、歴史の表舞台で活躍することが可能となったのである。
第二章:出雲争乱と鰐淵寺の選択
戦国時代、鰐淵寺は出雲国の支配権を巡る尼子氏と毛利氏の激しい抗争の渦中に置かれた。本章では、この二大勢力の間で、鰐淵寺がいかにして自らの存続を図ったのかを追う。特に、長年の支配者であった尼子氏から、新興の毛利氏へと加担するという重大な政治的決断の背景と影響を分析する。
第一節:尼子氏統治下の鰐淵寺
出雲国を本拠とした戦国大名・尼子氏は、鰐淵寺を重要な寺社と位置づけ、その統制と協調に努めていたと考えられる。天文12年(1543年)には、当主であった尼子晴久の命によって鰐淵寺の造営が行われたという記録も残っており、両者の間に一定の保護関係があったことを示している 19 。
また、尼子氏の興亡を描いた軍記物語『雲陽軍実記』には、尼子氏の重臣である山中氏が鰐淵寺の麓に屋敷を構えていたとの記述が見られる 20 。これは、尼子氏の支配体制と鰐淵寺周辺地域が密接な関係にあったことをうかがわせる。
しかし、その一方で、戦国大名の支配力が強化されるにつれて、寺領への干渉や臨時的な軍役負担の要求など、寺院の伝統的な特権や自律性を脅かす動きも顕在化したと推測される。史料には、戦国期に尼子・毛利両氏の「干渉により、寺領が減少」したと記されており 2 、尼子氏の支配が必ずしも鰐淵寺にとって安泰なものではなかった可能性が示唆される。このような潜在的な緊張関係が、後の政治的選択に影響を与えたことは想像に難くない。
第二節:毛利氏出雲侵攻と鰐淵寺の戦略的転換
永禄年間(1558年~1570年)、安芸国から勢力を拡大した毛利元就は、満を持して出雲国への本格的な侵攻を開始する。この時、元就は鰐淵寺に赴き、尼子氏討伐の戦勝祈願を行ったと伝えられている 23 。これは、元就が鰐淵寺の持つ宗教的権威と、出雲国内におけるその影響力を高く評価し、自軍の正当性を高めるとともに、在地勢力を味方につけるための戦略的布石であったと考えられる。
この国家存亡の機において、鰐淵寺は重大な決断を下す。寺の中心的な僧坊であった「和多坊」の住持・栄芸(えげい)が、一貫して毛利氏を支持する方針を打ち出したのである 8 。栄芸の協力は、単なる祈祷に留まらなかった。情報提供、在地国人衆への調略、兵站の支援など、その「助力」は多岐にわたり、毛利氏の出雲平定に大きく貢献したとされている 24 。
この功績により、毛利氏の勝利後、鰐淵寺は手厚い保護を受けることとなった。特に、元就の子である毛利輝元が鰐淵寺の根本堂を再建したことは、両者の協力関係を象徴する事業であった 8 。鰐淵寺のこの選択は、結果として寺院の存続と戦国大名という新たな庇護者の獲得に成功したのである。
鰐淵寺の毛利氏への加担は、単なる「寝返り」として片付けるべきではない。それは、寺院の存続と権益の維持・拡大という、組織としての至上命題に基づいた、極めて合理的かつ戦略的な政治判断であった。尼子氏の支配下で寺領への干渉が進み、その将来性に疑問符が付き始めていた中で、西から怒涛の勢いで迫る毛利氏に与することは、旧来の権益を新たな支配者に再確認させ、さらなる庇護を得るための最善の策であった。和多坊栄芸は、一人の宗教家であると同時に、自らが率いる巨大組織の将来を見据えた、冷徹なリアリズムを持つ政治家・戦略家でもあった。彼の決断は、宗教的理念のみならず、寺院という組織の存続を第一に考えた、戦国時代ならではの現実的な政治行動の典型例と言えよう。
第三章:「鰐淵寺厳空」の実像への探求
本報告書の核心として、史料を駆使して「厳空」という名の謎を解き明かし、その歴史的実体として、前章でその名が浮上した和多坊栄芸の生涯を再構築する。
第一節:「厳空」の名を追って―史料の壁
まず結論から述べると、国の重要文化財に指定されている494点に及ぶ『鰐淵寺文書』をはじめ 26 、江戸時代の地誌である『雲陽誌』 17 、その他、現代に至るまでの各種研究論文やデータベースを精査した結果、「厳空」という名の僧侶を鰐淵寺の記録の中から特定することはできなかった。
この史料上の不在は、いくつかの可能性を示唆する。第一に、「厳空」が本名や公的な記録に用いられる名ではなく、内々で用いられた法名や道号であった可能性。第二に、その厳格な人柄や戦乱を生き抜いた卓越した手腕から、後世の人々が畏敬や畏怖の念を込めて付けた異名であった可能性。そして第三に、口承で語り継がれる過程や、信頼性の低い地誌などに記録される際に、「栄芸」という名が、より僧侶らしい響きを持つ「厳空」へと変化、あるいは誤記された可能性である。いずれにせよ、「厳空」という名は、公式の歴史記録からは姿を消している。
第二節:最有力候補・和多坊栄芸の生涯
「厳空」の名は史料に見えない。しかし、利用者より提示された人物像と、史料上に明確な足跡を残す和多坊栄芸の経歴を比較すると、両者が同一人物である可能性が極めて濃厚に浮かび上がってくる。
- 地位と役割の一致: 栄芸は、鰐淵寺の数ある僧坊の中でも中心的な存在であった「和多坊」の長であった 22 。さらに、現存する自身の肖像画の賛文から、権大僧都・法印大和尚という極めて高い僧位にあったことが確認できる 28 。これは、伝承にある「旧仏教系の住持」という記述と完全に合致する。
- 大名との関係の一致: 史料には、毛利元就が栄芸に「心酔した」 22 、「親交を深めた」 25 と記されており、両者が単なる庇護者と被庇護者の関係を超えた、強固な信頼関係で結ばれていたことがわかる。これは「大名の要請を受けて」という伝承の背景を雄弁に物語っている。
- 軍事活動の一致: 栄芸が毛利氏の出雲侵攻に際して行った「助力」や「支持」 8 こそが、「一軍を率いて合戦に参加した」という伝承の核になったと考えるのが最も自然である。実際の活動は、僧兵を率いて前線で戦うといった直接的な戦闘指揮よりも、在地勢力への調略、情報提供、後方支援といった、より戦略的な役割が主であった可能性が高い。しかし、その貢献が毛利軍の勝利に不可欠であったがゆえに、後世に語り継がれる中で、より英雄的な「僧将」としてのイメージが付与されていったのであろう。
- 活動年代の一致: 決定的証拠となるのが、活動年代である。栄芸の没年は、鰐淵寺に現存する彼自身の肖像画『栄藝僧正像』の賛文によって、天正12年(1584年)7月27日と特定できる 28 。この年代は、利用者が示す活動年代「1504年~1592年頃」の範囲内に完全に収まる。
これらの比較から、「鰐淵寺厳空」として伝わる人物の歴史的実体が、和多坊栄芸その人であることは、ほぼ疑いようがない。
比較分析表:「鰐淵寺厳空」の伝承と「和多坊栄芸」の史実
以下の表は、「厳空」の伝承と「栄芸」の史実を比較し、両者が同一人物であることを視覚的かつ決定的に示すものである。
|
比較項目 |
鰐淵寺厳空の伝承(利用者提供情報) |
和多坊栄芸の史実(調査結果) |
根拠史料 |
|
活動拠点 |
出雲・鰐淵寺 |
出雲・鰐淵寺(中心僧坊・和多坊の長) |
8 |
|
地位 |
旧仏教系の住持 |
天台宗の権大僧都・法印大和尚 |
28 |
|
活動年代 |
1504年~1592年頃 |
生年不詳~天正12年(1584年)没 |
28 |
|
活動内容 |
布教活動 |
鰐淵寺の管理運営、毛利氏との交渉 |
8 |
|
軍事活動 |
大名の要請で一軍を率い合戦に参加 |
毛利元就に与し、出雲侵攻に「助力」・「支持」 |
8 |
|
関係大名 |
(特定の大名) |
毛利元就・輝元 |
8 |
「厳空」という名の由来に関する考察
栄芸の実像を明らかにした上で、なぜ彼が「厳空」という名で記憶されているのか、学術的な仮説を提示する。確定的な史料がない以上、いずれも断定はできないが、最も可能性が高いのは、第三節冒頭で述べた「伝承過程での変化説」であろう。栄芸の死後、彼の卓越した政治手腕と、戦国の世を生き抜いた厳格な姿勢が語り継がれる中で、その名がより宗教的な響きを持ち、人物像を象徴する「厳空」という呼称に置き換わっていったのではないか。
いずれにせよ、史実上の活動が明確に確認できる「和多坊栄芸」こそが、「鰐淵寺厳空」として語り継がれてきた人物の歴史的実体であると結論付けて差し支えない。
結論:戦国を生きた高僧―栄芸の生涯にみる寺院の姿
本調査報告は、「鰐淵寺厳空」という名の人物を直接的に示す一次史料は現存しないものの、その伝承される人物像が、鰐淵寺和多坊の住持であった高僧・栄芸の生涯と驚くほど一致することを明らかにした。したがって、「厳空」とは、後世に伝わる栄芸の異名、あるいは伝承上の呼称であり、両者は同一人物であると結論付けるのが最も妥当である。
栄芸の生涯は、戦国時代の高僧が、単に仏道修行や教学研究に明け暮れるだけの存在ではなかったことを示す好例である。彼らは自らが属する寺院という巨大組織の存続と繁栄のため、時には戦国大名と対等に渡り合い、政治・軍事の舞台で重要な役割を担う「政治家」であり「戦略家」としての一面を併せ持っていた。栄芸が毛利氏に与した決断は、その最たるものであり、中世寺社勢力の現実的な生存戦略を如実に示している。
しかし、栄芸の活躍は、中世を通じて強大な力を誇った寺社勢力がその権勢の頂点に達した姿であると同時に、その時代の終わりの始まりを告げるものでもあった。栄芸の死後まもなく、天下を統一した豊臣秀吉は全国に刀狩りを実施し、寺社が独自の軍事力を保持することを禁じた 3 。続く江戸幕府による厳格な寺社制度の確立は、鰐淵寺のような寺院が独立した政治力・軍事力を行使する時代に、完全な終止符を打った。その意味で、栄芸の生涯は、中世的寺社勢力の最後の輝きであったと総括することができる。
最後に、今後の展望について触れておきたい。鰐淵寺には、今なお多くの未解読の古文書や、その全容が解明されていない考古学的遺構が眠っている 7 。島根大学などが中心となって進める総合的な学術調査の進展によっては 11 、栄芸のさらなる詳細な活動内容や、あるいは「厳空」という名の謎を解き明かす新たな手がかりが発見される可能性も残されている。一人の僧将の探求は、戦国時代の宗教と社会の関係性を解き明かす、より大きな研究へと繋がっているのである。
引用文献
- 城下町彷徨 芸州 広島 - JR西日本 https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/13_vol_149/issue/01.html
- 国史跡鰐淵寺境内のご紹介 - 出雲市 https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1516949654620/index.html
- 僧兵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%A7%E5%85%B5
- izumo-kankou.gr.jp https://izumo-kankou.gr.jp/683#:~:text=%E9%B0%90%E6%B7%B5%E5%AF%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E6%8E%A8%E5%8F%A42,%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 鰐淵寺(がくえんじ) - 出雲観光ガイド https://izumo-kankou.gr.jp/385
- 鰐淵寺境内 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/273862
- 歴史・文化サイトカード https://kunibiki-geopark.jp/wp-content/uploads/2025/03/1-A-14%E3%80%80%E9%B0%90%E6%B7%B5%E5%AF%BA%E3%80%81%E6%B5%AE%E6%B5%AA%E6%BB%9D.pdf
- 鰐淵寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B0%90%E6%B7%B5%E5%AF%BA
- 鰐淵寺(ガクエンジ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%B0%90%E6%B7%B5%E5%AF%BA-460103
- 鰐淵寺 | みー散歩~神社仏閣御朱印めぐり~ https://ameblo.jp/mi-sanpo194/entry-12763196654.html
- 出雲鰐淵寺の歴史的・総合的研究〔科学研究費プロジェクト〕 - 山陰研究センター - 島根大学 https://www.src.shimane-u.ac.jp/kenkyu_jigyou/src_kyodou_project/jrp_0911.html
- 第二番 鰐淵寺 | 出雲国神仏霊場 https://shinbutsu.jp/shrines-temples/gakuenji/
- 鰐淵寺の書置き御朱印と見どころを徹底紹介 https://www.goshuinbukuro.com/entry/gakuenji
- 第43回 武蔵坊弁慶まつり - 出雲観光ガイド https://izumo-kankou.gr.jp/5283
- 鰐淵寺 - 出雲観光ガイド https://izumo-kankou.gr.jp/683
- 祭・イベント詳細: 鰐淵寺(がくえんじ)・武蔵坊弁慶まつり - まちむら交流きこう https://www.kouryu.or.jp/festival/detail/32203/5915/
- 武蔵坊弁慶まつり | しまね観光ナビ|島根県公式観光情報サイト https://www.kankou-shimane.com/destination/20940
- ふるさと - 出雲市立光中学校 https://www.izumo.ed.jp/hikari-chu/furusato.html
- 小笠原長雄 - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/tag/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E9%95%B7%E9%9B%84
- 鰐淵探訪 - 山中鹿介 - 出雲市 https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1296807065695/html/common/63db1825037.html
- 山中幸盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E4%B8%AD%E5%B9%B8%E7%9B%9B
- 国史跡鰐淵寺境内 史跡関連情報 - 出雲市 https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1447810718645/index.html
- 戦国の水利要衝 鳶ケ巣城趾・鳶が巣山 - 山陰の山 出雲國風土記の山々 https://biotop21.web.fc2.com/tobi.htm
- 鰐淵探訪 - 鰐淵寺 - 出雲市 https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1296807065695/html/common/63db1825017.html
- 鰐淵寺 | 中国観音霊場|中国路山陽・山陰の名刹古刹37ヶ寺を結ぶ魅力あふれる巡拝ルート https://www.kannon.org/author/jiin28/
- 鰐淵寺文書(四百九十四通) - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/377794
- 共同利用・共同拠点における共同研究により古文書群が重要文化財に - 東京大学 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/z0206_00003.html
- 8178_栄藝僧正像(鰐淵寺) - 東京文化財研究所 https://www.tobunken.go.jp/materials/nenki/810761.html
- 21320123 研究成果報告書 https://kaken.nii.ac.jp/file/KAKENHI-PROJECT-21320123/21320123seika.pdf