一火流砲術書
一火流砲術は筑前泊一火が種子島で創始。高弟が青山幸成に仕え尼崎藩の公式武芸に。実戦技術が泰平の世で藩の武備へと変化した武芸伝播の成功例。
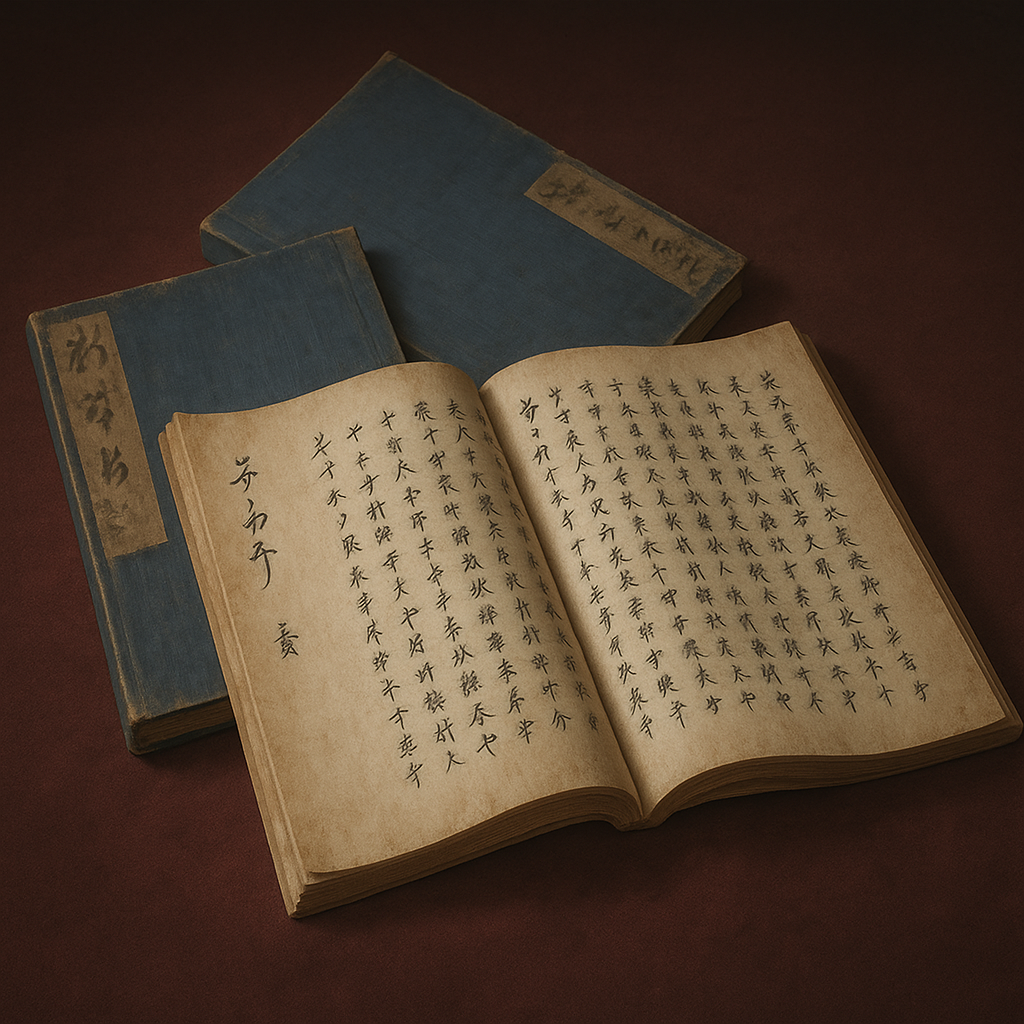
『一火流砲術書』の総合的考察:戦国期砲術の系譜と一火流の真相
序章:謎の砲術流派「一火流」への探求
日本の武芸史において、鉄砲の伝来は戦国の様相を一変させた画期的な出来事であった。それに伴い、鉄砲を専門に扱う「砲術」は、瞬く間に全国の武士にとって必須の武芸となり、数多の流派が勃興した。その中にあって「一火流(いっかりゅう)」は、創始者や伝承の概要が断片的に伝わるものの、その全体像は長らく深い謎に包まれてきた。本報告書は、戦国時代という視点から「一火流砲術書」という伝書、およびその母体である一火流砲術そのものを、流祖、技術、伝承の三つの側面から立体的に解明することを目的とする。
調査の出発点は、利用者が提示した「泊兵部少輔一火(とまりひょうぶのしょうゆういっか)なる人物が創始し、その秘伝を記した書」という情報である 1 。本報告書は、この伝承を単に追認するに留まらず、現存する史料を駆使してその裏付けと再解釈を試みる。その過程で、一見孤立した流派に見える一火流が、戦国末期から江戸初期にかけての武家社会の構造と、いかに密接に結びついていたかが明らかになる。
本調査を通じて、二つの核心的な結論が導き出された。第一に、一火流の伝播の軌跡である。九州の筑前国に生まれたこの一地方流派は、創始者の弟子が徳川譜代大名に仕官し、その主君が畿内の要衝である摂津国尼崎藩へと転封される過程を通じて、日本の中心部へと伝わるという、武芸伝播の具体的な成功例を示している。第二に、「一火流砲術書」の実態である。特定の表題を持つ一冊の書物の現存は確認できないものの、尼崎藩の公式記録に「一火流」の名が明確に記されていることから、その教えは単一の書物としてではなく、藩の武芸指南役の家で代々受け継がれる巻物や覚書、免許状といった「伝書群」として存在した可能性が極めて高い。
本報告書は、これらの点を踏まえ、第一章で流祖・泊一火の実像に迫り、第二章で『一火流砲術書』の想定される内容を復元、第三章でその伝承の具体的な経路を解明する。そして最終章において、これらの分析を統合し、戦国砲術史における一火流の歴史的意義を結論づける。
第一章:流祖・泊一火の実像
一火流砲術の理解は、その創始者である泊一火という人物の解明から始めなければならない。彼はどのような背景を持ち、いかにして一派を成すに至ったのか。史料に残された断片的な記述を繋ぎ合わせることで、その輪郭が浮かび上がってくる。
出自と背景:筑前の士「泊」氏
諸記録によれば、泊一火は「筑前の人物」または「筑前の士」とされている 1 。この「筑前国」とは、現在の福岡県西部に相当する地域である。さらに注目すべきは、彼の姓である「泊(とまり)」である。筑前国志摩郡には、古くから「泊」という地名(現在の福岡市西区唐泊など)が存在し、戦国時代にはその地を拠点とする在郷武士「泊氏」が活動していたことが確認されている 4 。泊氏一族は、源姓を称し、内部で遺領を巡る争いを起こした記録も残るなど、地域に根差した武士団であった 7 。
これらの事実から、泊一火は単に抽象的な「筑前の士」ではなく、この泊氏の一族、あるいはこの地と極めて深い関わりを持つ人物であった可能性が非常に高い。これにより、伝説上の存在であった泊一火は、特定の地域社会に根差した、より実在性の高い人物像として捉えることができる。通称を「兵部少輔」と称したことも、彼が武士階級に属していたことを示唆している 1 。
求道の軌跡:種子島での七年
泊一火の経歴で最も重要な点は、天正年間(1573年~1592年)に、鉄砲技術の先進地であった大隅国種子島に渡り、実に7年もの歳月を費やして修行したという伝承である 1 。この長期にわたる滞在の末、彼は砲術の「妙旨」を究め、一火流を創始したとされる 2 。
当時の種子島は、1543年の鉄砲伝来以来、国内における鉄砲生産と技術研究の一大拠点となっていた 9 。全国から武士や鍛冶が最新技術を学ぶために集まる、いわば「研究開発センター」としての役割を果たしており、一火がこの地を目指したことは、彼の砲術に対する並々ならぬ探求心の表れと言える。
また、一部の史料は、彼が種子島に渡る以前に「津田流」を学んでいた可能性を指摘している 2 。津田流は、紀州根来寺を拠点とし、鉄砲の国産化や集団運用法の開発に大きく貢献した、日本砲術の源流とも言うべき流派である 3 。もしこの伝承が事実であれば、一火は既存の有力流派の技術を基礎としながらも、それに飽き足らず、技術の原点である種子島に直接赴くことで、独自の理論と技術を確立しようとした、極めて意欲的な武芸家であったと評価できる。
一火流の創始と戦国砲術史における位置づけ
7年間の修行を終えた泊一火は、故郷の筑前に戻り、自らの探求の成果を「一火流」として体系化した 2 。この流派が、当時の砲術界においてどのような位置にあったのかを理解するために、同時代の主要な流派と比較することは有益である。
表1:戦国期における主要砲術流派の比較
|
流派名 |
流祖 |
創始時期(目安) |
拠点 |
技術的特徴・備考 |
主要な伝承藩・勢力 |
|
一火流 |
泊一火 |
天正年間 |
筑前国 |
種子島での修行に基づく。詳細は不明だが、後に尼崎藩のお抱え流となる。 |
尼崎藩(青山家) |
|
津田流 |
津田監物 |
天文年間 |
紀伊国 |
根来衆を背景に持ち、鉄砲の国産化と集団運用に貢献。多くの流派の源流となる 3 。 |
根来寺、諸大名 |
|
稲富流 |
稲富一夢 |
天正年間 |
丹後国 |
照尺を用いた遠距離射撃、詳細な伝書体系で知られる。徳川家康にも仕えた 3 。 |
細川家、徳川家、米沢藩など |
|
田付流 |
田付景澄 |
慶長年間 |
江戸 |
幕府鉄砲方として代々仕え、実戦的な技術を伝えた 3 。 |
江戸幕府 |
|
井上流(外記流) |
井上正継 |
慶長年間 |
江戸 |
田付流と並び幕府鉄砲方を務めた。西国で「外記流」として広まる 3 。 |
江戸幕府、西国諸藩 |
|
陽流 |
高野安長 |
不詳(江戸初期か) |
筑前国 |
抱大筒(大口径火縄銃)の扱いに特化。福岡藩黒田家のお留め流(藩外不出) 12 。 |
福岡藩(黒田家) |
この比較から、一火流のいくつかの特徴が浮かび上がる。まず、創始時期が天正年間であることから、稲富流などとほぼ同時期に、戦国末期の最も実戦的な要求が厳しい時代に誕生したことがわかる。また、同じ筑前国で後に成立する陽流が、福岡藩黒田家のお留め流として藩外不出の秘伝とされたのに対し、一火流は藩の外部へと伝播していく異なる道を辿った。そして何よりも、その伝承が特定の譜代大名家との結びつきによってなされた点に、田付流や井上流といった幕府お抱えの流派との類似性を見出すことができる。一火流は、戦国末期の地方に生まれながら、武士社会の力学の中でその価値を認められ、生き残っていった流派だったのである。
第二章:『一火流砲術書』の内容復元と考察
一火流の核心に迫る上で、「一火流砲術書」の存在は極めて重要である。しかし、この「砲術書」は具体的にどのようなものであったのか。現存が確認できない以上、その内容を他流派の伝書や武芸の普遍的な構造から類推し、復元を試みる必要がある。
現存史料の不在と「秘伝書」の普遍的構造
まず結論から述べると、国立国会図書館や主要大学図書館の蔵書データベースを調査した限りでは、「一火流砲術書」という特定の表題を持つ書物は、現在のところ一点も確認されていない 13 。しかし、これは一火流の技術体系や伝書が存在しなかったことを直接意味するものではない。
近世以前の武芸流派における「秘伝書」は、今日我々が想像するような単一の書籍とは形態が異なる場合が多い。その教えは、流派の奥義や段階に応じて、巻物、切紙、目録、免許皆伝書といった複数の文書に分割して記され、師から弟子へと段階的に伝授されるのが一般的であった 17 。これらの伝書群は、藩の武芸指南役を務める家などで門外不出の秘宝として厳重に保管された。したがって、「一火流砲術書」とは、これら一連の伝書群の総称であったと考えるのが最も妥当である。
他流派の伝書の内容は、一火流の教えを推測する上で貴重な手がかりとなる。例えば、近世を代表する砲術流派である稲富流の伝書には、鉄砲の起源、射撃の心得、射撃姿勢、弾丸の種類、玉目(口径)に応じた鉄砲の仕様、火薬原料の配合、照準具の説明など、鉄砲に関する包括的な知識が体系的に記されている 11 。また、福岡藩の陽流には「陽流砲術教歌巻」という、教えを和歌の形式で詠んだ伝書が存在し、精神的な心得が重視されていたことが窺える 19 。一火流の伝書群もまた、こうした技術論と精神論を両輪とする構成であったと推測される。
想定される技術体系:一火流の「妙旨」とは
泊一火が種子島での7年間の修行の末に掴んだという「妙旨」とは、具体的にどのような技術体系だったのだろうか。他流派の教えを参考に、その内容を復元的に考察する。
基礎技術
砲術の根幹を成すのは、火縄銃を正確かつ迅速に操作する一連の基本動作である。一火流の伝書にも、以下のような項目が図解入りで解説されていた可能性が高い。
- 装填法: 銃口から火薬(胴薬)と弾丸を入れ、槊杖(かるか)で突き固める手順 20 。
- 火付法: 火皿に点火薬(口薬)を盛り、火蓋を閉じる作法。また、火縄への着火と保持の方法。例えば、火縄の両端に火を点け、二つ折りにして指に挟む「二口火(ふたくちび)」のような、連続射撃に備えるための工夫も含まれていたかもしれない 20 。
- 射法: 標的を狙い、引き金を引いて発射するまでの一連の動作。構え方(立射、膝射、伏射など)、照準の合わせ方、呼吸法などが詳述されていたと考えられる 17 。
応用技術と流派の独自性
実戦では、単純な射撃技術だけでは不十分である。一火流の「妙旨」は、より高度な応用技術や戦術的思考を含んでいたと推測される。
- 射撃術の応用: 標的までの距離に応じた火薬量の調整、風や雨といった天候が弾道に与える影響の計算と補正、夜間や悪条件下での射撃法、移動する目標を狙う「動的射撃」などが含まれたであろう。
- 「妙旨」の考察: 泊一火が到達した「妙旨」とは、単なる射撃の巧みさを超えた、より高次の概念であった可能性が高い。それは、戦況を瞬時に読み解き、地形や天候、敵の配置といった諸条件を総合的に判断し、最も効果的な一撃を、最も効果的な時期に加えるための「戦術眼」であったかもしれない。陽流の教歌にある「しめ所両手一眼心意気 目当に星ののくは引金」(要は、両手と眼と精神を一致させ、照準が定まった瞬間に無心で引き金を引くこと)という教えのように、一火流においても、技術と精神が一体となった境地こそが「妙旨」と呼ばれたのではないだろうか 19 。
精神性と心得:砲術家の心構え
武芸の伝書は、技術の解説に先立ち、あるいはその締めくくりとして、流派の由来や武人としての倫理観、精神的な心得を説くのが常である。一火流の伝書群にも、射撃に臨む際の精神統一の重要性、不動心、敵を侮らず、己を過信しない謙虚さ、そして何よりも平時における鍛錬の継続を説く教えが含まれていたと想像される。砲術は一撃で人の命を奪う強力な武芸であるからこそ、その担い手には高い倫理観と克己心が求められた。一火流の教えもまた、単なる殺人術ではなく、心身を鍛え上げる「道」としての側面を強く持っていたに違いない。
第三章:一火流の伝承と展開
一火流が単なる一代限りの芸で終わらず、後世に伝承されたのは、高弟の存在と、彼が仕えた主君の力によるところが大きい。筑前国で生まれたこの砲術は、一人の武士の仕官をきっかけに、畿内の有力な藩へと移植され、その地で根付いていくことになる。
高弟・岡田重勝と青山氏への仕官
泊一火の弟子として、史料にその名が確認できる唯一の人物が、岡田助之丞重勝(おかだすけのじょうしげかつ)である 1 。彼は織豊時代(安土桃山時代)に活動した砲術家であり、一火流の技を師から受け継ぎ、次代へと繋ぐ重要な役割を果たした。
その岡田重勝が仕えた主君は、「青山幸能(あおやまゆきのう)」と記録されている 21 。しかし、同時代の徳川家臣団や大名の中に「幸能」という名の人物は見当たらない 24 。一方で、徳川家康の重臣・青山忠成の四男で、二代将軍・秀忠、三代将軍・家光に仕えた譜代大名に、青山幸成(あおやまよしなり)という人物が存在する 27 。幸成は、後に一火流が伝承されることになる尼崎藩の初代藩主である。これらの状況証拠から、「幸能」は「幸成」の誤記または誤伝であると断定するのが最も合理的である。
主君となった青山幸成は、徳川政権の中枢に近い有力な武将であった。天正14年(1586年)に生まれ、大坂の陣などで武功を重ね、書院番頭などの要職を歴任した 30 。最終的には遠江国掛川藩主を経て、寛永12年(1635年)、大坂の西の守りを固める戦略的要衝、摂津国尼崎藩5万石の初代藩主として入封した 28 。
幸成が、数ある砲術流派の中から、岡田重勝が身につけた一火流を評価し、自らの家臣団に採用したという事実は、極めて重要である。これは、一火流の技術が、戦国の実戦を生き抜いてきた有力大名の眼鏡に適うほど、実用性の高いものであったことを何よりも雄弁に物語っている。そして、幸成の尼崎への転封は、九州の一地方で生まれた一火流という砲術を、日本の政治・軍事の中心地帯である畿内へと移転させる、決定的な契機となったのである。
尼崎藩における一火流の継承
この推測を裏付ける決定的な史料が存在する。尼崎市立歴史博物館(あまがさきアーカイブズ)が公開している「尼崎藩砲術調練関係史料概要」には、以下の記述がある。
「戸田氏・青山氏の尼崎藩主時代は、泊兵部少輔一火に始まる一火流砲術が伝承されたという」 33 。
また、同市のWeb版尼崎地域史事典『apedia』にも、「尼崎藩では、近世初期以来泊兵部少輔一火(に始まる一火流砲術が伝承された)」との記述が見られる 34 。これらの公的記録は、一火流が単なる伝説や個人の芸ではなく、尼崎藩の公式な武芸として、藩政史の中に明確に位置づけられていたことを証明する第一級の史料である。
青山家が尼崎藩主であった期間(1635年~1711年)、一火流は藩の砲術の中核を担っていたと考えられる。藩士たちは、岡田重勝の流れを汲む指南役のもとで一火流を学び、藩の武備を支えていたのであろう。
しかし、武芸の世界もまた、盛者必衰の理から逃れることはできない。青山家が丹後国宮津藩へ、次いで美濃国郡上藩へと転封となり、尼崎藩主が桜井松平家に代わると、藩の砲術にも変化が生じた。先の史料概要によれば、松平氏の時代になると、享保9年(1724年)に大和国郡山から奥山儀太夫が招かれて「武衛流」を、また寛政年間(1789年~1801年)には家松幸内によって「荻野流」が伝えられている 33 。
これは、藩における武芸流派の採用が、藩主の個人的な縁故や好み、あるいは時代の要請に応じた技術革新(より体系化された流派や、特定の用途に特化した流派の導入など)によって変化することを示す典型的な事例である。また、複数の流派を藩内で競わせることで、全体の技術水準の維持・向上を図るという政策的な意図があった可能性も考えられる。青山家と共に尼崎に入った一火流は、やがて他の有力流派との共存と競争の中で、その役割を徐々に変化させていったと推測される。この変遷は、泰平の世となった江戸時代の藩において、武芸がどのように維持され、あるいは淘汰されていったかを示す、興味深い歴史のダイナミズムを内包している。
第四章:総合分析と結論
これまでの調査で明らかになった事実を統合し、一火流砲術とその伝書が持つ歴史的意義を再評価するとともに、今後の研究への展望を提示し、本報告書の結論としたい。
一火流の歴史的意義の再評価
一火流の歴史は、単なる一武芸流派の興亡史に留まらない。それは、戦国末期から江戸初期にかけての日本の社会変動と、武芸のあり方の変容を映し出す、貴重なケーススタディである。
第一に、一火流は「武芸伝播のモデル」としての価値を持つ。その軌跡は、戦国末期に九州の一地方で生まれた実践的な技術が、①卓越した技術を持つ武芸家(泊一火)、②その技を継承し仕官の機会を掴んだ弟子(岡田重勝)、③その価値を認め採用した有力な主君(青山幸成)、そして④主君の全国的な配置転換(尼崎への転封)という、江戸幕藩体制の成立過程と完全に連動して、畿内の中核的な藩にまで伝播した見事な事例である。これは、武芸の伝承が、技術そのものの優劣だけでなく、武家社会の主従関係という社会構造に深く根差した現象であったことを示している。
第二に、一火流は「戦国から泰平の世へ」という時代の転換期における砲術の役割の変化を象徴している。泊一火が種子島で命がけで究めたであろうその技術は、本来、敵を殺傷し、城を落とすための実戦の術であったはずだ。しかし、それが尼崎藩に伝承される頃には、世はすでに「元和偃武」後の泰平の時代へと移行していた。藩における一火流の役割は、純粋な戦闘技術としてだけでなく、藩の武威を示すための武備として、また、藩主への上覧演武といった儀礼的なものへと、その重心を移していったと考えられる 33 。これは、砲術そのものが持つ意味が、戦の道具から、武士の身体と精神を鍛える「武道」へと昇華していく過程の一端を物語っている。
『一火流砲術書』研究の今後の展望
本報告書は、史料に基づき、一火流という砲術流派の実在とその伝承経路を明らかにした。これにより、今後の研究の焦点は、その「具体的な技術内容」の解明へと移るべきである。
その可能性が最も高い場所は、一火流が公式に伝承された尼崎藩の記録を保管する、尼崎市立歴史博物館(あまがさきアーカイブズ)であることは論を俟たない。同館には、尼崎藩士の家に伝来した文書群や、藩の砲術調練に関する史料が所蔵されている 33 。これらの未整理の藩政史料や、藩士の子孫宅に今なお残されている可能性のある古文書の中に、一火流の具体的な構え、火薬の調合、射法などを記した伝書や覚書、図解などが含まれている可能性は決して低くない。特に「尼崎藩砲術調練関係史料」や、内田家、片岡家といった藩士の文書群を精査することは、今後の研究における急務と言えるだろう 35 。
結論:一火流とは何だったのか
結論として、一火流砲術とは、戦国時代末期の筑前国に、泊一火という一人の傑出した武芸家の探求心によって生まれた、実戦的な砲術流派であった。その真価は、徳川譜代大名・青山幸成という慧眼の主君に見出され、彼の尼崎移封という政治的・軍事的な要請に伴い、藩の公式武芸として採用されるという、武士社会における一つの成功を収めた。
『一火流砲術書』という名の特定の書物は、今日その姿を見ることはできない。しかし、その教えは「一火流」という名と共に、尼崎藩の歴史の中に確かに刻み込まれている。その物語は、一人の武芸者の情熱と技が、いかにして時代と社会の大きなうねりの中で受け継がれ、そして変容していったかを我々に教えてくれる。一火流の探求は、戦国という時代の熱気と、それに生きた人々の息遣いを今に伝える、貴重な歴史の証言なのである。
引用文献
- 泊一火 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%8A%E4%B8%80%E7%81%AB
- 一火流(いっかりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E7%81%AB%E6%B5%81-1504935
- 砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93
- ① - 福岡市の文化財 https://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/files/NewsBlocks/d5aa985d-5152-4659-9a60-2db74cf8be83/value01/NewsParagraph77fileja.pdf
- 市史だより - 福岡市 http://www.city.fukuoka.lg.jp/shishi/pdf/kouhou18.pdf
- 筑前国怡土庄故地現地調査速報 - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1520164/p142.pdf
- 志摩郡泊氏のお家騒動にみる「戦国時代の志摩郡における権力階層」 2018年2月 http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/182233398.html
- 泊一火(とまり いっか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B3%8A%E4%B8%80%E7%81%AB-1094944
- 全国火縄銃大会 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/41/41411/91137_1_%E9%89%84%E7%A0%B2%E4%BC%9D%E6%9D%A5%E4%BB%8A%E3%82%88%E3%81%BF%E3%81%8C%E3%81%88%E3%82%8B%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%81%AB%E7%B8%84%E9%8A%83%E5%A4%A7%E4%BC%9A.pdf
- 日本本土に初めて鉄砲をもたらした砲術家・津田監物算長(岩出市、和歌山市) https://oishikogennofumotokara.hatenablog.com/entry/2023/03/11/000000
- 稲富流鉄砲秘伝書 いなどめりゅうてっぽうひでんしょ - ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/kyuhaku/P15002?locale=ja
- 陽流砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%BD%E6%B5%81%E7%A0%B2%E8%A1%93
- 一火流秘傳書 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000001-I2612110964604
- 国立国会図書館―National Diet Library https://www.ndl.go.jp/
- 京都府立京都学・歴彩館 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/library/FA026813?l=en
- 京都学・歴彩館紀要 - CiNii 雑誌 https://ci.nii.ac.jp/ncid/AA12849789
- 54 稲冨流砲術書 (いなとみりゅうほうじゅつしょ) - 知の職人たち-南葵文庫に見る江戸のモノづくり- https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/html/tenjikai/tenjikai2006/shiryo_06.html
- 稲富流鉄砲秘伝書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/538411
- 陽流砲術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/072/
- 火縄銃 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%B8%84%E9%8A%83
- 岡田重勝(おかだ しげかつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B2%A1%E7%94%B0%E9%87%8D%E5%8B%9D-1061976
- 岡田重勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E7%94%B0%E9%87%8D%E5%8B%9D
- 岡田重勝とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%B2%A1%E7%94%B0%E9%87%8D%E5%8B%9D
- 青山吉能- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%9D%92%E5%B1%B1%E5%90%89%E8%83%BD
- 青山吉能- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%9D%92%E5%B1%B1%E5%90%89%E8%83%BD
- キャラクターボイス一覧| ドラゴンクエストX オンライン https://www.dqx.jp/online/promotion/voice/
- 青山忠成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B1%B1%E5%BF%A0%E6%88%90
- 青山幸成 - apedia http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E9%9D%92%E5%B1%B1%E5%B9%B8%E6%88%90
- 青山幸成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B1%B1%E5%B9%B8%E6%88%90
- 青山幸成(解説) https://fururen.net/siryoukan/tenji/dekigoto/ryousyu/aoyamaryou.html
- あおやま - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/aoyama.html
- 青山家(幸成系)のガイド | 攻城団 https://kojodan.jp/family/46/
- 尼崎藩砲術調練関係史料概要 http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/collections/records/catalogs/pdf/096004.pdf
- 砲術 - apedia https://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E7%A0%B2%E8%A1%93
- 尼崎藩士が修めた武術について調べたい。 | レファレンス協同 ... https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000221667