人見流馬術書
人見流馬術は、大坪流を源流とし、戦国期の実戦から江戸期の心身鍛錬へと変容。乃木希典の武士道精神を育み、近代における武士の役割の変化を映し出す、その歴史を紐解く。
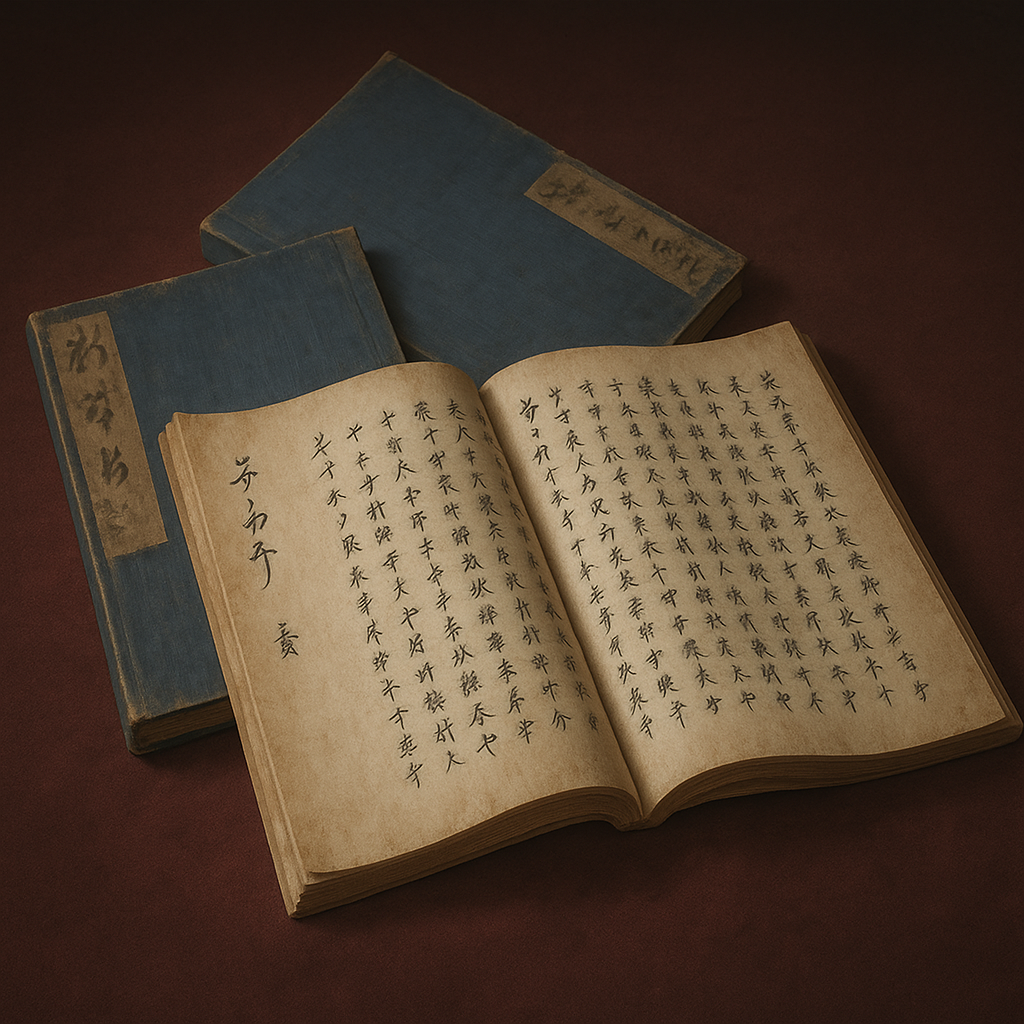
「人見流馬術書」の総合的考察:戦国時代の視点から見たその実相と武士道精神への継承
序論
本報告書は、特定の伝書が現存しない「人見流馬術」について、その起源、教授された歴史的背景、そして近代への影響を多角的に分析し、その全体像を学術的に復元することを目的とする。人見流は、日露戦争で活躍した陸軍大将・乃木希典が幼少期に修めた馬術として知られているが、その具体的な内容はこれまで不明瞭な点が多かった。本報告書では、この泰平の世である江戸時代に完成された馬術を、実戦が常態であった「戦国時代の視点」という比較軸を用いて分析する。このアプローチにより、単に一つの流派を解明するに留まらず、日本の武士階級における馬術観、ひいては武芸そのものの思想的変遷を浮き彫りにすることを目指す。
研究を進めるにあたり、人見流に関する直接的な一次資料が極めて限定的であるという課題が存在する。この課題を克服するため、本報告書は断片的な記録を繋ぎ合わせる手法を採用する。具体的には、人見流の源流と考えられる大坪流の伝書、実際に教授が行われた長府藩の藩史、そして最も著名な門弟である乃木希典の伝記など、広範な周辺資料を駆使する。これらの資料に基づく論理的推論を通じて、これまで謎に包まれていた人見流馬術の実態に迫り、その歴史的意義を再評価するものである。
第一章:人見流馬術の源流と系譜
人見流馬術の本質を理解するためには、まず日本の馬術史全体の中にそれを位置づける必要がある。人見流は孤立して誕生したものではなく、古くから続く日本の武芸の大きな伝統の流れから派生した一支流であった。本章では、その源流を室町時代まで遡り、その系譜を明らかにする。
第一節:日本馬術の二大潮流―小笠原流と大坪流
日本の馬術は、古代の記録にその萌芽が見られる。天武天皇の時代にはすでに「馬的射(うまゆみ)」、すなわち後の流鏑馬の原型となる騎射が行われていた記録が残る 1 。鎌倉時代に入ると、源頼朝が弓馬の道を武士の必須技能として奨励し、流鏑馬(やぶさめ)、笠懸(かさがけ)、犬追物(いぬおうもの)の「馬上三物」が武士の嗜みとして確立された 2 。これらは神事としての側面も持ちながら 4 、実戦的な騎射技術を錬磨する場でもあった。
室町時代に至り、これらの実戦的馬術は体系化され、特定の流派として確立される。その中で、日本の馬術史における二大潮流が形成された。一つは、新羅三郎義光以来の源家の伝統を継承し、足利将軍家の師範家となった小笠原氏によって体系化された 小笠原流 である。小笠原流は、騎射を中心としつつも、礼法と結びつき、儀礼的な側面を強く持つ流派として発展した 2 。
もう一つが、本報告書の主題である人見流の直接的な源流となる 大坪流 である。創始者とされる大坪慶秀(道禅)は、小笠原流の馬術を学んだ後、より軍用馬術に重点を置いた新しい一派を創始した 5 。大坪流は、小笠原流が幕府の保護下で秘伝を守り、その伝統を厳格に維持したのとは対照的に、全国の諸大名に広く受け入れられ、多くの分派・支流を生み出す母体となった 5 。この開放的な伝播こそが、後に長府藩において人見流という一つの伝承が生まれる土壌となったのである。
第二節:大坪流の思想と発展
大坪流の神髄は、その技術のみならず、その根底に流れる思想にある。創始者・大坪慶秀が残したとされる「 鞍上に人なく、鞍下に馬なし 」という言葉は、大坪流の理想とする境地を端的に示している 5 。これは、乗り手と馬が完全に一体化し、あたかも鞍の上には人がおらず、鞍の下には馬がいないかのような自然な状態を指す。単なる技術論を超え、馬との精神的な合一を目指す、禅にも通じる深い思想的背景を持っていた。
大坪流は、斎藤好玄といった名人を輩出し、戦国時代から江戸初期にかけてその隆盛を極めた。江戸幕府を開いた徳川家康自身も大坪流の達人であり、戦時必須の武技として馬術を奨励したため、幕府や諸藩において大坪流は公式な武芸として重んじられた 2 。
しかし、二百数十年におよぶ泰平の世が続いた江戸中期になると、馬術のあり方も変化を遂げる。実戦の機会が失われる中で、いわゆる「箱庭式馬術」や、馬の歩調に合わせてリズミカルに乗る「拍子乗り」といった、華美で演武的な技術が流行し始めた 2 。これは、馬術が実戦技術から、武士の教養や儀礼の一部へとその性格を変化させていったことの現れであった。この流れの中で、八代将軍徳川吉宗は武芸奨励策の一環として、実用的な馬術の再興を図り、その気運の中で大坪流も新たな展開を見せることとなる 2 。
第三節:人見流の直接的源流の探求
人見流の直接の創始者に関して、「人見」姓の人物が馬術の一派を興したという明確な記録は、現存する資料からは見出すことができない。しかし、その名称の由来についてはいくつかの可能性が考えられる。武蔵七党の一つである猪俣党の庶流として、鎌倉時代に人見光行という武士が存在した記録がある 8 。また、剣術の天流の系譜には「人見熊之助」という名も見られる 9 。これらの事実から、「人見」が武士の姓として存在し、武芸に関わっていたことは確かである。
乃木希典が人見流を学んだのが幕末の長府藩であることを考慮すると、その源流は江戸中期以降に再興された大坪流の一派であると考えるのが最も合理的である。特に、八代将軍吉宗の武芸奨励を受けて大坪流を再編・大成した斎藤主税定易(さいとう ちから さだやす)の系統、すなわち「 大坪本流 」がその直接的な源流であった可能性が極めて高い 2 。
これらの状況証拠を統合すると、一つの有力な結論が導き出される。それは、「人見流」という名称が、全く新しい流派の「創始」を意味するのではなく、既存の権威ある流派である大坪流の地方における「 呼称 」であったという可能性である。武術の歴史において、ある地域で特定の師範が指導する系統が、その師範の姓や地域の名前を冠して呼ばれることは決して珍しくない。したがって、大坪流の正統な教えを継承した「人見」姓の師範、あるいはその家系が長府藩の馬術師範となり、藩内においてその系統が「人見流」として定着したと推察される。これは、人見流がゼロから生まれた孤立した流派ではなく、大坪流という大きな権威を背景に持つ、由緒正しい一地方伝承であったことを示唆している。
第二章:長府藩における人見流の展開
人見流馬術がどのような場で、いかなる目的で教授されていたのかを理解するためには、その舞台となった長府藩の歴史的・文化的文脈を分析することが不可欠である。本章では、長府藩の武士教育における人見流の具体的な役割と、その実践の様子を明らかにする。
第一節:長府藩の文武奨励
長州藩の支藩である長府藩は、教育を極めて重視していた。1792年(寛政4年)、第10代藩主毛利匡芳は、門閥にとらわれず有能な人材を登用するため、藩校「 敬業館 」を創設した 11 。敬業館では、藩士の子弟は15歳になると必ず入学することが義務付けられ、文武両道の修練に励んだ 11 。
その教育方針は極めて厳格であった。学問を解せず、武芸も修められない者は、たとえ嫡子であっても廃嫡される可能性があったという記録は、藩が文武の道を単なる教養ではなく、武士としての存在意義そのものと捉えていたことを示している 12 。藩では、人見流馬術の他にも、剣術(今枝流)、槍術(宝蔵院流)、そして大筒を特徴とする砲術(櫟木流)など、多岐にわたる武術が専門の師範によって教授されており、人見流もこの藩の公式な武芸教育体系の一翼を担っていた 13 。
第二節:藩士・乃木希典と師・工藤八右衛門
乃木希典は、嘉永二年(1849年)、長府藩士・乃木希次の子として江戸の藩邸で生まれた 15 。父・希次の職務は、藩主の警護を務める「馬廻役」であり、乃木家にとって馬は職務上も極めて密接な存在であった 16 。この家庭環境は、後の乃木の馬に対する深い愛情を育む一因となったであろう。
安政五年(1858年)に父と共に長府へ帰った乃木は、文久元年(1861年)、13歳の時から 工藤八右衛門 という師範に就いて人見流馬術を学び始めた 15 。これは、前述の敬業館における藩の公式教育の一環であり、彼の武士としての人格形成の初期段階において、極めて重要な要素であった。長府藩では、馬術師範家が特別に昇格した記録も残っており 19 、馬術が藩内で重視されていたことが窺える。工藤八右衛門もまた、藩から公認された馬術師範(御馬方)であったと考えられる。
第三節:江戸後期における藩の馬術稽古の実態
幕末期の長府藩における人見流の稽古は、藩が管理する整備された馬場で行われていたと推察される。その内容は、実戦での乱戦を想定したものよりも、儀礼的な乗馬術や、定められた型をいかに正確に、そして美しく演武するかに重点が置かれていたであろう。
時代背景として、黒船来航以降、西洋式の軍備導入が急速に進む中で、櫟木流砲術のような伝統砲術でさえも、その実戦的価値は相対的に低下しつつあった 2 。伝統的な和流馬術も例外ではなく、戦闘技術としての役割は、新たな騎兵戦術にその座を譲りつつあった。しかし、その価値が完全に失われたわけではない。むしろ、その役割が変容したと見るべきである。
この時代の藩校教育における人見流馬術は、戦闘技術の習得という直接的な目的よりも、武士の「 身体的・精神的規範 」を涵養するための教育装置として、より重要な機能を持っていた。馬という、力強く、そして御しがたい動物を制御する訓練を通じて、乗り手は忍耐力、克己心、そして威厳ある態度を身につける。馬との対話を通じて、力だけでは従わせられない相手を理解し、導く統率力を学ぶ。藩という組織の構成員として、また将来の指導者として相応しい精神と身体、そして洗練された所作を身につけさせるための「人間形成の道」として、人見流の稽古は位置づけられていたのである。これは、戦闘集団から統治機構へとその役割を大きく変えた、江戸時代の武士階級のあり方を象徴している。
第三章:「人見流馬術書」の内容の学術的推察
「人見流馬術書」そのものは現存しないが、その源流である大坪本流の教えや、江戸時代の馬術の一般的な傾向から、その内容を学術的に推察することは可能である。それは単なる技術の羅列ではなく、馬という生き物と武士との関係性を規定する、包括的な知識体系であったと考えられる。
第一節:五馭の法―馬術の総合科学
人見流の教えの根幹をなしていたのは、その源流である大坪本流の斎藤定易が体系化した「 五馭(ごぎょ)の法 」であったと強く推察される 2 。これは馬術を五つの専門分野に分類した総合的な学問体系であり、「人見流馬術書」もこの構成に沿って編纂されていた可能性が高い。
- 医 (Medical): 馬の病気の診断と治療法、薬草の知識など、獣医学的側面。軍馬の健康を維持するための必須知識であった。
- 相 (Appraisal): 良馬を見分けるための馬体や性質の鑑定法。優れた軍馬を確保するための相馬術。
- 常 (Daily Care): 日常的な飼育法、調教、手入れの方法。馬の能力を最大限に引き出すための馬匹管理学。
- 礼 (Ceremony): 登城や行列といった公式な場における乗馬の作法、馬具の規定など、礼法としての側面。武士の威儀を示す上で重要であった。
- 軍 (Military): 戦場での乗り方、馬上での武器(刀、槍、弓)の扱い、集団での陣形行動など、本来の軍事技術。
この五つの要素からなる体系は、馬を単なる乗り物や兵器としてではなく、武士が総合的に理解し、管理し、その能力を最大限に引き出すべきパートナーと見なす、江戸時代の洗練された馬術思想を反映している。
第二節:伝書に記された技術と心得
「人見流馬術書」には、具体的な技術論も詳細に記されていたであろう。特に、江戸時代に流行した「 拍子乗り 」と呼ばれる、馬の歩調に合わせたリズミカルで優雅な乗り方は、重要な項目の一つであったと考えられる 2 。また、手綱一本で馬の複雑な動きを制御するための、精緻な手綱捌きの秘伝も図解入りで解説されていたと推察される。
馬具、特に鞍(くら)と鐙(あぶみ)の重要性についても、多くのページが割かれていたはずである。大坪流は独自の鞍の製法を編み出したことでも知られており、その構造や手入れの方法、正しい装着法などが記されていたであろう 5 。
さらに、技術論以上に重視されていたのが精神論である。「 己を正しうして馬を咎めず 」という大坪流の基本的な心構えは、繰り返し説かれていたに違いない 5 。馬が乗り手の意のままにならないのは、馬が悪いのではなく、乗り手の心や技術に未熟な点があるからだ、という内省的な教えである。そして、最終的な目標である「鞍上に人なく、鞍下に馬なし」という人馬一体の境地に至るための精神修養の道筋が、段階的に示されていたと考えられる。
第三節:失われた実戦性と洗練された様式美
「五馭の法」という体系の中で、泰平の世が続いた江戸後期の人見流においては、「軍」の比重は相対的に低下し、代わりに「礼」の比重が高まっていた可能性が高い。また、当時渡来した朝鮮の曲馬術なども影響を与え、技術はより観賞用、演武用として洗練され、様式美が追求された 2 。
これらの点を総合すると、「人見流馬術書」がどのような書物であったか、その性格が浮かび上がってくる。それは、戦場で生き残るための苛烈な技術を記した「 戦闘教本 」から、武士としての総合的な教養と品格を示すための「 百科全書的指南書 」へと、その性格を大きく変容させていた。獣医学(医)、鑑定眼(相)、管理能力(常)、儀礼の知識(礼)といった要素は、いずれも平時における武士の能力と教養を示す重要な指標となる。戦国時代であれば、馬の価値は何よりもまず戦場での働きによって決まったが、江戸時代においては、血統の良さ、姿の美しさ、儀式での完璧な振る舞いといった価値が重要性を増す。
したがって、「人見流馬術書」に求められた内容も、敵を効率的に討ち果たす技術よりも、良馬を鑑定し、健康に育て、儀式で完璧に乗りこなすという、総合的な「マネジメント能力」と「美的センス」を証明するための知識体系が中心となっていた。これは、武士が「戦士」から「官僚・支配者」へとその社会的役割を変化させたことの、武芸における直接的な反映であったと言える。
第四章:戦国時代の視点からの比較分析
本章では、前章でその内容を推察した人見流馬術を、その源流が生まれた戦国時代の過酷な実戦で求められた馬術と比較対照する。この比較を通じて、江戸時代の馬術が何を獲得し、何を失ったのか、その歴史的価値と限界を浮き彫りにする。
第一節:戦場の馬術―生存と殺戮の技術
戦国時代の戦場において、騎馬武者は戦局を左右する重要な役割を担っていた。彼らの任務は、高速での移動による索敵や伝令、側面や背後からの奇襲、そして何よりも敵陣に突撃して戦況を打開することであった。馬は単なる移動手段ではなく、機動力と破壊力を兼ね備えた「生きた兵器」そのものであった 2 。
この環境で求められた技術は、徹頭徹尾、実用性に貫かれていた。整備されていない野山や河川といった不整地を高速で走破し、敵の矢や鉄砲による攻撃を瞬時に回避し、馬上での槍や刀による戦闘はもちろん、敵と組み合って落馬させる馬上組討にも対応できなければならなかった。そこでは、乗り姿の美しさや型の正確さよりも、いかに生き残り、いかに敵を効率的に殺傷するかという生存性が最優先された。
第二節:泰平の馬術―心身鍛錬と儀礼の道
一方、人見流に代表される江戸期の馬術は、その様相を大きく異にする。稽古の場は、危険な自然地形ではなく、藩が管理する安全で整備された馬場が中心であった。技術は、状況に応じて変化する実戦の動きではなく、あらかじめ定められた型を反復練習することによって習得された。
その目的もまた、敵を倒すことから、定められた型をいかに完璧に、そして美しくこなすか、いかに馬と呼吸を合わせ一体化するかという、内面的な「求道」へと変化した。馬術は、殺戮の技術から、心身を鍛錬し、武士としての品格を陶冶するための「道」へと昇華されたのである。
第三節:戦国武者が「人見流馬術書」を読んだら
もし、戦国時代の歴戦の武者がタイムスリップし、「人見流馬術書」を手に取ったとしたら、どのような評価を下すだろうか。
まず、高く評価するであろう点は、「五馭の法」のうち「医」や「相」に関する知識である。軍馬の質を維持し、その能力を最大限に引き出すための獣医学的知識や相馬術は、戦国武者にとっても極めて有益であり、実践的な価値を見出したであろう。「軍」の項に記された基本的な乗り方や手綱捌きも、新兵の基礎訓練として有用だと考えたはずである。
一方で、無用、あるいは形骸化していると断じる点も多かったに違いない。「礼」に関する詳細な規定や、「拍子乗り」のような演武的な技術は、一刻を争う戦場では全く役に立たないどころか、隙を生む危険なものとして切り捨てられたであろう。また、「人馬一体」という精神論も、より即物的で効果的な「馬を意のままに動かす技術」に比べれば、観念的で悠長なものと見なされたかもしれない。
この両者の差異を明確にするため、以下の比較表を作成した。
表1:戦国期実戦馬術と江戸期人見流馬術の比較
|
項目 |
戦国期実戦馬術 |
江戸期人見流馬術(推察) |
|
主目的 |
戦場での生存、索敵、突撃、殺傷 |
心身の鍛錬、儀礼の実践、品格の陶冶 |
|
稽古場所 |
野山、河川など自然地形 |
藩の整備された馬場 |
|
重視される技術 |
悪路走破、急停止・急旋回、馬上組討 |
正確な型、美しい姿勢、拍子乗り |
|
馬との関係 |
兵器、機動力の源泉 |
パートナー、精神修養の対象 |
|
思想的背景 |
実利主義、生存術 |
求道主義、人馬一体の哲学 |
|
伝書の内容 |
(あるとすれば)実戦的な技法、陣形 |
五馭の法(医・相・常・礼・軍) |
この比較から明らかになるのは、江戸期の馬術のいわゆる「形骸化」が、単なる技術の劣化を意味するのではないということである。それは、武士階級の価値観そのものが、「 武力 」から「 教養 」へと移行したことの必然的な現れであった。戦国時代、武士の価値は戦場での「武功」によって直接的に測られた。しかし、統治階級となった江戸時代の武士の価値は、家格や役職、そしてそれに相応しい「教養」や「品格」によって測られるようになった。
馬術は、この新しい価値基準に対応するために自己変革を遂げたのである。馬に関する包括的な知識(五馭の法)を持ち、儀礼(礼)を完璧にこなし、美しい乗り方(様式美)を披露することが、高い教養と品格の証明となった。したがって、戦国期の視点から見える「形骸化」は、江戸期の武士にとっては、より高度な文化への「洗練」であり「深化」であった。これは、武芸が殺人の技術から、支配階級としてのアイデンティティを形成・維持するための文化的資本へと、その社会的機能を大きく変化させたことを明確に示している。
第五章:乃木希典と人見流―近代における武士道精神の継承
最終章では、江戸時代に完成された人見流馬術が、近代日本の軍人である乃木希典にどのような影響を与えたのかを考察する。これにより、伝統武芸が激動の近代化の中で果たした精神的な役割を論じる。
第一節:人格形成と武士の素養
乃木希典が幼少期に、人見流馬術をはじめ、剣術(田宮流)、槍術(宝蔵院流)、弓術(日置流)、砲術(洋式砲術)など、多岐にわたる武芸を修めたことは、彼の精神的バックボーンを形成する上で決定的な役割を果たした 15 。これらの修練は、単なる技術の習得に留まらず、武士としての心構え、すなわち克己、忍耐、礼節といった精神性を身体に深く刻み込む過程であった。
特に、馬という自我を持つ生き物と向き合う馬術は、彼の人間性に大きな影響を与えたと考えられる。力ずくでは決して従わない馬をパートナーとするには、自制心、粘り強い忍耐、そして相手を理解しようとする姿勢が不可欠である。乃木が終生、深い愛情を馬に注いだことはよく知られており、殉死の直前にも厩舎の愛馬にカステラを与えたという逸話は、彼が馬術の修練を通じて育んだ、生き物への慈しみの心を象徴している 20 。
第二節:日露戦争と武士道
乃木の名を世界史に刻んだ日露戦争、特に凄惨を極めた旅順攻囲戦において見せた彼の姿は、人見流で培われた精神性と無関係ではない。二人の息子を戦場で失いながらも、個人的な感情を抑え、司令官としての任務を最後まで遂行した強靭な克己心。そして、降伏した敵将ステッセルと水師営で会見した際に見せた、敗者への礼節と武人としての敬意は、西洋的な軍事合理性だけでは説明できない、日本の武士道精神の発露として世界に報じられた 22 。
この精神性は、彼が幼い頃から学んだ人見流の教え、すなわち「己を正しうして馬を咎めず」という自己への厳しさや、儀礼を重んじる心と深く響き合っている。戦いの場においても礼を失わない態度は、人見流の「五馭の法」における「礼」の精神が、彼の行動規範の根底にあったことを示唆している。
第三節:失われゆく伝統と殉死の美学
日露戦争後、学習院長に就任した乃木は、学生たちに馬術を積極的に奨励した 23 。これは、彼が近代教育の中に、失われつつある武士的な精神性を注入しようとした試みであった。彼にとって馬術は、もはや近代戦における戦闘技術ではなく、次代を担う若者たちの人間性を陶冶するための「道」そのものであった。
そして、明治天皇大葬の日、乃木は静子夫人と共に殉死を遂げる。主君に殉じるというこの行為は、武士道の究極の形の実践であり、彼が幼少期から身体に叩き込んできた伝統武芸の精神的帰結であった 20 。
この一連の乃木の生涯を俯瞰するとき、彼にとって人見流馬術が持った意味が明らかになる。それは、機関銃や榴弾砲が支配する近代の戦場では直接役に立たない「 過去の技術 」であった。しかし同時に、近代国家の指導者として、また一人の武人として生きるために不可欠な「 武士の魂 」を保持するための、終生の精神的支柱であった。陸軍大将として、彼は伝統馬術の軍事的限界を誰よりも深く理解していたはずである 2 。それでもなお、彼が馬を愛し、馬術を精神教育の手段として重視したのは、技術(スキル)と精神(スピリット)を明確に区別していたからに他ならない。人見流の「技術」は時代遅れになったかもしれないが、その修練を通じて得られる「精神」―克己、礼節、忠誠、そして人馬一体の調和を追求する心―は、時代を超えて普遍的な価値を持つと、彼は固く信じていた。彼の生涯、特にその最期は、急速な西洋化・近代化の奔流の中で、失われゆく日本の伝統的精神(武士道)を、自らの身体と行動をもって体現し、後世に伝えようとする強烈な意志の表れであった。そして、長府藩の馬場で始まった人見流馬術の修練は、その強靭な意志を育んだ、紛れもない原体験の一つだったのである。
結論
本報告書における分析を通じて、「人見流馬術」およびその失われた伝書の歴史的意義が明らかになった。人見流馬術は、室町時代に創始された大坪流を源流とし、長府藩という特定の教育的土壌の中で育まれた、江戸時代の武士教育を象徴する馬術であった。そして、「人見流馬術書」は、単なる技術解説書ではなく、馬に関する総合的な知識体系(五馭の法)と、武士としてあるべき品格を説く、百科全書的な指南書であったと結論づけられる。
本報告書の分析はまた、日本の武士社会における馬の位置づけが、時代と共に劇的に変遷したことを示した。戦国期における、生存と殺戮のための「兵器」としての馬。江戸期における、心身を鍛錬し、一体化を目指す「求道の伴侶」としての馬。そして近代における、乃木希典に象徴されるような、失われゆく「武士道精神の象徴」としての馬。人見流馬術は、この壮大な歴史的変遷の重要な一幕を担っていたのである。
今後の展望として、長府藩の藩史料や、乃木の師であった工藤八右衛門に関するさらなる調査が期待される。それらの研究を通じて、本報告書で学術的に推察した人見流の具体的な稽古内容や思想が、より一層明確になることであろう。
引用文献
- 流鏑馬 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E9%8F%91%E9%A6%AC
- 馬術(バジュツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A6%AC%E8%A1%93-169116
- 流鏑馬―日本の古式弓馬術の800年の伝統を今に― | December 2023 | Highlighting Japan https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202312/202312_11_jp.html
- 【日本の馬術】流鏑馬だけじゃない和式馬術の紹介 - 乗馬メディア EQUIA エクイア https://equia.jp/trivia/post-6122.html
- 大坪流とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E5%9D%AA%E6%B5%81
- 古馬術“大坪流”について資料はあるか。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000292351&page=ref_view
- 大坪流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%AA%E6%B5%81
- 人見光行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E8%A6%8B%E5%85%89%E8%A1%8C
- 天流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%B5%81
- 日 本 在 来 馬 と 西 洋 馬 https://jvma-vet.jp/mag/06406/a6.pdf
- 敬業館 - 下関長府観光協会 https://chofukankou.com/%E6%95%AC%E6%A5%AD%E9%A4%A8/
- 下関市長府 敬業館及集童場址 | 試撃行 https://access21-co.xsrv.jp/shigekikou/archives/22598
- 長府藩櫟 木 流砲術保存会 - 下関市 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/uploaded/attachment/14957.pdf
- 長府藩人物禄へ - ぬしと朝寝がしてみたい https://sinsaku.access21-co.jp/11cyousyu-cyoufu.html
- 乃木希典 - 城下町長府 http://jchofu.my.coocan.jp/nogi.htm
- 乃木希典 Nogi Maresuke - Web書画ミュージアム - 長良川画廊 https://www.nagaragawagarou.com/visualmuseum/m-maresuke.html
- 長府藩侍屋敷長屋 - ニッポン旅マガジン https://tabi-mag.jp/ya0364/
- 乃木将軍と那須野の生活 - 石ぐら会 https://ishigurakai.web.fc2.com/nyumon/h23_kawashima.pdf
- 長州藩の家臣団 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B7%9E%E8%97%A9%E3%81%AE%E5%AE%B6%E8%87%A3%E5%9B%A3
- 849夜 『乃木大将と日本人』 スタンレー・ウォシュバン https://1000ya.isis.ne.jp/0849.html
- 3. 学習院の愛馬 「乃木号」 https://www.gakushuin.ac.jp/univ/ua/publication/pdf/ml_04_02.pdf
- 敗者をいたわる武士道精神を近代で実践した将軍「乃木希典」とは? - 男の隠れ家デジタル https://otokonokakurega.com/learn/secret-base/22087/
- 馬の - 学校法人学習院 https://www.gakushuin.ac.jp/univ/ua/publication/pdf/ml_25_06.pdf