大東流柔術書
大東流柔術書は、新羅三郎義光を遠祖とし、武田家を経て会津藩に伝わる秘伝「御式内」と伝承される。しかし史実では、武田惣角が近代に諸流を統合し、歴史物語を構築して完成させた複合体なり。
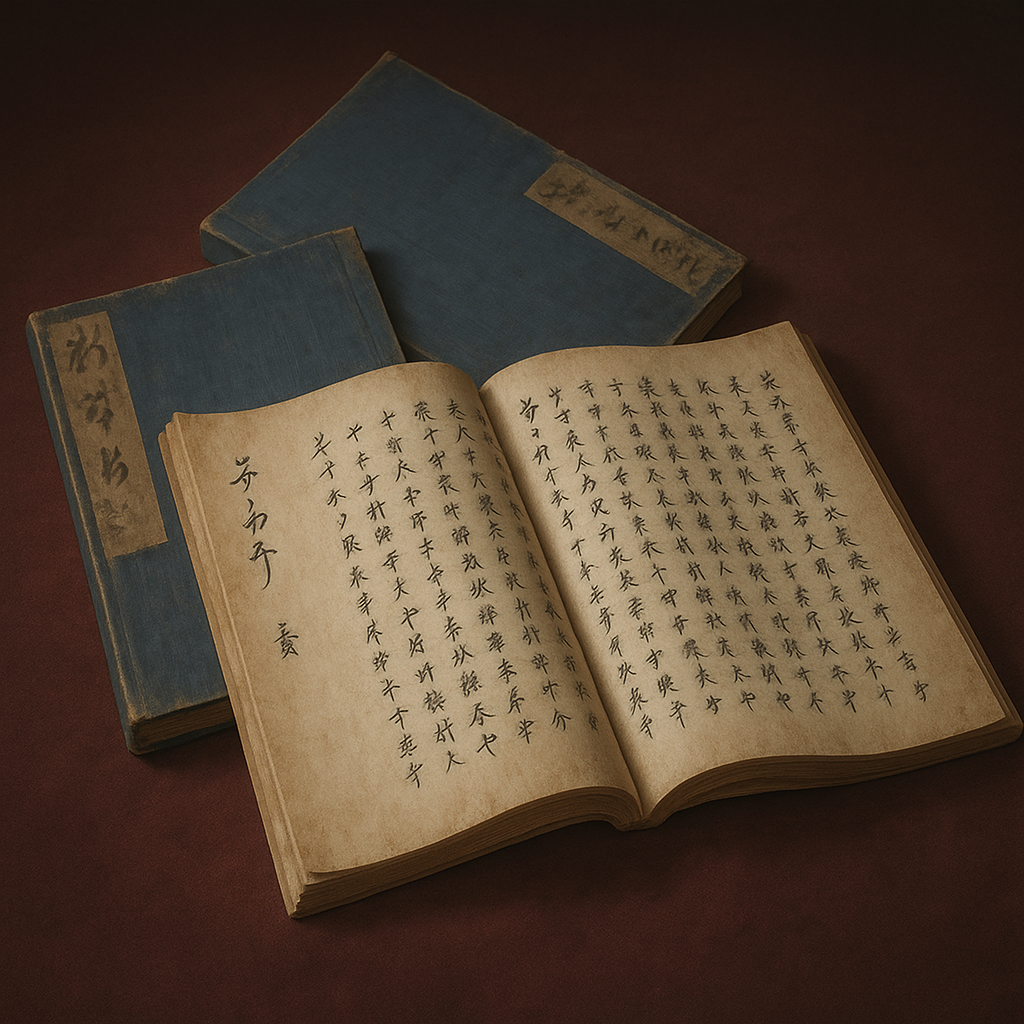
戦国時代の視座から解き明かす「大東流柔術書」―伝承と史実の深層―
序論:問いの再設定―「大東流柔術書」とは何か
本報告書は、「日本の戦国時代」という視点から「大東流柔術書」について徹底的に調査せよ、という要請に応えるものである。調査の出発点として提示された「新羅三郎義光を遠祖とし、甲斐武田家に伝来した合気の術」という伝承は、大東流の自己認識を理解する上で不可欠な要素である 1 。しかし、本報告書はその枠内に留まることなく、より広範かつ深層的な学術的探求を目指す。
この探求にあたり、「大東流柔術書」という主題を二つの側面から捉えることが不可欠である。一つは、新羅三郎義光から甲斐武田家を経て伝来したとされる、物理的な巻物や伝書、すなわち**「物質としての書」 という側面である。もう一つは、その歴史、思想、そして膨大な技術体系の総体を指す、 「無形の体系としての書」**という側面である。この両面から多角的にアプローチすることにより、伝承の背後に隠された歴史的真実と、その物語が構築された背景を解き明かすことが可能となる。
本報告書は三部構成を採る。第一部では、大東流が自ら語る壮麗な系譜、すなわち「無形の書」の内容を詳述する。第二部では、その伝承を歴史学、武術史、郷土史研究の成果に照らして徹底的に再検証し、伝承と史実の乖離を明らかにする。そして第三部では、現存する物理的な記録類、すなわち近代に生まれた「物質としての書」を分析する。この三段階の分析を通じて、「大東流柔術書」という存在の多層的な実像に迫る。
第一部:伝承における「大東流柔術書」―創造された壮麗なる系譜
この第一部では、大東流が公式に語る歴史、すなわち「無形の体系としての書」の内容を詳細に記述する。ここでは史実性の検証を一旦保留し、まずその物語の構造と、それが持つ権威の源泉を理解することに主眼を置く。
第一章:清和源氏と新羅三郎義光―「合気」の濫觴
大東流の公式な伝承によれば、その源流は今から900年以上前の平安時代後期に遡る 2 。流祖とされるのは、清和天皇の末裔であり、武家の棟梁たる清和源氏の中でも特に武勇に優れた武将、新羅三郎源義光である 4 。伝承では、義光が代々清和源氏に伝わる武術を集大成し、さらなる研究工夫を加えて大東流の礎を築いたとされる 3 。
この創始の物語は、具体的かつ鮮烈な逸話によって彩られている。義光は、討ち取った兵士の死体を解剖して人体の骨格や関節の構造を徹底的に研究し、相手の力を利用して制する「逆極手の技」を極めたという 3 。さらに、女郎蜘蛛が自らの巣にかかった自分より数倍も大きな獲物を巧みに絡め捕る様を観察し、そこから「合氣柔術の極意」を悟ったと伝えられている 3 。これらの逸話は、大東流の技術が単なる腕力に頼るものではなく、合理的な身体操作と自然の理に基づいていることを象徴している。
流派の名称である「大東」もまた、義光に由来するとされる。彼がかつて住んでいた屋敷が「大東館」と呼ばれていたことから、その名が付けられたという 1 。
この始祖設定は、単なる起源譚に留まらない。日本の武術流派がその権威を確立する上で、歴史上の偉人や象徴的な出来事を系譜に組み込むことは常套的な手法であった 6 。清和源氏という武家の最高血統を始祖に据えることで、大東流は他の多くの武術とは一線を画す、別格の由緒と歴史的深みを持つという言説を構築したのである。この「権威付けの物語」こそが、「無形の書」の第一章に他ならない。
第二章:甲斐武田家への伝来―戦国武将と秘伝の術
新羅三郎義光によって大成された武術は、その子孫であり、後に甲斐武田家を名乗る一族に代々受け継がれ、家伝の秘術として伝承されたとされている 3 。特に、源氏伝来の「御旗」や「御鎧」といった武家の正統性を示す象徴と共に伝えられたという点は、この武術が単なる一技術ではなく、武田家の根幹を成すものであったことを物語っている 1 。
本報告書の主題である戦国時代、特に「甲斐の虎」と恐れられた武田信玄の時代において、この武術は武田家の武威を支える重要な要素であったと位置づけられている 4 。戦国最強と謳われた武田軍団の強さの源泉に、この門外不出の術があったという物語は、大東流の戦闘における実用性と有効性を強烈に印象付ける。
史実として、この時期の甲斐武田家に「大東流」と呼ばれる武術が存在したことを示す直接的な記録は見当たらない。しかし、伝承におけるこの繋がりは、歴史的事実の記述というよりも、流派の**「武威」**を高めるための象徴的な装置として極めて効果的に機能している。明治期以降、近代化の波の中で多くの古武術がその存在意義を問われる中、「戦場で磨かれた実戦性」は最高の価値を持った。戦国最強の武田家の名を冠することは、その価値を無言のうちに主張する行為であり、流派のアイデンティティを形成する上で不可欠な要素であった。
第三章:会津藩への継承―殿中武術「御式内」の誕生
伝承によれば、この秘術が新たな地平を迎えるのは、天正10年(1582年)の武田家滅亡後である。武田家の一族であった武田国次が会津の地へ逃れ、時の領主であった芦名家に仕えたことにより、甲斐武田家の秘術が会津の地に根付いたとされる 3 。
その後、会津松平藩の治世下において、この術は「御式内(おしきうち)」という名で呼ばれるようになる 7 。そして、藩主や五百石以上の重臣、奥女中といったごく限られた層にのみ伝授される「御留流」、すなわち門外不出の秘伝となった 3 。特に、戦場での合戦術から、城内での不意の襲撃に対応するための殿中護身武術として再編成された点が特徴的である 3 。これにより、座った状態からの技や、狭い空間での体捌きなど、大東流独特の技術体系が磨かれたとされている。
この「御式内」という概念は、伝承の論理的整合性を保つ上で極めて巧妙な装置である。なぜこれほど由緒ある武術が、明治時代になるまで歴史の表舞台に全く登場しなかったのか、という根本的な問いに対し、「藩の最高機密であり、門外不出の秘伝であったから」という完璧な答えを提供する。この「秘伝性」の強調は、記録の不在という客観的な事実を逆手に取り、「それこそが本物の秘伝である証拠」へと転換させる効果を持つ。これは、後の武田惣角による流派の公開を、単なる新流派の旗揚げではなく、「永らく封印されていた古の秘術の解放」という、よりドラマチックな出来事として演出するための重要な布石となっているのである。
第二部:歴史的視点からの再検証―構築された伝統の解体
この第二部では、第一部で詳述した壮大な伝承を、歴史学、武術史、そして近年の郷土史研究の成果に照らして徹底的に検証する。伝承と史実の間に存在する乖離を浮き彫りにし、なぜそのような物語が構築されたのか、その歴史的背景と力学に迫る。
第一章:戦国時代における柔術の実相
大東流の伝承が描く「戦国時代の秘術」というイメージと、武術史研究が明らかにした「戦国時代の武術」の実像には、明確な乖離が存在する。戦国時代の合戦における武士の格闘術は、甲冑を着用した状態での組み討ち、すなわち「甲冑柔術」や「組討」が主体であった 8 。これは、刀や槍が折れたり手放したりした際の最終的な戦闘手段であり、相手を地面に倒し、鎧の隙間から短刀でとどめを刺すことを目的とした、極めて実戦的な技術であった。
一方で、「柔術」という名称や、特定の流祖と理論を持つ体系化された流派が登場するのは、戦乱が収束に向かう戦国時代末期から江戸時代初期にかけてである。史料でその存在を確認できる最古の柔術流派は、天文元年(1532年)に竹内久盛が創始した竹内流(小具足腰廻)とされている 5 。
大東流の技術体系、特にその中心をなす精緻な関節技や「合気」による崩しは、素肌(平服)を前提としたものが多く、戦乱が収まった江戸時代以降に発展した柔術の様相を色濃く呈している 6 。鉄の籠手で覆われた相手の手首に、現代の大東流のような繊細な技をかけることは極めて困難である。この技術史的な観点から見れば、大東流の洗練された技法は、戦国期の甲冑組討術と直接的な連続性を見出すことは難しく、むしろ平和な江戸時代を背景として発展したと考える方が自然である 6 。したがって、伝承における戦国時代への言及は、技術的な系譜を示すものではなく、流派のアイデンティティを形成するための**「時代的権威付け」**、すなわち「我々は戦国武士の精神を受け継ぐ実戦武術である」という宣言として解釈するのが妥当であろう。
第二章:「御式内」の謎―会津藩史料の沈黙
伝承の根幹をなす会津藩の秘伝武術「御式内」であるが、その存在は歴史学的に極めて疑わしいものとされている。会津藩が編纂した公式の記録や、藩の歴史を記した『新編会津風土記』などを精査しても、「大東流」あるいは「御式内」という名称の武術が藩で教えられていたという記録は一切発見されていない 11 。会津藩で公式に稽古されていた柔術流派としては、神道精武流、神妙流、稲上心妙流などの名が記録されているが、そこに大東流の名はない 13 。
この史料上の不在を受け、近年の研究では、「御式内」という名称自体が後世の創作である可能性が強く指摘されている。具体的には、会津藩の職制における最上位の家格を示す「御敷居内(おしきいない)」という言葉から着想を得て、武田惣角が自らの武術に権威を与えるために引用したのではないか、という説が有力視されている 11 。
では、惣角の武術の源流はどこにあったのか。郷土史家・池月映らの研究によれば、より現実的な伝承経路が浮かび上がっている。それは、戊辰戦争後、惣角の家に同居していた元会津藩御供番(藩主護衛役)の佐藤金右衛門が伝える柔術であったという説である 11 。この個人的な伝承を、藩の公式な秘伝「御式内」という壮大な物語に「上書き」することで、明治という新時代にふさわしい権威を創造したと考えられる。つまり、「御式内」の史料上の不在は、それが秘伝であった証拠ではなく、そもそも藩の公式武術としては存在しなかったことの証左であり、大東流の成立史における**「ミッシング・リンク」
は、歴史の闇に埋もれた秘伝ではなく、明治期に個人の武術家が自らの技術を権威付けるために 「創造した空白」**であったと解釈できるのである。
第三章:歴史の転換点―武田惣角という存在
大東流の歴史を語る上で、武田惣角(1859-1943)という人物の存在は決定的に重要である。伝承では、彼はあくまで古流を復興させた「中興の祖」と位置づけられている 3 。しかし、近年の武術史研究においては、彼こそが会津に伝わっていた柔術や、全国を武者修行する中で体得した多流派の武術を統合・体系化し、「大東流合気柔術」として完成させた**「実質的創始者」**と見なす見方が支配的となっている 9 。
伝承において惣角の師とされる元会津藩家老・西郷頼母(保科近悳)の役割も、再検討が必要である。西郷が惣角に技術を伝授したという直接的な証拠は乏しく、むしろ、会津藩の権威を象徴する西郷が、惣角が創始した流派に歴史的な「お墨付き」を与える後援者としての役割を果たしたと考えるのが自然である 9 。
また、「大東流柔術」が「大東流合気柔術」と改称されたのは大正11年(1922年)であり、比較的近代のことである 4 。「合気」という概念には、惣角が修行したとされる修験道の気合術や、近代的な精神性、身体観が導入された可能性が指摘されている 17 。
惣角という人物を理解するためには、伝承によって描かれた姿と、戸籍や郷土史料などの客観的記録から浮かび上がる姿を比較することが不可欠である。両者の間には、無視できない大きな隔たりが存在する。
表1:武田惣角に関する伝承と歴史研究の比較
|
項目 |
伝承における記述 (主に大東流内部の伝承に基づく) |
近年の歴史研究による指摘 (戸籍、郷土史料等に基づく) |
典拠 |
|
出自 |
会津藩士・武田惣吉の次男 |
農民(足軽分)の竹田惣吉の子。明治5年に武田姓となる |
15 |
|
父の武術 |
剣術、棒術、槍術、相撲、大東流を父から学ぶ |
宮相撲の力士。戊辰戦争では大砲の運搬係。武術指導の記録は不明確 |
3 |
|
剣術の師 |
渋谷東馬より小野派一刀流を学ぶ |
渋谷東馬は明治維新後、新政府の監視下で剣術を教えていない可能性が高い |
3 |
|
柔術の師 |
会津藩家老・西郷頼母(保科近悳)より御式内を学ぶ |
西郷頼母の日誌に惣角の名はない。同居人の佐藤金右衛門から学んだ説が有力 |
3 |
|
流派の創始 |
古来の流派を復興させた「中興の祖」 |
諸流を統合し、西郷頼母の後援を得て創始した「実質的創始者」 |
3 |
この表が示すように、「会津藩士の子」と「農民の子」とでは、明治社会における出発点が全く異なる。この大きなギャップを埋め、自らの武術に絶対的な権威を与えるために、第一部で述べたような清和源氏から続く壮大な歴史物語が戦略的に構築されたと考えられる。武田惣角は、卓越した武術家であると同時に、自らの技術を価値あるものとして世に広めるための物語を創造した、非凡なプロデューサーでもあったのである。
第三部:実在する「書」―近代に記録された大東流
この第三部では、観念的な「無形の書」から離れ、現実に存在する物理的な「書」、すなわち巻物、記録、写真集などを分析する。これら近代の産物こそが、「大東流柔術書」の具体的な実体であり、その歴史と技術を今日に伝える貴重な史料である。
第一章:武田惣角が発行した伝書と記録
「大東流柔術書」という物質的な書物を探求する上で、歴史の出発点となるのは、武田惣角自身が発行した伝書(巻物)である。江戸時代以前に遡る「大東流」の伝書は一切発見されておらず、現存が確認されている最古のものは、明治32年(1899年)以降に惣角が門弟に授与したものである 18 。
これらの伝書、例えば「秘伝目録」や「教授代理」の免状には、技術の箇条書きと共に、第一部で詳述した「新羅三郎義光→甲斐武田家→会津藩御式内」という壮大な歴史が系譜として記されていた。これにより、それまで口伝であったかもしれない物語が、権威ある文字として固定化され、門弟へと受け継がれていった。惣角が作成した伝書は、単なる技術の目録ではなかった。それは、彼が構築した**「歴史物語」を権威ある文書として保証する証書**であり、門弟は技と共にこの物語を受け継ぐことで、自らが壮大な歴史の一部であるという自覚を持つことができたのである。
さらに惣角は、門弟の名前と身分を記録した「英名録」と、教授料を記録した「謝礼録」を几帳面に残した 16 。これらの記録は、彼の活動が日本全国に及び、その門弟には陸海軍の将校、警察官、裁判官、そして後の合気道開祖となる植芝盛平といった、近代日本のエリート層が多数含まれていたことを具体的に示している 2 。これらは、大東流の近代史を実証的に研究する上で不可欠な第一級の史料であり、観念的ではない、社会に根差した活動の実体を記録した「書」と言える。
第二章:久琢磨と『総伝』―技法の視覚的百科事典
「大東流柔術書」という問いに対する、もう一つの、そして最も具体的な答えが、久琢磨(ひさ たくま)によって編纂された写真伝書『総伝』である。久は大阪朝日新聞社の社員であり、社内で植芝盛平と武田惣角の両名から大東流を学ぶという稀有な機会に恵まれた 16 。彼は、習った技を忘れないように、また後世に正確に伝えるために、同僚の協力を得て稽古の様子を連続写真で撮影し続けた 10 。
この膨大な写真群を整理・編纂したのが、全11巻からなる『総伝』である 10 。その内容は、植芝盛平が教えた技と、後に教授を引き継いだ武田惣角が教えた技の両方が収録されており、基本技から秘伝奥義、さらには女性向けの護身術に至るまで、500以上の技が網羅されている 10 。これは、大東流の技術体系を網羅的に知ることができる、まさに**「技法の視覚的百科事典」**と呼ぶべき「書」である。
『総伝』の成立は、大東流の歴史における一つの転換点を示す。口伝や一子相伝といった前近代的な伝承形態が重視された世界に、写真という近代技術が導入され、秘伝とされた技が客観的な記録として定着したのである。武田惣角が発行した巻物が、流派の権威を保証する「物語の書」であるとすれば、久琢磨が遺した『総伝』は、その技術の具体的な内容を証明する「技術の書」と言える。この二つの「書」が揃ったことで、「大東流柔術」という概念は、その神話的側面と技術的側面の両方において、近代的な形で完成したのである。
結論:戦国時代の視座から見た「大東流柔術書」の再解釈
本報告書における徹底的な調査の結果、以下の結論に至る。
第一に、「大東流柔術書」という、戦国時代に成立し、連綿と受け継がれてきた単一の物理的な書物は、歴史学的にはその存在を確認できない。伝承の舞台となる戦国時代の武術の実態や、会津藩の公式記録は、むしろその存在を否定する方向に作用する。
第二に、しかし「大東流柔術書」は別の形で、しかし明確に存在する。それは、明治という激動の時代に、武田惣角という非凡な武術家が、自らの卓越した技術体系に歴史的権威と物語性を与えるために構築した、**「歴史的物語(ナラティブ)と技術体系の複合体」**である。その「書」は、惣角が発行した伝書によって文字として記され、久琢磨の『総伝』によって技法として視覚化されることで、近代においてその実体を確立した。
第三に、利用者様の問いの核心である戦国時代との関係性は、史実としての直接的な系譜ではなく、流派の権威と精神的支柱を形成するための**「創られた伝統」**として、極めて重要な役割を果たした。それは、武士道への回帰が叫ばれた近代日本において、大東流が持つべき「武威」と「正統性」を象徴する、不可欠な物語であった。大東流の技の内に、戦国以来の古流武術、特に剣術の理合が昇華されている可能性は否定できないが 21 、その歴史物語そのものは、近代に書かれた壮大な「書」なのである。
したがって、「大東流柔術書」を戦国時代の視点から調査するということは、失われた古文書を探す考古学的な作業ではない。それは、近代日本人が「戦国」という時代にいかなる理想と武の魂を見出し、それを自らの武術の根源として位置づけようとしたのか、その精神史的営為を解き明かす作業に他ならない。
引用文献
- 『信長の野望蒼天録』家宝一覧-書物- http://hima.que.ne.jp/souten/shomotsu.html
- 大東流光道について https://aiki.akasaka1chome.com/%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E6%B5%81%E5%85%89%E9%81%93%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-2/
- 今からおよそ900年前に清和天皇の末孫である新羅三郎源義光が、代々清和源氏に伝承されていた武術を元に、これにさらなる研究工夫をこらして集大成したものであると伝えられています。義光は、討ち殺した賊兵の屍体を解剖研究してその骨格の組立を調べ - 大東流合気柔術幸心会 https://koshinkai.tokyo/daito-ryu/
- 副査/万/~i+!‑ - 順天堂大学 https://www.juntendo.ac.jp/assets/2012-M-728.pdf
- 大東流合気柔術の起源の謎 - 合気道ブログ|稽古日記 - Seesaa http://aikidoblog777.seesaa.net/article/313612978.html
- 大東流の歴史観には問題があり! https://www.daitouryu.com/japanese/wh_daitouryu/hist.html
- 大東流の歴史と山本角義の継承|会津伝合気柔術の正統 - (一社)氣と丹田の合氣道会 楽心館 https://aiki.jp/daitoryu/
- 柔術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113207/
- 柔術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E8%A1%93
- 総伝:大東流合気柔術の秘書 - 横浜合気道場 - Yokohama AikiDojo https://www.yokohamaaikidojo.com/ja/articles-jp/93-soden-the-secret-technical-manual-of-daito-ryu-aiki-jujutsu
- 御式内 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%BC%8F%E5%86%85
- 投技 山嵐に関する研究 https://shobi-u.repo.nii.ac.jp/record/628/files/%E2%91%A4%E8%97%AA%E5%B4%8E%E8%81%A1.pdf
- 会津藩の武術流派 - FC2WEB http://baragaki.fc2web.com/jitenbujyutu.htm
- 「合気道・合気武術」の達人・名人・秘伝の師範たち https://webhiden.jp/mastercat/aiki/
- 武田惣角 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E6%83%A3%E8%A7%92
- 大東流合気柔術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E6%B5%81%E5%90%88%E6%B0%97%E6%9F%94%E8%A1%93
- 合気 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E6%B0%97
- 大東流伝承の謎1|juzen - note https://note.com/juzen/n/n4f8a273070c0
- 大東流中興の祖 武 田 惣 角 | 合気道史探究 - どう出版 https://www.dou-shuppan.com/aikido_w/ts/
- 武田惣角先生直伝 大東流合氣柔術總傳のことⅡ|juzen - note https://note.com/juzen/n/nb7c9dae416fd
- 大東流合気柔術の系譜と会津剣術の歴史|武田惣角から現代の継承者へ - 楽心館 https://aiki.jp/daitoryu/history/
- 小野派一刀流(会津伝系)の歴史と特徴|武田惣角・山本角義による剣術伝承 https://aiki.jp/daitoryu/onohaittouryukenjyutsu/