射法訓
『射法訓』は、吉見順正が通し矢の極限実践から得た弓術の教え。戦国武士のリアリズムから江戸武士道の精神へ、武士道の変容を象徴。身体と心の運用を説く。
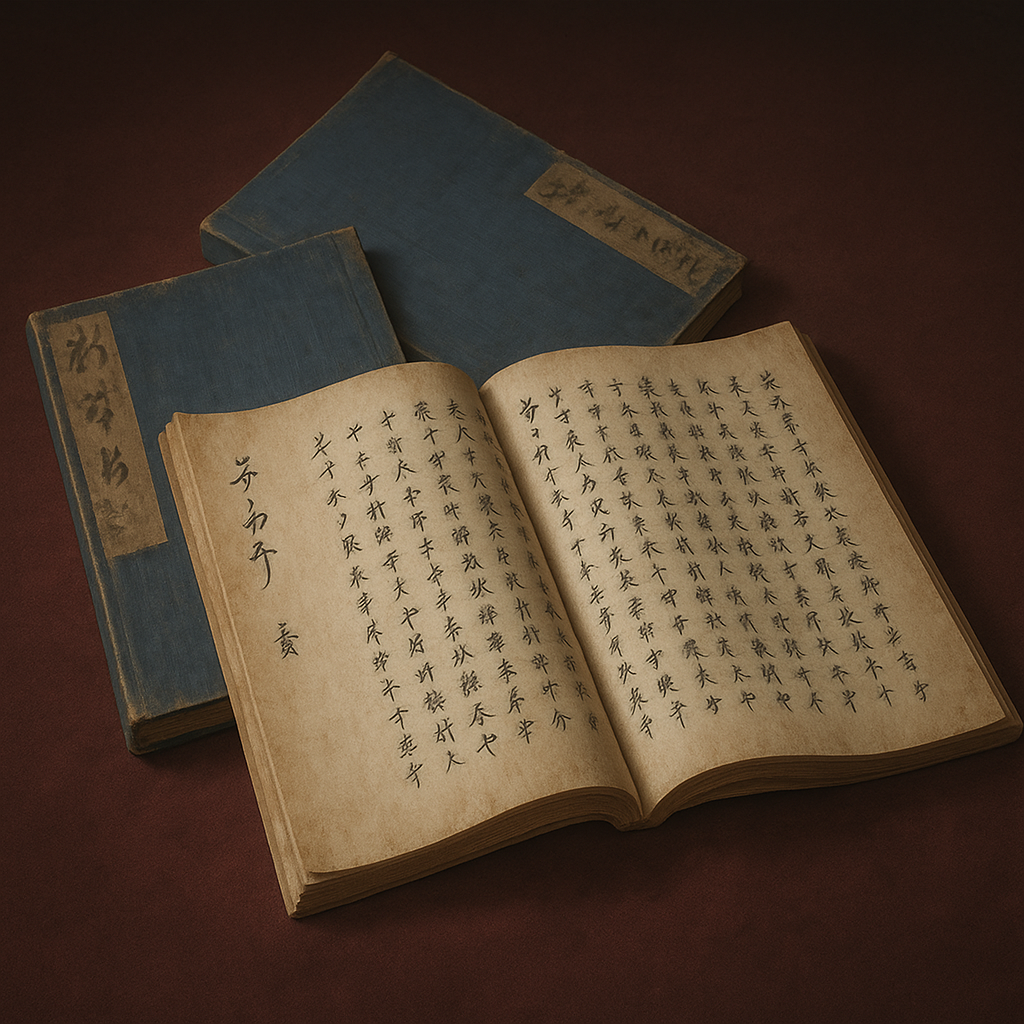
『射法訓』の総合的研究 ― 戦国武士の魂から江戸武士道の精神へ
序論:『射法訓』への誘い
『射法訓』全文の提示と現代における位置づけ
現代日本の弓道において、その精神的支柱として最も広く知られ、多くの道場に掲げられているテキストがある。それが『射法訓』である。一般に知られる本文は、以下の通りである。
射法は、 弓を射ずして骨を射ること最も肝要なり。
心を総体の中央に置き、 而して弓手三分の二弦を推し、 妻手三分の一弓を引き、 而して心を納む是れ和合なり。
然る後胸の中筋に従い、 宜しく左右に分かるる如くこれを離つべし。
書に曰く 鉄石相剋して火の出ずる事急なり。
即ち金体白色西半月の位なり。 1
この簡潔かつ深遠な言葉で綴られた教えは、弓を引く上での技術的な要諦と、それに伴うべき心構えの双方を説いている。しかし、この広く流布している本文が全てではない。研究によれば、この核心部分に至る前文が存在し、それを含めて初めて全文となるとも言われている 5 。また、その出典や正確な全文については、未だ議論の余地が残されており、このテキスト自体が歴史の中で形成され、解釈されてきたものであることを物語っている 3 。
現代において『射法訓』が持つ権威の源泉は、公益財団法人全日本弓道連盟が公式の教えとして『弓道教本』に採録したことにある 3 。これにより、特定の流派の伝書であったものが、日本の弓道全体を貫く普遍的な理念として位置づけられることとなった。
著者・吉見順正と紀州竹林流の概要
『射法訓』の作者とされるのは、吉見順正(よしみ じゅんせい)、本名を吉見台右衛門経武(よしみ だいえもん つねたけ)という人物である 7 。彼は、江戸時代前期の紀州藩士であり、弓術の一大流派である日置流竹林派、その中でも特に紀州藩で栄えた「紀州竹林流」の中興の祖と仰がれる達人であった 9 。
特筆すべきは、彼が単なる思想家や理論家ではなかったという点である。吉見順正は、京都三十三間堂(蓮華王院本堂)の軒下約120メートルを射通す「通し矢(堂射)」において、明暦2年(1656年)に一昼夜で6,343本を射通し、「射越の誉」を得た当代随一の射手であった 7 。彼の言葉は、極限の実践の中から絞り出された、血の通ったものであった。
本報告書の中心課題:なぜ泰平の世に『射法訓』は生まれたのか ― 戦国時代の弓術との断絶と連続性
本報告書が探求する中心的な問いは、ここにある。『射法訓』が成立したのは、長きにわたる戦乱が終わり、幕藩体制が安定期に入った江戸時代前期である。武士の役割が戦闘者から為政者へと移り変わり、弓矢が戦場の主要な武器としての役割を終えた泰平の世において、なぜこれほどまでに高度な精神性と、抽象的ながらも緻密な技術論が求められたのか。
この問いを解明するため、本報告書はご依頼の視座である「戦国時代」にまで遡る。戦場で敵を殺傷するための実用的な「武術」であった戦国時代の弓術と、『射法訓』に象徴される精神修養の「武道」としての江戸時代の弓術。その両者を比較分析することで、両者の間に横たわる深い断絶と、その底流で確かに受け継がれた連続性を明らかにしていく。それは、戦国武士の荒々しい魂が、いかにして江戸武士道の洗練された精神へと変容を遂げたのか、その壮大な歴史のドラマを『射法訓』という一つのテキストを通して読み解く試みである。
第一部:『射法訓』の源流 ― 戦闘技術から修養の道へ
『射法訓』という深遠な思想が生まれるためには、その土壌となる歴史的・思想的な大転換が必要であった。本章では、戦国時代のリアリズムに満ちた弓術から、江戸時代の精神性を重んじる武士道への変遷を辿り、そのダイナミズムの中に『射法訓』の源流を探る。
第一章:戦場の弓術 ― 戦国時代のリアリズム
日置流の勃興と実戦的射法(武射)
戦国時代の弓術を語る上で、日置流(へきりゅう)の存在は欠かすことができない。室町時代中期(15世紀後半)に、大和の人とされる日置弾正正次(へきだんじょうまさつぐ)によって創始されたこの流派は、それまでの公家社会における儀礼的な騎射中心の弓術とは一線を画す、画期的なものであった 13 。その最大の特徴は、徒歩の武士(歩射)による集団戦闘を想定した、徹底的に実戦的な射法(武射)にあった 15 。
応仁の乱以降、合戦の主役が一部の特権的な武士による一騎討ちから、足軽など下級兵士による集団戦へと移行する中で、日置流の合理的な射法は時代の要請に合致した。弓兵を集団で訓練し、規格化された弓具を用いて効率的に矢の雨を降らせる戦術は、戦国大名の軍事戦略に不可欠な要素となり、日置流は瞬く間に武家弓術の主流としての地位を確立したのである 13 。
例えば、薩摩日置流に伝わる「腰矢指矢(こしやさしや)」という射法は、甲冑をまとった武者が、腰の矢筒から矢を素早く取り出しては矢継ぎ早に放ち、敵の突撃を制圧する。さらには、隊列を組んで交互に射撃しながら前進し、最後は弓を槍のように構えて敵陣に突入するという、極めて具体的な戦闘状況を想定した技術体系である 17 。ここには、内面的な自己探求の入り込む余地はなく、ただひたすらに敵を制圧し、生き残るためのリアリズムが貫かれている。
戦国武将の死生観:辞世の句に見る精神世界
常に死と隣り合わせに生きた戦国武将たちの精神世界は、彼らが死に際に遺した「辞世の句」に凝縮されている。そこには、泰平の世の武士道が追求したような、自己の人格完成といった内面的なテーマは希薄である。
天下統一を目前にしながら、夢半ばで世を去った豊臣秀吉は、「露と落ち 露と消えにし 我が身かな 浪速のことは 夢のまた夢」と詠んだ 18 。その栄華を極めた人生すら、儚い夢であったという無常観が色濃く漂う。主君を討った明智光秀は、「心知らぬ人は何とも言わば謂え 身をも惜しまじ名をも惜しまじ」と、己の行動の正当性への強い矜持と、世評を超越した覚悟を示した 19 。また、生涯を戦に明け暮れた上杉謙信の「極楽も 地獄も先は 有明の 月の心に 懸かる雲なし」という句には、自らの死後の行方すら意に介さない、一点の曇りもない恬淡とした心境が表れている 20 。
これらの句に共通するのは、彼らの精神が、目前の戦いに勝利し、家名を後世に残し、自らの行動を歴史の中でどう位置づけるかという、極めて現実的かつ外向的な目標に集約されていたという事実である。その関心は、個人の内面的な救済や哲学的探求ではなく、あくまで家や主君といった外部の共同体への責任と、戦場での功名という即物的な価値に結びついていた。これは、『射法訓』が説く「心を総体の中央に置く」といった内省的な精神性とは、明らかに質を異にするものである。
機能美の追求:戦国時代の甲冑と武具に宿る精神性
戦国武士の精神性は、彼らが身にまとった甲冑にも色濃く反映されている。戦国時代の甲冑は、単に身を守るための防具ではなかった。それは、敵味方が入り乱れる戦場で自らの存在を誇示し、己の武威や信条、美意識を表現するための、極めて重要なメディアであった 21 。
兜に付けられた「前立(まえだて)」には、強さの象徴である獣の角、生命力を表す日輪、あるいは不死再生を願う月輪など、多様なモチーフが用いられ、武将たちはそのデザインに自らのアイデンティティを託した 24 。これらの装飾は、一見すると非実用的に見えるかもしれないが、その根底にあるのは、防御性能という実用性を極限まで追求した結果として生まれる「機能美」と、武将個人の精神性を象徴する装飾性が分かちがたく結びついた、戦国時代特有の美学である 25 。
ここから読み取れるのは、戦国武士にとって、実利(機能性)と精神(自己表現)が未だ分化していない、渾然一体となった世界観である。弓術が純粋な戦闘技術であり、死生観が即物的であり、甲冑が機能と自己顕示を兼ね備えていた。これらの事実は全て、戦国時代の武士の精神が、徹頭徹尾「外部」への働きかけ、すなわち敵を倒し、功名を立て、自己をアピールすることを主目的としていたことを示している。したがって、『射法訓』にみられるような、自己の内面へと深く沈潜していく思想の登場は、この戦国的リアリズムからの質的な大転換、すなわち歴史的なパラダイムシフトを意味するのである。
第二章:武士道の変容 ― 「術」から「道」への昇華
戦国の世が終わり、徳川幕府による泰平の時代が訪れると、武士のあり方は根底から変容を迫られた。この社会構造の変化こそが、『射法訓』のような精神性の高い武道思想が生まれる直接的な背景となった。
江戸初期における武芸の精神化
江戸時代前期、武士の主な役割は、戦場で敵を討つ「戦闘者」から、藩政を担う「行政官僚」へと大きくシフトした 21 。これにより、かつては殺傷の技術であった武芸は、その実用的な目的を失い、存在意義の危機に立たされた。この危機を乗り越えるために、武芸は新たな価値を見出す必要に迫られた。それが、技術の練磨を通じて自己の人格を陶冶し、人間性を高めるための修養法、すなわち「術」から「道」への昇華であった 27 。
この思想的転換を象徴するのが、柳生新陰流に伝わる「活人剣(かつじんけん)」の思想である。これは、剣を単に人を殺すための道具(殺人刀)と捉えるのではなく、天下の安寧を乱す悪を断ち、結果として万民を活かすための手段と位置づける考え方である 29 。剣聖・塚原卜伝が説いた「戦わずして勝つ」という境地や、平和思想としての「活人剣」もまた、この大きな潮流の中に位置づけられる 32 。武技の目的が、敵の殺傷という具体的な成果から、秩序の維持や自己の完成といった、より抽象的で内面的な目標へと昇華されていったのである。
沢庵宗彭『不動智神妙録』に見る「剣禅一致」
この「武道の精神化」という時代の潮流を、最も鮮やかに理論化した書物が、臨済宗の僧・沢庵宗彭(たくあん そうほう)が、将軍家剣術指南役であった柳生宗矩(やぎゅう むねのり)に与えたとされる『不動智神妙録(ふどうちしんみょうろく)』である 34 。
沢庵はこの書の中で、禅の思想を用いて剣術の極意を解き明かした。彼が説く「不動智」とは、心が石のように全く動かないことではなく、むしろ心が何物にも捉われず、自由自在に動く境地を指す 34 。相手の動きや自分の太刀筋、勝ち負けへのこだわりといった、あらゆるものに「心を止めない」こと。それが、いかなる状況にも滞りなく対応できる究極の心法であると説く。また、稽古を重ねることで、様々な技術や知識に捉われた不自由な状態から脱し、再び無心であった「初心」に還ることの重要性や、理論(理の修行)と実践(事の修行)が車の両輪のように不可分であることを強調している 34 。
注目すべきは、これらの教えが『射法訓』の精神性と深く共鳴している点である。「心を総体の中央に置く」という教えは、「心の置き所」を問う沢庵の議論と通底し、「左右に分かるる如くこれを離つべし」という自然な離れの思想は、作為を捨てて無心で対応すべしという不動智の教えと重なる。これは、『射法訓』が決して弓術という分野に閉じた孤立した思想ではなく、江戸時代前期の武芸家たちが共通して直面した「泰平の世における武芸の存在意義」という問いに対する、時代を代表する一つの答えであったことを示している。剣術における『不動智神妙録』と、弓術における『射法訓』は、同じ時代の精神が生み出した双子の思想と言うことができるだろう。
第三章:竹林派の成立と相克 ― 三十三間堂「通し矢」の時代
『射法訓』の簡潔で抽象的な言葉の裏には、常人の想像を絶する極めて過酷な実践の歴史が隠されている。それが、京都・三十三間堂を舞台に繰り広げられた「通し矢(堂射)」である。この競技の興隆こそが、『射法訓』を生み出す直接的な原動力となった。
日置流からの分派と竹林派の誕生
戦国時代を経て武家弓術の主流となった日置流は、江戸時代に入ると多くの分派を生み出した 13 。その中でも、石堂竹林坊如成(いしどうちくりんぼう じょせい)を祖とする竹林派は、特異な発展を遂げる 11 。如成は元々僧侶であったとされ、その教えは当初から精神的な側面を重視していた可能性が指摘されている 13 。この竹林派が、三十三間堂の通し矢と深く結びつき、その歴史を牽引していくことになるのである 13 。
竹林派は主に、尾張藩に伝わった「尾州竹林派」と、紀州藩に伝わった「紀州竹林派」の二大勢力に分かれて発展した 13 。そしてこの両藩が、藩の威信をかけて、通し矢の記録更新に鎬を削ることになる。
紀州藩と尾張藩の威信をかけた競争
三十三間堂の通し矢は、本堂の南端から北端まで、軒下の低い空間(高さ約5.5メートル、幅約2.5メートル)を、約120メートルの距離を射通すという、極めて難易度の高い競技であった 39 。特に江戸時代前期、徳川御三家としてのライバル意識が強かった紀州藩と尾張藩は、この通し矢を藩の威信を示す絶好の機会と捉え、熾烈な記録更新競争を繰り広げた 11 。
この競争は、単なる射手個人の技量を競うものではなかった。藩は最高の射手を選抜し、弓師、矢師、記録員、応援団に至るまで、専門家集団を組織して京都へ送り込んだ 41 。それはまさに、藩の総合力が問われる一大国家プロジェクトであり、勝者には「天下一」の称号と莫大な名誉が与えられた 12 。この極限状況は、より遠くへ、より正確に、そしてより多くの矢を射るための技術革新を強烈に促進した。射法そのものの研究はもちろんのこと、長時間の射に耐えうる強靭な弓や、指を保護しつつ鋭い離れを可能にする「ゆがけ(弽)」など、弓具の飛躍的な改良もこの時期に進んだのである 7 。
この競争の激しさは、残された記録からも明らかである。
【表1】三十三間堂通し矢 主要記録一覧(尾州対紀州)
|
年代 (西暦) |
射手名 |
所属藩 |
総矢数 |
通し矢数 |
備考 |
|
寛文2年 (1662) |
星野勘左衛門茂則 |
尾州 |
10,025本 |
6,666本 |
天下一となる 42 |
|
寛文8年 (1668) |
葛西園右衛門 |
紀州 |
- |
7,077本 |
星野の記録を破り天下一となる 42 |
|
寛文9年 (1669) |
星野勘左衛門茂則 |
尾州 |
10,542本 |
8,000本 |
再び天下一に。前人未到の8,000本を達成 11 |
|
貞享3年 (1686) |
和佐大八郎範遠 |
紀州 |
13,053本 |
8,133本 |
18歳で不滅の大記録を樹立 11 |
この表が示すのは、常軌を逸したパフォーマンスへの渇望である。一昼夜で1万本を超える矢を放ち、その6割以上を的に通すという行為は、単なる技術の練磨だけでは到達できない。強靭な体力、揺るぎない精神力、そしてそれらを支える合理的な身体運用法が不可欠であった。
ここに、『射法訓』を読み解く重要な鍵がある。吉見順正自身もこの過酷な競争の当事者であり、天下一の栄誉を手にした名手であった 7 。彼が遺した『射法訓』の簡潔で抽象的な言葉群は、決して単なる精神論や観念的な教えではない。それは、この通し矢という極限の実践の中から生まれ、一昼夜にわたる極度の疲労とプレッシャーの中でも安定した射を維持し、弓具の性能を最大限に引き出すための、極めて実践的なノウハウが凝縮された「身体と心の運用マニュアル」の要諦であった。現代の言葉で言えば、トップアスリートのために編まれた、バイオメカニクスとスポーツ心理学を統合した究極の指南書に他ならなかったのである。
第二部:『射法訓』の深層解析 ― 技と心の探求
『射法訓』の真価を理解するためには、その言葉が生まれた歴史的背景と同時に、テキストそのものと、その著者である吉見順正という人物の実像に深く分け入る必要がある。本章では、『射法訓』の本文を逐語的に解釈し、その背後にある思想の核心に迫る。
第一章:著者・吉見順正の実像
『射法訓』の言葉に重みを与えているのは、著者である吉見順正が、理論と実践、そして技術開発を一身で体現した稀有な人物であったという事実である。
紀州藩士としての経歴と通し矢の業績
吉見順正、本名・吉見台右衛門経武は、紀州徳川家に仕える武士であった 9 。彼は当初、ライバル藩である尾張の竹林派の名手、尾林与次右衛門(瓦林与次右衛門成直とも)に師事して弓を学んだとされる 7 。この事実は、当時の流派間の交流が決して閉鎖的なものではなく、優れた技術を求めて藩の垣根を越えた学習が行われていたことを示している。やがて彼は紀州に戻り、尾州で学んだ技術を基盤に、紀州竹林流を大成させ、その中興の祖と称されるに至った 10 。
彼の名を不動のものとしたのが、前述の三十三間堂通し矢における偉業である。明暦2年(1656年)、彼は総矢数9,343本のうち6,343本を射通し、「射越の誉」という最高の栄誉を手にした 7 。さらに重要なのは、彼が後に8,133本という不滅の金字塔を打ち立てる和佐大八郎(わさ だいはちろう)の師であったという事実である 10 。順正の教え、すなわち『射法訓』に凝縮された思想と技術が、弓術史上最高のパフォーマンスを生み出す直接的な土台となったのである。
弓具への工夫:「ゆがけ」の改良に見る探究心
順正が単なる弓の名手や指導者にとどまらなかったことを示す、興味深い逸話が残されている。それは、彼が「ゆがけの拇指の皮の中に角(つの)を入れる事を工夫した」という記録である 7 。
「ゆがけ(弽)」とは、弦を引く右手にはめる鹿革製の手袋であり、特に弦を引っ掛ける親指部分(帽子)の構造は、離れの鋭さや指の保護に直結する、弓具の中でも極めて重要なパーツである。通し矢のように一昼夜で数千、数万の矢を射る状況では、親指にかかる負担は想像を絶する。その中で、安定して弦を保持し、かつ鋭い離れを維持し続けるためには、ゆがけの構造が決定的に重要となる。順正が考案したとされる、親指の内部に角製の芯を入れるという工夫は、帽子の剛性を高め、指を保護すると同時に、弦のかかりを安定させるための、極めて合理的かつ実践的な発明であった。
この事実は、順正が精神論だけに偏った思想家ではなく、物理的な道具の構造と機能にも深い洞察を持つ、科学的な探究心を備えた技術者・エンジニアであったことを雄弁に物語っている。彼の思想は、極限の実践(通し矢)から生まれ、具体的な理論(射法訓)として体系化され、そして物理的な技術開発(ゆがけの改良)となって結実した。この「実践」「理論」「技術」の三側面を統合した存在として吉見順正を捉えることこそ、『射法訓』を正しく理解するための第一歩なのである。
第二章:本文の逐語的解釈と哲理
吉見順正という人物の実像を踏まえた上で、『射法訓』の本文を一句ずつ詳細に読み解いていく。そこには、通し矢という極限の実践に裏打ちされた、具体的かつ深遠な身体哲学が秘められている。
「射法は、弓を射ずして骨を射ること最も肝要なり」
冒頭に掲げられたこの一句は、『射法訓』全体の根本原理を宣言するものである。これは、弓矢という道具の操作や、表面的な筋肉の力に意識を奪われるのではなく、射手の身体そのもの、特に「筋骨」、すなわち骨格構造の正しい働きによって射を行うべきであるという教えである 4 。
「骨で射る」とは、具体的には、腕や肩といった末端の筋肉の力みに頼るのではなく、足元から大地に根を張り、体幹(胴体)で生み出した力を、骨格の連動を通じて効率的に弓へと伝える身体操作法を指す 46 。肩甲骨や背骨を意識し、関節に無理な負担をかけずに力を伝達することで、長時間の射においても疲労を最小限に抑え、安定した射を維持することが可能となる。これはまさに、通し矢という過酷な競技の中から生まれた、極めて合理的なバイオメカニクスの知恵である 9 。
「心を総体の中央に置き」
次に説かれるのは、心のあり方である。「総体の中央」とは、へその下あたりに位置する「丹田(たんでん)」を指すのが一般的な解釈である 4 。これは、精神的な意識の集中点を、頭や胸ではなく、身体の重心であり、力の源とされる丹田に定めることで、心気の安定を図り、いかなる状況でも動揺しない精神状態(不動心)を作り出すことを意味する。この教えは、沢庵宗彭が『不動智神妙録』で説いた、心を特定の場所に固定せず、しかし身体の中心に据えるべきだという「心の置き所」の議論と深く通底している 35 。
「而して弓手三分の二弦を推し、妻手三分の一弓を引き、而して心を納む是れ和合なり」
この一節は、しばしば左手(弓手)と右手(妻手)の力の配分比率として解釈されるが、その本質はより深い。これは、単なる量的な比率ではなく、弓を押し開く弓手と、弦を引いて離れを司る妻手の、質的な役割の違いとその調和(和合)を説いたものである 4 。
竹林派の伝書には、「剛は父 繋は母なり 矢は子なり 片思ひして子は育つまじ」という歌がある 7 。ここで言う「剛」すなわち弓手は、骨格を支え、力強く押し広げる父性的な役割を担う。一方、「繋(かけ)」すなわち妻手は、繊細に弦を保持し、生命(矢)を産み出す母性的な役割を担う。この父性と母性が、どちらか一方に偏ることなく、調和し、協力し合うことで、初めて立派な子供、すなわち鋭く正しい矢が育まれる。この陰陽思想にも通じる比喩は、
2/3と1/3という数字が、単なる物理的な力の配分ではなく、両手の役割の質的な違いと、その理想的なバランスを象徴的に表現したものであることを示唆している。この両手の調和の上に、丹田に定めた心が静かに納まることで、心・身・弓が一体となった理想的な状態「和合」が完成するのである。
「然る後胸の中筋に従い、宜しく左右に分かるる如くこれを離つべし」
「離れ」は、弓術において最も難しく、また最も重要な瞬間である。この句は、その理想の離れが、指先で弦を「放す」という意識的な小手先の操作であってはならないと説く 7 。そうではなく、十分に引き収め、左右均等に張り合った力(伸合い)が極まった結果として、胸の中心(中筋)から左右の肘が自然に、あたかも観音開きのように開いていく伸張運動の結果として、無意識的・偶発的に生じるべきものであることを示している。これは、竹林派に伝わる「雨露離(うろの離れ)」、すなわち里芋の葉に溜まった露が、その重みに耐えかねて自然に滑り落ちる様に例えられる、一切の作為のない自然な離れの境地を表現したものである 7 。
「書に曰く鉄石相剋して火の出ずる事急なり」
ここで言う「書」とは、特定の経典ではなく、竹林派に代々伝わる伝書、例えば「四巻の書」などを指すと考えられている 8 。この句は、理想の離れの鋭さと迅疾さを、鮮烈な比喩で表現したものである。十分に満ちた心身の力(詰め合い・伸合い)が最高潮に達した時、あたかも火打石と火打金が激しく打ち合わされて、瞬時に火花が散るように、鋭く、力強く、かつ自然に「離れ」が生じる。その爆発的なエネルギーの解放の様を「急なり」と表現しているのである 7 。
「即ち金体白色、西半月の位なり」
『射法訓』の結びとなるこの一句は、最も難解であり、その思想的背景を色濃く反映している。これは、離れの後に訪れる「残心(残身)」、すなわち矢を放った後の心身の状態の理想形を、密教的な宇宙観、特に五行思想を用いて表現したものである 4 。
「金体」の「金」は五行における「金」であり、季節では「秋」、方位では「西」、色では「白」に対応する。それは、万物が成熟し、引き締まり、研ぎ澄まされた静謐さと鋭気を象徴する。この句が描くのは、夜明け前の静寂の中、東の空に明けの明星(金星)が白く輝き、西の空には有明の半月が静かにかかっている、という荘厳で清澄な情景である。射によって心身の全てを解放し、到達した無心の境地、その静かで気高い射手の姿を、この宇宙的な情景に重ね合わせているのである 7 。
一部には、この天文現象の科学的な正確性を問う議論もあるが 49 、それは本質的な問題ではない。重要なのは、これが具体的な風景描写ではなく、射によって到達しうる最高の精神的境地(位)を、象徴的なイメージを用いて詩的に表現したものであるという点である。
第三章:『射法訓』と密教思想
『射法訓』の難解な結びの句が示唆するように、その思想的基盤には、禅宗以上に、真言宗に代表される密教思想、特に五大・五行思想が深く関わっている。
真言宗の五大思想と射法
吉見順正が活躍した紀州は、真言宗の総本山である高野山の膝元であり、その文化的・思想的影響が強かったことは想像に難くない。竹林派に伝わる「五輪砕き(ごりんくだき)」または「射法五身(しゃほうごみ)」と呼ばれる教えは、この密教思想との関連を明確に示している 48 。これは、宇宙を構成する五つの根本要素「五大」(地・水・火・風・空)に、射の各段階を対応させ、射行全体を一つの小宇宙の生成流転プロセスとして捉える思想である。
この思想によれば、射手の身体は小宇宙であり、その一連の動作は、大宇宙の法則と調和しなければならない。この身体宇宙観こそが、「骨で射る」という身体構造への着目や、「自然の離れ」といった作為を排した動きの追求の根底にある、哲学的基盤となっている。
【表2】射法と五大・五行思想の対応関係
この「五輪砕き」の思想を、射のプロセスと対応させると、以下のような関係が見えてくる。これは、『射法訓』の言葉を、その背後にある思想的枠組みを通して理解するための一助となる。
|
思想要素 |
色・方位・形状 |
射法段階 |
解釈・象徴的意味 |
|
地輪 (土体) |
黄色・中央・方形 |
弓構・胴造 |
大地のように不動の土台を築く段階。心身の安定。 |
|
水輪 (水体) |
黒色・北・円形 |
打起・引分 |
水が方円の器に従うように、隅々まで均等に力が満ちていく段階。円滑な力の移行。 |
|
火輪 (火体) |
赤色・南・三角形 |
会 |
火が燃え盛るように、エネルギーが最高潮に達し、満ち満ちた状態。力の充実。 |
|
風輪 (火体) |
赤色・南・三角形 |
離れ |
「鉄石相剋して火の出ずる事急なり」。鋭く、迅疾なエネルギーの解放。石火の離れ。 |
|
空輪 (金体) |
白色・西・半月形 |
残心 |
全てを解放した後の、静かで気高い無心の境地。「金体白色西半月の位」。 |
注:上記対応は諸説あり、流派の伝承によって解釈が異なる場合がある 48 。特に「離れ」を火輪、「残心」を金体(空輪)と見なす解釈が一般的である。
この表が示すように、『射法訓』は単なる技術論や精神論の断片的な集合ではない。それは、身体の動き(射法)と、精神の状態(心)、そして宇宙の法則(五大思想)とを一体のものとして捉える、壮大で包括的な「身体哲学」なのである。射手は自らの身体を通して宇宙の理を体現し、一射一射のうちに世界の生成と完成を経験する。この深遠な世界観こそ、『射法訓』が時代を超えて人々を魅了し続ける根源的な力と言えるだろう。
第三部:『射法訓』の現代的意義と影響
江戸時代前期に生まれた『射法訓』は、三百数十年以上の時を経て、現代の弓道界において中心的な教典としての地位を占めている。しかし、その権威化の過程と、特に西洋への伝播においては、本来の文脈から切り離された解釈や、ある種の誤解が生じたことも事実である。本章では、その現代的受容の光と影を検証する。
第一章:近代弓道における『射法訓』の権威化
全日本弓道連盟の成立と『弓道教本』
『射法訓』が今日の不動の地位を築く上で決定的な転機となったのは、第二次世界大戦後の弓道界の再編であった。大戦後、GHQ(連合国軍総司令部)による武道禁止令を経て、日本の武道は存続の危機に立たされた 6 。1949年、弓道界の再興と統一を目指して「日本弓道連盟」(後の公益財団法人全日本弓道連盟)が設立される 6 。
新連盟が直面した最大の課題は、江戸時代以来、多数の流派に分かれ、それぞれに異なっていた射法や礼法をいかにして統一するか、という点であった 52 。試合や昇段審査を全国規模で公平に行うためには、流派を超えた共通の基準が不可欠であった。この要請に応える形で、1953年(昭和28年)に『弓道教本 第一巻 射法篇』が発刊された 6 。
この初代『弓道教本』に、紀州竹林流の伝書であった『射法訓』が、弓道の根本理念を示すものとして採録されたのである。この瞬間、『射法訓』は一介の流派の教えから、全国数万の弓道家が学ぶべき「正典(カノン)」へと、その地位を大きく変えた。その背景には、教本編纂に携わった千葉胤次(ちば たねつぐ)ら連盟幹部の尽力があった 54 。
この権威化のプロセスを深く考察すると、一つの構造が見えてくる。『射法訓』の言葉は、具体的すぎる技術論を避け、抽象的で哲学的な比喩を多用している。この「解釈の余地」の大きさが、多様な流派の射手たちにとって、それぞれの流儀の教えと矛盾することなく受け入れやすいという、極めて好都合な特性を持っていた。結果として、『射法訓』は、その本来の歴史的文脈(紀州竹林派、通し矢、密教思想)からある程度切り離され、より普遍的で公的な「弓道の精神」を象徴するテキストとして聖典化されるに至った。その権威は、内容の普遍性もさることながら、戦後の弓道界再編という歴史的・組織的な要請によって「創出」された側面が強いのである。
現代弓道の理念「真・善・美」との接続
現代の全日本弓道連盟が掲げる弓道の最高目標は、「真・善・美」の三文字に集約される 56 。これは、単なる的中に留まらない、弓道が追求すべき理想の姿を示したものである。
- 真 (Shin) : 偽りのない正しい射を追求すること。正しく射られた矢は必ず的に中るという「正射必中」の理念 56 。
- 善 (Zen) : 常に平常心を保ち、他者を敬い、慈しむ心。礼節を重んじ、争わない精神 56 。
- 美 (Bi) : 「真」の正しい射法と、「善」の徳高い心が一体となった時に現れる、調和のとれた美しい射品・射格 56 。
この「真・善・美」という理念体系が確立される中で、『射法訓』は、この抽象的な目標を体現するための具体的な指針として解釈されるようになった。「真」の追求は「弓を射ずして骨を射る」という正しい身体運用に、「善」の心は「心を総体の中央に置く」という精神の安定に、そして「美」の境地は、全てが調和した結果として現れる「金体白色西半月の位」に、それぞれ対応すると考えられたのである。『射法訓』は、近代的な理念である「真・善・美」と結びつくことで、その権威をさらに強固なものとしたと言える。
第二章:西洋への伝播と誤解 ― ヘリゲル『弓と禅』をめぐって
『射法訓』が持つ精神性は、日本国内に留まらず、海を越えて西洋世界にも大きな影響を与えた。しかし、その伝播の過程では、文化的な翻訳の困難さから、重大な誤解もまた生まれた。その象徴が、ドイツ人哲学者オイゲン・ヘリゲル(Eugen Herrigel)の著作『弓と禅(Zen in the Art of Archery)』である。
『弓と禅』が形成した「弓道=禅」というイメージ
1924年から1929年にかけて日本に滞在したヘリゲルが、帰国後の1948年に出版した『弓と禅』は、自らの弓道体験を禅の修行のプロセスとして描いた書物であり、西洋において空前のベストセラーとなった 59 。この本を通じて、弓道は「動く禅」として広く知られるようになり、「Kyudo = Zen」というイメージが世界的に定着した 59 。多くの西洋人が、この本に触発されて弓道の門を叩いたことは事実であり、その功績は無視できない 59 。
しかし、この「弓道=禅」という図式は、多くの弓道史研究者から、その単純さと不正確さを厳しく批判されている 59 。ヘリゲルの著作は、弓道という日本の伝統文化の一側面を、西洋の哲学的関心というフィルターを通して再構築したものであり、必ずしもその全体像を正確に伝えているとは言えないのである。
著者ヘリゲルの師・阿波研造の思想と竹林派
ヘリゲルが師事した弓道家は、阿波研造(あわ けんぞう)という人物である 11 。阿波は日置流竹林派の流れを汲む射手であり、その点では『射法訓』の系譜に連なる。しかし、彼の思想は極めて独創的かつ特異なものであった。彼は自らの教えを「大射道教(だいしゃどうきょう)」と名付け、弓道を一種の宗教的・神秘主義的な行いとして説いた 61 。その教えは、当時の主流の弓道界からも、また正統な禅宗からも一線を画す、阿波個人の強烈なカリスマ性に支えられたものであった 59 。
ヘリゲルは、この阿波の特異な教えを、禅の修行経験がないまま、自らの哲学的関心に基づいて「禅」として理解しようとした。さらに、両者の間には通訳が存在し、その通訳がヘリゲルの理解を助けるために意図的に自由な翻訳(超訳)を行った可能性も指摘されている 59 。つまり、ヘリゲルが『弓と禅』で描いた世界は、①阿波研造という特異な射手の思想、②ヘリゲル自身の「禅」への哲学的バイアス、③通訳を介したコミュニケーションの不確実性、という三つの要素が複合的に絡み合って生まれた「神話」である可能性が高いのである。
『射法訓』の本来の思想と、西洋的解釈の乖離
このヘリゲル的な「弓道=禅」のイメージと、『射法訓』が生まれた本来の文脈との間には、埋めがたい乖離が存在する。
第一に、思想的背景の違いである。『射法訓』の背後にあるのは、禅宗よりもむしろ真言密教の宇宙観であることは、既に述べた通りである 8 。
第二に、実践の性格の違いである。『射法訓』が生まれた土壌は、三十三間堂の通し矢という、藩の威信を背負い、ライバルと記録を競い合う、極めてアスレティックで競争的な実践であった。そこには、超人的な記録を達成するという明確な目標と、それを実現するための強靭な意志、そして極度の緊張感が存在した。
これに対し、ヘリゲルが描く弓道は、的を狙うことすら否定され、自我を捨てて無心でいれば、あたかも「それ」が射させてくれるかのような、受動的で非競争的な神秘主義に彩られている 63 。この解釈は、『射法訓』の背景にある、命がけの競争心や、記録更新への渇望といった、武士道が持つ荒々しい側面を完全に捨象してしまっている。それは、西洋の知性が東洋の神秘に憧れて作り出した、ロマンティックだが歴史的実態とは異なる「オリエンタリズム」的幻想の一種であると、批判的に考察せざるを得ないのである。
結論:武士の魂の変容 ― 『射法訓』が現代に語りかけるもの
本報告書は、「日本の戦国時代」という視座から『射法訓』を徹底的に調査し、その歴史的、思想的、技術的背景を多角的に分析してきた。その探求の旅路の終わりに、我々はこの簡潔なテキストが持つ、時代を超えた重層的な意味を改めて確認することができる。
戦国時代の「死ぬための技術」から江戸時代の「生きるための道」へ
『射法訓』は、日本の武士の精神史における、一大転換点を象徴する記念碑的なテキストである。その根底には、戦国時代の弓術が持っていた即物的で外向的な性格から、江戸時代の内面的・求道的な武士道への、武士の魂の劇的な変容がある。
戦国時代の弓術は、徹頭徹尾、戦場で敵を殺し、自らが生き残るための「死ぬための技術」であった。その価値は、主君への忠誠や戦場での功名といった、外部の共同体によって測られるものであった。しかし、戦乱が終わり泰平の世が訪れると、武芸はその存在意義を問い直される。その中で生まれた『射法訓』は、弓を引くという行為を通じて、自己の内面と向き合い、心身を統御し、人格を磨き上げるという、「生きるための道」としての武道の誕生を高らかに宣言したのである。
身体、精神、技術の三位一体
『射法訓』が示す武士道の精髄は、身体、精神、技術の三要素が、分かちがたく結びついた「三位一体」の思想にある。
「弓を射ずして骨を射る」という教えは、骨格構造に基づいた合理的な身体運用法、すなわち高度な「身体知」を要求する。
「心を総体の中央に置く」という教えは、丹田への集中による不動の心、すなわち洗練された「精神統制術」を説く。
そして、「金体白色西半月の位」という結びの句は、射手の身体を小宇宙と見なし、その営みを大宇宙の法則と調和させようとする、密教的な「哲学的思惟」へと通じている。
これら三つの要素は、互いに独立して存在するのではなく、一つの射行の中に有機的に統合されている。『射法訓』は、この三位一体の追求こそが武道の核心であると、我々に示している。
時代を超えて継承されるべき文化遺産
『射法訓』は、単なる弓術の一流派の教えに留まるものではない。それは、極限状況下で心身をいかに制御し、最高のパフォーマンスを発揮するかという、人間にとって普遍的な問いに対する、日本の武士たちが三百数十年の時をかけて見出した一つの答えである。
その思想は、現代においても、スポーツや芸術、ビジネス、さらには我々の日々の生き方そのものにおいて、多くの示唆を与えてくれる。自己の内面を見つめ、身体の声に耳を澄まし、精神を研ぎ澄まして一つの目的に向かう。そのプロセスの中にこそ、真の成長と充足があることを、『射法訓』は静かに、しかし力強く語りかけている。歴史的誤解や神話のベールを取り払い、その本来の文脈の中で読み解くとき、『射法訓』は、我々が未来へと継承すべき、かけがえのない精神的・身体的文化遺産として、その真の輝きを放つのである。
引用文献
- 射法訓 射法は、 弓を射ずして骨を射ること最も肝要なり。 心を総体の中央に置き https://kyudo.ch/wp-content/uploads/2020/10/Shahokun-%E5%B0%84%E6%B3%95%E8%A8%93.pdf
- 1-29 射法訓全文の解説 http://www.syaho.com/mb.cgi?eid=350
- 射法訓の全文を探しています。 - 梶田稔のホームページ https://www.kajita-m.jp/syahokun.htm
- 射法訓の教えの要点について解説してください - 理論弓道 https://rkyudo-riron.com/category185/entry68
- 弓道を勉強しませんか?射法訓。 - note https://note.com/yuduru_910/n/n2b2846b4128c
- 全日本弓道連盟 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%BC%93%E9%81%93%E9%80%A3%E7%9B%9F
- 「射法訓解説」へ - 梶田稔のホームページ https://www.kajita-m.jp/0001matsui1shahokun.htm
- Deeper Understanding of the Shaho-Kun and Raiki-Shagi Part VI - Green Leaves Forest https://gaijinexplorer.wordpress.com/2018/01/09/deeper-understanding-of-the-shaho-kun-and-raiki-shagi-part-vi-latter-parts-of-the-shaho-kun/
- 石川県立武道館 館長の部屋::射法は弓を射ずして・・・ https://www.ishikawa-spc.jp/budokan/blog/index.php?e=39&PHPSESSID=222b75495ceb0efc0b8cb3f5d8521bb0
- 夏の巻 https://www.kajita-m.jp/0006matsui-natu.htm
- 本多流について 文:小林暉昌氏(S40卒 東京大学弓術部師範) https://www.kyujyutubu.com/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%B5%81%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
- #弓道002 射法訓|モリンゲン - note https://note.com/bb_28/n/n9d8c45bb385a
- 日置流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%BD%AE%E6%B5%81
- 日置流(ヘキリュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E7%BD%AE%E6%B5%81-129199
- 弓術とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47462/
- 弓術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%93%E8%A1%93
- 薩摩日置流腰矢弓矢 第四回世界弓道大会(名古屋2024) Koshiya Kumiyumi, Battlefield Archery Demonstration 4World Kyudo Taikai - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=wqeNebLkvp4
- 最期に思い出すのは敵? 家族? これまで? これから? 【辞世の句―戦国武将編】 - いい葬儀 https://www.e-sogi.com/guide/10068/
- 辞世の句に秘められた思いとは|【弁慶鮨】公式 - 太田市 http://www.ota-benkei.com/column_20.html
- 偉人の遺した言葉、"辞世の句"を紹介。その意味を紐解く - 家族葬のファミーユ【Coeurlien】 https://www.famille-kazokusou.com/magazine/manner/495
- 第2章 戦国時代から江戸時代へ ~錦絵や洒落本、歌舞伎から - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/3/2.html
- “本物の甲冑姿が現代に蘇る”戦国武将を正確な甲冑装束姿で再現 「武将彫刻シリーズ」 端午の節句にむけて4月より数量限定再販 | 株式会社謙信 - アットプレス https://www.atpress.ne.jp/news/305193
- 武将像について – ART OF WAR – 本物の戦国武将の甲冑姿 https://art-of-war.tokyo.jp/abusyozo/
- 甲冑の歴史と変遷 - 刀剣ワールド https://www.touken-hiroba.jp/blog/7308498-2/
- SENGOKU-SUMIE COLLECTION https://www.ameyoko.net/marukin/html/victorinox/html/137037_x.html
- 武士(サムライ)とは?|三人閑談 - 三田評論ONLINE https://www.mita-hyoron.keio.ac.jp/3-person-chat/202002-1.html
- 江戸時代の剣術稽古の変遷から学べる型に関する考え方 - note https://note.com/matsurugi/n/n1d64ba44dbd6
- 古武道と現代武道/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/kobudo/
- 江戸幕府と近世武芸 4章 https://www.nipponbudokan.or.jp/pdf/shinkoujigyou/202503/junior_shidou/budo_04.pdf
- 「つ」 塚原卜伝 鹿島新当流 - 鹿嶋市ホームページ https://city.kashima.ibaraki.jp/site/karuta/16036.html
- 【解説後編】不動智神妙録(ふどうちしんみょうろく)とは?沢庵が柳生宗矩の活人剣思想に与えた影響 - 2回まで無料合気道体験!合心館京都大阪 https://www.aishinkankyoto.jp/fudochi-shinmyoroku2/
- 剣聖や医聖の生き方 | かんながらの道 https://www.caguya.com/kannagara/?p=19888
- 無敗の剣聖 塚原卜伝|鹿嶋市 https://ibamemo.com/2017/05/06/bokuden/
- 【解説前編】不動智神妙録(ふどうちしんみょうろく)とは?沢庵が柳生宗矩に伝えた剣禅一致の極地 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/fudochi-shinmyoroku1/
- 不動智神妙録 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E6%99%BA%E7%A5%9E%E5%A6%99%E9%8C%B2
- 沢庵宗彭 - 不動智神妙録/太阿記/玲瓏集 - 筑摩書房 https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480511683/
- 不動智神妙録 - 株式会社新経営サービス https://www.skg.co.jp/bimonthly/1514/
- 禅滴 平成28年度 - -愛知学院大学 禅研究所- https://zenken.agu.ac.jp/zen/text/h28.html
- 通し矢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E3%81%97%E7%9F%A2
- 通し矢(大的大会・日程・着物袴姿・・・)三十三間堂見どころ - 京都ガイド - 京都ガイド https://kyototravel.info/tooshiya
- 三十三間堂の通し矢競技 - Budo World https://budo-world.taiiku.tsukuba.ac.jp/2016/03/02/%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%89%E9%96%93%E5%A0%82%E3%81%AE%E9%80%9A%E3%81%97%E7%9F%A2%E7%AB%B6%E6%8A%80/
- 3 竹林流正統系譜、名古屋市史人物列伝 - 射法.com http://www.syaho.com/sb.cgi?eid=251
- 三十三間堂の通し矢2025:タイムスケジュールとルール、アクセスを解説 | ページ 2 https://kyotokankoyagi.com/sanjusangendo-toshiya-jp/2
- 5 尾州竹林と紀州竹林の交流 - 射法.com http://www.syaho.com/sb.cgi?eid=253
- 射法訓 http://www.hidatakayama.ne.jp/yumihiki/syahokun.html
- 骨を射る | 弓道の曲がりくねった長い道 https://ameblo.jp/triplecroix/entry-12088219410.html
- 吉見順正射法訓の「骨を射る」の意味を正確に理解する - 理論弓道 https://rkyudo-riron.com/category396/entry55
- 弓道四方山話 > 巻の壱 「天の巻」 > 1-29 射法訓全文の解説 http://www.syaho.com/sb.cgi?eid=350
- 金体白色、西半月のくらい (投稿56件)[1~56] - EcoEcoMan http://ecoecoman.com/kyudo/bbs200906oth/2007091002133337.html
- 一語一得 / One Story, One Lesson|International Kyudo Federation 国際弓道連盟 https://www.ikyf.org/ichigoichie/003.html
- 概要|全日本弓道連盟について|公益財団法人 全日本弓道連盟 https://www.kyudo.jp/aboutus/overview.html
- 弓道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%93%E9%81%93
- #弓道006 弓道教本|モリンゲン - note https://note.com/bb_28/n/n0624c1632b4c
- #弓道008 千葉 胤次|モリンゲン - note https://note.com/bb_28/n/n58673ace6917
- 千葉胤次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E8%83%A4%E6%AC%A1
- 弓道の心|公益財団法人全日本弓道連盟 https://www.kyudo.jp/howto/
- 「弓道の背景にある日本文化」へ https://www.kajita-m.jp/0001matsui3nihon%20bunka.htm
- #弓道003 真善美|モリンゲン - note https://note.com/bb_28/n/ne2420f198572
- The Myth of Zen in the Art of Archery - thezensite http://www.thezensite.com/ZenEssays/CriticalZen/The_Myth_of_Zen_in_the_Art_of_Archery.pdf
- Zen in the Art of Archery by Eugen Herrigel - Goodreads https://www.goodreads.com/book/show/103758.Zen_in_the_Art_of_Archery
- Zen in the Art of Archery - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Zen_in_the_Art_of_Archery
- The Myth of Zen in the Art of Archery [Archive] - E-Budo.com https://www.e-budo.com/archive/index.php/t-5556.html
- Book review — Zen in the Art of Archery by Eugen Herrigel - Empty Mirror https://www.emptymirrorbooks.com/reviews/book-review-zen-in-the-art-of-archery-by-eugen-herrigel