愚子見記
『愚子見記』は、江戸初期の工匠・平政隆が著した建築技術書。天守創案者を丹羽長秀とする記述は、通説と異なるが、技術者コミュニティの「内なる歴史」を伝える。戦国の記憶を継承した証。
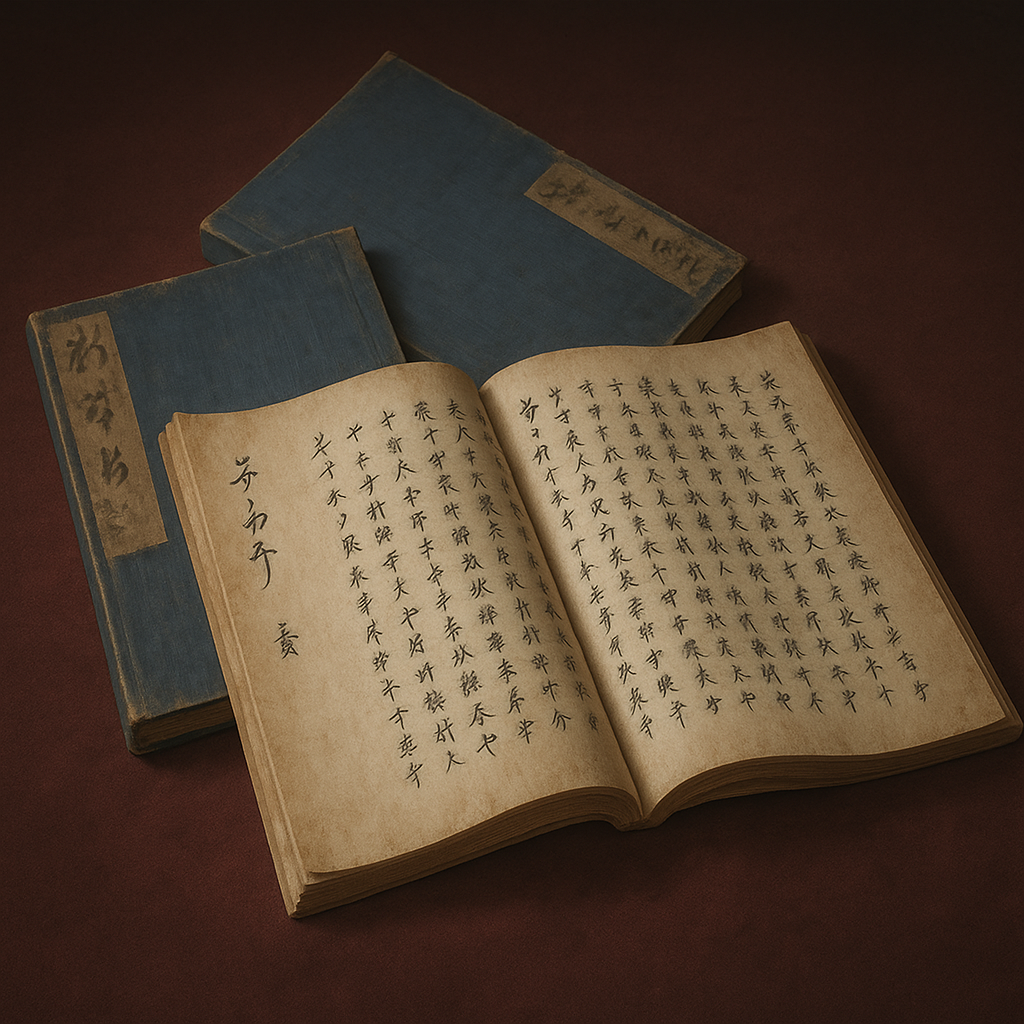
『愚子見記』の徹底分析報告書:戦国の記憶は江戸の工匠にいかに語り継がれたか
序論:江戸時代に記された戦国の記憶―『愚子見記』とは何か
『愚子見記(ぐしけんき)』は、江戸時代前期の天和三年(1683年)に、法隆寺お抱えの工匠であった平政隆(たいらのまさたか)によって著された全九冊から成る建築技術書である 1 。その名は、一流の工匠が自らを「愚かな子」と謙遜したことに由来すると考えられる 3 。本書は単なる建築の技法書に留まらず、その内容は吉凶、尺度、武具、調度品にまで及び、当時の工匠が持つべき知識体系を網羅した一種の百科全書的な性格を帯びている 1 。特に建築史の分野では、近世初期における内裏や諸社寺の建物の具体的な形状、寸法、建築費の積算、工事仕様などが詳細に記されており、他に類を見ない第一級の史料として研究者から高く評価されてきた 1 。
しかし、本書の価値は江戸時代の建築技術を伝える点だけに留まらない。泰平の世である江戸時代に成立したにもかかわらず、本書には戦国時代の事象、とりわけ「天守の創案者は丹羽長秀である」という、通説とは異なる注目すべき記述が含まれている 5 。この記述は、本書を単なる技術の記録としてではなく、歴史的記憶の継承という観点から分析する必要性を示唆する。
本報告書では、この「丹羽長秀創案者説」を分析の入り口とし、『愚子見記』が戦国という激動の時代の記憶、約一世紀の時を経て、専門技術者集団の中でいかに伝承され、意味づけられ、再構築されたかを示す「歴史的記憶の産物」として徹底的に解明することを目的とする。この分析を通じて、技術伝承の本質、すなわち知識や技能だけでなく、その職能集団が共有する歴史観や職業的アイデンティティまでもが、世代を超えて受け継がれていく様相を明らかにする。
第一部:『愚子見記』が提示する核心的言説―天守の創案者、丹羽長秀
第一章:記述内容の精査と解釈
『愚子見記』が城郭史研究において特異な位置を占める最大の理由は、その核心的な言説にある。本書は、近世城郭の象徴である天守について、通説を覆す見解を提示している。
『愚子見記』における記述
本書は、その本文中において明確に「天守の創案者は丹羽長秀である」と説いている 5 。この一文は、本書に収められた数多の技術的記述の中でひときわ異彩を放ち、長年にわたり研究者の関心を集めてきた。この「創案者」という言葉が、天守という建築形式の設計思想そのものを発明した人物を指すのか、あるいはそれまでになかった大規模な天守建築を初めて実現させた普請(工事)の最高責任者を指すのか、その解釈は分かれうる。しかし、いずれにせよ、天守の起源を織田信長や松永久秀に求める通説とは一線を画す、独自の歴史認識がここにはっきりと示されている。
言説の背景にある丹羽長秀の実像
では、なぜ平政隆は丹羽長秀を「創案者」として記憶したのであろうか。その背景には、丹羽長秀の歴史上の実績が深く関わっている。丹羽長秀は、織田信長の最も信頼する重臣の一人であり、柴田勝家、明智光秀、羽柴秀吉と並び称される織田家宿老の一角を占めていた。その誠実さと卓越した実務能力は信長から高く評価され、「米五郎左(よねごろうざ)」と称されたという逸話は有名である。これは、秀吉の「木綿藤吉」と対比され、米のように日常生活に欠かすことのできない、地味ながらも必須の存在であると認められていたことを示している 7 。
長秀の数ある功績の中でも、後世の工匠たちに最も強い印象を残したのが、天正四年(1576年)から始まった安土城の築城において「普請総奉行」という最高責任者を務めたことであった 8 。この前代未聞の巨大プロジェクトにおいて、長秀は信長の壮大な構想を実現すべく、全国から最高の技術を持つ石工や大工を組織し、膨大な資材を調達し、複雑な工程を管理した 11 。信長が「天守には金箔を施せ」「石垣は切れ目なく美しく積み上げよ」といった細部にわたる指示を出す中、長秀は現場の総指揮官として、あらゆる困難を乗り越え、ついに天下布武の象徴たる安土城を完成させたのである 11 。
この歴史的事実こそが、約一世紀の時を経て、大工たちの間で「天守創案者」という伝説を生み出す肥沃な土壌となったことは想像に難くない。現場の工匠たちにとって、主君である信長は究極の発注者ではあるが、直接的に技術的な指示を出し、現場の諸問題を解決し、彼らをまとめ上げたのは普請総奉行の丹羽長秀であった。工匠たちの視点から見れば、信長の壮大なビジョンを具体的な建築物へと昇華させた長秀こそが、尊敬と畏敬の念を抱くべき直接の指導者であり、自分たちの職能の偉大なる先達として語り継ぐにふさわしい人物であった。このため、安土城という画期的な建築物を実現させた「偉大な管理者」の記憶が、時を経てその建築物自体の「創造主」の記憶へと、いわば神話的に昇華したと考えられる。これは、特定の職能集団が自らの技術の淵源を、尊敬すべき歴史上の人物に求めるという、文化的な記憶の形成過程の一例と見なすことができる。したがって、『愚子見記』の記述は、アカデミズムが構築する歴史とは異なる、技術者コミュニティの内部から見た「もう一つの歴史」を反映していると言えよう。
第二部:比較史的アプローチによる「丹羽長秀創案者説」の検証
『愚子見記』が提示する丹羽長秀創案者説の歴史的意義を正しく評価するためには、これを孤立した言説としてではなく、天守の起源に関する他の学説との比較の中で位置づける必要がある。
第二章:通説における天守の起源と発展
現代の城郭史研究において、天守の起源は単一ではなく、複数の要素が複合的に発展した結果であると考えられている。
天守の萌芽期―信長以前
天守の直接的な起源については諸説あるが、古くは物見櫓として機能した「井楼(せいろう)」や、城の防御拠点であった大型の「大櫓(おおやぐら)」が徐々に高層化・大規模化し、城の象徴的建築物へと発展したとする説が有力である 12 。これらは当初、仮設的な性格が強かったが、戦国時代を通じて恒久的な建築物へと進化していった。
恒久的な高層建築物としての天守の先駆的な事例として特に重要視されるのが、戦国の梟雄・松永久秀が永禄年間(1558年~1569年)に築いた大和多聞山城や信貴山城である。特に多聞山城には四階建ての櫓があったことが同時代の記録『多聞院日記』から確認されており、これが単なる防御施設ではなく、権威の象徴としての高層建築の可能性を初めて示した例として挙げられることが多い 14 。
画期としての安土城天主
こうした萌芽的な動きがあった中で、現代我々がイメージするような、城主の権力を天下に誇示するための巨大で華麗な天守の直接的な起源は、織田信長が天正七年(1579年)に完成させた安土城の「天主」にあるというのが、学界における確固たる通説である 12 。
安土城の天主は、それまでの櫓とは一線を画す存在であった。地下1階、地上6階建て(一説には7階)の壮大な建築物であり、軍事的な司令塔であると同時に、信長自身の居住空間であり、重要な政治儀礼が執り行われる場でもあった 12 。その内部は狩野永徳ら当代一流の絵師による障壁画で彩られ、最上階は金色に輝いていたと伝えられる。これは、信長が自らの覇業を可視化し、天下に知らしめるための壮大な装置であった 12 。また、「てんしゅ」の呼称として、守護を意味する「守」ではなく、世界の主を意味する「主」の字を用いたことも画期的であり、その起源をキリスト教の「デウス(天主)」や仏教世界の中心である須弥山の主「帝釈天」に求める説も存在する 13 。
天守の展開―秀吉から家康へ
信長の死後、彼の後継者となった豊臣秀吉は、安土城天主のコンセプトをさらに推し進めた。秀吉が築いた大坂城や伏見城には、安土城を凌駕するほど絢爛豪華な天守が建てられ、その内部には黄金の茶室まで設けられたと記録されている 12 。秀吉の築城活動により、巨大な天守を築くことは全国の大名の間に広まり、天守建築は一つの流行となった。
江戸時代に入ると、徳川家康が江戸城や名古屋城に新たな天守を築き、天守建築は最後の輝きを見せる。しかし、徳川の治世が安定すると、軍事的な緊張は緩和され、天守の役割も変化した。そして慶長二十年(1615年)に発布された一国一城令や、その後の武家諸法度によって新たな城の建設や増改築が厳しく制限されると、天守建築の時代は事実上の終焉を迎えた 12 。
第三章:史料批判の視点から見た丹羽長秀説
通説的な天守の発展史の中に『愚子見記』の丹羽長秀説を置くとき、その特異性が際立つ。この説を歴史学的に評価するためには、厳密な史料批判が不可欠である。
一次史料との比較検討
安土城の築城に関する最も信頼性の高い同時代史料は、織田信長の家臣であった太田牛一が記した『信長公記』である。この史料には、丹羽長秀が「御普請の奉行」として築城を指揮したことが明記されているが、彼が天守を「創案」したとは一切記されていない。むしろ、城の構想から細部の意匠に至るまで、その建設を主導したのは信長自身であったことが、全体の文脈から強く示唆されている。
一方、『愚子見見記』の成立は、安土城の完成から約100年後の天和三年(1683年)である 1 。これは、著者の平政隆が安土城築城を直接見聞したわけではなく、伝聞や何らかの記録に基づいて記述したことを意味する。したがって、『愚子見記』のこの記述は、歴史的事実そのものを直接示す一次史料としてではなく、後世に成立した二次史料、あるいは専門家集団の内部で伝承された内容を書き留めたものとして扱うのが妥当である。
学術史における評価
日本の建築史、特に城郭史研究を牽引した建築史家・内藤昌氏は、『愚子見記』の学術的価値を高く評価し、1988年に井上書院から刊行された復刻版では校注を担当している 1 。内藤氏は本書を近世建築史研究における重要史料と位置づけているが、丹羽長秀創案者説に関しては、あくまで後世の工匠たちの間に生まれた伝承として捉え、天守の起源を信長に求める通説的な立場を崩していない(内藤氏の著作『城の日本史』などでの論調から推察される) 19 。
現代の城郭史研究においても、丹羽長秀説が通説を覆す新たな証拠として扱われることはない。「大工の間に伝わった興味深い伝承」として紹介されることはあっても、それが歴史的事実として受け入れられているわけではない。
このことから導き出されるのは、『愚子見記』は「歴史の教科書」として読むべき史料ではない、ということである。その記述の歴史的正確性を問うならば、丹羽長秀説は低い評価とならざるを得ない。しかし、この史料を単に「間違い」として切り捨てるのは、その本質を見誤ることになる。本書の真の価値は、歴史の事実を正確に伝えることにあるのではなく、「江戸時代前期のトップレベルの工匠が、自らの専門分野の起源をどのように認識し、語り継いでいたか」という、職能集団内部で形成・共有される「内なる歴史(Internal History)」の様相を極めて具体的に記録している点にある。その視点から見れば、丹羽長秀説は、歴史のもう一つの側面を照らし出す、極めて雄弁な史料となるのである。
表1:天守の起源に関する主要学説の比較
|
学説名 |
主な提唱者・典拠史料 |
概要・特徴 |
現代における評価 |
|
丹羽長秀 創案者説 |
平政隆『愚子見記』 5 |
安土城の普請総奉行であった丹羽長秀を天守の創案者とする。工匠の視点からの伝承。 |
異説。歴史的事実とは見なされないが、技術者集団の歴史認識を示す史料として価値がある。 |
|
織田信長 安土城起源説 |
内藤昌、西ヶ谷恭弘ら多数の研究者、『信長公記』など |
権力の象徴としての巨大天守は、織田信長が安土城で創造したとする。最も有力な通説 12 。 |
通説。多くの研究者に支持されており、考古学的・文献学的にも裏付けが強い。 |
|
松永久秀 多聞山城起源説 |
宮上茂隆ら、『多聞院日記』 15 |
安土城に先立ち、松永久秀が多聞山城に築いた四階櫓が、天守の直接的な先駆であるとする説 14 。 |
有力な説の一つ。安土城以前の天守の発展段階を考える上で重要視されている。 |
|
井楼・櫓 発達説 |
西ヶ谷恭弘ら 12 |
古代の楼観や中世の井楼・櫓といった軍事施設が、徐々に大規模化・恒久化して天守になったとする説。 |
天守の機能的・形態的な起源を説明する上で基本的な考え方として広く受け入れられている。 |
第三部:著者・平政隆と『愚子見記』の史料的文脈
『愚子見記』の記述、特に丹羽長秀説を深く理解するためには、著者である平政隆がどのような人物で、いかなる知識体系の中に生きていたのか、そして本書がどのような史料的文脈の中に位置づけられるのかを解き明かす必要がある。
表2:『愚子見記』成立と関連年表
|
年代(西暦) |
元号 |
出来事 |
関連性 |
|
1535年 |
天文4年 |
丹羽長秀、生まれる。 |
「創案者」とされる人物の活動開始。 |
|
1576年 |
天正4年 |
安土城の築城が開始される。丹羽長秀が普請総奉行に就任 9 。 |
丹羽長秀説の根源となる歴史的出来事。 |
|
1579年 |
天正7年 |
安土城天主が完成 14 。 |
天守建築史における画期。 |
|
1582年 |
天正10年 |
本能寺の変。織田信長死去。安土城焼失。 |
|
|
1585年 |
天正13年 |
丹羽長秀、死去。 |
|
|
1602年 |
慶長7年 |
『愚子見記』に大和郡山城天守が二条城に移築されたと記される年 20 。 |
本書の具体的な記述の一例。 |
|
1671年 |
寛文11年 |
平政隆、『愚子見記』の執筆を開始 21 。 |
執筆開始。安土城完成から約90年後。 |
|
1683年 |
天和3年 |
『愚子見記』の奥書が書かれる 1 。 |
本書の基準となる成立年。 |
|
1686年頃 |
貞享3年頃 |
平政隆、『愚子見記』の追記を終了したと推定される 21 。 |
執筆期間の終了。 |
第四章:著者・平政隆の知識体系
この年表が示すように、平政隆が生きた時代は、丹羽長秀が活躍した戦国末期から約一世紀も後のことである。この時間的な隔たりこそが、歴史的事実が「記憶」や「伝承」として変容する余地を生んだ。
平政隆(今奥政隆)の経歴
『愚子見記』の著者である平政隆は、本名を今奥政隆という 22 。彼は、日本最古の木造建築群を擁する法隆寺に所属する宮大工であった 1 。それと同時に、彼はより大きな組織の一員でもあった。それは、江戸幕府の作事方(建設部門)を統括した大工頭・中井大和守家の支配下にある工匠という立場である 4 。この事実は、平政隆が単なる一地方の寺大工ではなく、幕府の公儀作事を担う広範な技術者ネットワークの中に位置していたことを示唆しており、彼の知識の源泉を考える上で極めて重要である。
知識の二つの源泉
平政隆の知識体系は、大きく二つの源泉から成り立っていたと考えられる。
- 法隆寺の伝統 : 彼は、飛鳥時代から連綿と受け継がれてきた建築技術の殿堂である法隆寺の工匠として、寺に伝わる古文書や、師から弟子へと伝えられる口伝、そして修理などを通じて得られる実地の知見に精通していた。後世、「最後の宮大工」と称された西岡常一が、自身の技術と思想を語る中で『愚子見記』に言及していることからも、本書が法隆寺大工の正統な知識体系の一部をなしていたことが窺える 23 。
- 中井家のネットワーク : もう一つの源泉は、彼が属していた中井家の存在である。京都大工頭を世襲した中井家は、禁裏(皇居)や二条城、徳川幕府が重視した主要寺社など、畿内および近江における幕府の重要建築プロジェクトの設計・積算・監督を一手に担う、当代最高峰の技術者集団であった 24 。平政隆は、この中井家が持つ広範なネットワークを通じて、通常の一工匠では知り得ない、城郭や御所といった公儀建築の最新かつ詳細な設計情報や仕様にアクセスできる、特権的な立場にあったと考えられる。
『愚子見記』の成立過程
論文「『愚子見記』の成立」によれば、本書は一度に完成したものではなく、寛文十一年(1671年)から貞享三年(1686年)頃までの約15年間にわたり、段階的に追記・編纂された長期的なプロジェクトであった 21 。その過程は、平政隆の知識の源泉を反映している。執筆の初期段階では、法隆寺大工としての知識、すなわち寺社建築に関する記述が中心であった。しかし、時が経つにつれて、中井家が管轄する地域の建築、すなわち京都御所や城郭に関する記事、さらには数学や度量衡といったより普遍的な知識が加えられ、全九巻の百科全書的な書物へと発展していった 21 。この成立過程は、平政隆の知識が、法隆寺という特定の場に根差した伝統知から、中井家を通じて得られるより公的で広範な情報へと拡大・統合されていったことを物語っている。
第五章:戦国時代を映すその他の記述とその史料価値
『愚子見記』が戦国時代という視点から注目されるのは、丹羽長秀説だけではない。本書には、戦国末期から江戸初期にかけての城郭に関する、他の史料では見られない具体的な記述が複数含まれている。
城郭に関する具体的な記述
- 大坂城・江戸城の寸法 : 本書には、豊臣秀頼が大坂夏の陣の後に再建した大坂城天守や、徳川家康が築いた慶長度江戸城天守について、その平面の寸法(間数)や様式に関する具体的な記述が見られる 26 。これらの天守は既に焼失して現存しないため、その実像に迫る上で本書の記述は極めて貴重な情報源となる。特に、幕府大工に伝わる「江戸御天守図(中井家指図)」などの他の絵図史料と本書の記述を比較検討することで、失われた天守の姿をより立体的に復元する試みが行われている 27 。
- 大和郡山城天守の移築説 : 本書は、「慶長七年(1602)に(豊臣秀長の居城であった)大和郡山城の天守が、徳川家康によって二条城に移築された」という驚くべき記述を含んでいる 20 。この天守移築説は、他の同時代史料では明確な裏付けが難しく、長らく城郭史研究における論争の的となってきた。『愚子見記』は、この説を支持する数少ない、しかし重要な文献的根拠の一つとして、今日でも議論を喚起し続けている。
武具・調度に関する記述
本書は建築技術に留まらず、武具や調度品にも言及している 1 。これらの記述は、戦国時代から江戸初期にかけての武家の文化や装備、生活様式を知る上での手がかりとなる可能性がある。ただし、その記述の具体性や情報源については、建築の記述ほど詳細な研究が進んでおらず、今後の課題として残されている。
史料としての信頼性と限界
これらの記述の史料価値を判断する上で重要なのは、本書が持つ二面性である。丹羽長秀説のような、約100年前の出来事に関する「物語的」な記述は、記憶や伝承に基づくものであり、歴史的事実とは慎重に区別する必要がある。一方で、大坂城や江戸城の寸法、郡山城の移築年といった、より具体的で専門的な「技術的」な記述は、著者自身の専門性や、彼がアクセス可能であった中井家の情報源を考慮すると、高い信頼性を持つ可能性がある。
このことから、『愚子見記』は「記憶」と「記録」が混在するハイブリッド史料であると特徴づけることができる。平政隆は、自らの専門分野のルーツやアイデンティティを語る際には、尊敬すべき先達の偉業を物語る「記憶」の様式を用い、一方で現役の工匠として実務に資する具体的な建築仕様を語る際には、寸法や年代といった「記録」の様式を用いた。この使い分けは、彼が過去の偉業への敬意と、現在進行形の職務に不可欠な実務的知識の両方を、分かちがたく重視していたことを示している。
そして、この「記録」としての側面の信頼性をさらに検証し、その価値を最大限に引き出すための鍵となるのが、京都大学附属図書館などに所蔵されている膨大な「中井家文書」である 24 。この史料群には、中井家が手掛けた二条城や禁裏などの詳細な建築図面が多数含まれている。『愚子見記』の城郭に関する記述、特に郡山城移築説などの典拠が、この中井家文書の中に眠っている可能性は十分に考えられる。両史料群を体系的に比較研究することは、『愚子見記』の記述の裏付けを得るだけでなく、逆に中井家文書の図面の解釈を補うといった相乗効果も期待でき、近世建築史研究における重要なフロンティアと言えるだろう。
結論:『愚子見記』の史料的価値と丹羽長秀説が示唆するもの
本報告書では、江戸時代の建築技術書『愚子見記』を、「戦国時代」という視点から多角的に分析してきた。その核心にある「天守の創案者は丹羽長秀である」という記述を手がかりに、本書の性格、史料的価値、そしてそれが内包する歴史的記憶の様相を明らかにしてきた。
『愚子見記』の総合的評価
結論として、『愚子見記』は、単なる建築技術の解説書ではない。それは、江戸時代前期の最高水準の工匠が、自らの専門分野における知識と技術、そしてその職能の歴史とアイデンティティを、後世のために体系化しようとした壮大な試みの産物である。本書は、大坂城や江戸城の寸法といった具体的な数値を記した「技術記録」としての側面と、丹羽長秀の偉業を物語る「歴史的記憶」の側面を併せ持つ、他に類を見ないハイブリッド史料である。この二面性を理解することこそが、本書を正しく読み解くための鍵となる。
丹羽長秀創案者説の最終的結論
丹羽長秀が天守を「創案」したという記述は、厳密な史料批判に基づけば、歴史的事実そのものではないと結論づけられる。それは、後世の工匠たちが、戦国時代の終わりを告げる画期的な建築プロジェクトであった安土城の築城を、普請総奉行として見事に成功させた偉大な先達に対して捧げた、最大級の敬意が生んだ「職能の神話」と解釈するのが最も妥当である。
しかし、この説は事実ではないからといって決して無価値なのではない。むしろ、事実ではないからこそ、その背後にある文化的・精神的な意味が浮かび上がってくる。この記述は、技術者たちが自らの職能の起源を輝かしい歴史の中に位置づけ、尊敬すべき先達の記憶を語り継ぐことで、自らの仕事に誇りと意味を見出そうとした、技術伝承の極めて人間的な側面を雄弁に物語っているのである。
本書が現代に問いかけるもの
『愚子見記』の研究は、我々に、歴史とは単一の客観的な事実の連なりとしてのみ存在するのではなく、社会の様々な階層や集団に属する多様な人々によって、それぞれの視点から語られ、記憶される多層的な物語であることを改めて教えてくれる。
特に、戦国という激動の時代が、泰平の世にいかにして記憶され、専門技術の文脈の中でいかに意味づけられていったか。『愚子見記』は、その貴重な一断面を我々に見せてくれる。技術と歴史、記録と記憶が交差するこの一点を深く探求することにこそ、本書を「戦国時代という視点」で読み解くことの真の意義が存在するのである。
引用文献
- 『愚子見記』について知りたい。 | レファレンス協同データベース - 国立国会図書館 https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000136748&page=ref_view
- 最終価格 愚子見記 法隆寺蔵本完全復刻版 平政隆 井上書院 - Yahoo!フリマ https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/item/z54752114
- 熊本城の重要文化財建造物 https://www.city.kumamoto.jp/kiji00361089/3_61089_423511_up_nrheld5e.pdf
- 江戸の職人発展史 https://www.token.or.jp/magazine/g200310/g200310_2.htm
- 『信長の野望蒼天録』家宝一覧-書物- http://hima.que.ne.jp/souten/shomotsu.html
- 信長の野望革新 家宝一覧-茶道具- http://hima.que.ne.jp/kakushin/shomotsu.html
- 信長に「友であり兄弟」と言わしめた 丹羽長秀の生涯 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CcDEH1JILLc
- 丹羽長秀と愛刀/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/sengoku-sword/favoriteswords-niwanagahide/
- 丹羽長秀は何をした人?「米のように欠かせない男が安土城の普請に腕を振るった」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/nagahide-niwa
- (丹羽長秀と城一覧) - /ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/16999_tour_080/
- 丹羽長秀(にわ ながひで) 拙者の履歴書 Vol.76~信長公と共に駆けた生涯 - note https://note.com/digitaljokers/n/n06536ff8bddf
- 天守の歴史/ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/16924_tour_005/
- かるーいお城の雑学(その4)天守とは? 天守建築の起源や呼び名のルーツ https://sekimeitiko-osiro.hateblo.jp/entry/tennsyutoha-kigenn
- 天守 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%AE%88
- かるーいお城の雑学(その5)天守建築のはじまりの謎 https://sekimeitiko-osiro.hateblo.jp/entry/tensyu-kenntikunonazo
- 【理文先生のお城がっこう】城歩き編 第38回 天守の歴史1 - 城びと https://shirobito.jp/article/1337
- 【超入門!お城セミナー】天守っていつからあるの? - 城びと https://shirobito.jp/article/224
- 愚子見記, 平政隆(編著), 愚子見記全九帖-法隆寺蔵本復刻 - 日本建築学会 https://www.aij.or.jp/paper/detail.html?productId=78037
- 江戸城天守は、高く、輝いていた。 | ポンタックのブログ at DESIGN OFFICE TAK https://www.pontak.jp/traditional-architecture-japan-edo-castle/
- 大和郡山城出土の金箔瓦について - 統合 考古学論攷第46冊_m.indd http://www.kashikoken.jp/under_construction/wp-content/uploads/2023/05/kiyo46-okada.pdf
- 『愚子見記』の成立 - J-Stage https://www.jstage.jst.go.jp/article/aijax/369/0/369_KJ00004066635/_article/-char/ja/
- 江戸時代の建築に関する技術書『愚子見記』の古本を出張買取しました https://www.koshokaitori.com/kosyo/20191122a/
- 西岡常一 社寺建築講座 - MAXAM https://www.maxam.jp/contents/%E8%A5%BF%E5%B2%A1%E5%B8%B8%E4%B8%80-%E7%A4%BE%E5%AF%BA%E5%BB%BA%E7%AF%89%E8%AC%9B%E5%BA%A7/
- 中井家絵図・書類 - 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/collection/nakai
- 21560667 研究成果報告書 https://kaken.nii.ac.jp/en/file/KAKENHI-PROJECT-21560667/21560667seika.pdf
- 豊臣秀頼の大坂城再建天守-復元篇- http://castles.chicappa.jp/2008-1st-sp/1st-report
- 城の再発見! 天守が建てられた本当の理由 – 歴史の奥底に封印された「凶暴なる実像」をサルベージ ! ! https://castles.xsrv.jp/
- 中井家絵図・書類 禁裏之部」1067点を「京都大学貴重資料デジタルアーカイブ」で公開 https://current.ndl.go.jp/car/40308
- 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ: トップページ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/