松屋筆記
『松屋会記』は、奈良の豪商松屋家三代が記した茶会記。わび茶草創期から江戸初期まで約120年間を記録。戦国茶の湯文化の変遷を映す。
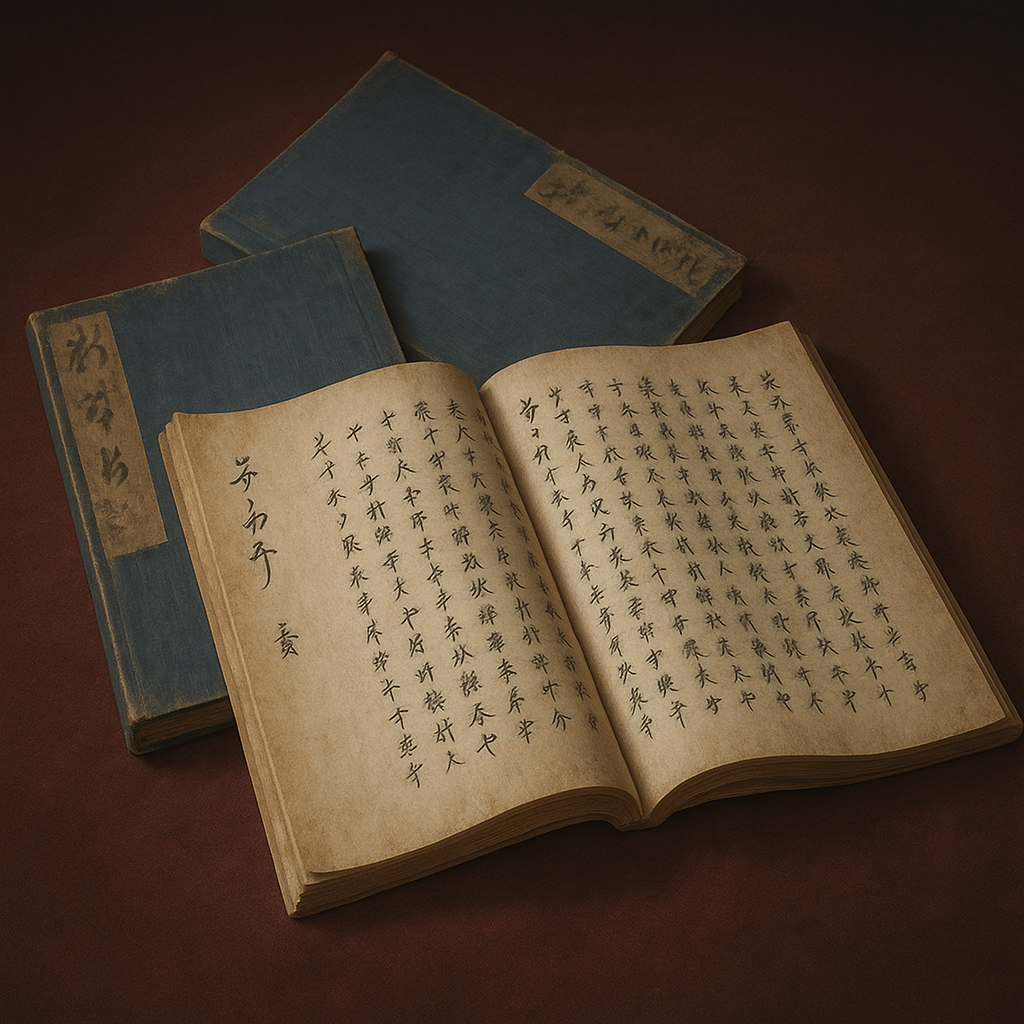
戦国時代の茶の湯と社会を映す一級史料 —『松屋会記』の総合的考察
序論:『松屋筆記』という名称の整理と史料的価値
名称の整理—『松屋筆記』と『松屋会記』
まず、『松屋筆記』という名称について整理する必要がある。この名称は、歴史上、二つの異なる文献を指す可能性があるためである。
一つは、江戸時代後期の国学者、小山田与清(おやまだともきよ)が著した随筆集『松屋筆記(まつのやひっき)』である 1 。これは文化年間(1804-1818)末年から弘化2年(1845)頃までの約30年間にわたり、古今東西の書物から記事を抜き書きし、与清自身の考証や論評を加えたもので、全120巻に及ぶ浩瀚な著作である 3 。国学者の考証随筆として高く評価されているが、本稿で主題とする戦国時代の茶会記とは全くの別物である。
もう一つが、本稿の主題である、奈良の豪商・松屋家に三代にわたって伝えられた茶会記であり、これも通称として『松屋筆記(まつやひっき)』あるいは『松屋日記』と呼ばれることがある 4 。しかし、学術的には、この茶会記は『松屋会記(まつやかいき)』という名称で統一されているのが一般的である。呼称の混同を避け、学術的な正確性を期すため、本報告では以降、この茶会記を『松屋会記』と呼称する。
四大茶会記における『松屋会記』の位置づけ
『松屋会記』は、茶道史研究において最も重要な史料群とされる「四大茶会記」の一つに数えられる。他の三つは、堺の豪商・津田家に伝わった『天王寺屋会記(てんのうじやかいき)』、同じく堺の今井宗久による『今井宗久茶湯日記抜書(いまいそうきゅうちゃのゆにっきぬきがき)』、そして博多の豪商・神屋宗湛の『宗湛日記(そうたんにっき)』である 5 。
これらの茶会記の中でも、『松屋会記』の史料的価値は極めて高い。その最大の理由は、天文2年(1533)に起筆されており、現存する茶会記としては最古級に属する点にある 6 。わび茶が形成され、千利休によって大成され、そして江戸時代初期の武家茶道へと変遷していく、まさに茶の湯の黄金時代を、一貫して記録し続けた唯一無二の史料なのである。
その独自性を理解するために、四大茶会記を比較すると以下のようになる。
表1:四大茶会記の比較
|
茶会記名 |
記録者 |
記録期間 |
拠点 |
主な特徴 |
|
松屋会記 |
松屋久政・久好・久重 |
約117年間 (1533–1650) |
奈良 |
わび茶草創期から江戸初期までの長期記録。千利休の最初期の茶会や松永久秀の動向など、奈良の視点からの貴重な情報を含む 4 。 |
|
天王寺屋会記 |
津田宗達・宗及・宗凡 |
約42年間 (1548–1590) |
堺 |
織田・豊臣政権と密接に関わった堺の視点。桃山時代の茶の湯を知る上での基本史料 5 。 |
|
今井宗久茶湯日記抜書 |
今井宗久 |
抄録 (1558–1582頃) |
堺 |
織田信長の茶頭の一人としての記録。政権中枢の茶の湯の様子を伝える。 |
|
宗湛日記 |
神屋宗湛 |
約27年間 (1586–1613) |
博多 |
豊臣秀吉政権下における九州の茶の湯文化と中央との交流を記録。 |
この表からも明らかなように、『松屋会記』の約120年にわたる記録期間は他の追随を許さない 11 。これにより、単一の家系による「定点観測」として、茶の湯文化の長期的な変遷—道具の好み、会席料理の内容、茶室の設え、人々の価値観の変化—を克明に追跡することが可能となる。さらに、その拠点が「奈良」であるという点が、この史料に比類なき個性を与えている。堺や京が茶の湯の新たな中心地として台頭する中で、わび茶の祖・村田珠光を生んだ古都・奈良の伝統を背負う松屋家の視点は、茶道史を複眼的・立体的に理解する上で不可欠な要素なのである。
第一部 記録者たち—奈良の豪商・松屋三代の肖像
第一章 松屋家の出自と奈良における社会的地位
『松屋会記』を理解するためには、まずその記録者である松屋家の人物像と、彼らが置かれていた社会的背景を把握することが不可欠である。
松屋家の本姓は土門(どもん)といい、代々「源三郎」を名乗る奈良の塗師(ぬし)の家系であった 7 。彼らの生業は、漆器の製作および販売であり、その高い技術力によって財を成した豪商であった 4 。彼らが単なる富裕な商人ではなかったことは、その文化的活動からも明らかである。天正15年(1587)に豊臣秀吉が催した北野大茶会には、奈良を代表する町衆「奈良三十六衆」の一人として、三代目の松屋久政が参会している 13 。これは、松屋家が奈良の経済界のみならず、文化的な名士としても公に認められていたことを示す動かぬ証拠である。
松屋家が他の地域の茶人と一線を画していたのは、彼らが抱いていた「南都(なんと)の茶道」への誇りであった。堺や京で新しい茶の湯の流行が生まれる中、松屋家の人々は、わび茶の創始者・村田珠光を輩出した自分たちの土地、奈良の茶の湯の伝統に強い自負心を持っていた 6 。この地域的アイデンティティは、『松屋会記』の記録の底流に常に存在し、単なる流行の追随ではない、地に足のついた文化実践の記録としての性格を強めている。彼らは生業である塗師としての審美眼を、茶の湯という総合芸術の世界に持ち込み、実践した文化人であった。その専門的な美意識が、彼らの茶の湯の根幹をなし、記録の質を高めていたことは想像に難くない。
第二章 会記を書き継いだ三人の当主
『松屋会記』は、天文2年(1533)から慶安3年(1650)まで、三代の当主によって書き継がれた 12 。この三世代にわたる継続的な記録こそが、この史料の最大の価値である。
三代・松屋久政(1521–1598)— 記録の創始者
久政は、天文2年(1533)、わずか13歳(数え年)の若さで『松屋会記』を起筆した人物である 9 。彼の記録は、戦国時代の緊張感が色濃く反映された茶の湯の世界を今に伝えている。
特筆すべきは、千利休との深い交流である。天文13年(1544)には、まだ堺の一茶人に過ぎなかった若き日の利休(当時は宗易)が催した茶会に招かれており、その詳細な記録を残している 9。これは、天下の茶頭となる以前の利休の姿を伝える、現存する最古級の記録であり、利休研究における第一級の史料となっている。
また、久政は大和国を支配した戦国武将・松永久秀や、わび茶の祖・村田珠光の弟子である古市澄胤(ふるいちちょういん)といった、当代の重要人物たちとも頻繁に茶会を催し、深い交流を結んでいた 15。彼の記録は、戦国乱世における文化人たちのネットワークを生々しく描き出している。
四代・松屋久好(?–1633)— 移行期の記録者
久好は、父・久政から会記を受け継ぎ、安土桃山時代から江戸幕府成立へと至る、まさに時代の転換期の茶の湯を記録した 9 。彼の時代の茶会は、戦国の緊張が和らぎ、茶の湯文化が武家社会全体へと広く浸透していく過渡期の様相を呈していたと考えられる。久政の記録が持つ緊迫感とは異なる、新たな時代の到来を予感させる記録を残した。
五代・松屋久重(1566–1652)— 確立期の記録者
久重は慶安3年(1650)まで記録を続け、1世紀以上にわたる松屋家の茶の湯の記録を締めくくった 9 。彼の会記には、小堀遠州に代表されるような、泰平の世における洗練された「きれいさび」の茶の湯の世界が記録されている。興味深いことに、その遠州も若き日の文禄3年(1594)、久政が催した茶会に客として参席した記録が残っている 18 。
久重はまた、単なる記録者にとどまらず、松屋家の名声を高めるための戦略的な文化活動も行っている。例えば、後述する家宝の掛物「白鷺図(はくろず)」の由緒を権威づけるため、大徳寺の僧侶に依頼して由来書を作成させるなど、文化財の価値を「創造」する営みにも積極的に関与した 7。
このように、久政が記録した戦国乱世の茶、久好が記録した移行期の茶、そして久重が記録した泰平の世の茶と、三代にわたる記録は、社会の変動と共に文化がいかに変容していくかを、一つの家系の視点から見事に捉えている。これこそが、『松屋会記』が単なる個人の日記を超え、文化史の「定点観測」記録として比類なき価値を持つ所以である。
第二部 『松屋会記』に映る戦国時代の茶の湯
第一章 わび茶の源流と展開—奈良からの視点
茶道史は、しばしば堺の商人である武野紹鷗(たけのじょうおう)と千利休の系譜を中心に語られる。しかし、『松屋会記』は、その歴史観に再考を迫る重要な視点、すなわち「わび茶の祖、奈良の村田珠光」という源流の重要性を強く示唆している。
珠光は奈良の出身であり、高価な中国渡来の道具(唐物)を至上とする当時の風潮に対し、「和漢のさかいをまぎらかすこと肝要」(和物と唐物の境界を意識せず、双方の美点を取り入れることが重要)と説き、信楽や備前といった素朴な国産の焼物(和物)にも美を見出す、新たな価値観を茶の湯の世界にもたらした 19 。
『松屋会記』には、珠光が記したとされる「心の文」を掛け物として茶席に掛けた記録が残っており、松屋家が珠光の精神的遺産を直接受け継ぐ存在であったことを物語っている 6。
この珠光の精神は、『松屋会記』全体を貫くテーマである「唐物中心から和物へ」という美意識の変遷に具体的に現れている 4 。会記の初期には豪華な唐物道具が茶会の主役であったが、時代が下るにつれて、土の匂いがするような素朴な信楽焼や備前焼の道具が、わびの美意識を体現するものとして積極的に用いられるようになる過程が克明に記録されている 22 。
この文脈で特に注目すべきは、前述した天文13年(1544)の千利休の茶会記録である。この茶会で、若き利休はあえて簡素な「珠光茶碗」を用いて久政をもてなしている 16 。これは、利休がわび茶を大成するにあたり、師である武野紹鷗ら堺の茶風だけでなく、奈良の珠光の精神からも深く影響を受けていたことを示す決定的な証拠である。『松屋会記』は、わび茶の系譜を、堺中心の単線的な物語から、奈良という源流を持つ、より豊かで複雑なものとして捉え直すための鍵となる史料なのである。
第二章 茶室の武将と茶人—政治と文化の交差点
戦国時代の茶の湯は、単なる趣味や芸事ではなかった。それは、身分や立場を超えた人間関係を構築し、時には政治的な駆け引きも行われる、重要な社会的プラットフォームであった。『松屋会記』は、その実態を具体的に伝えている。
松永久秀との密接な関係
大和国を実質的に支配した戦国武将・松永久秀は、松屋久政の茶会に頻繁に顔を出す常連客であり、また自らも久政を茶会に招く亭主でもあった 17 。
両者の深い信頼関係を象徴するのが、永禄10年(1567)の東大寺大仏殿焼き討ち前夜の逸話である。久秀は、合戦の直前、松屋に使者を送り、「明日は南都を焼き討ちにするゆえ、家宝である『松屋肩衝』と『鷺の絵』の二品を持って今夜中に立ち退くように」と密かに伝えたという 15。
この逸話は、「三好家乗っ取り」「将軍暗殺」「大仏殿焼き討ち」という三悪事で知られる久秀の、通説とは異なる一面を浮き彫りにする。彼は、美を愛し、その守り手である松屋家との文化を通じた絆を何よりも大切にする、一人の教養人でもあった。茶の湯が、政治的な立場を超えた人間的な信頼関係を育む場であったことを、これほど雄弁に物語るエピソードはない。
千利休ら他の茶人・武将との交流
久政が記録した若き日の利休の茶会は、彼が天下の茶頭となる以前、まだ堺で頭角を現しつつあった一茶人の姿を活写しており、利休という人物の成長過程を研究する上で欠かせない 9 。
その他にも、会記には筒井順慶といった大和の国衆や、次代を担う小堀遠州 18、そして堺の津田宗及や今井宗久といった茶人たちが登場し、茶会という場で武将、商人、職人といった異なる階層の人々が交流していた様子が記録されている 17。
ここで『天王寺屋会記』と比較すると、『松屋会記』の持つ独自の価値が一層明確になる。『天王寺屋会記』が織田・豊臣という中央政権に近い立場から「天下人の茶の湯」を記録しているのに対し 5 、『松屋会記』は松永久秀や筒井順慶といった地域領主との日常的な交流を記録している。両者を突き合わせることで、中央の「公儀の茶」と、地方における文化的生活としての茶の湯が、互いに影響を与え合いながら展開していく様子を立体的に復元することができるのである。
第三部 名物が語るもの—「松屋三名物」の美意識と価値
松屋家には、その名声を象徴する「松屋三名物」と呼ばれる三つの家宝が伝わっていた。これらの名物は、単に高価な道具であるだけでなく、戦国時代の美意識や価値観、そして松屋家のアイデンティティを雄弁に物語る。
第一章 松屋肩衝—時代を超えて愛された名物茶入
「松屋肩衝(まつやかたつき)」は、大名物として知られる唐物(中国製)の肩衝茶入である 15 。背は低いが、堂々とした風格を持つ姿が特徴とされる 24 。
その伝来は、室町幕府八代将軍・足利義政に始まり、村田珠光、古市澄胤を経て松屋家へと伝わったとされる 25。その後、大坂の商人、薩摩の島津家などを経て、昭和3年(1928)の実業家・根津嘉一郎による落札を経て、現在は根津美術館の所蔵となっている 24。
この茶入の価値を物語るのは、その華麗な伝来だけではない。珠光、利休、古田織部、小堀遠州という、各時代を代表する茶の湯の宗匠たちが、それぞれ自らの好みでこの茶入のための仕覆(しふく、茶入を入れる絹の袋)をあつらえているという事実である 28。これは、時代の美意識がどのように変わろうとも、「松屋肩衝」が常に最高の茶入として賞賛され続けたことの何よりの証左である。
第二章 徐煕筆 白鷺図—「わび」の象徴と価値の創造
「徐煕筆 白鷺図(じょきひつ はくろず)」は、松屋三名物の一つに数えられる掛物である。この絵は「利休がわびの掛物として大変ほめた」と伝えられ、わび茶の美意識を象徴する作品として名高い 6 。
この掛物は、10世紀中国・南唐の画家である徐煕の筆とされてきたが、現在ではこの伝承は後世に作られたものと考えられている 7。
興味深いのは、この「伝承」が形成される過程である。寛永16年(1639)、五代当主の久重は、茶の湯を通じて親交のあった大徳寺の僧・天祐紹杲(てんゆうしょうこう)に依頼し、『徐煕鷺画記』という由来書を執筆させた 7。この文書によって、この絵は単なる美しい鷺の絵から、「足利義政公遺愛の軸」という権威ある物語をまとった名物へと昇華した。この戦略的な行為により、絵の価値は飛躍的に高まり、同時に松屋家の名声も全国に轟くことになったのである。
この事例は、この時代の「名物」の価値が、作品本来の美的価値だけでなく、それに付与される「由緒」や「物語」によって構築されていたことを示す格好の例である。松屋家は、単なる名物の所有者ではなく、そのブランド価値を戦略的に管理・向上させる、能動的な文化のプロデューサーでもあったのだ。
第三章 存星の長盆—塗師の誇りの結晶
三名物の最後の一つは、「存星(ぞんせい)の長盆」である 9 。存星とは、彩漆で文様を描き、その輪郭を線彫りする中国由来の漆芸技法である。
松屋家が、家宝の筆頭に、自らの生業である漆芸の最高峰の作品を据えていたという事実は、極めて象徴的である。これは、彼らが自分たちの専門分野において最高の技術と審美眼を持ち、それを茶の湯という総合芸術の中に統合していたことの証である。彼らにとって茶の湯は単なる趣味ではなく、自らのアイデンティティそのものを表現する場であった。この盆は、塗師・松屋家の誇りの結晶と言えるだろう。
結論:『松屋会記』が現代に伝えるもの
本報告で詳述してきたように、『松屋会記』は単なる茶会の覚書ではない。それは、第一に、わび茶の草創期から確立期に至る1世紀以上の文化変容を記録した、比類なき年代記である。第二に、戦国時代の政治・社会・文化を、奈良という独自の視点から映し出す鏡である。そして第三に、職人であり文化の目利きでもあった松屋家の、美意識と戦略の結晶である。
『松屋会記』は、千利休や織田信長といった歴史の主役たちだけでなく、松永久秀のような複雑な人物の多面的な姿や、小堀遠州のような次代の才能の登場を、生々しい一次情報として伝えている。そして何よりも、堺の『天王寺屋会記』と併せ読むことで、中央政権の動向と地方の文化交流という、戦国時代の文化のダイナミズムを立体的に復元することを可能にする。
この記録を通じて我々が学ぶのは、動乱の時代にあっても、戦国の人々が一碗の茶を介して深い人間関係を築き、美を追求し、文化を創造し伝承しようとしていたという事実である。それは、人間の精神的・文化的活動が持つ、普遍的で時代を超えた価値を教えてくれる。『松屋会記』は、日本の文化史、社会史、さらには思想史の研究にとって、汲めども尽きぬ示唆を与え続ける、第一級の文化遺産なのである。
引用文献
- 松屋筆記とは? わかりやすく解説 - デジタル大辞泉 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%BE%E5%B1%8B%E7%AD%86%E8%A8%98
- 松屋筆記(マツノヤヒッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E5%B1%8B%E7%AD%86%E8%A8%98-635027
- 松屋筆記 第1 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b33345.html
- 松屋会記(まつやかいき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E5%B1%8B%E4%BC%9A%E8%A8%98-1595633
- 天王寺屋会記(てんのうじやかいき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%B1%8B%E4%BC%9A%E8%A8%98-1566346
- 表千家不審菴:茶人のことば https://www.omotesenke.jp/chanoyu/7_2_69b.html
- 松屋名物﹁白鷺緑藻図﹂考 https://nara-wu.repo.nii.ac.jp/record/2001995/files/issn09132201v37pp148-137.pdf
- 『松屋会記』 解説 - 表千家 https://www.omotesenke.jp/chanoyu/7_8_1a_win01.html
- 松屋久政 まつやひさまさ - 表千家 https://www.omotesenke.jp/cgi-bin/result.cgi?id=213
- 天王寺屋会記 てんのうじやかいき - 表千家 https://www.omotesenke.jp/cgi-bin/result.cgi?id=277
- 松屋会記 | 本の総合カタログBooks 出版書誌データベース https://www.books.or.jp/book-details/9784473043320
- 松屋会記 (茶書古典集成2) - 竹内 順一 - 楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17785482/
- 松屋久政(まつや ひさまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E5%B1%8B%E4%B9%85%E6%94%BF-1111470
- 奈良佐保短期大学の近辺に存在する茶関係の史跡について(2) -岡田亀 ... https://www.narasaho-c.ac.jp/assets/pdf/college_info/research-bulletin/a1400469850224.pdf
- 松屋肩衝 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E6%9D%BE%E5%B1%8B%E8%82%A9%E8%A1%9D
- 「千利休」は豊臣政権におけるフィクサーだった! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/65
- 戦国武将と茶の湯「松永久秀」第四回:掲示板:寺子屋 素読ノ会|Beach - ビーチ https://www.beach.jp/circleboard/ad25106/topic/1100100036476
- 小堀遠州(こぼりえんしゅう) https://www.koborienshu.org/%E5%B0%8F%E5%A0%80%E9%81%A0%E5%B7%9E/
- 侘び茶の成立 豪華な上流階級の茶の湯から草庵の茶へ | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/822
- 侘び茶を完成させた文化人・武野紹鴎について - far east tea company https://fareastteacompany.com/ja/blogs/fareastteaclub/people-related-to-japanese-tea-takeno-joo
- 村田珠光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E7%94%B0%E7%8F%A0%E5%85%89
- 千利休の侘び茶における美学(上) https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/record/2015464/files/HABITUS_27_166.pdf
- 第 51話 〜津田宗及 - ここまで知らなかった!なにわ大坂をつくった100人=足跡を訪ねて=|関西・大阪21世紀協会 https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/osaka100/051.html
- 肩衝茶入 銘松屋 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/218400
- 唐物肩衝茶入〈銘松屋/〉 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/154798
- 美意識 - 武者小路千家 卜深庵 https://www.bokushinan.com/post/__%E7%BE%8E%E6%84%8F%E8%AD%98-1
- 肩衝茶入 銘 松屋 - 根津美術館 https://www.nezu-muse.or.jp/sp/collection/detail.php?id=40091
- 松屋肩衝 - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/67290