歴代宝案
『歴代宝案』は、琉球王国の外交文書集。戦国期の日本が琉球を介し国際貿易に組み込まれた様を克明に記す。二度の焼失を乗り越え、日本の戦国史研究に新たな視点をもたらす貴重な史料である。
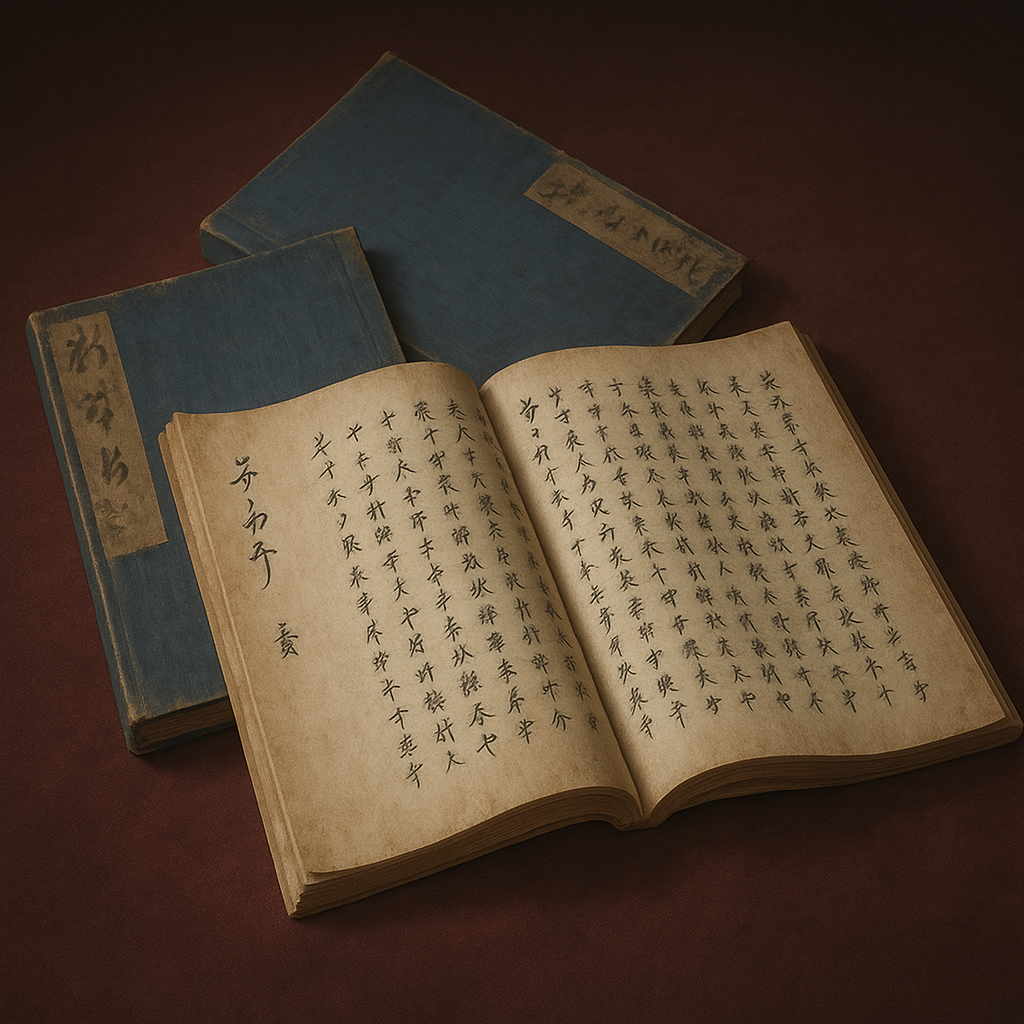
『歴代宝案』から読み解く日本の戦国時代 ―琉球王国の外交文書が照らし出すもう一つの貌―
序章:『歴代宝案』への誘い―戦国日本の窓としての琉球外交文書
本報告書は、琉球王国が後世に遺した第一級の外交史料群である『歴代宝案』を、日本の「戦国時代」という特定の分析視角から、詳細かつ徹底的に調査し、その歴史的意義を再評価することを目的とする。一般的に、日本の戦国時代(おおよそ15世紀後半から16世紀末)は、応仁の乱に始まり、織田信長、豊臣秀吉による天下統一事業に至るまで、絶え間ない内乱と社会変動の時代として認識されている。しかし、その視線は日本列島内部の動向に集中しがちであり、当時の日本が東アジア・東南アジアの広大な交易ネットワークといかに深く結びついていたかという側面は、必ずしも十分に光が当てられてきたとは言えない。この失われた環を繋ぎ、戦国時代の日本をよりグローバルな文脈で捉え直すための鍵こそが、『歴代宝案』に他ならない 1 。
本報告書が探求する中心的な問いは、以下の二点に集約される。第一に、室町幕府の権威が失墜し、統一された外交主体を欠いていた戦国時代の日本に対し、独立した海洋国家であった琉球王国は、どのように向き合い、いかなる関係性を構築していたのか。第二に、その関係性は、分裂状態にあった日本の政治経済、さらには明を中心とする当時の東アジア国際秩序全体に、どのような影響を及ぼしていたのか。これらの問いに答えるため、本報告書は『歴代宝案』の記録を丹念に読み解いていく。
構成として、本報告書は三部構成を採る。第一部「『歴代宝案』の基礎的理解」では、この史料群そのものの成り立ち、構成、内容、そして喪失と再構築の数奇な運命を詳述し、分析の土台を固める。第二部「二つの世界―『大交易時代』の琉球と戦国時代の日本」では、本報告書の主題となる二つの対照的な社会、すなわち海洋交易国家として黄金期にあった琉球と、内乱に明け暮れていた日本の政治経済状況を概観する。そして最も核心的な部分である第三部「『歴代宝案』から読み解く戦国日本と琉球の交点」では、両者の具体的な接点を、経済的・政治的側面から多角的に分析する。結論として、これらの分析を通じて、日本の戦国時代史研究における『歴代宝案』の新たな価値と可能性を提示するものである。
第一部:『歴代宝案』の基礎的理解
第一章:『歴代宝案』とは何か
定義と編纂目的
『歴代宝案』とは、琉球王国が尚巴志王代の1424年(永楽22年)から尚泰王代の1867年(同治6年)に至るまでの実に444年間にわたり、中国(明・清)や朝鮮、東南アジア諸国との間で交わした外交文書の控えや関連文書を、漢文で集成した膨大な史料群である 1 。その収録文書は現存するだけでも約4320件にのぼり、琉球史はもちろんのこと、前近代の東アジア海域交流史を解明する上で比類なき価値を持つ第一級史料と位置づけられている 3 。
しかし、『歴代宝案』の真の価値は、単なる過去の記録の集成という点にとどまらない。その編纂目的は、極めて実用的な性格を帯びていた。これは、未来の外交交渉に備えるため、過去の外交案件の処理方法や文書の書式をいつでも参照できるように整理された、実践的な「外交マニュアル」だったのである 1 。外交の最前線に立つ役人たちが、新たな外交文書を作成する際に、過去の先例を調べ、適切な表現や対応策を学ぶための手引書として機能していた 5 。
この実用主義的な性格は、「宝案」という名称にも表れている。「宝案」という言葉は二重の意味合いを持つと解釈されている。一つは文字通り「歴代の貴重な公文書(宝の案書集)」という意味であり、国家の宝として後世に伝えるべき重要な記録であることを示している 1 。もう一つは、「案」を「案件」と捉える解釈である 5 。特に第一集では、文書が皇帝からの詔勅、福建布政使司からの咨文といったように、案件の種類ごとに分類整理されており、実務上の検索の便が図られている。この名称自体が、琉球王国が外交文書を単なる記録ではなく、国家の存続と繁栄を支えるための戦略的資産、すなわち「宝」として認識していたことを物語っている。
この事実は、琉球が高度に制度化された外交能力を持つ主権国家であったことの何よりの証左である。外交とは、場当たり的な対応で成り立つものではない。相手国との関係性の歴史、儀礼的な作法、国際慣習など、膨大な知識と経験の蓄積が不可欠である 6 。『歴代宝案』が先例参照のための実用的な手引書として編纂され、継続的に利用されていたという事実は、琉球の外交が個人の才覚のみに依存するのではなく、組織的かつ体系的な情報管理システムに基づいて運営されていたことを示している。これは、琉球が単なる中継貿易の拠点ではなく、洗練された官僚機構を持つ成熟した国家として、東アジアの国際社会で主体的に行動していたことを意味する。戦国時代の日本において、これほど長期間にわたり、体系化された外交文書群を国家事業として維持・管理した政治勢力は存在しない。この一点だけでも、『歴代宝案』の存在は際立っている。
編纂の担い手―久米村の役割
『歴代宝案』の編纂、そして琉球の外交実務そのものを一貫して担ったのが、「久米村(クニンダ)」と呼ばれる特殊なコミュニティの人々であった 1 。彼らは14世紀末に明の洪武帝から派遣されたとされる閩人三十六姓の子孫たちであり、中国語(漢文)の読解と作成に極めて堪能な専門家集団であった 4 。琉球の外交・交易の最前線において、彼らは通訳、航海士、文書作成官など、不可欠な役割を果たし、まさに琉球王国を支える頭脳集団として機能した。
『歴代宝案』の最初の体系的な編纂事業は、1697年(康熙36年)に行われた第一集の成立である。この事業は、当時の久米村の指導者であった紫金大夫・蔡鐸(さいたく)らを中心として、首里王府の命令によって進められた 5 。彼らは、それまで久米村の天妃宮(てんぴぐう、航海の女神・媽祖を祀る廟)に蓄積されていた「旧案」あるいは「案書」と呼ばれる膨大な文書群を、約8ヶ月かけて整理・校訂し、49巻にまとめ上げた 7 。この事業は、単に散逸しがちな文書を保存するという消極的な目的だけでなく、数百年にわたる外交資産を体系化し、将来の外交交渉に万全を期すという、国家の未来を見据えた戦略的なプロジェクトであったと言える。
第二章:構成と内容
全体の構成
『歴代宝案』は、その編纂時期と内容から、大きく「第一集」「第二集」「第三集」、そして「別集」に区分される 8 。もともとの原本は、第一集49巻、第二集200巻、第三集13巻、目録4巻、別集4巻の合計270巻前後から構成されていたと推定されている 10 。しかし、後述する原本の焼失により、現存するのは戦前に作成された各種の写本を基に復元された約250巻である 10 。
各集の内容と特徴
各集は、それぞれ異なる時代の琉球外交の様相を反映しており、その内容は以下の通りである。
-
第一集(1424年~1696年、現存42巻)
この第一集こそが、琉球の「大交易時代」を最も色濃く記録している部分であり、日本の戦国時代とほぼ時期を同じくする。収録されているのは、宗主国であった明および清初期の中国との間の文書はもちろんのこと、朝鮮、そしてシャム(アユタヤ朝)、マラッカ、パレンバン、ジャワ、スマトラといった東南アジアの諸王国・港市国家との間で交わされた往復文書である 7。内容が文書の種類(皇帝からの詔勅、中国官庁からの咨文、琉球国王からの表奏など)ごとに分類・整理されている点が、他の集にはない大きな特徴である 5。これは、1697年の編纂時に、過去の膨大な記録を体系的に整理しようとした意図を反映している。 -
第二集(1697年~1855年、現存187巻)
第二集は、第一集の編纂以降、新たに蓄積された外交文書を逐次まとめたものであり、その大半は清朝との間の文書で占められている 8。第一集とは異なり、文書は基本的に年代順に収録されている。この時期になると、かつてのような東南アジア諸国との直接的で広範な交易は下火となり、琉球の対外関係が中国(清)との朝貢関係を主軸として再編されていく過程がうかがえる。 -
第三集(1859年~1867年、現存13巻)
第三集は、琉球王国末期の動乱期を記録している。アヘン戦争以降、欧米列強の船舶が頻繁に来航するようになり、東アジアの国際秩序が大きく揺らぐ中で、琉球がこの新たな挑戦にどのように対応しようとしたか、特に宗主国である清朝とどのような協議を行ったかを示す貴重な文書が含まれている 4。
史料としての独創性
『歴代宝案』は、いくつかの点で他に類を見ない独創的な価値を持つ。その一つが、中国史研究にとっても極めて重要な記録を含んでいる点である。特に、17世紀半ばの明から清への王朝交代期において、琉球が明の滅亡後も江南で抵抗を続けた南明政権と交わした外交文書が含まれている 4 。これらの記録は、中国大陸側にもほとんど現存しておらず、当時の混乱した国際情勢を生々しく伝える一次史料として、世界的に見ても高い評価を受けている。
さらに、『歴代宝案』は、前近代の東アジアにおける国際秩序、すなわち「冊封・朝貢体制」が、単なる理念や形式ではなく、現実にどのように機能していたかを具体的に解き明かすための、最も詳細な事例集でもある 6 。皇帝からの勅書、朝貢使節の派遣、交易品のリスト、海難事故の処理、漂流民の送還といった多岐にわたる記録を通じて、国家間の儀礼、経済的相互依存、そして紛争解決のメカニズムが、生き生きと描き出されている。
第三章:喪失と再構築の物語
『歴代宝案』が今日、我々の目に触れることができるのは、幾多の危機を乗り越えた奇跡的な継承の物語の成果である。その歴史は、琉球(沖縄)が近代史の荒波にいかに翻弄されてきたかを象徴している。
二つの原本の悲劇的運命
琉球王国時代、『歴代宝案』は国家の至宝として、首里王府と久米村天妃宮の二か所に一部ずつ保管されるという、極めて厳重な二部体制で管理されていた 4 。これは、火災などの不慮の事故によって国家の記憶が完全に失われることを防ぐための、賢明なリスク管理であった。しかし、近代以降の激動は、この二重の防護さえも打ち破るものであった。
-
王府保管本(首里王府本)の焼失
1879年の琉球処分によって琉球王国が解体され沖縄県が設置されると、首里城にあった王府保管本は、他の王府文書と共に明治政府に接収された。沖縄県庁での一時保管を経て、東京の内務省に移管されたが、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災の火災によって、他の多くの貴重な文化財と共に灰燼に帰した 4。琉球の知の遺産が、日本の新たな中央集権体制の下で東京に集められた結果、失われたこの出来事は、琉球の自己決定権の喪失を象徴する悲劇であった。 -
久米村保管本(天妃宮本)の焼失
一方、久米村に保管されていたもう一部の原本は、王府本の焼失後、その価値が再認識されることとなった。1931年(昭和6年)、久米村の旧家で発見され、1933年(昭和8年)に沖縄県立図書館へ寄託された 8。この時、閲覧には原本を用いず、別途作成した写本を供するという厳格な条件が付けられ、副本の作成が進められた。しかし、この最後の原本もまた、第二次世界大戦末期の1945年、米軍との激しい地上戦(沖縄戦)の戦禍の中で焼失したとされている 1。沖縄戦という破滅的な出来事が、数多くの人命だけでなく、数世紀にわたって受け継がれてきた文化的な蓄積をも根こそぎ破壊したのである。
写本による奇跡的な継承
二つの原本が失われ、『歴代宝案』は永久に失われたかに思われた。しかし、幸運にも、原本が焼失する以前の1930年代から40年代初頭にかけて、複数の研究者や機関によって、いくつかの写本や写真版(青写真本)が作成されており、それらが奇跡的に戦禍を免れて現存していた 4 。
これらの写本群の中でも、今日の研究の根幹を成しているのが、以下の三つの系統である。
-
台湾大学本
最も網羅性が高く、研究の基礎となっているのが、国立台湾大学図書館に所蔵されている筆写本である 10。これは、戦前の1935年(昭和10年)、当時日本の植民地であった台湾の台北帝国大学で日中交渉史を研究していた小葉田淳助教授が、沖縄県立図書館に保管されていた久米村本(副本)の筆写を久場政盛らに依頼して作成させたものである 1。この写本が戦後、台湾大学に引き継がれたことで、『歴代宝案』の全体像が失われずに済んだ。 -
鎌倉芳太郎本・東恩納寛惇本
美術史家・鎌倉芳太郎や歴史家・東恩納寛惇によって作成された、写真技術(青写真)を用いた影印本も現存している 8。これらは筆写による誤りを排除できる点で価値が高い。 -
旧県立図書館副本
沖縄県立図書館が原本から作成した副本の一部は、沖縄戦で疎開先にあったものが戦後米軍によって発見・回収され、現在は那覇市歴史博物館に所蔵されている 4。これもまた、原本の姿を伝える貴重な一次資料である。
今日の我々が手にすることができる『歴代宝案』は、これら断片的に残された複数の写本を、研究者たちが相互に比較・校訂し、本文を復元するという、気の遠くなるような作業の賜物である 12 。戦後、沖縄県は県の重要事業として、これらの写本を基にした校訂本の作成と、現代語訳・注釈を付した訳注本の刊行を長期計画で進めており、その成果は広く公開されている 3 。
『歴代宝案』の喪失と再構築の歴史は、単なる文献学上のエピソードではない。それは、沖縄の人々が、近代化、戦争、そして戦後の占領という激動の中で、自らの歴史とアイデンティティの根幹を成す文化遺産をいかにして守り、取り戻そうとしてきたかという、粘り強い文化復興運動の物語そのものである 14 。
第二部:二つの世界―「大交易時代」の琉球と戦国時代の日本
『歴代宝案』が記録した時代、特に日本の戦国時代と重なる15世紀から16世紀にかけて、琉球と日本は実に対照的な状況にあった。一方は海洋国家として国際社会の中で安定と繁栄を享受し、もう一方は内乱によって統一性を失い、混乱の中にあった。この対比を理解することが、両者の関係性を読み解く上で不可欠である。
第四章:「万国の津梁」琉球王国の繁栄
東アジアの国際秩序と琉球
15世紀から16世紀にかけての琉球王国は、その歴史上、最も輝かしい黄金期、すなわち「大交易時代」の只中にあった。この繁栄の基盤となっていたのが、明を中心とする東アジアの国際秩序、すなわち冊封・朝貢体制への巧みな適応であった 6 。琉球は1372年に明の冊封を受けて以降、歴代の国王が明皇帝から承認(冊封)を受ける見返りに、定期的に使節を派遣して貢物を献上(朝貢)するという関係を維持した。
この朝貢は、単なる儀礼的な服属関係を意味するものではなかった。それは、莫大な利益を生む公式な貿易の機会であった。『歴代宝案』が成立する以前の記録を含む『明史』によれば、明代を通じて琉球が派遣した朝貢使節の回数は171回に達し、これは2位の安南(ベトナム)の89回や、日本の19回を圧倒的に凌駕するものであった 15 。この頻繁な朝貢を通じて、琉球は中国の高品質な生糸、絹織物、陶磁器などを合法的に、かつ大量に入手する権利を独占的に得ていた。
中継貿易国家としての黄金期
琉球は、この朝貢貿易で得た中国産品を元手として、東南アジアや日本との間で活発な中継貿易を展開した。かつて首里城の正殿に掲げられていた鐘の銘文に刻まれた「万国の津梁(ばんこくのしんりょう)」、すなわち「世界の架け橋」という言葉は、この時代の琉球の役割を見事に表現している 1 。
『歴代宝案』の第一集には、その具体的な活動が詳細に記録されている。琉球船は、北は朝鮮、西は中国大陸、そして南はシャム(アユタヤ朝)、マラッカ、パレンバン(スマトラ島)、ジャワ島など、東シナ海から南シナ海に広がる広大な海域を縦横無尽に航行した 2 。彼らは、東アジアの産物(日本の銅、硫黄、刀剣、扇子や、中国の絹織物、陶磁器)を東南アジアへ運び、その見返りとして東南アジアの特産品(シャムの蘇木(そぼく、赤色染料)、スマトラやジャワの胡椒、丁子(クローブ)などの香辛料、象牙、錫など)を琉球に持ち帰った。そして、それらの南方の物産を再び中国や日本、朝鮮へと転売することで、莫大な利益を上げていたのである。琉球の首都であった那覇の港は、まさにアジア各地の珍しい宝が集まる国際的なハブ港として栄華を極めた。
第五章:分裂と動乱の日本列島
政治状況:中央権力の不在
琉球が国際交易国家として繁栄の頂点にあった頃、日本列島は深刻な政治的混乱の時代を迎えていた。1467年に勃発した応仁の乱を契機として、室町幕府の権威は完全に失墜し、日本は統一された国家としての実体を失った。足利将軍は名目上の権威に過ぎず、各地では守護大名や、彼らにとって代わった戦国大名、さらには有力な寺社勢力などが群雄割拠し、領地の拡大を巡って絶え間ない戦乱を繰り広げていた。
この政治的分裂は、対外関係にも深刻な影響を及ぼした。琉球王国にとって、交渉相手となるべき「日本」という単一の窓口はもはや存在しなかった。彼らが向き合っていたのは、京都の無力な幕府ではなく、九州の島津氏や大内氏といった西日本の有力大名や、堺、博多、坊津(ぼうのつ、鹿児島県)といった自治的な港湾都市の商人たちという、複数の、そして相互に競合する勢力の集合体であった。
経済状況:勘合貿易の機能不全と倭寇
日明間の唯一の公式な貿易ルートであった勘合貿易(勘合符を用いた朝貢貿易)もまた、日本の国内情勢の混乱によって深刻な機能不全に陥っていた。幕府の衰退と共に、勘合貿易の主導権は管領家の細川氏と、西国の大大名である大内氏の手に移り、両者はその利権を巡って激しく対立した。この対立は、1523年に明の港町・寧波(ニンポー)で両者の使節団が武力衝突を起こすという「寧波の乱」にまで発展し、日明関係を著しく悪化させた。最終的に、勘合貿易は16世紀半ばには完全に途絶してしまう 17 。
しかし、日本国内では、戦国大名や新興の商人層の間で、奢侈品や文化的シンボルとして中国産の生糸や陶磁器(唐物)への需要はむしろ高まっていた。公式ルートが閉塞したことで、人々は非公式なルートを通じてでもこれらの品々を渇望するようになった。この状況が、琉球の中継貿易国家としての役割を、日本側から見て一層重要性を増す結果となった。
同時に、日本の政治的混乱は、東アジアの海域全体を脅かす不安定要因を生み出していた。それが「倭寇」と呼ばれる海賊兼密貿易商人集団の活動である。彼らは中国や朝鮮の沿岸部を襲撃し、略奪行為を繰り返した。琉球の交易船もその例外ではなく、倭寇の脅威から積荷と船員を守るため、自衛用の大砲を装備するなど、武装を余儀なくされていた 19 。
このように、15世紀から16世紀にかけての東アジア海域は、琉球の「安定」と日本の「不安定」という、二つの対照的な要素が共存する世界であった。そして、この二つの要素は無関係なのではなく、相互に深く影響を与え合う、いわば表裏一体の関係にあった。琉球の繁栄は、明との安定した政治関係に支えられていた。一方、日本の混乱は、公式な日明貿易を機能不全に陥らせた。その結果、日本の商人たちは、政治的リスクの高い勘合貿易を避け、安定的かつ合法的に中国産品を入手できる琉球の国際市場を目指した 20 。つまり、日本の「不安定」が、琉球の「安定」した交易システムへの需要を喚起し、その繁栄を支える一因となっていたのである。琉球の黄金時代は、日本の戦国時代の混乱と分かちがたく結びついていたと言える。
第三部:『歴代宝案』から読み解く戦国日本と琉球の交点
『歴代宝案』は、琉球側から見た公式な記録である。しかし、その行間を丹念に読み解き、日本側の状況と照らし合わせることで、戦国時代の日本と琉球が織りなした複雑でダイナミックな関係性が浮かび上がってくる。それは、経済的な相互依存と、水面下での政治的な緊張関係が交錯する姿であった。
第六章:経済の結節点としての中継貿易
戦国時代の日本にとって、琉球は単なる隣国ではなく、アジアの広大な市場へとつながる不可欠な経済的結節点であった。勘合貿易の途絶によって公式な対中貿易ルートを失った日本は、琉球を介することで、世界経済のネットワークに組み込まれていたのである。
日本から琉球へ―戦略物資の輸出
戦国時代の日本は、内乱の時代であると同時に、特定の産品を大量に生産する輸出国でもあった。『歴代宝案』には、琉球が中国や東南アジア諸国へ送った進物や交易品のリストが数多く記録されているが、その中には明らかに日本を供給源とする物資が含まれている。
-
刀剣
『歴代宝案』第一集には、1425年に中山王尚巴志がシャム(アユタヤ朝)国王へ宛てた文書の控えがあり、その進物品の中に「刀剣」が明確に記されている 22。また、中国への朝貢品リストにも刀剣は頻繁に登場する 23。戦国時代の日本は、絶え間ない戦闘を通じて刀剣の生産技術が飛躍的に向上し、世界的に見ても最高品質の刀剣を大量生産できる唯一の地域であった。これらの日本刀が琉球を経由して、武具としての需要が高い東南アジアの王国や、権威の象徴として珍重された中国へと再輸出されていたことが強く示唆される。これは、日本の戦争経済が、国内需要を満たすだけでなく、国際市場向けの輸出産業として機能していたことを物語っている。戦争そのものが、輸出可能な商品(武器)を生み出すという、特異な経済サイクルが成立していたのである。 -
銅・硫黄
銅と硫黄もまた、当時の日本の重要な輸出品であった。特に硫黄は、火薬の主原料であり、鉄砲が普及し始めた東アジア世界において極めて重要な戦略物資であった。『歴代宝案』には、琉球がシャムへ一度に2,500斤(約1.5トン)もの硫黄を贈ったという記録が複数回見られる 23。火山国である日本は良質な硫黄の産地であり、この大量の硫黄の供給源は日本であった可能性が極めて高い。日本の戦国大名や商人は、自国の天然資源を琉球を通じて輸出することで、戦争を継続するための軍資金や、必要物資を輸入するための外貨を獲得していたと考えられる。
琉球から日本へ―唐物・南蛮物の輸入
一方で、日本の商人たちは、琉球がアジア中から集めてくる希少な物産を求めて、積極的に海を渡った。特に、自治都市として繁栄し、強力な経済力を持っていた堺や、古くからの対外交易の拠点であった博多、そして南九州の坊津といった港の商人たちは、琉球交易の重要な担い手であった 18 。
彼らが求めたのは、中国産の生糸や絹織物、陶磁器といった「唐物」であり、また、東南アジア産の胡椒や丁子といった香辛料、蘇木のような染料、象牙などの「南蛮物」であった 20 。これらの品々は、戦国大名たちの権威を飾る奢侈品として、また茶の湯などの新しい文化を彩る道具として、日本国内で高い需要があった。
日本の商人たちにとって、琉球は政治的なリスクを回避するための「経済的な迂回路」として極めて重要な役割を果たした。勘合貿易は、幕府や細川氏、大内氏といった特定の政治権力が利権を独占する、極めて政治性の高い貿易であった 17 。これに関与することは、日本の内乱の当事者になるリスクを常に伴った。それに対し、琉球との交易は、純粋な商業活動として行うことができた。琉球は、政治的に中立な国際市場を提供し、あらゆる地域の商人を歓迎した。堺や博多の商人たちは、日本の熾烈な政治的対立から距離を置きつつ、安定的かつ安全に利益を上げるための最適な場所として琉球を選んだのである。琉球王国の存在が、日本の商業資本の成長と蓄積を、陰ながら支えていたと言っても過言ではない。
|
品目 |
主な生産地 |
日本からの輸出品 or 日本への輸入品 |
琉球からの再輸出先 |
『歴代宝案』における言及例 |
|
刀剣 |
日本 |
輸出品 |
シャム、中国 |
22 |
|
銅 |
日本 |
輸出品 |
中国 |
23 |
|
硫黄 |
日本 |
輸出品 |
シャム、中国 |
23 |
|
蘇木(染料) |
シャム、東南アジア |
輸入品 |
中国、日本 |
23 |
|
胡椒・香辛料 |
スマトラ、ジャワなど |
輸入品 |
中国、日本 |
23 |
|
絹織物・陶磁器 |
中国 |
輸入品 |
日本、東南アジア |
20 |
|
象牙・錫 |
東南アジア |
輸入品 |
中国、日本 |
23 |
この表が示すように、琉球は単なる物資の通過点ではなく、多方向からの物資が集積され、付加価値を付けて再分配される、複雑で高度なハブとして機能していた。日本の産品が琉球を通じてアジア各地へ、そしてアジア各地の産品が琉球を通じて日本へという双方向の流れは、戦国時代の日本経済が決して閉鎖的ではなく、琉球を介してグローバルなネットワークに深く組み込まれていたことを明確に示している。
第七章:政治的ダイナミズムと水面下の交渉
経済的には密接な関係にあった琉球と日本だが、その政治的関係は複雑な様相を呈していた。『歴代宝案』は公式な外交文書であるため、その記述は抑制的であるが、背後にある政治的ダイナミズムを読み取ることができる。
統一権力なき日本との「非公式」な関係
『歴代宝案』を精査して気づく最も重要な点の一つは、室町幕府の将軍や天皇といった、当時の日本の公式な中央権力との間のやり取りがほとんど見られないことである。これは、琉球側が、京都にある幕府や朝廷がもはや日本を実効的に統治する能力を失っていることを正確に認識していたことの現れである。琉球の関心は、名目上の権威者ではなく、実利的な交易が可能であり、かつ地政学的に重要な西日本の港市や、それを支配する有力大名に向けられていた。琉球の外交は、極めて現実主義的かつプラグマティックだったのである。
島津氏の台頭と琉球への圧力
16世紀後半、日本の政治情勢が大きく動く中で、琉球の対日関係も新たな段階に入る。九州南部で勢力を拡大し、薩摩・大隅・日向の三国を統一した島津氏が、琉球にとって無視できない隣接勢力として台頭してきたのである 26 。
島津氏は、琉球が独占的に有する対明貿易の莫大な利権に強い関心を抱いていた 27 。当初は交易相手として関係を築いていたが、その勢力拡大に伴い、次第に琉球に対して政治的・軍事的な圧力を強めるようになっていく。
この緊張関係が決定的となったのが、豊臣秀吉による天下統一事業と、それに続く朝鮮出兵(文禄・慶長の役)であった。秀吉は、自らが頂点に立つ新たな国際秩序を構築しようとし、琉球にも服属と軍役負担を要求した。その際、秀吉と琉球の間の交渉窓口となったのが島津氏であった 29 。日本の政治的統一の動きが、それまで巧みな外交で独立を保ってきた琉球の主権を、直接的に脅かし始めたのである。この時期の緊張の高まりは、最終的に豊臣政権崩壊後の1609年(慶長14年)、徳川家康の許可を得た島津氏による琉球侵攻という、琉球王国の歴史を大きく変える出来事へと繋がっていく 30 。
『歴代宝案』自体には、島津氏との直接的で生々しい交渉記録は多くは残されていない。しかし、この時期の琉球の外交文書の背後には、常に日本の政治情勢、とりわけ隣国である島津氏の動向が大きな影を落としていたことは間違いない。この点をより深く理解するためには、『歴代宝案』を琉球側の視点として捉えつつ、島津家が遺した『島津家文書』などの日本側史料と突き合わせ、複眼的な視点で分析することが不可欠である 32 。
第八章:『歴代宝案』が語らないこと―史料の限界と行間を読む
『歴代宝案』は比類なき価値を持つ史料であるが、万能ではない。その性格に由来する限界を認識し、記録の行間を読むことで、より実態に近い歴史像を再構築することができる。
史料の性格的限界
『歴代宝案』は、あくまで琉球王府が管理した「公式な外交文書」の集成である。そのため、国家間の公式なやり取りや、王府が関与した朝貢貿易については詳細な記録が残されている一方で、その枠外で行われていた活動については、ほとんど記録されていない。
例えば、堺や博多の商人たちが、具体的にどれほどの頻度で琉球へ渡航し、どのような規模の交易を行っていたのか、その実態を『歴代宝案』から直接知ることは困難である。また、倭寇に代表されるような、国家の管理を外れた密貿易や私的な交易、個人の往来といった水面下の交流についても、その記録は断片的なものにとどまる。これらの非公式な経済活動の実態を明らかにするためには、『歴代宝案』の記述を補完する、日本側の古文書(例えば『島津家文書』など)や、各地の港から出土する貿易陶磁器などの考古学的な知見と組み合わせた、学際的なアプローチが求められる。
琉球側から見た「日本」像の再構築
これらの限界を踏まえた上で、『歴代宝案』から琉球側が抱いていた「日本」のイメージを再構築することは可能である。琉球の外交官たちの目に映っていたのは、決して統一された国家としての「日本」ではなかった。それは、複数の顔を持つ、複雑で捉えどころのない存在であった。
第一に、日本は高品質な刀剣、銅、硫黄といった、中継貿易に不可欠な「産品の供給源」であった。第二に、堺や博多の商人たちに代表される、唐物や南蛮物を買ってくれる重要な「交易のパートナー」であった。そして第三に、倭寇や、次第に圧力を強めてくる島津氏に象徴される、王国の安全と独立を脅かす「潜在的な脅威」でもあった。
琉球の外交官たちは、このように分裂し、かつ流動的な日本の情勢を冷静に分析し、国益を最大化するために、特定の勢力と深く結びつくことを避け、是々非々の実利的な関係を築いていたと考えられる。彼らにとって、戦国時代の日本は、大きな利益をもたらす「好機」と、いつ牙を剥くかわからない「脅威」が同居する、決して油断のならない隣人だったのである。
結論:戦国史研究における『歴代宝案』の再評価
本報告書は、琉球王国の外交文書集『歴代宝案』を分析の主軸に据え、日本の戦国時代を東アジア海域世界の文脈から捉え直すことを試みた。その分析を通じて明らかになったのは、『歴代宝案』が単なる琉球史の一史料にとどまらず、日本の戦国時代史研究に新たな視角と深みを与える、極めて重要な「鍵」であるという事実である。
総括として、『歴代宝案』が戦国史研究に貢献する点は、以下の三点に集約される。
第一に、 経済史の視点 からの貢献である。『歴代宝案』の記録は、戦国時代の日本経済が、内需や領国経済だけで完結していたのではなく、琉球という結節点を介して、東アジア・東南アジアの広大な国際貿易ネットワークと深く連動していたことを実証する。特に、刀剣や硫黄といった物資の輸出は、日本の戦争経済が、戦争の副産物を輸出して外貨を獲得するという「戦争輸出経済」とも言うべき側面を持っていたことを示唆しており、戦国時代の経済構造をより立体的に理解する上で新たな視点を提供する。
第二に、 国際関係史の視点 からの貢献である。統一された外交主体を欠き、内乱状態にあった日本が、国際社会からどのように認識され、どのように扱われていたのか。『歴代宝案』は、琉球という最も近しい隣人の視点から、その実態を垣間見せてくれる。そこに見えるのは、中央の権威(幕府)が無視され、実利的な交易が可能な西日本の勢力(大名や商人)が交渉相手として選択されるという、極めて現実主義的な国際関係の姿である。これは、戦国時代を「内から」見る視点だけでは得られない、貴重な外部からの客観的な評価軸を与えてくれる。
第三に、 グローバルヒストリーの視点 からの貢献である。『歴代宝案』は、戦国時代の日本で起きていた事象を、日本列島という閉じた空間から解き放つ。日本の戦乱が生み出した刀剣が、琉球船によってシャムの王宮に届けられ、日本の火山が生んだ硫黄が、東南アジアのどこかで火薬に姿を変えていたかもしれない。このように、『歴代宝案』は、日本の地域史を、より広範な世界のモノ・ヒト・情報の動きの中に位置付けることを可能にし、戦国時代を世界史的な文脈の中で捉え直すための具体的な証拠を提供する。
今後の展望として、『歴代宝案』の研究は、日本の戦国史と東アジア海域史という、これまでやや別個に扱われがちであった二つの研究領域を架橋する、極めて重要な役割を担うであろう。今後、日本側の各種史料や、貿易陶磁器などの考古学的知見とのさらなる統合研究を進めることで、我々が知る戦国時代の貌は、より豊かで、立体的で、そして世界に開かれたものへと変貌していくに違いない。
引用文献
- 歴代宝案の栞 (PDF 4.5MB) - 沖縄県 https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/665/rekidaishiori2018.pdf
- 朝貢国・琉球における「朝貢」と「貿易」 https://www.chikyu.ac.jp/sociosys/PDF/okamoto-01.pdf
- Ⅸ 史料編集事業 - 沖縄県 https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/314/h2909.pdf
- 宝案入門 ―海 ... - 琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ https://ryuoki-archive.jp/columns/d_columns/3188/
- 『歴代宝案』という名称の由来について - 琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ https://ryuoki-archive.jp/columns/d_columns/2050/
- 漢文で書かれた『歴代宝案』の意味 - 琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ https://ryuoki-archive.jp/columns/d_columns/2011/
- Untitled - 琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ https://ryuoki-archive.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/koutei01-02_kaisetu.pdf
- 那覇市歴史博物館所蔵 「 歴代宝案」に関する史料学的考察 一生成 ... http://www.edu.city.naha.okinawa.jp/tsuboya/kiyou/kiyou13%20jun.pdf
- ryuoki-archive.jp https://ryuoki-archive.jp/columns/d_columns/3188/#:~:text=%E3%80%8E%E6%AD%B4%E4%BB%A3%E5%AE%9D%E6%A1%88%E3%80%8F%E3%81%AE%E6%A7%8B%E6%88%90,%E9%A0%86%E3%81%AB%E5%8F%8E%E9%8C%B2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 歴代宝案 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B4%E4%BB%A3%E5%AE%9D%E6%A1%88
- 続 2・3・2 15-16世紀東アジア、朝貢と密貿易、琉球の世界 http://koekisi.web.fc2.com/koekisi2/page012.html
- 『歴代宝案』と档案史料 - 琉球大学学術リポジトリ https://u-ryukyu.repo.nii.ac.jp/record/2011998/files/No5p001-015.pdf
- 史料編集事業 - 沖縄県 https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/309/10.pdf
- 歴史の虫眼鏡 歴代宝案―琉球王国の外交史料 - おきでん百添アワー 「ウチナー紀聞」公式サイト|毎週日曜日 11:00放送|美しい沖縄の風景・文化・歴史・人を映像で伝えるテレビ番組 https://uchina-kibun.com/list/2024/05/21/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AE%E8%99%AB%E7%9C%BC%E9%8F%A1%E3%80%80%E6%AD%B4%E4%BB%A3%E5%AE%9D%E6%A1%88%E2%80%95%E7%90%89%E7%90%83%E7%8E%8B%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%A4%96%E4%BA%A4%E5%8F%B2%E6%96%99/
- 高良 倉吉氏 - 日本海事センター https://www.jpmac.or.jp/file/105_2.pdf
- 大航海時代の海域アジアと琉球|出版 - 思文閣 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/list/9784784219896/
- 海上交易と島津氏 - 鹿児島ぶら歩き - Seesaa http://burakago.seesaa.net/article/417250961.html
- 琉球王国を江戸時代に支配した薩摩藩。その目的は貿易の独占? - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/18457/
- 《東アジアのハブ》として栄えた海の王国・沖縄|キーワードで探る琉球王国の秘密① https://discoverjapan-web.com/article/130593
- 古琉球と琉球王国 | 日本近現代史のWEB講座 http://jugyo-jh.com/nihonsi/%E8%BF%91%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E5%8F%B2%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E8%AC%9B%E5%BA%A7/%E5%8F%A4%E7%90%89%E7%90%83%E3%81%A8%E7%90%89%E7%90%83%E7%8E%8B%E5%9B%BD/
- 総合研究所所報 - 甲南大学 https://www.konan-u.ac.jp/souken/wp-content/uploads/2015/02/ccfdff4f45cd424f0639aea5351a1f7b.pdf
- 【1089ブログ】琉球の船が運んだもの - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/rblog/1/2022/06/09/ryukyu_6/
- 琉球王国の外交文書ーよみがえる『歴代宝案』ー https://ryuoki-archive.jp/wp/wp-content/uploads/2022/12/kityoukouen.pdf
- 琉球の進貢品-硫黄編 - 琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ https://ryuoki-archive.jp/columns/d_columns/2278/
- 呂宋の海へ~アジアネットワークの中の堺~(1) | つーる・ど・堺【堺・南大阪の地域情報】 https://toursakai.jp/2018/post_201/
- 琉球の朝貢と冊封の歴史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E3%81%AE%E6%9C%9D%E8%B2%A2%E3%81%A8%E5%86%8A%E5%B0%81%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2
- 琉球出兵 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/pr/gaiyou/rekishi/tyuusei/ryukyu.html
- 琉球王国/琉球帰属問題 - 世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh07-035.html
- 秀吉と島津氏と琉球の関係 - 沖縄の歴史 http://rca.open.ed.jp/history/story/epoch3/shinryaku_1.html
- 交流史資料紹介 - 琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ https://ryuoki-archive.jp/ryu-search/d_public/
- 琉球王国を江戸時代に支配した薩摩藩。その目的は貿易の独占? (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/18457/?pg=2
- 東京大学史料編纂所蔵島津家本『琉球外国関係文書』目録 https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/personal/yokoyama/okinawa/frame.htm
- 島津氏関係文書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/581953