漢書
『漢書』は班固ら編纂の前漢正史。戦国武将は統治・軍事・人間形成の鏡とし、領国経営や天下統一の指針とした。家訓にも影響を与え、徳川家康も重用。近世社会を形成せし源流。
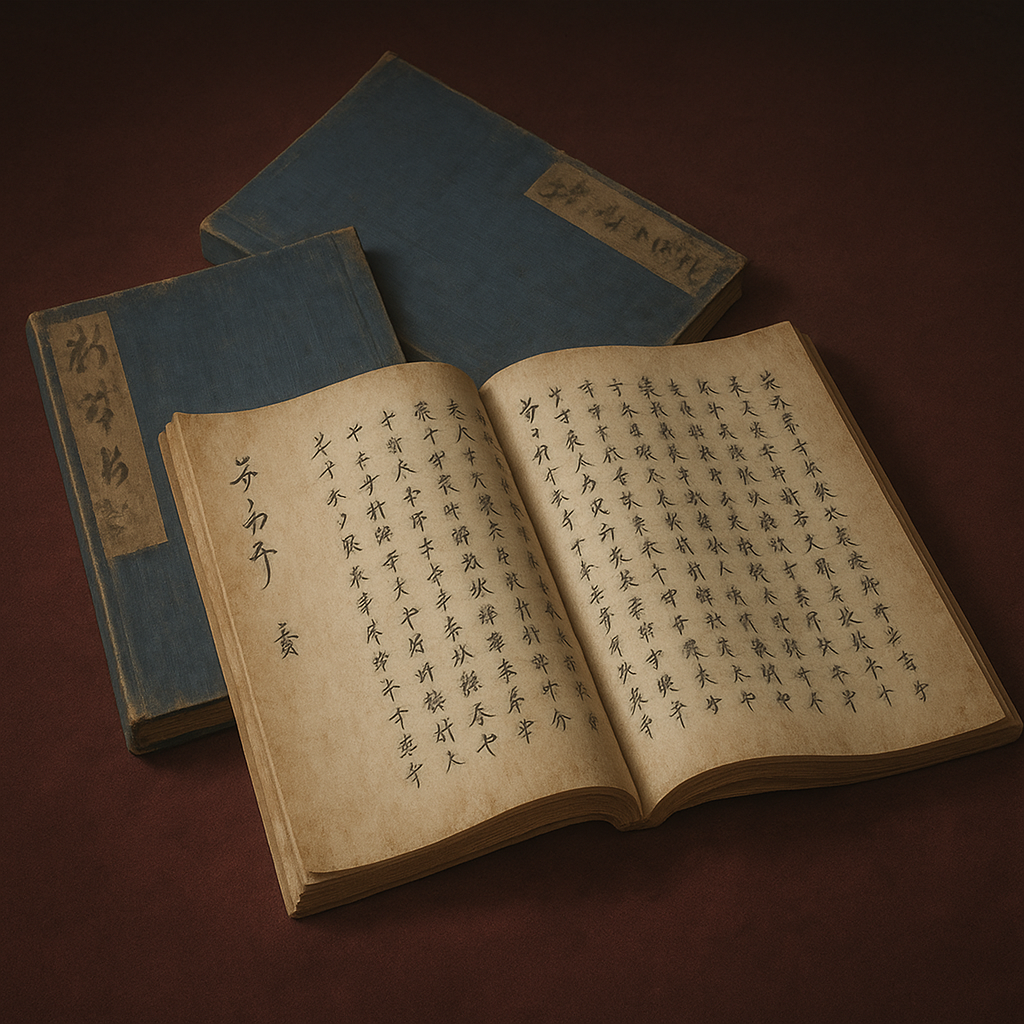
『漢書』の深層分析:日本の戦国時代という視点から
序論:乱世の鏡としての『漢書』
後漢の班固らによって編纂された『漢書』は、中国前漢一代の歴史を記した、紀伝体の正史である。高祖劉邦の建国から武帝の匈奴征伐、そして王莽による簒奪に至るまでの約230年間の興亡を、荘重かつ格調高い筆致で描き出している。その史料的価値は、司馬遷の『史記』と双璧をなし、後世の歴史叙述の不動の規範となった。
しかし、本書の価値は単なる古代中国史の記録に留まらない。本報告書は、この中国古典を「日本の戦国時代」という特異なレンズを通して再検証し、その多層的な意義を徹底的に解明することを目的とする。すなわち、下剋上が常態化し、旧来の権威が失墜した戦乱の世において、天下統一を目指す武将たちが、遠い異国の、数百年以上も前の王朝史にいかなる実践的価値を見出したのかという問いを探求するものである。
彼らにとって『漢書』は、単なる教養や趣味の対象ではなかった。それは、自らが生きる乱世を映し出し、新たな統治体制を構想するための「鏡」であり、国家経営の「教科書」であり、そして武人としての生き方を律する「修養の書」であった。本報告書では、『漢書』そのものの詳細な分析から始め、日本における受容史を概観した上で、戦国という時代に焦点を絞り、この偉大な歴史書が統治、軍事戦略、そして人間形成の各側面において果たした役割を重層的に明らかにしていく。
第一部:『漢書』の全体像 — 編纂、構成、思想的特質
戦国武将たちが『漢書』に何を見出したかを理解するためには、まずこの書物がいかなる背景と意図のもとに生み出されたのかを深く知る必要がある。その編纂過程、構成、そして根底に流れる思想は、後世の読者、特に権力者たちにとって重要な意味を持っていた。
第一章:班氏一族の偉業
『漢書』の完成は、一個人の天才によるものではなく、班氏一族三代にわたる数十年の歳月をかけた知の継承と情熱の結晶であった。
その端緒を開いたのは、後漢初期の学者であった父・班彪(はんぴょう)である。彼は、司馬遷の『史記』が漢の武帝の治世半ばで途絶えていることを惜しみ、その後を継ぐべく『史記後伝』65篇を著した。これは、歴史を連続したものとして捉え、自らが生きる時代の正統性を過去に求めるという、儒教的知識人の使命感の表れであった。
父の死後、長子の班固がその遺志を継いで本格的な編纂に着手する。しかし、この事業は大きな困難を伴った。「私的に国史を修訂する」という行為は、朝廷への潜在的な批判と見なされかねない、極めて危険なものであった。案の定、班固は他者からの密告により「国史を私的に改竄し、不軌を企てている」との嫌疑をかけられ、逮捕・投獄されるという憂き目に遭う。
この窮地を救ったのが、弟の班超(はんちょう)であった。彼は都に駆けつけ、兄の事業が父の遺志を継ぎ、漢王朝の徳を称揚するものであって、決して国家を謗るものではないことを皇帝に力説した。その訴えが聞き入れられ、班固の草稿に目を通した明帝は、その卓越した才能と内容を高く評価し、彼を釈放した。さらに、宮中の図書を管理する蘭台令史に任命し、国家の蔵書を自由に閲覧する便宜を与えた。これにより、班固の事業は私的な編纂から国家的な大事業へと昇華し、20年以上の歳月をかけてその大部分を完成させたのである。
しかし、班固は晩年、政争に巻き込まれて無念の獄死を遂げる。この時、『漢書』の「八表」と「天文志」は未完のままであった。この父兄の偉業を完成させたのが、妹の班昭(はんしょう)である。彼女は和帝の勅命を受け、宮中の東観蔵書閣にて作業を引き継ぎ、ついにこの歴史的大著を完成させた。また、馬続(ばしょく)という学者も「天文志」の作成を補佐したとされる。
班固の逮捕と、その後の国家的事業への転換という経緯は、『漢書』が単なる学術書ではなく、「国家公認の正史」という絶大な権威を持つことを示している。歴史の解釈と記述は、王朝の正統性を担保する重要な政治行為であり、その公的な権威は、後の時代の為政者たちがこの書を重視する大きな理由となった。
第二章:歴史叙述の新たな地平
『漢書』が画期的であったのは、その内容のみならず、歴史叙述の形式において新たな地平を切り開いた点にある。
最大の特徴は、中国史上初の「断代史」という形式を確立したことである。神話の時代から前漢の武帝期までを網羅した司馬遷の『史記』が「通史」であるのに対し、『漢書』は前漢という一つの王朝の始終に限定して記述した。この「一王朝一史書」という形式は、後の各王朝が自らの正史を編纂する際の不動の規範となった。
構成においては、『史記』の紀伝体(本紀・表・志・列伝から成る歴史叙述形式)を継承しつつも、重要な変更を加えている。第一に、諸侯の記録である「世家」を廃止し、その内容を皇帝一族は「本紀」に、その他の人物は「列伝」に吸収した。第二に、社会制度や文化を分野別に記述した「書」を「志」と改称し、律暦、礼楽、刑法、食貨、地理、芸文など、より体系的に国家の諸制度を網羅した。第三に、「表」の部門を拡充し、官職制度の変遷を示す「百官公卿表」や、古代から秦までの著名人を儒教的価値観に基づいて九段階に格付けした「古今人表」などを新たに創設した。
これらの変更は、単なる形式上の違いに留まらない。それは、班固の歴史観、ひいては漢王朝の国家イデオロギーを色濃く反映している。「世家」の廃止は、皇帝を唯一絶対の中心とし、諸侯の相対的な独立性を認めない、中央集権的な国家観の表れである。また、「志」の充実は、国家を英雄個人の活躍譚としてだけでなく、法制度や経済、文化といった「システム」の集合体として体系的に捉えようとする視点の確立を示している。群雄が割拠し、実力主義が支配する戦国時代の武将たちにとって、この中央集権的で体系的な国家像は、天下統一後の新たな統治体制を構想する上で、極めて重要な示唆を与えるものであった。
【表1:『史記』と『漢書』の構成比較】
|
項目 |
『史記』(司馬遷) |
『漢書』(班固ら) |
備考(思想的・形式的変化) |
|
形式 |
通史 |
断代史 |
前漢一代に限定。後の正史の規範となる。 |
|
本紀 |
12巻(帝王の記録) |
12巻(帝王の記録) |
継承。ただし項羽を本紀から列伝に格下げし、漢の正統性を強調。 |
|
表 |
10巻(年表) |
8巻(年表) |
**「百官公卿表」「古今人表」**などを新設し、制度史と人物評価の視点を強化。 |
|
書 |
8巻(制度・文化史) |
- |
「志」に改称・発展。 |
|
志 |
- |
10巻(制度・文化史) |
「書」を継承し、律暦、礼楽、刑法、食貨、地理など、より体系的に国家制度を記述。 |
|
世家 |
30巻(諸侯の記録) |
- |
**廃止。**皇帝中心の中央集権的国家観を反映。諸侯は列伝に吸収。 |
|
列伝 |
70巻(個人の伝記) |
70巻(個人の伝記) |
継承。 |
|
総数 |
130巻 |
100巻(現行本は120巻) |
|
第三章:儒教国家の理想像
『漢書』と『史記』の最も顕著な違いの一つは、その根底に流れる思想にある。『史記』が時に敗者や反逆者にも共感的な筆致を向け、多様な価値観を許容する自由闊達な精神に貫かれているのに対し、『漢書』は儒教の価値観を絶対的な基準とし、それに基づいて人物や出来事を厳格に評価する傾向が強い。その最大の目的は、漢王朝の正統性と、その統治が天命に基づく徳によるものであることを称揚することにあった。
その思想的立場は、具体的な記述にも明確に表れている。例えば、『史記』では王に匹敵する英雄として「本紀」に立てられた項羽や、反乱の指導者でありながら諸侯に準ずる「世家」に位置づけられた陳渉を、『漢書』ではいずれも臣下の伝記である「列伝」へと格下げしている。これは、漢王朝こそが天命を受けた唯一の正統な王朝であるという歴史観を明確に示すための編集方針であった。
文体においては、詔勅や上奏文などをそのまま引用する箇所が多く、物語としての劇的な面白さでは『史記』に一歩譲ると評価されることもあるが、その分、史料としての正確性や客観性は高いとされている。そして、その文章は極めて荘重かつ典雅であり、対句表現を多用した華麗な格調は、後漢の貴族階級の間で文章作成の最高の手本とされたほど、文学的にも高く評価されている。この整然とした構成と儒教的価値観に裏打ちされた格調の高さは、『漢書』に国家の公式な歴史書としての威厳を与えている。
第二部:日本における『漢書』受容の潮流 — 古代から中世へ
戦国時代における『漢書』の受容を論じる前提として、それ以前の日本でこの書物がいかに受け入れられ、読み継がれてきたかを理解することが不可欠である。漢籍は、日本の国家形成と文化の発展に深く関わってきた。
第一章:古代国家の形成と漢籍
漢籍そのものは、古代より日本列島に伝来し、朝廷や有力氏族によって貴重な知識の源泉として収集・受容されていた。奈良時代の正倉院文書や出土木簡は、当時の官人たちが漢籍を学び、行政に活用していた実態を物語っている。
特に7世紀から8世紀にかけての律令国家形成期において、中国の制度や思想は国家建設の重要なモデルであった。『日本書紀』の編纂に見られるように、日本の為政者たちは中国の正史を手本として自らの歴史を記述し、国家の正統性を示そうと試みた。また、淡海三船が歴代天皇に漢風諡号を追贈した事実は、中国文化への深い理解が国家の威信を高める上で不可欠と考えられていたことを示している。
このような文脈の中で、『漢書』は極めて重要な位置を占めていた。とりわけその「地理志」に見える「夫れ楽浪海中に倭人有り、分かれて百余国を為す。歳時を以て来たり献見すと云う」という一節は、中国の正史に現れる日本(倭)に関する最古級の記録である。この記述は、古代日本の人々が、大陸の巨大な文明世界の中に自らを位置づけ、客観的に認識するための最初の拠り所となった。それは、当時の日本が多数の小国に分立していたこと、そして紀元前の段階で既に漢王朝と朝貢関係にあったことを示す、動かぬ証拠であった。
平安時代に入ると、漢籍、特に『白氏文集』などの漢詩文は、貴族社会における必須の教養となった。『源氏物語』や『枕草子』といった国風文化の精華とされる作品にも漢籍からの引用が随所に見られ、漢学の素養が個人の文化的洗練度を測る重要な指標であったことがうかがえる。
第二章:知の担い手としての禅僧
鎌倉・室町時代になると、漢籍研究の中心的な担い手は、公家社会から五山を中心とする禅宗寺院へと移行していく。
京都と鎌倉に置かれた五山の禅僧たちは、禅の修行に励むと同時に、漢詩文の創作活動(五山文学)に情熱を注ぎ、高度な漢学の知識を蓄積・発展させた。彼らは自らの学識を深め、後進を育成するために、経書や史書といった漢籍の講義を盛んに行った。その講義録は「抄物(しょうもの)」と呼ばれる独自の形式で書き留められ、中世日本の学問における貴重な知的遺産となった。
『漢書』もまた、これらの学僧たちによる講義の重要なテキストの一つであった。記録によれば、特に桃源瑞仙(とうげんずいせん)や景徐周麟(けいじょしゅうりん)といった高名な学僧が『漢書』の講義を行い、『漢書抄』という抄物を残している。これらの抄物は、単なる先行注釈の書き写しではなく、複数の講義録や中国の注釈書を比較検討し、さらには自らの見解を加えて再構成された、極めて高度な研究成果であった。
この事実は、戦国時代の武将たちが漢籍の知識を得る過程を考える上で、決定的に重要である。彼らの多くは、原典を直接読み解いたのではなく、教育係や政治顧問として仕えた禅僧という「知的フィルター」を通して、解釈され、日本向けに「加工」された知識を吸収していたのである。武将たちに提供された『漢書』の知識は、単なる文字の翻訳ではなかった。それは、禅や儒教の思想的文脈で再解釈され、当時の日本の社会情勢に照らし合わせて意味づけされた「生きた知」であった。この知的伝統の蓄積こそが、異国の古典を戦国武将にとって実践的な指針へと変える、重要な触媒となったのである。
第三部:戦国時代という視点 — 乱世の武将と『漢書』
戦国時代は、武力による下剋上が支配する一方で、各大名が領国経営の安定化と支配の正当性を模索した時代でもあった。この時代、漢籍、とりわけ『漢書』は、乱世を生き抜くための実践的な知の宝庫として、武将たちに新たな価値を見出されていく。
第一章:統治の教科書として — 経済・法制思想の参照
戦国大名たちは、自らの領国を安定的に支配するために、「分国法」と呼ばれる独自の法律を制定した。これは、単なる武力による支配から、法に基づく秩序ある統治へと移行しようとする意志の表れであり、その思想的背景には、中国の正史に描かれた国家経営の理念が影響していたと考えられる。
その格好の典拠となったのが、『漢書』の「志」の部分である。特に「食貨志」は、国家の根幹をなす「食」(農業)と「貨」(商業・財貨)について論じ、土地制度、税制、専売、貨幣制度といった国家の経済政策全般を体系的に記述したものであった。例えば、織田信長が実施した楽市楽座や関所の撤廃といった商業振興策、あるいは後北条氏が精力的に進めた検地の徹底、税制改革、通貨統一といった先進的な領国経営は、『漢書』食貨志に描かれた、国家が経済に積極的に関与して民生の安定を図るという思想と軌を一にする。直接的な引用の有無にかかわらず、彼らが目指した統治の理想像として参照された可能性は極めて高い。
同様に、「刑法志」は、刑罰の起源を天地の秩序に求め、礼教による教化を主とし、刑罰をその補助的なものと位置づける儒教的な法思想を説いている。中でも、漢の高祖・劉邦が秦の煩雑で苛烈な法律を廃し、民心を得るために「法三章」(殺人の罪、傷害の罪、窃盗の罪のみを問う)に簡素化したという逸話は、為政者の鑑として広く知られていた。領民の支持が支配の安定に直結する戦国時代において、この思想は武将たちに重要な示唆を与えたであろう。
戦国武将がこれらの制度論に関心を寄せたのは、単に富国強兵策のヒントを求めたからだけではない。より根源的には、自らの武力による実力支配を、天下の秩序を回復し民を安んじるための「公的な統治」へと昇華させ、その正当性を確立するための理論的根拠を求めていたからである。『漢書』は、その「公」の論理を提供する、最高の教科書であった。
第二章:兵法の鏡として — 高祖・武帝の戦略と戦術
戦国武将にとって、『孫子』や『三略』といった専門的な兵法書が必読であったことは言うまでもない。しかし彼らは同時に、『史記』や『漢書』に描かれる実際の戦史を、より大局的な戦略や政略を学ぶためのケーススタディとして重視した。
特に『漢書』が描く二人の皇帝の姿は、対照的ながらも示唆に富むものであった。一人は、漢の創業者である高祖・劉邦である。彼は無位無官の庶民から身を起こし、わずか数年で天下を統一した英雄として描かれている。その成功の要因は、個人的な武勇よりも、韓信や張良、蕭何といった優れた臣下の才能を見抜き、その言をよく聞き入れた度量の広さ、そして宿敵・項羽とは対照的に、寛容さをもって人心を掌握した点にあるとされている。この物語は、下剋上が常であった戦国武将たちにとって、自らの境遇を重ね合わせやすい、魅力的な成功モデルであった。
もう一人は、漢の最盛期を築いた武帝である。彼が主導した大規模な対匈奴戦争の記述は、国家の総力を挙げた一大軍事キャンペーンの実例として、武将たちの構想力を刺激した。衛青や霍去病といった出自にとらわれず有能な将軍を抜擢し、数万の騎兵を中核とする機動部隊を編成して、長距離遠征を敢行する戦術は、単なる一城一国の争奪戦を超えた、天下統一後の国家戦略を構想する上で、重要な参照点となったのである。
第三章:武将の教養と人間形成 — 家訓に見る漢籍の影響
漢籍の知識は、国家経営や軍事戦略といったマクロな領域だけでなく、武将個人の倫理観や行動規範、すなわち人間形成にも深く浸透していた。その実態を如実に示すのが、各家に遺された「家訓」である。
その代表例が、武田信玄の弟・信繁が遺したとされる『武田信繁家訓』(九十九箇条)である。この家訓は、その条文のほとんどに典拠となる漢籍の一節が引用されていることで知られる。引用される書物は『論語』が最も多いが、『史記』や『老子』と並んで『漢書』も含まれており、漢籍の教えが武士の具体的な行動規範を形成する上で、いかに直接的な典拠となっていたかを示す好例である。
他の武将の遺訓にも、同様の傾向が見られる。例えば、伊達政宗が遺したとされる「五常訓」は、儒教の基本徳目である「仁・義・礼・智・信」について、「仁に過ぐれば弱くなる。義に過ぐれば固くなる」と、それぞれが過剰になることの弊害を説き、バランスの重要性を強調している。これは、儒教の教えを深く理解し、自らの経験に照らして実践的な教訓へと昇華させた、優れた洞察を示している。また、黒田如水・長政父子の遺訓には、「君罰(主君からの罰)よりも民罰(民衆からの反発)が最も恐ろしい」という一節があり、民を治世の根本と見なす民本主義的な思想がうかがえる。これは、『漢書』をはじめとする中国の歴史書に繰り返し現れる「民は国の本なり」という思想の反映に他ならない。
これらの家訓は、漢籍が単なる知識ではなく、戦国武将の内面に深く根を下ろし、彼らの世界観や倫理観を形成する上で不可欠な要素であったことを雄弁に物語っている。
第四章:天下統一の思想的基盤 — 徳川家康の漢籍活用
戦国時代における漢籍受容の潮流は、徳川家康という人物において一つの頂点を迎える。家康にとって漢籍は、個人の教養や統治術の参考というレベルを超え、戦国乱世を終結させ、新たに構築する江戸幕府の支配体制そのものを正当化し、安定させるための「国家イデオロギー」を創出する事業の中核に位置づけられていた。
家康は、戦国武将の中でも際立って学問への関心が高く、特に漢籍の収集と学習に生涯を通じて情熱を注いだ。その学問的素地は、今川家の人質時代に受けた禅僧・太原雪斎の教育に源流を持つとされる。天下人となった後、彼は藤原惺窩や林羅山といった当代一流の儒学者をブレーンとして重用し、彼らの知識を幕府の制度設計や外交政策に積極的に活用した。
家康の事業で特筆すべきは、先進的な出版活動である。彼は関ヶ原の戦いの前から、朝鮮伝来の銅活字印刷技術を用いて、『貞観政要』や『群書治要』といった帝王学の書を次々と刊行した(伏見版・駿河版)。これは、武力のみに頼る「武断政治」から、学問と徳に基づく「文治政治」へと国家のあり方を転換させようとする、壮大な文化戦略であった。
さらに、彼は膨大な古典籍の収集にも心血を注いだ。駿府城に築かれた蔵書群(駿河文庫)は、後の江戸城紅葉山文庫の基礎となり、幕府の知の中枢を形成した。また、京都五山の禅僧たちに命じて大規模な古典籍の書写事業を行わせるなど、散逸しがちな知の遺産を国家事業として保存・集積することに多大な努力を払った。
この文脈において、『漢書』が持つ意味は大きい。朱子学が説く「大義名分論」や上下秩序の絶対性が、将軍を頂点とする幕藩体制を理論的に支えるイデオロギーであったとすれば、『漢書』は、儒教を国家教学とし、皇帝を中心とする強力な中央集権体制を確立した漢王朝の成功譚として、その思想を裏付ける最高の歴史的実例を提供した。家康の一連の事業は、戦国時代の漢籍受容の集大成であり、武士が単なる「戦う者」から「治める者」へと自己変革を遂げるための、思想的インフラ整備であったと言える。
結論:戦国時代における『漢書』の多層的価値
後漢の班固らによって編纂された『漢書』は、日本の戦国時代において、単なる異国の歴史書という枠を遥かに超えた多層的な価値を有していた。それは、乱世を生きる武将たちにとって、実践的な知の宝庫であり、未来を構想するための不可欠な羅針盤であった。
第一に、『漢書』は**「統治の教科書」**であった。「食貨志」や「刑法志」に描かれた体系的な国家経営の理念は、戦国大名が分国法を定め、領国経済を安定させようとする際に、その思想的根拠とモデルを提供した。武力による支配を、法と仁政に基づく「公」の統治へと昇華させるための理論的支柱となったのである。
第二に、それは**「兵法の鏡」**であった。高祖劉邦の天下統一の過程や、武帝による対外戦争の記録は、専門的な兵法書とは異なる、より大局的な戦略眼や政略的思考を養うための絶好のケーススタディを提供した。王朝興亡のダイナミズムは、武将たちに歴史の教訓を学び取らせ、自らの戦略を練る上でのインスピレーションを与えた。
第三に、それは**「修養の書」**であった。武田信繁や伊達政宗らの家訓に見られるように、『漢書』を含む漢籍の教えは、武将個人の内面に深く浸透し、為政者として、また一人の武人としての倫理観や行動規範を形成する上で重要な役割を果たした。
戦国時代を通じて深化した『漢書』をはじめとする漢籍の受容は、徳川家康による天下統一事業において、新たな統治イデオロギーの基盤として結実した。武士階級が漢学の素養を必須の教養とする江戸時代の「文治主義」は、戦国武将たちの知への渇望と、乱世における実践なくしてはあり得なかった。『漢書』が描いた統一王朝の理想と現実は、時代と国境を超えて日本の武将たちに響き続け、日本の近世社会を形成する上での思想的源流の一つとなったのである。