落穂集
『地方落穂集』は、江戸中期の地方行政実務書。戦国期の検地・訴訟制度が近世へ継承・変容し、安定した統治システムへと定着する様を克明に記す。戦国から近世へのダイナミズムを映す「制度の化石」である。
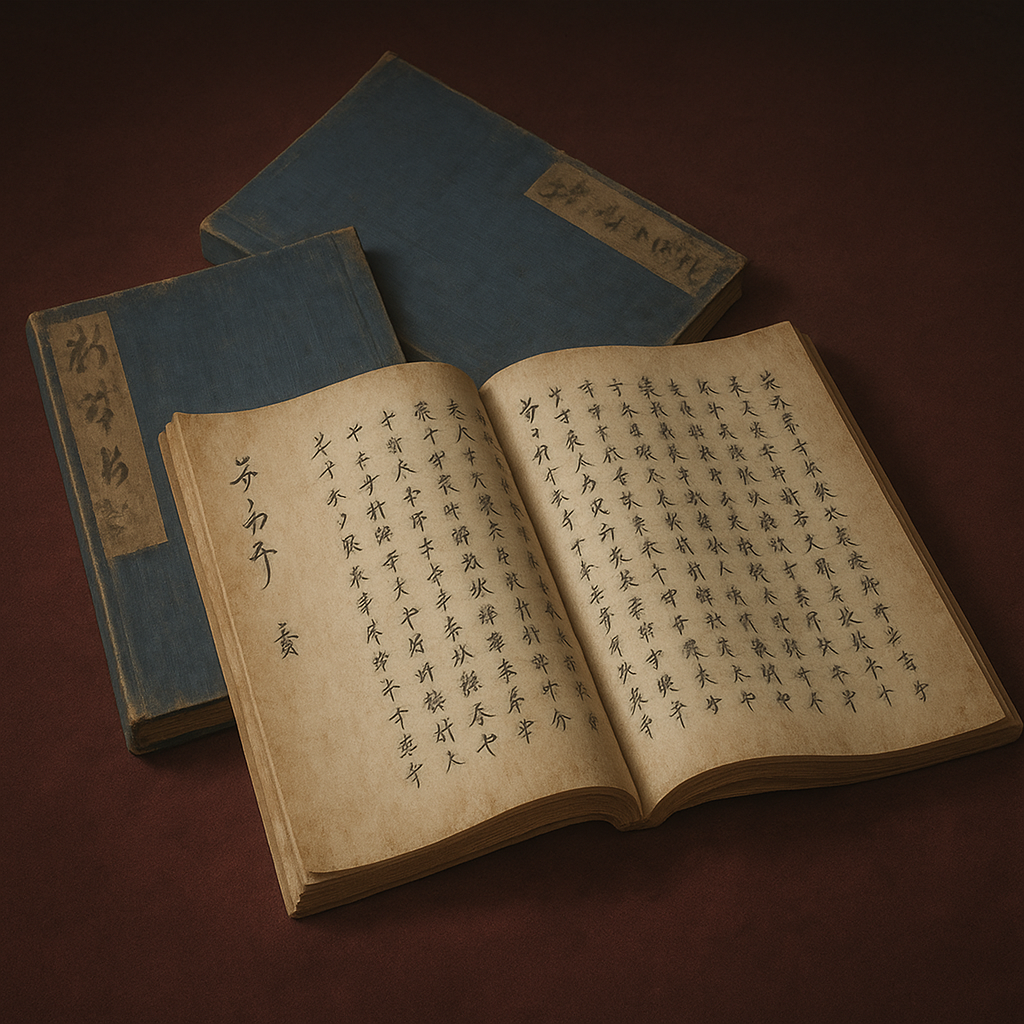
『落穂集』から読み解く戦国統治システムの遺産と変容
序論:『落穂集』研究の視座設定
本報告書は、江戸時代中期に成立した地方行政実務書『地方落穂集』を、戦国時代に生起した統治システムの大変革、すなわち土地支配と法秩序の再編が、いかにして安定した近世的支配体制へと制度化・日常化されたかを解明するための、絶好の史料として位置づけるものである。したがって、本書を単に江戸時代の一文献として解説するのではなく、「戦国時代の帰結」という歴史的連続性の視座から徹底的に分析することを目的とする。
調査を進めるにあたり、「落穂集」という名称を持つ文献が複数存在することが明らかになった 1 。これらは徳川家康の言行録、大坂の風俗誌、あるいは個人の著作など多岐にわたり、それぞれ異なる文脈で編纂されたものである。本報告書では、利用者の関心事である法制度・経済に関する記述が特に豊富な『地方落穂集』を主たる分析対象とする 5 。この選定は、同書が戦国時代に端を発する近世的な土地制度と訴訟制度の定着過程を最も具体的に示しているという判断に基づく。
分析の枠組みとして、本報告書は三部構成をとる。第一部では、まず分析対象である『地方落穂集』を、他の同名異本と明確に区別し、その文献学的正体を特定する。第二部では、歴史的背景として、戦国時代に起こった土地支配と法秩序における「統治革命」を概観する。具体的には、太閤検地に代表される検地制度の変遷と、喧嘩両成敗に象徴される裁判権の確立を論じる。そして第三部において、『地方落穂集』の具体的な記述内容と、第二部で論じた戦国期の制度的遺産とを接続させ、革命的な政策が日常的な行政実務へと変容していく様相を明らかにする。最後に結論として、これら全体の分析を総括し、『地方落穂集』が持つ歴史的意義を提示する。
第一部:『落穂集』の正体 ― 文献学的整理と特定
第一章:錯綜する「落穂集」
「落穂集」という書名は、特定の単一の著作を指すものではなく、江戸時代を通じて様々な主題と目的の下で編まれた複数の文献に用いられてきた。この多義性は、分析対象を明確化する上で最初の課題となる。主要なものを整理すると、以下の通りである。
- 大道寺友山著『落穂集』 : 江戸時代前期から中期の兵法家、大道寺友山(重祐)によって著されたとされる文献群。これには二つの主要な形式が存在する。一つは、1542年(天文11年)の徳川家康の誕生から1615年(元和元年)の大坂の陣後までを編年体で記述した聞書であり、もう一つは、家康をはじめとする諸大名や武家の逸話、江戸の世相などを問答形式で記したものである 4 。両者ともに享保12年から13年(1727年-1728年)頃の成立とされ、武士の心得や徳川治世の称揚といった性格が強く、本報告書の主題である地方行政の実務とは趣を異にする 1 。
- 浜松歌国著『摂陽落穂集』 : 幕末期に大坂で活躍した狂言作者、浜松歌国(1776年-1827年)による著作。これは近世大坂の風俗や世相を生き生きと描き出した年代記、随筆であり、『御治世見聞録摂陽年鑑』などと並ぶ、都市文化史の貴重な資料である 3 。しかし、これもまた幕府や藩の地方支配制度を体系的に論じたものではない。
- その他の『落穂集』 : 上記以外にも、「落穂集」の名を持つ文献は散見される。例えば、華道家元池坊総務所が編纂した華道書や 2 、特定の個人の回想録 2 、さらにはバハイ教の宗教的文書に至るまで、その内容は極めて多様である 6 。
このように、単に「落穂集」という名称だけでは、その内容を特定することは不可能である。したがって、本報告書が主題とする「検地や訴訟など、当時の法制度や経済に関する記述が豊富」な文献は、これらのいずれでもなく、次に詳述する『地方落穂集』であることを明確にする必要がある。
表1:主要な「落穂集」の比較
|
書名 |
推定著者 |
推定成立年代 |
主題・内容 |
文献の性格 |
|
落穂集 |
大道寺友山 |
享保12-13年 (1727-28年) 頃 |
徳川家康の事績、武家の逸話、江戸の世相 |
聞書、武家故実書 |
|
摂陽落穂集 |
浜松歌国 |
19世紀前半 (化政期頃) |
近世大坂の風俗、世相 |
年代記、随筆 |
|
地方落穂集 |
武陽隠士泰路 |
宝暦13年 (1763年) |
検地、年貢、訴訟、仕置など地方行政全般 |
地方行政実務書 |
|
落穂集 |
横山夢草 |
1985年 |
華道 |
専門書 |
|
落穂集 |
(バハイ教) |
- |
宗教的教え |
聖典 |
第二章:地方書の金字塔『地方落穂集』
本報告書の分析対象である『地方落穂集』は、江戸時代の地方行政に関する実務書、いわゆる「地方書(じかたしょ)」の代表格として知られる文献である。
著者と成立年代については、刊本の奥付などから「宝暦十三癸未孟春武陽隠士泰路」という記述が見られ、一般的には1763年(宝暦13年)に武陽(武蔵国)の隠士である泰路なる人物によって編纂されたとされている 5 。ただし、泰路という人物の素性は詳らかではない。また、編者は泰路であるとしても、書物としての体裁が整えられたのは1778年(安永7年)頃、春木魯石の手によるという異説も存在し、その成立過程には研究上の論点が含まれている 5 。
本書の最大の特徴は、その内容の網羅性にある。検地の手法、石高の算定基準である石盛(こくもり)、収穫前の作柄調査である検見(けみ)、年貢を金銭で納める石代納(こくだいのう)といった租税制度から、訴訟(公事)の手続き、刑罰(仕置)の適用に至るまで、地方支配のあらゆる側面が、具体的な書式例を交えながら詳述されている 5 。その記述は、後代の『地方凡例録』のような体系性を欠き、「雑然としている」と評されることもある 5 。しかし、この一見した雑然さこそが、本書の性格を物語っている。すなわち、『地方落穂集』は、体系的な理論書ではなく、現場の役人が日々直面するであろう多種多様な問題への対処法や、長年蓄積された慣習、幕府や藩からの通達(触書)などを、実用性を第一に集積した成果物なのである。この「雑然さ」は、本書が机上の空論ではなく、江戸中期の地方支配の現場で実際に機能していた「生きた知識」の集大成であることの証左と解釈できる。
その史料的価値は極めて高く、後世に与えた影響も大きい。例えば、江戸時代の地方書の最高傑作と評される大石久敬の『地方凡例録』(1794年成立)は、その執筆にあたって『地方落穂集』を重要な参考文献の一つとした 5 。これは、『地方落穂集』が当時の地方行政に関する知識の一大集成と見なされていたことを示している。さらに、化政期(1804年-1830年)には『続地方落穂集』が、天保年間(1830年-1844年)には『地方落穂集追加』といった続編や補遺が次々と編まれており 5 、本書が後代の役人たちにとって必携の書として参照され続けたことを物語っている。
第二部:戦国時代の統治革命 ― 『地方落穂集』に至る道程
『地方落穂集』に描かれた整然とした行政システムを理解するためには、その前提となった戦国時代の統治構造の劇的な変革に遡る必要がある。戦国時代は、単なる戦乱の時代ではなく、中世的な支配秩序が解体され、近世的な中央集権体制の礎が築かれた「統治革命」の時代であった。その革命の核心は、「土地支配の再編」と「秩序の創出」という二つの側面に集約される。
第一章:土地支配の再編 ― 検地制度の変遷
戦国大名の検地 ― 荘園制解体への序曲
中世の土地支配は、荘園制に代表されるように、公家、寺社、武士といった多様な主体が、一つの土地に対して重層的な権利を持つ複雑な構造であった。戦国大名は、自らの領国を一体的に支配(一円支配)し、安定した財源を確保するため、この複雑な権利関係を整理し、土地からの収益を直接把握する必要に迫られた。そのための最も基本的な手段が検地であった 11 。
この動きにおいて先進的であったのが後北条氏である。初代の北条早雲は、16世紀初頭には既に領国で検地を実施しており、これは荘園制という旧来の枠組みを実力で否定し、大名による一元的な土地支配を目指す明確な意志の現れであった 12 。後北条氏は、検地によって土地の面積や状況を把握し、それを基に年貢や公事を賦課する体制を整えていった 13 。
しかし、後北条氏のような一部の例外を除き、多くの戦国大名の検地には限界があった。一つは、家臣団や在地領主の抵抗が大きく、領内全域で徹底した調査を行うことが困難であった点である 11 。もう一つは、その手法が、家臣や村落に土地の面積や収穫高を自己申告させる「指出検地(さしだしけんち)」に留まることが多かった点である 14 。この方式は、申告者が意図的に過少申告を行う余地が大きく、正確な実態把握には程遠いものであった 15 。
画期としての太閤検地 ― 近世的土地支配の確立
戦国大名による検地の試みを、全国的かつ統一的な規模で完成させ、近世的な土地支配制度を確立したのが、豊臣秀吉による太閤検地である。1582年(天正10年)から始まったこの事業は、日本史上初の全国規模の土地調査であり、その後の日本の社会構造を決定づける画期的な政策であった 16 。
太閤検地の革命性は、その徹底した「基準の統一」にあった。第一に、度量衡が統一された。1間を6尺3寸(約191cm)とし、1間四方を1歩(ぶ)、300歩を1反(たん)とする面積の基準を定め、米を計量する枡も京枡に統一した 18 。これにより、日本全国の土地を同一の物差しで測ることが可能になった。第二に、土地の生産力を示す統一基準として「石盛(こくもり)」が導入された。田畑は上・中・下・下々といった等級に分けられ、それぞれの等級ごとに1反当たりの標準収穫高(石盛)が定められた 19 。
この統一された面積と石盛を掛け合わせることで、個々の土地の公称生産高である「石高(こくだか)」が算出された。この石高制の確立こそが、太閤検地の最大の成果である。これは単なる税制改革に留まらなかった。それは、土地に対する「情報の革命」であった。太閤検地は、まず検地竿という精密な道具を用いて土地の物理的実態を正確に把握する「可視化」のプロセスであった 20 。同時に、米の取れない畑や屋敷地でさえも米の生産力に換算して石高を算出するという、多様な価値を「石高」という単一の抽象的な数値に変換する「抽象化」のプロセスでもあった 19 。
この「可視化」と「抽象化」の結合により、日本全国のあらゆる土地が、相互に比較可能で、加減乗除が可能な「データ」へと変換された。この情報革命の結果、大名の所領全体を石高で把握し、それに応じて軍役を課したり、あるいは大名を別の土地へ配置転換(移封)したりといった、合理的かつ官僚的な全国統治が可能となったのである 19 。
さらに、検地の結果作成された検地帳には、土地の面積や石高だけでなく、その土地を実際に耕作している農民の名前が登録された。これにより、農民は土地の保有権を公的に認められる(一地一作人の原則)一方で、石高に応じた年貢を領主に直接納める義務を負うことになった 19 。この過程で、荘園領主のような中間搾取層は排除され、領主と農民の直接的な支配=被支配関係が確立された 11 。これは武士を土地から切り離し、城下町に集住させる兵農分離を決定的にするものでもあった 22 。
徳川家康の関東支配と「関東流」農政
豊臣政権下で確立された石高制を継承し、さらに発展させたのが徳川家康である。特に、1590年(天正18年)に家康が関東へ移封されて以降の領国経営は、近世の地方支配のモデルケースとなった。
家康は、代官頭の伊奈忠次らを登用し、後北条氏の旧領を中心とした関東一円で大規模な検地を実施するとともに、それを基盤とした壮大な治水・新田開発事業に着手した 23 。利根川の流路を東へ移す「利根川東遷事業」や荒川の西遷事業に代表されるこれらのプロジェクトは、洪水地帯であった関東平野を広大な穀倉地帯へと変貌させた 25 。治水によって生まれた耕作可能地に用水路を整備し、新田開発を奨励するという、治水と開発を一体で進めるこの合理的な農政は「関東流」と呼ばれ、幕府の財政基盤を盤石なものにした 26 。これは、太閤検地で確立された石高制を、単に把握するだけでなく、積極的に増大させていくという、よりダイナミックな土地政策への展開であった。
第二章:秩序の創出 ― 訴訟制度の確立
「自力救済」から「公儀の裁判」へ
中世社会の紛争解決は、当事者間の実力行使、すなわち「自力救済」に委ねられることが一般的であった 28 。武士同士の所領争いや名誉をめぐる対立は、しばしば私的な合戦や決闘によって解決が図られた。この慣習は、社会の安定を著しく阻害するものであり、領国の一元的な支配を目指す戦国大名にとって、克服すべき最大の課題の一つであった。大名が真の支配者となるためには、領内の紛争解決権を独占し、自らの裁判権を絶対的なものとして確立する必要があったのである 29 。
分国法における「喧嘩両成敗」の思想
この課題に対する戦国大名の回答が、自らが制定した領国基本法である「分国法」の中に盛り込まれた「喧嘩両成敗」の規定であった。例えば、今川氏の『今川仮名目録』や伊達氏の『塵芥集』には、「喧嘩の事、是非に及ばず成敗を加ふべし」(喧嘩については、どちらが正しいかを問わず、双方を処罰する)という趣旨の条文が明記されている 28 。
この法理は、一見すると非合理に映るかもしれないが、その目的は極めて明確であった。それは、喧嘩の理非曲直を裁くことではなく、私闘という紛争解決手段そのものを禁圧することにあった 31 。どちらに理があろうとも、実力行使に及んだ時点で双方とも処罰されるのであれば、誰もが私闘をためらうようになる。その結果、すべての紛争は、大名が主宰する裁判の場に持ち込まれざるを得なくなる。
これは単なる紛争解決法の転換ではなかった。それは、戦国大名による「公共」概念の創出であった。それまで「私」の領域であった紛争解決を、大名を頂点とする「公」の領域へと強制的に移行させることで、大名は領国における唯一の暴力行使の主体、すなわち「公権力」としての地位を確立した。喧嘩両成敗は、領民に対して「汝らの争いは、もはや汝らだけのものではない。それは領国全体の秩序に関わる『公』の問題である」という新しい観念を提示し、バラバラな在地勢力の集合体であった領国を、単一の法秩序に服する政治的共同体へと変質させる、強力なイデオロギー装置として機能したのである 32 。
近世的法秩序への継承
戦国大名によって創出された、私闘を禁じ公儀の裁判権を絶対化するという思想は、天下統一の過程でさらに強化された。豊臣秀吉が発令した惣無事令は、大名間の私闘を禁じるものであり、喧嘩両成敗の論理を全国規模に拡大したものであった。そして、徳川幕府が制定した武家諸法度によって、この原則は武士社会の鉄則として完全に定着した 33 。
江戸時代に入り、泰平の世が続くと、法制度も次第にその性格を変えていく。戦国時代に見られたような、支配者の権威を示すための過酷で野蛮な刑罰は、社会秩序を維持するための、より体系的で合理的な訴訟・刑罰制度へと洗練されていった 34 。この安定した法秩序の確立こそが、260年以上にわたる江戸の平和を支える基盤となったのである。
第三部:『地方落穂集』に見る戦国時代の制度的帰結
『地方落穂集』が編纂された18世紀半ばは、戦国時代の統治革命から約150年の歳月が経過した時期にあたる。この書物に詳述された地方行政の実務は、戦国期に創出された制度が、いかにして安定的で日常的な統治技術として社会の隅々にまで定着したかを具体的に示している。
第一章:完成された石高制 ― 検地・年貢収取の実務
『地方落穂集』における検地・年貢関連記述の分析
『地方落穂集』は、その内容の多くを検地と年貢収取に関する実務解説に割いている。検地を行う際の手順、田畑の等級を定めて石盛を算定する方法、年ごとの収穫高を査定する検見の作法、さらには年貢を米ではなく金銭で納める石代納の換算率に至るまで、極めて具体的かつ詳細な規定が記されている 5 。
これらの記述は、太閤検地によって確立された石高制の諸原則が、1世紀半の時を経て、いかに細密な行政マニュアルへと落とし込まれ、代官や村役人の日常業務として定着したかを如実に示している。戦国末期において土地支配のあり方を根底から覆した「革命的」な政策であった石高制は、『地方落穂集』の時代には、もはやその是非が問われることのない、自明の統治基盤となっていた。本書の関心は、石高制というシステムの根本原理ではなく、それをいかに円滑、公正、かつ効率的に「運用」するかという、極めて実務的な側面に集中している。
この変化は、制度目的の変容としても捉えることができる。戦国期や江戸初期において、石高は各大名が動員すべき軍役(兵士や武具の数)を算出するための基準として、極めて重要な軍事的意味を持っていた。しかし、長期にわたる平和が続いた18世紀には、その軍事的性格は後退し、幕府や藩の財政を支える安定した年貢を収取するための、財政的基準としての性格が前面に出るようになった。制度の骨格は戦国時代から継承されつつも、その運用目的は時代の要請に応じて変化したのである。
この運用を支えたのが、煩雑とも思える詳細な手続き規定であった。例えば、年貢率を左右する検見は、少しでも多く徴収したい領主側と、少しでも負担を軽くしたい農民側の利害が鋭く対立する場であった。もし役人の裁量に任せれば、恣意的な判断が横行し、農民の不満が爆発しかねない。『地方落穂集』に記されたような細密な手続きは、役人の恣意性を抑制し、農民に一定の予測可能性と公正さを担保する機能を果たした。それは、潜在的な社会対立を、剥き出しの暴力による収奪ではなく、ルールに基づいた「手続き」によって管理・吸収しようとする、高度な統治技術の現れであった。戦国時代の支配が実力に依拠していたとすれば、近世の支配は、このような制度的管理能力に依拠していたのである。
第二章:定着した公儀の権威 ― 訴訟・仕置の実態
『地方落穂集』における訴訟・仕置関連記述の分析
『地方落穂集』は、租税制度と並んで、訴訟(公事)と刑罰(仕置)に関する実務についても多くの記述を割いている。特に、訴状の具体的な書式や、様々な紛争類型に応じた裁許の先例、各種の刑罰の内容などが詳細に解説されている点は注目に値する 5 。
これらの記述が示すのは、戦国大名が分国法を通じて目指した「裁判権の独占」と「公儀の権威」が、江戸幕府の法体系の下で完全に制度化され、郡代や代官といった地方役人から村役人のレベルにまで浸透している実態である。『地方落穂集』に描かれる世界では、個人間や村同士の紛争は、もはや当事者間の暴力(自力救済)によって解決されるべきものではなく、定められた書式で訴状を提出し、公的な場で裁かれるのが当然のこととなっている。戦国期に始まった自力救済の否定が、社会の常識として隅々にまで行き渡ったことを意味する。
ここにも、法意識の変化が見て取れる。本書に記される訴訟や仕置のあり方は、戦国期の「野蛮さ」から脱却し、より予測可能性が高く、安定した法秩序を志向している 34 。法は、もはや支配者が権威を示すための臨時の支配手段ではなく、社会の恒常的な維持装置としての役割を担うようになったのである。
さらに重要なのは、このような訴訟制度の整備が、民衆を単なる法の「受動的な客体」から、「能動的な利用者」へと変える側面を持っていたことである。『地方落穂集』が訴訟の「書式」を具体的に示すことは、民衆がどのような手続きを踏めば、公儀の裁判権にアクセスできるかを示した「手引書」としての機能も果たした。戦国時代の喧嘩両成敗が、上からの権力による私闘の禁圧という側面が強かったのに対し、制度が整備された江戸時代には、民衆は自らの権利や利益(例えば、水利権や金銭貸借)を守るために、この制度を積極的に「利用」するようになった。公儀の権威は、民衆に利用されることによって、かえってその正統性を高め、社会に深く根付いていった。それは、権力が民衆を一方的に支配するだけでなく、民衆が権力の提供する秩序を内面化し、活用することで、支配体制全体が安定するという、より洗練された統治の姿であった。
結論:戦国から近世への連続性の中の『地方落穂集』
本報告書で詳述してきたように、『地方落穂集』は、単なる江戸時代の一地方書という評価に留まるものではない。それは、戦国時代に織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らによって推進された統治システムの大変革 ― すなわち、石高制による一元的な土地・人民把握と、公儀による裁判権の独占 ― が、約150年の歳月を経て、安定的かつ実務的な官僚支配の技術として、いかに社会の末端にまで定着したかを具体的に示す、いわば「制度の化石」である。
分析を通じて明らかになったのは、戦国から近世への「継承と変容」のダイナミズムである。太閤検地によって確立された石高制の骨格や、分国法に由来する公儀の裁判権といった、戦国時代に創出された「革命的」な制度は、江戸時代にほぼそのまま継承された。しかし、その運用目的は大きく変容した。天下統一のための軍事的・動員的性格は薄れ、長期的な社会秩序を維持するための財政的・司法的性格が前面に出るようになった。革命は日常となり、暴力は手続きに置き換えられた。この「継承と変容」のプロセスこそが、戦国から近世への移行の本質であり、『地方落穂集』はその具体的な現れに他ならない。
したがって、『地方落穂集』のような地方書を丹念に読み解くことは、法制史や経済史という専門領域の枠を超えて、より広範な問いに答えるための鍵を提供する。それは、近世日本の社会構造、権力と民衆の相互関係、そして「平和」を制度的に維持するための統治技術のあり方を、より深く理解するための貴重な窓となるのである。今後の研究においても、本書のような実務書に記録された「生きた知識」の分析は、日本の歴史的特質を解明する上で、依然として重要な意義を持ち続けるであろう。
引用文献
- フィクションとしての「問鉄砲」(パート2) −家康神話創出の一事例(その2)− http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=10385
- 落穂集(横山夢草著 ; 華道家元池坊総務所編) / 古本、中古本 - 日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=457313716
- 「大阪市史史料」目録 № 表題 編者 発行年月 内容 概略 時期 分類 よみ 1 近来年代記(上) 1980/3 https://www.oml.city.osaka.lg.jp/upload/1_shishishiryo_mokuroku_1.pdf
- 落穂集(おちぼしゆう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%90%BD%E7%A9%82%E9%9B%86-1513881
- 地方落穂集(じかたおちぼしゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%90%BD%E7%A9%82%E9%9B%86-72428
- 【落穂集】 - バハイ共同体 【Japan Baha'i Network】 https://www.bahaijp.org/writings/%E6%9B%B8%E7%89%A9%E3%81%AE%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89/%E3%80%90%E8%90%BD%E7%A9%82%E9%9B%86%E3%80%91%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%91/
- 地方凡例録 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%87%A1%E4%BE%8B%E9%8C%B2
- 《校正地方凡例録》(こうせいじかたはんれいろく)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A0%A1%E6%AD%A3%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%87%A1%E4%BE%8B%E9%8C%B2-1314303
- 地方凡例録(じかたはんれいろく)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説 - goo国語辞書 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%87%A1%E4%BE%8B%E9%8C%B2/
- 江戸の改変 https://edo-tokyo-museum.repo.nii.ac.jp/record/286/files/kiyo11_1(248)_24(225).pdf
- 検地 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%9C%B0
- 氏康の領国経営 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/007/
- 戦国大名後北条氏における検地実施過程と年貢収取 : 伊豆国西浦の事例をもとに https://omu.repo.nii.ac.jp/record/12890/files/2023000041.pdf
- 指出検地(さしだしけんち)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%8C%87%E5%87%BA%E6%A4%9C%E5%9C%B0-837720
- 太閤検地 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/taiko-kenchi/
- 土地調査の歴史 - 福島県ホームページ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36045a/tochichosa-history.html
- 日本の土地調査の歴史 - 太田市ホームページ(農村整備課) https://www.city.ota.gunma.jp/page/4077.html
- 秀吉株式会社の研究(1)太閤検地で基準を統一|Biz Clip(ビズクリップ) https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-052.html
- 太閤検地と刀狩り - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/taikokenchi-katanagari/
- 太閤検地 - 国税庁 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/1104/index.htm
- 第6章 郷土の三英傑に学ぶ資金調達 - 秀吉、太閤検地で構造改革を推進 https://jp.fujitsu.com/family/sibu/toukai/sanei/sanei-23.html
- 全国統一を成し遂げた豊臣秀吉:社会安定化のために構造改革 - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b06906/
- 【一 徳川氏の関東入国】 - ADEAC https://adeac.jp/nagara-town/text-list/d100010/ht040010
- 徳川家康の関東国替えは「左遷」にあらず、大河3本を消す大工事で市場開拓 https://diamond.jp/articles/-/307636
- 関東郡代伊奈氏の200年展 https://araijuku2011.jp/wp-content/uploads/2016/10/%E4%BC%8A%E5%A5%88%E6%B0%8F%E5%B1%95%E5%86%8A%E5%AD%90%E7%89%88B.pdf
- 伊奈忠次について | バラのまち埼玉県伊奈町公式ホームページ Ina Town Official Web site https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000004028.html
- 伊奈忠次・忠治父子の物語 - 新井宿駅と地域まちづくり協議会 https://araijuku2011.jp/wp-content/uploads/2016/10/%E5%B0%8F%E5%86%8A%E5%AD%90%E6%B0%B4%E3%82%92%E6%B2%BB%E3%82%81%E3%80%81%E6%B0%B4%E3%82%92%E5%88%A9%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8B%E9%96%8B%E3%81%8D%E7%94%A8.pdf
- 26 戦国大名 - 石田謙治の日本史 https://kenjiishida.jimdoweb.com/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E9%80%9A%E5%8F%B2/%E5%AE%A4%E7%94%BA/26-%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D/
- 3章 中世 1 https://www.zkai.co.jp/wp-content/uploads/sites/18/2021/06/06215026/a1963977d7f064526a16ce9f1a1834ce.pdf
- 今川仮名目録 ~スライド本文・補足説明~ https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/1649/1/4-2.pdf
- 戦国大名の分国支配 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D%E3%81%AE%E5%88%86%E5%9B%BD%E6%94%AF%E9%85%8D/
- 戦国大名も苦労した〜白か黒かつけない喧嘩の解決法〜|くるみ - note https://note.com/rssh613k/n/n3555701ab36d
- 歴史に見る合議制/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/77606/
- 2011年6月 江戸時代における裁判制度の実際の姿とは- お裁きの真実を追究 - 神戸学院大学 https://www.kobegakuin.ac.jp/gakuho-net/infocus/2011/2011_06.html