身自鏡
『身自鏡』は、戦国武士・玉木吉保が毛利三代に仕え、検地奉行や医師として活躍した生涯を記す。戦国期の教育、秀吉の容貌、武家の食文化など、個人の視点から時代の息吹を伝える貴重な史料。
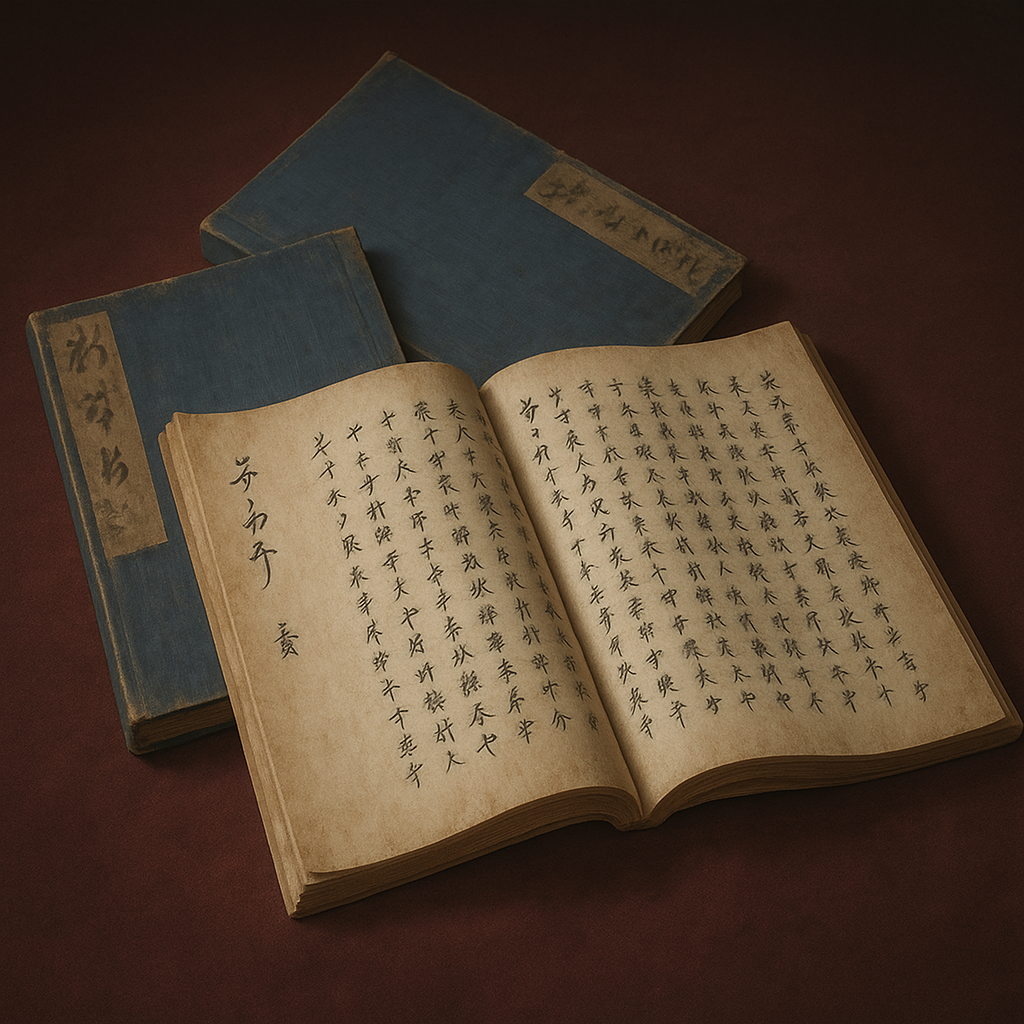
『身自鏡』の総合的研究――戦国武士・玉木吉保の生涯と記憶が映し出す時代像
序論:『身自鏡』への誘い
戦国時代という未曾有の動乱期を生きた一人の武士、玉木吉保(たまきよしやす)が晩年に遺した自叙伝『身自鏡(みのかがみ)』。これは単なる一個人の一代記にとどまらず、戦乱から泰平へと向かう時代の大きな転換点を、地方武士というミクロな視点から克明に記録した、日本史においても類稀なる歴史の証言である。本書は、毛利元就・輝元・秀就の三代に仕えた吉保が、元和三年(1617年)に自身の誕生から老年に至るまでの事跡を回顧して著したものであり、その記述は合戦の記憶から日々の生活、教育、さらには食文化にまで及ぶ 1 。
一般に『身自鏡』は、「戦国時代の地方武士の生活を知る貴重な資料」として高く評価されている 1 。しかし、その真の価値は、単なる生活史の記録という一面に留まるものではない。著者である玉木吉保自身が、武士として戦場を駆け、吏僚として検地を差配し、そして晩年には医師・文人として多彩な文化活動を行った多面的な人物であった 2 。この著者の持つ複合的なアイデンティティは、史料の記述に如何なる深度と射程を与えているのか。また、個人の「記憶」という主観的なフィルターを通して描かれた世界は、客観的な歴史像とどのように交差し、我々に何を語りかけるのか。
本報告書は、これらの問いに答えるべく、『身自鏡』という鏡に映し出された戦国という時代、そして玉木吉保という人物の実像を、現存する研究成果を網羅しつつ、多角的に分析・再構築することを目的とする。第一部では著者・玉木吉保の生涯と人物像を、第二部では『身自鏡』そのものの構造と内容を、そして第三部では史料としての価値と限界を徹底的に解明し、この稀有な自叙伝が持つ不朽の意義を明らかにしていく。
第一部:著者・玉木吉保の実像――戦国乱世を生き抜いた多才なる毛利家臣
玉木吉保という人物を理解することは、『身自鏡』の記述を深く読み解くための不可欠な前提である。彼は単なる一介の武士ではなく、戦国乱世から江戸初期の泰平の世へと移行する社会変動の中で、武芸のみならず、行政手腕や文化的素養を武器に自己の価値を確立し、家を存続させた戦略的な生涯を送った。
第一章:生涯と毛利家臣としての軌跡
玉木吉保は、天文21年(1552年)に玉木忠吉の子として生まれ、寛永10年(1633年)に82歳という長寿を全うした 2 。彼の生涯は、織田信長の台頭から豊臣政権、そして徳川幕府の成立という、日本の歴史が最も劇的に動いた時代と完全に重なっている。
出自と家系の伝承
『身自鏡』や関連史料によれば、玉木氏の出自には壮大な伝承が付与されている。その祖先は天竺(インド)の王子であり、日本へ渡航して紀伊国熊野に住み、「玉置大明神」と称されたという 3 。これは、自家の起源を神聖なものに結びつけることで、その権威を高めようとする、中世から近世にかけての武士階級にしばしば見られる意識の表れである。その後、一族は後醍醐天皇の時代に安芸国佐東郡温帯村に定着したとされ、毛利氏が中国地方の覇者となる以前からの在地領主、すなわち国人であったことがうかがえる 3 。
毛利三代への奉公と吏僚としての側面
吉保は、毛利元就、輝元、秀就の三代にわたって仕えた、忠実な譜代の家臣であった 2 。そのキャリアは、永禄12年(1569年)の大内輝弘の乱への参加から始まる 2 。これは、周防国山口に侵攻した大内氏の残党を撃退した戦いであり、吉保は青年期から毛利家の武士として実戦経験を積んでいたことがわかる。
しかし、彼の真価は単なる戦闘員としてのみ発揮されたわけではない。『身自鏡』が特に詳細に記録しているのは、彼の吏僚、すなわち行政官僚としての側面である。同書によれば、吉保は30歳と31歳の時、すなわち天正11年(1583年)と12年に、毛利氏の命を受けて伊予国へ検地のために渡っている 6 。さらにその後も、長門国大津郡、周防国大島郡、出雲国仁田郡、安芸国佐西・佐東・高田郡、石見国と、毛利氏の広大な領国において次々と検地奉行としての任務を遂行した 6 。
この記録は極めて重要である。なぜなら、これは豊臣秀吉による全国的な太閤検地が本格化する以前から、毛利氏が独自に領国経営の近代化、すなわち従来の貫文高制から石高制への移行を視野に入れた先進的な検地事業を進めていたことを示す動かぬ証拠だからである 6 。そして、玉木吉保がその実務を担う、高度な算術・測量・行政能力を備えた「吏僚型武士」として、主家から絶大な信頼を寄せられていたことを物語っている。戦国大名の領国経営が、勇猛な武将による軍事行動だけでなく、吉保のような専門技能を持つ家臣団によって緻密に支えられていた事実が、彼の記録から鮮明に浮かび上がる。
関ヶ原以降と晩年
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおける吉保の具体的な動向は詳らかではないが、毛利家が敗戦によって防長二国へと減封されると、彼もまた主家に従い移住した 2 。この主家の苦境は、吉保自身のキャリアにも大きな転機をもたらした。彼は50歳を過ぎた頃から、自身の健康のため、そして新たな奉公の形を模索するかのように、医術に専念するようになる 2 。武力が絶対的な価値を持った戦乱の時代が終わり、武士の役割が変容していく中で、彼は医術という新たな専門性へと自己の活路を見出したのである。このキャリアシフトは、戦国から江戸へと向かう時代の大きなうねりを、一人の武士がいかに生き抜いたかを示す象徴的な出来事と言えよう。
第二章:武士の枠を超えた文化人として
玉木吉保の人物像を特徴づけるのは、武士や吏僚としての側面だけではない。彼は医術、執筆、連歌、料理といった多岐にわたる分野で非凡な才能を発揮した、当代一流の文化人でもあった 2 。
医師「偽真」としての活動
吉保の名は、後世においては武将としてよりも、むしろ医師として知られている側面がある 2 。「偽真(ぎしん)」という医師名を名乗り、数多くの人々を治療したと推測される 2 。特筆すべきは、彼の医術が単なる経験則に基づいた民間療法ではなく、「その効用は現代でも通用する現代的なものである」と評価されるほど、体系的かつ先進的な知識に裏打ちされていた点である 2 。これは、彼が戦乱の世にあっても向学心を失わず、最新の医学知識を貪欲に吸収していたことを示唆している。
著作活動の全体像
彼の知的好奇心と体系化への意欲は、多彩な著作活動にも結実している。『身自鏡』はその代表作であるが、それ以外にも、特に医術に関する重要な書物を複数残した 2 。
【表1】玉木吉保の著作一覧
|
著書名 |
ジャンル |
概要 |
特徴 |
|
身自鏡 |
自叙伝 |
自身の先祖から老年に至るまでの出来事を年代順に記述。 |
戦国期の武士の生活、教育、食文化などを知る貴重な一次史料 1 。 |
|
歌薬性 |
医薬書 |
生薬とその効能を、覚えやすい和歌の形式でまとめたもの 2 。 |
難解な薬学知識を、武士の必須教養であった和歌を用いて普及させようとする教育的配慮が見られる。 |
|
歌脈書 |
診療書 |
脈の診察方法(脈診)を、同様に和歌の形式で解説したもの 2 。 |
〃 |
|
医術車輪書 |
医術書 |
病を敵、薬を将、治療の過程を合戦に見立てて解説した、ユニークな軍記物語風の医術書 2 。 |
武士としてのアイデンティティを、医術という新たな専門分野の解説に応用した独創的な発想が光る。 |
この著作リスト、特に『医術車輪書』の構成は、吉保の思考様式を理解する上で非常に示唆に富む。彼は武士としての自己を捨てて医師になったのではなく、武士としての経験や価値観を土台として、医術という新たな知の体系を再構築しようとした。この知的作業は、彼の多角的なキャリアが単なる寄せ集めではなく、一貫した人格の中で有機的に統合されていたことの証左である。
多方面にわたる教養
医術や執筆活動に加え、吉保が連歌や料理にも深い造詣を持っていたことは、戦国武士の教養の幅広さを物語っている 2 。特に料理に関する彼の知識は、単なる趣味の域を超え、哲学的思索を伴う高度なものであった。この点は、次章で詳述するが、武士にとって文化的な素養が、武芸と同様に重要な社会的資本であったことを示している。
玉木吉保の生涯は、まさに時代の申し子であった。戦闘員、行政官僚、文化人という三つの顔を巧みに使い分ける彼の生き様は、激動の時代を生き抜くための、一個人の壮大な生存戦略そのものであったと言えるだろう。
第二部:『身自鏡』の構造と内容の深層分析――一個人の記憶が語る時代の息吹
『身自鏡』は、玉木吉保というフィルターを通して、戦国時代という巨大な事象を映し出す。そこには、大名たちの動向を記した公式の歴史書には決して現れることのない、個人の生々しい体験と、時代の微細な肌触りが刻印されている。
第一章:執筆の動機と史料の構成
『身自鏡』がどのような意図で、どのような形式で書かれたのかを理解することは、その内容を正確に解釈するための第一歩である。
本書は、元和三年(1617年)、吉保が66歳の時に、当時の主君であった毛利秀就のために著されたと記録されている 5 。この執筆背景は極めて重要である。なぜなら、これは本書が単なる私的な回想録や日記ではなく、主君への上申書、あるいは玉木家が代々毛利家へ尽くしてきた忠勤の記録を後世に伝えるための、半ば公的な性格を持つ著作であったことを意味するからである。この「奉公の書」という性格は、記述の選択やトーンに大きな影響を与えていると考えられる。
構成としては、自身の先祖の伝承から筆を起こし、自らの誕生から老年に至るまでの出来事を年代順に記述していく、典型的な年代記(クロニクル)の形式をとっている 1 。その文体は、客観的で無味乾燥なものではなく、著者自身の体験に基づいた実感を伴い、時に感情を交えながら語られるため、非常に生き生きとした印象を与える 1 。
第二章:記録された戦国期の日常と非日常
『身自鏡』には、戦国武士が経験したであろう、ありふれた日常と、合戦や歴史的事件といった非日常が混在して記録されている。その中でも特に注目すべきは、教育と、歴史上の人物に関する証言である。
武士の教育――寺院教育の実態
『身自鏡』が持つ史料的価値の中でも、特にユニークで貴重とされるのが、著者自身が受けた教育に関する詳細な記述である。吉保は永禄7年(1564年)、13歳の時に真言宗の勝楽寺に入り、仏道修行とともに学問を修めた 1 。『身自鏡』には、この時の体験に基づき、当時の寺院でどのような教授法がとられ、どのような教科書が用いられていたかが具体的に記されている 1 。
これは、戦国期の武士階級の子弟が、武芸の訓練だけでなく、寺院という教育機関を通じて読み書き算盤や古典の素養を身につけていた実態を、当事者の視点から伝える他に類を見ない記録である。武士の識字率や教養レベルを考える上で、本書は第一級の教育史料としての価値を持つ。
時代の証言――豊臣秀吉の容貌描写
『身自鏡』は、歴史上の著名な人物に関する生々しい証言を含んでいる点でも注目される。その最も有名な例が、天下人・豊臣秀吉の容貌に関する記述である。吉保は、天正9年(1581年)の鳥取城攻めの際に、敵将であった羽柴秀吉の姿を初めて間近で見た時の印象を、次のように記している。
「赤ひげに猿眼(さるまなこ)にて空うそぶきてぞ出られける」 7
意訳すれば、「赤みがかった髭で、目は猿のように鋭く、嘯くような(あるいは、ぼんやりと遠くを見つめるような)表情で馬に乗って出てこられた」となる。この「猿眼」という表現は、後世に定着する秀吉の「猿」というイメージを裏付ける、同時代人の一次史料として頻繁に引用される 9 。
しかし、この記述を解釈する際には注意が必要である。これは写真のような客観的な写実描写ではなく、あくまで毛利家の家臣である吉保が、敵将に対して抱いた主観的な印象や評価が色濃く反映されたものであると考えるべきである。事実、他の同時代史料を見ると、秀吉の容貌は様々に描写されている。イエズス会宣教師ルイス・フロイスは「醜悪な容貌の持主で、片手には六本の指があった」と酷評し 9 、朝鮮の使節は「その目は鼠のごとし」と記している 9 。これらの多様な記述を比較検討することで、一つの固定化されたイメージの裏にある、多面的で複雑な秀吉の実像に迫ることができる。『身自鏡』の記述は、客観的な事実を伝えるというよりも、当時の人々が秀吉という人物を「どう認識したか」という心性の歴史を探る上で、極めて豊かな情報を提供してくれるのである。
第三章:「料理のこと」に見る戦国期の食文化
『身自鏡』の白眉とも言えるのが、巻末に収められた「料理のこと」と題された一章である。ここには、玉木吉保の料理に対する深い造詣と、当時の武家社会における豊かな食文化が凝縮されている。
料理哲学と五行思想
吉保は、この章の冒頭で「夫料理調味,非賤しき事(それりょうりちょうみ、いやしきことにあらず)」と断言し、料理を単なる食事の準備ではなく、高尚な文化的営為と位置づける 10 。さらに彼は、料理を天地開闢や、地・水・火・風・空の五体五輪、青・黄・赤・白・黒の五色、そして酸・苦・甘・辛・鹹の五味といった、壮大な陰陽五行思想と結びつけて論じている 10 。これは、彼の料理観が、宇宙の秩序や自然の摂理を皿の上に体現しようとする、極めて高度な哲学的思索に裏打ちされていたことを示している。このような記述は、中央の公家文化や禅宗文化が、安芸という一地方の武士層にまで深く浸透し、受容・実践されていたことを証明するものであり、文化史における「中央と地方」という単純な二項対立的な見方を再考させる力を持つ。
具体的な食材と調理法
吉保の料理論は、単なる観念論に終わらない。本書には、当時の食生活を具体的に復元するための豊富な情報が含まれている。
【表2】『身自鏡』に記された季節の食材と料理の要点
|
季節 |
食材の例 |
関連する記述・調理法の要点 |
思想的背景 |
|
初春 |
ふきのとう、わかめ |
新鮮な旬のものを尊ぶ姿勢がうかがえる 10 。 |
春は五行の「木」、色は「青」。毛利氏の饗応献立に見られる「青膾」などと関連性が指摘される 10 。 |
|
暮春 |
わらび、小あゆ |
〃 |
〃 |
|
年中 |
とうふ、ふ、かわうそ、きじ、くじら |
鯨やかわうそといった、現代では珍しい食材も利用されていたことがわかる 10 。 |
五味(醋・苦・甘・辛・醎)の調和を重視する思想が根底にある 10 。 |
|
その他 |
青頸鴨、しほ鳥 |
汁物の「つま」として、竹の子、うど、みょうが、しいたけなどが具体的に挙げられている 10 。 |
料理は天地自然の理に適うべきであるという、吉保の哲学を反映している。 |
これらの具体的な記述、特に汁物、膾(なます)、さしみの調理法に関する詳細な記録は 10 、現代における戦国時代の饗応料理の再現プロジェクトにおいて、中心的な参考文献として活用されている 11 。『身自鏡』の記述と、同時代の他の料理書を組み合わせることで、失われた戦国の食卓が現代に蘇るのである。
第三部:史料としての『身自鏡』――その価値、限界、そして現代的意義
『身自鏡』を歴史資料として扱う上で、その特性を正確に理解し、価値と限界を見極めることは不可欠である。個人の記憶に基づく自叙伝という形式は、本書に比類なき価値を与えると同時に、利用にあたっての注意点も内包している。
第一章:一次史料としての特質と信頼性
自叙伝の強みと限界
『身自鏡』の最大の強みは、玉木吉保という一個人の直接的な体験に基づいて書かれている点にある。そのため、大名家の公式記録や年代記には決して現れることのない、個人の感情の機微、生活の細部、戦場の空気感といった、生々しい実感が記録されている 1 。特に、地方武士が受けた教育の実態 1 、領国経営の最前線であった検地行政の様子 6 、そして武家の日常を彩った食文化 10 といったミクロな視点からの情報は、他の史料では得難い、本書ならではの価値と言える。
一方で、本書は著者の記憶に大きく依存しているため、その記述には限界も存在する。例えば、年月日に関しては若干の記憶違いが見られることが指摘されている 1 。また、自叙伝という性質上、無意識のうちに自己の功績を強調したり、都合の悪い事実を省略したりする傾向や、主君・毛利家への配慮からくる主観的な評価が含まれている可能性は常に念頭に置く必要がある。したがって、本書の記述を利用する際には、他の客観的な史料との比較検討、すなわち厳密な史料批判の作業が不可欠となる。
個人記録の独自性
鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡』が、日記形式をとりながらも、実際には後年の編纂物としての性格を強く持つことと比較すると、『身自鏡』の持つ「個人性」はより際立つ 15 。『身自鏡』は、徹頭徹尾、玉木吉保という一個人の視点から、彼が生きた世界が描かれている。この徹底した個人性こそが、幕府や大名といった巨大権力の視点から描かれるマクロな歴史とは異なる、もう一つの歴史像、すなわち「下からの歴史」を我々に提示してくれるのである。
第二章:近代史学における受容と研究史
『身自鏡』が今日、一級の歴史資料として広く認知されるに至るまでには、先人たちによる発見と研究の積み重ねがあった。
先駆的研究と多分野での活用
本史料の価値をいち早く見出し、学界に紹介したのは、大正期の歴史学者であり文学博士でもあった三浦周行である。彼は『身自鏡』の写本を調査し、その重要性を論じた研究「或ろ戦國武士の自叙傳」を発表した 3 。これが、近代史学における『身自鏡』研究の嚆矢となった。
三浦による紹介以降、『身自鏡』はその内容の豊かさから、様々な研究分野で活用されるようになった。戦国時代の武士の生活史 1 はもちろんのこと、教育史(寺院教育の実態) 1 、政治・経済史(毛利氏の検地研究) 6 、そして近年特に注目を集めている食文化史(饗応料理の研究) 10 など、極めて多岐にわたる分野で、欠くことのできない基礎史料として利用されている。
史料の所蔵とアクセス
『身自鏡』の原本は、かつて玉木家に伝来していたが 3 、現在、その写本は東京大学史料編纂所に所蔵されていることが確認されている 13 。また、複数の叢書に翻刻(活字化されたもの)が収録されており、研究者が比較的容易に本文にアクセスできる環境が整っている。さらに、篭谷真智子氏による論文「「身自鏡」について」 17 をはじめ、個別のテーマに焦点を当てた研究も蓄積されており、その学術的価値は今後もさらに深められていくことが期待される。
本書が主君・秀就のために書かれたという事実は 5 、その内容全体を解釈する上で決定的な鍵となる。これは単なる自己満足の回顧録ではない。自らの武功、行政官僚としての上級家臣に比肩する働き、そして高度な文化教養の全てを具体的に列挙することで、玉木家がいかに有能であり、毛利家にとって不可欠な存在であるかを、主君と後世に対して強くアピールする、「奉公の集大成」としての性格を帯びている。特に関ヶ原の敗戦による減封という未曾有の苦境にあった毛利家において、自家の価値を改めて示し、家中における地位を確保しようとする、吉保の強い意志と戦略が込められた書物と読み解くことができる。本書は、吉保個人の記憶の記録であると同時に、近世大名家臣団へと再編成されていく中で、玉木家の「家」の存続をかけた戦略書でもあったのである。
結論:『身自鏡』が未来に伝えるもの
毛利氏家臣・玉木吉保が遺した自叙伝『身自鏡』は、一人の武士の生涯記録という枠を遥かに超え、戦国という時代そのものの多面的で深遠な肖像画として、現代の我々の前に立ち現れる。彼のペンを通して、我々は武士がただ戦うだけの存在ではなく、学び、統治し、文化を創造し、そして時代の変化に適応しながら生き抜いた、極めて人間的な存在であったことを知る。
本報告書で明らかにしてきたように、『身自鏡』の価値はその多層性にある。著者・玉木吉保の、武士・吏僚・文化人という複合的なキャリアは、乱世から泰平の世への社会変容を生きるための生存戦略そのものであった。彼の記録は、毛利氏の先進的な領国経営の実態を伝え、豊臣秀吉のような歴史上の人物に対する同時代人の主観的な眼差しを記録し、そして五行思想に裏打ちされた高度な食文化が地方武家社会にまで浸透していた事実を証明する。
個人の主観的な記憶という、史料としての「限界」は、見方を変えれば、公式記録からは決してうかがい知ることのできない、時代の空気や人々の心性を伝える「強み」でもある。『身自鏡』は、歴史が勝者や権力者だけの物語ではなく、無数の個人の生と思考の積み重ねによって織りなされているという、歴史学の根本的な視座を我々に再認識させる。
戦乱の世を武と知で生き抜き、泰平の世で医術という新たな専門性を追求した玉木吉保の姿は、変化の時代を生きる現代の我々にも、多くの示唆を与えてくれるだろう。総合史料としての『身自鏡』の不朽の価値は、今後も歴史学の様々な分野の研究を通して、さらに豊かに明らかにされていくに違いない。この一冊の古文書は、まさに過去から未来へと向けられた、時代の記憶の鏡なのである。
引用文献
- 身自鏡(みのかがみ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%BA%AB%E8%87%AA%E9%8F%A1-1209557
- 玉木吉保 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E6%9C%A8%E5%90%89%E4%BF%9D
- Kyoto University Research Information Repository https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstream/2433/247115/1/shirin_005_1_11.pdf
- 安芸武田氏ゆかりに神社と寺院 http://www.cf.city.hiroshima.jp/gionnishi-k/webstation/rekishi/takeda-tera-jinjya/takeda-kanren-jinjya.html
- 『元就公山口御下向之節饗応次第』および 『身自鏡』からみる戦国期毛利氏の 饗応献立の料理 - 日本家政学会 https://www.jshe.jp/shibu_hp/chugoku_shikoku/pdf/74_11.pdf
- 一 太閤検地前の伊予 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/64/view/8027
- 戦国武将の肖像画エピソードが面白い!豊臣秀吉・徳川家康・伊達政宗の逸話を紹介 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/89240/
- 豊臣秀吉は「猿」ではなく「犬」に似ていた⁉︎秘密の多いその容貌を徹底解剖! - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/126653/
- AIで再現「豊臣秀吉ってどんな顔?」戦国武将シリーズ2 - note https://note.com/hanare_abotok/n/n6894fcd490b7
- 『身自鏡』に記された五輪・五行思想からみた戦国期毛利氏の食 https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajscs/33/0/33_48/_article/-char/ja/
- 【健康科学科】戦国期毛利氏の饗応食の試食会を三原市で行いました - 県立広島大学 https://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/healthy/20190228-mouri.html
- 『元就公山口御下向之節饗応次第』に記された戦国期毛利氏の饗応献立の再現とその活用 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jfcj/18/0/18_27/_article/-char/ja/
- 戦国期毛利氏の饗応食再現を通した中世の食の考察 とその継承のための教育資料の作成 https://www.syokubunka.or.jp/assets/data/research/202109.pdf
- 研究者詳細 - 石橋 ちなみ https://kyoiku-kenkyudb.omu.ac.jp/html/100002569_ja.html
- 吾妻鏡の研究・明治時代 - 鎌倉・北道倶楽部 http://www.ktmchi.com/RKS_2/AZM_01.html
- 吾妻鏡|日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2029
- 「身自鏡」について | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I127415