騎士用本
「騎士用本」は、16世紀欧州騎士と戦国武士の騎馬文化を比較。欧州は重装騎兵とランスチャージ、日本は在来馬と騎射・集団戦。環境に最適化され、異なる騎馬文化を形成。
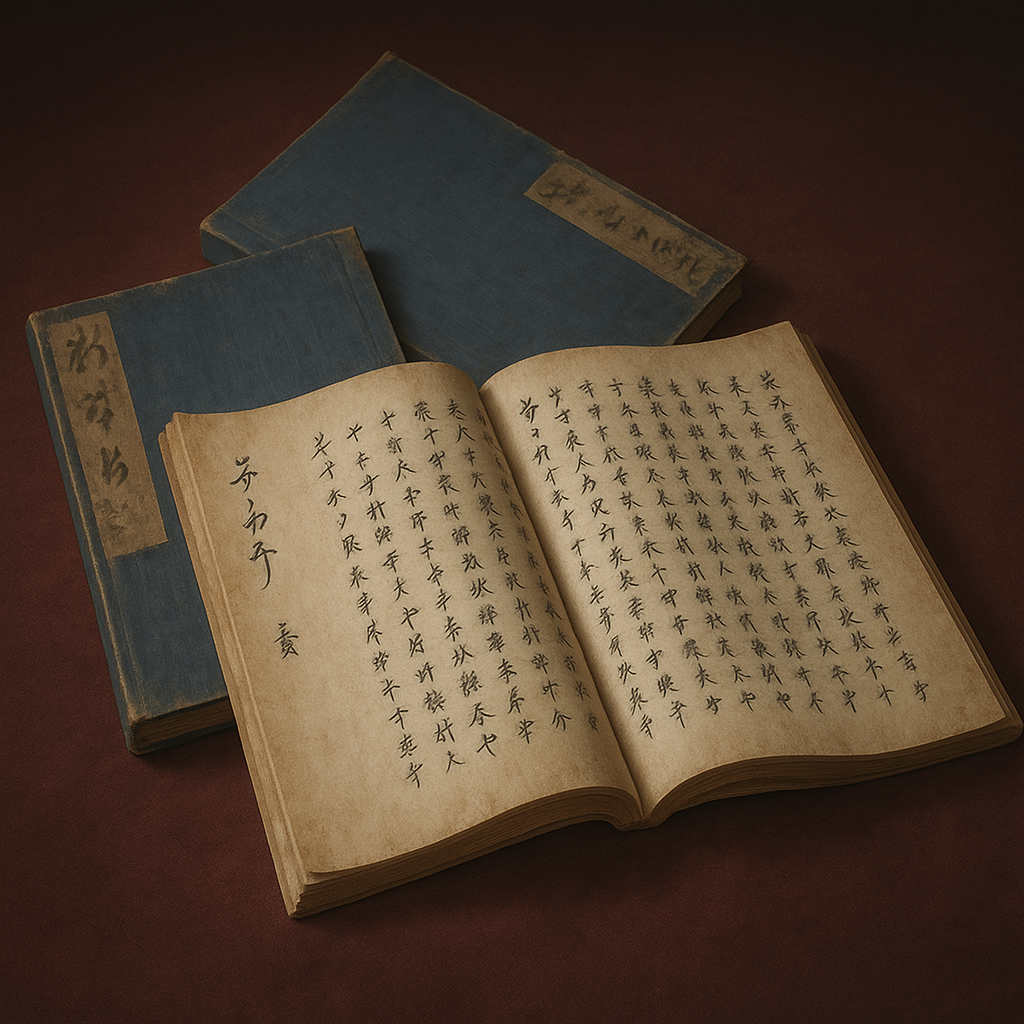
騎士用本と戦国武士:16世紀、二つの騎馬文化の比較分析
序論
16世紀、奇しくも時を同じくして、ヨーロッパと日本でそれぞれ頂点を迎えた二つの騎馬文化が存在した。一方はルネサンス期ヨーロッパの騎士文化であり、その馬術理論はナポリの馬術家フェデリコ・グリゾーネが1550年に著した『Gli ordini di cavalcare』(邦題案:乗馬術の体系)によって、一個の「科学」へと昇華された。もう一方は、群雄割拠の戦国日本で武士たちが実践した「弓馬の道」である。本報告書は、このグリゾーネの「騎士用本」を分析の基軸とし、戦国武士の馬術文化とを、馬匹、馬具、戦術、思想の各側面から徹底的に比較分析する。これにより、両者が置かれた環境と要求に対し、いかにして最適化されていったのか、その「並行進化」の実態を立体的に解明することを目的とする。ご提示いただいた「西洋馬術の指南書」という基本情報に留まらず、両文化の深層に横たわる構造的な差異とその必然性を探求する。
第一章:騎士の世界 ― ルネサンス期ヨーロッパと『Gli ordini di cavalcare』
本章では、グリゾーネの馬術書が生まれた背景、すなわちルネサンス期ヨーロッパの騎士と、彼らが形成した騎馬文化の全体像を解き明かす。それは、重装化する甲冑、大型化する軍馬、そしてその両者を戦場で一体として機能させるための高度な技術体系の世界であった。
1. ルネサンスの騎士と軍馬デストリア
16世紀のヨーロッパにおける戦場において、騎士は依然として戦局を左右する決戦兵力の中核をなしていた。冶金技術の向上によって生み出されたプレートアーマー(全身鎧)は、騎士の防御力を飛躍的に高めたが、同時にその重量も著しく増大させた 1 。この数十キログラムにも及ぶ鉄の塊を身にまとった人間を乗せ、なおかつ戦闘時の激しい機動に耐えうるためには、並外れて強靭な軍馬が不可欠であった。
この要求に応える形で品種改良が進められたのが、騎士が騎乗した軍馬「デストリア」である 1 。デストリアは、その大きさと力強さで知られるが、近年の研究では、その体高は現代の競走馬であるサラブレッドを超えるような巨大なものではなく、平均して14ハンド(約142cm)から15ハンド(約152cm)、特に優れた個体でも16ハンド(約163cm)程度であったと考えられている 2 。デストリアを特徴づけたのは、単なる体高ではなく、重装騎士を乗せて敵陣に突撃するための爆発的な瞬発力と、それを支える強力な後躯、そして筋骨隆々たる強健な体格であった 2 。これらは戦闘専用に幼駒の頃から特別に育成された高価な牡馬であり、所有すること自体が騎士の富と社会的地位を誇示する象徴でもあった 2 。
ここで見られるのは、騎士の重装化とデストリアの大型化・強力化が、単なる個別の事象ではなく、相互に影響を与え合いながら進んだ「軍事技術の共進化」とでも言うべき現象である。甲冑の性能向上が騎士の生存率を高める一方で、その重量増は従来の馬の機動力を奪う。この課題を克服すべく、より強力で耐荷重能力の高いデストリアが求められ、その登場はさらなる重装化や、馬自身に馬鎧(バーディング)を施す余裕さえ生み出した 1 。この「騎士の装甲」と「軍馬の能力」の相互作用こそが、ヨーロッパ特有の重装騎兵という、戦場の主役たる兵種を完成させたのである。
2. 馬術の科学化:グリゾーネの馬術書
このような時代背景の中、1550年にナポリで出版されたフェデリコ・グリゾーネの『Gli ordini di cavalcare』は、馬術史における画期的な一冊となった。古代ギリシャの軍人クセノフォンが馬術に関する著作を残して以来、実に二千年近くもの間、馬術は主に経験豊かな師から弟子への口伝や個人的な技術の蓄積に頼ってきた 6 。グリゾーネの著作は、この経験知の集合体を、体系的かつ理論的に整理し、誰でも学習・伝達可能な形で提示した、近代ヨーロッパで最初の印刷された馬術書であった 8 。
本書の登場により、馬術は単なる職人的な技術から、理論と実践を伴う「高貴な芸術(noble art form)」へとその地位を高められた 9 。その内容は、馬の性質や気性を見極める方法、臆病さや反抗といった悪癖を矯正する具体的な手順、そして戦争と日常の実用のための調教法を網羅していた 8 。特に、馬の口の形状や感受性に応じて使い分けるべき多種多様な轡(はみ)を、詳細な木版画の図解と共に解説した部分は、本書の大きな特徴であり、馬の制御を科学的に捉えようとする彼の姿勢を明確に示している 8 。この革新的な馬術書はたちまちベストセラーとなり、イタリア語の初版以降、フランス語、ドイツ語、英語など各国語に翻訳され、ヨーロッパ全土の宮廷や軍隊における馬術の発展に絶大な影響を及ぼしたのである 10 。
3. グリゾーネ馬術の核心:戦闘のための高等馬術
グリゾーネが体系化した馬術は、フランス語で「マネージュ(Manège)」と呼ばれ、現代における馬場馬術の直接的な源流とされる 9 。しかし、その本質は観賞用の優雅な演技ではなく、極めて実戦的な戦闘技術の集大成であった 13 。その目的は、騎士の必殺戦術である「ランスチャージ」を、戦場で最大限に効率化することにあった。
ランスチャージとは、馬の疾走速度と重量、そして乗り手である騎士の体重の全てを、長く頑丈な槍(ランス)の先端一点に集中させて敵を粉砕する、破壊的な突撃戦法である 14 。しかし、この一撃は万能ではなく、敵陣を貫通した後、あるいは最初の一撃を外した後、いかに迅速に体勢を立て直し、再攻撃に移るかが騎士の生死を分けた。グリゾーネの馬術は、まさにこの「突撃から再突撃へ」という一連の戦闘サイクルを、洗練された連続動作として完成させるための技術体系だったのである。
その具体的なプロセスは以下の通りである。
- レポローネ(Repolone): 敵に対する直線的な襲歩(ギャロップ)による突撃。これがランスチャージの基本となる機動である 13 。
- ペサード(Pesade): 突撃後、馬を急停止させ、その勢いを利用して後肢で立ち上がらせる運動。これは単なる見栄えのための演技ではない。馬の重心を後方に集約させ、前肢を浮かせることで、狭い場所での素早い方向転換を可能にするための、極めて合理的な準備運動であった 13 。
- ピルエット(Pirouette): ペサードで後方に集めた重心を軸に、後肢をほとんど動かすことなくその場で180度旋回する技術。これにより、騎士は敵に背を向ける時間を最小限に抑え、即座に次の突撃態勢へと移行することができた 13 。
この「レポローネ → ペサード → ピルエット → 再びレポローネ」という連続動作こそ、グリゾーネ馬術の軍事的本質である。現代、ウィーンのスペイン式宮廷馬術学校などで披露される高等馬術の華麗な跳躍演技(ルヴァード、クールベット、カプリオーレなど)も、元をたどれば、このペサードから発展した、馬の運動能力を極限まで高めるための戦闘機動であった 17 。その意味で、これらの古典馬術は、その軍事的起源が時代と共に形骸化し、芸術として洗練されて現代に受け継がれた「生きた化石」と見なすことができるのである。
4. 騎士の武具と馬具:ランスチャージを支えるシステム
ランスチャージという特異な戦術を可能にしたのは、馬術だけでなく、それを支える武具と馬具のシステムであった。
- 西洋鞍の構造: 騎士が用いた鞍は、頑丈な木製の鞍骨(ツリー)を基礎構造としていた 19 。その最大の特徴は、乗り手の体を深く、そして固く包み込む形状にある。特に、鞍の前方に高くそびえる前輪(ポメル)と、背後を支える後輪(カントル)は、ランスが敵に命中した際の凄まじい衝撃で騎手が後方に吹き飛ばされたり、落馬したりするのを防ぐために不可欠な構造であった 22 。この鞍は、騎手を馬体に「固定」し、人馬一体の「運動エネルギー体」を作り出すための装置だったのである。
- 多様な轡(はみ)の役割: 前述の通り、グリゾーネは馬の口の形状や気性、調教の段階に応じて、驚くほど多様な轡を図解し、その効果を論じた 8 。これらは、馬の頭と頸を、騎手の意のままに制御された状態(コレクション)に保つための道具であった。手綱を通じて伝えられる騎手の微細な扶助(合図)を正確に馬に伝えるコミュニケーションツールであると同時に、時には馬に苦痛を与えてでも強制的に従わせるための、強力な制裁具としての側面も持っていた 9 。グリゾーネの調教法において、轡は馬との対話と支配の根幹をなす、極めて重要な要素だったのである。
- 鐙(あぶみ)の役割: 騎乗時の安定性を高める鐙は、特にランスを脇に抱えて構える際に、騎手の上半身を鞍に固定するための重要な支点として機能した 14 。深く座り、鐙を踏ん張ることで、騎士は馬の突進力を自身の腕、そしてランスの穂先へとロスなく伝えることができた。
5. 乗り手の哲学:騎士道と馬
馬は、騎士にとって単なる兵器や移動手段ではなかった。騎士(フランス語: chevalier)という言葉自体が馬(cheval)に由来するように、馬は騎士のアイデンティティそのものと不可分に結びついていた 25 。
- 馬と騎士道: 馬を所有し、乗りこなすことは、土地と富を持つ支配階級の証であり、社会的なステータスシンボルであった 26 。同時に、戦場や長い旅路において苦楽を共にする文字通りの「伴侶」でもあり、その関係性は騎士物語の中でも頻繁に描かれている 27 。騎士道精神において、愛馬を失うことは自らの名誉を失うことに等しいとされ、戦闘中に敵の馬を意図的に狙うことは卑劣な行為と見なされた 27 。鞍は騎士の揺るがぬ勇気の象徴とさえされた 28 。
- グリゾーネの調教思想: 彼は馬術を「高貴な芸術」と位置づける一方で、その調教法には、現代の視点からは極めて残酷と評される側面も含まれていた 9 。例えば、抵抗する馬の尾にハリネズミを結びつけたり、水濠を渡ることを怖がる馬の頭を水中に押しつけて溺れさせかけたりといった、過酷な罰が記述されている 10 。
しかし、この一見矛盾するグリゾーネの思想を深く考察すると、ルネサンスという時代の精神性が浮かび上がってくる。彼の調教法に見られる「残酷さ」は、単なる非人道的な嗜好やサディズムではない。それは、戦場という極限状況下で「兵器」としての馬に、絶対的な信頼性と完璧な服従を求める、冷徹なまでの合理主義と実用主義の産物なのである。戦場で馬が騎手の意に反した行動を取ることは、騎手の死に直結する 11 。したがって、馬が持つ恐怖心や抵抗といった「不確定要素」は、戦闘が始まる前に徹底的に排除し、騎手の意思を絶対的なものとして刷り込む必要があった。彼が記述した厳しい罰は、この「絶対的服従」を確立するための、計算された手段であった 10 。
一方で、彼は罰だけでなく、正しい行動に対する報酬(優しい声や愛撫)の重要性も繰り返し説いている。罰の究極的な目的は、馬に「誤りの原因を理解させること」にあると述べ、馬を単なる機械ではなく、思考し学習する能力を持つ存在として認識していた 9 。この思想は、一見すると矛盾する「芸術性」と「実用性」、「人間的理解」と「非情な支配」を内包している。これこそが、神と科学、芸術と戦争が分かちがたく結びついていた、ルネサンスという時代の複雑な精神性を色濃く反映していると言えよう。
第二章:武士の世界 ― 戦国日本と弓馬の道
同じ16世紀、海の向こうの日本では、ヨーロッパとは全く異なる騎馬文化が発展していた。それは、小柄な馬と共に山野を駆け、弓を主兵装とした武士たちが築き上げた、「弓馬の道」の世界であった。
1. 戦国の武士と在来馬
戦国時代の日本においても、騎馬武者は軍の中核を成すエリート層であった 30 。彼らは自らの知行地から上がる収入で馬と武具を自弁する地主階級であり、馬上に乗る権利と技術を持つことが、正式な武士の証と見なされていた 30 。
しかし、彼らが騎乗した馬は、ヨーロッパのデストリアとは似ても似つかぬ存在であった。武士が用いたのは、木曽馬や北海道和種(道産子)に代表される、古来より日本列島に生息してきた在来馬である 31 。これらの馬の体高は平均して125cmから135cm程度であり、現代の感覚で言えばポニーに近い、非常に小柄な馬であった 31 。しかし、彼らは日本の山がちで複雑な地形に巧みに適応し、粗食にもよく耐え、優れた持久力と頑健さを備えていた 32 。その体格は、重装騎士を乗せての正面突撃には不向きであったが、日本の風土における機動的な運用には最適化されていたのである。
また、日本の馬は去勢されずに飼育されることが多かったため、気性の荒い牡馬同士が密集すると互いに争いやすく、ヨーロッパの騎兵隊のような整然とした密集隊形を組むことには、文化的な側面だけでなく、生物学的な困難も伴ったという指摘もある 36 。
2. 弓馬の道:日本の伝統馬術
日本の馬術は、武士の発生と共に発展し、室町時代にはその技術体系が専門的な流派として確立された。その代表格が、小笠原流と大坪流である 37 。これらの流派は、時の支配者である足利将軍家の馬術師範を務めるなど、武家社会において高い権威と地位を誇っていた 38 。
特に大坪流は、その理念として「馬術専一」を掲げていた点が興味深い 38 。これは、馬上での槍術や刀術といった直接的な戦闘技術とは一線を画し、純粋に馬を意のままに操るための操縦技術の洗練に特化していたことを意味する。この事実は、馬を操る専門技術と、馬上あるいは下馬して戦う武芸とが、ある程度分化して捉えられていた可能性を示唆している。
日本の伝統馬術の技術的な根幹には、「騎射三物(きしゃみつもの)」と呼ばれる三つの訓練法があった。それは、疾走する馬上から的を射る「流鏑馬(やぶさめ)」、より実戦的な角度の的を狙う「笠懸(かさがけ)」、そして馬場で放たれた犬を追いながら射る「犬追物(いぬおうもの)」である 31 。これらの訓練体系が示すように、日本の馬術は、その黎明期から一貫して、馬上から弓を射る「騎射」の技術を至上のものとして発展してきたのである。
3. 戦国合戦の実像:集団戦術と鉄砲の衝撃
武士の戦い方が、時代と共に大きく変容したことは、戦国時代の騎馬文化を理解する上で決定的に重要である。かつて平安・鎌倉時代の合戦では、騎馬武者同士が名乗りを上げて弓矢で射合う一騎討ちが、戦いの華とされた 30 。しかし、南北朝の動乱を経て、戦国時代に至ると、合戦の主役は個々の武勇を誇る騎馬武者から、大量に動員された足軽による集団戦へと完全に移行していた 30 。
この戦術パラダイムの変化に伴い、騎馬隊の役割も大きく変わった。彼らはもはや、単独で敵陣を粉砕する決戦兵力ではなくなった。その優れた機動力を活かし、味方の足軽槍隊や弓隊と緊密に連携しながら、敵陣の側面を脅かして攪乱し、奇襲をかけ、敗走する敵を追撃し、あるいは味方戦線の危機を救うための火消し役といった、より多角的で機動的な任務を担うようになったのである 30 。「戦国最強」と謳われた武田騎馬軍団も、ヨーロッパ的な重装騎兵による正面突撃部隊ではなく、その機動力を最大限に活用した戦術集団であったと、近年の研究では考えられている 30 。
そして、この流れを決定づけたのが、1543年の鉄砲伝来であった 42 。火縄銃は、それまでの弓矢とは比較にならない威力と貫通力を持ち、熟練を要さずに足軽でも扱うことができたため、瞬く間に日本全土に普及した 45 。織田信長が鉄砲の三段撃ち(その実態については諸説ある)を駆使して武田騎馬隊を破ったとされる長篠の戦いは、その象徴的な出来事である 40 。鉄砲の集団運用は、騎馬武者の突撃という戦術的価値を著しく低下させ、戦の主役を完全に歩兵へと移した。
この歴史的経緯を俯瞰すると、一つの重要な結論が導き出される。戦国時代の日本では、ヨーロッパのランスチャージに相当するような、重装騎兵による決定的突撃戦術は、本格的に確立される以前に、その軍事的な存在意義そのものを失ってしまったのである。日本の馬はもともと小型で重装化には不向きであり、武士の主兵装は弓であった 34 。戦闘の主体が集団歩兵戦へと移行する中で、騎馬の役割は突撃よりも指揮や機動へとシフトしていた 30 。そこへ、騎馬突撃に対する究極のカウンターウェポンである火器(鉄砲)が導入された 44 。これにより、ヨーロッパで数世紀にわたって繰り広げられた「槍(ランス)と盾(甲冑)」の進化のシーソーゲームが、日本では発生しなかった。戦術パラダイムは一気に「飛び道具と集団」へとジャンプし、その結果、グリゾーネが体系化したような、重装騎兵の突撃を前提とする高度な馬術は、日本の軍事環境においては必要とされなかったのである。
4. 武士の武具と馬具:騎射への最適化
日本の武具と馬具は、騎射という戦闘スタイルに最適化される形で、独自の進化を遂げた。
- 和鞍(わぐら)の構造と機能: 和鞍は、西洋の鞍とは全く異なる思想で設計されている。その最大の特徴は、鞍の前後に高くそびえる前輪(まえわ)と後輪(しずわ)、そして乗り手が座る部分(居木)が硬い木製で平らである点にある 49 。これは、騎手が深く座ることを目的とした西洋鞍とは正反対で、騎手が鐙の上に膝を立てて立ち上がり、腰を捻って前後左右あらゆる方向に弓を射るための「立ち透かし(たちすかし)」という特殊な騎乗法を可能にするための構造である 49 。素材は木であり、しばしば漆や蒔絵、螺鈿(らでん)といった日本の伝統工芸技術によって、豪華絢爛な装飾が施されることもあった 51 。
- 和鐙(わあぶみ): 日本の鐙は、足のつま先だけをかける西洋の輪鐙とは異なり、足裏全体をしっかりと乗せることができる「舌長鐙(したながあぶみ)」が平安時代末期から主流となった 53 。これにより、立ち上がった際の安定性が格段に増し、不安定な馬上で上半身を自在に使う騎射の技術を支えた。
- 和轡(わばみ): 西洋の轡が馬の口を強力に制御するために複雑な構造を発展させたのとは対照的に、日本の轡(和轡)は一本の棒状のものが多く、構造は比較的簡素であった 53 。これは、手綱を強く張って力で馬を制御するのではなく、騎手の体重移動と連動させた繊細な扶助を主としていた、日本独自の馬とのコミュニケーション方法を示唆している 53 。
5. 武人の哲学:武士道と馬
武士の精神的支柱は、後に「武士道」として体系化されるが、その原形は「弓馬の道(きゅうばのみち)」あるいは「弓矢の道」と呼ばれていた 55 。その名の通り、弓を射ることと馬を乗りこなすことに長けていることこそが、武士の根源的なアイデンティティであり、その職能そのものであった 57 。
馬は、武士にとって戦場で命を預ける重要なパートナーであり、移動と戦闘のための不可欠な手段であった 58 。流鏑馬が神事として神社に奉納されるように、馬は神聖な存在として敬われる側面も持っていた 39 。しかし、その関係性は、あくまで主君への忠義や家名の存続といった、より大きな集団的な価値観の中に位置づけられていた。個人の武勇や名誉の象徴として馬を捉える騎士道とは、その精神性の核において、微妙な、しかし決定的な違いがあったのである。
第三章:二つの世界の邂逅 ― 徹底比較分析
第一章と第二章で詳述した内容に基づき、16世紀のヨーロッパと日本における騎馬文化の差異を、表を用いて明確化し、その背景にある本質的な違いを浮き彫りにする。
1. 軍馬の比較:デストリア対在来馬
両者の戦術思想の違いは、単なる文化的な選択ではなく、根底にある「ハードウェア」としての馬の性能差に大きく起因していた。この物理的・生物学的な制約を一覧することで、なぜ日本でランスチャージが発展しなかったのか、その根源的な理由が明らかになる。
|
項目 |
西洋軍馬(デストリア) |
日本在来馬(木曽馬など) |
|
平均体高 |
150~160cm 2 |
125~135cm 32 |
|
体格的特徴 |
筋骨隆々、強力な後躯、重装甲に対応 2 |
胴長短足、小型で頑健、山地に適応 32 |
|
主な用途 |
重装騎士による正面突撃(ランスチャージ) 1 |
軽装武士による騎射、機動的な戦闘 31 |
|
育成と価値 |
戦闘専用に高コストで育成されるエリート馬 2 |
農耕・運搬と軍事を兼務する多目的馬 34 |
|
戦場での役割 |
決戦兵力(ショック・トルーパー) 14 |
機動部隊(指揮、攪乱、追撃、偵察) 30 |
2. 馬具と騎乗法の比較:安定性対機動性
馬具という「テクノロジー」は、特定の戦闘ドクトリン(戦術思想)と不可分に結びついている。鞍の形状の違いは、単なるデザインの差異ではなく、騎手の身体の使い方、ひいては主兵装(ランスか弓か)の選択を決定づける。この比較は、文化と技術の相互作用を理解する上で中心的な役割を果たす。
|
項目 |
西洋軍陣鞍 |
和鞍(軍陣鞍) |
|
構造 |
深い座席、高い前輪・後輪で体を固定 22 |
平らな木製の座席、極端に高い前輪・後輪 49 |
|
主目的 |
騎手の身体を安定させ、突撃の衝撃に耐える 14 |
騎手が鐙の上で立ち、上半身を自由に動かす 49 |
|
適合騎乗法 |
ディープシート・シッティング(深く座る騎乗法) |
立ち透かし(Tachisukashi) |
|
適合主兵装 |
ランス、刀剣 14 |
弓、長槍 31 |
|
轡(はみ) |
多様で複雑な構造。強力な制御を重視 8 |
比較的簡素な構造。重心移動による扶助が主 53 |
3. 戦術思想と精神性の比較
これらのハードウェアとテクノロジーの違いは、戦術思想と精神性の違いとなって表れる。
- 戦術思想の比較: ヨーロッパの騎士は、デストリアという強力な馬とランスという破壊的な武器を組み合わせ、個の力を最大化することで戦局を決定づけようとする「一点突破の決戦主義」を志向した。対照的に、戦国武士は、集団戦術への移行という時代の流れの中で、騎馬の役割を突撃力から機動力へと転換させ、歩兵部隊との連携を前提とした「統合的な戦力運用」を志向した。
- 精神性の比較: 騎士道は、キリスト教的な倫理観と結びつき、神への奉仕、弱者の保護、そして宮廷文化の中で貴婦人への献身といったロマンチックな側面を発展させた 14 。対して武士道は、主君への絶対的な忠誠と家名の存続という、より現実的で集団主義的な価値観にその根幹を置いていた 56 。馬の位置づけも、騎士にとっては個人の武勇と名誉を体現する象徴であったのに対し 27 、武士にとっては「弓馬の道」という言葉に示される通り、自らの職能と一体化した、より実用的な存在であった 55 。
第四章:仮説的遭遇 ― グリゾーネの教えは戦国日本に届いたか
16世紀半ば、日本とヨーロッパは歴史的な邂逅を果たした。では、グリゾーネによって体系化された西洋馬術の知識は、戦国時代の日本に伝わり、影響を与える可能性はなかったのだろうか。本章では、その歴史的接点を探り、なぜ西洋馬術が受容されなかったのか、その理由を多角的に論証する。
1. 南蛮貿易と情報の奔流
1543年の鉄砲伝来に始まり、ポルトガル商人やイエズス会宣教師の来航は、日本にヨーロッパの文化や技術、そして情報を大量にもたらした 36 。鉄砲やキリスト教といった目に見えるものだけでなく、天文学、医学、航海術など、様々な知識がこの時期に流入したことは想像に難くない。グリゾーネの馬術書もまた、この情報の奔流の中に含まれていた可能性はゼロではない。
2. 天正遣欧少年使節と西洋馬
より決定的と言える接点が、天正遣欧少年使節である。1582年に九州のキリシタン大名によって派遣された4人の少年使節は、ヨーロッパ各地を巡り、ローマ教皇に謁見した 60 。彼らが訪れたのは、まさにグリゾーネの馬術が宮廷文化の華として確立されていたルネサンス期のイタリアそのものであった。彼らが、当時の最高峰の文化であった高等馬術の演技を目の当たりにした可能性は極めて高い。
事実、彼らは帰国の際に、豊臣秀吉への献上品としてアラビア馬を連れ帰っている 36 。その雄大な体躯は、秀吉や居並ぶ諸大名を大いに驚嘆させたと記録されている 36 。また、宣教師ルイス・フロイスの『日本史』には、秀吉の居城である聚楽第において、ポルトガル式の見事な馬術が披露されたとの記述もある 36 。しかし、これらの出来事が日本の馬術に具体的な影響を与えたという形跡は、歴史上どこにも見出すことはできない。それは単なる珍しい見世物、あるいは外交儀礼上の献上品として消費されたに過ぎなかった。
3. パラダイムの衝突:なぜ西洋馬術は受容されなかったのか
西洋馬術が戦国時代の日本に受容されなかったのは、知識や機会がなかったからではない。それは、戦国日本の軍事・社会システム全体と、西洋馬術という文化体系との間に、到底埋めることのできない「パラダイムの断絶」が存在したからである。その理由は、以下の四点に集約される。
- 生物学的・地理的制約: そもそも日本には、重装騎士を乗せてランスチャージを行うためのデストリアのような大型馬が存在しなかった。また、平野の少ない山がちな国土は、重装騎兵による大規模な集団突撃には不向きな地形であった 32 。
- 戦術的陳腐化: これまで繰り返し述べてきたように、日本では鉄砲の急速な普及により、騎馬による正面突撃という戦術そのものが、すでに有効性を失い、時代遅れとなっていた 42 。価値を失った戦術のために、全く新しい馬術体系と、それに付随する高コストなシステムを導入する軍事的合理性は皆無であった。
- 技術的・経済的障壁: グリゾーネの馬術を導入するということは、単に乗り方を変えるだけではない。それは、馬の品種改良から始まり、ランスチャージに耐える特殊な鞍や、複雑な構造を持つ轡、さらには乗り手である騎士の甲冑に至るまで、関連する全ての技術体系をセットで輸入、あるいは国産化することを意味する。これは、当時の日本の技術的・経済的基盤から見て、あまりにも非現実的な要求であった。
- 文化的親和性の欠如: 日本には、すでに「弓馬の道」として高度に洗練され、武士の精神性と固く結びついた独自の馬術文化が存在した。その担い手である武士たちにとって、全く異なる思想と身体操作を要求する西洋馬術は、異質で実用性に乏しい曲芸のように映ったであろう。
4. 後世への布石:江戸・明治期における導入
西洋馬術が日本に本格的に導入され、定着するのは、全く異なる時代背景においてであった。実戦の必要性がなくなった平和な江戸時代、8代将軍徳川吉宗がオランダから馬術家を招いて導入を試みたのがその始まりである 36 。そして、国家体制そのものを西洋化し、富国強兵を目指した明治時代に至り、陸軍の兵制改革の一環として、初めて組織的に導入された 6 。これは、軍事ドクトリンや社会全体の変革という、新しい文化を受容するための「土壌」が整って初めて、異文化の移植が可能になることを示す好例と言える。
結論
本報告書は、16世紀のヨーロッパと日本に存在した二つの騎馬文化を、フェデリコ・グリゾーネの『Gli ordini di cavalcare』を基軸として比較分析した。その結果、以下の結論が導き出された。
グリゾーネの馬術書が体系化した騎士の乗馬術は、ルネサンス期ヨーロッパの「重装騎兵による決定的正面突撃」という軍事思想を背景に、大型の軍馬デストリア、身体を固定する西洋鞍、馬を強力に制御する轡、そしてランスという兵器を一つの有機的なシステムとして完成させた、科学的馬術の金字塔であった。それは、個の力を極限まで高め、戦場の一点に投射することで戦局を打開しようとする、ヨーロッパの軍事思想の論理的帰結であった。
一方、戦国武士が実践した「弓馬の道」は、日本の小型在来馬と山がちな地形という環境、そして「騎射から集団歩兵戦へ」という戦術史の大きな変遷に適応する形で、独自の洗練を遂げた、実践的馬術の体系であった。立ち透かしを可能にする和鞍と、騎手の重心移動を重視する乗り方は、機動性と柔軟性を最大限に引き出し、集団戦の中での多様な任務に対応するための、日本の軍事環境が生んだ論理的帰結であった。
両者は、どちらが優れ、どちらが劣るという優劣で語られるべきものではない。それぞれが、全く異なる環境と歴史的要請の中で、それぞれの論理に基づいて最適化された「並行進化」の頂点なのである。16世紀の日本とヨーロッパは、馬という一つの生き物を介して、全く異なる二つの「完璧な世界」を、奇しくも同時に築き上げていた。本報告書が、その二つの世界の構造的な差異と、その背景に横たわる歴史の必然性を明らかにする一助となれば幸いである。
引用文献
- 「鎧(よろい)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%8E%A7
- Destrier - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Destrier
- Knights and destriers: representations and symbolism of the medieval warhorse in medieval art https://mad.hypotheses.org/375
- The Destrier - English Historical Fiction Authors https://englishhistoryauthors.blogspot.com/2014/10/the-destrier.html
- What is a destrier? Why did knights stop using them after the middle ages? - Quora https://www.quora.com/What-is-a-destrier-Why-did-knights-stop-using-them-after-the-middle-ages
- 馬術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E8%A1%93
- 馬術の起源を詳しく紹介!馬術が始まったのはいつから?発祥国はどこの国? - ジョッパーズ https://jodhpurs.jp/contents/blog/20240322-26315/
- Ordini di cavalcare, et modi di conoscere le nature de cavalli, di ... https://www.libreriagovi.com/17th-century/ordini-di-cavalcare-et-modi-di-conoscere-le-nature-de-cavalli-di-emendare-i-loro-vitii-dammaestrargl
- THE LEGACY OF FEDERICO GRISONE Elizabeth M. Tobey In ... - Brill https://brill.com/downloadpdf/book/edcoll/9789004222427/B9789004222427_007.pdf
- Federico Grisone - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Grisone
- Federigo Grisone: The Art of Horsemanship - Village Antiques https://www.villageantiques.ch/print-collection/federigo-grisone-the-art-of-horsemanship/
- Biobibliographie - Grisone, Federico (15.. - La Bibliothèque Mondiale Du Cheval https://labibliothequemondialeducheval.org/biobiblio/doc/pddn_p.BMC_4118.html
- “Maneggi and jumps”. The basic exercises of Renaissance ... https://worksofchivalry.com/maneggi-and-jumps-the-basic-exercises-of-renaissance-horsemanship-part-1/
- 騎士という存在 | ミリタリーショップ レプマート https://repmart.jp/blog/knight/
- ランス(西欧) - bukipedia @ ウィキ https://w.atwiki.jp/bukipedia/pages/54.html
- 【武器解説】中世騎士の槍・ランス【ゆっくり解説】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=XBEwkeS2YOY
- スペイン式宮廷馬術学校 - Austria.info https://www.austria.info/ja/inspiration/spanish-riding-school
- スペイン式宮廷馬術学校 - Austria.info https://www.austria.info/ja/inspiration/spanish-riding-school/
- 中世の馬 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E4%B8%96%E3%81%AE%E9%A6%AC
- Western vs. English Saddle - Texas Saddlery https://txsaddlery.com/blogs/news/western-vs-english-saddle
- What Is the Difference Between English and Western Saddles? - TexanSaddles.com https://texansaddles.com/blogs/saddle-research/what-is-the-difference-between-english-and-western-saddles
- Saddle https://www.1066.co.nz/Mosaic%20DVD/text/horse/Saddles.htm
- Federico Grisone – was he really such a baddie? - The Horse Magazine https://www.horsemagazine.com/thm/2015/03/federico-grisone-was-he-really-such-a-baddie/
- (PDF) Military Equitation or a Method of Breaking Horses (and Teaching Soldiers to Ride, Designed for - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/258693289_Military_Equitation_or_a_Method_of_Breaking_Horses_and_Teaching_Soldiers_to_Ride_Designed_for
- 騎士道物語の表すもの|哲学記事|NPO法人ニューアクロポリス https://www.acropolis.jp/articles/35
- 「馬」と「剣」~騎士を因数分解する|伊藤 敏《世界史講師》 - note https://note.com/less_sugar_in17/n/n4cf9be9e7f43
- 〔論 説〕 - 中英語騎士物語における騎士と馬との関係についての ... https://cuc.repo.nii.ac.jp/record/5658/files/Kiy20180026%E8%B2%9D%E5%A1%9A.pdf
- 騎士道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A8%8E%E5%A3%AB%E9%81%93
- Ordini di cavalcare http://greenhorseasd.altervista.org/libri/Ordini_di_cavalcare.pdf
- 騎馬隊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A8%8E%E9%A6%AC%E9%9A%8A
- 騎馬隊と流鏑馬/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/40364/
- 馬の豆知識 馬の種類(日本在来馬) - みんなの乗馬 https://www.minnano-jouba.com/mame_chishiki02.html
- 日本古来の在来馬「トカラ馬」が来園します - 東京ズーネット https://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=news&inst=ueno&link_num=7720
- 日本在来馬 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9C%A8%E6%9D%A5%E9%A6%AC
- 天下城ノート3・戦国の合戦と騎馬部隊 https://www.sasakijo.com/archive/tenka3.html
- 日 本 在 来 馬 と 西 洋 馬 - 公益社団法人日本獣医師会 https://jvma-vet.jp/mag/06406/a6.pdf
- 乗馬の起源 https://equia.jp/trivia/post-15695.html
- 大坪流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%AA%E6%B5%81
- 流鏑馬―日本の古式弓馬術の800年の伝統を今に― | December 2023 | Highlighting Japan https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202312/202312_11_jp.html
- 騎馬武者とは/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/kibamusya/about-kibamusya/
- 日本近世までの戦場での戦い方 https://umenoyaissei.com/nihonkinseimadenosenjou.html
- 火縄銃(鉄砲)の普及と甲冑の変化/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/40369/
- 火縄銃と長篠の戦い/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/arquebus-basic/hinawaju-nagashino/
- なぜ鉄砲 が急速に普及したのか、鉄砲は何を変えたのか - 戦国リサーチノート by 攻城団 https://research-note.kojodan.jp/entry/2025/05/01/142211
- 騎馬隊は馬から降りて戦った!?戦国時代、出陣した時の装備とは? https://sengoku-his.com/166
- 火縄銃(鉄砲)とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47464/
- 武田軍も鉄砲を使っていた? 「鉛の研究」で見えた長篠合戦の新事実 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8874
- 長篠の戦いと鉄砲・西洋銃/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/89110/
- 鞍の種類いろいろ | Pacalla(パカラ) https://pacalla.com/article/article-1645/
- 馬場鞍・障害鞍の違いとは?2つの鞍を徹底比較! https://jodhpurs.jp/contents/blog/20230314-22293/
- 和鞍の修復/ホームメイト https://www.touken-collection-kuwana.jp/exhibition-detail/repair-cultural-property-wagura/
- Saddle (Kura) - Japanese - The Metropolitan Museum of Art https://www.metmuseum.org/art/collection/search/26572
- 和式馬具とは - NPO法人日本和種馬文化研究協会 https://www.washuuma-bunka.org/index.php/information/washikibagu/
- 鞍(くら)と鐙(あぶみ)の基本/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/36809/
- 武士道の謂れ https://www.umenoyaissei.com/bushidounoiware.html
- 弓馬の道(キュウバノミチ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BC%93%E9%A6%AC%E3%81%AE%E9%81%93-477297
- 「武士とは馬に乗る人」 東大教授・本郷和人の日本史講座 - YouTube https://www.youtube.com/shorts/87MCkhOeXtc
- 武士道と剣道/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/109205/
- にっぽんの在来馬、伝統馬事芸能 JRA https://www.jra.go.jp/gallery/update/info/geinou/index.html
- 天正遣欧少年使節 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E9%81%A3%E6%AC%A7%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BD%BF%E7%AF%80
- 【終了】西洋馬術導入の地=浜離宮 - 東京都公園協会 https://www.tokyo-park.or.jp/park/hama-rikyu/news/2024/11_2_4.html