北条氏直
北条氏直は後北条氏五代当主。天正壬午の乱で勢力を拡大するも、豊臣秀吉の天下統一に抗しきれず小田原合戦で降伏。高野山へ追放後赦免され、豊臣大名として再起するも病没。
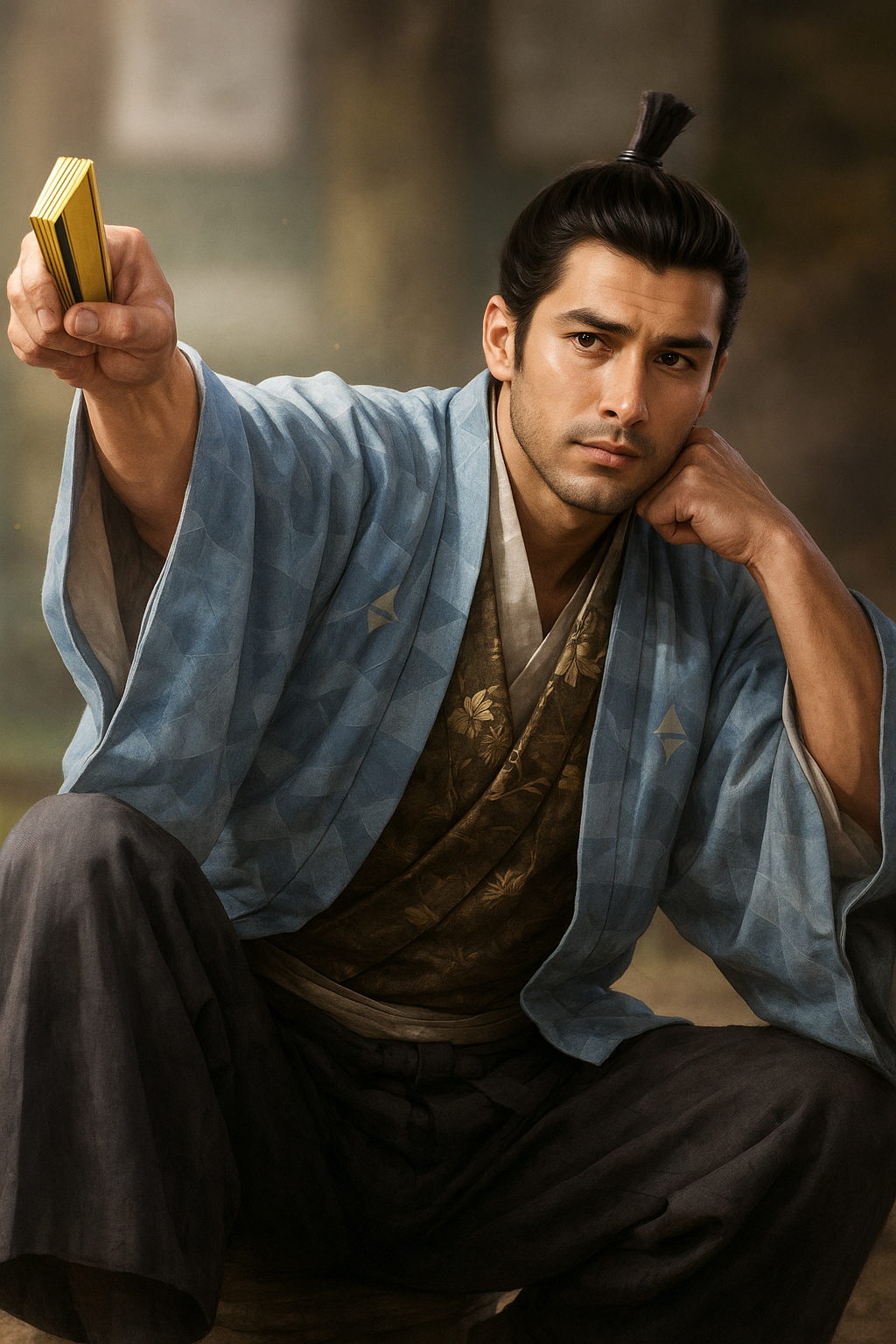
北条氏直:戦国終焉に関東の巨星墜つ
序論
北条氏直研究の意義と本報告書の目的
後北条氏五代、その最後の当主である北条氏直は、戦国時代の終焉と近世日本の幕開けという、我が国史における一大転換点にその身を置いた人物である。彼の治世下における決断と行動は、関東に一大勢力を築き上げた後北条氏の命運を最終的に決定づけることとなった。本報告書は、現存する多様な史料群を丹念に検証し、氏直の生涯、その政治的・軍事的活動、領国統治の具体相、そして歴史の中に彼がどのように位置づけられてきたのかを、多角的な視座から明らかにすることを目的とする。特に、父である氏政との複雑な権力関係、天下統一を目前にした豊臣秀吉との対立の深層、そして北条家滅亡後の氏直自身の動向に焦点を当てることで、彼が置かれた極めて困難な状況と、それに対する彼の対応の実像に迫りたい。
第一章:北条氏直の出自と家督相続
第一節:生誕と家系
北条氏直は、永禄5年(1562年)、後北条氏四代当主・北条氏政の次男として、関東支配の拠点であった小田原城において生を受けた 1 。兄である新九郎が早世したため、氏直が嫡男として遇されることとなった 1 。幼名は国王丸と称し 1 、後に仮名として新九郎を名乗った 1 。母は甲斐の武田信玄の娘である黄梅院であり 1 、この出自により、氏直は武田義信や武田勝頼の外甥という関係にあった 1 。
氏直の母、黄梅院の生涯については、従来、永禄11年(1568年)末に武田氏が駿河へ侵攻したことにより、夫である氏政と離縁させられ、実家である武田家へ送り返された後、永禄12年(1569年)6月に病没したという説が広く知られていた 1 。しかしながら、近年の研究においては、この通説に疑義が呈され、黄梅院は離縁されることなく小田原城内でその生涯を終えたとする見解が有力視されている 1 。さらに、氏直の実母は黄梅院ではなく、北条家譜代の重臣であった笠原康明の娘ではないかという説も提示されており 3 、この点は氏直の幼少期における立場や、甲斐武田氏との関係性を理解する上で、極めて重要な論点となっている。
氏直の出自は、甲相同盟に代表される、戦国時代特有の複雑かつ流動的な大名間の外交関係を色濃く反映している。生母に関する説の変遷は、史料の再解釈や新史料の発見による歴史研究の進展を示すと同時に、氏直自身のアイデンティティ形成や、北条家内部における彼の立場、さらには武田氏との関係認識に、少なからぬ影響を与えた可能性が考えられる。仮に黄梅院が小田原で死去したという説が事実であれば、武田氏との関係が悪化した時期における氏直の心理的状況は、従来考えられてきたものとは異なる様相を呈するであろう。例えば、母の死が、武田氏との断交を決意した父・氏政の判断に何らかの影響を及ぼし、それが氏直の対武田観にも投影されたというシナリオも想定しうる。また、もし氏直の母が笠原康明の娘であったとすれば、北条家臣団内部の勢力図や、嫡男としての氏直を支持する基盤に変化が生じた可能性も否定できない。笠原氏は北条家における譜代の重臣であり、その外孫であるという事実は、氏直の立場をより強固なものとする一方で、武田氏との血縁関係が薄まることにより、外交戦略上の意味合いも変容したであろう。
以下に、北条氏直の生母に関する諸説を比較検討のため、表として示す。
表1:北条氏直の生母に関する諸説比較
|
説 |
内容 |
主な根拠史料・提唱者 |
氏直の立場・北条家外交への示唆 |
|
通説 |
黄梅院(武田信玄娘)。武田氏の駿河侵攻後、離縁され甲斐へ帰国、その後病死 1 。 |
従来の歴史書・記録など |
武田氏との血縁が強調される。離縁・母の死が若き氏直に精神的影響を与えた可能性。 |
|
新説 |
黄梅院。離縁されず小田原城内で死去 1 。 |
近年の史料研究(書状など) |
武田氏との関係悪化後も、一定期間は黄梅院が小田原に在住。氏直の立場への直接的影響は通説より少ない可能性。 |
|
異説 |
笠原康明(北条家重臣)の娘 3 。 |
浅倉直美氏の研究(黄梅院の出産記録の不在など) 3 。 |
武田氏との直接的な血縁関係が薄まる。北条家臣団内部の支持基盤に影響。外交戦略上、武田氏との関係よりも、国内の安定や家臣団との連携を重視する方向性を示唆する可能性。 |
この表は、氏直研究の基礎となる出自について、複数の説が存在することを明確にし、それぞれの説が持つ歴史的文脈や解釈の違いを提示することで、より深い理解を促すものである。歴史研究が常に進展し、新たな視点が生まれることを示す好例と言えよう。
第二節:家督相続の経緯と初期の活動
氏直の幼少期から青年期にかけては、後北条氏を取り巻く情勢が大きく変動する時期と重なる。永禄12年(1569年)5月、当時没落しつつあった今川氏の当主・今川氏真の猶子となり、名目上その家督を相続することで、将来的な駿河領有の権利を得たとされる 1 。しかし、武田信玄による駿河侵攻と実効支配が進んだため、この構想は現実のものとはならなかった。この今川氏との養子縁組は、氏直の母・黄梅院の死去(あるいは武田氏との関係性の変化)、または叔母にあたる早川殿(今川氏真の正室)が男子を出産したことなど、複数の要因が絡み合い、遅くとも元亀3年(1572年)までには解消されたと見られている 1 。
天正5年(1577年)3月までには元服を済ませ、仮名である「新九郎」を正式に名乗るようになった 1 。同年11月には、上総国において初陣を飾る。この戦いにおいて、氏直は父・氏政と共に軍を率い、安房国の里見義弘と戦い、最終的には和睦を成立させた(房相一和)。この和睦の条件として、氏政の娘が里見義頼に嫁いでおり、北条氏と里見氏は同盟関係に入った 1 。
そして天正8年(1580年)8月19日、父・氏政が隠居したことにより、氏直は19歳で後北条家第五代当主の座を継承した 1 。特筆すべきは、この家督相続が、氏政が出陣中という異例の状況下で行われたことである 1 。従来の通説では、隠居後も氏政が実権を掌握し続けたとされてきたが、近年の研究では、内政や家臣団の統制に関する権限は速やかに氏直に移譲され、軍事に関する権限も一部が委ねられた一方で、氏政は外交と軍事の主要部分を引き続き担当するという、一種の二頭体制であったとの見方が有力となっている 1 。
氏直の家督相続は、単なる形式的な権限移譲ではなく、父・氏政との間での明確な役割分担を伴うものであった。この二頭体制が、その後の北条家の意思決定プロセスや対外政策の展開にどのような影響を及ぼしたのかについては、詳細な検討を要する。氏政が出陣中に隠居し、氏直に家督を譲った真の狙いは何だったのか。単なる権限委譲に留まらない、例えば対外的、あるいは対内的な何らかの戦略的意図が存在した可能性も否定できない。この二頭体制と、当時北条家内部に存在したとされる穏健派と強硬派の対立(ただし、 1 では氏政が必ずしも強硬派ではなかった可能性も示唆されている)が、豊臣政権への対応をより複雑なものにした要因の一つであったかもしれない。また、このような権力構造が、家臣団の間に混乱や派閥対立を生じさせなかったか、あるいは内外の敵対勢力に北条家の内部分裂という印象を与え、それが外交交渉や軍事戦略において不利に作用した可能性も考察すべき点である。
第二章:北条氏直の関東における政治・軍事活動
第一節:天正壬午の乱と勢力拡大
氏直が家督を相続して間もない天正9年(1581年)、叔父にあたる武田勝頼と伊豆三島において対陣する事態が生じた 1 。翌天正10年(1582年)3月、織田信長の侵攻により武田氏が滅亡すると、関東の勢力図は大きく塗り替わる可能性を秘めることとなる。さらに同年6月、信長が本能寺の変で横死すると、この政治的空白を好機と捉えた氏直は、叔父の北条氏邦らと共に大規模な軍勢を率いて上野国への侵攻を開始した 1 。
この動きの中で、北条軍は織田方の大名であった滝川一益の軍勢と神流川において激突し、これに勝利を収めた(神流川の戦い)。勢いに乗った北条軍は、上野国からさらに信濃国へと進攻し、佐久郡や小県郡をその支配下に収めることに成功した 1 。
しかし、甲斐国においては、同じく武田氏の旧領獲得を目指す徳川家康の軍勢と衝突することになる。氏直は甲斐若神子城に本陣を置き、家康軍と約80日間にわたって対峙した(天正壬午の乱) 1 。この間、北条方についていた真田昌幸らが離反し、また黒駒合戦において徳川方に敗退するなど、戦線は膠着状態に陥った 1 。
最終的に、織田信雄・信孝兄弟の調停により、北条氏と徳川氏の間で和睦が成立する。その条件は、上野国を北条氏直が、甲斐国と信濃国を徳川家康がそれぞれ領有するというものであった。さらに、この和睦を強固なものとするため、家康の娘である督姫が氏直に嫁ぐことが決定された 1 。この一連の動きにより、北条家は長年の悲願であった関東のほぼ全域(下野国の一部と常陸国を除く)を支配下に置くという目標に大きく近づくこととなった 4 。
本能寺の変という未曾有の政変を利して、迅速に軍事行動を起こしたことは、北条家の関東における覇権確立への強い意志の表れと言える。徳川家康との和睦および婚姻同盟の締結は、短期的には北条領国の安定に寄与したものの、長期的には中央で急速に台頭しつつあった豊臣政権との関係において、複雑な要素を内包することになる。特に督姫との婚姻は、家康との個人的な繋がりを深めることとなり、後の小田原合戦における氏直の助命に繋がる重要な伏線となった 1 。天正壬午の乱における真田昌幸の離反は、その後の名胡桃城事件へと繋がる根深い因縁の始まりと見なすこともできよう。徳川との同盟締結は、北条家が中央政権(織田、そして豊臣)から一定の距離を置き、関東における独自の勢力圏確立をより強く志向する姿勢を鮮明にした結果と解釈できる。この同盟が、豊臣秀吉の「関東惣無事令」に対する北条家の認識を結果的に甘くさせた可能性も否定できない。
第二節:沼尻の合戦とその意義
天正壬午の乱を経て関東における勢力を拡大した北条氏であったが、その支配に対する抵抗も根強かった。天正12年(1584年)、常陸国の佐竹義重や下野国の宇都宮国綱らを中心とする反北条連合軍と、北条氏直率いる軍勢が下野国沼尻において対峙するに至った。これが沼尻の合戦である 1 。
史料によれば、北条軍の兵力は約70,000、対する佐竹・宇都宮連合軍は約20,000から30,000とされ、兵力では北条方が圧倒していた。注目すべきは、連合軍が当時最新兵器であった鉄砲を8,000丁以上も用意していたと伝えられている点である 6 。これは、織田信長が長篠の戦いで用いたとされる鉄砲の数を上回るものであり、当時の戦術における鉄砲の重要性の高まりを示している。
合戦は、両軍ともに決定的な大規模戦闘を避ける形で長期戦の様相を呈し、一説には110日間に及ぶ長陣であったとも記録されている 6 。この間、北条方は調略を駆使し、連合軍に参加していた皆川広照らを寝返らせることに成功し、連合軍の退路となっていた岩船山の陣城を攻略した 6 。
最終的に、両陣営の間で講和が成立し、合戦は引き分けという形で終結した。しかし、その後の戦後処理においては北条氏が優位に進め、連合軍に与していた由良氏や長尾氏は北条氏に降伏することとなった 6 。この結果に対し、佐竹氏傘下の真壁氏幹は、主君である佐竹義重の対応を激しく非難する書状を送っている 6 。
沼尻の合戦は、いくつかの重要な意義を持つ。第一に、北条氏の北関東への影響力の強大さを示すと同時に、佐竹氏や宇都宮氏を中心とする反北条勢力の抵抗がいかに激しいものであったかを物語っている。第二に、この合戦を最後に、父である北条氏政が直接軍勢を率いて出陣する姿は見られなくなる。そして同年12月には、氏直が氏政の官途名であった「左京大夫」を名乗り始めており、これにより、名実ともに氏直が後北条家の当主として内外に認識されるようになったことを象徴している 1 。沼尻の合戦における北条氏の調略成功は、関東諸勢力の内部結束が必ずしも強固ではなかったことを示唆している。この合戦の結果、北条氏が北関東における優位を確立したことは、豊臣秀吉による「関東惣無事令」発令の遠因の一つとなった可能性も考えられる。秀吉が関東地方の安定化をより強く意識する契機となったかもしれない。また、佐竹・宇都宮氏にとって、この合戦での実質的な敗北は、彼らが中央の豊臣政権への依存を一層深める結果を招き 6 、後の小田原征伐における対北条包囲網の形成へと繋がったと推察される。
第三節:壬生氏・皆川氏等、関東諸勢力との関係
沼尻の合戦後、北条氏は北関東における影響力をさらに強固なものとするため、外交と軍事の両面を巧みに用いて、周辺の諸勢力に対する圧力を強めていった 6 。その結果、天正14年(1586年)には、下野国の有力国衆であった佐野宗綱が長尾氏との戦いで戦死すると、その後継者争いに介入し、最終的に北条一族である北条氏忠を佐野氏の養子として送り込むことに成功した 6 。
同じく天正14年(1586年)、下野国の皆川広照と壬生義雄も北条氏に降伏し、これにより下野国の西半地域は実質的に北条氏の勢力範囲となった 6 。
壬生氏については、当主であった壬生義雄の父・綱雄の代から、宇都宮氏からの独立と後北条氏との連携を模索する動きが見られた。義雄自身も最終的には後北条氏に味方する道を選び、天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐の際には、小田原城に籠城したが、落城直後に病没したと伝えられている 7 。
一方、皆川氏の当主であった皆川広照は、その父・俊宗の代には上杉方として北条氏と敵対した時期もあったが、広照の代になると北条氏に属するようになった 9 。広照は北条氏政の養女を正室として迎えるなど、北条氏との関係を深め、宇都宮氏攻めの際には北条軍の先陣を務めるなど、その軍事行動にも積極的に協力した 9 。
このように、北条氏は沼尻の合戦以降、巧みな外交戦略と軍事力を背景に関東の諸勢力を次々と傘下に収め、その支配領域を着実に拡大していった。養子縁組や婚姻政策は、初代早雲以来、北条氏が伝統的に用いてきた勢力拡大の有効な手段であり、氏直の代においてもその効果を発揮していたと言える。北条氏の急速な勢力拡大は、関東における伝統的な権威であった古河公方や関東管領の存在を一層形骸化させる結果を招いたと考えられる。そして、このような関東における力の空白と北条氏の突出した勢力は、中央で天下統一を進める豊臣秀吉にとって、新たな秩序構築の必要性を感じさせ、「関東惣無事令」という形で介入する正当性を高める一因となった可能性が指摘できる。
第三章:北条氏直の統治政策
第一節:後北条氏の検地政策と氏直の時代の特徴
後北条氏は、初代早雲の時代より領国経営の根幹として検地を重視し、実施してきた 11 。特に、当主が代替わりする際には大規模な検地を行う「代替わり検地」が伝統となっており、これは新当主による領国支配の意思を内外に示し、支配体制を再編・強化する上で重要な意味を持っていた 11 。例えば、三代当主の氏康は、天文10年(1541年)に家督を継承すると、その翌年から翌々年にかけて、相模国中央部、武蔵国南部および東南部、さらに伊豆国の一部に至る広範囲で一斉検地を断行した。この検地は、氏康自身の直轄領に留まらず、有力家臣の所領や寺社領にも及んでおり、氏康の権力が強大化していく過程を如実に示している 11 。
後北条氏が行った検地の特徴として、農民からの自己申告に基づいて行われる「指出(さしだし)」形式であった点が挙げられる 13 。これは、後の豊臣秀吉による全国的な検地(太閤検地)が、より強権的かつ統一的な基準で行われたのとは対照的である。また、後北条氏の検地は、必ずしも領国全域を網羅するものではなく、特定の地域に限定して実施されたり、一部では徹底さを欠いたりする側面もあったと指摘されている 13 。検地の主な目的は、第一に土地とそれに関わる収益を把握し、軍役負担を明確にすること、第二に家臣団の知行を再確認し主従関係を明確化すること、第三に家臣団の勢力を抑制し、後北条氏自身が農民を直接的に把握する体制を強化することにあったと考えられている 13 。伊豆国西浦の事例では、氏康の代である天文12年(1543年)に検地が実施され、「野帳」や「検地書出」といった詳細な記録文書が作成されたことが確認されている 14 。
しかしながら、五代当主である北条氏直の家督相続時においては、この伝統的な「代替わり検地」は実施されなかった。その代わりに「反銭(たんせん)」が増徴されたとの記録がある 12 。この政策転換は極めて注目すべき点であり、その背景には、当時の後北条氏が置かれていた複雑な状況があったと推察される。例えば、目前に迫っていた豊臣秀吉との対決に備えるための軍備増強が急務であり、大規模な検地を実施する時間的・人的・財政的余裕がなかった可能性、あるいは父・氏政の強い意向が働いた可能性などが考えられる。
氏直が代替わり検地を行わなかった(あるいは行うことができなかった)具体的な理由は、史料からは明確に断定できないものの、いくつかの要因が複合的に作用した結果であろう。目前に迫る豊臣政権との対決準備を優先したという説は、当時の緊迫した情勢を考慮すると説得力を持つ。この「反銭増徴」という措置が、検地によって得られるはずであった所領把握の正確性や、それに基づく軍役賦課の公平性をどの程度代替し得たのか、また、この政策変更が家臣団や農民層にどのような影響を与えたのかは、さらなる検討を要する課題である。代替わり検地の不実施と反銭増徴という一連の動きは、後北条氏の支配基盤に何らかの揺らぎをもたらした可能性も否定できない。検地による正確な領地把握と、それに基づく公平な軍役・租税負担という原則が揺らぐことは、家臣や民衆の間に不満を醸成し、結果として豊臣秀吉による調略が成功しやすい土壌を作り出したとも考えられる。この政策変更は、後北条氏の統治方針が、伝統的な安定志向から、より短期的な財政確保や軍事力強化へとシフトしつつあったことを示唆しており、時代の大きな変化、すなわち豊臣政権による天下統一の進展に対する、ある種の焦りの現れと解釈することも可能であろう。
以下に、後北条氏歴代当主の代替わり政策を比較し、氏直の代における特徴を明確にするため、表を示す。
表2:後北条氏歴代当主の代替わり政策比較
|
当主 |
家督相続年 |
代替わり検地の実施状況 |
主要な税制改革・家臣団統制策 |
備考(氏直の代について) |
|
初代 早雲 |
- (実質的な領国形成期) |
永正3年(1506年)相模国西郡宮地などで検地実施の記録あり 12 |
伝馬制度の整備など領国経営の基礎確立 15 |
- |
|
二代 氏綱 |
永正15年(1518年) |
永正17年(1520年)小田原城周辺・鎌倉で代替わり検地実施 12 |
「禄寿応穏」の理念に基づく民政重視 |
- |
|
三代 氏康 |
天文10年(1541年) |
天文11・12年(1542・43年)相模・武蔵・伊豆で大規模な代替わり検地実施 11 |
天文19年(1550年)税制改革(諸点役を段銭・懸銭に統合) 11 、「小田原衆所領役帳」作成(永禄2年・1559年) 11 |
- |
|
四代 氏政 |
永禄2年(1559年)頃 (実質的な権限掌握は氏康隠居後) |
代替わり検地の記録なし 12 |
氏康の政策を継承・発展 |
- |
|
五代 氏直 |
天正8年(1580年) |
代替わり検地実施されず 12 |
反銭が増徴される 12 |
豊臣秀吉との対立激化という時代背景。軍備増強のための財政確保が優先された可能性。検地不実施が支配基盤に与えた影響についてはさらなる考察が必要。 |
この表は、後北条氏の統治政策における連続性と変化、とりわけ氏直の代における政策の特異性を浮き彫りにするものである。
第二節:税制と家臣団統制
後北条氏の領国経営において、税制と家臣団統制は車の両輪であった。三代当主・氏康は天文19年(1550年)、画期的な税制改革を断行した。それまで領国内に存在した「諸点役(しょてんやく)」と呼ばれる雑多な税を整理し、所領の公定生産高である貫高に対して、その6パーセントを「段銭(たんせん)」、4パーセントを「懸銭(かけせん)」として徴収する形に統合したのである 11 。これにより、農民は年貢の他に、この段銭、懸銭、そして家屋にかかる棟別銭(むねべつせん)を加えた、いわゆる「三税」を納めることとなり、税負担の体系が明確化された 11 。
後北条氏の貢租制度全般を見ると、基本となる年貢は田からの収穫物である「田租」(米で納入されたが、表示は貨幣単位の貫文で行われた)と、畠からの収穫物である「畠租」であり、貨幣経済の浸透に伴い、銭での納入も広く行われていた 13 。これらに加えて、前述の懸銭や反銭、棟別銭といった附加税が課されていた 13 。
家臣団統制の面では、永禄2年(1559年)に作成された「小田原衆所領役帳」がその象徴である 11 。これは、家臣が保有する所領の規模に応じて、軍役や普請役などの負担を規定するための台帳であり、後北条氏による家臣団統制が高度な段階に達していたことを示している。この役帳の作成や検地の実施は、単に税収や軍事力を確保するだけでなく、主君と家臣の関係を明確にし、家臣団の勢力を適切に抑制するとともに、後北条氏自身が領内の農民を直接的に把握し、支配力を強化することを目的としていた 13 。
氏康の時代に確立されたこれらの税制や家臣団統制の仕組みが、氏直の時代にどのように運用され、あるいは変化したのかは重要な検討課題である。特に、前節で触れた「反銭増徴」が、既存の税制にどのような影響を与えたのか、詳細な分析が求められる。氏直の時代に行われた「反銭増徴」が、氏康によって確立された「三税」の枠組みを根本から変えるものであったのか、それとも既存の枠組みの中での税率変更に過ぎなかったのかは、史料からの判断が難しい部分もある。また、「小田原衆所領役帳」が氏直の時代にも引き続き更新され、活用されていたのか、もしそうであれば、豊臣氏との対決を目前に控えた時期の軍役強化にどのように利用されたのかも明らかにする必要がある。氏直の時代の財政政策、特に反銭増徴が、農民や国衆の負担増に繋がり、彼らの北条家に対する忠誠心に影響を与えた可能性も考慮すべきである。史料 13 には、農民が租税の減額を要求したり、要求が通らない場合には離村したりする事例や、後北条氏が税の滞納者に対して「妻子牛馬可取」(妻子や牛馬を没収する)といった極めて厳しい態度で臨んだことが記されており、氏直の代に増税が行われたとすれば、こうした領主と民衆の間の緊張関係が一層高まった可能性も否定できない。
第四章:豊臣政権との対立と小田原合戦
第一節:関東惣無事令と名胡桃城事件の勃発
中央で天下統一事業を推進する豊臣秀吉は、天正15年(1587年)頃から「関東惣無事令」(または「関東・奥両国惣無事令」)を発令し、関東および奥羽地方における大名間の私的な戦闘を禁じた 1 。これは、豊臣政権の権威のもとに全国の秩序を再編しようとするものであり、これに違反する行為は、豊臣政権への直接的な挑戦と見なされた。
北条氏直は、秀吉の強大な実力を認識しており、天正16年(1588年)には叔父である北条氏規を上洛させ、秀吉との交渉に臨ませている 1 。しかし、両者の関係は、天正17年(1589年)10月に発生した名胡桃城事件によって決定的に破綻する。この事件は、北条氏の家臣で沼田城代であった猪俣邦憲が、真田昌幸の領地であった上野国の名胡桃城を武力で奪取したというものであった 1 。これが惣無事令に違反する行為であるとして、秀吉は北条氏を厳しく糾弾した 1 。
氏直は、名胡桃城事件は北条本家の命令によるものではなく、既に城は真田方に返還したなどと弁明したが、秀吉はこれを受け入れなかった 1 。秀吉は、北条氏政の上洛がない場合には、北条氏討伐のために自ら関東へ出馬する意向を伝え、諸大名に対して北条討伐の準備を命じる陣触れを発した 16 。史料 16 によれば、名胡桃城占拠には北条側の言い分として、名胡桃城主が北条方に内通し救援を依頼してきたという事情があったとされつつも、惣無事令下での軍事行動そのものが問題視されたと指摘されている。また、この時期、秀吉と北条氏は互いに歩み寄りの姿勢を見せながらも、一方で軍備を増強するという、いわば「不思議な状態」にあったとも記されている。
名胡桃城事件は、単なる国境紛争に留まらず、豊臣政権が構築しようとしていた全国的な支配秩序(惣無事令)に対する北条氏の姿勢が問われた重大な局面であった。北条側の弁明と秀吉側の強硬な態度の背景には、両者の間に存在した中央政権に対する認識の齟齬や、秀吉の天下統一事業における北条氏の位置づけ、そして北条氏が関東における独自の勢力圏を維持しようとする意志があったと考えられる。この事件が猪俣邦憲の独断によるものであったのか、あるいは北条家中枢による黙認や指示があったのか、その真相は北条氏の危機管理能力や中央集権の度合いを測る上で重要な鍵となる。また、氏直や氏政が、豊臣秀吉の「惣無事令」の持つ真の意味と、それに違反した場合に何が起こりうるのかを、どこまで正確に理解していたのかも問われるべき点である。
第二節:小田原合戦の展開と氏直の役割
天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐が開始された 1 。秀吉が動員した軍勢の総数は、21万とも22万とも称される、未曾有の大軍であった 16 。対する北条軍は、領国内の兵力を総動員しても約5万6千であり 17 、その兵力差は歴然としていた。
氏直は、この事態を予期し、領国内に動員令を発するとともに、本拠地である小田原城をはじめとする各支城の修築を進め、臨戦態勢を整えていた 1 。しかし、豊臣軍の圧倒的な兵力の前に、戦況は北条方にとって極めて不利に進展する。同年3月29日には、箱根路の要衝であった山中城がわずか1日で落城し、4月1日には足柄城が無血開城するなど、関東各地の北条氏の支城が次々と豊臣軍の手に落ちていった 20 。
そして、4月3日、豊臣軍による小田原城の包囲戦が開始された 17 。秀吉は、小田原城を見下ろす笠懸山(石垣山)に一夜にして城を築いたと伝えられる「石垣山一夜城」を本陣とし、長期戦の構えを見せた 17 。氏直は、父である氏政と共に小田原城に籠城し、この未曾有の国難に対処することとなった 17 。
圧倒的な兵力差に加え、周到な兵站準備、水軍による海上封鎖、そして巧みな調略を伴う豊臣軍の前に、北条軍は苦戦を強いられた。氏直は当主として籠城戦を指揮する名目上の立場にはあったものの、実質的な戦略決定においては、依然として父・氏政の意向が強く働いていたと考えられている。各支城が予想以上に早く陥落したことは、小田原城籠城策の前提を大きく揺るがし、城内の士気や戦略に深刻な影響を与えたであろう。小田原合戦は、戦国時代の終焉を象徴する戦いの一つであり、この合戦における戦術、兵站、情報戦などは、その後の日本の軍事史に多くの教訓を残したと言える。
第三節:籠城策の評価と北条氏の降伏
小田原城における籠城は、約3ヶ月間に及んだ 1 。北条氏政は、かつて上杉謙信や武田信玄といった強敵の大軍を、小田原城での籠城戦によって退けた成功体験を有しており、今回も同様の戦略を選択したと考えられている 17 。しかし、史料 50 では、兵糧の準備が不十分な状況での籠城策を批判的に見ており、当時の北条氏が置かれた状況の厳しさをうかがわせる。
長期にわたる籠城の中で、城内では重臣であった松田憲秀の庶子・笠原政晴が豊臣方に内応しようとした事件も露見した 1 。さらに、史料 51 では、松田憲秀自身が秀吉と内通し、戦後の伊豆・相模両国の安堵を約束されていたが、実行直前に計画が発覚したという通説も紹介されている。これらの動きは、北条家臣団の結束が必ずしも盤石ではなかった可能性を示唆している。
追い詰められた北条方は、天正18年(1590年)7月1日、ついに豊臣方との和議を決断する。そして7月5日、氏直は豊臣方の武将である滝川雄利の陣所へ赴き、自らの切腹と引き換えに城兵将兵の助命を嘆願し、降伏した 1 。
秀吉は、氏直のこの潔い申し出に感銘を受け、また、氏直が徳川家康の婿であったという事情も考慮し、その助命を認めた。一方で、父である氏政、叔父の氏照、そして宿老の大道寺政繁、松田憲秀に対しては切腹が命じられた 1 。
小田原合戦における籠城策の是非については、歴史的評価が分かれるところである。過去の成功体験に固執した結果、時代の変化に対応できなかったという批判 17 がある一方で、圧倒的な兵力差を考慮すれば、他に有効な手段は限られており、籠城は次善の策であったという見方も存在する。史料 51 では、籠城策を継続したことにより、結果的に多くの死傷者を出す事態を避けられたのは、松田憲秀や北条氏規の功績であるとしつつも、松田憲秀が独断で豊臣方と戦後処理に関する駆け引きを行っていた点を失敗として指摘している。氏直が降伏の際に示した態度は、総大将としての責任感の表れとして、敵将である秀吉にも一定の評価を与えた 5 。過去の成功体験(上杉謙信や武田信玄との戦い)が、今回の豊臣秀吉との戦いにおける状況判断を誤らせた可能性は否定できない。秀吉軍の圧倒的な規模、高度な兵站能力、そして何よりも「天下統一」という明確かつ強固な意志の強さを見誤ったのではないかという指摘は、傾聴に値する。
第五章:小田原合戦後の北条氏直
第一節:高野山への追放と赦免への道
小田原城開城後、北条氏直の処遇は、天正18年(1590年)7月12日、紀伊国高野山への追放と決定された 1 。同月21日、氏直は太田氏房ら一門衆や側近を含む家臣約30名、総勢約300名と共に小田原を発ち、高野山へと向かった。この一行には、徳川家康の重臣である榊原康政が付き添った 1 。
同年8月12日、氏直一行は高野山高室院の「小田原坊」と呼ばれる宿坊に到着し、謹慎生活に入った。この時期、氏直は「見性斎」と号したと伝えられる 1 。その後、同年11月10日には、豊臣秀吉の配慮により、冬の高野山の厳しい寒さを避けるため、山麓の天野(現在の和歌山県伊都郡かつらぎ町天野)へ移った。秀吉は氏直らに対し、生活に必要な扶持米や衣服、酒茶などを届けさせたといい、また、高室院も北条家とは初代宗瑞以来の長い付き合いがあり、金銭的な援助も含め、親身になって氏直らの世話をしたと記録されている 21 。
この謹慎期間中、氏直の義父にあたる徳川家康が中心となって、秀吉に対し氏直の赦免を熱心に働きかけた 1 。氏直自身も、天正19年(1591年)1月から赦免に向けた活動を開始したとされる 1 。これらの働きかけが功を奏し、同年2月7日、ついに秀吉から氏直の赦免が許可された 1 。
高野山への追放は、かつて関東に覇を唱えた大名の当主であった氏直にとって、屈辱以外の何物でもなかったであろう。しかし、その一方で、秀吉による一定の配慮が見られる点は注目に値する。これは、氏直が家康の婿であるという立場が大きく影響した結果と考えられる 5 。家康が氏直の赦免に向けて積極的に動いた背景には、単なる旧知の間柄という個人的な感情に留まらない、何らかの政治的な計算があった可能性も否定できない。秀吉が氏直を助命し、さらに赦免へと進んだのは、家康への配慮のみならず、旧北条領の安定化や、氏直を将来的に何らかの形で政治的に利用する意図があった可能性も探る必要があるだろう。
第二節:豊臣大名としての復活と最期
天正19年(1591年)2月に豊臣秀吉から赦免の許可を得た北条氏直は、同年春には大坂泉南(現在の岸和田市)にあったとされる興応寺に移り、さらに5月には大坂の織田信勝(信長の弟・信包か)の旧屋敷跡へと居を移した 21 。同年5月12日付の書状からは「見性斎」を称するようになったことが確認できる 21 。
そして同年8月19日、氏直は秀吉に拝謁し、正式に赦免されるとともに、河内国および関東において1万石の知行を与えられ、豊臣政権下の一大名として復活を遂げた 1 。この際、翌年に予定されていた朝鮮出兵への参加も命じられている 21 。同年8月27日には、小田原から正室である督姫(徳川家康の娘)の一行が大坂に到着し、氏直と再会を果たした 21 。
しかし、大名としての再起も束の間、氏直は同年10月下旬頃から疱瘡(天然痘)を患い、11月4日、わずか30歳という若さでその生涯を閉じた 1 。
氏直の死後、後北条家の家名は、叔父である北条氏規の子・氏盛が継承し、河内国狭山において1万石余の領地を与えられ、狭山藩として幕末まで存続することとなった 5 。
1万石という規模ではあったものの、大名としての復活は、氏直本人及びその義父である徳川家康にとって、一定の成果であったと言えるだろう。しかし、その直後の病死は、あまりにも早すぎる悲劇的な結末であった。朝鮮出兵への参加命令は、豊臣政権下における大名としての義務であり、氏直もその例外ではなかったことを示している。氏直に与えられた1万石の具体的な領地がどこであったのか、そしてその統治の実態がどのようなものであったのかについては、史料が乏しく詳細は不明な点が多い。もし氏直が長生きし、その後の徳川家康による天下取りの時代を迎えていたならば、彼がどのような役割を果たした可能性があるのか、歴史の「もしも」を考えさせる。氏直の早世は、旧北条家臣団の再結集への望みを事実上断ち切る結果となり、彼らが徳川家をはじめとする他の大名家に仕官する流れを加速させた一因となったのではないだろうか。
第六章:北条氏直の人物像と歴史的評価
第一節:史料に見る人物像と性格
北条氏直の人物像や性格を伝える史料や記述は断片的ではあるものの、いくつかの側面をうかがい知ることができる。例えば、ウェブサイト「serai.jp」の記事では、氏直を「関東の有力大名・北条氏の最後の当主」であり、「小田原合戦の際には父・氏政に異を唱えて、義父の家康と通じて北条家存続の道を探る人物」として紹介している 2 。また、小田原市観光協会が作成した「小説 北条五代」のキャラクター紹介においては、氏直を「人に好かれる性格。自己犠牲の精神が高い。武よりも学問を好んだ」と描写し、その所持品として「北条五代記、早雲寺のお守り」を挙げている 24 。
これらの記述は、氏直が温厚で理知的、そして自己犠牲的な精神の持ち主であった可能性を示唆している。実際に、小田原合戦で降伏する際、自らの切腹と引き換えに城兵将兵の助命を嘆願した行動は、敵将である豊臣秀吉にも感銘を与えたとされている 1 。また、赦免後に秀吉に拝謁し、朝鮮出兵を命じられた際には、高野山高室院へ持仏である五躰尊の無事を祈念するよう依頼するなど、信仰心の一端も垣間見える 21 。
しかし、これらの評価や描写は、氏直の一側面を捉えたものに過ぎない可能性も考慮しなければならない。特に、父である氏政との複雑な権力関係や、豊臣秀吉という強大な統一権力者との対峙の中で見せた苦悩や下した決断から、より多角的かつ深層的な人物像を掘り下げる必要がある。「武よりも学問を好んだ」という評価が、戦国乱世の終焉期における当主として、具体的にどのように作用したのか、肯定的な面と否定的な面の両方から検討する必要があろう。氏直の「人に好かれる性格」や「自己犠牲の精神」は、徳川家康や豊臣秀吉といった当代の実力者たちに一定の好印象を与え、結果として自身の助命や赦免に繋がった可能性がある。しかし、それは同時に、戦国武将に求められる非情な決断力や、権謀術数を駆使する政治的駆け引きにおいては、むしろ弱点として作用した可能性も否定できない。
第二節:統治者としての能力と限界
北条氏直が後北条家の家督を相続した際、内政や家臣団の統制に関する権限は直ちに移譲されたものの、外交と軍事の主要部分は依然として父・氏政が掌握するという二頭体制であった 1 。この特殊な権力構造は、氏直の統治者としての能力発揮に少なからぬ影響を与えたと考えられる。
彼の治世における重要な政策の一つとして、伝統であった当主代替わり時の検地を行わず、代わりに反銭を増徴するという措置を取った点が挙げられる 12 。この判断の背景には、目前に迫る豊臣秀吉との対決に備えるための財政的逼迫があったと推測されるが、領国支配の根幹に関わる検地を行わなかったことの是非は問われるべきであろう。
豊臣秀吉との外交交渉においては、叔父である北条氏規を上洛させて交渉に当たらせたものの、名胡桃城事件の発生により両者の関係は破綻に至った。氏直自身は事件への直接的な関与を否定し弁明したが、秀吉の強硬な姿勢を変えることはできなかった 1 。
歴史家の加来耕三氏は、その著作「武将の失敗学 凡庸二代で亡国となる北条氏政-氏直」の中で、氏政と氏直の二代にわたる凡庸さが北条家の滅亡に繋がったと厳しく評価している 25 。特に史料 52 では、父・氏政が「凡庸の自覚なさゆえに、亡国を招いた」と指摘されており、氏直もまた、この評価から免れることは難しい状況にあった。
氏直の統治者としての評価は、父・氏政との権力分担という特殊な状況を考慮しつつ行う必要がある。豊臣政権という、それまでの日本の歴史上類を見ない強大な統一権力への対応は、氏直にとって最大の試練であった。そして、その結果として後北条氏を滅亡に至らしめたという点で、彼の統治能力には限界があったと評価されることが多い。加来耕三氏による「凡庸」という評価は厳しいものではあるが、その具体的な論拠を史実に基づいて検証することが求められる。例えば、豊臣秀吉の真意や関東惣無事令の持つ意味を正確に読み取ることができなかった外交感覚の欠如、あるいは広大な領国と多数の家臣団を完全に掌握しきれなかった統率力の問題などが指摘できるかもしれない。史料 50 に見られる「政治の中枢である畿内にいないため情報が不足している、所詮は東国の田舎侍に過ぎない」という籠城策批判の文脈は、中央政権との情報格差や国際情勢に対する認識の甘さを示唆しているとも解釈できる。
以下に、北条氏直の主要な政策・判断とそれに対する評価をまとめた表を示す。
表3:北条氏直の主要政策・判断とそれに対する評価
|
主要な出来事・政策 |
概要 |
氏直の判断・役割 |
肯定的評価の可能性 |
否定的評価(「凡庸」と評される点など) |
関連史料例 |
|
家督相続時の体制 |
天正8年(1580年)家督相続。父氏政との二頭政治体制。 |
内政・家臣統制は担当するも、外交・軍事の主要部分は氏政が掌握。 |
安定的な権力移譲、経験豊富な父の補佐。 |
指導権の不明確さ、主体性の発揮の困難さ、意思決定の遅延。 |
1 |
|
代替わり検地不実施と反銭増徴 |
伝統的な代替わり検地を行わず、反銭を増徴。 |
財政難への対応、軍備増強優先の可能性。 |
緊急時の現実的対応。 |
領国把握の不徹底、民衆・家臣の負担増、支配基盤の動揺。 |
12 |
|
対豊臣外交(氏規派遣、名胡桃城事件対応) |
叔父氏規を上洛させ交渉。名胡桃城事件発生後、弁明。 |
交渉は氏規に委任。事件への直接関与は否定。 |
和平努力、豊臣政権への一定の配慮。 |
秀吉の意図の誤認、事件処理の不手際、危機管理能力の欠如。 |
1 |
|
小田原合戦(籠城策、降伏) |
豊臣軍の圧倒的兵力に対し小田原城に籠城。最終的に降伏。 |
籠城戦を指揮(氏政と共に)。自らの切腹と引き換えに将兵の助命を嘆願。 |
兵士の犠牲を最小限に抑えようとした責任感(降伏時)。 |
過去の成功体験への固執、戦略の柔軟性の欠如、情報収集・分析能力の不足。 |
1 |
この表は、氏直の統治者としての行動と判断を具体的に整理し、それに対する多角的な評価を提示することで、読者が氏直の功罪を客観的に考察する材料を提供する。
第三節:後世の作品における描かれ方と現代的視点からの再評価
北条氏直は、後世の歴史小説や映像作品において、しばしば悲劇の当主、あるいは父祖の偉業と時代の大きな流れの狭間で翻弄された人物として描かれる傾向がある。例えば、火坂雅志氏と伊東潤氏の共著による長編歴史小説『北条五代』では、その下巻において氏政・氏直父子の苦悩と決断が中心的に描かれている 26 。小田原市観光協会の同小説キャラクター紹介では、氏直は「人に好かれる性格。自己犠牲の精神が高い。武よりも学問を好んだ」とされ、穏やかで知的な側面が強調されている 24 。また、2023年に放送されたNHK大河ドラマ『どうする家康』においては、氏直は父・氏政の強硬路線に異を唱え、義父である徳川家康と通じることで北条家の存続の道を探ろうとする人物として描かれた(演:西山潤) 2 。
これらの描写は、氏直の人間的な側面や、彼が置かれた困難な状況への同情を誘う一方で、戦国末期の当主としての主体的な判断や政治的力量については、やや曖昧な印象を与えることも少なくない。しかし、近年の歴史研究の進展や、大河ドラマのような大衆文化における新たな解釈は、従来の氏直像に多様な光を当て、その再評価を促しつつある。
後北条氏全体の統治については、約100年間にわたり関東地方を安定的に治め、その間、大規模な民衆一揆も起こらなかったことなどから、「北条マジック」とも称される肯定的な評価も存在する 30 。このような長期安定政権の最後の当主であった氏直が、その滅亡の責任を一身に負うべきなのか、あるいは時代の不可抗力の中で最善を尽くそうとしたのか、現代的な視点からの再検討が求められる。氏直を単に「悲劇の当主」としてのみ捉えることは、彼が下した主体的な判断や、困難な状況の中で見せたかもしれない指導力を見過ごす危険性を孕んでいる。現代の危機管理やリーダーシップ論といった観点から、氏直の行動や意思決定プロセスを再評価することも、新たな氏直像を構築する上で有益であろう。北条氏滅亡という結果から逆算して、氏直の行動全てが否定的に評価される傾向を排し、彼が置かれた状況の極度の困難さや、彼なりに最善を尽くそうとした側面(例えば、徳川家康との連携模索を、単なる延命策ではなく、何らかの形で北条家そのものを残そうとする現実的な努力であったと評価するなど)も公平に考慮に入れる必要がある。
結論
北条氏直の生涯の総括と、後北条氏滅亡における歴史的意義
北条氏直は、戦国大名後北条氏の第五代、そして最後の当主として、父祖が約一世紀にわたり築き上げてきた関東における広大な領国と強固な支配体制を継承した。しかし、彼の治世は、豊臣秀吉による天下統一という、日本の歴史における未曾有の大きな変革の波と真正面から対峙する時代であった。結果として、氏直はその強大な勢力を維持することができず、後北条氏は滅亡の道を辿ることとなる。
氏直の生涯を振り返ると、父・氏政との二頭体制という特殊な権力構造の下で、必ずしも自身の意のままに采配を振るえなかった側面がうかがえる。伝統であった当主代替わり時の検地を行わず、反銭増徴という異例の措置で対応したことは、当時の北条氏が直面していた財政的・軍事的逼迫を物語っている。また、豊臣政権との外交交渉においては、名胡桃城事件への対応の遅れや認識の甘さが致命的な結果を招き、最終的には小田原合戦における籠城策も、圧倒的な兵力と周到な戦略を持つ豊臣軍の前に限界を露呈した。これらの点は、氏直の治世における課題と困難を象徴していると言えよう。
一方で、小田原城開城に際して見せた、自らの命と引き換えに将兵の助命を嘆願する潔い態度は、敵将である秀吉にも感銘を与えたとされ、彼の人間性の一端を示している。また、高野山への追放後も、義父である徳川家康の尽力や自らの働きかけにより赦免を勝ち取り、短い期間ではあったものの、豊臣政権下の一大名として再起を果たした事実は、単に「凡庸な当主」という一面的な評価では捉えきれない、氏直の複雑な人物像を示唆している。
後北条氏の滅亡は、単に一つの戦国大名家が終焉を迎えたというに留まらず、関東地方における戦国時代の終焉を決定づけるとともに、豊臣秀吉による全国統一事業の完成を国内外に強く印象づける画期的な出来事であった。北条氏直の生涯と、彼が率いた後北条氏の終焉は、群雄割拠の戦国乱世から、中央集権的な近世へと移行する時代の大きな転換点において、旧来の地域権力が直面した苦悩と、その避け難い末路を如実に示している。氏直の研究は、この歴史的転換期を理解する上で、依然として多くの示唆を与えてくれると言えるであろう。
主要参考文献一覧
- 浅倉直美「神流川の戦いと戦後の神流川流域」(黒田基樹編『シリーズ・中世関東武士の研究 第29巻 北条氏直』戎光祥出版、2020年) 31
- 浅倉直美「後北条氏の上野制覇」(黒田基樹編『シリーズ・中世関東武士の研究 第29巻 北条氏直』戎光祥出版、2020年) 31
- 池上裕子「武田氏滅亡から『足柄当番之事』へ」(黒田基樹編『シリーズ・中世関東武士の研究 第29巻 北条氏直』戎光祥出版、2020年) 31
- 和泉清司「戦国大名後北条氏における知行制――買得地を中心として」(黒田基樹編『シリーズ・中世関東武士の研究 第29巻 北条氏直』戎光祥出版、2020年) 31
- 戎光祥出版ウェブサイト「シリーズ・中世関東武士の研究 第29巻 北条氏直」 31
- 神奈川県立歴史博物館ウェブサイト「北条氏直書状(長尾顕長宛)」 38
- 加来耕三「武将の失敗学 凡庸二代で亡国となる北条氏政-氏直」『商工ジャーナル』34巻11号(2008年11月) 25
- 黒田基樹「北条氏直の研究」(黒田基樹編『シリーズ・中世関東武士の研究 第29巻 北条氏直』戎光祥出版、2020年) 31
- 黒田基樹「北条氏直論」(関連論文・著作を参照) 39
- 座間美都治「北条氏直と高室院文書」(黒田基樹編『シリーズ・中世関東武士の研究 第29巻 北条氏直』戎光祥出版、2020年) 31
- 長塚孝「『小田原一手役之書立』考」(黒田基樹編『シリーズ・中世関東武士の研究 第29巻 北条氏直』戎光祥出版、2020年) 31
- 峰岸純夫「『地衆』――後北条氏による百姓の軍事編成」(黒田基樹編『シリーズ・中世関東武士の研究 第29巻 北条氏直』戎光祥出版、2020年) 31
- その他、本文中に引用した各史料・研究( 1 など)
巻末付録
表4:北条氏直関連年表
|
年代(和暦) |
年代(西暦) |
北条氏直の動向 |
国内外の主要な出来事 |
|
永禄5年 |
1562年 |
小田原城にて誕生(国王丸) 1 。 |
武田信玄と上杉謙信、川中島の戦い(第四次) |
|
永禄11年 |
1568年 |
(母・黄梅院の離縁説、武田氏駿河侵攻) 1 |
織田信長、足利義昭を奉じ上洛 |
|
永禄12年 |
1569年 |
今川氏真の猶子となり家督相続(名目上) 1 。(母・黄梅院死去説) 1 |
|
|
元亀3年 |
1572年 |
この頃までに今川氏との縁組解消か 1 。 |
武田信玄、西上作戦開始(三方ヶ原の戦い) |
|
天正5年 |
1577年 |
3月までに元服、「新九郎」を名乗る 1 。11月、上総にて初陣、里見氏と和睦(房相一和) 1 。 |
手取川の戦い |
|
天正8年 |
1580年 |
8月19日、父・氏政の隠居により家督相続 1 。 |
石山本願寺、信長に降伏 |
|
天正9年 |
1581年 |
叔父・武田勝頼と三島で対陣 1 。 |
|
|
天正10年 |
1582年 |
3月、武田氏滅亡。6月、本能寺の変。上野侵攻開始、神流川の戦いで滝川一益に勝利。信濃佐久・小県郡を支配下に。甲斐若神子城で徳川家康と対陣(天正壬午の乱)。10月、家康と和睦、督姫との婚姻決定 1 。 |
本能寺の変、山崎の戦い、清洲会議 |
|
天正12年 |
1584年 |
沼尻の合戦で佐竹・宇都宮連合軍と対峙、引き分け後、北条優位に戦後処理 6 。この頃から氏直が「左京大夫」を名乗る 1 。 |
小牧・長久手の戦い |
|
天正14年 |
1586年 |
佐野氏へ氏忠養子入り。皆川広照・壬生義雄ら降伏、下野西半を勢力下に 6 。 |
豊臣秀吉、太政大臣に任官 |
|
天正15年 |
1587年 |
(豊臣秀吉、関東惣無事令発令) 16 |
九州平定、バテレン追放令 |
|
天正16年 |
1588年 |
叔父・氏規を上洛させ秀吉と交渉 1 。 |
聚楽第行幸、刀狩令 |
|
天正17年 |
1589年 |
10月、名胡桃城事件発生 18 。 |
|
|
天正18年 |
1590年 |
3月~7月、小田原合戦。7月5日、降伏。氏政・氏照ら切腹。氏直は高野山へ追放決定 1 。8月、高野山高室院に入る 21 。11月、天野へ移る 21 。 |
豊臣秀吉、天下統一をほぼ達成 |
|
天正19年 |
1591年 |
2月、秀吉より赦免許可 1 。春、大坂へ。8月、秀吉に拝謁、1万石で大名復帰、朝鮮出兵を命じられる。督姫と再会 5 。10月下旬より疱瘡を患う。11月4日、大坂にて死去、享年30 1 。 |
千利休切腹、九戸政実の乱 |
引用文献
- 北条氏直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E7%9B%B4
- 北条氏政の長男・北条氏直が辿った生涯|義父・家康と通じて北条家存続の道を探る五代目当主【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1142312
- 北条氏直は武田信玄の孫ではなかった! http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-109389.html
- 北条氏政を苦しめた組織の「官僚化」 | 歴史人 https://www.rekishijin.com/23322
- 後北条家存続のため家康を頼った!家康の婿・北条氏直が歩んだ30 ... https://mag.japaaan.com/archives/206381/3
- 沼尻の合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BC%E5%B0%BB%E3%81%AE%E5%90%88%E6%88%A6
- 壬生義雄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AC%E7%94%9F%E7%BE%A9%E9%9B%84
- 壬生町-地域史料デジタルアーカイブ:壬生の歴史 https://adeac.jp/mibu-town/texthtml/d100080/mp020010-100020/ht000380
- 皆川広照 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%86%E5%B7%9D%E5%BA%83%E7%85%A7
- 皆川城々門 https://www.asahi-net.or.jp/~cn3h-kkc/shiro/minagawa.htm
- 氏康の領国経営 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/007/
- 【北条氏の検地】 - ADEAC https://adeac.jp/lib-city-tama/text-list/d100010/ht051060
- 後北条氏の農村支配について : 貢租制度を 中心として https://hosei.ecats-library.jp/da/repository/00011820/shigaku_13_moriya.pdf
- omu.repo.nii.ac.jp https://omu.repo.nii.ac.jp/record/12890/files/2023000041.pdf
- 北条氏康とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E5%BA%B7
- 【3万5千 VS 22万】小田原征伐|北条家が圧倒的不利な状況でも ... https://sengokubanashi.net/history/odawara-seibatsu/
- 小田原合戦 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/011/
- 小田原征伐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%BE%81%E4%BC%90
- 小田原征伐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%BE%81%E4%BC%90#%E5%90%8D%E8%83%A1%E6%A1%83%E5%9F%8E%E4%BA%8B%E4%BB%B6
- 小田原合戦 北条氏5代100年の最後 - 城びと https://shirobito.jp/article/376
- 北条氏直~高野山から大阪出仕まで http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2020/07/post-1e5421.html
- [座談会]小田原合戦 −北条氏と豊臣秀吉− /永原慶二・岩崎宗純・山口 博・篠﨑孝子|Web版 有鄰 420号 - 有隣堂 https://www.yurindo.co.jp/yurin/article/420
- 北条氏政とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E6%94%BF
- 北条五代PRキャラクター - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/hojo/ki-20150144.html
- 武将の失敗学 凡庸二代で亡国となる北条氏政-氏直 | CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1522543655544356736
- 小田原北条家の関連書籍紹介|北条左京大夫氏直 - note https://note.com/shinkuroujinao/n/n470d85dc9003
- 北条五代 (上) | 火坂雅志 伊東潤 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E4%BA%94%E4%BB%A3-%E4%B8%8A-%E7%81%AB%E5%9D%82%E9%9B%85%E5%BF%97/dp/4022517379
- 『北条五代 (上)』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/17060799
- 北条五代 上巻 | 伊東潤公式サイト https://itojun.corkagency.com/works/houjou1/
- 百年の - 小田原市観光協会 https://www.odawara-kankou.com/work/odawara_hojo100.pdf
- シリーズ・中世関東武士の研究 第 29巻 北条氏直 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/550/
- 第18回情報科学技術フォーラム - IEICE https://www.ieice.org/publications/conference-FIT-DVDs/FIT2019/data/pdf/program.pdf
- 6ページ目:【5/21更新】カラオケDAM最新アニメ映像&楽曲配信情報まとめ【毎週更新】 https://www.animatetimes.com/news/details.php?id=1747710821&p=6
- 兵庫県立美術館 年報 https://www.artm.pref.hyogo.jp/artcenter/pdf/nenpou_2022.pdf
- 「郷土神奈川」総目次 創刊号〜第50号 - 神奈川県立の図書館 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2021/01/kyoudo_kanagawa_soumokuji.pdf
- 2023年度特別陳列 【戦国大名北条氏と西相模・伊豆】 関連文献リスト - 神奈川県立歴史博物館 https://ch.kanagawa-museum.jp/uploads/library-R5_houjou-list20240330.pdf
- 戦国時代における幕府安堵制の展開と機能 - 機関リポジトリ HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/81128/hogaku0220302770.pdf
- 北条氏直書状 - 神奈川県立歴史博物館 https://ch.kanagawa-museum.jp/dm/gohojyo/collection/d_collection_08.html
- 中世後期における下総千葉氏関係文書について(後) https://www.city.chiba.jp/chiba-shi/research/shiryo/documents/shiryomokuroku_02.pdf
- 総論 北条氏政の研究 https://www.ebisukosyo.co.jp/docs/pdf/%E8%A9%A6%E3%81%97%E8%AA%AD%E3%81%BF/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F%E6%94%BF.pdf
- 大河ドラマ「真田丸」ワンポイント解説(21)|学部・研究科レポート - 駿河台大学 https://www.surugadai.ac.jp/gakubu_in/hogaku/news/2016/21-1.html
- 郷土士の歴史探究記事 その28 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2018/12/post-fe54.html
- 18H00714 研究成果報告書 - KAKEN https://kaken.nii.ac.jp/file/KAKENHI-PROJECT-18H00714/18H00714seika.pdf
- 印判状に見られる日付上押印について https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/2751/files/kenkyuhokoku_224_07.pdf
- 郷土士の歴史探究記事 その68 http://kyoudosi.cocolog-nifty.com/blog/2021/10/post-0c6818.html
- 橋本郷土研究会資料 復刻版 - さがみはらの公民館 https://www.sagamihara-kouminkan.jp/hashimoto-k/kyoudop-hukkokuban.pdf
- 私は「富士山登山鉄道構想」に反対です - 屋根のない博物館のホームページ http://yanenonaihakubutukan.net/bakanakon.html
- 戦国時代|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1930
- 深大寺城に関する一考察 - 東京 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/928/attach_96441_2.pdf
- 「どうする家康」第33回「裏切り者」 徳川家中の愚かさが数正を裏切り者にしていくまで - note https://note.com/tender_bee49/n/na0c0181f9dfb
- 松田憲秀の内応説 2019 年 7 月 4 日 https://matsudake1188.jp/matsudake-norihide.pdf
- 戦国武将と戦国姫の失敗学 歴史の失敗学3――乱世での生き抜く術 ... https://www.amazon.co.jp/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%81%A8%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A7%AB%E3%81%AE%E5%A4%B1%E6%95%97%E5%AD%A6-%E4%B9%B1%E4%B8%96%E3%81%A7%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%8A%9C%E3%81%8F%E8%A1%93%E3%81%A8%E4%BB%95%E8%88%9E%E3%81%84%E6%96%B9-%E5%8A%A0%E6%9D%A5-%E8%80%95%E4%B8%89/dp/4296201859
- 「北条氏綱像」は後世に改変されたのか? http://maricopolo.cocolog-nifty.com/blog/2020/03/post-2a0cb8.html
- 北条氏直の家臣団 - note https://note.com/shinkuroujinao/n/n8573c7f97c46
- kokubunken.repo.nii.ac.jp https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/1474/files/KA1067.pdf
- 戦国大名北条氏文書の研究 http://www.iwata-shoin.co.jp/shohyo/sho1013.htm