大久保長安
大久保長安は猿楽師の子から家康側近となり、鉱山経営・検地・街道整備で初期幕府財政に貢献。「天下の総代官」と称されたが、死後不正蓄財・陰謀嫌疑で一族処刑。
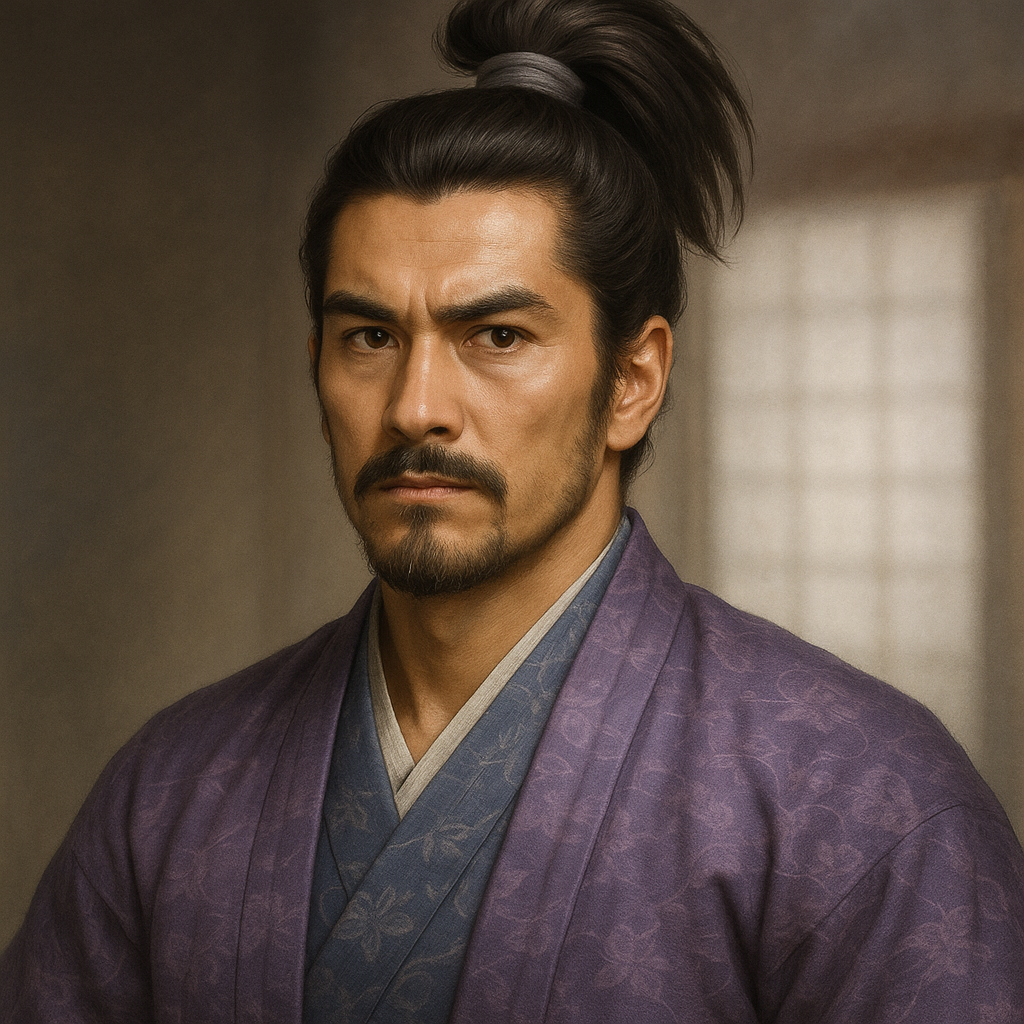
大久保長安の実像:初期江戸幕府を支えた異能の技術官僚とその時代
序章:大久保長安という人物
本報告は、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて、徳川家康のもとで絶大な権勢を誇った人物、大久保長安(1545-1613)の生涯と業績、そして彼を襲った「大久保長安事件」の真相、さらには後世における歴史的評価の変遷を、現存する諸資料に基づき徹底的に調査・分析し、その実像に迫ることを目的とする。
大久保長安は、猿楽師の子という異色の出自から身を起こし、武田信玄に見出された後、その滅亡後は徳川家康に仕えた。鉱山経営、検地、街道整備、都市開発など多岐にわたる分野で卓越した手腕を発揮し、初期江戸幕府の財政基盤確立と中央集権体制の構築に大きく貢献したことは疑いようがない 1 。その功績は、彼を「天下の総代官」と称されるほどの地位に押し上げた。
しかし、栄華を極めた長安の生涯は、その死後に暗転する。生前の不正蓄財や幕府転覆の陰謀などが疑われ、長安の一族は処刑、財産は没収されるという悲劇的な末路を辿ったのである 2 。長安の生涯は、個人の才能が身分を超えて評価される戦国乱世の気風と、確立期にあった徳川政権が内包する権力闘争の厳しさ、そして政権安定への強い意志を映し出していると言えよう。彼の異例な出世と悲劇的な失脚は、単なる個人の物語に留まらず、徳川政権初期の権力構造、経済政策、そして人物登用のあり方について、多くの示唆を与えてくれる。
第一部:大久保長安の生涯と業績
第一章:出自と武田家臣時代
猿楽師の子から武田氏家臣へ
大久保長安は天文14年(1545年)、甲斐国に生まれた 2 。父は猿楽師の大蔵大夫金春七郎喜然(あるいは信安とも)とされ、長安はその次男であった 2 。幼名を藤十郎、後に十兵衛と称した 2 。父・信安は春日大社の能楽師の流れを汲み、大和国から播磨国を経て甲斐へ移り住み、武田信玄お抱えの猿楽師となったと伝えられている 9 。
このような出自にもかかわらず、長安は信玄にその才能を見出され、猿楽の道ではなく武士として取り立てられた。一説には、武田氏の譜代家老であった土屋昌続の与力に任じられたとも 9 、あるいは蔵前衆(代官)として武田領内の財政や農村支配、さらには黒川金山などの鉱山開発といった実務に従事したとも言われている 2 。この際、信玄より土屋姓を授かったとする記述も存在する 2 。武田信玄が猿楽師の子である長安を、その出自に関わらず能力本位で登用し、財政や鉱山開発といった専門分野で活躍させたことは、信玄の先進的な人材活用術を示すと同時に、長安が早期から実務能力を磨く機会を得たことを意味する。武田氏の領国経営、特に金山開発に関する知識や経験(いわゆる甲州流)は、長安にとって極めて重要な財産となり、これが後の徳川政権下での目覚ましい活躍の素地を形成したと考えられる。武田信玄没後は、その子である武田勝頼に仕えた 9 。
第二章:徳川家康への登用と初期の活躍
登用の経緯と大久保姓の拝受
天正10年(1582年)、織田信長・徳川家康連合軍による甲州征伐によって武田氏が滅亡すると、長安は新たな主君として徳川家康に仕えることとなる 2 。一説には、武田勝頼に疎まれたため、武田氏滅亡以前に自ら武田氏を離れ、猿楽師として三河国に移り住んでいたとも伝えられている 9 。
当時、家康は武田氏の旧臣を積極的に登用しており 3 、長安もその一人であった。家康の重臣である大久保忠隣の推挙、あるいは庇護を受けたことが契機となり、家康から大久保の姓を賜り、大久保十兵衛長安と名乗るようになったとされる 2 。当初は猿楽師として家康に仕えたという説もあるが 2 、武田氏滅亡後の混乱した甲斐国の内政再建に、本多正信や伊奈忠次の下で実質的に関与したともされている 9 。
関東代官頭としての基盤構築
天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐後、家康が関東へ移封されると、長安の人生は大きな転機を迎える。家康は長安を代官頭に抜擢し、関東経営の枢要を担わせたのである 2 。長安は武蔵国八王子(現在の東京都八王子市横山町、小門町産千代稲荷神社付近)に陣屋を構え、関東十八代官や八王子千人同心を統括した 2 。八王子は甲州方面からの江戸防衛の要衝であり、軍事的・経済的にも極めて重要な拠点であった。長安はこの地で、甲州街道の整備、浅川の治水工事、八王子宿の建設と発展に辣腕を振るい、家康の関東支配体制の確立に不可欠な役割を果たした。家康が長安をこのような重要拠点と広範な権限を要する地位に任命したことは、武田氏旧領の統治経験や、鉱山開発・財政に関する専門知識を高く評価していたことの証左と言えよう。
また、この時期、長安は伊奈忠次と共に各地で検地を実施し、「大久保縄」と呼ばれる独自の検地手法を確立したことも特筆される 2 。これらの検地、街道整備、治水といった事業は、領国経営の根幹であり、長安の行政手腕が遺憾なく発揮された分野であった。これは、武田氏の下で培われた経験が、新たな主君の下で大きく花開いた結果と言えるだろう。
表1:大久保長安 主要年表
|
年代 |
出来事 |
典拠 (例) |
|
天文14年(1545年) |
甲斐国に生まれる |
2 |
|
(詳細時期不明) |
武田信玄・勝頼に仕える |
2 |
|
天正10年(1582年) |
武田氏滅亡後、徳川家康に仕える。大久保姓を賜る |
2 |
|
天正18年(1590年) |
関東代官頭に任命され、八王子に陣屋を置く |
2 |
|
慶長5年(1600年) |
関ヶ原の戦い。戦後、佐渡金山奉行、石見銀山奉行などを歴任 |
9 |
|
慶長6年(1601年) |
甲斐奉行、石見奉行、美濃代官などに任命。東海道・中山道の伝馬制を定める |
2 |
|
慶長8年(1603年) |
石見守に叙任 |
2 |
|
慶長9年(1604年) |
東海・東山・北陸3道の一里塚建設を指揮 |
2 |
|
慶長18年(1613年)4月25日 |
駿府にて死去(享年69) |
2 |
|
慶長18年(1613年)5月以降 |
不正が発覚し、財産没収、遺子7人切腹(大久保長安事件) |
6 |
第三章:鉱山経営と幕府財政への貢献
主要鉱山(石見、佐渡、伊豆等)の開発と運営
関ヶ原の戦いに勝利し、天下の実権を掌握した徳川家康にとって、喫緊の課題は新たな政権の財政基盤を確立することであった。この国家的な事業において、大久保長安は中心的な役割を果たすことになる。関ヶ原の戦後、豊臣氏の支配下にあった佐渡金山(新潟県)や生野銀山(兵庫県)などが徳川氏の直轄領となると、長安はこれらの接収と経営を次々と任された 9 。
慶長6年(1601年)以降、長安は石見銀山奉行(島根県)、佐渡金山奉行、伊豆金山奉行(静岡県)などを歴任し、文字通り全国の主要な金銀山を管轄するに至る 2 。特に石見銀山と佐渡金山は、後に世界遺産にも登録されるほどの重要な鉱山であり、これらの開発・運営における長安の手腕の高さがうかがえる 5 。石見銀山においては、「大久保間歩」と呼ばれる最大級の坑道跡が現在も残されており、これは長安の指揮下で極めて大規模な開発が行われたことを物語る貴重な証左である 14 。
新技術(甲州流採鉱法、アマルガム法)の導入とその効果
長安の鉱山経営における最大の功績の一つは、先進的な技術を積極的に導入し、金銀の生産性を飛躍的に向上させたことである。彼は、武田氏時代に培われた「甲州流採鉱法」と呼ばれる、横方向に坑道を掘り進めて鉱脈を効率的に探査・採掘する技術を各地の鉱山に導入した 3 。
さらに、当時の最先端技術であった西洋の製錬技術の導入にも積極的であった。特に石見銀山では、ポルトガルから伝わったとされる水銀アマルガム法(水銀を用いて鉱石から効率的に銀を抽出する方法、「水銀流し」とも呼ばれた)を導入し、莫大な量の銀を生産したと記録されている 11 。佐渡金山においても、アマルガム法の導入を試みた形跡が確認されている 18 。
これらの新技術の導入は、日本の鉱業史における重要な転換点であったと言える。従来の手法に比べて格段に効率的な採掘・製錬が可能となり、金銀の産出量は飛躍的に増大した 3 。この技術革新による資源開発の成功は、単に一地方の鉱山の生産性を高めたというに留まらず、国家財政そのものに巨大なインパクトを与えたのである。
金銀増産と初期幕府財政の確立
大久保長安が開発・運営を指揮した金銀山からの莫大な産出は、徳川家康に巨万の富をもたらし、江戸幕府草創期の財政を文字通り支える大黒柱となった 1 。成立間もない徳川幕府は、大坂の陣をはじめとする大規模な軍事行動や、全国支配体制の構築に必要な莫大な経費を要したが、これらの財源の多くは、長安が管轄する鉱山からの収益によって賄われたと考えられる。
家康は早くから貨幣鋳造権の重要性を深く認識しており、関ヶ原の合戦の翌年である慶長6年(1601年)には、金貨(慶長小判など)及び銀貨(慶長丁銀など)の鋳造を開始している 3 。この貨幣鋳造事業においても、長安が管轄する甲州金座などが重要な役割を担った 2 。駿府城の天守を造営する際には、長安が黄金30万枚という巨額の資金を献上したという逸話も伝わっており 19 、これは彼の財政における影響力の大きさと、家康からの信頼の厚さを物語っている。長安の役割は、単なる鉱山経営の責任者という範疇を超え、国家の経済戦略を担う財政家としての側面を強く帯びていたのである。
第四章:「天下の総代官」としての多岐にわたる活動
大久保長安の活躍は鉱山経営に留まらず、その卓越した行政手腕は多方面に及んだ。彼は「天下の総代官」と称されるほど広範な権限を有し、幕府の基盤固めに不可欠な諸政策を次々と実行していった 4 。
検地の実施(石見検地、大久保縄)と年貢増収への影響
長安は、伊奈忠次と並び、徳川氏の支配領域において大規模な検地を実施した。彼が行った検地は、その厳格さと統一性から「石見検地」あるいは「大久保縄」と呼ばれ、後の幕府検地の模範の一つとされた 2 。具体的には、1反を300歩と定め、検地に使用する竿の長さを従来の6尺5寸から6尺1分に短縮するなどの手法を用いた。これにより、年貢徴収の基準となる石高の打ち出しが実質的に増加し、幕府の歳入増に大きく貢献した。
美濃国(現在の岐阜県南部)では、関ヶ原の戦後、国内の検地総奉行に任じられ、現地の諸大名を動員して大規模な検地を断行した。この検地は慶長14年(1609年)から慶長15年(1610年)にかけて行われ、「石見検地」の名で知られ、例えば苗木領(現在の岐阜県中津川市など)の貢租にも大きな影響を与えたと記録されている 20 。
長安による検地は、単に税収を増やすという財政的な側面に留まらず、全国の土地と生産力を幕府が直接的かつ統一的に把握し、支配体制を強化するという中央集権化政策の重要な一環であった。統一された基準による検地の実施は、それまで地域ごとに存在した曖昧さを排除し、幕府の財政基盤をより確固たるものにするとともに、幕府の権威を全国に示す効果も持っていた。
交通網の整備(一里塚、街道、宿場伝馬制度)と中央集権化への寄与
広大な領国を効率的に統治するためには、迅速な情報伝達と円滑な物資輸送が不可欠である。大久保長安は、この点においても先駆的な役割を果たした。慶長6年(1601年)、長安は彦坂元正と共に、主要街道である東海道と中山道に伝馬制を定めた 2 。これは、公用の旅行者や物資の輸送を効率化するための制度であり、後の宿駅制度の基礎となった。
さらに、慶長8年(1603年)に石見守に叙任された後 2 、慶長9年(1604年)には、東海、東山、北陸の三道に一里塚を建設する事業を指揮した 2 。一里塚は街道の里程を示す目印となり、旅人の便宜を図るとともに、計画的な街道整備を象徴するものであった。八王子においては、甲州街道の整備を自ら指揮し、従来よりも直線的で道幅の広い道路へと改修した記録が残っている 5 。
これらの交通網整備は、物資の流通を活性化させ、情報の伝達速度を向上させるだけでなく、大名の参勤交代の実施基盤ともなり、江戸を中心とする幕府の全国支配体制と中央集権化を強力に支えた 21 。長安が主導したこれらのインフラ整備は、まさに江戸幕府の「支配の血管」を構築するものであり、経済的な全国市場の形成を促し、幕府の権力を全国隅々にまで浸透させる上で極めて重要な意味を持っていた。
都市開発(八王子宿等)と地域社会への影響
長安は、関東代官頭として武蔵国八王子に陣屋を構え、この地を拠点に積極的な都市開発を行った。八王子宿の建設にあたっては、浅川の治水工事を行い氾濫を防ぐとともに、甲州街道を宿の中心に貫通させ、商業都市としての発展の基礎を築いた 2 。また、江戸防衛の西の拠点として、旧武田家臣団を中心とする八王子千人同心を組織し、軍事的な機能も持たせた 9 。八王子の町づくりは、商業的発展と軍事的要衝としての役割を両立させる、計画的な都市設計であったと言える。その影響は八王子に留まらず、全国各地の町立てにも積極的に関与したと伝えられている 5 。
その他の役職(勘定奉行、老中等)と幕政への関与
大久保長安の才能は多岐にわたり、鉱山経営やインフラ整備に留まらず、幕政の中枢においても重用された。彼は「所務奉行」として幕府財政を実質的に掌握し、これは後の勘定奉行の前身、あるいはそれに近い職務であったと考えられている 2 。
さらに、加判の列(幕政の重要事項に署名する資格を持つ重臣)に加えられ、年寄衆(後の老中)として幕政の最高意思決定にも関与したとされる 12 。この他にも、大和代官、石見銀山検分役、佐渡金山接収役、甲斐奉行、石見奉行、美濃代官など、驚くほど多くの重要な役職を兼任し、その権勢は絶大なものであった 9 。
その功績と広範な人脈から、長安は徳川家臣団の中に一大派閥を形成し、徳川政権初期の重鎮であった本多正信と勢力を二分するほどの影響力を持ったとまで言われている 4 。家康からの信任も極めて厚く、長安が中風を患った際には、家康自らが調合した薬を与えられたという逸話も残されている 11 。
第二部:大久保長安事件の真相
第一章:事件の勃発と長安の死
慶長18年(1613年)4月25日、大久保長安は駿府(現在の静岡市)において、中風のために69年の生涯を閉じた 2 。しかし、その死は平穏なものではなかった。死後わずか数日にして、徳川家康は長安の葬儀の中止を命じ、生前の不正行為を理由として、長安の財産調査を開始するという異例の措置をとったのである 6 。
江戸時代後期の編纂物である『慶長年録』によれば、家康は長安が生前から豪奢な生活を送り、その権勢を誇示するような振る舞いをしていたことを知りつつも、彼の類稀なる有能さゆえにこれを不問に付し、その死を待って罪を問うた、とされている 7 。この記述が事実であれば、長安の失脚は家康によって周到に計画されていた可能性も示唆される。
第二章:嫌疑の内容と捜査・処罰の実態
不正蓄財の嫌疑
大久保長安にかけられた最も主要な嫌疑は、生前の金銀隠匿、すなわち莫大な私財の不正な蓄積であった 2 。捜査の結果、諸国から集められた金銀およそ5,000貫目(現在の価値に換算することは困難だが、極めて巨額)や、多数の茶道具などが没収されたと記録されている 7 。
長安の豪奢な生活ぶりは生前から有名であり、同時代史料である『当代記』には、彼が鉱山巡察の際に70人から80人もの遊女を含む250人もの供を連れ、行く先々の自身の代官所を思うままに造作し、道中の民百姓に迷惑をかけたことなどが具体的に記されている 7 。これらの記録は、長安がその権勢を背景に贅沢な生活を送っていたことを裏付けており、不正蓄財の嫌疑に一定の根拠を与えている。
幕府転覆計画の嫌疑とその史料的根拠
不正蓄財という比較的具体的な嫌疑に加え、より重大な「幕府転覆計画」という嫌疑が長安にかけられたとされることがある。『徳川実紀』(江戸時代後期に編纂された徳川幕府の公式史書)には、長安の死後、彼の寝所の床下にあった石室から、諸大名と通じた連判状や、朝鮮へ財宝を密かに送った証拠などが見つかり、「大不敬」の行いもあった、という記述が「疑わしい話」として収録されている 9 。これが、長安が徳川家康の六男である松平忠輝(長安の娘婿の一人の主君)を通じて諸大名と連携し、幕府転覆を企てていたとする説の根拠とされることがある。
しかしながら、同時代の主要な史料である『駿府記』や『当代記』、あるいは信頼性の高い近年の研究において、この「幕府転覆計画」が明確な証拠をもって確認されているわけではない 7 。『学校では教えてくれない日本史事件の謎』という一般向けの書籍の目次情報に「大久保長安事件―伊達政宗らと幕府転覆を謀る?」といった章題が見られるものの 27 、その具体的な論拠や学術的な裏付けは不明である。
キリスト教との関わり、岡本大八事件との関連性
長安がキリスト教と深く関わっていた、あるいは慶長17年(1612年)に発覚したキリシタンがらみの疑獄事件である岡本大八事件に連座したという直接的な嫌疑や、それを裏付ける確かな史料は、主要な研究資料からは明確に確認されていない 7 。
岡本大八事件は、徳川家康の側近であった本多正純の家臣・岡本大八が、キリシタン大名であった有馬晴信から多額の賄賂を受け取った事件である。この事件は、幕府によるキリスト教禁教政策を一層強化する大きな要因となった 26 。長安の屋敷で、事件関係者の対決が行われたという記録は存在するものの 26 、これは長安自身がキリスト教に深く関与していたことを直接示すものではない。一部の資料では、大久保長安事件や岡本大八事件などをきっかけとして幕府がキリスト教弾圧を本格化させたと述べられているが 34 、長安自身がキリシタンであった、あるいはキリスト教徒と共謀して何らかの計画を企てていたという具体的な証拠は示されていない。
これらのことから、不正蓄財という比較的具体的な嫌疑に加えて、幕府転覆計画やキリスト教との関わりといったより重大な嫌疑が、事件後、何らかの政治的意図をもって後付けされたり、あるいは誇張されて広まったりした可能性が考えられる。これらは、長安一派を徹底的に排除し、その厳しい処分を正当化するためのプロパガンダとして利用されたのではないかという見方も成り立つ。
遺子及び関係者の処罰状況
大久保長安の死後、彼の一族と関係者に対する処罰は極めて過酷なものであった。まず、長安の財産は全て没収された。そして、彼の妻と7人の男子(嫡男・藤十郎、次男・外記、三男で青山成重の養子となっていた青山成国、四男・雲十郎、五男・内膳ら)全員に死罪が命じられ、慶長18年(1613年)7月9日に切腹させられた 2 。これにより、大久保長安の直系は断絶した。
事件の影響は長安の近親者に留まらなかった。彼と縁戚関係にあった大名や幕府の有力者も多数連座し、改易(所領没収)、減封、あるいは流罪といった厳しい処分を受けた。主な例としては、長安の三男・成国の養父であり、当時は幕府の老中であった青山成重、長安と共謀して知行(領地)を隠匿したとされた石川康長、堺奉行であった米津親勝、そして武田氏の血を引く武田信道・信正父子などが挙げられる 6 。
さらに、長安を徳川家康に推挙し、その庇護者であったとされる大久保忠隣も、この事件の余波を受けて失脚するという事態に至った 6 。一方で、長安には処刑された7人の男子の他に娘が2人おり、長女は服部半蔵(正成)の子・正重に、次女は剣豪の三井吉正に嫁いでいた。この娘2名は処罰の対象とはならず、それぞれの子孫を通じて長安の血筋は外孫の家系に伝わったとされている 9 。
表2:大久保長安事件 関係者処罰一覧
|
氏名 |
長安との関係 |
処罰内容 |
典拠 (例) |
|
長安の遺子7名 |
実子 |
切腹 |
6 |
|
大久保忠隣 |
長安の庇護者、大久保姓の由来 |
改易(失脚) |
6 |
|
青山成重 |
長安の三男成国の養父、老中 |
改易 |
7 |
|
石川康長 |
長安と共謀し知行隠匿 |
改易 |
7 |
|
米津親勝 |
堺奉行、長安と結託し私曲 |
流罪後切腹 |
7 |
|
武田信道 |
(詳細な関係は要調査) |
配流 |
7 |
|
武田信正 |
信道の子 |
配流 |
7 |
|
久貝正俊 |
徒頭 |
叱責 |
7 |
|
弓気多昌吉 |
大納戸 |
叱責 |
7 |
|
鵜殿重長 |
(詳細な関係は要調査) |
改易後切腹 |
7 |
第三章:事件の真相をめぐる諸説
大久保長安事件の真相については、現在に至るまで確定的な説はなく、様々な要因が複雑に絡み合っていたと考えられている。主な説としては、以下のものが挙げられる。
長安自身の驕りや不正行為を原因とする説
これは、長安が生前の豪奢な生活や、その権勢を背景とした奔放な振る舞い、そして実際に不正な蓄財を行っていたことが、徳川家康の不興を買い、死後の厳罰に繋がったとする見方である 7 。前述の通り、『当代記』などには、長安の派手な鉱山巡察の様子などが記録されており、これらの行動が彼の失脚の一因となった可能性は否定できない。『慶長年録』には、家康が長安の不正を知りつつも、その卓越した能力を惜しんで生前は不問とし、死後に処断したという記述があり、この説を補強している 7 。
本多正信ら政敵による陰謀説
徳川家康の家臣団内部における権力闘争が事件の背景にあったとする説も有力である。大久保長安は、その功績と人脈から一大派閥を形成し、徳川家家臣団の中で本多正信・正純親子と勢力を二分するほどの存在となっていた 4 。
『慶長年録』や『徳川実紀』といった史料には、長安の庇護者であった大久保忠隣と本多正信が不和であったため、正信が長安の死後に家康に讒言し、これが事件の主たる原因となったという記述が見られる 7 。また、岡本大八事件において本多派が面目を失墜したことへの報復として、長安事件を利用して大久保派の失脚を狙ったという見方も存在する 26 。あるウェブサイトで行われた歴史ファンの投票では、本多親子との権力闘争に敗れたことが粛清の最大の理由であるとする見方が最も多くの支持を集めている 36 。
徳川家康の深謀遠慮と幕府権力確立の視点
事件の背後には、徳川家康自身の政治的な深謀遠慮があったとする見方も根強い。長安が一代で築き上げた巨大な財力、広範な支配力、そして一部の西国大名との繋がりなどが、成立間もない江戸幕府の安定にとって潜在的な脅威と家康の目に映り、その死を好機として、幕府権力のさらなる集中と中央集権体制の強化のために、長安一派を粛清したというものである 2 。
長安は、さしたる武功もないまま、家康の側近として異例の出世を遂げ、強大な権勢を振るった。これは、他の譜代家臣からの嫉妬や反感を招きやすかったであろうし、家康としても、特定の家臣への過度な権力集中が幕府の基盤を揺るがすことを警戒していた可能性は十分に考えられる 26 。大久保長安研究の第一人者である村上直氏は、長安の莫大な資産や広大な支配領域に対して幕府上層部の年寄衆が抱いた危惧と、彼らの間での権力争いが事件の根本的な原因であったと見ている 37 。
これらの説は必ずしも排他的なものではなく、大久保長安事件の真相は、長安自身の行動、政敵による策謀、そして家康および幕府中枢の政治的判断が複雑に絡み合った結果であると考えるのが妥当であろう。この事件は、能力主義的な人材登用と、幕藩体制確立期における権力集中と厳格な統制強化という、初期徳川政権が持つ二面性を象徴的に示していると言える。長安の行動が政敵に攻撃の口実を与え、家康がそれを利用して、あるいは政敵の動きに乗じる形で、幕府の権力基盤をより強固なものにしようとした、という複合的な構図が浮かび上がってくる。これは、初期の江戸幕府がまだ盤石ではなく、有力な家臣の動向に常に神経を尖らせていたことの証左とも解釈できる。
第三部:歴史的評価と遺産
第一章:同時代史料(『駿府記』『当代記』等)に見る長安像
大久保長安の生きた時代に近い史料として、『駿府記』と『当代記』が挙げられる。これらの史料は、長安の人物像や彼が関わった出来事について断片的ながら貴重な情報を提供している。
『駿府記』は、徳川家康の駿府隠居時代の日記であり、慶長16年(1611年)に長安が駿府城に到着したことや 38 、名古屋城の普請に長安が関与していたことなどが記録されている 39 。しかし、この史料は家康の動静が中心であり、長安個人に焦点を当てた詳細な評価や事件の背景に関する記述は限定的である。
一方、『当代記』は、長安の出自が猿楽師の次男であること 11 、彼の豪奢な生活ぶり 7 、そして大久保長安事件に関連して石川康長が長安と結んで隠田を申告しなかった罪に問われたこと 26 など、より具体的な情報を含んでいる。また、長安が駿府城天守の造営のために黄金30万枚を献上したという逸話もこの史料に見られる 19 。
これらの同時代史料は、長安の能力の一端や彼の派手な生活、そして失脚に至る事件の表面的な理由などを伝えている。しかし、その記述は断片的であり、長安の鉱山経営の具体的な手法や、財政家としての詳細な政策立案のプロセス、あるいは事件の深層にある政治的力学については、これらの史料のみから全貌を解明することは難しい。特に、失脚した人物に関する記述は、その失脚を正当化する意図が含まれている可能性も考慮に入れる必要があり、史料批判の視点が不可欠である。これらの史料を基礎としつつも、考古学的な発見(例えば石見銀山の大久保間歩 14 )や、後世の専門家による研究(例えば村上直氏の研究 37 )を組み合わせることで、より多角的かつ客観的な長安像を構築する必要がある。
第二章:後世における評価の変遷と研究史(村上直氏の研究を中心に)
大久保長安の歴史的評価は、その劇的な失脚と一族処刑という結末から、長らく「悪代官」「不正蓄財に明け暮れた奸臣」といったネガティブなイメージがつきまとってきた 41 。しかし、近年の研究、特に実証的な歴史学の進展に伴い、彼の卓越した行政手腕や初期江戸幕府の財政基盤確立への多大な貢献が再評価される動きが見られる 4 。
この再評価の流れにおいて、歴史学者の村上直氏の研究は極めて重要な位置を占めている。村上氏は大久保長安研究の第一人者と目されており、長年にわたり多数の論文を発表してきた 37 。その集大成とも言える著作『論集代官頭大久保長安の研究』は、長安の出自、甲斐武田氏の蔵前衆との関連、関東における在地支配、初期幕政における役割、石見銀山や佐渡鉱山の支配と経営、そして大久保長安事件の真相など、長安に関するあらゆる側面を網羅的に論じた画期的な研究書である 37 。村上氏はこの中で、大久保長安事件の真相について、長安の莫大な資産や広大な支配領域に対して幕府上層部の年寄衆が抱いた危惧と、彼らの間での権力争いが事件の根本的な原因であったという見解を提示している 37 。
「歴史の中で消されてきた長安の事績がよくわかる名著」 40 と評されるように、村上氏の研究は、従来の長安に対する一面的な評価を覆し、その功績と実像を明らかにする上で大きな貢献を果たした。また、八王子市民を対象としたアンケート調査で、長安に対して肯定的なイメージを持つ人が多いという結果が出ていることは 37 、学術的な研究成果が一般の歴史認識にも影響を与え、地域レベルでの長安への関心と再評価の高まりを示していると言えよう。これは、事件の衝撃的な結末による負のイメージが先行していた状態から、彼の具体的な業績(鉱山開発、インフラ整備、財政確立など)が広く知られるようになるにつれて、初期幕府における不可欠な功労者としての側面が重視されるようになったことを意味する。
第三章:史跡、伝承、そして現代への影響
大久保長安の生涯と業績は、その死後の汚名にもかかわらず、彼が活動した各地に数多くの史跡や伝承として刻まれ、現代にも影響を与え続けている。
墓所・供養塔
長安の墓所や供養塔は、彼が深く関わったとされる複数の場所に存在する。
- 島根県大田市: 石見銀山の所在地である大田市大森町には、長安が生前に自身の冥福を祈って建立したとされる逆修墓と、江戸時代後期の寛政6年(1794年)にその事績を顕彰して建てられた紀功碑および五輪墓が大安寺跡に残されている 9 。また、同県温泉津町の愛宕神社にも長安の逆修墓が存在すると伝えられている 9 。
- 新潟県佐渡市: 佐渡金山のあった佐渡市相川にも大安寺があり、これは大久保長安が創建したとされ、境内には長安の逆修塔(国指定史跡)が現存する 47 。
- 山梨県甲府市: 甲斐国とも縁の深い甲府市の天尊躰寺にも長安の墓があり、これは長安が生前の遺言により同寺に葬られたためと伝えられている 49 。
これらの墓所や供養塔の存在は、長安が各地で大きな影響力を持ち、その死後も記憶されていたことを示している。
屋敷跡・関連史跡
長安が活動の拠点とした場所には、今もその面影を伝える屋敷跡や関連史跡が残る。
- 東京都八王子市: 長安が関東代官頭として陣屋を構えた八王子市小門町の産千代稲荷神社境内には、「大久保石見守長安陣屋跡」の碑が建てられている 5 。また、長安が浅川の治水のために築いたとされる石見土手の一部も現存すると言われている 9 。
- 静岡県伊豆市: 伊豆金山のあった土肥地区には、土肥金山跡に大久保長安の像が設置されている 50 。
- 新潟県佐渡市: 佐渡市沢根には、鶴子銀山を管理した代官屋敷跡があり、近年の発掘調査によってその構造の一部が明らかになっている 51 。
- 島根県大田市: かつて一里塚の目印として長安が植えたと伝承されてきた「定めの松」(クロマツ)は、残念ながら2023年までに枯死してしまった 9 。
これらの史跡は、長安の広範な活動範囲と、彼が各地の行政や開発に深く関与していたことを具体的に示している。
伝承・逸話
大久保長安の人物像や生涯については、多くの興味深い伝承や逸話が語り継がれている。
- 無類の女性好きで、常に70人から80人もの側女を抱えていたという 9 。
- 金山奉行であったことから派手好きで、自らの死にあたっては黄金の棺を用い、華麗な葬儀を行うよう遺言したと伝えられる 9 。
- その死後、墓から遺体を掘り出され、磔にされたという凄惨な話も伝わっている 4 。これは、事件後の幕府による徹底的な断罪措置を象徴する逸話と言えるだろう。
- 伊豆や佐渡の金山には、長安が横領した莫大な金銀を隠したという、いわゆる「大久保長安埋蔵金伝説」も存在する 50 。
これらの伝承や逸話は、長安の非凡な生涯と、その劇的な失脚が人々に与えた強烈な印象を反映している。
現代への影響
大久保長安の業績は、数世紀の時を経た現代においても、様々な形で評価され、影響を与えている。
- 長安が開発に尽力した石見銀山遺跡とその文化的景観、そして佐渡島の金山は、ユネスコの世界遺産に登録され、その歴史的価値が国際的にも広く認められている 5 。これは、長安の鉱山経営の手腕と、それが日本の歴史に与えた影響の大きさを示すものと言える。
- 東京都八王子市では、長安が築いた都市基盤が現代の街の礎となっており、その功績を顕彰する市民団体による活動や、関連史跡を巡るスタンプラリーなども企画・実施されている 12 。
- その波乱に満ちた謎めいた生涯は、多くの歴史小説やテレビドラマ、漫画などの創作物の題材となり、歴史ファンを中心に今もなお関心を集め続けている 9 。
- 中央の公式記録では断罪された長安であるが、彼が実際に活動し大きな功績を残した地域においては、史跡の保存や伝承の継承、顕彰活動が積極的に行われている。これは、幕府による公式の評価とは別に、地域に根差した記憶と評価が存在し、それが現代において歴史的・文化的な資源として再評価されていることを示している。
終章:総括と今後の課題
大久保長安の歴史的意義の再確認
大久保長安は、猿楽師の子という出自から、その卓越した実務能力と先見性をもって徳川家康に重用され、鉱山開発、財政運営、検地、交通網や都市の整備など、多岐にわたる分野で初期江戸幕府の基盤確立に決定的かつ広範な貢献をした稀有な人物であった。彼の業績なくして、徳川幕府の初期における財政的安定と中央集権体制の迅速な構築は困難であった可能性が高い。
その生涯は、戦国時代から江戸時代初期への移行期における社会の流動性と、新興勢力である徳川政権下での高度な専門知識を持つ技術官僚の台頭、そしてその権勢が孕む危うさと限界を象徴している。
大久保長安事件は、単に一個人の不正蓄財事件として片付けられるべきものではなく、初期幕府内部における権力闘争、財政の掌握と管理、思想統制の萌芽、そして中央集権体制を確立していく過程で発生した、極めて複雑な政治的事件として捉える必要がある。彼の失脚は、徳川政権が安定期へ移行する中で、個人の才能に依存した統治から、より組織的で統制された官僚システムへと移行していく過渡期の出来事としても理解できよう。
本報告の限界と今後の研究への展望
本報告は、現時点で入手可能な公開資料群に基づいて大久保長安の実像に迫ろうと試みたものであるが、いくつかの限界も認識している。一次史料の網羅的な調査や、未発見・未公開史料の発掘・分析には至っておらず、今後の研究によって新たな事実が明らかになる可能性は十分にある。
今後の課題としては、まず、同時代史料である『駿府記』や『当代記』における大久保長安関連の記述について、より詳細なテキストクリティークと文脈分析を行う必要がある。特に大久保長安事件の具体的な嫌疑内容、例えば幕府転覆計画やキリスト教との関わりといった点については、史料的裏付けをより一層精査し、その信憑性を検証する必要がある。
また、長安が導入したとされる甲州流採鉱法やアマルガム法といった鉱山技術の具体的な内容と、それが金銀産出量に与えた影響を定量的に明らかにすることも重要な課題である。これには、鉱山遺跡の考古学的調査や、当時の産出量に関する記録の再検討、さらには諸外国の鉱山技術史との比較研究などが有効であろう。
さらに、長安の経済政策や財政運営の全体像、彼が築いたとされる広範な人脈ネットワークの実態、そして彼が統治した各地の地域社会に与えた具体的な影響についても、さらなる実証的な研究が期待される。これらの研究を通じて、大久保長安という人物の多面的な実像と、彼が生きた時代の特質がより深く理解されることを展望する。
引用文献
- 大久保長安 | 書籍 - PHP研究所 https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-56959-8
- 大久保長安(オオクボナガヤス)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E9%95%B7%E5%AE%89-39137
- 家康 鉱山開発で資金を稼ぐ - 郷土の三英傑に学ぶ https://jp.fujitsu.com/family/sibu/toukai/sanei/sanei-24.html
- 江戸幕府の金山開発の礎を築いた大久保長安 - おたからや https://www.otakaraya.jp/contents/gold-platinum/gold/edobakuhu-gold/
- 2つの世界遺産「石見銀山・佐渡金山」をつくった【大久保長安 ... https://www.simizukobo.com/ookubonagayasu
- 大久保長安の生涯 - 石見銀山通信 - JUGEMブログ https://iwami-gg.jugem.jp/?eid=4513
- 大久保長安事件 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E9%95%B7%E5%AE%89%E4%BA%8B%E4%BB%B6
- 江戸の金山奉行 大久保長安の謎 - 現代書館 http://www.gendaishokan.co.jp/goods/ISBN978-4-7684-5669-9.htm
- 大久保長安 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E9%95%B7%E5%AE%89
- 武田から徳川へ移った大久保長安と一族の悲劇~息子たちが全員切腹の顛末とは? https://bushoojapan.com/bushoo/tokugawa/2024/04/24/178476
- 信玄と家康に仕えた「大久保長安」悲惨すぎる末路 板倉勝重と同じく実力を認められたものの https://toyokeizai.net/articles/-/723231?display=b
- 大久保長安どんな人? - 八王子のまちづくりと伝承地 https://www.mizu.gr.jp/images/main/bunkajuku/houkoku/014/document_fukushima.pdf
- 八王子町会自治会連合会(千人町地区) https://chojiren-hachioji.jp/pages/27/
- 大久保間歩(石見銀山) | しまね観光ナビ|島根県公式観光情報サイト https://www.kankou-shimane.com/destination/20288
- 大久保長安墓所 1603 年から 1867 年まで、日本を統治した徳川幕府の創始者として今では知られ https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001553597.pdf
- 世界遺産 石見銀山 - ふぐ加工品の和田珍味|うず煮の福乃和通販サイト https://wadachinmi.co.jp/honten/ginzan.html
- 【歴史編】認めてほめる人材育成に長けた名将――武田信玄 - トロフィー生活 http://www.trophy-seikatsu.com/wp/blog/hyousyoukougaku/takeda-shingen.html
- www.city.sado.niigata.jp https://www.city.sado.niigata.jp/uploaded/attachment/37939.pdf
- 家康公の史話と伝説とエピソードを訪ねて - 駿府城内の伝説から - 静岡市観光 https://www.visit-shizuoka.com/t/oogosho400/study/13_02.htm
- 【天領支配――大久保長安】 - ADEAC https://adeac.jp/nakatsugawa-city/text-list/d100010/ht011470
- 第一章 陸上交通 | 滝沢市 https://www.city.takizawa.iwate.jp/about-takizawa/gaiyo/bunkazai-history/sonshi/sonshi-kotsutsushin/p20241125163609
- 日本における道路技術の発達 - Browse by Subject - Passing on "The Japanese Experience" - Library - Institute of Developing Economies https://d-arch.ide.go.jp/je_archive/english/society/wp_unu_jpn10.html
- 日本史/江戸時代 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/period-edo/
- ミツカン水の文化 第14回里川文化塾 「大久保長安・八王子の治水とまちづくり」日時 https://www.mizu.gr.jp/images/main/bunkajuku/houkoku/014/document_suzuki.pdf
- 江戸幕府の行政機構 https://glim-re.repo.nii.ac.jp/record/117/files/keizai_10_1_45_61.pdf
- 石川氏改易ガイド https://www.oshiro-m.org/wp-content/uploads/2015/04/g3_2.pdf
- CiNii Books Content Search - 鎌倉 https://ci.nii.ac.jp/books/contents?p=87&contents=%E9%8E%8C%E5%80%89&count=50&sortorder=1&l=en
- CiNii Books 内容検索 - 鎌倉 https://ci.nii.ac.jp/books/contents?p=22&contents=%E9%8E%8C%E5%80%89&count=200&sortorder=1
- 『学校では教えてくれない日本史事件の謎』 | 学研出版サイト https://hon.gakken.jp/book/1340310500
- 学校では教えてくれない日本史事件の謎 - 史上に残る大事件の知られざる真相に迫る! - 9784054031050 - 楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/4027945/
- 学校では教えてくれない日本史事件の謎 / 学研編集部【編 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784054031050
- https://ci.nii.ac.jp/books/contents/CS00000001/
- https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA7769087X
- 林又七「クルス透かし」鐔 - 日本刀・刀装具の研究 http://katana.mane-ana.co.jp/matashichi.html
- 家康公の略年表 - 駿府大御所時代 - 静岡市観光 https://www.visit-shizuoka.com/t/oogosho400/study/11_07.htm
- 大久保忠隣改易の真相は? - ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/yorons/240
- 株式会社清水工房・揺籃社|特集ページ|あなたの思いをかたちに https://www.simizukobo.com/feature
- 歴史の目的をめぐって 駿府城(駿河国) https://rekimoku.xsrv.jp/3-zyoukaku-13-sunpujo.html
- 第一章 名古屋城の築城 https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/center/uploads/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%AB%A0_1.pdf
- 論集代官頭大久保長安の研究 | 村上直 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E8%AB%96%E9%9B%86%E4%BB%A3%E5%AE%98%E9%A0%AD%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E9%95%B7%E5%AE%89%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E9%A6%AC%E5%A0%B4%E6%86%B2%E4%B8%80/dp/4897083265
- 元祖悪代官、大久保長安がすごい! - 株式会社未来図 https://miraiz-corp.jp/2024/02/22/088/
- 大久保長安 家康を創った男! | 山岩 淳, 遠藤 進, 金子 純子 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E9%95%B7%E5%AE%89-%E5%AE%B6%E5%BA%B7%E3%82%92%E5%89%B5%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%94%B7%EF%BC%81-%E5%B1%B1%E5%B2%A9-%E6%B7%B3/dp/4897084393
- 慶長期近江国の支配 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/48398/1/72_71.pdf
- 村上直 (歴史学者) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E7%9B%B4_(%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%AD%A6%E8%80%85)
- 論集代官頭大久保長安の研究 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB13112507
- 大久保石見守の墓 | しまね観光ナビ|島根県公式観光情報サイト https://www.kankou-shimane.com/destination/21183
- 相川:江戸時代の繁栄:ギャラリー - 新潟県佐渡市公式ホームページ https://www.city.sado.niigata.jp/site/mine/4492.html
- 大安寺 - さど観光ナビ https://www.visitsado.com/spot/detail0469/
- 信玄公が愛した山梨に残る徳川家康の足跡 #2 天尊躰寺(てんそんたいじ) https://www.yamanashi-kankou.jp/special/shigen_ieyasu_kosyukin_sontaiji_02.html
- 箱根に眠る埋蔵金!金山奉行の横領金は存在するのか - 東スポnote https://note.tokyo-sports.co.jp/n/n8e5855aa3401
- 鶴子銀山代官屋敷跡 https://edomegane.com/spot/tsurushi/02/
- 【八王子十五宿めぐり絵図&大久保長安スタンプラリー】 - 清水工房 https://www.simizukobo.com/news/3926
- 八王子を舞台にした小説 https://www.library.city.hachioji.tokyo.jp/upload/known/66e0fe52a5dd7.pdf
- 【大久保長安】おすすめWeb小説一覧を人気順で読もう - カクヨム https://kakuyomu.jp/tags/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E9%95%B7%E5%AE%89
- 直木賞-選評の概要-第99回 https://prizesworld.com/naoki/senpyo/senpyo99.htm