小田政清
小田政清は備中国の国人領主。庄氏との抗争で一時伊予へ亡命するも再起し、毛利氏に帰属。軍馬や鉄砲の売買にも関与した可能性があり、子の代で豊臣政権の転封により備中支配を終えた。
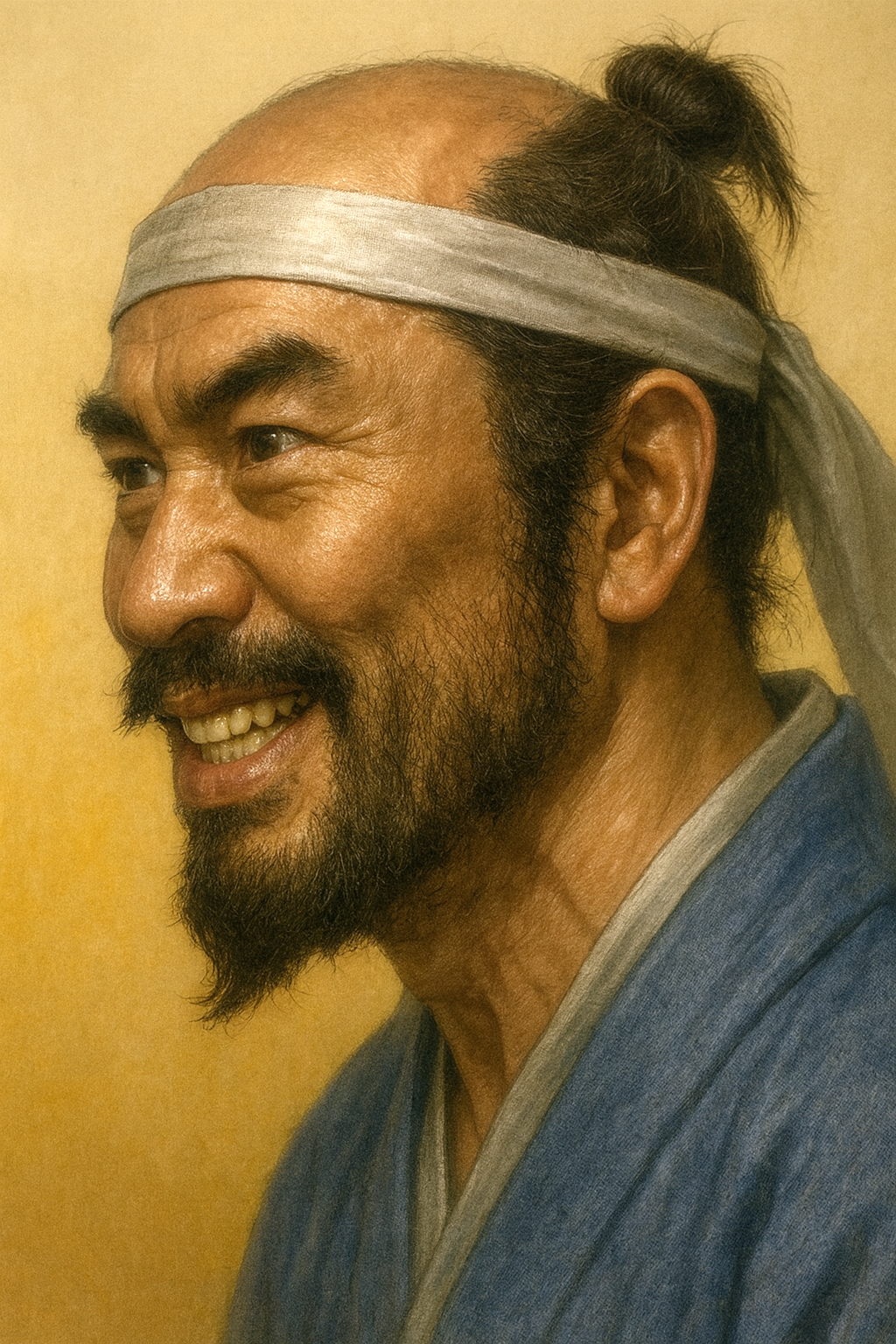
戦国期備中における国人領主・小田政清の実像 ― 激動の時代を生き抜いた戦略と一族の軌跡
序論:備中の雄、小田政清
日本の戦国時代は、織田信長や豊臣秀吉といった天下人の物語に光が当てられがちである。しかし、その華やかな歴史の陰には、地方で自らの領地と一族の存続をかけて激動の時代を生き抜いた、無数の武将たちが存在する。本報告書が主題とする小田政清(おだ まさきよ)も、そうした地方領主の一人である。
彼が活動の拠点とした備中国(現在の岡山県西部)は、戦国時代を通じて、西国の覇者を目指す安芸の毛利氏、山陰から勢力を伸ばす出雲の尼子氏、そして後に中国地方東部に一大勢力を築く備前の宇喜多氏といった大国の力が衝突する、まさに「境目」の地であった 1 。このような地政学的環境は、備中に本拠を置く「国人衆(くにしゅう)」と呼ばれる在地領主たちに、常に過酷な選択を強いた 3 。彼らは、独立を維持することが極めて困難な状況下で、いずれの大勢力に与し、いかにして自らの所領と一族を守り抜くかという、存亡を賭けた戦略的判断を迫られ続けたのである。
小田政清は、この備中という舞台で、一軍を率いる国人衆の頭領として大きな影響力を持った人物である。彼の生涯は、敗北と亡命、そして不屈の精神による再起と、波乱に満ちている。本報告書は、小田政清個人の生涯を詳細に追跡するとともに、彼が属した備中 小田氏の出自から終焉までを俯瞰する。さらに、彼を取り巻く庄氏や三村氏といった他の国人領主との関係、そして毛利氏などの大勢力との関わりを分析することで、戦国時代の地方社会における権力闘争のダイナミズムを具体的に解き明かすことを目的とする。
また、本報告書では、小田政清が軍馬や鉄砲の取引に関与していた可能性についても、直接的な史料がない中で、状況証拠を積み重ねてその蓋然性を検証する。備中が有した経済的基盤や、当時の軍事技術の動向を踏まえることで、一国人領主の経済活動の実態、すなわち領国経営と軍事力維持に不可欠な「軍事経済システム」の管理運営者としての一面にも光を当てたい。
小田政清という一人の武将の生涯を深く掘り下げることは、戦国史のミクロな実態、すなわち英雄たちの物語の背景で繰り広げられた、地方領主たちのリアルな生存競争の姿を浮き彫りにすることに繋がるであろう。
第一章:備中 小田氏の出自と文化的基盤
小田政清の人物像を理解するためには、まず彼が属した「備中 小田氏」が、いかにしてこの地に根を下ろし、どのような特質を持つ一族であったかを知る必要がある。備中 小田氏は、関東の名族である常陸小田氏とは系統を異にする、独自の歴史を持つ一族である 4 。その起源は、武威と文化という二つの側面によって特徴づけられる。
一族の起源 ― 中央からの支配者
備中 小田氏の歴史は、室町時代中期の応安2年(1369年)に遡る 2 。この年、足利将軍家に仕える幕臣であった床上小松秀清(とこのうえこまつ ひできよ)が、室町幕府から備中国小田郡の地頭職に任命され、京都から下向したことに始まる 6 。彼はこの地の支配拠点として、神戸山城(こうべやまじょう)を築いた 2 。
秀清の子である二代目の康清(やすきよ)の代に、本拠地の地名である「小田」を姓として名乗り始め、ここに「備中 小田氏」が誕生した 5 。このように、小田氏は土着の豪族ではなく、中央権力である室町幕府によって派遣された、いわば「落下傘」の支配者であった。これは、在地勢力との間に潜在的な緊張関係を生む可能性をはらむ一方で、中央との繋がりを持つことが一族の権威の源泉ともなった。
文化的権威の確立 ― 歌人・正徹の輩出
備中 小田氏を特異な存在たらしめているのは、その武家としての側面だけではない。室町時代を代表する歌人の一人であり、「藤原定家の再来」とまで評された正徹(しょうてつ)が、この一族の出身であると伝えられている点である 6 。『矢掛町史』などの記録によれば、正徹は二代当主・小田康清の子、あるいは弟であったとされる 6 。
正徹は若くして京に上り、冷泉為尹(れいぜいためまさ)や今川了俊(いまがわりょうしゅん)といった当代一流の文化人に和歌を学び、歌壇において絶大な名声を獲得した 7 。地方の国人領主の一族から、中央の文化シーンを牽引するほどの人物が輩出されたことは、極めて異例である。
この事実は、小田氏が単に武力によって領地を支配しようとしたのではなく、和歌という当時最高の教養と文化を身につけ、それを在地に示すことで、自らの支配の正統性と権威を確立しようとした、高度な戦略の表れであったと解釈できる。中央から来た新興の支配者として、在地社会に受け入れられ、その地位を盤石なものにするために、武力(神戸山城)と文化(正徹)という二つの柱を巧みに利用したのである。この文化的基盤は、後に小田政清が激動の時代を生き抜く上での、見えざる力となった可能性も考えられる。
第二章:小田政清の生涯 ― 挫折、再起、そして飛躍
小田政清は、備中 小田氏の五代当主とされ、一族の歴史の中でも最も激動の時代を生きた人物である 2 。彼の生涯は、周辺勢力との絶え間ない緊張関係の中で、巧みな戦略と不屈の精神をもって自らの道を切り拓いた、一人の国人領主の壮絶な物語である。その軌跡を追うにあたり、まず彼の活動に関わる主要な出来事を年表にまとめる。
|
年代(西暦) |
元号 |
出来事 |
典拠 |
|
1369年 |
応安2年 |
始祖・床上小松秀清が小田郷の地頭職として下向、神戸山城を築く。 |
5 |
|
1553年 |
天文22年 |
小田氏、安芸の毛利氏の傘下に入る。 |
2 |
|
1555年 |
弘治元年 |
小田政清、出城として岩屋山城を築くも、庄氏・三好氏に攻められ、本拠・神戸山城と共に落城。一時、伊予国へ亡命する。 |
8 |
|
1565年 |
永禄8年 |
庄氏と和睦し、小田郷へ帰還。新たに馬鞍山城を築き、本拠を移転する。 |
5 |
|
1569年 |
永禄12年 |
毛利輝元に従い、三村氏らと共に庄氏の拠点・猿掛城攻めに参加する。 |
10 |
|
1595年 |
文禄4年 |
政清の子・元家の代、毛利氏の都合により安芸国へ転封。226年にわたる備中支配が終焉を迎える。 |
5 |
第一節:国人領主としての基盤構築
小田政清が家督を継いだ16世紀半ば、備中は大国の草刈り場と化しつつあった。このような状況下で、彼はまず自らの支配領域である小田郷の防備を固めることから着手した。彼の軍事戦略は、単一の拠点に依存するのではなく、複数の城を有機的に連携させた「面」による防衛体制の構築にあった。
当初の本拠は、一族の始祖が築いた神戸山城であった 8 。政清はこれに加え、小田川流域を見渡せる戦略的要地に次々と城を築き、あるいは支配下に置いた。その代表的なものが、出城として築かれた岩屋山城、弟の小田乗清を城将として配置した折敷山城、そして田鶴山城などである 2 。これらの城郭群は、小田郷を取り囲むように配置され、敵の侵攻を多方面から警戒・迎撃するための防衛ネットワークを形成していた。この城郭網の構築は、彼が優れた軍事的才覚と、領地を防衛するための明確な戦略思想を持っていたことを示している。
|
城郭名 |
標高 |
築城/支配年 |
戦略的位置づけと関連事項 |
典拠 |
|
神戸山城 |
不明 |
1369年~ |
小田氏初代からの本拠地。政清の代に庄氏に攻められ一時失陥。 |
5 |
|
岩屋山城 |
151m |
1555年 |
政清が庄氏を狙って築いた出城。しかし、逆に攻められ落城。 |
8 |
|
折敷山城 |
60m |
1555年頃 |
岩屋山城の南方約1.5kmに位置。弟の乗清を城将として配置。 |
2 |
|
田鶴山城 |
82m |
不明 |
政清が築城したとされる支城の一つ。 |
2 |
|
馬鞍山城 |
224m |
1565年 |
伊予から帰還後、新たに築いた本拠地。より防御に優れた山城。 |
2 |
第二節:庄氏との抗争と伊予亡命 ― 試練と再起
勢力拡大を目指す政清にとって、最大の障壁となったのが、同じ備中の有力国人である庄氏であった。弘治元年(1555年)、政清は庄氏を牽制すべく、その勢力圏に近い岩屋山に出城を築いた 9 。しかし、この動きは庄氏を刺激する結果となる。庄氏は、当時畿内で勢力を誇っていた三好氏の援軍を得て反撃に転じ、岩屋山城だけでなく、小田氏の本拠である神戸山城にまで攻め寄せた 8 。この戦いで政清は敗北し、二つの城を失うという手痛い打撃を受け、本拠地を追われることになった。
領地を失った政清が亡命先として選んだのは、瀬戸内海を隔てた対岸の伊予国(現在の愛媛県)であった 8 。なぜ伊予であったのか、その理由は史料に明記されていない。しかし、この選択は、彼の活動範囲が備中国内に留まっていなかったことを示唆している。当時の伊予は河野氏が支配し、村上水軍などの海賊衆が活動する海の世界であった。政清がこれらの海上勢力と何らかの繋がりを持っていたか、あるいは彼を攻撃した三好氏と敵対する勢力を頼った可能性が考えられる。この亡命は、彼が瀬戸内海を介した広域的な人的・政治的ネットワークの中に身を置いていたことの重要な傍証と言える。
国人領主にとって本拠地の喪失は、一族の滅亡に直結しかねない致命的な事態である。しかし、政清はここで終わらなかった。伊予での雌伏の時を経て、10年後の永禄8年(1565年)、彼は宿敵であった庄氏と和睦を結び、故郷である小田郷への復帰を果たす 5 。
帰還した彼が取った行動は、単なる旧領の回復に留まらなかった。彼は、かつての本拠・神戸山城には戻らず、より標高が高く防御に優れた馬鞍山(標高224m)に新たな城を築き、そこを本拠とした 2 。これは、一度本拠を落とされた苦い経験から学び、より堅固な拠点を求める合理的な判断であった。さらに、この馬鞍山城は、瀬戸内海側の笠岡に本拠を置く村上氏の進攻に備える意図があったとも伝えられており 2 、脅威の対象の変化に対応した戦略思想の深化が見て取れる。この一連の動きは、政清が単なる武将ではなく、敗北から学び、より高度な戦略を構築できる、強靭な精神力と戦略眼を持った人物であったことを物語っている。
第三節:激動の中国地方と毛利氏への帰属
政清が庄氏との抗争に明け暮れていた16世紀半ば、中国地方全体の勢力図は大きく動いていた。出雲の尼子氏と安芸の毛利氏が、中国地方の覇権を巡って激しい争いを繰り広げていたのである。備中は両勢力の最前線となり、現地の国人たちは否応なくその渦中に巻き込まれていった 12 。
このような状況下で、小田政清は極めて重要な決断を下す。天文22年(1553年)、彼は毛利氏の傘下に入ることを選択したのである 2 。この決断が下された時期は、特筆に値する。毛利元就が厳島の戦い(1555年)で陶晴賢を破り、中国地方の覇者としての地位を確立する以前の段階であった 14 。当時はまだ、尼子・毛利のどちらが勝利するか、予断を許さない状況だったのである。
この早期の帰属が、毛利元就の将来性を見抜いた「先見の明」によるものか、あるいは国境を接する安芸の毛利氏と敵対することの不利を悟り、眼前の強者と結ぶことを選んだ「現実主義」の表れであったかは断定できない。しかし、結果としてこの決断は、小田氏の運命を大きく左右することになった。
事実、後に庄氏に敗れて伊予へ亡命した政清が、10年後に帰還し再起を果たせた背景には、毛利氏という強力な後ろ盾の存在があった可能性が高い。毛利氏の傘下にあったからこそ、庄氏との和睦も有利に進められたと推察される。
毛利方としての彼の立場は、永禄12年(1569年)の出来事からも明らかである。この年、毛利輝元が、かつて政清の宿敵であった庄氏の拠点・猿掛城を攻撃した際、政清は三村氏らと共に毛利軍の部将として従軍している 10 。かつての敵を、新たな主君の下で共に攻めるという構図は、戦国時代の国人領主が置かれた複雑な立場を象徴している。
この政清の選択は、後に毛利氏と宇喜多氏の同盟を不服として毛利に背き、織田信長と結んだ結果、備中兵乱で滅亡した三村元親の運命とは実に対照的である 16 。大国の狭間で生き残るためには、時勢を読み、的確な相手と同盟を結ぶ外交手腕がいかに重要であったか。小田政清の生涯は、そのことを雄弁に物語っている。
第四節:国人領主としての統治と経済力
一軍を率い、城を築き、外交を展開するためには、強固な経済基盤が不可欠である。小田政清の領主としての実像に迫る上で、その統治能力と経済力は重要な指標となる。
史料には「小田治部太夫(じぶだゆう)政清」という呼称が伝わっている 18 。「治部大輔(じぶのたいふ)」は、朝廷の官職である治部省の次官であり、格式の高い官途名である 19 。戦国時代の官途名は、朝廷から正式に叙任されたものと、自称・私称のものがあったが、政清がどちらであったかは不明である。しかし、いずれにせよこの称号を名乗ること自体が、領内の民や家臣に対する権威付けとなり、他の国人領主や大名との交渉において自らの格を示す上で重要な意味を持った。石田三成の「治部少輔」よりも格上とされる「大輔」を名乗っていたことは、彼の自負の高さと、戦国社会における「箔付け」の重要性を物語っている。
彼の経済力の源泉は、その所領にあった。小田氏が支配した小田郡は、全域で34,000石の石高があり、そのうち小田氏は約3分の1を支配していたとの推計がある 2 。これは約11,000石に相当し、一国人領主としては決して小さくない規模であった。
さらに、ユーザーが関心を寄せる「軍馬や鉄砲の売買」について考察すると、政清が自ら商人として活動したとは考えにくい。むしろ、彼は自領とその周辺の経済資源を管理・統制する「軍事経済の管理者」であったと見るべきである。備中には古くから銅や硫化鉄鉱石の鉱山が存在し、鉄資源に恵まれていた 20 。また、隣国の備前では、伝統的な刀鍛冶の技術を応用して鉄砲が生産されていた可能性が指摘されている 21 。
鉄砲は、戦の勝敗を左右する最新兵器であり、その調達と運用は領主の死活問題であった 22 。政清が、①領内の鉄資源を掌握して武具生産の基盤とし、②年貢や特産品による収入を元手に、備前や、鉄砲生産の中心地であった堺・国友などから高価な鉄砲を輸入(購入)し、③そうして強化した軍事力を背景に外交交渉を有利に進める、という一連の「軍事経済システム」を運営していた可能性は十分に考えられる。彼の経済活動は、単なる商業ではなく、領国経営と軍事力維持に直結した、国人領主としての統治行為そのものであったと結論づけられる。
第三章:小田政清の家族と一族の終焉
戦国武将にとって、家族、特に婚姻は一族の存続と勢力拡大を左右する重要な戦略であった。小田政清の縁組には、彼の周到な戦略家としての一面が垣間見える。そして、彼が築き上げた備中での支配も、子の代には、より大きな歴史のうねりの中で終焉を迎えることとなる。
重層的な婚姻戦略
小田政清の婚姻政策は、内と外に向けた二重の構造を持っていた。
まず、内向きの戦略として、彼は自らの支配基盤を固めるために、家臣との結びつきを強化した。政清の妻は、平家の武将・妹尾兼康の子孫とされ、小田氏の家臣として神戸山城の城代を務めた真安重康(さねやす しげやす)の娘であった 18 。重臣の娘を正室に迎えることで、家臣団との一体感を醸成し、内部の結束を固める狙いがあったと考えられる。
一方で、外向きの戦略として、彼は周辺の有力国人との同盟関係を構築した。政清の子である六郎左衛門実康(さねやす)は、備中の有力国人であった三村氏の娘を妻に迎えている 18 。これは、当時毛利氏の傘下で備中における最大勢力となりつつあった三村氏との関係を強化し、自らの立場を安定させるための政略結婚であったことは明らかである。
このように、内部の結束と外部との同盟という、重層的な婚姻戦略を展開していた点に、政清の戦略家としてのしたたかさが見て取れる。なお、岡山県矢掛町には、現在も「小田政清夫妻の墓」とされる五輪塔が残されており、彼らがこの地に生きた記憶を今に伝えている 11 。
一族の終焉と歴史の転換
小田政清の後を継いだのは、子の小田元家(もといえ)であった 5 。元家も父の路線を継承し、毛利氏の忠実な配下として活動した。天正10年(1582年)の備中高松城の戦いや、文禄元年(1592年)からの文禄の役(朝鮮出兵)にも、毛利軍の一員として従軍している 2 。
しかし、彼らの運命を大きく変えたのは、戦場での働きではなく、天下統一を成し遂げた豊臣秀吉による新しい全国秩序の構築であった。秀吉は、全国の土地を再調査する「太閤検地」を断行し、大名の領地を再編(知行割)した。
その結果、文禄4年(1595年)、小田氏は主君である毛利氏の都合により、先祖代々の土地である備中 小田郷を離れ、安芸国(現在の広島県)へ転封(領地替え)を命じられた 5 。これにより、応安2年(1369年)の始祖・秀清の下向以来、226年間にわたって続いた備中 小田氏の在地領主としての歴史は、幕を閉じたのである。七代目当主の元家は、父祖の地を去る無念の思いを和歌に託したと伝えられている 7 。
この転封は、小田氏が何か失策を犯した結果ではない。これは、毛利氏のような大大名でさえ、豊臣政権の下でその領国支配を安堵される代わりに、配下の国人領主たちの所領を再編・整理する必要に迫られたために起こった、必然的な出来事であった。小田氏の終焉は、戦国時代を通じて地域に根を張り、半独立的な権力を誇った「国人衆の時代」が終わりを告げ、彼らが大名の家臣団に完全に組み込まれていく、歴史の大きな転換点を象徴する出来事であったと言えよう。
結論:戦国史における小田政清の歴史的評価
備中の国人領主・小田政清の生涯は、戦国時代という激動の時代を生きた地方武将の典型的な姿を示すと同時に、その中に非凡な資質と戦略性を見出すことができる、極めて興味深い事例である。
第一に、小田政清は、一度は本拠を失い、異郷へ亡命するという最大の危機に直面しながらも、10年の歳月を経て再起を果たした**「強靭な生存者」**であった。彼の不屈の精神と、復帰後に旧来の拠点に固執せず、より防御力の高い馬鞍山城へ本拠を移した合理的な判断は、敗北から学ぶことのできる優れた将であったことを示している。
第二に、彼は大国の狭間で翻弄されるだけの無力な存在ではなかった。尼子・毛利という二大勢力が激突する中で、いち早く毛利氏への帰属を決断した先見性(あるいは現実主義)、家臣や周辺勢力と結んだ重層的な婚姻政策、そして領国の経済力を背景とした軍事力の維持など、自らの意思で道を切り拓こうとする**「戦略家」**としての一面が際立っている。彼の行動は、常に一族の存続という明確な目的意識に貫かれていた。
第三に、彼の生涯は、備中という一地方を舞台としながらも、戦国時代の権力構造の力学を凝縮して見せてくれる、貴重な歴史の縮図である。彼の物語を通じて、我々は「織田信長」や「豊臣秀吉」といった英雄たちの歴史の陰で、無数の地方領主たちが繰り広げた、リアルな生存競争の実態を垣間見ることができる。大勢力への帰属のタイミング、宿敵との和睦、そして新たな主君の下でかつての敵を攻めるという皮肉な運命は、国人領主たちが置かれた複雑で過酷な現実を浮き彫りにしている。
最終的に、彼の一族は豊臣政権による全国統一という、一個人の力では抗いようのない歴史の大きな潮流の中で、二百年以上にわたる本拠地を去ることになった。これは、小田政清個人の限界というよりも、地域に根差した半独立的な国人領主という存在そのものが、新しい時代の中でその役割を終えたことを象徴している。
総じて、小田政清は、戦国史の主役として語られることはないかもしれない。しかし、彼の波乱に満ちた生涯は、大国の思惑が交錯する「境目」の地で、知力と胆力、そして戦略の限りを尽くして生き抜こうとした一人の武将の確かな足跡を我々に示してくれる。彼の存在は、戦国時代をより立体的かつ多角的に理解する上で、決して見過ごすことのできない価値を持っていると言えるだろう。
引用文献
- 備前・備中・美作戦国史-戦国通史 http://www2.harimaya.com/sengoku/sengokusi/bimu_01.html
- 新緑の旧山陽道備中堀越宿と小田氏 | 史跡散策 https://ameblo.jp/chikuzen1831/entry-12374160572.html
- おかやまの中世争乱史 - 岡山県ホームページ https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/622711.html
- 小田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E6%B0%8F
- 備中 馬鞍山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bicchu/makurayama-jyo/
- 史跡 - 矢掛の文化財 https://bunkazai.yakage-kyouiku.info/shiteibunkazai/ticp/ticp_7
- 小田(岡山県矢掛町) - すさまじきもの ~歌枕 探訪~ http://saigyo.sakura.ne.jp/oda.html
- 備中 岩屋山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bicchu/oda-iwayayama-jyo/
- 岩屋山城 小田郡矢掛町 https://ameblo.jp/inaba-houki-castle/entry-12872813768.html
- 備中猿掛城主 庄氏 http://okayamaken.fc2web.com/mabi/shousi.htm
- 神戸山城 小田郡矢掛町 | 山城攻略日記 https://ameblo.jp/inaba-houki-castle/entry-12872812536.html
- 尼子家の「御一家再興」戦争と山中幸盛 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/event/plusonline/online2.data/1kou.pdf
- 植木秀長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E6%9C%A8%E7%A7%80%E9%95%B7
- (2) 毛利氏の出雲侵攻と尼子義久の降伏 永禄5年7月 三沢氏や三刀屋氏を始めとする出雲の国衆の多くが毛利氏に帰属【史料4】 - 松江市 https://www.city.matsue.lg.jp/material/files/group/34/nakano1.pdf
- 「尼子晴久」山陰山陽8カ国の守護となり、尼子最盛期を築く! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/759
- 三村家親・元親の墓 -戦国探求 https://sengokutan9.com/sengokusiseki/okayama/Mimuraiechikamotochikahaka.html
- 備中兵乱~第3次・備中松山合戦、三村元親の自刃 - 今日は何の日?徒然日記 https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2018/06/62-98b4.html
- 真安家小田郡小田村 https://gos.but.jp/saneyasu.htm
- 治部の大輔(じぶのたいふ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B2%BB%E9%83%A8%E3%81%AE%E5%A4%A7%E8%BC%94-2047423
- 岡山県の城下町・備中高梁/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/castle-town/bittyuutakahasi/
- 宇喜多氏と備前長船・鉄砲鍛冶 http://kiwarabi.html.xdomain.jp/ukitaosafune.pdf
- 小学校社会/6学年/歴史編/戦乱の世の中と日本の統一-戦国時代・安土桃山時代 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A/6%E5%AD%A6%E5%B9%B4/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%B7%A8/%E6%88%A6%E4%B9%B1%E3%81%AE%E4%B8%96%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%B5%B1%E4%B8%80-%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%83%BB%E5%AE%89%E5%9C%9F%E6%A1%83%E5%B1%B1%E6%99%82%E4%BB%A3
- 源三位頼政の後裔山縣氏流小田氏 http://www1.megaegg.ne.jp/~yorimasa830/index.html