斎藤龍興
斎藤龍興は義龍の子で若くして美濃国主となるも、織田信長の侵攻と家臣離反で美濃を失い、流浪の末に戦死。暗愚と評されるが若年故の苦悩も。
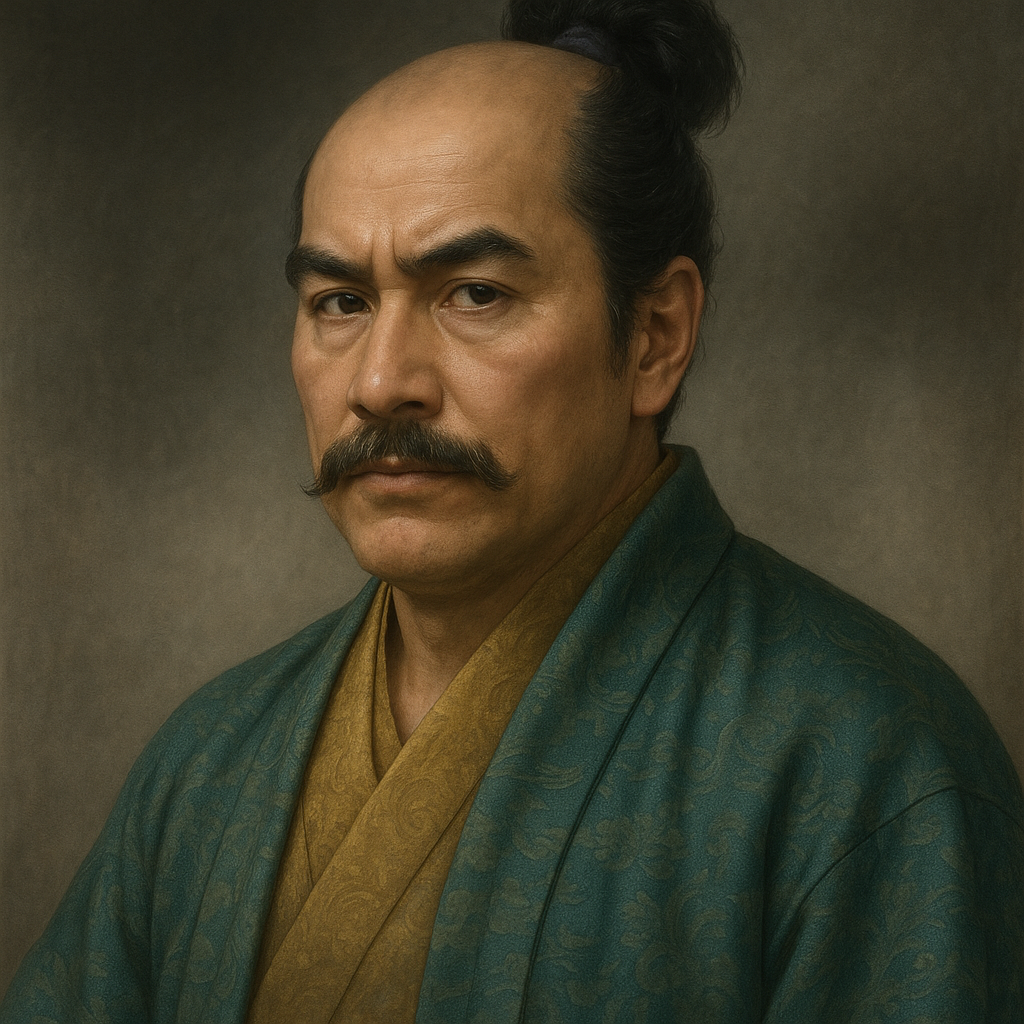
斎藤龍興:戦国末期、美濃に散った若き獅子の生涯と評価
序章
- 本稿の目的と概要
本稿では、戦国時代の武将、斎藤龍興(さいとう たつおき)の生涯と彼が生きた時代を、現存する史料と近年の研究成果に基づいて詳細に検討する。龍興は、祖父・斎藤道三、父・斎藤義龍という強烈な個性を持つ先代たちの後を継ぎ、若くして美濃国(現在の岐阜県南部)の国主となった。しかし、その治世は隣国尾張の織田信長の執拗な侵攻に晒され、内には家臣団の離反という困難を抱え、最終的には美濃を失い、流浪の末に若くして命を落とすという悲劇的な運命を辿った。
従来、龍興は酒色に溺れ、政務を顧みない「暗愚な君主」として描かれることが多かった。しかし、近年の研究では、そうした評価の背景にある史料の偏りや、若年当主が直面したであろう困難な状況を考慮し、その実像を多角的に捉え直そうとする動きが見られる。
本稿は、龍興の出自と家督相続の経緯、美濃国主としての治世における内外の情勢、織田信長との熾烈な抗争、美濃失陥後の流浪と抵抗の軌跡、そして最期と後世における評価の変遷を丹念に追うことで、斎藤龍興という人物の実像に迫ることを目的とする。特に、従来の「暗愚」という評価の妥当性、若年で大国の舵取りを任された故の苦悩、そして彼を取り巻く複雑な人間関係や政治状況が、その運命に如何なる影響を与えたのかという点にも焦点を当てて考察を進める。
第一章:斎藤龍興の出自と家督相続
- 斎藤龍興の誕生と家系
斎藤龍興は、天文17年(1548年)頃、美濃国に生を受けたとされる 1 。父は斎藤義龍(さいとう よしたつ)、祖父は「美濃のマムシ」と恐れられ、一代で美濃国主の座を掴んだ斎藤道三(さいとう どうさん)である 1 。龍興の幼名は記録に残らず、生母の顔も定かではないとされるが 1 、後に一国を背負う運命にあった。
道三と義龍の父子関係は極めて険悪であった。義龍は、弘治2年(1556年)4月、長良川の戦いにおいて父・道三を討ち取り、名実ともに美濃斎藤氏の当主となった 1 。この時、龍興はわずか8歳であったと伝えられる 1 。祖父・道三が築き上げた美濃の支配体制は、父・義龍の時代へと移行したが、その過程で生じた父子の確執と祖父の非業の死は、幼い龍興の心に大きな影を落としたであろうことは想像に難くない。道三は商人としての経験を活かし経済を重視した国造りを進めたのに対し、義龍は武断政治を好み、周辺諸国への軍事的圧力を強めようとするなど、国政の方針においても両者は対立していた 1 。こうした祖父と父の間の緊張関係は、家臣団をも二分し、斎藤家の内部に不安定要素を抱え込ませる結果となった。この複雑な家庭環境と権力闘争の記憶は、後の龍興の性格形成や統治能力に、何らかの形で影響を及ぼした可能性が考えられる。
- 生母・近江の方について
龍興の生母は、近江(現在の滋賀県)の浅井氏出身の女性で、「近江の方(おうみのかた)」または「近江局(おうみのつぼね)」と称されたと伝えられている 4 。彼女の出自については二つの説が存在する。『美濃国諸家譜』では浅井久政(あざい ひさまさ)の娘とされているが、龍興の生年(天文16年または17年)を考慮すると、大永6年(1526年)生まれとされる久政の娘である可能性は低い 4 。そのため、久政の父である浅井亮政(あざい すけまさ)の娘、すなわち久政の妹が養女として義龍に嫁いだとする説が有力視されている 4 。『系図纂要』にも浅井亮政の娘(久政の妹で養女)と記載されており、この説を補強している 4 。
生母が近江浅井氏の出身であるという事実は、後に龍興が織田信長に美濃を追われた際に、浅井長政(あざい ながまさ)を頼る重要な伏線となる。戦国時代において、婚姻を通じた同盟関係や縁戚関係は、各勢力の存亡に大きな影響を与える要素であり、母方の実家はしばしば窮地に陥った際の亡命先や支援の受け皿となり得た。斎藤氏と浅井氏の間にこのような繋がりがあったことは、当時の複雑な外交関係の一端を示している。
- 幼名、別名、官位
龍興の幼名は喜太郎(きたろう)と伝えられている 5 。通称としては刑部大輔(ぎょうぶたいふ)を名乗り、その他に右兵衛大夫(うひょうえたいふ)、また諱(いみな)として義糺(よしただ)、義輔(よしすけ)といった名も記録に見られる 5 。
官位に関しては、龍興自身が正式に叙任された記録は明確ではないものの、「刑部大輔」や「右兵衛大夫」といった呼称は、当時の武家社会において一定の社会的地位を示す官職名に由来するものであると考えられる。父・義龍は、父・道三を討った後、その正当性を高めるために足利将軍家の一門である一色氏を称し、一色左京大夫(いっしきさきょうのだいぶ)と名乗った時期がある 4 。これは、美濃の旧守護であった土岐氏よりも格上の家柄を名乗ることで、国内における自らの権威を強化しようとする意図があったとされている 4 。龍興もまた、この父の路線を継承し、「一色龍興」と称されることがある 9 。さらに、義龍の代には、家臣たちにも一色氏ゆかりの姓への改姓が見られたが、その具体的な時期が義龍の死後、龍興の治世である永禄4年(1561年)であったとする説 4 もあり、これは龍興政権初期における体制固めの一環であった可能性を示唆しており興味深い。
- 父・義龍の急逝と若年での家督相続の経緯(永禄4年/1561年)
永禄4年(1561年)5月11日、父・斎藤義龍が病により34歳という若さで急逝した 1 。これにより、龍興はわずか13歳(一説には14歳)にして斎藤家の家督を相続し、美濃国主として稲葉山城(後の岐阜城)の城主となった 1 。
父の突然の死は、若き龍興にとって計り知れない衝撃であったろう。ある記録によれば、家督相続に際し、初めて臨んだ評定の場で、側近から「主君、今は悲しんでいる場合ではございませぬ。美濃の国は今、お若き当主様の決断を待っております」と促され、必死に涙をこらえたと伝えられている 1 。父・義龍は、祖父・道三を武力で排除して美濃を掌握し、隣国・尾張の織田信長の侵攻を度々退けるなど、一定の統治能力と武威を示した人物であった 12 。その義龍の早すぎる死は、斎藤家にとって大きな打撃であり、経験の浅い龍興が強大な内外の課題に直面することを意味していた。この若年での家督相続は、その後の家臣団の動揺や、織田信長による美濃侵攻の激化を招く大きな要因の一つとなったのである。
第二章:美濃国主としての治世と内外の情勢
- 家督相続時の美濃国の政治的・軍事的状況
斎藤龍興が家督を相続した永禄4年(1561年)当時の美濃国は、決して安泰とは言えない状況にあった。父・義龍は強権的な手法で国内をまとめようとしたが、その急死により、若年の龍興がその後を継ぐことになったため、国内の動揺は避けられなかった。
* **織田信長との関係(初期の対立)**
父・義龍の代から、尾張の織田信長による美濃への侵攻は断続的に続いていた [3, 5, 13, 14]。信長にとって、美濃は上洛ルートを確保し、天下統一の足掛かりとする上で戦略的に極めて重要な地域であった。道三と信長はかつて同盟関係にあり、道三の娘である濃姫(帰蝶)が信長に嫁いでいたが [4, 15]、道三が義龍に討たれたことで、この同盟関係は事実上破綻していた。義龍の死は、信長にとって美濃攻略の絶好の機会と映った。龍興が家督を継いだわずか2日後の永禄4年5月13日には、信長は早くも美濃へ出兵している [16]。龍興の治世は、当初からこの強大な隣国との絶え間ない緊張と衝突の中に置かれることとなった。
* **浅井長政との関係**
近江の浅井長政とは、龍興の母・近江の方が浅井氏の出身であることから縁戚関係にあった [11]。この関係は、龍興にとって数少ない頼れる要素の一つであった。当初、浅井氏は斎藤氏と共同で織田氏に対抗する姿勢を見せることもあったが、戦国時代の同盟関係は常に流動的であり、各勢力の利害関係の変化によって容易に反故にされるものであった。信長もまた、妹のお市を浅井長政に嫁がせるなど [17]、浅井氏との同盟を重視しており、斎藤氏、織田氏、浅井氏の三者は、時に協力し、時に敵対するという複雑な力関係の中にあった。龍興の母方の縁は、当初は対織田の連携を期待させるものであったが、信長の巧みな外交戦略と勢力拡大の前に、その効果は限定的なものとならざるを得なかった。
* **国内の家臣団の状況(美濃三人衆、竹中半兵衛など)**
父・義龍は、長井道利ら6人の側近に政治を補佐させる新体制(六人衆)を敷いて国政の安定を図ろうとしたが [8]、その死後、龍興の若さも相まって国内の統制は揺らぎ始めた。美濃は、守護であった土岐氏の力が弱体化した後、斎藤道三による下剋上が行われた土地であり、国人領主の独立性が比較的強い地域であった [3, 18]。義龍自身も、父・道三を打倒する際には多くの家臣を味方につけたが、その統治下においても国人たちの反発に直面することがあったとされている [11]。
龍興政権を支えるべき主要家臣には、後に「西美濃三人衆」と称される稲葉良通(いなば よしみち、後の一鉄)、安藤守就(あんどう もりなり)、氏家直元(うじいえ なおもと、卜全)らがいた [19, 20, 21, 22]。彼らは元々土岐氏の旧臣でもあり、斎藤氏に対する忠誠心が絶対的なものであったとは言い難い側面があった [11]。若年の龍興が彼ら有力国人を完全に掌握することは困難であり、これが後の家臣離反の遠因となった。
また、智謀の将として名高い竹中重治(たけなか しげはる、半兵衛)も龍興に仕えていたが [10, 13, 19, 23, 24, 25]、その才能を十分に発揮できる状況ではなかったとされる。龍興政権の最大の弱点は、この家臣団をまとめ上げ、その力を結集できなかった点にあると言える。
- 治世における主要な出来事
龍興の治世は、織田信長の侵攻と、それに伴う国内の混乱に終始したと言っても過言ではない。
* **織田信長との主要な合戦**
* **森部の戦い(永禄4年/1561年5月)**: 義龍の死の直後、信長は美濃へ侵攻。龍興方はこの戦いで敗北を喫し、重臣の日比野清実や長井隼人佐(長井衛安)らが討死した [1, 8, 16]。この敗戦は、若き龍興にとって自身の無力さを痛感させられる出来事であったと伝えられている [1]。龍興政権の脆弱な船出を象徴する戦いであった。
* **新加納の戦い(永禄6年/1563年4月)**: 信長は5700の兵を率いて再び美濃に侵攻。これに対し、斎藤軍は3500の兵で迎撃した。兵力で劣る斎藤軍であったが、この戦いでは龍興の家臣・竹中半兵衛の巧みな伏兵策により、信長軍を撃退したとされる [24, 26, 27, 28, 29]。しかし、この戦功を挙げた半兵衛に対し、龍興は適切な褒賞を与えるどころか、かえって彼を疎んじたとも伝えられており、これが後の稲葉山城乗っ取り事件の一因になったという説もある [24, 26]。この逸話は、龍興の将器に疑問を投げかけるものとして語られることが多いが、後世の創作である可能性も考慮する必要がある [1, 6]。龍興自身の采配や戦術に関する具体的な記録は乏しく、この戦いにおける勝利も主に半兵衛の功績として語られている。
* **河野島の戦い(永禄9年/1566年閏8月)**: 信長が美濃国境まで進軍した際、予期せぬ木曽川の出水に遭遇し、中州である河野島(現在の岐阜県各務原市)へ退避した。この機を捉えた斎藤龍興は直ちに進軍し、織田軍は川べりまで後退して布陣する苦戦を強いられた [30, 31, 32]。この戦いの詳細は史料に乏しく不明な点が多いが [31]、信長も常に順風満帆だったわけではなく、斎藤軍が地の利や状況を活かして反撃する場面もあったことを示している。
これら一連の合戦は、斎藤氏が織田氏に対して劣勢に立たされつつも、時には局地的な勝利を収めるなど、一定の抵抗力を持っていたことを示している。しかし、信長の戦略的な圧力と、斎藤家内部の結束の乱れにより、徐々に追い詰められていく過程が読み取れる。
* **竹中半兵衛による稲葉山城乗っ取り事件(永禄7年/1564年2月)**
永禄7年(1564年)2月、龍興の治世を揺るがす重大な事件が発生する。家臣の竹中半兵衛が、舅である安藤守就らと共謀し、わずか16人(または十数人)とも言われる手勢で、龍興の居城である稲葉山城を占拠したのである [6, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35]。不意を突かれた龍興は、寝巻姿で城から逃亡したとも伝えられている [33, 34]。
この前代未聞の事件の背景には、龍興の政務に対する姿勢が大きく関わっていたとされる。龍興は酒色に溺れて遊興にふけり、斎藤飛騨守(さいとう ひだのかみ)ら特定の近習ばかりを寵愛し、半兵衛や西美濃三人衆といった経験豊富な重臣たちを疎んじたという [1, 6, 10, 13, 25, 29, 33, 34, 36]。半兵衛の行動は、こうした主君の堕落を諫めるためのものであったという説が有力である [6, 23, 24, 25, 33, 34]。また、半兵衛自身が龍興やその側近から侮辱を受けたことへの私怨、特に近習の斎藤飛騨守に対する個人的な恨みが原因であったとする説もある [37, 38, 39]。実際、城の乗っ取りの際に、半兵衛は斎藤飛騨守らを討ち取っている [36, 37]。この斎藤飛騨守は、龍興の寵愛を背景に権勢を振るったとされ、旧来の重臣層からは龍興を惑わす奸臣と見なされていた可能性が高い [36]。『信長公記』などには、飛騨守が櫓の上から半兵衛に小便をかけるという屈辱的な行為に及んだという逸話も記されており [39]、これが直接的な引き金になったとも考えられる。
半兵衛は稲葉山城を半年ほど占拠した後、龍興に城を返還し、自らは斎藤家を出奔した [6, 24, 26, 27, 28, 33]。この際、織田信長から城を明け渡すよう誘いがあったが、半兵衛はこれを拒否したと伝えられている [27, 28]。
この稲葉山城乗っ取り事件は、斎藤氏の権威を著しく失墜させ、その弱体化を内外に露呈する結果となった。龍興の君主としての指導力に対する家臣団の不信感は決定的となり、織田信長にとっては美濃攻略を一層容易にする状況を生み出した。半兵衛の真意が主家への諫言であったとしても、その行動は結果的に斎藤氏の命運を大きく縮めることになったと言わざるを得ない。
* **美濃三人衆(稲葉良通、安藤守就、氏家直元)ら家臣の離反**
竹中半兵衛による稲葉山城乗っ取り事件以降、斎藤氏の弱体化は誰の目にも明らかとなり、家臣団の動揺は頂点に達した。龍興の若さと統率力不足、特定の近習への偏愛とそれに伴う重臣の軽視、そして織田信長の度重なる侵攻と巧みな調略工作が複合的に作用し、家臣たちの心は次第に龍興から離れていった [1, 6, 11, 33]。永禄9年(1566年)頃の加納口の戦いでの敗北は、家臣たちの忠誠心をさらに揺るがせた [1]。龍興が時に酒に溺れ、家臣を過酷に罰したことも、離反を加速させる要因となったとされる [1]。
そして永禄10年(1567年)、ついに西美濃三人衆、すなわち稲葉良通(一鉄)、安藤守就、氏家直元(卜全)が、織田信長に内通し、人質を差し出してその軍門に降った [2, 6, 9, 20, 21, 22, 28, 30, 33, 40, 41, 42]。彼らは美濃の軍事・政治の中核を担う有力な国人領主であり、その離反は斎藤龍興にとって致命的な打撃となった。これにより、斎藤家の本拠地である稲葉山城は孤立無援の状態に陥り、滅亡は目前に迫っていた。この出来事は、戦国時代において国人領主の動向がいかに大名の運命を左右したかを示す典型的な事例と言える。なお、龍興に対する「暗愚」という評価は、これらの離反した家臣たちが自らの行動を正当化するために広めた可能性も否定できない [6]。
- 表1:斎藤龍興 主要家臣一覧
|
家臣名 |
通称・別名 |
主な活動・動向 |
最終的な去就(龍興との関係) |
|
稲葉良通(一鉄) |
彦六、六郎、伊予守 |
西美濃三人衆の一。土岐氏、斎藤道三・義龍に仕える。龍興の代に織田信長に内通 19 。 |
龍興を見限り、信長に降る。 |
|
安藤守就 |
伊賀守、道足 |
西美濃三人衆の一。竹中半兵衛の舅。龍興の代に織田信長に内通 19 。 |
龍興を見限り、信長に降る。 |
|
氏家直元(卜全) |
常陸守、卜全 |
西美濃三人衆の一。龍興の代に織田信長に内通 19 。 |
龍興を見限り、信長に降る。 |
|
竹中重治(半兵衛) |
半兵衛、重虎 |
龍興の家臣。稲葉山城を一時占拠し、龍興を諫めたとされる。その後、斎藤家を出奔 6 。 |
龍興に稲葉山城を返還後、出奔。後に豊臣秀吉に仕える。 |
|
遠藤慶隆 |
六郎左衛門、但馬守 |
龍興に仕える 19 。 |
詳細は不明だが、斎藤氏滅亡後は織田氏、豊臣氏、徳川氏に仕えた。 |
|
不破光治 |
河内守 |
斎藤道三の土岐氏へのクーデターに反対。義龍・龍興に仕えた後、信長に仕える 19 。 |
龍興を見限り、信長に仕える。 |
|
長井道利 |
隼人佐 |
義龍の側近(六人衆の一)。龍興の代にも重臣として活動。稲葉山城の戦いなどで防衛の指揮を執る 4 。 |
斎藤氏滅亡まで龍興に従った可能性が高い。 |
|
斎藤飛騨守 |
|
龍興の近習として寵愛を受ける。竹中半兵衛ら重臣と対立し、稲葉山城乗っ取り事件の際に半兵衛に討たれたとされる 6 。 |
稲葉山城乗っ取り事件の際に竹中半兵衛に討たれる。 |
- 表2:対織田信長 主要合戦一覧
|
年月日(西暦) |
合戦名 |
主要指揮官(斎藤軍) |
主要指揮官(織田軍) |
結果(斎藤軍から見て) |
備考(戦術的特徴や影響など) |
|
永禄4年5月(1561年) |
森部の戦い |
斎藤龍興、日比野清実、長井衛安 |
織田信長 |
敗北 |
義龍死後の織田軍の迅速な侵攻。斎藤方の重臣戦死 1 。 |
|
永禄6年4月(1563年) |
新加納の戦い |
斎藤龍興、竹中半兵衛 |
織田信長 |
勝利 |
竹中半兵衛の伏兵策により織田軍を撃退したとされる 24 。 |
|
永禄9年閏8月(1566年) |
河野島の戦い |
斎藤龍興 |
織田信長 |
織田軍苦戦(詳細不明) |
木曽川の出水により河野島に退避した織田軍を斎藤軍が攻撃 30 。 |
|
永禄10年8月(1567年) |
稲葉山城の戦い |
斎藤龍興 |
織田信長 |
敗北(落城) |
美濃三人衆の内応により織田軍が圧勝。龍興は伊勢長島へ逃亡 3 。 |
第三章:美濃失陥と流浪、抗戦
- 稲葉山城の陥落と美濃からの逃亡(永禄10年/1567年8月)
永禄10年(1567年)8月、西美濃三人衆をはじめとする有力家臣の多くが織田信長に内通したことにより、斎藤龍興の本拠地・稲葉山城は、もはや風前の灯火であった 1 。信長の軍勢は圧倒的な兵力で稲葉山城を包囲。織田軍の進撃はあまりにも迅速であり、龍興は有効な対策を講じる間もなく、城下はたちまち戦火に包まれた 33 。
『フロイス日本史』などの記録によれば、信長は夜間に兵の一部を敵の背後に回り込ませるという巧みな計略を用い、油断していた龍興軍を挟撃し、混乱に陥れたとされる 27 。城内では兵士の投降が相次ぎ、もはや抵抗する術はなかった。龍興は、祖父・道三が築き、父・義龍が守った美濃の地を失うという屈辱と、家臣たちに見捨てられた孤独感、そして自らの力不足への悔恨を胸に、わずかな供回りの者と共に舟で長良川を下り、伊勢長島(現在の三重県桑名市長島町)へと落ち延びた 1 。この時、龍興はわずか19歳または20歳であった 1 。稲葉山城の陥落は、斎藤氏による美濃支配の終焉を意味する決定的な出来事であり、龍興の指揮能力の限界と家臣団の崩壊が露呈した結果と言える。同時に、信長の巧みな調略と圧倒的な軍事力が際立つ戦いであった。
- 伊勢長島一向一揆への参加と役割
美濃を追われた龍興が最初に身を寄せたのは、伊勢長島の一向一揆勢力であった 1 。伊勢長島は、木曽三川の河口に位置する輪中地帯であり、本願寺門徒の強固な拠点として知られ、織田信長にとって最大の敵対勢力の一つであった。龍興は、この一向一揆勢力と連携することで、信長への抵抗を継続し、再起の機会をうかがおうとしたと考えられる。
龍興が長島一向一揆の中で具体的にどのような役割を果たしたかについての詳細な史料は乏しいものの、元亀元年(1570年)に本願寺顕如(ほんがんじ けんにょ)が発した織田信長打倒の檄文が長島一向一揆蜂起の大きなきっかけの一つとなっており 46 、龍興もこの反信長の流れに身を投じ、一揆勢と共に信長軍と戦ったと見られる 1 。美濃を失った龍興にとって、単独での抵抗はもはや不可能であり、他の反信長勢力との連携は必然的な選択であった。一向一揆側にとっても、元美濃国主である龍興の参加は、自らの勢力拡大や大義名分を掲げる上で利用価値があった可能性が考えられる。
- 三好三人衆との連携と具体的な活動(本圀寺の変など)
伊勢長島での抵抗も長くは続かず、龍興はその後、畿内へと活動の場を移す。永禄12年(1569年)頃には、当時畿内で織田信長と激しく対立していた三好三人衆(みよし さんにんしゅう)――三好長逸(みよし ながやす)、三好宗渭(みよし そうい、政康)、岩成友通(いわなり ともみち)――と結託した 2 。三好三人衆は、かつて畿内に強大な勢力を誇った三好長慶(みよし ながよし)の死後、織田信長の上洛によってその勢力を削がれていたが、依然として反信長の旗幟を鮮明にしていた。
龍興は、この三好三人衆と共に、永禄13年(元亀元年/1570年)1月、信長が擁立した室町幕府15代将軍・足利義昭(あしかが よしあき)を襲撃する事件(本圀寺の変、または六条合戦)に参加した 6 。これは、信長の留守を狙って義昭を排除し、信長政権の根幹を揺るがそうとする試みであったが、信長方の迅速な反撃により失敗に終わった。この本圀寺の変への参加は、龍興が単に庇護を求めるだけでなく、積極的に反信長包囲網の一翼を担い、軍事行動を起こしていたことを物語っている。
- 越前朝倉義景への臣従と客将としての待遇
三好三人衆との連携も破綻した後、龍興は新たな庇護者を求めて北陸へと向かった。まず、母・近江の方が浅井氏出身であった縁を頼り、近江の浅井長政のもとに一時身を寄せたとされる 11 。当時、浅井長政は織田信長の妹・お市を妻としていたが、後に信長と対立し、反信長勢力の中核を担うことになる。
その後、龍興は越前(現在の福井県東部)の大名である朝倉義景(あさくら よしかげ)を頼り、その客分となった 1 。朝倉氏は越前の名門であり、足利将軍家とも深い繋がりを持ち、信長包囲網が形成される中で浅井氏と共にその中心的な役割を担っていた。龍興が朝倉氏のもとでどのような待遇を受けたかについての具体的な史料は乏しいが、朝倉義景もまた反信長勢力の一角であり、元美濃国主である龍興を庇護することで、対信長戦線における自らの立場を強化し、また美濃方面への影響力を保持しようとした可能性が考えられる。
元亀元年(1570年)6月に起こった姉川の戦いでは、龍興は浅井・朝倉連合軍の一員として、自ら少数の家臣団を率いて参戦したと伝えられている 1 。この戦いで浅井・朝倉連合軍は織田・徳川連合軍に敗北を喫し、龍興の美濃奪還の夢はさらに遠のいた。朝倉氏のもとでの生活は、龍興にとって美濃回復の最後の望みを託すものであったが、朝倉義景自身も信長との対決において次第に劣勢に立たされており、龍興の夢を実現させる力はもはや残されていなかった。
第四章:最期と後世の評価
- 刀禰坂の戦いと討死(天正元年/1573年8月14日)
斎藤龍興の流浪と抗戦の生涯は、天正元年(1573年)8月、越前国刀禰坂(現在の福井県敦賀市)において終焉を迎える。この年、織田信長は浅井長政・朝倉義景を滅ぼすべく、大規模な軍事行動を開始した。まず浅井氏の小谷城を包囲し、救援に赴こうとした朝倉義景の軍勢を、信長は自ら兵を率いて迎撃した。
8月13日から14日にかけて行われた刀禰坂の戦いは、朝倉軍にとって壊滅的な敗北となった 1 。織田軍の猛追を受けた朝倉軍は総崩れとなり、多くの将兵が討ち死にした。斎藤龍興もまた、朝倉軍の一員としてこの戦いに参加しており、奮戦虚しく戦場で命を落としたとされる。享年は26(一説には25歳、あるいは27歳とも)であった 1 。
その最期については、かつて自らの家臣であった氏家直元の子、氏家直昌(またはその配下の者)によって討ち取られたという説も伝えられている 6 。もしこの説が事実であれば、かつての主君が旧臣の子によって討たれるという、戦国時代の非情さと皮肉な運命を象徴する出来事と言えるだろう。龍興の死は、斎藤道三以来の美濃斎藤氏の完全な滅亡を意味し、織田信長の天下統一事業がまた一歩前進したことを示すものであった。
- 生存説・伝説について(越中国での伝承など)
斎藤龍興の最期については、刀禰坂での戦死が通説となっているが、一方で、彼は生き延びていたとする生存説や伝説も存在する。特に越中国(現在の富山県)には、龍興に関する興味深い伝承が残されている 5 。
それによると、龍興は刀禰坂の戦いで死なず、越中国へ落ち延びて「九右ェ門」と名を変え、その地を開拓して余生を送ったという 5 。江戸時代に入った慶長16年(1611年)、この九右ェ門は家督を子に譲り、草高を持参して布市興国寺(現在の富山市)で出家し、住持となったとされる 9 。興国寺には、龍興が持参したと伝えられる鎧鞍や念持仏である木造阿弥陀如来立像が現在も残されているという 9 。そして、寛永9年(1632年)6月19日に86歳(または85歳)で示寂し、その墓は富山市経力の本誓寺の前にあると伝えられている 9 。
このような生存説は、敗軍の将や悲劇的な最期を遂げた歴史上の人物に対してしばしば見られるものであり、龍興に対する人々の同情や、その名を惜しむ気持ち、あるいは何らかの政治的意図が背景にあった可能性も考えられる。史実としての確証は低いものの、具体的な寺伝や遺品が伴うこの伝承は、地域史として非常に興味深いものであり、龍興という人物が後世の人々に与えた影響の一端を示していると言えるだろう。
- 人物像に関する逸話
斎藤龍興の人物像については、肯定的なものと否定的なものの両方が伝えられている。
* **酒色に溺れたとの評価:** 最も広く知られているのは、特に美濃国主時代の後半から稲葉山城を失う前後の時期にかけて、龍興が酒色にふけり、政務を疎かにした「暗君」「凡庸な君主」であったという評価である [1, 6, 10, 13, 25, 33, 34, 71]。この評価は、家臣の離反や美濃失陥の大きな要因として語られることが多い。
* **近習の寵愛と重臣の軽視:** 上記の評価と関連して、龍興は斎藤飛騨守ら特定の気に入りの側近(近習)のみを重用し、竹中半兵衛や西美濃三人衆といった経験豊富な重臣たちの意見に耳を貸さず、彼らを疎んじたとされる [1, 6, 13, 25, 33, 34, 36]。これが家臣団の不満を高め、最終的な離反を招いた一因と考えられている [1, 6]。
* **キリシタンへの関心:** 一方で、龍興が畿内に滞在していた時期に、キリスト教に関心を示したという記録もいくつか残っている [9]。イエズス会の宣教師ガスパル・ヴィレラと面会し、「万物の霊長たらんと創造されたのなら、なぜ人間の意志に世は容易に従わないのだろうか。こんな荒んだ世の中を一生懸命、善良に生きている者達が現世では何ら報いも受けられないのは、何故なのか」といった哲学的な問いを発したという逸話が伝えられている [72]。ヴィレラは、龍興の疑問に対して納得のいくように説明したと記録されているが、この問答の内容の高度さや、当時の龍興の年齢(若年であった)、そして置かれていた状況(流浪の身)を考えると、この逸話の信憑性については慎重な検討が必要である。宣教師側が自らの教養や布教の成果を示すために脚色した可能性も指摘されている。
これらの逸話から浮かび上がる龍興像は、単純に「暗君」と断じるには複雑な側面を持っている。特に、酒色に溺れたという評価は、織田方や離反した元家臣によって、彼らの行動を正当化するために誇張された可能性も否定できない。
- 近年の研究動向と再評価(木下聡氏の研究など)
斎藤龍興に対する従来の「暗君」「凡庸な君主」といった否定的な評価は、近年の研究において見直されつつある。特に歴史学者の木下聡氏は、その著作『斎藤氏四代 人天を守護し、仏想を伝えず』などを通じて、龍興の実像に迫る新たな視点を提示している 18 。
これらの研究では、龍興が若年で家督を相続し、内外からの強大な圧力に晒された極めて困難な状況下にあった点が強調される 1 。信長の執拗な侵攻に対し、数年間にわたって美濃を防衛し続けた事実も再評価の対象となっている 76 。
また、「酒色に溺れた」「放埒であった」といった従来の評価については、その多くが後世の軍記物語や、織田信長側の史料、あるいは龍興から離反した元家臣たちの記録に依拠しており、彼らの立場から龍興を貶めるために誇張された可能性が高いと指摘されている 1 。龍興が実際に政務を放棄していたかどうかも疑問視されており、龍興自身が発給した文書が現在1通も確認されていないことを根拠に政務放棄と見なすのは早計であり、むしろ父・義龍の代に確立された重臣たちによる合議制的な政務運営体制が機能していたため、龍興が直接指示を発する必要がなかったのではないか、という新たな解釈も提示されている 71 。
竹中半兵衛による稲葉山城乗っ取り事件についても、龍興の遊惰を諫めるためであったという通説に対し、半兵衛個人の動機や、斎藤家内部の権力闘争といったより複雑な背景があった可能性が示唆されている 71 。
これらの研究は、龍興を単に「暗君」として片付けるのではなく、彼が置かれた歴史的状況や、史料に残された記述の背景を多角的に分析し、より客観的でニュアンスに富んだ龍興像を構築しようとする試みであると言える。その結果、龍興は「信長・半兵衛の引き立て役」 75 という従来の役割から解き放たれ、彼自身の苦悩や行動原理に光が当てられつつある。
終章
- 斎藤龍興の生涯の総括と歴史的意義
斎藤龍興の生涯は、戦国時代の激動期において、名門の血を引きながらも若くして国主となり、強大な隣国・織田信長の勃興という時代の大きなうねりの中で、必死に抗いながらも最終的には敗れ去った悲劇的な武将の物語として総括できる。祖父・斎藤道三の「マムシ」と称された智謀と、父・斎藤義龍の武勇を受け継ぐことが期待されたであろう龍興であったが、13歳という若さでの家督相続は、彼にとってあまりにも重い責務であった 1 。
父・義龍の急死は、斎藤家にとって大きな権力の空白を生み、織田信長に美濃侵攻の絶好の機会を与えた。龍興は、信長の執拗な攻撃に晒されながらも、時には竹中半兵衛らの活躍によって局地的な勝利を収めるなど、数年間にわたり美濃の防衛に努めた。しかし、国内では西美濃三人衆をはじめとする有力家臣の離反が相次ぎ、家中の結束を保つことができなかった 1 。これは、龍興個人の統率力の問題だけでなく、斎藤氏の美濃支配の基盤が必ずしも盤石でなかったこと、そして信長の巧みな調略が効果を発揮したことによるものであろう。
稲葉山城を失い、美濃を追われた後も、龍興は伊勢長島の一向一揆に身を寄せ、三好三人衆と結び、さらには越前の朝倉義景を頼るなど、執拗に織田信長への抵抗を続けた 1 。その姿は、単に「暗愚」という言葉では片付けられない、最後まで再起を諦めなかった武将としての一面をうかがわせる。しかし、時代の趨勢は明らかに信長にあり、天正元年(1573年)、刀禰坂の戦いで朝倉軍と共に戦い、26歳という若さでその生涯を閉じた 1 。
後世、龍興は「酒色に溺れた暗君」という評価が一般的であったが、近年の研究では、そうした評価が織田方や離反した家臣によって作られた側面があること、そして若年当主が置かれた困難な状況を考慮する必要性が指摘されている 1 。彼が直面した内外の困難、家臣団掌握の難しさ、そして最後まで抵抗を試みた姿勢などを踏まえれば、より多角的で nuanced な理解が求められる。
斎藤龍興の敗北と斎藤氏の滅亡は、織田信長の天下統一事業における重要な画期であり、戦国時代の終焉と新たな時代の到来を象徴する出来事の一つとして歴史に刻まれている。彼の生涯は、個人の資質や努力だけでは抗うことのできない時代の大きな流れと、その中で翻弄される人間の悲劇を、現代に生きる我々に示唆していると言えるだろう。
参考文献
- 木下聡『斎藤氏四代―人天を守護し、仏想を伝えず―』ミネルヴァ書房、2020年 4
- 桑田忠親『斉藤道三』新人物往来社、1973年 4
- 太田牛一『信長公記』(関連現代語訳、解説書を含む) 4
- ルイス・フロイス『日本史』(関連書簡を含む) 27
- 『美濃国諸旧記』 4
- 『美濃国諸家譜』 4
- 『厳助往年記』 4
- 『神宮文庫所蔵文書』 97
- その他、本稿で参照した各種史料・論文については、各該当箇所にスニペットIDを記載した。
引用文献
- 斎藤龍興(さいとう たつおき) 拙者の履歴書 Vol.24〜若くして国を失いし主 - note https://note.com/digitaljokers/n/n2491f0bebbc9
- 斎藤竜興(さいとうたつおき)|Historist(ヒストリスト) https://www.historist.jp/word_j_sa/entry/033384/
- 斎藤道三の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7564/
- 斎藤義龍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E7%BE%A9%E9%BE%8D
- 斎藤龍興の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/180
- 斎藤龍興~信長に徹底抗戦した男は、ほんとうに暗愚だったのか | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4205
- 斎藤義龍の肖像画、名言、年表、子孫を紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/178
- 父を討ち、信長の前に立ちはだかった!マムシの子・斎藤義龍の数奇な生涯に迫る https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/80404/
- 斎藤龍興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E9%BE%8D%E8%88%88
- さいとう - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/saito.html
- 明智光秀と斎藤龍興ーーあるいは越前でニアミス? - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2020/09/20/100000
- 斎藤義龍は何をした人?「毒をもって毒を制す、マムシの息子は父・道三を殺した」ハナシ https://busho.fun/person/yoshitatsu-saito
- 昔人の物語(110) 竹中半兵衛『「義」もある軍師』 | 医薬経済オンライン https://iyakukeizai.com/beholder/article/2090
- 斎藤龍興(さいとうたつおき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%96%8E%E8%97%A4%E9%BE%8D%E8%88%88-68114
- 美濃のマムシと呼ばれた男、斎藤道三。恐るべき下剋上の真実とは - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/76374/
- 美濃攻め―軽海編 - FC2WEB http://tenkafubu.fc2web.com/mino/htm/west.htm
- 『明智軍記』(第9話)|【note版】戦国未来の戦国紀行 https://note.com/senmi/n/n6a6eb1151009
- おまけ 美濃守護代・斎藤家の歴史 - 輝きの不如帰 〜細川藤孝に転生したので金の力とハッタリ外交で室町幕府を再興して将軍を我がものにする〜(夏樹とも) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054894224985/episodes/1177354054896823887
- 斎藤龍興の家臣 - 歴史の目的をめぐって https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-11-saito-tatsuoki-kashin.html
- 織田信長公三十六功臣 | 建勲神社 https://kenkun-jinja.org/nmv36/
- 稲葉一鉄(イナバイッテツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A8%B2%E8%91%89%E4%B8%80%E9%89%84-15441
- 【理文先生のお城がっこう】歴史編 第43回 織田信長の居城(岐阜城1) https://shirobito.jp/article/1443
- 竹中半兵衛 名軍師/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/90096/
- 竹中半兵衛は何をした人?「稲葉山城を16人で奪った天才軍師が秀吉を出世させた」ハナシ https://busho.fun/person/hanbee-takenaka
- センゴク - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%82%AF
- 新加納の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%8A%A0%E7%B4%8D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 稲葉山城の戦いとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A8%B2%E8%91%89%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 稲葉山城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E8%91%89%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- まるで婦人のような優男! 織田信長が惚れ込んだ戦国時代の天才軍師「竹中重治」の逸話【前編】 https://mag.japaaan.com/archives/233775
- 第六十九話 斎藤龍興の裏切り - 長政記~戦国に転移し、滅亡の歴史に抗う(スタジオぞうさん) https://kakuyomu.jp/works/16818093092828939670/episodes/16818622171570398206
- 河野島の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 意外と負けていた…織田信長の「敗北3パターン」 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/7980
- 稲葉山城の戦い古戦場:岐阜県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/inabayamajo/
- 織田信長も失敗した難攻不落の城を1日で?若き竹中半兵衛が稲葉山城を乗っ取った驚きの理由 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/104953/
- chapter_2_s.pdf - 岐阜市 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/148/chapter_2_s.pdf
- 戦国異聞 池田さん - 浅井家との同盟話 https://ncode.syosetu.com/n1183ep/30/
- まるで婦人のような優男! 織田信長が惚れ込んだ戦国時代の天才 ... https://mag.japaaan.com/archives/234016
- 竹中半兵衛の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7491/
- 竹中半兵衛と黒田官兵衛―伝説の軍師「羽柴の二兵衛」とは - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/1753
- 安土桃山時代と江戸町人文化についての考察 https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/record/10387/files/kdoc_k_00037_01.pdf
- 岐阜城の歴史/ホームメイト https://www.touken-collection-kuwana.jp/mie-gifu-castle/gifu-castle/
- 斎藤龍興/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/toyotomi-kyoudai/saitou-tatsuoki/
- '稲葉山城の戦い'~『戦乱』再現 記録~ | 旧「君主」エナ元在住ゾノヤスのブログ https://ameblo.jp/zonoyasu/entry-12660775626.html
- 長島一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86
- 長島一向一揆古戦場:三重県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/nagashima/
- 新桑名市誕生10周年記念シンポジウム「戦国・織豊期@桑名」資料集(PDF:3074KB) https://www.city.kuwana.lg.jp/documents/11574/symposium10.pdf
- 信長にみる『孫子』の兵法|Sakura - note https://note.com/sakura_c_blossom/n/nbca5e12f8bac
- 氏家卜全(うじいえ ぼくぜん/氏家直元) 拙者の履歴書 Vol.302~三人衆から織田への転身 https://note.com/digitaljokers/n/nd79d58d944ac
- 問題1 - 家康公検定 https://ieyasukou.jp/iwswps/wp-content/uploads/2021/08/c3d58bd968ce146e8c7b4de55c00ce7a.pdf
- 史実で辿る足利義昭上洛作戦。朝倉義景との蜜月、信長への鞍替え。でも本命は上杉謙信だった? 【麒麟がくる 満喫リポート】 https://serai.jp/hobby/1007630
- 細川藤孝~「文武両道」の男は、かくして戦国乱世を生き抜いた | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/7862
- 戦国の世と丹波 https://www.tanba-mori.or.jp/wp/wp-content/uploads/h25tnb.pdf
- 日本史/安土桃山時代 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/period-azuchimomoyama/
- 日根野弘就(ひねの ひろなり) 拙者の履歴書 Vol.304~三代に仕えし美濃武士 - note https://note.com/digitaljokers/n/nc3aee53efd48
- 永禄〜天正年間における摂関家内部対立の様相 近衛前久の政治闘争を中心として https://oujjas.com/wp-content/uploads/2023/02/OUJJAS_2022_02_102-109.pdf
- 中公新書 - 中央公論新社 https://www.chuko.co.jp/mokuroku/shinsho_mokuroku_2025.pdf
- 戦国時代 (日本) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
- 敗 戦 直 後 の 京 都 民 主 戦 線 - 京都大学学術情報リポジトリ https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/73001/1/KJ00000077646.pdf
- 織田信長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7
- センゴクとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%82%AF
- えちぜん年代記|越前町 織田文化歴史館 https://www.town.echizen.fukui.jp/otabunreki/panel/29.html
- 第一章 前田利家と家族 - 近世加賀藩と富山藩について http://kinseikagatoyama.seesaa.net/article/364357863.html
- 問題1 今回の検定テーマは「家康公の平和外交 https://ieyasukou.jp/pdf/ieyasukoukentei_2022mondai-kaitoukaisetsu.pdf
- 勉強会概要2 - 高崎史志の会 https://www.ne.jp/asahi/histrian/takasaki/new1026.html
- 千葉貞胤 https://chibasi.net/souke16.htm
- 福井県文書館研究紀要 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/08/2020bulletin/images/all.pdf
- 明智光秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80
- 是非に及ばず http://www.tokugikon.jp/gikonshi/288/288toku_kiko.pdf
- まえがき - ハロー通訳アカデミー https://hello.ac/historytext.pdf
- 歴史の目的をめぐって 斎藤龍興 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-11-saito-tatsuoki.html
- 斎藤氏四代:人天を守護し、仏想を伝えず (ミネルヴァ日本評伝選 205) | 木下 聡 |本 https://www.amazon.co.jp/%E6%96%8E%E8%97%A4%E6%B0%8F%E5%9B%9B%E4%BB%A3-%E4%BA%BA%E5%A4%A9%E3%82%92%E5%AE%88%E8%AD%B7%E3%81%97%E3%80%81%E4%BB%8F%E6%83%B3%E3%82%92%E4%BC%9D%E3%81%88%E3%81%9A-%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%83%B4%E3%82%A1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%A9%95%E4%BC%9D%E9%81%B8-%E6%9C%A8%E4%B8%8B-%E8%81%A1/dp/4623088081
- 斎藤龍興とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%96%8E%E8%97%A4%E9%BE%8D%E8%88%88
- 斎藤道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E9%81%93%E4%B8%89
- 木下聡『斎藤氏四代 人天を守護し、仏想を伝えず』 | 実以のブログ https://ameblo.jp/sumacoemi/entry-12633858947.html
- 斎藤氏四代 - ミネルヴァ書房 ―人文・法経・教育・心理・福祉など ... https://www.minervashobo.co.jp/book/b496812.html
- 「斎藤氏四代」書評 道三はいつ「マムシ」になったか|好書好日 https://book.asahi.com/article/13325196
- 美濃斎藤氏 http://www.iwata-shoin.co.jp/bookdata/ISBN978-4-87294-891-2.htm
- 斎藤氏四代 : 人天を守護し、仏想を伝えず - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB2969317X
- 第3章 史跡等の現状 - 岐阜市 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/558/seibi3.4s.pdf
- 平成27年度 国際日本文化研究センター外部評価委員会 外部評価報告書 https://www.nichibun.ac.jp/ja/uploads/pdf/gaibuhyouka27.pdf
- 第3章 岐阜城跡の調査 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/558/hozonkatuyou345.pdf
- Proceedings of the 13th International Symposium on Japanese Language Education and Japanese Studies - 香港日本語教育研究会 https://www.japanese-edu.org.hk/PDF/Proceedings_final.pdf
- 中国研究月報 | 中国研究所Homepage https://www.institute-of-chinese-affairs.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%9C%88%E5%A0%B1
- 「情報処理」創刊号からの総目次 - 情報処理学会 https://www.ipsj.or.jp/magazine/contents_m.html
- 研究者詳細 - 佐藤 滋 https://w-rdb.waseda.jp/html/100002497_ja.html
- 國學院大學研究開発推進機構 日本文化研究所年報 https://www.kokugakuin.ac.jp/assets/uploads/2022/03/AR14-IJCC.pdf
- 豊臣秀吉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89
- 『斎藤龍興』とは?織田信長に美濃を奪われた哀しきボンクラ戦国武将!!【麒麟がくる】 https://www.youtube.com/watch?v=MbyluSCaISU
- 「訳す事」と「解釈する事」-『信長公記』「首巻」の現代語訳を終えて - note https://note.com/senmi/n/nf4165266369d
- 犬山城を中心に信長の足跡をたどってみたら、美濃攻略の戦略が見えた! https://www.takamaruoffice.com/inuyama-jyo/nobunaga-strategy/
- 織田信長【美濃攻略】斎藤龍興から稲葉山城を奪い美濃を平定。北伊勢も攻略。 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=W1nkANjjArs
- 歴史の目的をめぐって 豊臣秀吉 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-20-toyotomi-hideyosi.html
- なにわ・大阪文化遺産学研究センター 2006 - 関西大学 https://www.kansai-u.ac.jp/Museum/naniwa/publication/book02.pdf
- DESCRIPTIO. - 岐阜市 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/148/chapter_3_s.pdf
- 1568年 – 69年 信長が上洛、今川家が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1568/
- 特別展「Gifu信長展」(2017年7月16日) | 城めぐりん https://ameblo.jp/hiibon33/entry-12294737319.html
- 斎藤義龍とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%96%8E%E8%97%A4%E7%BE%A9%E9%BE%8D