植木秀長
植木秀長は戦国時代の備中国の国人領主。細川・尼子・三村・宇喜多と主君を変え、淀堤の戦いや佐井田城の攻防で活躍。激動の乱世を生き抜いた典型的な地方武将である。
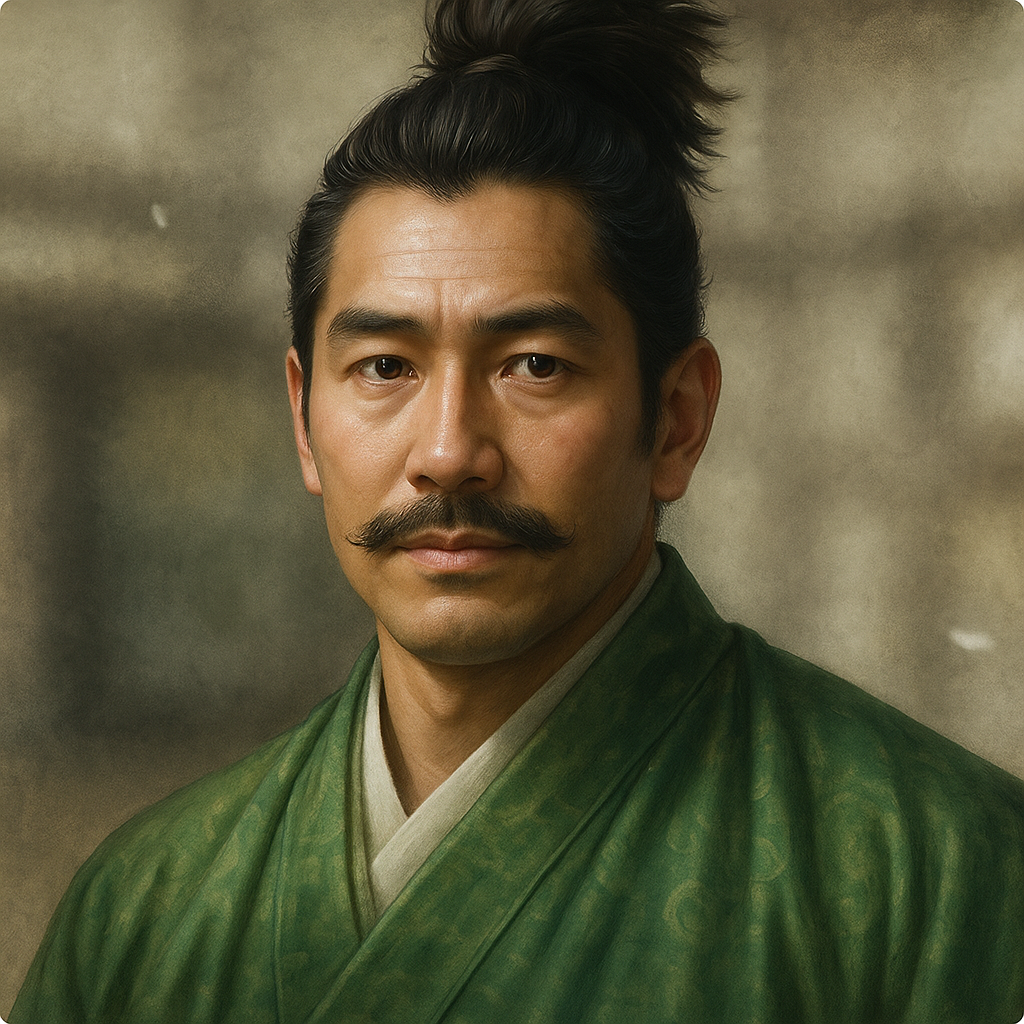
戦国武将・植木秀長の実像
序章:戦国乱世に生きた備中の国人、植木秀長
本報告書は、戦国時代の備中国(現在の岡山県西部)において活動した国人領主、植木秀長(うえき ひでなが)について、現存する史料に基づき、その生涯、事績、そして彼が生きた時代の特質を詳細に明らかにすることを目的とする。植木秀長は、備中国の呰部城主(あざえじょうしゅ)、後に佐井田城主(さいだじょうしゅ)としてその名が見える武将である 1 。彼の名は、豊臣秀長や上杉謙信といった戦国時代を代表する著名な大名とは異なり、一般には広く知られていないかもしれない。しかしながら、彼は地方史において、特に備中地域の戦国史を語る上で重要な足跡を残した人物と言える。
秀長が生きた戦国時代の備中国は、東の尼子氏、西の毛利氏、そして地元有力者の三村氏や、後に備前国から勢力を伸長してくる宇喜多氏など、複数の有力大名の勢力が複雑に入り乱れ、絶えずその影響下に置かれた地域であった。このような状況下で、秀長をはじめとする備中の国人領主たちは、自らの所領と一族の存続を賭けて、時には連携し、時には敵対し、またある時には強大な勢力に帰属するという、困難かつ流動的な選択を迫られ続けることとなった。植木秀長の生涯を追うことは、まさにそうした戦国乱世の縮図を垣間見ることに他ならない。
以下に、植木秀長の主要な事績をまとめた略年表を掲げる。
表1:植木秀長 略年表
|
和暦 |
西暦 |
年齢 (推定) |
主要な出来事 |
典拠 |
|
明応3年 |
1494年 |
0歳 |
生誕(推定) |
1 |
|
永正8年8月 |
1511年 |
18歳 |
淀堤の戦いに父・庄資信の代官として初陣。三好之長に味方し、大内義興軍と戦い一番槍の功名を挙げる。 |
1 |
|
天文2年 |
1533年 |
40歳 |
尼子晴久の備中侵攻に対し、庄為資らと共に抵抗。尼子方の上野頼氏が守る備中松山城を攻め、頼氏を討つ。 |
1 |
|
天文18年 |
1549年 |
56歳 |
福田神社に大銅鐸を寄進。銘に「呰部城主植木下総守」とあり、この頃は呰部城を本拠としていたことがわかる。 |
1 |
|
天文21年 |
1551年 |
58歳 |
室町幕府13代将軍足利義輝の側近・細川藤孝より、前年に戦で得た所領の安堵を受ける。この頃、中央には尼子晴久の家臣と認識されていた可能性がある。 |
1 |
|
天文21年 |
1552年 |
59歳 |
矢掛合戦勃発。三村・毛利連合軍と庄為資ら反毛利勢力が衝突。庄氏の勢力が大幅に衰退する。秀長はすぐには三村氏に臣従しなかったとみられる。 |
1 |
|
天文年間末頃以降 |
1550年代後半以降 |
- |
佐井田城を築城(推定)。 |
1 |
|
永禄10年 |
1567年 |
74歳 |
明善寺合戦。三村元親方として宇喜多直家軍と戦うも敗北。佐井田城に籠城後、宇喜多氏に降伏し鞍替えする。 |
1 |
|
永禄12年11月-12月 |
1569年 |
76歳 |
佐井田城の戦い。三村元親・毛利元清らの連合軍に佐井田城を包囲される。宇喜多直家からの援軍(戸川秀安ら)を得てこれを撃退し、穂井田実近を討ち取る。 |
1 |
|
永禄12年以降 |
1569年以降 |
76歳以降 |
佐井田城の戦いの後、史料から名が見えなくなり、まもなく死去したと推測される。嫡子・秀資が佐井田城主となる。 |
1 |
第一章:植木氏の出自と秀長の登場
第一節:植木氏のルーツと庄氏との関係
植木氏の出自を辿ると、その源流は関東の武士団である武蔵七党の一つ、児玉党に遡るとされ、室町時代には備中守護代も務めた名門、庄氏の支族にあたると考えられている 1 。近年の研究では、植木秀長の父は庄氏北家の庄資信(しょう すけのぶ、庄藤右衛門尉とも)であり、この資信が備中国呰部庄(あざえのしょう)の植木(現在の岡山県真庭市植木)を領有し、「植木殿」と称されていた。そして、その子である秀長の代から、領地の名を冠して「植木」を正式な姓として名乗るようになったとする説が有力視されている 1 。
この姓の変更は、単に庄氏という広範な一族からの分立を示すだけでなく、より深い意味合いを持つと考えられる。戦国時代において、武士が自らの本拠地名を姓として名乗る行為は、その土地に対する排他的な支配権を主張し、在地領主としてのアイデンティティを内外に明確に示す意図が含まれていた。秀長が「植木」を名乗ったことは、彼が「植木」の地を核とする独自の勢力圏を確立し、他の庄氏一族とは異なる主体性を持った領主として自立しようとした意志の表れと解釈できよう。これは、当時の社会において、分家や新興の勢力が、旧来の権威や本家筋から独立し、自らの力で勢力を築き上げていく過程でしばしば見られた現象の一例と言える。
なお、『備中府志』などの史料には、植木氏の系譜として清和源氏武田氏の流れを汲むとの記述も見られる。例えば、武田信光の子・信快を植木氏の祖とする系図が示されているが 2 、これが備中の植木秀長の家系に直接繋がるものであるか否かについては、慎重な検討を要する。しかし、これらの記述は、戦国期には多様な出自を持つ家系が「植木」という姓を名乗っていた可能性を示唆しており、その複雑な様相を伝えている。
第二節:秀長の生年と初陣
植木秀長の生年は、明応3年(1494年)と推定されている 1 。彼が歴史の表舞台に初めて登場するのは、永正8年(1511年)8月の淀堤(よどづつみ)の戦いである 1 。この時、秀長は18歳であったとされ、父・庄資信の代官として出陣し、細川澄元方に与した三好之長(みよし ゆきなが)に味方し、管領細川高国を支援する大内義興の軍勢と戦った。この戦いで秀長は一番槍の功名を挙げたと伝えられている 1 。
この淀堤の戦いは、当時の畿内における細川京兆家の内紛(澄元と高国の対立)に、周防の大内義興や阿波の三好氏といった有力者が介入した大規模な武力衝突であった。備中の国人である庄氏、ひいては植木氏がこの戦いに参加している事実は、彼らが細川京兆家と何らかの主従関係、あるいは協力関係にあり、その影響下で畿内の政争にも深く関与していたことを示している。また、父・資信は在京賄領として和泉国(現在の大阪府南部)にも拠点を有しており、そこを足掛かりとしてこの戦いに参じたものと見られている 1 。このことは、庄氏(植木氏)が単に備中の一地方領主にとどまらず、畿内にも一定の足場を持ち、中央の政治動向とも無縁ではなかったことを物語っている。18歳という若さで父の代官として出陣し、武功を立てたという記録は、秀長が早くから武将としての頭角を現していたことを示唆している。
第二章:備中における勢力争いと秀長の動静
第一節:尼子氏の備中侵攻と植木氏の対応
畿内での初陣から約20年後の天文2年(1533年)、出雲国を本拠とする尼子晴久(あまご はるひさ)が備中へ侵攻を開始すると、植木秀長はこれに直面することとなる 1 。この時、秀長は同じく備中の有力国人である庄為資(しょう ためすけ)らと連携し、尼子氏の勢力拡大に抵抗する姿勢を示した。具体的には、尼子方に与した上野頼氏(うえの よりうじ)が守る備中松山城を攻撃し、頼氏を討ち取った。さらに、秀長の弟である若林資行(わかばやし すけゆき)も大松山(おおまつやま)を攻略し、上野右衛門を討ったと記録されている 1 。
この時点における植木氏の行動は、外部勢力である尼子氏の侵攻に対し、地域の他の国人たちと協力して自律性を保とうとする、国人領主としての典型的な対応と言えるだろう。自らの所領を守り、備中における発言権を維持することが、彼らの最大の目的であったと考えられる。この戦いの結果、備中松山城は庄為資が、猿掛城(さるかけじょう)は穂井田実近(ほいだ さねちか)が領することとなった 1 。
第二節:三村氏の台頭と庄氏の衰退
しかし、備中を巡る情勢は尼子氏の侵攻だけでは終わらなかった。安芸国の毛利元就(もうり もとなり)の支援を受けた備中成羽の三村家親(みむら いえちか)が急速に勢力を拡大し始めると、それまで尼子方として一定の勢力を保っていた庄為資との間で対立が先鋭化する 1 。そして天文21年(1552年)、ついに矢掛合戦(やかげかっせん)が勃発し、三村・毛利連合軍と、庄為資を中心とする反毛利勢力(これには植木氏も含まれていた可能性がある)が激しく衝突した。緒戦こそ庄氏方が勝利を収めたものの、次第に三村・毛利連合軍の優勢が明らかとなり、庄為資らは追い詰められ和睦に至った 1 。
この和睦の結果は、庄氏にとって極めて厳しいものであった。和睦の条件として、猿掛城には三村家親の長男である荘元祐(しょう もとすけ、穂井田実近の養子となる)が入り、備中松山城は名目上は庄為資の持城とされたものの、実質的には三村家親が入城し、今後の対尼子戦を見据えつつ庄一族の動きを監視する体勢がとられた。これにより、草壁庄(くさかべのしょう)やその周辺に勢力を持っていた庄一族の多くが三村氏の指揮下に組み込まれ、庄氏全体の勢力は大幅に衰退することとなった 1 。
このような状況下で、植木秀長の立場は複雑であった。矢掛合戦後の庄氏一族の多くが三村氏の影響下に置かれた一方で、秀長自身はすぐには三村氏に臣従しなかった可能性が示唆されている。天文21年(1551年)10月5日には、室町幕府13代将軍足利義輝の側近である細川藤孝(ほそかわ ふじたか、後の幽斎)より、前年の天文20年(1550年)に戦によって獲得した700貫文の所領について安堵を受けている記録がある 1 。この時期、秀長は備中を含む8ヶ国の守護となっていた尼子晴久の家臣であると中央(室町幕府)にも認識されていたようである。また、天文23年(1554年)8月の時点でも、植木氏と縁の深い大森神社が尼子誠久(あまご さねひさ、晴久の子)から寄進を受けていることから 1 、依然として尼子氏との繋がりを維持していたことが窺える。
これらの事実は、秀長が周囲の庄一族とは一線を画し、一定の自立性を保とうと苦心していたことを示している。彼は、強大化する三村氏の圧力に抗しつつ、依然として西国に大きな影響力を有していた尼子氏との関係や、室町幕府という中央の権威を背景に、自らの立場を有利にしようと多角的な外交戦略を展開していたのかもしれない。しかし、その後、尼子氏の勢力が著しく衰退していくと、植木氏も最終的には三村氏の傘下に入らざるを得なくなったと考えられている 1 。この一連の動きは、戦国時代の国人領主が、めまぐるしく変化する大勢力のパワーバランスの中で、いかに巧みに、そして必死に立ち回り、自領と一族の存続を図ったかを示す好例と言えるだろう。
第三章:宇喜多氏への帰順と佐井田城
第一節:三村氏からの離反と宇喜多氏への臣従
三村氏の支配下に入った植木秀長であったが、その関係は長くは続かなかった。永禄10年(1567年)、備前国で急速に台頭してきた宇喜多直家(うきた なおいえ)と、備中を掌握していた三村元親(みむら もとちか、家親の子)との間で明善寺合戦(みょうぜんじかっせん)が勃発する。この戦いに、秀長は三村方として参戦したものの、三村軍は宇喜多軍に大敗を喫した 1 。
敗戦後、秀長は自らの本拠である佐井田城に籠城したが、宇喜多直家の弟・宇喜多忠家(うきた ただいえ)が率いる9,000とも言われる大軍に包囲されるに至り、ついに降伏。これを機に、秀長は三村氏から離反し、宇喜多氏へと鞍替えすることとなった 1 。この決断は、明善寺合戦における三村氏の敗北と宇喜多氏の圧倒的な力の差を目の当たりにし、もはや三村氏に将来はないと判断した結果であろう。自領と一族の保全を第一に考えれば、より強大な勢力に帰順することは、戦国武将にとって合理的な選択であり、秀長のこの行動もまた、乱世を生き抜くための冷徹な現実認識に基づくものであったと言える。
この時期、秀長は新たに佐井田城を築き、以後の植木一族の本拠地としたとされるが、その正確な築城時期については諸説あり、後述する 1 。
第二節:佐井田城の攻防(永禄12年)
宇喜多氏に帰順した植木秀長であったが、それによって平穏が訪れたわけではなかった。明善寺合戦での雪辱を期す三村元親は、毛利氏に援軍を要請。永禄12年(1569年)11月、毛利元清(もうり もときよ、元就の四男)や熊谷信直(くまがい のぶなお)らを加えた連合軍を率いて、宇喜多方の重要拠点となっていた佐井田城の奪還を試みたのである 1 。
佐井田城は三村・毛利連合軍の猛攻を受け、城内では兵糧が欠乏するなど、植木秀長は絶体絶命の窮地に立たされた。この危機的状況を打開すべく、秀長は夜陰に紛れて城を脱出させた嶺本与一兵衛(みねもと よいちべえ)を使者として、主君である宇喜多直家に緊急の援軍を要請した 1 。
この要請に応え、宇喜多直家は重臣の戸川秀安(とがわ ひでやす)を救援軍の大将として派遣した。同年12月、戸川秀安率いる宇喜多の援軍は佐井田城を包囲する三村・毛利連合軍と激戦を繰り広げた。この戦いで宇喜多軍は目覚ましい勝利を収め、毛利方の勇将であった穂井田実近(先の猿掛城主、荘元祐の養父)を討ち取り、総大将の三村元親をも負傷させて撤退させるという大きな戦果を挙げた 1 。
この佐井田城の攻防戦は、いくつかの重要な点を示している。第一に、佐井田城が備中北部における戦略的要衝であったこと。第二に、植木氏が宇喜多氏にとって、毛利・三村勢力に対する防衛線を構築し、備中への影響力を確保する上で、支援する価値のある存在と認識されていたことである。秀長にとっては、宇喜多氏の迅速かつ的確な救援がなければ、落城は免れなかったであろう。この勝利は、宇喜多氏の勢力拡大と、植木氏の宇喜多家中における立場を強固にする上で、大きな意味を持つものであった。
第三節:佐井田城の築城時期について
植木秀長が本拠とした佐井田城の築城時期については、明確な定説がなく、いくつかの説が存在する。軍記物である『西国太平記』には、秀長が永正14年(1517年)に佐井田城を築いたとの記述が見られる 1 。しかし、この記述を裏付ける同時代の史料は確認されていない。
むしろ、より信頼性の高い史料からは、異なる時期が示唆される。天文18年(1549年)、秀長が地元の福田神社に大銅鐸を寄進した際の銘文には、「呰部城主植木下総守」と記されている 1 。この事実は、天文18年の時点では秀長の本拠地が依然として呰部城であり、佐井田城はまだ築かれていなかったか、あるいは主要な拠点ではなかった可能性が高いことを示している。
これらのことから、佐井田城の実際の築城、あるいは植木氏の本拠地としての整備は、早くとも天文年間末頃(1550年代半ば以降)から永禄年間(1558年~1570年)にかけての時期であったと推測するのが妥当であろう 1 。 3 の記述によれば、佐井田城は「戦国時代に庄氏の一族植木秀長、孫下総守秀資へと受け継がれ」たとあり、その重要性について「備中北部攻防の中心城で、津々の加葉山城と連携し、要害堅固な備中三名城のひとつ」と高く評価されている。
佐井田城への本拠地移行の背景には、当時の備中における勢力図の激変が深く関わっていると考えられる。尼子氏の勢力後退、三村氏の台頭、そしてそれに続く宇喜多氏の備中進出といった目まぐるしい状況の変化の中で、秀長は新たな脅威に対応し、あるいは新たな主君となった宇喜多氏との連携をより強固にするために、従来の呰部城よりも戦略的に優位な地点に新たな拠点として佐井田城を築き、そこへ移った可能性が考えられる。城郭の選定と築城は、国人領主の戦略的思考と、彼らが置かれた軍事的・政治的環境を反映するものであり、佐井田城の築城もまた、植木秀長の生存戦略の一環であったと言えるだろう。
第四章:植木秀長の晩年と歴史からの退場
永禄12年(1569年)の佐井田城の戦いにおいて、宇喜多氏の援軍を得て三村・毛利連合軍を退けるという大きな軍功を立てた植木秀長であったが、この戦いを最後に、彼の名は各書物から見られなくなる 1 。
その後の植木氏の動向としては、秀長の嫡子とされる植木秀資(うえき ひですけ、 3 では「孫下総守秀資」と記されているが、 1 や 1 では嫡子とされている)が佐井田城主として歴史の記録に現れるようになる 1 。このことから、秀長は佐井田城の戦いの後、ほどなくして死去したと推測されている 1 。
『備中府志』からの引用を含む 2 の記述には、「秀長は三好長基に加勢し、淀堤の合戦に大内衆を破る。功をもって水田荘を賜う。その子秀資は浮田氏に属し、また尼子氏に属し、毛利氏に攻められて雲州に走る」とある。この「秀資」が秀長の嫡子と同一人物であるならば、彼のその後の動向の一端を示していることになる。宇喜多氏に属した後、何らかの理由で尼子氏に再び属し、最終的には毛利氏の攻撃を受けて出雲国へ逃れたという経緯は、依然として植木氏が厳しい状況下に置かれ続けたことを示唆している。ただし、帰属勢力が複数記されており、その時期や具体的な経緯については、さらなる史料の検討が必要である。
植木秀長の最期に関する具体的な記録、例えば死因や正確な没年などが不明であることは、戦国時代の地方武将の研究においてしばしば直面する典型的な困難さを示している。中央の著名な大名とは異なり、地方の国人領主に関する記録は散逸しやすく、その生涯の全貌を詳細に描き出すことは容易ではない。秀長が佐井田城の戦いという大きな軍事的成功の直後に歴史の表舞台から姿を消すという事実は、戦国の世の過酷さや、国人領主という立場の脆弱さを象徴しているかのようでもある。彼の死によって、植木氏が備中北部に築いた一定の勢力も、新たな局面を迎えることになったであろう。
第五章:植木秀長の歴史的意義と評価
植木秀長の生涯を概観すると、いくつかの歴史的意義と評価点が浮かび上がってくる。
第一に、彼は戦国時代の備中国という、大勢力の狭間に位置する戦略的要衝において、激動の時代を生き抜いた典型的な国人領主であったと言える。その生涯は、細川氏との関わりから始まり、尼子氏への抵抗と一時的従属、三村氏(およびその背後の毛利氏)への帰属、そして最終的には宇喜多氏への鞍替えという、目まぐるしい帰属勢力の変遷を辿った。これは、特定の強力な後ろ盾を持たない国人領主が、自領と一族の存続を図るために、絶えず周囲の情勢を読み、時には危険を冒してでも最も有利な選択を模索し続けた結果であり、当時の多くの国人領主に見られた行動様式を体現している。彼の選択は、日和見主義と断じるのは容易いが、むしろ限られた選択肢の中で最善を尽くした生存戦略と評価すべきであろう。
第二に、軍事指揮官としての側面も無視できない。18歳での初陣(淀堤の戦い)における一番槍の功名や、尼子方の上野頼氏を討った戦い、そして晩年の佐井田城の攻防戦で見せた籠城戦の指揮と宇喜多氏への的確な救援要請など、武将としての能力も有していたことが史料から窺える。特に佐井田城の戦いでは、宇喜多氏の援軍を得たとはいえ、毛利・三村という強大な連合軍を退けたことは、彼の武略と将器を示すものと言えよう。
第三に、植木秀長に関する研究は、史料的な限界という課題を抱えている。彼の生涯の重要な局面に関する記録は存在するものの、それらは断片的であり、合戦と合戦の間の具体的な動向や、領国経営といった内政面の手腕、あるいは彼個人の人物像を詳細に伝える史料は乏しい。特に晩年から最期にかけての記録がほとんど残されていないことは、その全貌解明を困難にしている。これは、戦国時代の地方武将研究に共通する課題であり、中央集権的な記録システムが未発達であった当時の状況を反映している。しかし、逆に言えば、このような「記録の少なさ」自体が、戦国期における地方権力のあり様や、歴史叙述における中央と地方の格差を考える上での一つの論点ともなり得る。
今後の新たな史料の発見や、周辺地域の史料との比較検討、考古学的調査の進展などによって、植木秀長という一人の武将、そして彼が率いた植木一族の実像が、より詳細に明らかになる可能性は残されている。
終章:結論
植木秀長は、戦国時代の備中国において、その生涯を通じて激動の渦中に身を置き、目まぐるしく変わる勢力図の中で、時には巧みな外交交渉を、時には武力による抵抗と帰順を繰り返しながら、自らの所領と一族の存続を図った国人領主であった。彼の名は全国的な知名度こそ高くないものの、備中という特定の地域史においては、戦国乱世の厳しさと複雑さを象徴する人物として、重要な位置を占めている。
彼の行動は、細川氏、尼子氏、三村氏(毛利氏)、そして宇喜多氏という、次々と現れる強大な勢力との関係性の中で規定され、その都度、生き残りのための最適な道を選択しようとした苦闘の連続であった。これは、中央の著名な大名とは異なる、地方の武将たちが直面した厳しい現実と、その中での必死の生存戦略を具体的に示す事例として、歴史研究において深い考察の対象となる。
呰部城、そして後に本拠とした佐井田城を中心とする彼の活動は、備中北部の地域社会に少なからぬ影響を与えたことは想像に難くない。佐井田城が「備中三名城のひとつ」と称えられたという伝承 3 も、植木氏の活動の一端を物語るものであろう。
植木秀長に関する史料は限られており、その生涯の全てを解明することは現時点では困難である。しかし、断片的な記録を繋ぎ合わせ、当時の時代背景や周辺状況を丹念に考察することによって、一人の地方武将の実像に迫る試みは、戦国時代の多様な地域社会の様相や、そこに生きた国人領主たちの実態をより深く理解する上で、極めて有意義な作業と言える。今後、さらなる研究が進展し、植木秀長とその時代に対する我々の理解が一層深まることが期待される。
引用文献
- 植木秀長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E6%9C%A8%E7%A7%80%E9%95%B7
- 植木氏 - 姓氏家系メモ https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E6%A4%8D%E6%9C%A8%E6%B0%8F
- 身がわり観音 - まんが日本昔ばなし〜データベース - syoukoukai.com http://nihon.syoukoukai.com/modules/stories/index.php?lid=145&cid=42