藤方朝成
藤方朝成は戦国乱世を生き抜き、旧主を裏切り織田・豊臣に仕え、子孫を旗本とした。その生涯は忠義と裏切り、名誉と実利が複雑に絡み合う。
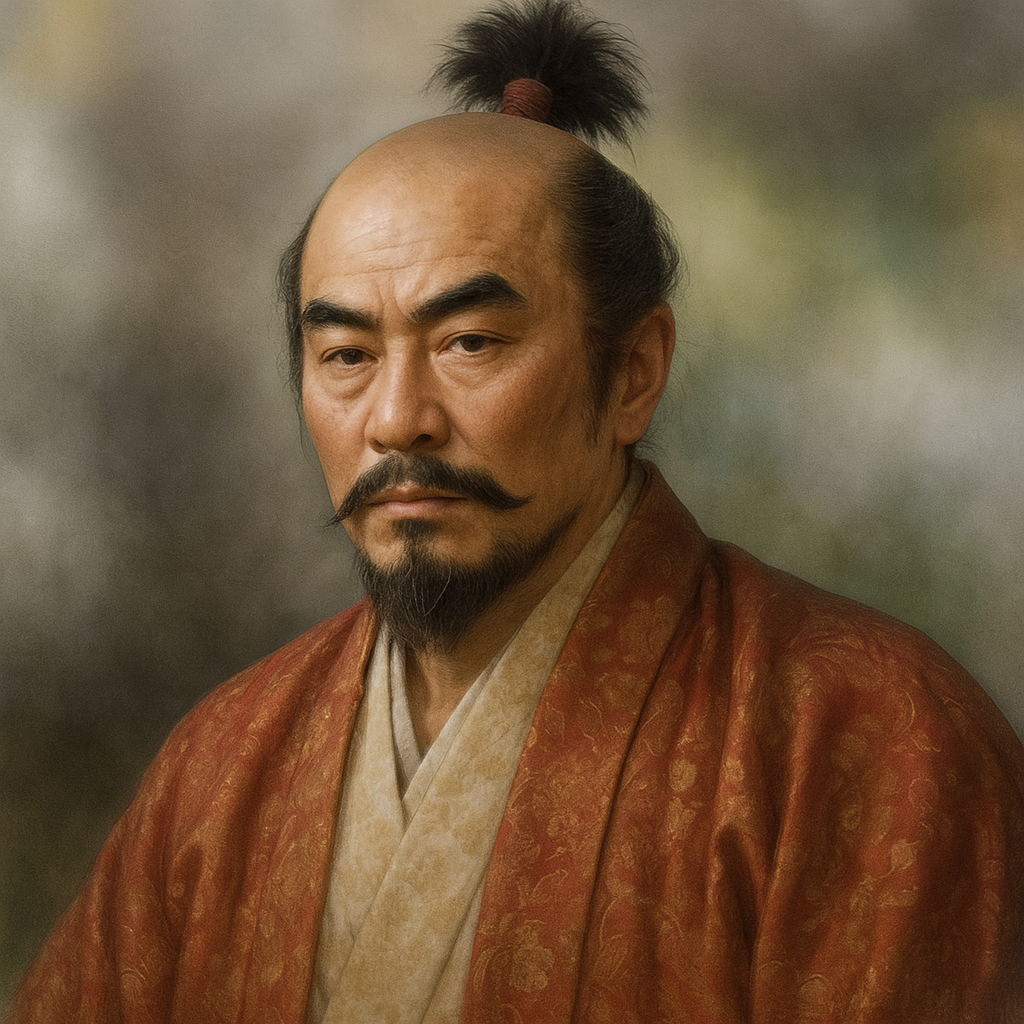
藤方朝成の生涯―名門の裏切りと一族存続の狭間で
序章:藤方朝成という存在―裏切りと生存の狭間で
戦国時代、主家の没落と新興勢力の台頭という激動の中で、多くの武将が己と一族の存続を賭けた決断を迫られました。伊勢国(現在の三重県中南部)の武将、藤方朝成(ふじかた ともなり)もその一人です。伊勢国司として長きにわたり南伊勢に君臨した名門・北畠氏の庶流に生まれながら、尾張の織田信長の軍門に降り、かつての主君である北畠具教(きたばたけ とものり)の暗殺に加担したとされる彼の生涯は、「裏切り者」という一面的な評価に留まらない、乱世の生存戦略を体現する複雑な物語を内包しています。
彼の行動は、単なる不忠義な裏切りだったのでしょうか。それとも、時代の大きな変化を的確に読み、一族を存続させるための苦渋の決断を下した、冷徹な現実主義者だったのでしょうか。本報告書は、『勢州軍記』に代表される軍記物語が描くドラマティックな逸話 1 と、江戸幕府の公式記録である『寛政重修諸家譜』が示す客観的な記録 2 という、性質の異なる史料群を丹念に比較・分析することで、藤方朝成という人物の実像に多角的に迫ることを目的とします。彼の選択の背景にある伊勢国の政治情勢、そしてその決断が彼自身と一族の運命に何をもたらしたのかを解き明かしていきます。
第一章:名門・北畠氏の庶流として
1.1 藤方氏の出自と伊勢国における地位
藤方朝成の行動を理解するためには、まず彼が属した藤方氏が、主家である北畠家の中でいかなる地位を占めていたかを確認する必要があります。
藤方氏は、南北朝時代から戦国時代末期にかけて約240年間にわたり伊勢国司として南伊勢に君臨した名門・北畠氏の庶流(分家)とされています 4 。その本拠は伊勢国陸田城(現在の三重県津市付近)であったと伝えられ 7 、北畠家の支配体制において、軍事的にも政治的にも重要な一翼を担っていたと考えられます。
特に注目すべきは、朝成の父・藤方慶由(よしゆき)の代には「藤方御所」と称されていた記録が存在することです 5 。通常、「御所」という呼称は、皇族や将軍家、あるいはそれに準ずる極めて高貴な身分に対して用いられる敬称であり、一介の家臣に対して使われることは極めて稀です。この異例の呼称は、藤方氏が単なる軍事的な家臣団の一員ではなく、北畠本家と強い血縁的・儀礼的な繋がりを持ち、国司家の権威を構成する「御一家」に準ずるような、別格の家格を有していたことを強く示唆しています。この高い地位は、後の織田信長への寝返りという行為の重大性と、当時の伊勢国人社会に与えた衝撃の大きさを一層際立たせる要因となったと見ることができます。
1.2 剣豪国司・北畠具教の時代
朝成が家臣として仕えた北畠家9代当主・北畠具教は、戦国時代を代表する文化人武将の一人です。彼は剣術をこよなく愛し、剣聖・塚原卜伝(つかはら ぼくでん)に師事してその奥義である「一の太刀」を伝授されたと伝わるほどの剣豪でした 8 。また、大和国の柳生宗厳(柳生石舟斎)とも親交があったとされます 8 。
武芸のみならず、政治・軍事両面においてもその辣腕を振るい、北伊勢への勢力拡大に尽力するなど、北畠家の最盛期を築き上げた英主として評価されています 5 。朝成は、このような強力なリーダーシップを持つ主君の下で、北畠家の中核をなす重臣として活動していました。当時の伊勢国は、南部の五郡を支配する北畠氏と、北伊勢に割拠する長野工藤氏をはじめとする諸豪族が対峙する構図にありましたが 4 、具教の時代、北畠家の支配は盤石に見えました。しかし、尾張から急速に勢力を拡大する織田信長の存在が、その均衡を根本から揺るがし始めていたのです。
第二章:裏切りか、時勢か―織田信長への帰順
2.1 永禄十二年(1569年)の伊勢侵攻
永禄12年(1569年)、織田信長は数万と号する圧倒的な大軍を率いて伊勢国へ侵攻を開始しました。これに対し、北畠具教・具房親子は、本城である大河内城(現在の三重県松阪市)に籠城し、50日に及ぶ激しい攻防戦を繰り広げました 11 。北畠勢は善戦したものの、織田軍の物量と巧みな調略の前に、次第に追い詰められていきます。
この戦いの趨勢を決定づけたのは、純粋な軍事的な圧力だけではありませんでした。信長は、北畠一門の中でも特に有力な存在であった木造城主・木造具政(こづくり ともまさ)の調略に成功します 5 。この調略を主導したのは、信長の家臣・滝川一益(たきがわ かずます)であり、彼は当時、僧籍にあって木造氏に仕えていた滝川雄利(かつとし、木造氏の一族出身)を通じて具政を説得し、織田方へ寝返らせることに成功したのです 13 。家中の中核である木造氏の離反は、北畠方にとって致命的な打撃となり、大河内城の和睦開城へと繋がっていきました。
2.2 朝成の決断とその背景
藤方朝成は、この永禄12年の織田軍侵攻の際に、主家である北畠氏を裏切り、織田信長に臣従したと記録されています 5 。彼のこの決断は、単なる個人の裏切り行為としてではなく、より大きな文脈の中で捉える必要があります。
木造具政は北畠晴具(具教の父)の子であり、具教の弟にあたる人物で、北畠一門の中でも極めて重い地位を占めていました 5 。その彼が織田方に寝返ったという事実は、北畠家臣団に深刻な動揺をもたらしたことは想像に難くありません。朝成の寝返りは、この木造氏の動向に追随した結果であった可能性が極めて高いと考えられます。つまり、彼の決断は、孤立した個人の裏切りというよりも、織田方の巧みな調略によって引き起こされた北畠家臣団の「連鎖的な内部分裂」の一環であったと見なすのが妥当でしょう。
信長軍の侵攻という外的圧力、そして滝川一益らによる内部からの調略が、家中の最大派閥であった木造氏を切り崩し、その動きを見て藤方氏をはじめとする他の有力国人も時勢に従った、という因果の連鎖がそこには見て取れます。この視点に立てば、朝成の行動は、主家への忠義を欠いた行為であると同時に、圧倒的な力の差と家中の分裂という現実を前に、自らと一族の存続を図るための、極めて現実的な政治判断であったと評価することもできるのです。
第三章:三瀬の変―旧主殺害の真相
3.1 事件の概要と信長の意図
大河内城での和睦の結果、信長の次男・茶筅丸(後の織田信雄、当時は信意)が、子のなかった北畠具房の養嗣子となり、形式上、北畠家の家督を継承しました 11 。これにより、伊勢国は事実上、織田家の支配下に組み込まれます。しかし、当主の座を譲ったとはいえ、具教は出家して不智斎と号し、三瀬御所(現在の三重県多気郡大台町)に隠居した後も、「大御所」として依然として強い影響力を保持していました 12 。武田信玄と密かに連携を図るなど、反信長の動きを見せていたとも言われます 12 。
信長にとって、剣豪としても名高い具教の存在は、伊勢支配を安定させる上での潜在的な脅威であり続けました。天正4年(1576年)11月25日、信長と信雄は、この脅威を根絶するため、具教をはじめとする北畠一族の主だった者たちを同日に謀殺するという、計画的な粛清作戦を決行します。これが世に言う「三瀬の変」です 17 。
3.2 刺客としての藤方朝成―諸説の比較検討
藤方朝成がこの暗殺計画において、信長から直接命令を受けた刺客の一人であったことは、多くの史料で一致して言及されています 12 。しかし、その後の具体的な行動については、史料によって記述が異なり、彼の人物像を解釈する上で最大の分岐点となっています。以下に、主要な二つの説を比較検討します。
|
説 |
概要 |
主な典拠史料 |
考察 |
|
説A(名代派遣説) |
旧主である具教を自らの手で討つことに逡巡し、直接の参加は避け、家臣の加留(軽野)左京進を名代として派遣したとされる説 1 。 |
『勢州軍記』など、後世に成立した軍記物語に多く見られる。 |
この説は、朝成の人間的な葛藤や苦悩を描き出しており、物語性が非常に高い。旧主への恩義と新主への忠誠との間で揺れ動く武将の姿は、軍記物語の読者の共感を呼びやすい典型的な描写と言えます。しかし、軍記物特有の脚色や創作の可能性も考慮する必要があり、史実をそのまま伝えているかについては慎重な検討が求められます。 |
|
説B(直接関与説) |
信長の命令に忠実に従い、自らが直接、あるいは父・慶由と共に具教殺害の現場に加担したとされる説 1 。 |
事件の概要を簡潔に記した記録や、それに基づく解釈に見られる。 |
こちらは、朝成の行動をより冷徹な現実主義者のそれとして捉える説です。物語的な葛藤は排され、織田家の家臣として与えられた任務を忠実に実行する側面が強調されます。彼の置かれた状況を鑑みれば、新主君からの命令を拒否することは、自らの一族を危険に晒すことに他ならず、この説にも十分な合理性があります。 |
どちらの説が真実であったかを断定する決定的な一次史料は現存していません。しかし、いずれの説を採るにせよ、彼が旧主殺害という重大な計画に深く関与した事実は動かしがたいものです。
3.3 父・慶由の自害―悲劇の代償
三瀬の変をめぐる逸話の中でも、特にドラマティックなのが、父・慶由の最期に関する伝承です。説A(名代派遣説)に付随する形で、息子の朝成が旧主殺害に加担したという知らせを聞いた父・慶由が、その不忠を嘆き、あるいは厳しく詰問した末に井戸に身を投げて自害した、と伝えられています 1 。
この逸話の史実性を確定することは困難ですが、史実か否か以上に、この物語が持つ機能に注目すべきです。この父の自害という悲劇は、藤方朝成の「裏切り」という行為を、単なる個人的な野心や保身から出たものではなく、一族の存続という、やむにやまれぬ事情によって引き起こされた「悲劇的な選択」であったと位置づけるための、道徳的な補完装置として機能していると考えられます。父が嘆き悲しんで死を選ぶほどの非道な行いであったと認めることで、朝成の行為を非難しつつも、その背景にある彼の苦悩や葛藤を暗示する効果が生まれます。つまり、この物語は、朝成個人の評価を「冷酷非情な裏切り者」から「時代の奔流に翻弄された悲劇の当事者」へと転換させる役割を担っているのです。これは、後世の藤方家が、自らの祖先の行為を正当化、あるいは悲劇化するために語り継いだ物語であった可能性も示唆しています。
第四章:織田信雄、そして豊臣政権下での後半生
4.1 織田信雄の家臣として
三瀬の変によって北畠氏の旧勢力は一掃され、伊勢国は名実ともに織田信雄の支配下に入りました。藤方朝成は、そのまま信雄の家臣として仕えることになります 7 。この時期、同じく北畠旧臣から信雄配下となった滝川雄利らと共に、信雄政権下で伊勢・伊賀の支配を支える中核的な家臣の一人として活動していたと考えられます 13 。旧主を排除したことによって、新体制下での地位を確固たるものにしたのです。
4.2 豊臣秀吉への臣従と知行
天正10年(1582年)の本能寺の変後、織田家の内紛を経て天下人の地位を確立したのは羽柴(豊臣)秀吉でした。主君である織田信雄は、天正12年(1584年)に秀吉と対立し、小牧・長久手の戦いを引き起こしますが、最終的には秀吉に屈し、後に改易されることになります。藤方朝成は、この一連の動乱の過程で信雄から離れ、新たな中央の覇者である豊臣秀吉に仕える道を選びました 7 。
秀吉の配下となった朝成は、鈴鹿郡庄野(現在の三重県鈴鹿市庄野町付近)において千石の知行を与えられたとされています 7 。この知行地と石高を直接的に証明する一次史料は限定的であり、一部の記録では出典の明記が求められているなど、さらなる検証が必要な点ではあります 7 。しかし、秀吉政権下で一定の所領を安堵され、その家臣団に組み込まれていたことは確かでしょう。
朝成の生涯を振り返ると、北畠具教から織田信雄、そして豊臣秀吉へと、仕える主君を次々と変えていることがわかります。これは、特定の主君個人への人格的な忠誠よりも、その時々の中央の覇者に臣従することで、自らと一族の地位を確保し続けるという、極めて現実的な行動原理に貫かれていたことを示しています。彼の選択は、まさに戦国乱世における地方豪族の典型的な生存戦略そのものであったと言えるでしょう。
第五章:藤方家のその後―旗本への道
藤方朝成の非情ともいえる決断が、彼の一族に何をもたらしたのか。その答えは、彼の息子・安正の生涯と、その後の藤方家の運命に明確に示されています。
5.1 息子・藤方安正の生涯
朝成の子・藤方安正(ふじかた やすまさ、1571年 - 1622年)の経歴は、父以上に目まぐるしい時代の変化を色濃く反映しています。彼ははじめ、織田信長の弟である織田信包(のぶかね)に仕えました。その後、信包が改易されると、天下人・秀吉の甥であり後継者と目されていた関白・豊臣秀次に仕官します。しかし、文禄4年(1595年)、秀次が秀吉の勘気を受けて自害に追い込まれると(秀次事件)、安正は主君を失い、浪人の身となりました 2 。
度重なる主家の変転にもかかわらず、安正は新たな道を切り開きます。浪人となった後、彼は次の天下人として台頭していた徳川家康に召し抱えられ、下総国(現在の千葉県北部など)に500石の知行を与えられて旗本(江戸幕府の直参)となったのです 2 。その後は二代将軍・徳川秀忠に仕え、藤方家は江戸幕府の体制下で安定した地位を確保することに成功しました。
5.2 『寛政重修諸家譜』に見る藤方氏
この藤方家の存続は、江戸幕府が編纂した公式な大名・旗本の系譜集である『寛政重修諸家譜』によって、明確に裏付けられています 3 。この信頼性の高い公式記録の存在は、『勢州軍記』などが記す「藤方氏の子孫は落ちぶれて大津で宿屋をやっていた」という記述 21 が、史実とは異なる創作、あるいは旧主を裏切った者への道徳的な教訓話であったことを強く示唆しています。
ここに、本報告書の核心ともいえる結論が導き出されます。藤方朝成の生涯で最も非難されるべき行為、すなわち「旧主殺害への加担」は、皮肉にも、彼の一族が戦国の動乱を生き抜き、最終的に徳川幕府の旗本という安定した地位を確保するための、決定的な布石となっていたのです。朝成が北畠氏を見限り、織田信長という中央政権と結びついたことによって、その息子・安正は、織田家、豊臣家(秀次系)、そして最終的に徳川家という、天下人の系譜を渡り歩く足がかりを得ました。もし朝成が北畠氏に殉じていれば、一族は主家と共に滅亡していた可能性が高いでしょう。彼の「裏切り」は、結果として一族を滅亡から救い、新たな支配体制下での繁栄の礎を築いたのです。これは、戦国時代の倫理観と、近世における「家」の存続という結果主義との間の、深刻な乖離を象徴する事例と言えます。
5.3 墓所と伝承
藤方朝成は慶長2年(1597年)に没したとされます 7 。彼の墓所の具体的な場所を特定する史料は現存しませんが、彼が本拠とした三重県津市には現在も「藤方」という地名が残り 26 、かつてこの地が藤方一族の所領であったことの名残を留めています。近隣にある天台真盛宗の西福寺 26 などが、一族の菩提寺であった可能性も考えられ、今後の研究が待たれるところです。
結論:乱世の生存者、藤方朝成
藤方朝成の生涯は、忠義と裏切り、名誉と実利が複雑に絡み合う戦国時代の縮図です。名門・北畠氏の庶流という高い家格に生まれながら、時代の奔流の中で主家を見限り、旧主殺害という消せない汚名を背負いました。
しかし、その非情ともいえる一連の決断は、彼の子孫を徳川幕府の旗本として近世まで存続させるという、明確な結果をもたらしました。『勢州軍記』が描く人間的な葛藤と悲劇の物語、そして『寛政重修諸家譜』が示す「家」の存続という客観的な事実。これら二つの側面を統合して初めて、藤方朝成という人物の全体像が浮かび上がります。
彼は単なる裏切り者ではなく、一族の未来をその双肩に背負い、非情な選択を重ねることで乱世を生き抜いた、一人の「生存者」として評価されるべきではないでしょうか。彼の物語は、戦国という時代が、そこに生きる武士たちに何を求め、何を強いたのかを、我々に生々しく伝えているのです。
引用文献
- 戦国期の北畠氏の一門 http://www.amigo2.ne.jp/~fuchisai/home/ichimon.htm
- 藤方安正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E6%96%B9%E5%AE%89%E6%AD%A3
- 『寛政重修諸家譜』(かんせい ちょうしゅう しょかふ) - 筒井氏同族研究会 https://tsutsuidouzoku.amebaownd.com/posts/7694092/
- 北畠家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E5%AE%B6
- 大河内城の戦いと城跡 | いいなん.net http://iinan.net/id/id/id-5/
- 戦国!室町時代・国巡り(3)伊勢・志摩編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n0d30d0b9bc2a
- 藤方朝成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E6%96%B9%E6%9C%9D%E6%88%90
- 北畠具教 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E5%85%B7%E6%95%99
- 北畠具教~三瀬の変・信長に謀殺された名門の剣豪大名~ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Nj-SWqwqA0s
- 伊勢の名門北畠氏の光と影 ~なぜ国司は滅んだのか~① - らいそく https://raisoku.com/9229
- 三重県津市、美杉村、伊勢市へ - 栗林義長の歴旅 http://www.rekitabi.sakura.ne.jp/H16/1602mie/1602mie-2.htm
- 三瀬館 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/mise.y/mise.y.html
- 滝川雄利 Takigawa Katsutoshi - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/takigawa-katsutoshi
- マイナー武将列伝・滝川雄利 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/gokuh/ghp/busho/oda_039.htm
- 三瀬館の見所と写真・100人城主の評価(三重県大台町) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1635/
- 北畠具教最期の地三瀬館などに行ってきました。 - note https://note.com/good5_/n/nb36006705595
- 三瀬の変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%80%AC%E3%81%AE%E5%A4%89
- 藤方朝成(ふじかたともなり)『信長の野望 天道』武将総覧 http://hima.que.ne.jp/tendou/tendou_data_d.cgi?equal1=C001
- 滝川氏城 織田信雄に仕えた滝川雄利が築いた伊賀攻略の拠点 | 小太郎の野望 https://seagullese.jugem.jp/?eid=415
- 滝川雄利 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%9D%E5%B7%9D%E9%9B%84%E5%88%A9
- 『勢州軍記』読もうぜ! - 藤方慶由の事 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n6314ey/11/
- 藤方安正 - 信長の野望・創造 戦国立志伝 攻略wiki http://souzou2016.wiki.fc2.com/wiki/%E8%97%A4%E6%96%B9%E5%AE%89%E6%AD%A3
- 3.寛政重修諸家譜 - 大名 - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/daimyou/contents/03.html
- 寛政重修諸家譜|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=909
- 江戸時代の幕臣を調べる | リサーチ・ナビ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/humanities/post_780
- 西福寺(三重県津市の天台宗寺院)|霊園・墓地のことなら「いいお墓」 https://www.e-ohaka.com/temple_detail/id027160.html
- 結城神社 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E7%A5%9E%E7%A4%BE
- 藤方の神社・神宮・寺院ランキングTOP2 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/tow_242010100/g1_20/