長続連
長続連は能登畠山氏の重臣。畠山七人衆の一員として国政を主導。親織田派として上杉謙信と対立。七尾城籠城戦で奮戦するも、遊佐続光らの謀反により討死。長氏の悲劇的な終焉を飾った。
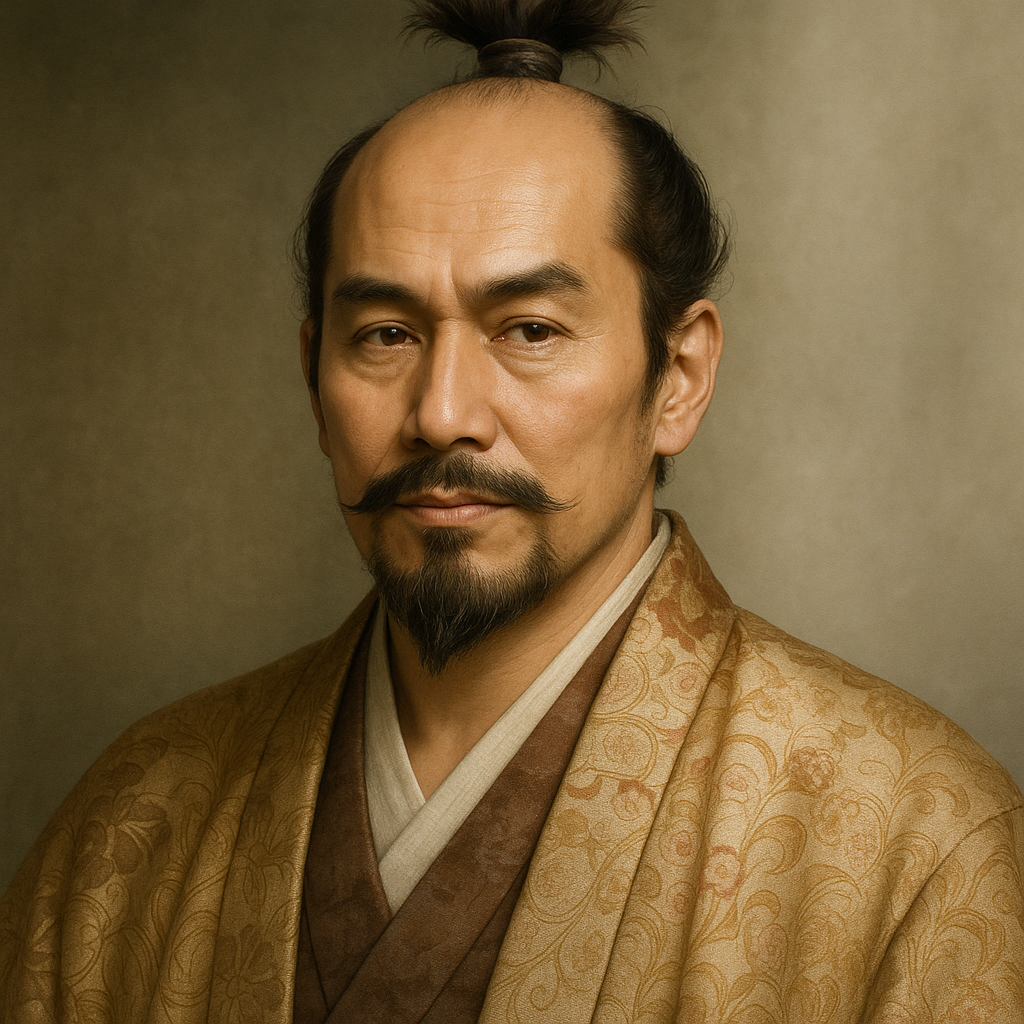
能登の戦国武将・長続連:その生涯と時代
序章:能登の戦国武将・長続連
本報告書は、日本の戦国時代、能登国(現在の石川県能登半島)にその名を刻んだ武将、長続連(ちょう つぐつら)の生涯と、彼が生きた時代背景を詳細に解明することを目的とする。長続連は、能登守護畠山氏の重臣として国政の中枢にありながら、越後の雄・上杉謙信による侵攻という未曽有の国難に直面し、七尾城の攻防戦の末、悲劇的な最期を遂げた人物である。彼の生涯は、戦国乱世における地方武将の苦悩、中央勢力との関係、そして一族の存亡を賭けた戦いを象徴している。本報告書では、現存する史料を基に、長続連の出自から、能登畠山氏における立場と役割、七尾城の戦いにおける動向、関連人物との関係性、その最期、さらには彼の一族や関連史跡、歴史的評価に至るまで、多角的に光を当てる。
第一部:長続連の生涯
第一章:出自と長氏の台頭
長続連の生年は詳らかではないが、その没年は天正5年(1577年)9月15日と記録されている 1 。この日付は、彼の運命を決定づけた七尾城落城の日と合致しており、彼の生涯が能登の戦国史における一大転換点と深く結びついていたことを物語っている。
長氏の祖は、鎌倉時代に幕府の御家人であった長谷部信連(はせべ のぶつら)に遡るとされる 3 。信連は遠江国長村(現在の静岡県)の出身で、幕府から能登国大屋荘を与えられ、能登の地に勢力を築いた。その後、子孫が姓を「長」と改めたと伝えられている 3 。長続連自身は平氏を称し、平加賀守盛信(あるいは信光)の次男として生まれた 2 。能登国鳳至郡穴水城主であった長英連(ちょう ひでつら)に男子がいなかったため、その婿養子として長氏の家督を継承した 2 。
この養子縁組は、戦国時代において家の存続や勢力拡大のためによく用いられた手段であり、長氏のケースも例外ではない。長氏は元々能登最大の国人領主の一角を占めていたが、畠山氏の重臣である平氏の家系から続連を養子に迎えたことは、能登守護畠山氏への従属関係をより強固なものにする意図があったと考えられる 2 。また、続連が主君である畠山義続(はたけやま よしつぐ)から偏諱(へんき:名前の一字を与えられること)を受けて「続連」と名乗った事実も 2 、畠山氏との主従関係を明確に示している。
長氏は穴水城(現在の石川県鳳至郡穴水町)を拠点とし 2 、能登有数の国人としての地位を固めていた。その地理的拠点は、能登半島内における勢力配置を考える上で重要な意味を持つ。長氏一族は、戦国末期の混乱を乗り越え、江戸時代には加賀藩の重臣として存続し、明治維新後には士族となり、さらには男爵家にも列せられている 3 。これは、長氏が時代を超えてその家格を維持し続けたことを示している。
第二章:能登畠山氏の重臣として
長続連は、能登畠山氏の家政において中心的な役割を担った。特に、天文19年(1550年)から翌年にかけて能登国内で発生した内乱の後、守護畠山氏の権力が揺らぐ中で成立した「畠山七人衆」と呼ばれる重臣会議の一員に名を連ねたことは、彼の政治的地位を象徴している 2 。この七人衆体制は、畠山氏の当主に代わって領国支配の実権を握るものであり 2 、守護大名であった能登畠山氏の権威が相対的に低下し、家臣団が国政の主導権を握りつつあった当時の状況を反映している。続連がこの合議体の一翼を担ったことは、彼が能登国政において非常に大きな発言力と影響力を持っていたことを意味する。
主君との関係においては、前述の通り畠山義続から偏諱を受けるなど、一定の信頼関係があったことがうかがえる。しかし、その一方で、永禄9年(1566年)には、同じく七人衆の一人であった遊佐続光(ゆさ つぐみつ)らと共に、当時の主君であった畠山義続・義綱(よしつな)父子を能登から追放し、義綱の子である義慶(よしのり)を新たな当主として擁立するという政変(永禄九年の政変)に深く関与している 2 。この行動は、続連が単に主君に忠実な家臣であっただけでなく、能登畠山氏内部の権力構造を自ら動かすほどの野心と実力を兼ね備えていたことを示している。この政変の原因としては、義綱の専制的な政治運営に対する重臣層の反発や、続連と他の重臣(例えば飯川光誠)との間の確執などが指摘されており 2 、能登畠山氏内部の権力闘争の激しさを物語っている。
中央の政治情勢が能登にも影響を及ぼす中、長続連は織田信長の勢力伸張に着目し、信長と誼を通じることで親織田派の筆頭と目されるようになった 2 。これは、越後の上杉謙信と通じる遊佐氏との間に明確な対立構造を生み出す要因となった 6 。中央の有力者である織田信長との連携は、地方勢力が激動の戦国時代を生き抜くための重要な外交戦略であった。続連のこの選択は、能登国内の政治バランスを大きく変動させ、最終的には上杉謙信による能登侵攻、そして七尾城の戦いという形で外部勢力の直接的な介入を招くことになる。彼の外交政策が、能登畠山氏の、そして彼自身の運命を左右する極めて重要な要素であったと言えるだろう。
第三章:七尾城の戦い
天正4年(1576年)、越後の上杉謙信は、かねてより乱れていた能登の治安回復を大義名分の一つとし、かつて畠山氏から人質として差し出されていた上条政繁を新たな畠山氏当主として擁立することを目論み、能登への侵攻を開始した 3 。これに対し、能登畠山家中は謙信の介入を拒否し、長続連の主導のもと、畠山氏の居城である七尾城(現在の石川県七尾市)での籠城戦を選択した 3 。
七尾城は、かつて畠山義総によって築かれた難攻不落と称される堅城であり、その縄張りは広く、春日山城にも匹敵すると言われた 8 。長続連は籠城戦の総指揮を執り、自らは大手口の守備を担当し、温井景隆(ぬくい かげたか)に古府谷(こぶだに)を、遊佐続光に蹴落口(けおとしぐち)の守備をそれぞれ分担させた 8 。さらに、謙信軍の背後を撹乱するため、笠師村や土川村、長浦村などの領民に一揆を起こすよう扇動したが、謙信はかつて一向一揆に苦しめられた経験から情報網を駆使し、これらを事前に鎮圧した 8 。
謙信は、七尾城の堅固さに攻めあぐね、まずその支城群(熊木城、黒滝城、富来城など)を次々と攻略し、七尾城を孤立させる戦略をとった 8 。しかし、それでも続連らは降伏しなかった。翌天正5年(1577年)に入り、3月に北条氏政が関東方面に出兵したため、謙信は本国の仕置を兼ねて一時越後へ帰国する 8 。この間隙を突いて畠山軍は反撃を試み、一部の城を奪還する動きも見せた 8 。
しかし、閏7月、謙信は再び能登へ出陣。続連は慌てて各地の城を放棄し、全兵力を七尾城に集中させ、領民に対しても半ば強制的に城内に籠もらせたため、城内は兵士と領民合わせて約1万5000人という過密状態になった 8 。籠城が長期化するにつれて城内の状況は悪化の一途をたどり、特に深刻だったのは疫病の蔓延であった 3 。不衛生な環境と食糧不足がそれに拍車をかけ、多くの将兵や領民が病に倒れた。そして、閏7月23日には、幼い当主であった畠山春王丸(はたけやま はるおうまる)も、わずか5歳で病死するという悲劇に見舞われた 9 。
この絶望的な状況下で、長続連は最後の望みを託し、中央の織田信長に救援を要請することを決断。当時、僧籍にあった三男の長連龍(ちょう つらたつ、後の孝恩寺)を密かに安土城へ派遣した 8 。信長はこの要請を受諾し、柴田勝家を総大将とする援軍を派遣したが、織田軍内部の不和(柴田勝家と羽柴秀吉の対立など 12 )や、能登・加賀の門徒が謙信に味方したことによる進軍の遅れなどから 9 、この援軍が七尾城に到着することはなかった。
第四章:謀反と非業の最期
七尾城内での絶望的な状況と、長引く籠城戦による疲弊は、城内の結束を徐々に蝕んでいった。特に、かねてより親上杉派と目され、親織田派の長続連と対立していた遊佐続光は、この状況を打開するための独自の動きを見せる。上杉謙信は、力攻めが困難と見るや調略に転じ、遊佐続光に対して内応を働きかけた 9 。謙信が提示した条件は、「内応すれば、畠山氏の旧領および長一族の所領を与える」というものであったと伝えられている 9 。
遊佐続光・盛光(もりみつ)父子は、この謙信の誘いに応じ、同じく親上杉派であった温井景隆や三宅長盛(みやけ ながもり)らと共謀して、城内で反乱を起こすことを決断した 9 。彼らは長綱連(ちょう つなつら、続連の嫡男)にも内応を持ちかけたが、綱連は「織田信長に援軍を要請しており、降伏はできない」としてこれを拒否したとされている 9 。
そして、天正5年(1577年)9月15日、中秋の名月の夜、遊佐続光らはついに反乱を実行に移した 1 。軍議と称して長続連、綱連らを自邸に誘い出して謀殺したとも 9 、あるいは城門を開いて上杉軍を城内に引き入れたとも言われる 3 。この謀反により、長続連、長綱連をはじめとする長一族の主だった者たち、百余人がことごとく討ち取られた 2 。この時、織田信長のもとへ援軍要請に赴いていた続連の三男・長連龍と、綱連の末子で乳母に抱かれて城から脱出した菊末丸(きくまつまる)のみが難を逃れた 2 。
鉄壁を誇った七尾城も、内部からの裏切りによってあっけなく陥落した。この事件により、約170年にわたり能登を支配した畠山氏は事実上滅亡し、能登は上杉謙信の支配下に置かれることとなった 3 。長続連の死は、彼の推し進めた親織田路線が最終的に破綻したことを意味し、能登の戦国史における大きな転換点となったのである。遊佐続光の行動については、単なる裏切り者として断罪するだけでなく、長く七尾を治めてきた遊佐氏の立場や、籠城による民衆の疲弊を憂慮した結果という見方も提示されており 15 、その評価は一筋縄ではいかない。
第二部:長続連を取り巻く環境と影響
第一章:主要関連人物との関係
長続連の生涯は、当時の有力な戦国大名や能登国内のライバルたちとの複雑な関係性の中で展開された。
- 上杉謙信 : 長続連にとって最大の敵対者であった。謙信は天正4年(1576年)と天正5年(1577年)の二度にわたり能登に侵攻し、七尾城を攻撃した 3 。謙信の軍事力と巧みな調略は、最終的に七尾城を陥落させ、長続連とその一族を破滅へと追いやった。謙信にとって能登攻略は、対織田戦略上、また日本海ルートを確保し上洛を目指す上で重要な意味を持っていた。七尾城はその堅固さから「聞きしに勝る名地で、加賀・越中・能登の要にあり」と謙信自身も高く評価しており 9 、その戦略的重要性を認識していたことがうかがえる。長続連の粘り強い抵抗は謙信を手こずらせたが、最終的には遊佐続光の内応という形で内部から崩壊させることに成功した。
- 織田信長 : 長続連が外交上の活路を見出そうとした相手である。続連は親織田派の重臣として信長に接近し、特に七尾城籠城戦の際には、三男の連龍を派遣して援軍を要請した 6 。信長もこの要請に応じ、柴田勝家を総大将とする援軍を派遣したが、織田軍内部での不和(柴田勝家と羽柴秀吉の対立 12 )や進軍の遅延などにより、援軍は七尾城落城に間に合わなかった 9 。信長にとって、能登の親織田派である長氏の存在は、北陸における対上杉戦略において重要な駒であったはずだが、結果として続連を見捨てる形となった。この事実は、当時の織田軍団が抱える内部問題や、遠隔地への迅速な軍事展開の難しさを示唆している。
- 遊佐続光 : 長続連の運命を直接的に左右した人物である。元々は同じ能登畠山氏の重臣であり、畠山七人衆の一員として国政を担った仲間であった 2 。しかし、外交方針において、親上杉派の遊佐氏と親織田派の長続連は激しく対立した 6 。この対立は、七尾城籠城戦という極限状況下で頂点に達し、遊佐続光は上杉謙信の内応工作に応じて長続連らを謀殺し、七尾城を開城した 3 。遊佐続光の行動は、単なる個人的な裏切りとして片付けられるべきではなく、能登畠山家が長年にわたり抱えてきた内部対立、外交方針の深刻な不一致、そしておそらくは両者の個人的な確執などが複雑に絡み合った結果と考えるべきであろう。 15 で指摘されているように、遊佐氏が畠山氏よりも長く七尾を実質的に治めてきたという自負や、領民の窮状を救おうとしたという動機も考慮に入れる必要があるかもしれない。
第二章:家族と長氏の再興
長続連の妻は、養父である長英連の娘であった 2 。続連には複数の子がおり、中でも歴史に名を残したのは長男の長綱連と三男の長連龍である 2 。
長綱連は、父・続連と共に能登畠山氏の重臣として活動し、七尾城の戦いにおいても父を助けて籠城戦を戦ったが、天正5年(1577年)9月15日の遊佐続光らの謀反により、父と共に討死した 3 。綱連には竹松丸、井上弥九郎、そして唯一生き延びた菊末丸という子がいた 2 。
一方、三男の長連龍(幼名:萬松、初名:好連、法名:宗顒)は、長氏の歴史において極めて重要な役割を果たした。彼は七尾城落城の際、織田信長への援軍要請のため安土に赴いており城外にいたため、一族の虐殺から幸運にも逃れることができた 9 。当初は臨済宗の僧侶として孝恩寺の住職を務めていたが 11 、この悲劇をきっかけに還俗。織田信長に仕え、父兄の仇である遊佐氏らを討伐し、能登の平定に大きく貢献した 4 。
本能寺の変後、織田信長の死後は前田利家に仕え、その信頼を得て数々の戦功を挙げた 14 。賤ヶ岳の戦い、末森城の戦い、小田原征伐、朝鮮出兵などに参陣し 18 、その武勇と忠誠心は高く評価された。前田利家は死に際し、息子利長への遺言の中で、長連龍を高山右近と共に「役に立つ人材である」と評している 14 。これらの功績により、連龍は加賀藩内で3万石以上の大身となり、加賀藩の重臣の中でも特に家格の高い「加賀八家」の一つに数えられるまでになった 14 。これにより、一度は滅亡寸前にまで追い込まれた長氏は、連龍の手によって見事に再興を遂げたのである。
長連龍の生涯は、父や兄の非業の死という悲劇を乗り越え、激動の戦国時代から江戸時代初期を生き抜き、家名を再興した武将の典型例と言える。彼の成功は、七尾城落城時に偶然城外にいたという運、織田信長という当時の最有力者に早期に結びつくことができた先見性、そして彼自身の卓越した武勇や政治的手腕、さらには前田利家との間に築かれた強固な信頼関係など、複数の要因が複合的に作用した結果であろう。また、長氏が元々能登の有力国人であったという出自や、織田信長から直接所領を安堵されていたという経緯も 14 、前田家中で特別な地位を築く上で有利に働いたと考えられる。
長氏略系図(長続連中心)
|
関係 |
氏名 |
備考 |
|
祖 |
長谷部信連 |
長氏の祖 3 |
|
実父 |
平加賀守盛信(信光)/平総知 |
2 |
|
養父 |
長英連 |
続連の養父、能登穴水城主 2 |
|
本人 |
長続連 |
|
|
妻 |
長英連の娘 |
2 |
|
長男 |
長綱連 |
七尾城で父と共に討死 3 。子に竹松丸、井上弥九郎、菊末丸 2 |
|
次男 |
杉山則直 |
七尾城落城時に自害か 2 |
|
三男 |
長連龍 (萬松、好連、宗顒) |
長家を再興、加賀八家の一つ 14 。妻に長綱連の女(玉)、神保氏張の妹(新)、前田利家の女 14 |
|
子 |
飯川義実 |
2 (養子か実子か詳細不明) |
|
子 |
長連常 |
七尾城で討死 2 |
|
子 |
長連盛 |
七尾城で討死 2 |
|
女 |
遊佐盛光室 |
2 |
第三部:長続連の人物像と史跡
第一章:人物像の考察
長続連の性格や能力を直接的に伝える一次史料は限られている。しかし、彼の行動や当時の状況に関する記録から、その人物像をある程度推察することは可能である。
能登畠山氏の重臣筆頭として家中の実権を掌握し 2 、外交においては織田信長との連携を重視するなど 2 、強い指導力と政治的判断力を有していたことは間違いない。 3 の記述では「暗躍した」とも評されており、これは単に陰謀を巡らせたという否定的な意味合いだけでなく、表立っては事を荒立てずに裏で交渉や工作を進める高度な政治手腕を持っていた可能性も示唆する。
上杉謙信という強大な敵に対しても、七尾城に籠城して徹底抗戦を選んだ姿勢からは、彼の不屈の意志と、困難な状況に屈しない精神力の強さがうかがえる 8 。一方で、七尾城籠城戦の際には、領民に対しても半ば強制的に城内への避難を強いたとされており 8 、目的を達成するためには強硬な手段も辞さない、あるいはそれだけ追い詰められていた状況であったとも考えられる。この行動は、一部からは非情な決断と見なされるかもしれないが、城の防衛力を最大限に高めようとする総力戦の意志の表れと解釈することもできる。
長続連の親織田路線という選択は、当時の能登が置かれた西の織田、北の越後上杉という二大勢力に挟まれた地政学的な状況と、能登畠山家中の複雑な勢力図を考慮した上での、彼なりの最善の策であった可能性が高い。しかし、その強硬な政治姿勢や外交方針が、遊佐続光ら反対派の反発を招き、最終的には内部からの崩壊を招いた一因となった側面も否定できない。
郷土史や後世の評価においては、長続連に関する詳細な逸話は多く残されていないようである 15 。しかし、 15 では、敵対した遊佐続光の立場について「裏切り者のイメージが強いわけですが、はたしてほんとうにそうなのか」と問いかけ、歴史の評価が勝者の視点に偏りがちであることへの警鐘を鳴らしている。これは、長続連に関しても、単なる「悲劇の忠臣」や「頑迷な抵抗者」といった一面的な評価ではなく、複雑な状況下で困難な選択を迫られた一人の武将として、多角的に捉え直す必要性を示唆している。彼の選択が結果として一族の悲劇と畠山氏の滅亡に繋がったという事実は重いが、その判断の背景には、当時の価値観や彼が置かれた状況に対する深い理解が求められる。
第二章:関連史跡と墓所
長続連とその一族に関連する史跡は、能登半島を中心にいくつか現存しており、彼らの生きた時代を今に伝えている。
- 穴水城(石川県鳳珠郡穴水町) : 長氏代々の居城であり、長続連もここを拠点としていた 2 。七尾城の戦いの際には、長氏が七尾城に籠城したため上杉方に攻略されたが、後に長連龍が一時的に奪還している 4 。現在は穴水城址公園として整備されており、麓にある穴水町歴史民俗資料館(長家史料館)では、長氏ゆかりの武具や古文書などが展示されている 4 。
- 怡岩院(石川県七尾市) : 長続連の墓所と伝えられている 2 。寺伝によれば、子の長連龍が父・続連の菩提を弔うために建立したとされる 22 。 22 の記述では、怡岩院の創建は正保2年(1645年)とされており、続連の没年(1577年)からは相当の時間が経過している。長連龍の没年は元和5年(1619年)であるため 14 、連龍自身が直接創建に関わったというよりは、その遺志を継いだ子孫(例えば連龍の子の連頼など)によるものか、あるいは連龍が創建に関わった初期の寺院が後に怡岩院として整備された可能性が考えられる。いずれにせよ、加賀藩で確固たる地位を築いた長氏が、改めて父祖の追善供養を行ったことを示している。
- 悦叟寺(石川県七尾市田鶴浜町) : 長続連の長男であり、父と共に七尾城で討死した長綱連をはじめ、七尾城落城の際の戦死者たちの墓所が境内にある 2 。寺の創建年代は不明だが、天正8年(1580年)に長連龍が鹿島半郡を領有した後、兵火で荒廃していた堂宇を一族の菩提のために再建し、兄・綱連の法号「瑞松院殿悦叟良喜」にちなんで寺名を瑞松山悦叟寺と改めたと伝えられている 23 。父・続連とは別の場所に手厚く葬られていることからも、連龍の兄や一族に対する強い追悼の念がうかがえる。
- 七尾城跡(石川県七尾市古城町) : 長続連が上杉謙信を相手に壮絶な籠城戦を繰り広げ、そして非業の最期を遂げた場所である 7 。現在は国指定史跡となっており、日本100名城にも選定されている 9 。城跡からは当時の石垣や曲輪の遺構が確認でき、戦国時代の山城の姿を今に伝えている。
- 金沢長町武家屋敷跡(石川県金沢市長町) : 長連龍以降、加賀藩の重臣「加賀八家」の一つとして栄えた長氏の屋敷があったことが、この地の地名「長町」の由来の一つとされている 28 。これは、長続連の悲劇的な死から始まった物語が、その子孫の代で名誉ある形で金沢の地に名を刻むに至ったことを示しており、歴史の栄枯盛衰とダイナミズムを感じさせる。
終章:長続連の歴史的意義
長続連の生涯と、その非業の最期は、戦国時代の能登地方における歴史的転換点と深く結びついている。彼の存在と行動は、いくつかの重要な歴史的意義を持っている。
第一に、長続連の死と七尾城の落城は、約170年間にわたって能登を支配してきた能登畠山氏の事実上の終焉を決定づけた 9 。続連は、その最後の局面において、親織田派の筆頭として畠山氏の運命を左右する極めて重要な役割を担った。彼の選択は、能登の独立を保つための必死の策であったかもしれないが、結果として外部勢力(上杉氏、そして間接的には織田氏)の介入を招き、畠山氏の滅亡を早めることになった。
第二に、長続連の動向は、上杉謙信と織田信長という当時の二大勢力が北陸地方で覇権を争った、戦国時代末期の緊迫した状況を象徴している。彼の親織田路線と、それに対抗する遊佐続光らの親上杉路線との対立は、中央の政局が地方の勢力図にいかに大きな影響を与え、内部抗争を激化させたかを示す好例と言える。能登は、まさにこの二大勢力の草刈り場と化したのである。
第三に、長続連自身の直接的な歴史的評価は、史料の制約もあり多くは残されていない。しかし、彼の三男である長連龍が、父祖の悲劇を乗り越えて長家を再興し、加賀百万石・前田家の重臣「加賀八家」の一つとして家名を高めたことにより、長氏の歴史は途絶えることなく後世へと繋がった。このことは、長続連の存在と、彼が残した血脈が、間接的にではあるが江戸時代の加賀藩の体制にも影響を与えたことを意味する。
長続連の悲劇的な最期は、戦国時代の武将が常に直面していた過酷な運命と、権力闘争の非情さを生々しく物語るものとして記憶されている。近年では、 15 で示唆されるように、彼と敵対した遊佐続光の立場からの再評価も試みられており、これは長続連についても、従来の「悲劇の武将」という一面的な評価に留まらず、より多角的かつ客観的な視点からの研究が今後も進められるべきであることを示している。彼の選択と行動は、能登という一地方が戦国乱世の巨大な渦に飲み込まれていく過程を鮮明に映し出しており、その歴史的意義は、彼個人の成功や失敗以上に、彼が生きた時代と場所が抱えていた構造的な矛盾や力学を体現している点にあると言えよう。
長続連関連年表
|
年代 |
出来事 |
典拠 |
|
生年不詳 |
|
|
|
天文11年(1542年) |
畠山家臣としての初見(長続連書状) |
2 |
|
天文19年(1550年)頃 |
畠山七人衆の一員となる |
2 |
|
永禄9年(1566年) |
永禄九年の政変に関与し、畠山義続・義綱父子を追放 |
2 |
|
元亀年間(1570年~1573年)頃 |
家督を嫡男・綱連に譲り、後見役となる |
2 |
|
天正4年(1576年) |
上杉謙信の能登侵攻開始。長続連主導のもと、七尾城籠城戦が始まる |
3 |
|
天正5年(1577年)閏7月23日 |
籠城中の七尾城内で、幼君・畠山春王丸が病死 |
9 |
|
天正5年(1577年)9月15日 |
遊佐続光らの謀反により、七尾城落城。長続連、嫡男・綱連ら長一族の多くと共に討死(怡岩院に葬られる) |
1 |
引用文献
- 戦国時代カレンダー 今日は何の日? 【9月20日~26日】 - note https://note.com/takamushi1966/n/nd83f13c67e95
- 長続連 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%B6%9A%E9%80%A3
- 長氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%B0%8F
- 穴水城 : 能登有数の国士 長氏一族の居城だった中世山城跡。 - 城めぐりチャンネル https://akiou.wordpress.com/2016/11/26/anamizu/
- 穴水城の見所と写真・100人城主の評価(石川県穴水町) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1049/
- The Hatakeyama Family and the Siege of Nanao Castle https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/en/R4-00543,html
- (1)築城時期 七尾城は能登畠山氏の居城で https://www.city.nanao.lg.jp/sportsbunka/documents/sironojyoukyou.pdf
- 七尾城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%B0%BE%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 能登・七尾城 ~"軍神"上杉謙信をうならせた難攻不落の堅城 | WEB ... https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8240?p=1
- www.mlit.go.jp https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001653745.pdf
- その生き様まさに不屈!一族滅亡寸前の中で生き残った戦国武将 ... https://mag.japaaan.com/archives/236928
- 織田信長の合戦年表 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/84754/
- 七尾城の戦いとは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%83%E5%B0%BE%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84
- 長連龍とは? わかりやすく解説 - 戦国武将 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%95%B7%E9%80%A3%E9%BE%8D
- 七尾城のマンガが公開されました! [七尾城プロジェクト] | 攻城団 ... https://kojodan.jp/info/story/3471.html
- 長綱連(ちょう つなつら)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E7%B6%B1%E9%80%A3-1091624
- 長連竜(ちょう・つらたつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E9%80%A3%E7%AB%9C-1091625
- 長連龍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%80%A3%E9%BE%8D
- 長氏歴代当主 http://www1.cnh.ne.jp/minton2/Gallery-7-24-1-tiyou-rekidai.html
- 田鶴浜建具発祥の地・長連龍菩提寺「東嶺寺」【七尾市田鶴浜町】 - のとルネ https://noto-renaissance.net/toureiji/
- 北陸の歴史・郷土博物館 「穴水町歴史民俗資料館・長家史料館」(石川県鳳珠郡穴水町) https://nan-etsu.com/anamizu-history-museum/
- 寺院紹介(ペット火葬・供養・祈祷など石川県は七尾市三引町に ... http://www.iganin.net/newpage12.html
- 【歴史】加賀八家、長家ゆかりの古刹、大仏さんの頭が鎮座する悦 ... https://iijikanazawa.com/news/contributiondetail.php?cid=6112
- 瑞松山 悦叟寺 - 曹洞宗石川県宗務所 https://www.sotozen-net.jp/temple/82
- 国史跡 七尾城跡 http://www.pcpulab.mydns.jp/main/nanaojyo.htm
- 七尾市教育委員会 https://www.city.nanao.lg.jp/sportsbunka/documents/nanaojyoufouramu1_s.pdf
- 能登畠山氏の歴史 | 七尾城のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/54/memo/3474.html
- 長町武家屋敷跡 | 金沢城のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/53/memo/473.html
- 長町武家屋敷跡界隈 長町界隅について(町の成り立ち、うつりかわり ... https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/H30-00646.html
- 金沢観光【歴史と伝統】長町武家屋敷跡、野村家、老舗記念館など、歴史スポットを巡る - 金沢日和 https://www.kanazawabiyori.com/modelcourse/history.html
- 長町武家屋敷めぐり:金沢城下の藩政時代の名残を留める武家屋敷跡 https://www.usagitabi.com/nagamati.html