宇治拾遺物語
『宇治拾遺物語』は鎌倉時代の説話集。多様な物語と口語的な文体で、戦国乱世に処世術や娯楽として受容され、後世の狂言や御伽草子に影響を与えた。
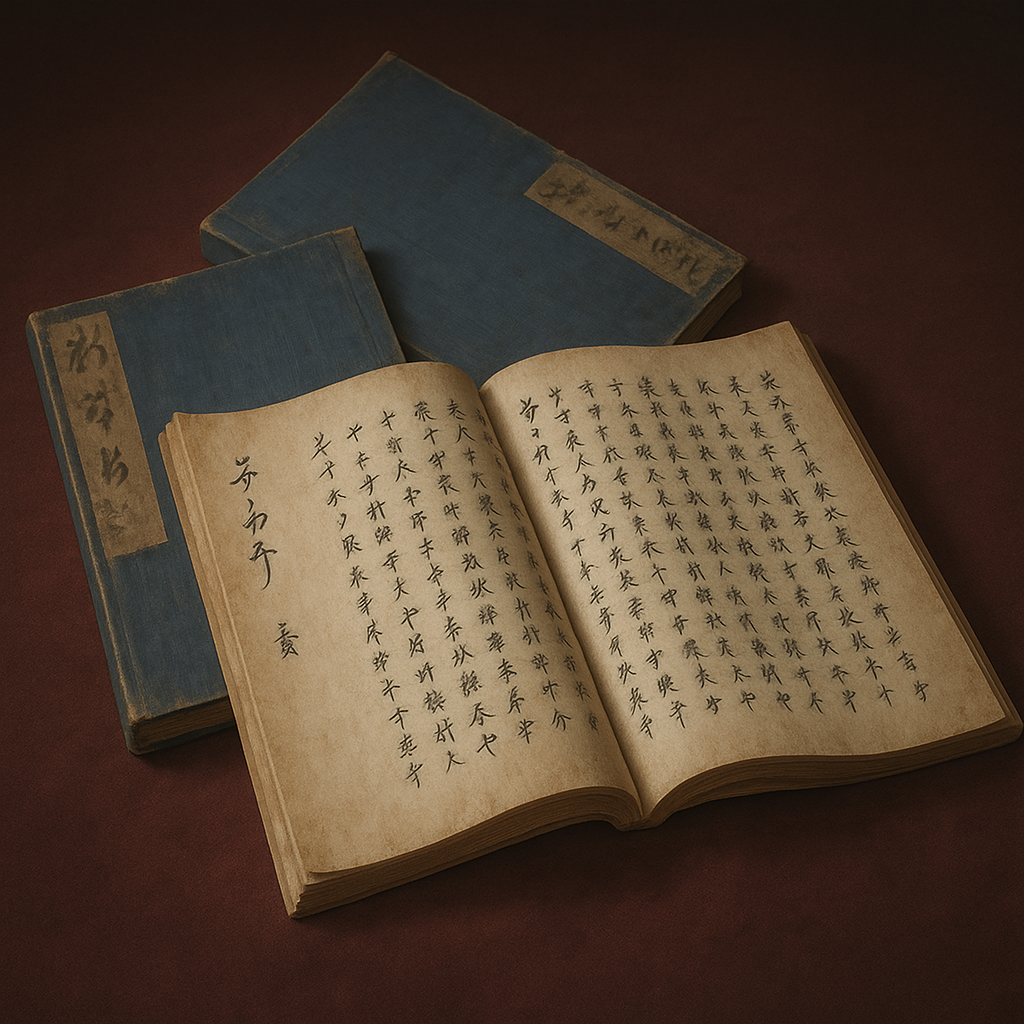
『宇治拾遺物語』の総合的考察 ―鎌倉の説話集は、戦国の乱世にいかに読まれたか―
序論:時代を超える物語の力
鎌倉時代初期、貴族の世が終わりを告げ、武士が新たな時代の担い手として台頭する激動のさなかに、一冊の説話集が編まれた。『宇治拾遺物語』である 1 。編者は詳らかでなく、その成立の詳しい経緯も謎に包まれているこの物語集は、仏の教えを説く荘重な話から、人の愚かさを笑う滑稽な話、さらには「こぶとり爺さん」や「雀の恩返し」といった後世の昔話の原型に至るまで、多種多様な物語を雑多に収めている 3 。
本報告書は、この鎌倉時代の産物である『宇治拾遺物語』を、単に古典文学の一作品として解説するに留まらない。約三百年後の戦国時代という、価値観が根底から覆され、下剋上が常態と化した乱世の視座から、この説話集がどのように読まれ、いかなる意味を持ち得たのかを徹底的に考察するものである。安定を求めたであろう旧時代の文化遺産が、なぜ実力のみがものをいう非情な時代に生きる人々の心に響いたのか。この問いを解き明かすことは、単なる作品研究を超え、時代を超えて生き続ける物語の力、そして文化の受容と変容のダイナミズムを明らかにすることに繋がるであろう。本報告は、作品そのものの構造的・文体的本質を解明する第一部と、戦国という時代のレンズを通してその多層的な価値を再発見する第二部から構成される。
第一部:『宇治拾遺物語』の全貌 ―作品の構造と本質―
第一章:成立の謎と背景
『宇治拾遺物語』の本質を理解するためには、まずそれが生まれた時代の空気と、その成立にまつわる謎めいた出自を深く掘り下げねばならない。
成立年代と時代背景
本作の成立は、鎌倉時代初期、建暦2年(1212年)から承久3年(1221年)頃と推定するのが通説である 1 。この時期は、平安時代以来の貴族中心の社会体制が大きく揺らぎ、武士階級が政治の実権を掌握していく過渡期にあたる。旧来の雅な価値観が相対化される一方で、地方や庶民の生活、そしてそこに生きる人々のありのままの姿に、新たな文学的関心が寄せられ始めた 6 。まさに「説話の時代」と称されるように、人々の口の端にのぼる様々な「はなし」を蒐集し、記録しようとする気運が高まっていたのである。
編者と成立経緯
『宇治拾遺物語』の大きな謎の一つは、編者が誰であるか全く不明であるという点だ 1 。特定の個人の思想や編集方針を前面に出すことなく、あたかも「世間の声」そのものを集めたかのような体裁を取っている。この編者の匿名性は、結果として作品に普遍性を与え、貴族、僧侶、武士、庶民といった多様な階層の物語が違和感なく混在することを可能にした。
作品の序文によれば、その成立には先行する一冊の説話集が深く関わっているとされる 5 。それは、平安後期の貴族であり、「宇治大納言」と称された源隆国が編んだと伝えられる『宇治大納言物語』である 9 。この『宇治大納言物語』は現在では散逸してしまったが、『宇治拾遺物語』の序文は、自らがその増補版であるか、あるいはそこから漏れた話を拾い集めたものであることを示唆している 5 。新興の武士や庶民の話題を多く含みながらも、その源流を源隆国という高名な貴族が編んだとされる由緒ある物語に接続すること。これは、作品としての正統性を主張し、多様な読者層に受け入れられる素地を形成するための、巧みな戦略であったと解釈することも可能であろう。
書名の由来
書名である「宇治拾遺物語」の由来についても、複数の説が存在する。最も一般的な解釈は、前述の通り『宇治大納言物語』から「拾い遺(おと)された」話を集めた「拾遺集」という意味であるとする説だ 2 。
しかし、もう一つ有力な説がある。室町時代の公卿である三条西実隆が記した日記『実隆公記』の文明7年(1475年)の条に、彼が『宇治大納言物語』や『宇治拾遺物語』といった書物を読んだ記録が残されている 5 。これらの書物が同一のものを指す可能性が高いことから、「拾遺」を「拾い集める」という意味ではなく、侍従の唐名(中国風の官職名)である「拾遺」に由来すると考える説である。これは、物語の編纂に関わった人物の官職にちなむという解釈であり、作品の出自に関するさらなる謎を投げかけている。
第二章:雑多なる説話の宇宙
『宇治拾遺物語』の最大の魅力は、その混沌ともいえる内容の多様性にある。全197話(流布本)は、聖と俗、貴と賤、善と悪といったあらゆる価値観を内包し、さながら一つの小宇宙を形成している。
構成の三大別
収録された説話は、内容によって大きく三つに分類することができる 5 。
- 仏教説話 : 高僧の奇跡譚や発心・往生の物語、あるいは戒律を破った僧侶の滑稽な失敗談など、仏教にまつわる話。ただし、後述する『今昔物語集』に比べて教訓臭は薄い 1 。
- 世俗説話 : 貴族社会の裏話、盗人や武士の活躍、機知に富んだ滑稽譚、男女の恋愛話など、人々の世俗的な営みを描いた話。本作の人間観察の鋭さが最も発揮される領域である 4 。
- 民間伝承 : 「鬼に瘤取らるる事」(こぶとり爺さん)、「雀報恩の事」(舌切り雀)、「長谷寺参籠の男、利生にあづかる事」(わらしべ長者)など、後世に広く知られる昔話の原型となった物語群 3 。
地理的・内容的広がり
物語の舞台は日本国内に留まらない。序文が「天竺の事もあり、大唐の事もあり、日本の事もあり」と記すように、インド、中国、そして日本という三国にまたがる広大な世界観を持っている 11 。
さらに序文は、内容の多様性を「それがうちに貴き事もあり、をかしき事もあり、恐ろしき事もあり、あはれなる事もあり、汚き事もあり」と表現する 15 。聖人の高貴な振る舞いが語られたかと思えば、次の話では人間の卑俗な欲望が赤裸々に描かれる。このような意図的な無秩序、すなわち雑纂(ざっさん)形式こそが、本作の編纂における最大の特徴である 16 。この一見無秩序な配列は、実は現実世界の混沌そのものを写し取ろうとする意図の表れとも考えられる。平安時代の『源氏物語』が描き出したような、洗練され秩序づけられた世界とは対照的に、鎌倉時代初期の社会の流動性や多様性をありのままに体現しているのである。聖なる話の直後に卑俗な笑い話が置かれることで、読者は人間の多面性や世界の予測不可能性を体感させられる。
編纂意図の考察
『宇治拾遺物語』は、明確な教訓を押し付けることを意図的に避けているように見える。もちろん、話の最後に「話末評語」として批評や教訓めいた言葉が添えられることもあるが、それすらも絶対的なものではない 17 。むしろ編者の関心は、善悪の彼岸から人間の欲望、愚かさ、賢さといったありのままの姿を客観的に描写し、そこに面白さを見出すことに向けられている 12 。これは、絶対的な価値観が崩壊し始めた時代の空気を色濃く反映している。単純な善悪二元論の物語よりも、このような複雑な人間観察の記録こそが、後の戦国時代の武将たちにとって、より実践的な処世術や人間心理の機微を学ぶためのテキストとなり得たのである。
第三章:文体と語りの妙
『宇治拾遺物語』の文学的価値を際立たせているのが、その独特の文体と語り口である。特に、先行する大説話集『今昔物語集』との比較は、本作の個性を浮き彫りにする。
『今昔物語集』との比較
『宇治拾遺物語』は、平安後期に成立した『今昔物語集』と約80話もの共通する説話を持つ 9 。しかし、研究者の間では、直接『今昔物語集』から話を取ったのではなく、両者が共に散逸した『宇治大納言物語』のような共通の源泉から取材した結果、内容が重なったと考えるのが一般的である 20 。
両者の決定的な違いは文体にある。『今昔物語集』が漢文の語彙や構造を多用した漢文訓読調の硬質な文体(和漢混淆文)で書かれているのに対し、『宇治拾遺物語』は、話し言葉に近い、流れるような和文調(仮名主体)で記されている 16 。この文体の違いが、物語の印象を大きく左右する。例えば、同じ説話を扱っていても、登場人物の名前や設定に差異が見られ、『宇治拾遺物語』の方がより細やかな情景描写や心理描写を試みている場合がある 22 。
この差異を明確にするため、以下の表に両者の特徴をまとめる。
表1:『宇治拾遺物語』と『今昔物語集』の比較
|
項目 |
宇治拾遺物語 |
今昔物語集 |
|
成立年代 |
13世紀前半(1212-1221年頃) |
12世紀前半(1120年頃) |
|
編者 |
未詳 |
源隆国説など諸説あるが未詳 |
|
巻数・話数 |
15巻・197話(流布本) |
31巻(うち3巻欠)・1059話 |
|
文体 |
和文調(仮名主体) |
漢文訓読調(和漢混淆文) |
|
語りの特徴 |
ユーモラス、写実的、生き生きとしている |
荘重、教訓的、定型的 |
|
構成 |
雑纂形式(分類なし) |
体系的(天竺・震旦・本朝の三国構成) |
|
思想的背景 |
仏教色は薄く、人間中心 |
仏教的因果応報思想が濃厚 |
語りの特徴
『今昔物語集』の文体が、出来事を客観的かつ権威的に「報告」するものであるとすれば、『宇治拾遺物語』のそれは、読者の耳元で面白い話を「語り聞かせる」口調に近い。この親しみやすさと臨場感が、読者の感情移入を促し、物語を単なる教訓ではなく、自分事として捉えさせる効果を持つ。
その語り口は、ユーモア、風刺、皮肉に満ちている 2 。時に語り手は、物語の中に深く没入し、登場人物と一体化してその言動を演じているかのような躍動感を生み出す 23 。この「共感性」の高さこそが、時代を超えて人々を惹きつけ、特に戦国時代のような過酷な時代において、一種の清涼剤や娯楽として機能した重要な要因であったと考えられる。
第二部:戦国時代のレンズを通した『宇治拾遺物語』
鎌倉時代に生まれた『宇治拾遺物語』は、いかにして戦国の世まで伝わり、当時の権力者や民衆にどのように受容されたのか。ここでは、時代というレンズを通して、物語が新たな意味を付与されていく過程を追う。
第一章:乱世における古典の伝承と価値
物理的伝承
『宇治拾遺物語』は、鎌倉時代から戦国時代にかけて、主に写本として伝えられてきた。当初は上下二巻本などの形態であったものが、後世に十五巻本として流布するなど、時代と共にその姿を変えていった 2 。安土桃山時代から江戸時代初期にかけては、日本で初期の活版印刷技術である古活字版も刊行されており、一定の読者層と需要が存在したことを物語っている 2 。
公家社会における受容
戦国時代の公家社会における受容の実態を示す、極めて重要な史料が存在する。当代随一の文化人であった三条西実隆の日記『実隆公記』である。その記述によれば、文明7年(1475年)、応仁の乱(1467-1477年)の戦火が未だ収まらない京の都で、実隆は後土御門天皇の御前で連日にわたり『宇治大納言物語』(『宇治拾遺物語』と同一視される)を読み上げている 5 。
この行為は、単なる娯楽の提供以上の意味を持っていた。政治的実権をほぼ失った朝廷が、その存在意義を「文化の守護者」という役割に見出そうとした象徴的行為であった。戦乱という究極の「現実」に対し、物語という「虚構」を対置させることで、荒廃した人心を慰撫し、人間性の回復を図ったのである 26 。また、奏読された『宇治拾遺物語』の貴賤聖俗を問わぬ多様な内容は、崩壊した社会のあらゆる側面を内包しており、混沌とした現実を理解し、受容するための哲学的営みであったとも解釈できる。
武家社会における価値
一方、戦国の武将たちが古典に求めたのは、雅な教養だけではなかった。彼らが求めたのは、裏切りや陰謀が渦巻く乱世を生き抜くための、より実践的な知恵、すなわち「処世術」であった 27 。その点で、『宇治拾遺物語』は格好の「人間学の教科書」として機能した可能性がある。
物語に登場する賢者、愚者、詐欺師、正直者といった多様な人間像は、敵や味方の本質を見抜くためのケーススタディとなったであろう。「利仁、芋粥の事」における五位と利仁の身分と欲望の対比 29 や、「袴垂、保昌に合ふ事」に見られる盗人と武士の息詰まる心理戦 14 などは、人の器量を見抜き、相手の裏を読むための具体的な教材となり得た。物語を読む行為が、戦略思考を鍛えるためのシミュレーションとして機能していたとしても不思議ではない。
第二章:戦国の価値観に響く物語
『宇治拾遺物語』の個々の説話は、戦国時代の主要な価値観と深く共鳴するテーマを内包していた。鎌倉時代に編まれた物語は、戦国の世において、本来の文脈から切り離され、新たな目的のもとに読み替えられていったのである。
無常観と現実主義
例えば、「利仁、芋粥の事」で描かれる、あれほど渇望した芋粥を飽きるほど振る舞われ、かえってその欲望の虚しさを知る五位の姿は、仏教的な無常観に通じる 29 。昨日の勝者が今日の敗者となる戦国の世の現実を生きる武将たちにとって、この物語は「執着は身を滅ぼす」という極めて現実的な教訓として響いたであろう。
また、芥川龍之介の小説「鼻」の原話として知られる「鼻長き僧の事」は、他人の目を過剰に気にする人間の滑稽な自意識を風刺している 4 。権威や虚飾が意味をなさなくなった実力主義の戦国時代において、人間の本質を突くこの物語は、痛烈な人間批評として受け止められた可能性がある。
実力と機知の称揚
本作には、身分は低くとも、その才覚や機知によって困難を乗り越え、あるいはしたたかに生き抜く人物が数多く登場する。盗人の鮮やかな手口を語る話 1 や、地方武士の活躍譚 30 などは、出自を問わず実力でのし上がることができた「下剋上」の時代精神を肯定するものとして、多くの人々に勇気と示唆を与えたに違いない。
教訓と戒め
一方で、人間関係が殺伐とし、裏切りが横行する乱世において、『宇治拾遺物語』が示す素朴な教訓は、かえって重要な処世の指針として機能した。「鬼に瘤取らるる事」の結びにある「ものうらやみはせまじきことなりとか(人を羨んではいけない)」という戒め 13 や、「雀報恩の事」が示す因果応報の理は、共同体の秩序が崩壊した時代だからこそ、心に刻むべき知恵として再評価されたと考えられる。
第三章:大衆文化への展開 ―狂言と御伽草子への影響―
『宇治拾遺物語』の精神は、書物の中に留まらなかった。それは、戦国時代に成熟期を迎えた新たな大衆文化の源流となり、より広い層へと浸透していった。
狂言への影響
室町時代に成立し、戦国時代にかけて大成した庶民の喜劇「狂言」は、人間の滑稽さや日常に潜む笑いを描く点で、『宇治拾遺物語』の世俗説話と精神を共有している 31 。「こぶとり爺さん」は、狂言の演目としても知られており、本作が直接の原話となった代表例である 13 。『宇治拾遺物語』の持つ、時に辛辣で、時に大らかな笑いの精神が、洗練された舞台芸術へと昇華されていったのである。死と隣り合わせの時代において、「笑い」は精神の均衡を保つための重要な文化装置であった。権力者を風刺し、人間の愚かさを笑い飛ばす狂言の精神は、その原型を『宇治拾遺物語』に見出すことができる。
御伽草子への影響
室町時代から安土桃山時代にかけて成立した、絵入りの短編物語群「御伽草子」もまた、『宇治拾遺物語』から多大な影響を受けている。「こぶとり爺さん」や「わらしべ長者」といった物語は、御伽草子の人気作として広く親しまれた 34 。
この過程で重要なのは、物語の変容である。『宇治拾遺物語』の各説話は、自己完結した「モジュール」として極めて扱いやすい性質を持っていた。そのため、狂言作者や御伽草子の編者たちは、これらのモジュールを自由に抽出し、自分たちの目的に合わせて再構成・脚色することが容易だった。この「モジュール性」こそが、『宇治拾遺物語』が後代の多様な文化の源泉となり得た最大の理由であり、その生命力の秘密である。説話集という断片的な形式から、より物語性の高い読み物へと形を変えることで、物語は公家や武士といった知識層だけでなく、より広い階層へと届けられていったのである 35 。
結論:鎌倉から戦国へ ―変容する解釈と物語の生命力―
本報告書は、『宇治拾遺物語』を、鎌倉時代初期の流動的な社会を反映した「雑多なる説話の宇宙」として捉え、その特質を分析してきた。そして、その雑多性、人間観察の鋭さ、共感を呼ぶ語り口が、約三百年後の戦国の世において、新たな価値と意味を付与されながら受容されていった過程を明らかにした。
公家にとっては、それは失われゆく文化の最後の砦であり、精神的な慰撫であった。武将にとっては、乱世を生き抜くための実践的な人間学の教科書であった。そして民衆にとっては、過酷な現実を忘れさせる娯楽であり、処世の知恵の源泉であった。同じ物語が、読む者の立場や時代の要請に応じて、全く異なる貌を見せたのである。
『宇治拾遺物語』の事例は、文学作品の価値が、作者の意図や成立時の文脈だけで固定されるものではないことを雄弁に物語っている。その真価は、後代の読者がいかに読み、解釈し、自らの文化の中に再生産していくかという「受容」の過程で絶えず創造され続ける。このダイナミズムこそが、本作が鎌倉から戦国、そして現代に至るまで、日本文化史において不朽の価値を持つ所以なのである。
引用文献
- 高等学校国語総合/宇治拾遺物語 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E7%B7%8F%E5%90%88/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E6%8B%BE%E9%81%BA%E7%89%A9%E8%AA%9E
- 宇治拾遺物語 - 古典文学 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=201
- 宇治拾遺物語|要約・解説・原文(一部) - 日本文学ガイド https://koten.sk46.com/sakuhin/uji.html
- タイトル一覧 |日本古典文学全集 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/contents/koten/title.html?era=%E4%B8%AD%E4%B8%96&genre=%E8%AA%AC%E8%A9%B1
- 宇治拾遺物語 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E6%8B%BE%E9%81%BA%E7%89%A9%E8%AA%9E
- 宇治拾遺物語 | 書物で見る日本古典文学史 | 国文学研究資料館 https://www.nijl.ac.jp/etenji/bungakushi/contents/detail/detail03-01_011.html
- 時代を彩る日本文学:平安から近代まで詳しく解説 - BesPes https://article.bespes-jt.com/ja/article/japanese-literature
- 宇治拾遺物語|日本の文学史いちらん|国語の部屋 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/~gakusyuu/bungaku/uzisyuuimonogatari.htm
- 日本人なら知っておきたい文学作品!平安時代に成立した日本最大の説話集『今昔物語』 https://chugaku-juken.com/konnzyakumonogatari/
- 宇治大納言物語(ウジダイナゴンモノガタリ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E5%A4%A7%E7%B4%8D%E8%A8%80%E7%89%A9%E8%AA%9E-34493
- 宇治拾遺物語 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E6%8B%BE%E9%81%BA%E7%89%A9%E8%AA%9E
- 宇治拾遺物語 http://www.mapbinder.com/Dictionary/Ujisyui.html
- こぶとりじいさん - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%93%E3%81%B6%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%98%E3%81%84%E3%81%95%E3%82%93
- 宇治拾遺物語 概要・目次 - 古典の改め https://classicstudies.jimdofree.com/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E6%8B%BE%E9%81%BA%E7%89%A9%E8%AA%9E/
- 宇治拾遺物語 https://hijiyama-u.repo.nii.ac.jp/record/1249/files/13-2.pdf
- 宇治拾遺物語 [やたがらすナビ] https://yatanavi.org/rhizome/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E6%8B%BE%E9%81%BA%E7%89%A9%E8%AA%9E
- ﹃宇治拾遺物語﹄説話の文章構造 http://doshishakokubun.koj.jp/koj_pdfs/06609.pdf
- Untitled https://doshisha.repo.nii.ac.jp/record/10181/files/j17004.pdf
- 文明七年(一四七五)十一月、当時蔵人頭だった三条西実隆は 後土御門天皇の御前で『宇治大納言物語』を読んでいた『実隆公 記』)。 - CORE https://core.ac.uk/download/144433930.pdf
- yatanavi.org https://yatanavi.org/rhizome/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E6%8B%BE%E9%81%BA%E7%89%A9%E8%AA%9E#:~:text=%E3%80%8E%E4%BB%8A%E6%98%94%E7%89%A9%E8%AA%9E%E9%9B%86%E3%80%8F%E3%81%A8%E5%A4%9A%E3%81%8F,%E3%81%AE%E8%AA%AC%E8%A9%B1%E3%82%92%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82
- 田中牧郎・山元啓史(2014.1)『今昔物語集』と『宇治拾遺物語』の同文説話における語の対応:語の文体的価値の記述 - ronbun yomu https://hjl.hatenablog.com/entry/2018/11/14/100000
- 『今昔物語集』巻二十四の考察 https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/26658/files/CLC_12_006.pdf
- 宇治拾遺物語の表現に関する考察 https://fwu.repo.nii.ac.jp/record/2041/files/KJ00000148934.pdf
- 宇治拾遺物語 (上本1) - 書陵部所蔵資料目録・画像公開システム - 宮内庁 https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Detail/1000508250001
- 宇治拾遺物語 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100238481
- 原勝郎 東山時代における一縉紳の生活 - 青空文庫 https://www.aozora.gr.jp/cards/001037/files/4995_17362.html
- 戦国武将の「リストラ」逆転物語 - HMV&BOOKS online https://www.hmv.co.jp/artist_%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97_000000000627677/item_%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%80%8D%E9%80%86%E8%BB%A2%E7%89%A9%E8%AA%9E_5541940
- 春秋戦国の処世術 : 中国古典に学ぶ「逆転の寓話」 - 新書マップ https://shinshomap.info/book/9784061496583
- 『宇治拾遺物語』「利仁暑預粥事(利仁、芋粥の事)」を読む ... https://heianmagazine.com/literature/ujisyuuimonogatari-imogayu
- 天武天皇伝承~宇治拾遺物語 | スポット一覧 | 京都府観光連盟公式サイト https://www.kyoto-kankou.or.jp/info_search/9108
- 楽天Kobo電子書籍ストア: 日本霊異記/今昔物語/宇治拾遺物語/発心集 - 伊藤比呂美 - 8909121457282 - 楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rk/7d00f725a6e238ec8543dc686d0f18b5/
- 新編 日本古典文学全集60・狂言集 | 書籍 - 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/books/09658060
- 日本霊異記/今昔物語/宇治拾遺物語/発心集 - 伊藤比呂美/福永武彦 - 小説・無料試し読みなら、電子書籍・コミックストア ブックライブ https://booklive.jp/product/index/title_id/456829/vol_no/001
- 本の紹介『宇治拾遺物語』 - 逍遊ゼミナール https://shoyu-seminar.com/archives/2507
- お伽草子における異類物の文学的意義 ―動物物(どうぶつもの)を中心に― https://nagasaki-u.repo.nii.ac.jp/record/619/files/SKK46_Moku.pdf