新当流兵法書
「新当流兵法書」は飯篠長威斎の香取神道流伝書。戦国乱世に「兵法は平法なり」と説き、総合武術を確立。血判と巻物で伝授され、塚原卜伝ら剣聖に影響を与えた日本武術の源流。
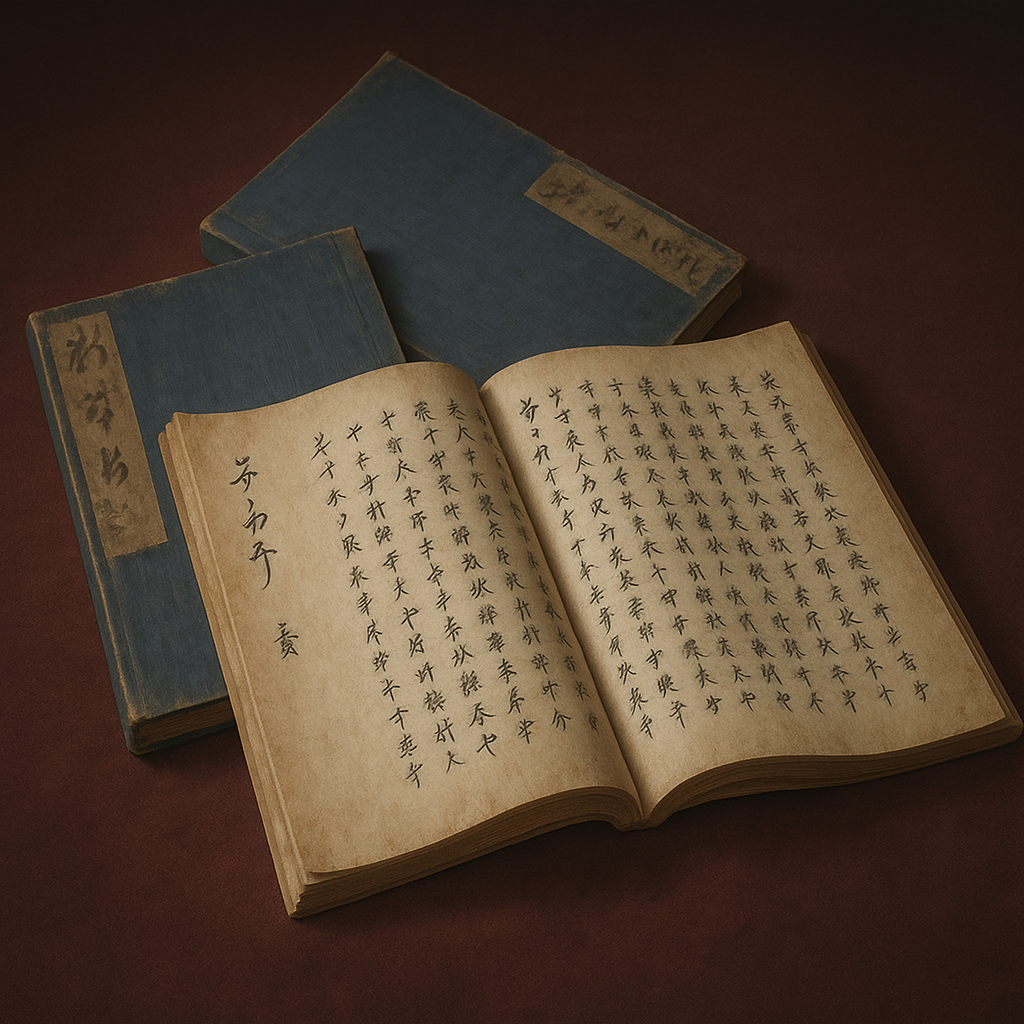
戦国時代における『新当流兵法書』の歴史的実像と天真正伝香取神道流の思想体系に関する総合的研究
序論:『新当流兵法書』を巡る問い ― 名称の曖昧性と本報告書の射程
「新当流兵法書」という名称は、日本の武術史、特に戦国時代を考察する上で、一筋縄では解き明かせない複雑な対象である。この名称は、特定の単一の書物を指し示すものではなく、室町時代中期に飯篠長威斎家直(いいざさちょういさいいえなお)が創始した天真正伝香取神道流(てんしんしょうでんかとりしんとうりゅう、以下、香取神道流)が、その成立初期において「新当流(しんとうりゅう)」とも呼称されており、その流派の思想と技術を記した伝書群を指す可能性が極めて高い 1 。
しかしながら、この問題をさらに複雑にしているのは、香取神道流の系譜に連なる不世出の剣豪、塚原卜伝高幹(つかはらぼくでんたかもと)が創始した流派もまた、同じく「新当流(しんとうりゅう)」と称されているという歴史的事実である 3 。これにより、後世の研究や伝承において、両者の区別が曖昧になり、歴史的な混同が生じやすい状況が生まれてきた。この名称を巡る曖昧性を解き明かし、その歴史的実体を特定することこそ、本報告書の重要な目的の一つである。
したがって、本報告書は、まず流祖・飯篠長威斎という人物の実像と、彼が生きた戦国乱世という時代背景に深く迫ることから始める。次に、香取神道流が単なる剣術に留まらない広範な「総合兵法」としての体系を解き明かす。その上で、「新当流兵法書」と称される伝書群の具体的な内容と、それが担った役割を分析し、最後に、戦国時代の武術史全体における香取神道流の広範かつ深遠な影響を論証する。この多角的なアプローチを通じて、「新当流兵法書」という言葉が指し示す歴史的遺産の真価を明らかにすることを目指す。
第一章:流祖・飯篠長威斎家直の実像 ― 戦国乱世に「平法」を求めた兵法家
1.1 生涯と時代背景:武士としての栄光と幻滅
飯篠長威斎家直は、日本の武術史において、その源流を形成した最重要人物の一人である。彼の出自は下総国香取郡飯篠村(現在の千葉県香取郡多古町)の郷士とされ、当初は地域の有力大名であった千葉氏に仕える武士であったと伝わる 6 。彼の生没年については諸説が存在し、元中4年(1387年)に生まれ、長享2年(1488年)に没したとする「102歳説」が広く知られている 6 。一方で、享年68歳とする説もあり 6 、確定には至っていないが、その驚異的な長寿の伝承が、彼の人物像に伝説的な色彩を与えていることは間違いない。
長威斎の思想形成の根源を理解するためには、彼が生きた時代、すなわち室町時代中期から戦国時代初期にかけての社会状況を把握することが不可欠である。この時代は、応仁の乱を経て旧来の権威が失墜し、全国各地で「下剋上」の風潮が蔓延する、まさに先の見えない混沌の時代であった。そのような中で、長威斎が仕えていた主家・千葉氏が内紛の末に滅亡するという悲劇が起こる 8 。これは、彼にとって単に仕官先を失うという個人的な出来事に留まらなかった。武士として戦場で武功を立て、忠義を尽くすことの虚しさ、そして人の命が軽んじられる乱世の非情さを、身をもって痛感する決定的な体験であったと推察される。
この武士としての生き方に対する深い幻滅こそが、長威斎を既存の武術観から脱却させ、新たな道の探求へと向かわせた原動力であった。彼は、敵を効率的に殺傷するための技術としての「兵法」に疑念を抱き、武術が本来持つべき真の意味を問い直すべく、俗世を離れて精神的な遍歴の道へと足を踏み入れたのである。彼の探求は、戦国の現実との厳しい対峙の中から生まれた、極めて切実なものであった。
1.2 香取神宮での悟りと神道流の創始:神託による正統性の確立
武士としての道を捨てた長威斎は、六十余歳にして、武神・経津主大神(ふつぬしのおおかみ)を祀る下総国一之宮、香取神宮に精神的な救いと新たな指針を求めた。彼は神宮に隣接する梅木山の不断所と呼ばれる修行の場に、実に千日間にも及ぶ参籠を行ったと伝えられている 11 。斎戒沐浴し、兵法の修練に明け暮れるという粉骨砕身の修行の末、ついに彼は神託を得て、剣の極意に達したとされる。
伝承によれば、修行満願の夜、長威斎の夢に経津主大神の化身が現れ、「汝、後に天下剣客の師とならん」との啓示と共に、一巻の神書を授けられたという 8 。この神からの啓示こそが、彼の流派が「天真正伝(てんしんしょうでん)」、すなわち「天の神から正しく伝えられた」という名を冠する由来となった 8 。
この「神託」という形式は、戦国時代という文脈において極めて重要な意味を持つ。当時、新たな流派を創始し、多くの門人を集めるためには、単に技術が優れているだけでは不十分であった。その教えがいかに正統であり、高い権威を持つかを証明する必要があったのである。長威斎は、自らが編み出した兵法を、一個人の創意工夫によるものではなく、武神から直接授けられた神聖不可侵の教えであると位置づけた。これは、神仏への信仰が武士の精神生活の根幹をなしていた当時の価値観 14 に深く訴えかけるものであり、他のいかなる流派も持ち得ない絶対的な優位性と、疑う余地のない権威を自らの流派に与えるための、卓越した戦略であったと解釈できる。神託は、香取神道流という新たな武術体系の誕生を告げる、荘厳な宣言だったのである。
1.3 「兵法は平法なり」― 長威斎の思想的革命
香取神道流の教えの核心であり、長威斎が到達した思想的頂点を示すのが、「兵法は平法(へいほう)なり」という理念である 8 。これは、武術(兵法)の究極的な目的は、敵を打ち破り殺傷すること(武力による支配)にあるのではなく、争いを未然に防ぎ、人と社会に平和と秩序をもたらすこと(平法)にある、という画期的な思想であった。
この思想は、「敵に勝つ者を上とし、敵を討つ者はこれに次ぐ」という彼の言葉に端的に表れている 17 。これは、実際に戈を交えて敵を討ち取るよりも、戦うことなくして相手を屈服させ、争いを収めることこそが、兵法の最も優れたあり方であると説くものである。この理念は、戦国という、より効率的に敵を殺傷する技術が追求された時代において、極めて逆説的であり、武術の価値基準そのものを転換させる革命的なものであった。
長威斎は、武術の価値を「殺傷能力の高さ」から「争いを抑止し、平和を構築する能力の高さ」へと昇華させたのである。この思想に基づき、彼は自らの道場を武士だけでなく、広く庶民にまで開放し、単なる戦闘技術としてではなく、人間完成を目指す心身鍛錬の「道」として武術を教えたと伝えられている 8 。これは、武術を個人の技から、社会全体の安寧に貢献するための普遍的な教えへと高める試みであり、後の武士道精神の形成にも多大な影響を与えた、日本思想史における重要な源流の一つと位置づけることができる。
第二章:天真正伝香取神道流の全貌 ― 日本武術の源流
2.1 総合武術としての体系:戦場のリアリズムが生んだカリキュラム
天真正伝香取神道流が「日本武道の源流」と称される最大の理由は、その体系が特定の武技に限定されず、戦場で生き抜くために必要なあらゆる知識と技術を網羅した「総合兵法」である点にある 11 。その内容は、剣術(太刀術、小太刀術、両刀)や居合術(抜刀術)といった刀剣の技法を中核としながらも、槍術、薙刀術、棒術といった長柄武器の操作、さらには至近距離での組討術である柔術、飛び道具である手裏剣術にまで及ぶ 2 。
しかし、香取神道流の射程はこれに留まらない。個人の戦闘技術に加え、軍勢の配置や進退を指揮する軍配法、城の設計や防御、攻略を学ぶ築城術、天候や地形を読んで戦術に活かす天文地理学、果ては敵地への潜入や情報収集を担う忍術までが、その広大なカリキュラムに含まれていた 11 。
この驚くべき網羅性は、単なる技術の寄せ集めではない。それは、戦国時代の高位の武士、すなわち一軍を率いる将が担うべき職務を完全に反映した、極めて実践的な教育体系であった。当時の武将には、一対一の個人的な武勇だけでなく、集団戦を指揮する能力、戦略的な拠点(城)を構築・防衛する知識、そして戦況を有利に導くための情報戦に至るまで、多岐にわたる能力が求められた。香取神道流は、いわば「戦国武将養成のための統合カリキュラム」であり、その実用性と包括性こそが、塚原卜伝や上泉信綱をはじめとする多くの武将や兵法家たちを惹きつけ、後世の数多の流派の母体となる礎を築いたのである。
2.2 戦国時代の戦闘術:甲冑を前提とした技法
香取神道流の形稽古には、それが生まれた戦国時代の戦闘の様相が、生々しいリアリズムをもって刻印されている。その技法の多くは、当時の武士が戦場で身に纏った甲冑、すなわち鎧兜を着用した状態での戦闘を前提として構築されている 2 。
そのため、刀で斬りつけても効果の薄い胴や兜の固い部分を狙うのではなく、甲冑の構造的な隙間や可動部分、すなわち防御の薄い弱点を正確に突くことを目的としている。具体的には、兜の錣(しころ)の下から狙う首筋、胴と草摺(くさずり)の間、脇の下、籠手(こて)で覆われない腕の内側、そして股といった、人体の急所が露出する箇所を、斬る、あるいは突く技法が数多く伝承されている 2 。
また、香取神道流の形は、他流派に比べて一つ一つが非常に長く、打太刀(うけだち、師匠役)と仕太刀(したち、弟子役)が何度も激しく技を応酬する複雑な構成を持つ 2 。これには二つの目的があったと考えられる。第一に、一進一退の攻防が続く戦場の過酷な状況を擬似的に再現し、それに耐えうる強靭な体力と気力、そして集中力を養うためである。第二に、技の真の狙いや極意を、部外者や未熟な門人が容易に盗み見ることができないよう、巧妙にカモフラージュする役割も果たしていた 20 。稽古中に木刀を激しく打ち合わせる音も、本来は肉を断ち骨を砕く斬撃の激しさを表現しつつ、真の狙いを隠すための工夫であったと解釈できる 20 。さらに、技を繰り出す際に発せられる「ヤー、トー」という独特の掛け声も、明治時代の資料に記録されるなど、古くからの特徴として知られている 2 。
2.3 伝授の体系:血判と巻物による知の継承
香取神道流への入門は、現代の武道団体のように単に書類を提出して会費を納めるのとは全く異なる、極めて厳粛な儀礼から始まる。それは「敬白神文之証(けいびゃくしんもんのあかし)」と呼ばれる誓紙に、自らの血をもって署名捺印する「血判」の儀式である 11 。この誓紙には、門人として守るべき厳しい規則が記されており、その内容は、流儀の教えを親子兄弟であっても他言しないこと、無闇に他者と争い兵法を用いないこと、免許なくして他流試合を行わないことなど、技術の悪用と漏洩を固く禁じるものであった 21 。
この血判という行為は、単なる形式的な契約ではない。それは、流派の守護神である香取大神に対して神聖な誓いを立てることで、門人となる者を俗世の人間関係から一旦切り離し、流儀という閉鎖的かつ神聖な知識共同体の一員として再定義する、強力な通過儀礼であった。生死に関わる危険な技術と思想を伝授するにあたり、神との契約という形で門人の倫理観に深く訴えかけ、流儀への絶対的な忠誠とコミットメントを確固たるものにするための、極めて効果的な心理的・社会的メカニズムだったのである。
流儀の技術と思想の伝授は、現代武道で一般的な段級位制ではなく、稽古の進捗、技術の習熟度、そして人格や流儀への貢献度などを師範が総合的に判断し、宗家から授与される「巻物」によって段階的に行われる 23 。これらは一般に「目録」「免許」「極意皆伝」といった階梯に分かれており、巻物を授かることは、単に技術レベルが向上したことの証明に留まらず、流儀の奥義に触れることを許された、正統な継承者であることの証であった 19 。近年、流派の権威と技術の正確性を守るため、この伝統的な伝授体系を補完するものとして、新たに「審査制度」も導入されている 2 。
第三章:『新当流兵法書』の正体 ― 伝書の内容と意義
3.1 現存する伝書とその記述:断片から実像を探る
「新当流兵法書」という具体的な名称を持つ史料は、断片的ではあるものの現存している。その代表的なものが、天正年間(1573年~1592年)に香取神道流の第六代(あるいは第七代)宗家であった飯篠盛繁(いいざさもりしげ)が記したと伝わる伝書である 1 。この伝書には、流祖・長威斎の出自について、一般的な下総国出身説とは異なり、「若狭国(現在の福井県)の住人」であり、香取神宮に参籠する以前に念阿弥慈恩(ねんあみじおん)が創始した「念流」の兵法を学んでいた、という極めて興味深い記述が含まれている 1 。これは、流派の創生期において、その来歴に関する複数の伝承が並存していた可能性を示唆しており、流派の歴史を多角的に捉える上で重要な史料である。
また、これとは別に、大分県の旧家に伝わる「盛嶽文書(もりだけもんじょ)」の中には、永禄8年(1565年)に藤原廣豊という人物が盛嶽氏に発行した『新当流兵法書』も確認されている 24 。さらに、『天真正飯篠目録』と題された伝授巻の存在も知られており 25 、これらの史料を総合的に勘案すると、「新当流兵法書」とは、特定の単一の書物を指す固有名詞ではなく、創始から戦国時代にかけての香取神道流の教えを記した伝書群の総称、あるいはその一系統の名称であったと結論づけるのが最も妥当である。
3.2 兵法書が担う役割:文字と口伝の二重構造
戦国時代における「兵法書」、すなわち「伝書(でんしょ)」や「巻物」が担っていた役割は、現代における教科書やマニュアルとは根本的に異なっていた。宮本武蔵が著した『五輪書』がそうであるように 26 、また中国古来の兵法書『孫子』や『呉子』が戦略・戦術の原理原則を説くように 27 、当時の兵法書は、技術の全てを網羅的に解説したものではなかった。
むしろ、その内容は流派の奥義や思想の核心部分を、極めて簡潔かつ象徴的な言葉や図、あるいは暗号めいた表現で記したものが大半であった。その真意を正確に理解するためには、師から弟子へと、面授(直接対面して教えること)によって伝えられる「口伝(くでん)」が不可欠であり、文字として記された伝書と、言葉で伝えられる口伝は、決して切り離すことのできない表裏一体の関係にあった 23 。
この二重構造は、複数の重要な機能を果たしていた。第一に、難解な記述は、部外者や敵対する流派による技術の盗用を防ぐための、一種のセキュリティ機能を有していた。第二に、巻物の授与という形式は、門弟間の階層秩序を可視化し、流派という知識共同体の内部結束を強める役割を担った。そして最も重要なのは、巻物を授かるという行為が、流派の正統な知を受け継ぐ者であるという権威とステータスを証明する、極めて重要な儀礼であった点である。伝書は、単なる技術の記録媒体ではなく、流派の正統性を証明し、その秘密と秩序を守るための社会的な装置として機能していたのである。
3.3 名称の変遷と混同:「神道流」と塚原卜伝の「新当流」
本報告書の核心的な論点である、二つの「しんとうりゅう」の関係性を明確に整理する。
まず、飯篠長威斎が創始した流派は、その成立期である室町時代中期から江戸時代初期にかけて、複数の名称で呼ばれていたことが確認されている。それらは「天真正伝香取神道流」という正式名称のほかに、「神道流」「新當流」「天真正新當流」、あるいは古い伝書では「香取新当流」といった呼称であった 2 。これは、流派のアイデンティティが確立されていく過程で、呼称に揺らぎがあったことを示している。
一方、剣聖・塚原卜伝は、その出自からして二つの偉大な武術の潮流をその身に宿していた。実父である卜部覚賢(うらべあきたか)から常陸国に伝わる鹿島神流(鹿島古流)を学び、その後、養父となった塚原安幹(つかはらやすもと)―彼は飯篠長威斎の高弟であった―から天真正伝香取神道流を学んだのである 3 。卜伝は、この二大源流を基盤とし、さらに諸国を巡る武者修行と鹿島神宮での千日参籠を経て、独自の境地を開眼する。そして、自らが大成させたこの新しい流派に、「新当流(しんとうりゅう)」という名を付けた 5 。
卜伝の「新当流」は、香取神道流を母体としながらも、鹿島の伝統的な剣技と卜伝自身の独創的な工夫が加えられた、「新しい当(まさ)に然るべき」流派であるという意味合いが込められていたと考えられる。この歴史的経緯により、読みが同じ(あるいは極めて近い)でありながら、出自と内容が異なる二つの「しんとうりゅう」が並立することとなり、後世における混同の最大の原因となった。
以下の表は、両者の違いを明確にするために整理したものである。
|
比較項目 |
飯篠長威斎の流派 |
塚原卜伝の流派 |
|
正式名称 |
天真正伝香取神道流 |
鹿島新当流 |
|
通称・初期名称 |
神道流、新當流、天真正新當流 |
新当流 |
|
創始者 |
飯篠長威斎家直 |
塚原卜伝高幹 |
|
創始の拠点 |
下総国・香取神宮 |
常陸国・鹿島神宮 |
|
中核思想 |
兵法は平法なり(平和希求、人間完成) |
活人剣、一之太刀(無心の剣) |
|
系統関係 |
親 (源流) |
子 (派生・発展) |
第四章:戦国武芸における神道流の影響
4.1 兵法三大源流としての位置づけ:他流との比較
天真正伝香取神道流は、後世の日本の剣術、ひいては武道全体に計り知れない影響を与えたことから、念流(ねんりゅう)、陰流(かげりゅう)と並び、兵法三大源流の一つに数えられている 2 。これら三つの源流は、それぞれが独自のアプローチで武術の理合を探求しており、その特徴を比較することで、香取神道流の独自性がより一層明確になる。
念流 は、念阿弥慈恩を始祖とし、その教えの核心は「護身の剣」あるいは「後手必勝」にある 33 。重心を後ろにかけ、地に足が根を張ったかのような安定した構えから、相手の攻撃を受け止め、無力化する技術に長けている 33 。肉を斬らせて骨を断つという思想や、鋭い刺突を特徴とし、実戦的な防御思想を体系化した 30 。
陰流 は、伊勢の武芸者・愛洲移香斎(あいすいこうさい)を始祖とする。その極意は、定まった構えを持たず、相手の目に見えない心の動き、すなわち「陰」を読み取り、それに自在に応じて勝利するという、極めて高度な心理戦にある 31 。蜘蛛の動きからその理を得たという伝承が象徴するように、力や速さに頼るのではなく、変化に応じて勝ちを得る「転(まろばし)」の理を追求した 36 。
これら二流派と比較した際、香取神道流の際立った特徴は、その圧倒的な「総合性」と、独自の「思想性」にある。念流や陰流が主として個人の対人戦闘技術を探求したのに対し、香取神道流は前述の通り、軍学や築城術までを含む包括的な兵法体系を構築した。さらに、「兵法は平法なり」という、武術の目的を社会の平和に置く崇高な理念を掲げた点において、他の二源流とは一線を画す独自の世界観を提示したのである。
|
比較項目 |
天真正伝香取神道流 |
念流 |
陰流(影流) |
|
源流名 |
天真正伝香取神道流 |
念流 |
陰流(影流) |
|
創始者 |
飯篠長威斎家直 |
念阿弥慈恩 |
愛洲移香斎 |
|
中核思想 |
兵法は平法なり(総合的・平和希求) |
護身、後手必勝(実践的・防御的) |
転(まろばし)、心法(心理的・応変) |
|
技術的特徴 |
総合武術、甲冑術、長い形 |
体中剣、独特の構え、刺突 |
無構え、相手の意図を読む |
4.2 塚原卜伝と鹿島新当流への継承:源流から大河へ
香取神道流が後世に与えた影響を語る上で、その教えを直接受け継ぎ、一大流派を築き上げた塚原卜伝の存在は欠かすことができない。前章で詳述した通り、卜伝は飯篠長威斎の高弟を養父に持ち、香取神道流の正統な教えを学んだ直系の弟子筋にあたる 3 。
卜伝の偉大さは、単に師の教えを忠実に守るに留まらなかった点にある。彼は、香取神道流という強固な基盤の上に、自らのルーツである鹿島の太刀の伝統と、生涯にわたる厳しい修行で得た独自の工夫を融合させた。そして、鹿島神宮での参籠を経て、相手と我という対立を超克した無心の境地である「一之太刀(ひとつのたち)」という新たな極意を開眼するに至る 37 。
この過程は、源流の偉大な教えが、次世代の天才的な武芸者の手によって、守られるだけでなく、さらに発展的に継承されていくという、武術史における理想的なモデルケースを示している。飯篠長威斎が掘り当てた源泉は、塚原卜伝という巨大な器を得て、日本全国へと流れていく大河となったのである。
4.3 後世への広がり:新陰流への影響
香取神道流の影響力は、塚原卜伝という直接的な系譜だけに限定されるものではなかった。その流れは、戦国時代最高の剣士として「剣聖」と謳われる上泉信綱(かみいずみのぶつな)、そして彼が創始した新陰流へと、深く静かに流れ込んでいる。
上泉信綱の剣技の形成過程において、香取神道流およびその流れを汲む鹿島新当流が大きな影響を与えたことは、複数の史料や伝承が示唆するところである 38 。特に、信綱が飯篠長威斎の高弟であった松本備前守政元(まつもとびぜんのかみまさもと)に師事したという伝承は 40 、香取神道流との直接的な繋がりを示すものとして極めて重要である。
この事実は、武術史において決定的な意味を持つ。上泉信綱が創始した新陰流は、後にその弟子である柳生宗厳(やぎゅうむねよし)とその一族によって、徳川将軍家の御流儀として採用され、江戸時代の武術界全体に絶大な影響力を及ぼすことになる。その新陰流の源流の一つに、香取神道流が存在するということは、飯篠長威斎の教えと技術が、塚原卜伝という直系の流れとは別に、上泉信綱というもう一つの偉大な水脈を通じて、日本の武術文化の根幹に深く浸透していったことを意味している。香取神道流は、まさに日本の剣術史における「偉大なる祖父」とも言うべき、普遍的かつ根源的な存在なのである。
結論:戦国時代における『新当流兵法書』の歴史的価値
本報告書における詳細な調査と分析の結果、「新当流兵法書」という言葉が指し示す歴史的実体は、特定の孤立した一冊の書物ではなく、飯篠長威斎家直が創始した天真正伝香取神道流の思想と技術、そしてその神聖な正統性を証明するために生み出された伝書群の総称、あるいはその成立初期における流派の呼称であったと結論づけることができる。
その歴史的価値は、単に現存最古級の武術流派の伝書であるという点に留まらない。最も重要な意義は、その根底に流れる思想の革新性にある。下剋上が横行し、力こそが正義とされた戦国の凄惨な時代にあって、飯篠長威斎は、武術を単なる殺戮の手段から、人間性を陶冶し、争いを未然に防ぎ、社会の平和を希求するための「平法」へと昇華させようと試みた。この思想は、当時の価値観を根底から問い直す、まさに革命的なものであった。
そして、この崇高な思想に裏打ちされた香取神道流の広範かつ実践的な総合兵法体系は、塚原卜伝や上泉信綱といった後代の天才たちに受け継がれ、彼らを通じて鹿島新当流や新陰流といった数多の重要な流派を生み出す豊かな源泉となった。それは、単に一つの流派の歴史に留まらず、後の武士道精神の形成や、現代に続く日本の武道文化の根幹に、計り知れないほど深く、そして広範な影響を与え続けている。天真正伝香取神道流とその伝書群は、戦国という時代が生んだ、日本が世界に誇るべき不朽の文化的遺産であると言えよう。
引用文献
- 香取神道流は関東七流に含まれるのか|木部二郎 - note https://note.com/kibejiro/n/n03fa8c3ea470
- 天真正伝香取神道流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9C%9F%E6%AD%A3%E4%BC%9D%E9%A6%99%E5%8F%96%E7%A5%9E%E9%81%93%E6%B5%81
- 剣術三大源流 - 大城あゆむ総合武道教室 https://tokyotate.com/column/13753/
- 剣術三大源流とその系統 - Budo World https://budo-world.taiiku.tsukuba.ac.jp/2016/03/02/%E5%89%A3%E8%A1%93%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%BA%90%E6%B5%81%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%B3%BB%E7%B5%B1/
- 鹿島新當流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E6%96%B0%E7%95%B6%E6%B5%81
- 飯篠長威斎(いいざさちょういさい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A3%AF%E7%AF%A0%E9%95%B7%E5%A8%81%E6%96%8E-1051897
- 天真正伝香取神道流始祖飯篠長威斎墓 - 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p411-010.html
- 飯篠長威斎家直 - みんなでかんがえるサーヴァント - アットウィキ (@WIKI) https://w.atwiki.jp/minnasaba/pages/1407.html
- 幸せな「老い方」へ、2通りの生き方。 | 高齢者住宅【中楽坊】 https://www.highness-co.jp/churakubou/detail/90
- 最古の剣術流派の一つ「天真正伝香取神道流」02 - History of Japanese Budo https://japanbudo.net/post-374/
- 流派について - 天真正伝香取神道流 http://katori-shintoryu.jp/%E6%B5%81%E6%B4%BE%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
- 武術 天真正伝香取神道流 - 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p211-005.html
- Vol.77 - 香取市 https://www.city.katori.lg.jp/culture_sport/bunkazai/isan/isan_vol071-080.files/h241015.pdf
- 武士道思想における死生観に関する一考察 https://toin.repo.nii.ac.jp/record/243/files/%E6%A1%90%E8%94%AD%E8%AB%96%E5%8F%A237%E5%8F%B7%2811%29%E9%AB%98%E7%80%AC.pdf
- 戦国武将の信仰/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96768/
- 戦国/江戸/明治維新 | 市谷亀岡八幡宮 | 新宿区市谷八幡町 https://ichigayahachiman.or.jp/shinto/shinto3/
- 千葉家騒動と飯篠長威斎家直 - 多古町 https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018012900087/
- 【香取神道流】1982年放送 千葉テレビドキュメンタリー - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=BbNx7a-c9PA
- JP – Tradition - 天真正伝香取神道流 https://shinbukan-katorishintoryu.org/?page_id=927&lang=ja
- 天真正伝香取神道流剣術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/024/
- 伝授体系 - Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Den Haag https://tenshinshodenkatorishintoryu.nl/ri-ben-yu/chuan-shou-ti-xi/
- 古流剣術の現存30流派をご紹介! 演武動画と創始年代・流祖・伝承地・特徴も合わせて解説! - すずしろブログ https://suzushiroblog.com/2023/11/13/koryuu-kenjutsu-30/
- 伝授体系 - 天真正伝香取神道流 http://katori-shintoryu.jp/%E4%BC%9D%E6%8E%88%E4%BD%93%E7%B3%BB/
- 剣術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%A3%E8%A1%93
- 『天真正飯篠目録』 Tenshinshô IiZasa Mokuroku https://japanbujut.exblog.jp/20087180/
- 五輪書「地の巻」をざっくり解説 ~武蔵の兵法とは? - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/chinokan/
- 『孫子の兵法』から学んでみた。社員の士気を向上させるモチベーションアップ術 - Cloud Campus https://cc.cyber-u.ac.jp/column/6705/index.html
- 代表的な兵法書は何?|弓削彼方 - note https://note.com/yugekanata/n/n25d8723135d6
- 戦国時代無敗の剣聖。あなたは塚原卜伝を知っているか? - 鹿行ナビ https://rokko-navi.media/culture/kashima-bokuden/
- 念流兵法 - 黒田藩傳 柳生新陰流兵法 修猷館 https://syuyukan.jimdofree.com/%E5%BF%B5%E6%B5%81%E5%85%B5%E6%B3%95/
- 日本最古の剣術流儀である念流の秘伝奥義を極めたという言い伝えが、黒田家に残っている。 そして、愛洲移香斎は - 柳生新陰流 - Jimdo https://syuyukan.jimdofree.com/%E9%99%B0%E6%B5%81/
- 兵法三大源流の流れを汲む剣術流派について|弓箭弦音 - note https://note.com/yumiya_tsurune/n/n96a1f43041fd
- 剣術の流派 | 殺陣教室・東京のスクール https://tate-school.com/archives/548
- 大石神影流剣術 7段論文 http://kanoukan.blog78.fc2.com/blog-entry-5745.html
- 異人に剣法を伝授された「念流」の始祖<念阿弥慈音> 剣をもって生き、闘い抜いた男たち https://www.rekishijin.com/31881
- 日向・鵜殿岩屋で開眼した「陰流」の始祖<愛洲移香斎> 剣で戦い抜いた男 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/32033
- 塚原卜伝-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73544/
- 上泉信綱-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73547/
- 天真正伝香取神道流 信武館 - SHANGHAI-ZINE 上海人 https://shanghai-zine.com/classifieds/29337/
- 上泉信綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%B3%89%E4%BF%A1%E7%B6%B1