鎌倉大草紙
『鎌倉大草紙』は、関東の百年戦争を描く軍記物語。鎌倉府の崩壊と享徳の乱を通じ、戦国時代への移行期を活写し、後北条氏台頭の土壌を示す。
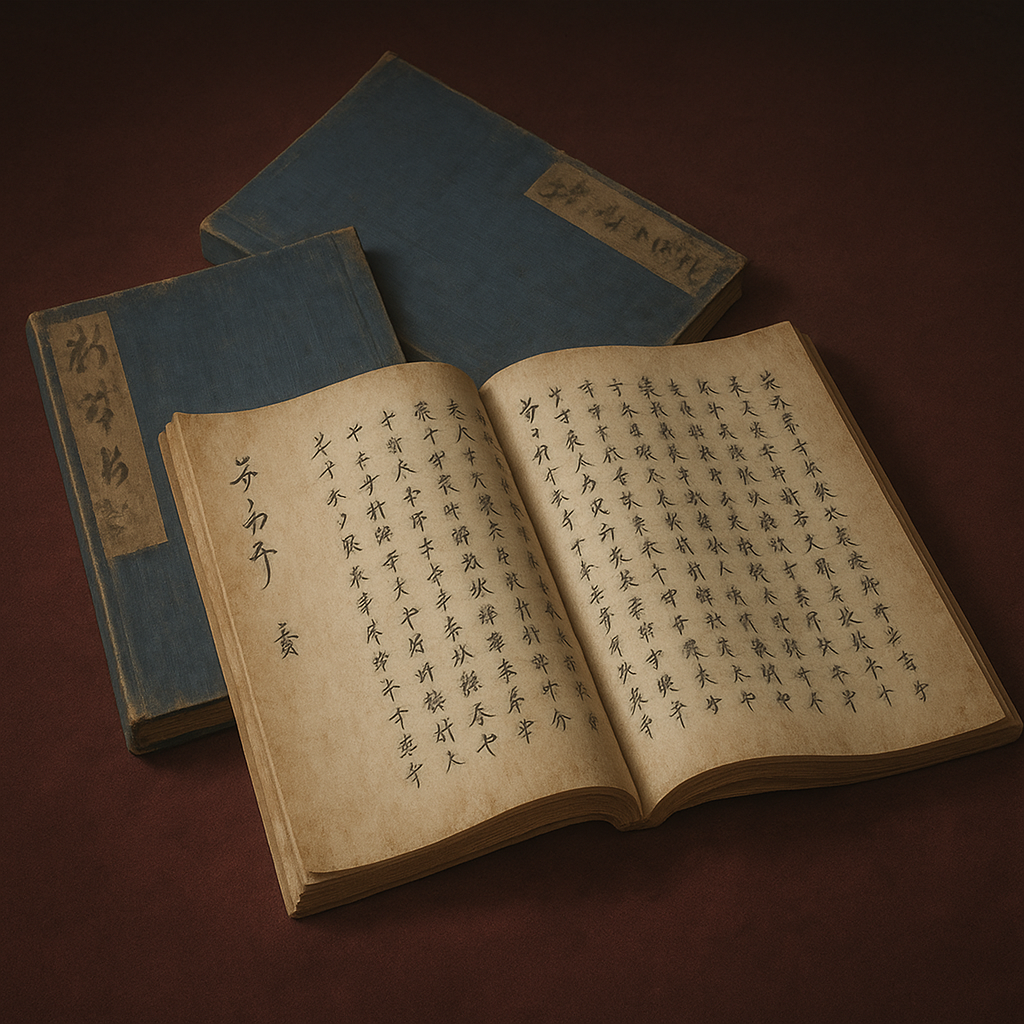
『鎌倉大草紙』の総合的分析:戦国乱世への序曲として
序論:『鎌倉大草紙』とは何か
軍記物語としての位置づけと概要
『鎌倉大草紙』(かまくらおおぞうし)は、室町時代末期から戦国時代初期にかけて成立したと推定される、作者不詳の軍記物語である 1 。本書は、康暦元年(1379年)に関東管領・上杉憲春が主君である鎌倉公方・足利氏満を諫めて自害した事件に始まり、文明十一年(1479年)に太田道灌が下総国の臼井城を攻略するまでの、約百年にわたる関東地方の動乱を編年体で記録している 3 。
物語の中心的な主題は、京都の室町幕府とは半ば独立した統治機関であった鎌倉府の長たる鎌倉公方足利氏と、それを補佐する関東管領上杉氏との間に生じた深刻な対立と、それが引き起こした絶え間ない抗争である 1 。この公方と管領の不和は、やがて関東全域の武士団を巻き込む大規模な内乱へと発展し、地域の政治秩序を根底から覆していく。本書は、その崩壊の過程を克明に描き出した、この時代を理解する上で不可欠な文献と位置づけられる。
別名『太平後記』の由来と意図
本書は『太平後記』という別名を持つことでも知られている 2 。これは、南北朝時代の全国的な動乱を描いた一大軍記『太平記』の続編、あるいはその後を継ぐものとして、作者が本書を明確に位置づけていたことを示唆する。この命名には、単なる年代的な後継という意味を超えた、作者の歴史観が色濃く反映されている。
この名称が提示するのは、関東で続いた百年間の争乱が、南北朝の戦乱終結によってもたらされた「太平」の時代の例外的な出来事ではなく、むしろ『太平記』に描かれた動乱が地続きで継続したものである、という歴史認識である。『太平記』は足利尊氏による室町幕府の創設という、一つの秩序回復をもって物語の幕を閉じる。しかし、『鎌倉大草紙』の作者は、その尊氏の子孫である鎌倉公方が新たな争乱の火種となった事実を描くことで、中央(京都)が見かけ上の安定を享受していた間も、関東には真の「太平」は訪れなかったと主張しているのである。ここには、中央の政治動向とは一線を画す関東の特殊性と、ある種の疎外感を背景とした、地方の視点からの歴史叙述の試みが明確に見て取れる。
本書が描き出す時代の重要性:関東における「戦国」の黎明期
『鎌倉大草紙』が扱う15世紀の関東地方は、京都で応仁・文明の乱(1467年~1477年)が勃発するよりも早く、恒常的な戦乱状態に突入した地域であった 7 。本書に描かれる永享の乱、結城合戦、そして関東の政治秩序に決定的な打撃を与えた享徳の乱といった一連の動乱は、旧来の室町幕府-鎌倉府体制を完全に崩壊させた。
この秩序の崩壊は、在地領主たちの自立化を促し、旧来の権威や血統によらない新たな実力者が台頭する土壌を形成した。その最も象徴的な存在が、後の関東の覇者となる後北条氏である。『鎌倉大草紙』は、まさにその秩序崩壊の過程を、同時代に近い視点から記録した第一級のドキュメントであり、関東における戦国時代の幕開けを告げる黎明期の様相を内側から描き出した貴重な証言と言えるだろう。
第一章:成立の謎―作者と時代背景
作者不詳の謎と有力説:東常縁関係者説
『鎌倉大草紙』の作者は、今日に至るまで明確には判明していない 1 。しかし、作品の内部に存在する複数の特徴から、室町時代を代表する歌人であり、同時に武将でもあった東常縁(とうのつねより)に近しい人物、あるいはその思想的・文化的影響を強く受けた人物が作者であるとする説が、最も有力視されている 2 。
この説を裏付ける根拠は、主に三点挙げられる。第一に、物語の終結点である。本書は文明十一年(1479年)の太田道灌による臼井城攻防戦で筆が置かれている 3 。この戦いは、享徳の乱を通じて分裂した名門・千葉氏のうち、古河公方方についた下総千葉氏の存亡に関わる重要な合戦であった 6 。第二に、特定の勢力への明確な肩入れが見られる点である。本書は、千葉氏の内紛において、一貫して上杉方についた武蔵千葉氏を正統な嫡流として擁護する立場を取っている 6 。そして、この武蔵千葉氏を軍事的に支援し、下総千葉氏と敵対した中心人物こそが、東常縁その人であった。第三に、作品内に挿入された和歌の逸話である。本書には、東常縁が敵将であった斎藤妙椿と戦場で和歌を詠み交わし、その風雅なやり取りを通じて奪われた所領を返還されたという有名なエピソードが記されている 6 。これは、作者が常縁の武人としての活躍のみならず、その文化的素養に対しても深い敬意と関心を抱いていたことを強く示唆している。
これらの状況証拠は、作者が東常縁の周辺にいた人物、例えば彼に仕えた家臣や、彼の思想に共鳴した知識人であった可能性を浮かび上がらせる。
成立年代の推定:戦国時代初期という時代の空気
記述の終点である1479年以降、遠くない時期、すなわち戦国時代の初期から近世初頭にかけて成立したと推定されている 2 。本書の全体を貫く基調として、君臣父子の秩序が崩壊していく様を嘆き、登場人物たちの行動から道徳的な教訓を引き出そうとする強い意図が感じられる 4 。このような道徳史観は、旧来の室町時代的な権威が失墜し、下剋上が横行し始めた戦国時代初期の知識人たちが抱いたであろう、社会の変動に対する危機感や、失われゆく秩序への郷愁を色濃く反映している。彼らは、目前で進行する混乱の原因を、過去の歴史の中に求め、そこに道徳的な意味を見出すことで、新たな時代の価値観を模索しようとしたのである。
複数著者説の可能性:内部構造の不均一性
一方で、『鎌倉大草紙』が単一の著者による一貫した著作ではない可能性も指摘されている 6 。作品を詳細に分析すると、巻によって、あるいは同一巻の中でも部分によって、その視点や筆致に不均一性が見られるからである。
具体的には、上巻から下巻の前半にかけては、鎌倉公方に対する忠実な臣下として、関東管領上杉氏の行動を賛美する傾向が顕著である 6 。しかし、下巻の後半、特に千葉氏の動向が物語の中心となる部分では、その上杉賛美の傾向が薄れ、千葉氏(特に武蔵千葉氏)の視点が前面に出てくる 6 。
この内部構造の不均一性は、本書の成立過程が単線的ではなかったことを物語っている。例えば、元々存在した「上杉氏の視点に近い記録」を核として、後に「武蔵千葉氏の正統性を主張したい編者」(おそらく東常縁の関係者)が、その記録に加筆・編集を施し、臼井城の戦いをクライマックスとする形で現在のテクストを完成させた、という可能性が考えられる。つまり、『鎌倉大草紙』は、単一の歴史認識によって書かれたものではなく、異なる立場や意図を持つ複数の歴史認識が、地層のように重なり合って形成された、重層的なテクストである可能性が高い。この複雑な成立過程こそが、本書の解釈を豊かにする鍵となっている。
第二章:書誌学的考察―二巻本と三巻本の錯綜
伝本の系統と混乱
『鎌倉大草紙』の伝本、すなわち写本や版本の系統は、歴史的に大きな混乱を経験してきた。現在知られている主要な系統は二つ存在する。一つは、江戸時代の国学者・塙保己一が編纂した一大叢書『群書類従』に収録された「二巻本」。もう一つは、明治期に近藤瓶城が編纂した『改訂史籍集覧』に収録された「三巻本」である 1 。
長らく、研究者の間では『群書類従』に収められた二巻本が基準とされてきた。しかし、この二巻本には、関東の歴史を語る上で欠くことのできない二大事件、すなわち鎌倉公方足利持氏が滅亡した「永享の乱」と、その遺児をめぐる「結城合戦」に関する記述が完全に欠落していた 1 。このため、二巻本は本来の姿から一部が失われた不完全な「欠本」であると見なされるのが一般的であった。
その後、明治時代に『史籍集覧』が刊行され、そこに永享の乱と結城合戦の記述を含む三巻構成の『鎌倉大草紙』が収録された。編者である近藤瓶城が、この三巻本を「全本」として紹介したことから、これが本来の完全な姿であるという認識が広く定着し、以降の研究や出版においてはこの三巻本が底本として用いられることが多くなった 1 。
欠落と補訂の痕跡:中巻が『永享記』とほぼ同文である問題
しかし、三巻本が「全本」であるという認識は、後の研究によって大きく揺らぐことになる。三巻本の中巻、すなわち永享の乱と結城合戦を扱う部分を詳細に検討した結果、この部分が『永享記』あるいは『結城戦場記』という別個の軍記物語と、文章表現の細部に至るまでほぼ同文であることが判明したのである 3 。
この事実は、三巻本の成立過程に関する重大な問題を提起する。すなわち、元々存在した『鎌倉大草紙』の中巻部分が、書写される過程のいずれかの段階で失われ、後世の誰かがその欠落部分を埋めるために、内容的に関連の深い別作品である『永享記』をそのまま挿入・補訂した可能性が極めて高いことを示している 3 。三巻本は、本来の姿ではなく、後世の編集によって作り上げられた「合成されたテクスト」であったのである。
原態の探求:田口寛氏らの近年の研究成果
この複雑な伝本問題に新たな光を当てたのが、田口寛氏らによる近年の総合的な書誌調査である。田口氏は、現存する多数の写本を比較検討した結果、これまで「欠本」とされてきた二巻本こそが、より本来の姿(原態)に近い形であると結論付けた 1 。
その最大の根拠は、三巻本の内部に存在する構造的な矛盾である。もし三巻本が元から一つの連続した作品として書かれたのであれば、中巻(『永享記』からの引用部分)と下巻(享徳の乱を扱う部分)はスムーズに繋がるはずである。しかし、実際には両者を続けて読むと、登場人物の動向や時間経過において、記述の重複や矛盾が散見される 1 。これは、由来の異なる二つのテクストを機械的に接合したために生じた不整合と考えられる。
『鎌倉大草紙』の成立と伝承の歴史は、この書物が単一の著者によって一度きりで完成された静的な「作品」ではないことを物語っている。むしろ、それは戦乱の時代の中で失われ、補われ、時には異なるテクストと融合しながら、形を変えつつ伝えられてきた動的な「テクスト群」と捉えるべきである。その書誌学的な複雑さ自体が、この物語が生まれた時代の混乱と、それでもなお歴史を記録し、後世に伝えようとした人々の格闘の痕跡を、生々しく我々に伝えているのである。
表1:『鎌倉大草紙』(三巻本・中巻)と『永享記』の記述比較
|
事件 |
『鎌倉大草紙』(三巻本)の記述抜粋 |
『永享記』の記述抜粋 |
比較分析 |
|
永享の乱の勃発 |
永享十年八月、公方様御結構の事有りて、管領憲実入道を御誅罰の為とて、武蔵府中へ御出勢なり。 |
永享十年八月、公方様御逆心の事有りて、管領憲実入道を御誅罰の為とて、武蔵府中へ御出勢なり。 |
ほぼ同文。「御結構」が『永享記』ではより直接的な「御逆心」となっている点に僅かな差異が見られるが、全体の構文と内容は一致する。 |
|
足利持氏の自害 |
されども御命は助け申さんと雖も、京都よりの御下知厳しかりければ、終に永享十一年二月十日、永安寺にして御自害有て失せ給ふ。 |
されども御命は助け申さんと雖も、京都よりの御下知厳しかりければ、終に永享十一年二月十日、永安寺にして御自害有て失せ給ふ。 |
完全に同文であり、補訂の事実を明確に示している。 |
|
結城城の落城 |
結城の城は、翌年四月十六日に落居して、氏朝父子兄弟一族、皆枕を並べて討死し、春王、安王両君は生捕られ給ふ。 |
結城の城は、翌年四月十六日に落居して、氏朝父子兄弟一族、皆枕を並べて討死し、春王、安王両君は生捕られ給ふ。 |
完全に同文。三巻本の中巻が『永享記』またはその系統の書物から直接取り込まれたことがわかる。 |
第三章:内容詳解―関東百年の興亡
『鎌倉大草紙』が描く約百年間は、関東地方が中央の権威から離れ、独自の力学によって動乱の渦に巻き込まれていく過程である。以下に、その主要な出来事と登場人物を概観し、物語の内容を詳解する。
表2:『鎌倉大草紙』主要出来事年表(1379年~1479年)
|
西暦/和暦 |
『鎌倉大草紙』記載の関東での主要事件 |
主要関連人物 |
同時期の京都(室町幕府) |
|
1379年 (康暦元) |
上杉憲春、鎌倉公方・足利氏満を諫めて自害。 |
足利氏満、上杉憲春 |
3代将軍・足利義満 |
|
1399年 (応永6) |
応永の乱。大内義弘が幕府に反乱。 |
足利満兼 |
3代将軍・足利義満 |
|
1416年 (応永23) |
上杉禅秀の乱。前管領・上杉禅秀が公方・持氏に反乱。 |
足利持氏、上杉禅秀(氏憲) |
4代将軍・足利義持 |
|
1438年 (永享10) |
永享の乱 。足利持氏が管領・上杉憲実を討伐しようとし、幕府軍に敗れる。 |
足利持氏、上杉憲実 |
6代将軍・足利義教 |
|
1439年 (永享11) |
足利持氏、永安寺にて自害。鎌倉府が事実上滅亡。 |
足利持氏 |
6代将軍・足利義教 |
|
1440年 (永享12) |
結城合戦 。結城氏朝らが持氏の遺児を擁して挙兵。 |
結城氏朝、春王丸、安王丸 |
6代将軍・足利義教 |
|
1441年 (嘉吉元) |
結城城落城。持氏遺児ら殺害。嘉吉の乱で将軍義教が暗殺される。 |
上杉憲実 |
7代将軍・足利義勝 |
|
1454年 (享徳3) |
享徳の乱 勃発。足利成氏が管領・上杉憲忠を謀殺。 |
足利成氏、上杉憲忠 |
8代将軍・足利義政 |
|
1455年 (康正元) |
成氏、下総古河を本拠とし「古河公方」となる。幕府は足利政知を「堀越公方」として派遣。関東が二分される。 |
足利成氏、足利政知、上杉房顕 |
8代将軍・足利義政 |
|
1467年 (応仁元) |
- |
- |
応仁の乱勃発 |
|
1476年 (文明8) |
長尾景春の乱。山内上杉家家宰・長尾景春が反乱。 |
長尾景春、太田道灌 |
応仁の乱終結 |
|
1479年 (文明11) |
太田道灌、古河公方方の臼井城を攻める。本書の記述が終わる。 |
太田道灌、千葉孝胤 |
8代将軍・足利義政 |
表3:主要登場人物と勢力関係
|
勢力 |
主要人物 |
役職・立場 |
主な動向 |
|
鎌倉公方 |
足利持氏 |
第4代鎌倉公方 |
幕府との対立を深め、永享の乱を引き起こし自害。本書における悲劇の中心人物。 |
|
|
足利成氏 |
第5代鎌倉公方(初代古河公方) |
父・持氏の仇である上杉氏を憎み、享徳の乱を開始。関東に長期の戦乱をもたらす。 |
|
関東管領 |
上杉憲実 |
関東管領(山内上杉家) |
幕府との協調を重視し、主君・持氏と対立。永享の乱後、政治から引退し諸国を放浪。 |
|
|
上杉憲忠 |
関東管領(山内上杉家) |
足利成氏によって謀殺され、享徳の乱の直接的な引き金となる。 |
|
主要武将 |
結城氏朝 |
下総の有力豪族 |
持氏の遺児を匿い、幕府に対して結城合戦を起こすも敗死。 |
|
|
太田道灌 |
扇谷上杉家 家宰 |
享徳の乱で名将として活躍。江戸城を築城したことでも知られる。本書の終盤の主役。 |
|
|
東常縁 |
武将、歌人 |
武蔵千葉氏を支援。作者との関連が深いと目される人物。 |
上巻:動乱の胎動(1379年~1417年頃)
物語は、鎌倉公方と関東管領の間に横たわる構造的な対立を象徴する、衝撃的な事件から幕を開ける。関東管領・上杉憲春は、主君である鎌倉公方・足利氏満の政策に反対し、諌言を重ねるも聞き入れられないことを嘆き、自らの腹を切り裂いて果てる 3 。主君への究極の抗議であるこの「諫死」は、鎌倉府という統治機構が、その発足当初から深刻な内部矛盾を抱えていたことを読者に強く印象付ける。
その後、鎌倉府の権威に挑戦する周辺豪族の反乱が相次ぐ。小山義政の乱や伊達政宗の乱などがそれであり、鎌倉府がこれらの鎮圧に苦慮する様子が描かれる。そして、応永二十三年(1416年)、鎌倉府を根底から揺るがす大事件「上杉禅秀の乱」が勃発する 3 。前関東管領であった上杉禅秀(氏憲)は、時の鎌倉公方・足利持氏との対立から、持氏の叔父らと結託して反旗を翻した。反乱軍の勢いは凄まじく、持氏は一時的に鎌倉を追われる事態にまで陥る。幕府の支援を得て乱はようやく鎮圧されるが、この事件は持氏の心に深い猜疑心を植え付けた。乱後、持氏は禅秀に与同した武士たちに対して過酷な粛清を行い、その強硬な姿勢が、さらなる対立の火種を育んでいくことになる 12 。
中巻:公方の悲劇(1438年~1441年)
中巻(三巻本)は、鎌倉府の事実上の滅亡へと至る二つの大きな戦乱、永享の乱と結城合戦を扱う。
傲慢で誇り高い性格の足利持氏は、父祖以来の独立的な気風を受け継ぎ、京都の将軍家としばしば対立した。これに対し、関東管領の上杉憲実は、幕府との協調を重んじる穏健派であった 13 。この両者の路線対立は次第に深刻化し、永享十年(1438年)、持氏はついに憲実の討伐を決意して兵を挙げる。これが「永享の乱」の始まりである 11 。窮地に陥った憲実は、幕府に救援を要請。時の六代将軍・足利義教は、かねてより持氏を危険視しており、これを機に持氏追討の大軍を関東へ派遣した。
幕府軍の圧倒的な兵力の前に持氏軍は敗走し、持氏は出家して恭順の意を示す。憲実は主君の助命を幕府に嘆願するが、義教はこれを許さず、持氏は永安寺で自害に追い込まれた 15 。これにより、初代・足利基氏以来約80年続いた鎌倉府は、事実上崩壊した。『鎌倉大草紙』は、持氏を悲劇の主人公として描きつつも、その頑なで人の諌言を聞き入れない性格が乱を招いたとする、道徳的な論評を加えている 16 。
持氏の死後、その遺児である春王丸と安王丸を擁立した下総の結城氏朝らが、幕府に対して反乱を起こす。これが「結城合戦」である 3 。関東各地の反幕府勢力が結城城に集結し、大規模な合戦となるが、幕府軍の包囲の前に一年近くにわたる籠城戦の末、城は落城。氏朝らは討死し、捕らえられた春王丸と安王丸は京都への護送中に殺害された。これにより、持氏の血筋は一旦途絶えたかに見えた。
下巻:戦国への扉(1454年~1479年)
下巻は、関東を30年近くにわたる泥沼の戦乱に陥れた「享徳の乱」の勃発から、その激化の過程を描く。
結城合戦の後、幕府は持氏の末子で唯一生き残っていた永寿王丸(後の足利成氏)を新たな鎌倉公方として鎌倉に送った。しかし、成氏は成長するにつれ、父・持氏を死に追いやり、兄たちを見殺しにした上杉氏一族への憎悪を募らせていく。そして享徳三年(1454年)十二月、成氏はついにその憎悪を行動に移す。関東管領・上杉憲忠を鎌倉の自邸に呼び出し、問答無用で謀殺したのである 3 。
この暴挙は、関東全域を巻き込む大乱の引き金となった。幕府は成氏を「朝敵」と断じ、その追討を上杉氏に命じた 20 。さらに幕府は、新たな鎌倉公方として将軍義政の弟・政知を「堀越公方」として伊豆に派遣する。一方、鎌倉を追われた成氏は、本拠地を下総の古河に移して「古河公方」と称し、関東の反上杉勢力を率いて徹底抗戦の構えを見せた 8 。
これにより、関東は利根川を境界として、西の上杉・堀越公方陣営と、東の古河公方陣営に完全に分裂。両陣営は一進一退の攻防を繰り返し、関東は恒常的な戦乱状態に陥った 8 。この乱の後半、扇谷上杉家の家宰であった太田道灌が名将として台頭し、各地で古河公方軍を打ち破る。物語の最後は、その道灌が古河公方方の重要拠点である下総臼井城を攻める場面で締めくくられる 2 。この結末は、前述の通り、作者の立場や関心を強く反映したものであり、関東の戦乱が未だ終わりの見えない状況で物語が閉じられていることを示している。
第四章:史料としての価値と限界
史料的価値:15世紀関東史の貴重な通史
『鎌倉大草紙』は、歴史学研究において、極めて高い史料的価値を持つ。その最大の理由は、本書が永享の乱から享徳の乱に至る、関東地方が戦国時代へと移行していく激動の時代を、連続した物語として描いたほぼ唯一の同時代的軍記物語である点にある 1 。この時期の関東の動向を記した他の史料、例えば京都の公家たちが記した日記(『康富記』など 21 )や、寺社や武家に残された古文書は、特定の事件や時点に関する断片的な情報を提供してくれるものの、事件の背景や因果関係、長期的な展開を追うことは難しい。
これに対し、『鎌倉大草紙』は、約百年にわたる政治・軍事動向を一つの大きな流れとして提示してくれる。これにより、研究者は個々の断片的な史実を、より広範な歴史的文脈の中に位置づけることが可能となる。また、享徳の乱の際に今川軍が鎌倉に乱入し、荏柄天神社の神体を略奪したという逸話 2 や、上杉憲忠を謀殺した足利成氏が江の島へ逃れた際の具体的な兵力が「五百余騎」であったという記述 23 など、他の史料には見られない具体的な情報が数多く含まれており、歴史像をより豊かに、より詳細に再構築するための貴重な手がかりを提供してくれる。
史料批判の視点:軍記物語としての限界
その一方で、『鎌倉大草紙』を歴史史料として利用する際には、慎重な史料批判が不可欠である。本書は客観的な歴史記録を目指したものではなく、あくまで文学作品としての側面を持つ「軍記物語」だからである 24 。
第一に、物語としての脚色や創作が含まれている可能性を常に念頭に置く必要がある。作者は、読者の興味を引き、物語を劇的に盛り上げるために、登場人物の心情を創作的に描写したり、合戦の様子を誇張したり、あるいは事件の展開に仏教的な因果応報論といった解釈を加えたりしている。史実と文学的創作の境界を、他の一次史料との比較検討を通じて慎重に見極めなければならない。
第二に、作者の明確なバイアスの存在である。第一章で論じたように、本書は特定の立場、特に武蔵千葉氏を擁護し、関東管領上杉氏の忠臣としての側面を強調する傾向がある 6 。したがって、これらの勢力に敵対した人物や集団については、不公平な、あるいは意図的に貶めるような記述がなされている可能性がある。これらの記述は、史実そのものとして鵜呑みにするのではなく、「作者がなぜそのように描きたかったのか」という、その背後にある意図を読み解くための材料として扱うべきである。
『鎌倉大草紙』の真の史料的価値は、そこに書かれている内容が100%事実であるか否かという点に留まらない。むしろ、戦国時代初期の人間が、自分たちのすぐ前の時代に起きた大混乱をどのように理解し、解釈し、そして物語として後世に伝えようとしたか、その「歴史認識の様態」そのものを明らかにできる点にこそ、本書の比類なき価値がある。作者は、目の前で進行する秩序崩壊という複雑な現実を、足利持氏の傲慢さや成氏の短慮といった、個々の登場人物の道徳的な欠陥に還元して説明しようとする。このような「道徳史観」 4 は、当時の武士階級が共有していた世界観の反映であり、我々は本書を通じて、単なる歴史上の事実だけでなく、その時代を生きた人々の精神性や価値観をも読み解くことができるのである。
第五章:戦国時代という視点から読み解く『鎌倉大草紙』
享徳の乱が拓いた戦国の世:後北条氏台頭の土壌
『鎌倉大草紙』が描き出す享徳の乱の長期化は、関東地方における旧来の権威構造を完全に破壊し、新たな時代の到来を準備した。この乱の最も重要な帰結は、関東における権威の多元化と、恒常的な対立構造の固定化であった 8 。古河公方、堀越公方、そして内紛を抱える関東管領の上杉家(山内家と扇谷家)が互いに牽制しあい、誰もが決定的な覇権を握れない「権力の空白地帯」が生まれたのである。
この30年近くに及ぶ戦乱は、既存の権威であった鎌倉公方と関東管領の軍事力と経済力を著しく消耗させた。その結果、彼らの権威は名目的なものとなり、地域の支配を実質的に担っていたのは、在地領主である「国衆」たちであった。彼らは、公方や管領の権威に頼るのではなく、自らの実力で領地を守り、勢力を拡大する必要に迫られた。この状況が、家柄や血統よりも実力が重視される「下剋上」の風潮を加速させたのである。
『鎌倉大草紙』が描くのは、単なる「戦国前夜」の物語ではない。それは、まさしく「戦国誕生」の物語である。本書が記録した秩序の崩壊プロセスそのものが、伊勢宗瑞(後の北条早雲)のような、旧来の権威や血縁に依らない新たなタイプの権力者が、外部から介入し、勢力を拡大するための絶好の機会を創出したからだ。本書の記述が終わる1479年からわずか十数年後、伊勢宗瑞は伊豆国に侵攻し(1493年頃)、関東の戦国史の主役へと躍り出る 7 。既存の権力者たちが互いに争って疲弊していたため、この新たな実力者の台頭を阻むことはできなかった。『鎌倉大草紙』が描いた百年にわたる混乱は、後北条氏に代表される戦国大名が誕生するための、直接的な原因であり、不可欠な歴史的条件だったのである。
戦国初期の眼差し:室町的教養と武士の価値観
本書は、血で血を洗う戦乱の記録でありながら、その随所に和歌を挿入するなど、室町時代的な文化的教養を色濃く反映している点も特徴的である 4 。特に、東常縁が敵将・斎藤妙椿と和歌を詠み交わす逸話 10 は、武力(武)だけでなく、教養(文)もまた優れた武将が備えるべき徳であるという、「文武両道」の価値観を明確に示している。
その一方で、物語全体を覆っているのは、栄華を極めた者も必ず滅びるという仏教的な無常観 27 と、裏切りや下剋上が日常的に頻発する非情な現実である。主君への忠義や一族の名誉といった武士の理想と、生き残るためには手段を選ばない現実の権力闘争との間の、埋めがたい緊張関係が、本書に文学的な深みを与えている。この理想と現実の乖離こそが、室町的な価値観が崩壊し、新たな戦国的な価値観が形成されつつある、時代の過渡期ならではの精神性を映し出している。
後世への遺産:関東戦国史の「マスターナラティブ」として
江戸時代に入り、世の中が安定すると、武士階級の間で過去の合戦を教訓として学ぶ「軍学」が隆盛した。『鎌倉大草紙』は、この軍学のテキストとして、また関東の戦国時代史を語る上での基本的な文献として、広く受容されることになった。
特に、上杉謙信の軍学(越後流)を大成したとされる宇佐美定祐が著した『北越軍談』 28 や、関東各地の合戦を網羅的に記述した『関八州古戦録』 29 といった、後世の軍記物語や軍学書は、『鎌倉大草紙』を重要な参照元として利用していることが、その記述内容の比較から確認できる 30 。
この事実は、歴史認識の形成過程において重要な示唆を与える。『鎌倉大草紙』によって形成された「足利持氏は傲慢な君主であった」「享徳の乱は足利成氏の短慮な暴挙から始まった」といった、特定の視点に基づいた物語的な解釈は、これらの後世の軍学書などを通じて繰り返し再生産された。そして、藩校などで軍学を学んだ江戸時代の武士たちの間に、それは揺るぎない「歴史的事実」として広く浸透していったのである。結果として、一軍記物語の作者が持っていたであろう特定の政治的バイアスや道徳的史観が、数百年後の人々の歴史観の根幹を成す「マスターナラティブ(基本となる物語)」として定着する上で、決定的な役割を果たした。我々が今日抱いている関東戦国史のイメージもまた、その源流を辿れば、『鎌倉大草紙』に行き着く部分が少なくないのである。
結論:『鎌倉大草紙』が現代に問いかけるもの
史実と物語の狭間に立つテクスト
『鎌倉大草紙』は、その成立過程の複雑さ、内容の多層性、そして後世への影響の大きさから、単に「室町時代の軍記物語」という枠に収めることのできない、極めて重要なテクストである。本書は、客観的な史実の記録でも、完全な文学的創作でもない。史実を核としながらも、戦国時代初期という激動の時代を生きた人間が、自らが直面する秩序崩壊の意味を過去の歴史の中に探り、理解しようと格闘した結果生まれた「物語られた歴史」なのである。
その錯綜した成り立ちと、史実と物語が分かちがたく結びついた内容は、歴史とは何か、そして史実はいかにして語り継がれ、人々の記憶の中で「事実」となっていくのかという、根源的な問いを我々に投げかける。
秩序崩壊の記録、戦国乱世への警鐘
本書が描く百年の歴史は、一つの安定した社会秩序がいかにして内部から崩壊していくかを、生々しく記録したドキュメントである。最高権力者である公方の驕りと猜疑心、それを支えるべき管領との致命的な不和、そして世代を超えて繰り返される憎悪の連鎖が、いかに破滅的な結果を招くかを、本書は克明に示している。
戦国時代という日本史上未曾有の乱世の幕開けを告げたこの物語は、単なる過去の記録に留まるものではない。それは、政治的・社会的な安定が、いかに脆く、そして一度失われた秩序を回復することがいかに困難であるかを示す、普遍的なケーススタディとして読むことができる。権力者たちの過ちと、それがもたらした悲劇を詳細に描いた『鎌倉大草紙』は、現代社会においても、リーダーシップのあり方や社会の分断がもたらす危険性について、重要な示唆を与え続けている。日本の歴史、特に戦国時代という時代の本質をより深く理解する上で、本書の価値を再評価することは、不可欠な作業と言えるだろう。
引用文献
- 鎌倉大草紙 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/009kamakuraoozoushi.pdf
- 鎌倉大草紙|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2212
- 鎌倉大草紙 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%A4%A7%E8%8D%89%E7%B4%99
- 鎌倉大草紙(かまくらおおぞうし)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%A4%A7%E8%8D%89%E7%B4%99-46532
- 現代語訳 鎌倉大草紙・永享記 〜 関東の室町時代の物語 - 芝蘭書房 - BOOTH https://booth.pm/ja/items/6964677
- 鎌倉大草紙とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%A4%A7%E8%8D%89%E7%B4%99
- 享徳の乱と戦国時代 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b507054.html
- 享徳の乱~関東でひと足早く始まった戦国時代! - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/9876/
- 臼井城(千葉県佐倉市) 2021年2月|産鉄族 - note https://note.com/santetsuzoku/n/n8e2314e94fc6
- 解 説:東常縁の和歌 https://gakuen.gifu-net.ed.jp/~contents/mizubunka/html/03021505/03021505_tx01.html
- 永享記 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/006eikyouki.pdf
- 将軍と鎌倉公方の対立の狭間で https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/50/1/ssr2-20.pdf
- 上杉憲実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%86%B2%E5%AE%9F
- 上杉憲実 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b33568.html
- 永享の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1
- 鎌倉持氏記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8E%8C%E5%80%89%E6%8C%81%E6%B0%8F%E8%A8%98
- 原胤房 ~千葉宗家の執権~ https://chibasi.net/hara11.htm
- 享徳の乱と応化・文明の乱 : 両乱における政治的 対立構造についての考察 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/223198554.pdf
- 享徳の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1
- 享徳の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11086/
- 鎌倉散策 鎌倉公方 二十一、享徳の乱と古河公方 https://ameblo.jp/kmkrlog/entry-12692660485.html
- 鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書 39 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/55/55818/132584_1_%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B8%82%E5%9F%8B%E8%94%B5%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E7%B7%8A%E6%80%A5%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf
- 戦国時代の幕を開けた「江の島合戦」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/19300
- 千葉兼胤 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/souke20.htm
- 伝東常縁筆詠草断簡(千葉県指定文化財) - 東庄町 https://www.town.tohnosho.chiba.jp/soshiki/machikominkan/gyomu/shogaigakushu/bunkazai/6216.html
- 解 説:東常縁と飯尾宗祇 https://dagwu.com/nagaragawa/html/03021605/03021605_tx01.html
- 「諸行無常」と「判官贔屓」 ―源平が残した日本人のメンタリティ - nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c10502/
- 北越軍談 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E8%B6%8A%E8%BB%8D%E8%AB%87
- 関八州古戦録 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E5%85%AB%E5%B7%9E%E5%8F%A4%E6%88%A6%E9%8C%B2
- カ(カネコ~カンレイ) - 埼玉苗字辞典 http://saitama-myouji.my.coocan.jp/2-2ka.html
- ス - 埼玉苗字辞典 http://saitama-myouji.my.coocan.jp/3-1su.html